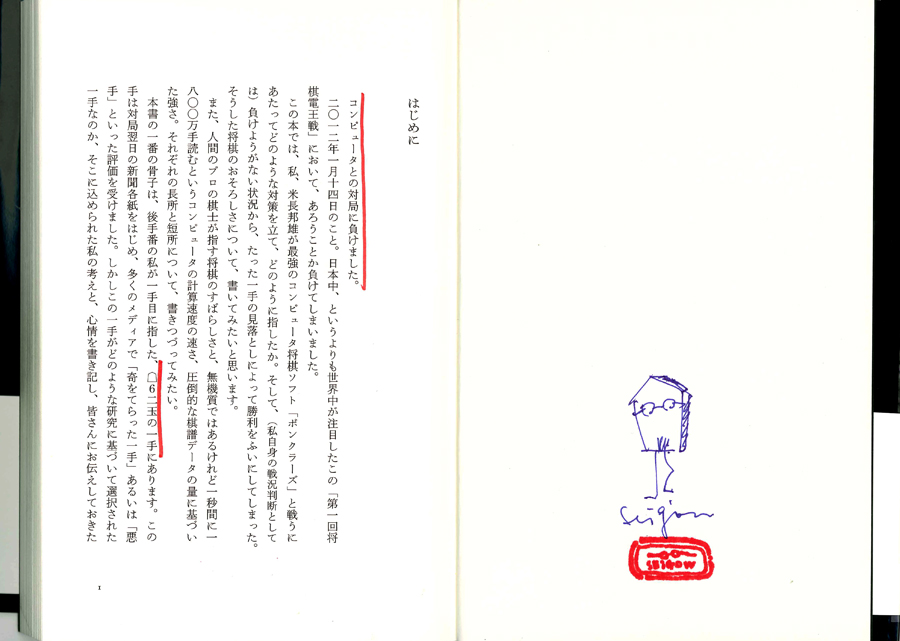われ敗れたり
コンピュータ将棋のすべてを語る
中央公論新社 2012
編集:井之上達矢
装幀:金澤浩二
劈頭、考え抜いた鬼手6二玉をもって奮戦したものの、
113手をもってあえなく討ち死にした。
しかしながら、よくぞ本書をすばやく上梓して、
その深慮遠謀の妖しい意図を世に問うた。
ゆえに本書は「読相篇」に入れるにふさわしい。
将棋も「読み」を仕事にしているのだから、
これは当然の配当だろうけれど、
それ以上に本書に吐露された告白が読ませるのだ。
久々にコクがあってキレのある告白を読めた。おまけに破れ目があるのが、よかった。
2012年1月14日、米長邦雄は世界最強のコンピュータ将棋ソフト「ボンクラーズ」との対局に挑んだ。初手に奇策6二玉を指し、前半を圧倒的に有利に進めながらも、79手目のボンクラーズの6六歩を見ていささか迷い、88手目の4五歩で決定的な敗着を打ち、ついに113手で投了して敗れた。
本書はその詳細な記録と悔しい思いを本気で吐露してみせた一冊だ。当日の局面はニコニコ動画でナマ配信されたので、あるいは覗いていた読者もいるだろうが、局中から後手の初手6二玉の鬼手が話題になり、喧々諤々の論議を呼んだ。局後も、プロ棋士や将棋ファンのあいだでこの手を評価する者と疑問視する者とが分かれ、久々に棋界周辺が熱気に包まれた。
米長は敗戦後も6二玉に至った全過程をあれこれ吟味して、この一手には米長の将棋ジンセーを振り返るべきすべてのエッセンスと、いまどきのコンピュータ・アルゴリズムに対する執拗な挑戦意識があったからだととの感懐に達したようだ。
ぼくは発売直後にすぐ読んだのだが、たいへん身につまされた。それまで米長の将棋にもふるまいにもとくに関心がなかったのだが、本書を読んでやたらに米長にはエライものがあるとも感じた。どうしてそんなふうに感じたのか、何がエライのか。今夜はあらためてそのへんをぼくの経験をいささかムリに交えつつ、少しくスケッチしてみる。
米長邦雄はぼくとほぼ同い歳である。山梨生まれの米長が半年ほど早い。その後の米長は「将棋指し」として50年以上を貫き、ぼくは「編集指し」として50年近くを貫いてきた。二人ともつまりは“指し物師”なのだ。
米長には3人の兄がいて、いずれも東大に進んだ。これを「兄たちはアタマが悪いから東大に行った。自分はアタマがいいから将棋指しになった」と嘯いた。ぼくには男兄弟がいない。妹は山登りと子育てが好きで、学校の成績は1番か2番を通していたようだが、ひどい喘息を克服したことを除いてはフツーの妹だ。それで妹とはカンケーなく早稲田に行って、ほとんど授業を無視して研究室に出入りし、学生運動でアジビラを切っていた。
米長には、どんな消化試合でもそれが相手にとって重要な対局ならば、全力をもって相手を打ち負かすという“行為の哲学”がある。ギョーカイでは米長哲学といわれる。この気持ち、よくわかる。
一方、米長は若い頃からたいそうな女好きで知られ、それをけっこう自慢しただけでなく、42歳で写真週刊誌で妖しいヌードを披露した。「ストレス解消法は何か」と問われたときは「口に出すわけにはいかない」とにやりと笑い、「可能ならばやりたいスポーツは?」という質問には「段違い平行棒」と答えた。
ぼくも大半の編集対局に手を抜かないが、とくにアマチュアがプロフェッショナルな何かに向かおうとしているときは、年齢にカンケーなくできるかぎり厳しくする。打つ手は厳しいが、このときの気持ちはたいへん温かい。なぜそのようにするかといえば、そのようなときこそぼくの中に秘められていた“方法”が露出するからだ。それを相手に盗んでほしいからだ。
もう少し、ムリクリな比較を続けると、女好きであることはほぼ御同類だろうが、ぼくは捌き方がへたくそで、たいていは「女ごころがわかっていない」と詰(なじ)られる。写真を撮られることは少なくはないけれど、ハダカになる気はない。なりたくもない。
それにしても米長の「段違い平行棒」はみごとな回答だった。なかなかこういう当意即妙は出てこない。ぼくのしてみたいスポーツは馬術か、もしくは長らく「70歳になってから暴走族になること」だったのだが、これはとんと自信がなくなった。なんであれ米長の自信には適わない。
米長は金に甘く、金に強いとも言っておかなくてはならない。将棋の金将の打ち方のことではない。カネに甘くて強いのだ。
だからいっとき株に手を出していた。米長流「株の儲け方」といった本もあったかと思う。株をやったのは「生活のことを気にするようでは将棋が弱くなる」という方針によるものらしいが、電話一本で儲かるしくみにモンダイを感じて、ある日、大枚を新居購入につぎこんでこのクセを封じ手にした。
ちなみにこんなことはナンの自慢にもならないが、癌の経験者としてはぼくが早く、米長は3年前に前立腺癌に罹り、放射線治療を受けた。『癌ノート』(ワニブックス)という手記もある。ボンクラーズとの対戦中もまだ治癒しきっていなかった。
米長の棋風は厚み重視の居飛車派だが、終盤になると複雑な攻防を好む棋癖があった。棋界では「泥沼流」とよばれる。本人はこれを「さわやか流」と名付ける。早指しは強かった。
しかし将棋ジンセーとしては時代のめぐりあわせで、大山康晴と中原誠が巨大に立ちはだかる壁となり、なかなか早指しとはいかず、前途がしばらく開かなかった。それでも1979年の8度目の王位挑戦で中原を破ると、その後は全面開花して史上3人目の四冠王となった。
ところが名人位だけはなぜか遅咲きで、50歳でやっと名人になった。ぼくはこのときだけは大いに称えたいと思ったものだ。遅咲き、大好きなのだ。けれどもとたんに若き羽生善治があらわれて、米長を打倒してさっさと名人に就いた。サイコーの栄誉とはそういうものなのだ。首相になったら、あとはその座を去るだけなのだ。米長もそれ以降はタイトル戦から遠ざかり、いまは日本将棋連盟の会長として全将棋界に君臨する。
ちなみにぼくは、そうとう自覚的に「遅咲き」を自分に課してきた。一番したいことをできるだけ後回しにするように言いきかせてきた。なぜそんなふうにしたかというと、したいと思ったことが薄っぺらになるのがつまらないからだ。それよりも課題とやりたいことが数珠つなぎに膨らんでいったほうがいい。編集指し物師は、複雑で多様であればあるほど、あとで腕を発揮できるのだ。
ま、ここまでくると将棋打ちとはいろいろ異なることもあろうけれど、それはともかく、では米長は、かなり好きなジンセーを歩んで永世棋聖と呼ばれ、いまは日本将棋連盟のトップにいるのにもかかわらず、なぜにまたわざわざリスクが高い世紀の対局に挑むことになったのかということだ。
お座興にしては度が過ぎているし、話題をとるには戦いが高度でありすぎる。そこには抜き差しならない前史があったようなのだ。
コンピュータに将棋ソフトが登場したのは37年ほど前のことだった。すぐにファミコン・ソフトにもなった。当初はどうしょうもなくへなちょこソフトで、ぼくですら時間つぶしにもならなかった(ぼくの棋力は当時は2級か3級。おそらく今も)。
そのソフトがいつしかアマチュア初段レベルに達してからは、加速度的に強くなっていった。とりわけ2005年に「激指」(げきさし)というソフトが登場すると、第18回アマチュア竜王戦全国大会に特別参加の資格で出場して、またたくまに3連勝するという驚くべき事件がおきた。アマチュアのトップクラスと同等の棋力になったのである。
そのうち、プロ棋士が余興でコンピュータ・ソフトと対戦して負けたという話も伝わってきた(「激指」はその後は市販ソフトになった)。これはプロとしては恥である。
連盟会長の立場にいる米長としてはこれはヤバイことになったと思い、「プロ棋士はコンピュータと指してはならない。ただし対局料が1億円以上であればいい」という異様なお触れを出した。
カネで「電子の攻勢」を阻もうとしたあたりが米長らしいのだが、ここには理屈もある。その話はあとでするとして、これで恥をかくことがなくなったと思いきや、大和証券グループの鈴木茂晴社長から「うちがスポンサーをするから、ネット将棋をやりましょう」と申し込んできた。
相手は、2006年5月の「世界コンピュータ将棋選手権」で優勝したソフト「ボナンザ」だ。このソフトは当時の電子将棋界の最強の英傑で、保木邦仁チームが開発した。1秒間で400万手を読んだ。
ついでながら保木はボナンザをオープンソースにし、後続する開発者たちに将棋アルゴリズムによる最強ソフトへの道を開いた。米長を打ち負かしたボンクラーズはこのボナンザをベースに開発されたものなのだ。こちらを開発したのは伊藤英紀である。富士通の子会社にいた。伊藤の工夫につぐ工夫で、ボンクラーズはなんと1秒に1800万手を読むという化け物ソフトになっていった。が、それはもう少しあとのこと。
話戻って、米長はこのボナンザの対局者として、最初は佐藤康光棋聖(当時)を選んだらしい。佐藤は周囲から「1秒で1億と3手を読む男」と言われていた。ところが佐藤はいともあっさりと固辞した。
米長は粘って「そんな堅いことを言わずに受けてくれ。1000万円以上の収入にもなる。しょせん遊びやないか」と口説いたが、佐藤はむっとして「米長センセイ、そこに正座してください」と眦(まなじり)を決した。これはマズイと居ずまいをただした米長に、佐藤は「プロが将棋を指すのに遊びということがありますか云々」と説教をした。
こうして2007年3月、米長はいろいろ反省を踏まえたうえで、ボナンザの相手に渡辺明竜王を選んだ。渡辺は応じた。対局料は1億円で、棋士には1割程度が入る。会場は一流ホテル。対局プロデュースには広告代理店が動いたので、フロアからスモークが出るという噴飯ものの演出になったが、それでも渡辺はなんとか勝った。
が、どう見てもヒヤヒヤするほどの接戦だったのである。米長はこれではそのうちプロが負けるのも遅くないと覚悟した。ボナンザと渡辺との戦いの記録は、保木邦仁・渡辺明の『ボナンザVS勝負脳』(角川新書)に詳しい。
2010年、情報処理学会から対局の申し込みがあった。将棋普及でいつもお世話になっている団体なので、逃げるわけにはいかない。今度は女流ナンバーワンだった清水市代女流王将を選んだ。相手は208台のスーパーコンピュータをつないだ「あから2010」。会場は東京大学本郷キャンパス。
どうなることかと全員が案じたが、米長は清水が艶やかな着物姿で臨んだことに、何か感動をおぼえた。けれども勝負は「あから」の圧勝だった。いよいよ絶体絶命である。米長は考えこんだすえ、「今後のプロとの対局には次の条件を満たしてほしい。第一候補は羽生善治で、対局料は7億800万円を払いなさい」と通達した。
7億円は法外だが、こういう計算だった。米長は羽生とこの件を相談したとき、羽生から「もし自分が対局するなら人間と戦う棋戦のすべてを欠場します。そして1年をかけてコンピュータ将棋を研究します」と聞いていた。そうだとすると羽生が1年のすべての棋戦を欠場するだけで数億円の損失になる。のみならずコンピュータとの対局後にどうなるかといえば、以前のタイトルが戻るわけではない。シード権も失ったままになる。その後は5番勝負や7番勝負に勝ち続けなれければならない。これらのリスクを計算するとおおよそ7億円になるというわけだ。いや、羽生なら7億円でも安いのではないか。
むろんこの数字で対局を申し込む連中はいまい。そこでここが米長の変なところだが、「おとり物件」「格安物件」を入れておいた。それが対局料をぐっと安くした1000万円の“米長旧名人”がお相手しますという特出しメニューだったのである。
この「おとり物件」に乗ってきた者がいた。中央公論新社の前社長の浅海保だった。1000万円なら乗ったということだ。その後、ドワンゴの川上量生会長も乗った。こうしてボンクラーズと米長との世紀の一戦が実現する運びとなったのだ。
対局コンピュータはボンクラーズと決まった。超々強敵である。持ち時間は3時間ずつ、使いきったら一手一分以内。会場は将棋会館。
対局日は2012年1月14日となった。対戦100日前の10月6日には記者会見もした。米長は「電王戦」という名前をつけた。会見の席上ではドワンゴの川上と振り駒をして、米長が後手番だということも決まった。さあ、特出しメニューながら、これで米長が本気になっていく。
自分の弱点を知ることは敵を知る以上に重要だ。そのくらいのことは十分に心得ている米長は、まず自己点検に入った。
いったい自分はどのくらい弱くなっているのか。仮りに名人をとった50歳が頂点だったとすると、自分は60歳で引退したのだから、そこまでで棋力はかなり落ちている。そこからさらに7~8年がたった。いま現在の自分ははたしてナンボのものなのか。
実力を計るのには誰かと対局したくらいではわからない。相手によっていろいろゆらぐ。諸君もこのことはよく弁まえたほうがいい。「読み」というものは、自分で自分が自分を相手に力をつけていくものなのだ。そこで米長は詰将棋を目盛りとしてみた。
20歳そこそこのときは「看寿の百番」をすべて解く熱意があった。才能も伸びた。69手詰でもへいちゃらだった。35歳のときは、そんな詰将棋が実践に出るわけがないだろうという気になった。それでも米長の将棋ジンセーは35歳からが本番だったので、19手詰や37手詰くらいのものを毎日解くようにしていた。「読み」の水準を維持するためだ。
このこと、ぼくが年齢にしたがって本をどのくらい読めるか、どの程度の深度や軽度で文章が書けるかということを、つねに絶やさず確かめ続けたのとほぼ同質のエクササイズなので、たいへんよくわかる。それをしていないと「読み」が落ちていく。そうすると相手が誰であろうと、どんな話を仕切れるのかの目盛りも失っていく。
米長は55歳を過ぎて衰えを少しずつ感じたと書いているが、ぼくもそのあたりから「読み」と「切れ」についての大局と細部の蝶番に多少の変化を感じていた。そこで「読み」の軌道を新たなメトリックをもって変えていくしかないと実感していた。それが55歳くらいからの「千夜千冊」の連打に向かうという大修行になったわけである。
米長のほうは65歳をこえて、詰将棋をしていても「これは10手以上かかりそうだ」と見えたとたんに、自分の気力が萎えていくのを思い知ったようだ。
しかし、これではとうていボンクラーズに向かえるはずがない。米長は気力をふりしぼって改めて詰将棋に向かうことにしたようだ。まさに米長必至の緊急千夜千冊だ。
ただし棋力を回復させるには、ゼッタイに答えを見ずにとことん自力で考え続けるということをする。正解があると知ったり、これを手前で拾おうとしてはパーなのだ。お題には素手で向うべきなのだ。こうして谷川浩司の『月下推敲』を毎日解いていくようにした。
ところが、ところがである。そうやって自分が1時間かかってやっと解いた詰将棋を、コンピュータのほうはあっというまに解いていく。とりあえず「激指」をやってみて愕然とした。1手10秒に設定すると、米長の勝率は2割を割った。市販ソフトを相手にこのザマなのだ。
米長はもっと全面的にならなきゃダメだと覚悟した。数十万円をはたいて高機能パソコンを仕入れ、伊藤英紀にお願いしてそこにボンクラーズをインストールしてもらうことにした。
当初はとうてい勝負にならなかったのだが、今度は必死に相手コンピュータの研究をしてみた。ボンクラーズは22秒できっかり指してくる。対する米長は2~3秒の早指しで応じていった。ことごとく勝負は負けた。ともかくどんな戦法も熟知している。矢倉の繊細きわまりない駆け引きも、相振り飛車の指しまわしも、横歩取りの激しい変化も、完璧だ。なにしろ米長将棋の棋譜を全部もっている。これでは勝てるわけがない。
けれどもそのうち、そうか、ああ指せばよかったのか、うんうんあそこに隙間があったのかと思えるようになった。まったく歯が立たないのではなくて、「自分に問題がある」ということが見えてきた。こうして12月半ばになって、ついにボンクラーズの一大弱点を発見することになったのである。
ぼくが感心したのは、米長がコンピュータ将棋にのめりこみながら、実は棋士というものが将棋盤に駒を並べることによってこそ、その実力の総体が縦横無尽にはたらくのだということに気がついたことである。
これは棋士には“身体知”が必要だということで、これに気がついたのはいまさらながらの大発見だ。アニー・ディラード(717夜)が10行の文章を書くのにも、ときに100平米の空間がいると言っていることと同じだ。そこで米長はパソコンの隣に将棋盤をおき、一手ずつ盤面に駒を並べて対局するようにした。パソコンを牛耳るにはパソコンが用意した端末に合わせていてはダメなのだ。これではいつまでたっても“PC読み”に従うしかなくなっていく。
そのうえで持ち時間をのばしていった。これで変化があらわれてきた。持ち時間1時間ならやや負け越す程度、3時間なら3局指して1勝2敗のところまでこぎつけた。
これで気持ちがだんだんふっ切れてきた。米長は「コンピュータのほうが自分より強い」ことを全面的に認めることができるようになる一方で、それなら特別の戦略を自分の身体知を十分に動けるようにして練ろうという気になっていったのだ。そしてある日、ボンクラーズにも解けない手筋があることを発見したのだった。
ボンクラーズは飛車と角と歩が相手陣地に入ったときは必ず成るようにプログラムされている。しかしアマチュアのファンなら知っての通り、7手詰めの詰将棋にさえ「角成らず」や「歩成らず」の局面はけっこう多い。
ところがこの手の問題で、ボンクラーズはミスを犯すのだ。また、入玉にめっぽうふらつくこともわかってきた。
そうか、ボンクラーズにも弱点があるのなら、これは必ずなんとかなるはずだ。しかしながら「成らず」も「入玉」も序盤ではおこらない。一気に序盤からリードして、そのまま巧みに「成らず」や「入玉」に持っていくにはどうするか。答えは一つ、おそらく初手からコンピュータを迷わせるべきなのだ。HALを狂わせることなのだ。
米長が後手番であることは決まっていた。ならばボンクラーズの先手の初手は7六歩になるだろう。で、どうするか。ボンクラーズを最初から迷わせるしかあるまい。
かくして思いついたのが世間を騒がせた初手6二玉だったのである。このヒントはボナンザの開発者の保木邦仁によるものだったらしいが、いったんそこに気がついた米長はここで大いに戦略的自信をもった。そして、この一手に賭けて、すべてを組み上げていくことにした。
ここから先、米長がどのように当日の対局に向かっていったかという用意周到はたいへんおもしろい。いや、大いに学ぶべきものがある。
まず、米長は当日の対局時に誰が駒を並べるかを指定させてほしいという条件を出した。指し手を決めるのはボンクラーズなのだから、誰が代わりに盤面を打っても事態は変わらないはずだが、そうではないことに米長はちゃんと気づいていた。
勝負はナマである。それには身体知も環境知もフル稼働できなければならず、そこでは“呼吸”も“間合い”も将棋そのものなのだ。これは編集にとって「場」が必須になっていることや「相互性」が重大な秘密を握っていることと、まったく同断だ。
そこで米長は、①将棋が強い、②私と同様に対局に真剣になれる、③目障りにならず、私の気を散らさない、④私を尊敬している、という4条件を満たせる打ち手を選び出すことにした。この条件を満たせる者は世界中でもそんなにいない。絞ればせいぜい3、4人であろう。米長は中村太地4段を選び出す。
このことについて、本書で興味深いことを明かしている。米長は現役のころから運がよくなりそうな相手とは付き合い、運が逃げそうな奴とはできるだけ付き合わないという方針を徹底してきたらしい。その区別をどこでするのかというと、「米長が負けたらおもしろい」と思う者は運を悪くする。「どうしても米長のいいとろを見たい」と思う者なら運がうまく動いていく。そのことで判断するのだという。
なるほど、これは言い得て妙である。味方か敵かを判定するのではない。敵であってもいい勝負をしたいと思っている連中は少なくない。そういう奴とはちゃんと付き合っていく。マスコミはたいていは米長が負ければおもしろいのだから、こんな連中とは適当にしか付き合えない。そんなふうにしてきたという。
なるほど、なるほどだ。米長はまずはコンピュータの指し手をセレンディップな男にすることで、アドバンテージをとったのだ。
次に、米長は椅子での対局を申し入れた。これはたんに正座ができない体になっていたからだが、こういうところをすかさず仕組んでいったのはさすがであった。
むろんかつての米長なら2日間の対局中、ずうっと正座をするのは平気だった。それどころか正座をすることで脳内物質が出ているだろうという覚醒状態もつくれた。勝負とは必ずやそういうものなのだ。それがダメになったのだから、この選択はきわめて妥当だったろう。
ぼくもステージ上でどんな椅子に坐るかによって、話の中身が微妙に変わってくることを知っている。
ついで当日のシミュレーションもした。いろいろ想定してみると、前日から将棋会館に泊まるべぎだという結論を得た。当日は100人を越す報道陣も知り合いも駆けつける。そんなところへ玄関から入っていけば、たちまちフラッシュをたかれ、何かと質問を受け、それだけで気が散っていく。だから泊まることにした。これなら対局場にすうっと入っていける。
もうひとつ手筈を整えることにした。当日は記者会見以外の取材にはいっさい応じない、撮影にも応じないということだ。
だいたいこんなことを決めて臨むことにしたのだが、最後の仕上げが残っていた。女房に「俺は勝てるだろうか」と聞くことだ。
女房は将棋についてはルールがわかる程度で、ふだんは意見を聞いてもナンの役に立たないのだが、だからこそ「あなたなら大丈夫でしょう」という仕上げの一言が聞きたかったのだ。ところが答えは仰天するものだった、なんと「あなたは勝てません」なのである。
さあ、そう言われると気になってくる。何をもって自分が勝てないと感じたのか。すると米長夫人はこう言ってのけた、「あなたには全盛時代にくらべて欠けているものがある」。
いったい何が欠けているのか。酒は飲んでない。将棋に対する情熱もそうとうに回復した。しいていえば前立腺癌が治っていないことくらいではないか。しかし、そんなことで「勝てない」とは言えまい。そこでおそるおそる聞いてみた。
すると夫人は世にも恐ろしいことを言ったのだ、「全盛期のあなたと今のあなたには、決定的な違いがあるんです。あなたはいま、若い愛人がいないはずです。それでは勝負に勝てません!」。
ガーン、ガーン、である。それではお言葉に甘えてとも言えないし、そんなことよりこの問題と自分が最後の勝負に出ようとしていることが緊密につながっているという意外な脈絡にショックを受けた。しかし、夫人の予想通り、米長は愛人を作らず、コンピュータを相手にして、そして敗れ去ったのである。
その後、米長は夫人の言葉の意味を「あなたはね、ナーバスになりすぎたのよ」という意味に解釈するようにしたそうだ。
このほか、本書にはいろいろ学ばされることが出入りする。身につまされることも少なくない。
万全を期していたはずだったのに、当日対局の午前中の打ち合いが終わり「休憩です」と言われて部屋を出た瞬間、女性記者が写真を撮ったとき、米長は苛々として「あなたはルール違反だ。すぐに将棋会館から出ていくべきだ」と言ってしまい、これでリズムを崩したという話など、なんとも含蓄のあるエピソードだった。ぼくもいろいろ思い当たることがあるからだ。
が、それらは本書を手にしてみて、諸君なりに感じてもらうのがいいだろう。また本書には詳しい棋譜と自戦解説も載っている。一度は並べてみるのもおもしろい。
それになにより、本書は将棋ファンにもコンピュータ派にも、また編集工学ファンにも絶妙な説得力をもつ。仕事もジンセーも、すべからく「読み」こそが問題なのだから。それゆえ本書は、千夜千冊「読相篇」に入るにふさわしい一冊だったのです。

『われ敗れたり:コンピュータ棋戦のすべてを語る』
著者:永世棋聖 米長邦雄(日本将棋連盟会長)
編集:井之上達矢
撮影:薈田純一
装幀:金澤浩二
2012年2月10日 初版発行
発行者:小林敬和
発行所:中央公論新社
【目次情報】
はじめに
第1章 人間を凌駕しようとするコンピュータ将棋ソフト
第2章 △6二玉への道
第3章 決戦に向けて
第4章 1月14日、千駄ヶ谷の戦い
第5章 記者会見全文
第6章 コンピュータ対人間、新しい時代の幕開け
第7章 自戦解説
第8章 棋士、そして将棋ソフト開発者の感想
あとがき
【著者情報】
米長邦雄(よねなが・くにお)
将棋棋士。永世棋聖。1943年6月に山梨県で生まれ、1963年4月にプロ入り、1984年には四冠王(棋聖、十段、棋王、王将)を達成する。1993年には史上最高齢の49歳11ヶ月で名人位を獲得し、2003年12月に引退。通算成績1103勝800敗1持将棋。2003年5月に日本将棋連盟専務理事となり、2005年5月には会長に選出された。2005年6月現在、日本将棋連盟会長、東京都教育委員会委員、日本財団評議員、日本テレビ放送番組審議会委員などを務めている。