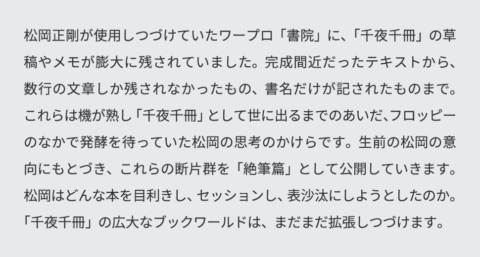方法(全5冊)
法政大学出版局 1984〜2006
Edgar Morin
La Methode 1977~2001
[訳]大津真作
編集:稲義人・藤田信行
ぼくは未来予想や予言があまり好きではないのだが、ずっと前から「20世紀は主題の世紀だったが、21世紀は方法の世紀になるだろう」と“予言”してきた。この“予言”は、量子力学のあらかたを展望した直後のウェルナー・ハイゼンベルク(220夜)が、「もはや方法を対象から切り離すことはできない」と書いたくだりを読んだときからハラが決まっていた時代メッセージだった。ずばり当たっていると思う。
ハイゼンベルクの「方法を対象から切り離すことはできない」というのは、「現象や内容すなわちコンテンツやコンテキスト」というものは、それを乗せたり運んだり切り出したりするハードウェアやソフトウェアの方法とともにある、ということだ。これは長らく「方法は主題を切り刻む道具にすぎない」という見方を大きくひっくりかえすものだった。
この「方法」を全面に出すという見方やその実践は、ぼくのなかでは「方法としての編集」へ、また「方法としての編集工学」として広がり、さまざまな成果として充実もし、多様にもなっていった。
一方、連志連衆會主催の「連塾」第1期で8回にわたって日本についてのトーク・パフォーマンスをすることになったとき、日本を考えるにあたって日本の正体を主題で求めるのではなく、「方法自体が日本の正体だ」と思うべきだろうと確信した。このことはその後、NHKから8回にわたる連続講座を頼まれたとき、「おもかげの国・うつろいの国」と題してテキストを書いたのだが、そのキーコンセプトを「日本という方法」とすることとして発展した(のちにこのテキストはNHKブックスから『日本という方法』として上梓された)。日本って方法そのもの国ではないか、日本の本質はその方法の束そのものにあるのではないかということだ。
このように、ぼくにとって「方法」は最も重要な看板なのである。ぼくに思想があるとして(ぼくは自分の思想を標榜することがあまり好きではないのだが)、まあそれでも思想があるとすれば、それは「方法を思想とみなすこと」がぼくの思想なのである。どんなことより方法を考えることは、ぼくの使命とさえいえるものなのだ。つまり思想は方法なのである。
方法の思索者としては、すでにハンス・ゲオルグ・ガダマーやパウル・カール・ファイヤーアーベント(1812夜)というダントツの大物がいる。主著として『真理と方法』(1960~1975)や『方法としての挑戦』(1975)があった。
いずれもきわめて示唆に富み、ぼくも少なからず影響を受けたのだが、ガダマーやファイヤーアーベントが何を思索して方法を重視したかについてはあらためて千夜千冊するとして、今夜はエドガール・モランによる方法思考をとりあげたい。
エドガール・モランのことは早くから気になっていた。
本もちらちら読んできた。翻訳順でいうと『カリフォルニア日記』『時代精神1・2』『方法・1』『意識ある科学』『方法・2』というふうに読んだのだが、一番気になった『方法』シリーズが1990年代に入ってから続刊されたので、こちらだけは本格的に読みこむことをしなかった。
そんなモランなのだが、日本ではあまり評価されてはこなかった。中村雄二郎さん(792夜)や福原義春さん(1114夜)とはモランの勇敢なフレームワークをめぐっていささか熱く語りあったことはあるけれど、いわゆる“フランス現代思想派”はいっこうにモランに言及しない。理由はわからない。きっと面倒くさいのだろう。ともかくも、その高邁な構想と主旨にくらべてあまり注目されなかったのである。
ちょっと気の毒なような気もするが、『方法』の原著の執筆そのものが長期にわたったことも影響しているのかもしれないし、構想が広範囲に大きすぎたのかもしれない。
なにしろ『方法・1』が「自然の自然」、2が「生命の生命」、3が「認識の認識」、4が「観念」、5が「人間の証明」というもので、この異様なタイトル5連発を見るだけでもたしかに面倒くさい。しかもその構成はかなり汎知学的なのだ。
今夜も『方法』の全体をレビューすることは不可能なので、この目次構成をまずはご覧いただきたい。モランが何を書きたかったのか、「方法」とはどういうことなのか、およその見当がつくだろう。短文になっているところは、ぼくが思い切ってサマライズをしてみたものだ。
方法とは何か。フランス語のメトード(methode)の語源はギリシア語の「歩くこと」から発している。
(絶筆)
執筆開始時期:2013年4月
■補足解説
今夜(1851夜)から千夜千冊「絶筆篇」がはじまります。
「絶筆篇」についての説明は本文冒頭に掲げました。開始の詳細については「遊刊エディスト」の記事をご覧ください。
絶筆篇初回としてとりあげた本書は、フランスの哲学者エドガール・モランが1977年刊行の『方法1』から2004年『方法6』(未訳)にいたるまで、数十年にわたって書き続けた大著のシリーズです。1921年生まれのモランはいまも健在で、今年(2025年)で104歳をむかえます。近年も『百歳の哲学者が語る人生のこと』(2022,河出書房新社)や『戦争から戦争へ』(2023,人文書院)を発表するなど、思索を絶やさず世界に影響を与え続けています。
モランが『方法』6部作で追求したことは、人間主体の核心部に自然(ピュシス)を位置づけ、人間世界と自然界を接続する方法を模索することでした。そのためにモランは自然科学、とりわけ宇宙物理・熱力学・量子力学・情報科学の領域で最新の成果を解釈しなおし、人間世界との共通点を照合していきました。そうすることで、近代西洋の合理化された知の体系から排除されてきた「未知のもの」に感覚を研ぎ澄ませることを目指そうとしたのです。
松岡は「世界を編集したいならエリッヒ・ヤンツの『自己組織化する宇宙』(1731夜)と、モランの『方法』を読み了えておくことが必要だ」とさまざまな場面で力説していました。そしてことあるごとに本書を「いつか千夜する」と宣言していましたが、あまりの大著だったために執筆に苦心したようで、未完の状態で長いあいだフロッピーの中に眠ったままとなっていました。
(補足解説・寺平賢司/松岡正剛事務所)
■関連する千夜千冊
1812夜 ポール・ファイヤアーベント『方法への挑戦』
哲学者ファイヤアーベントはアカデミズムのありかたに抵抗し、アナーキーな知を探求した。Anything goes(なんでもあり)の思想が「方法」を発動する。
12夜 ポール・ヴァレリー『テスト氏』
世界と自分を見るにあたって必要なのは方法であると断言した文学者ヴァレリー。松岡はヴァレリーの「世界と自分のあいだに落っこちているのは方法だ」という言葉に惚れていた。
1566夜 米盛裕二『アブダクション』
松岡の提唱する「編集工学」でとくに重視していた技法がアブダクション(仮説的推論)だった。「隠された意味」を追い求める方法の骨法が詳述されている。
■セイゴオ・マーキング

⊕『方法1〜5』⊕
∈ 著者:エドガール・モラン
∈ 編集:稲義人・藤田信行
∈ 発行所:法政大学出版局
∈ 製版・印刷:三和印刷
∈ 製本:鈴木製本所
∈ 発行:1984年〜2006年
⊕ 目次情報 ⊕
『方法・1』自然の自然
総序 谷間の精神
第一部 秩序・無秩序・組織
第1章 秩序と無秩序(自然>の諸法則>から諸法則の本性へ)
第2章 組織(対象からシステムへ)
第二部組織作用(活動的組織)
第1章機械存在
第2章 自己の生産(バックルと開放)
第3章 サイバネティクスからコミュニケーションにかかわる組織へ
第4章 複雑な因果性の出現
第5章 最初の認識論バックル
第三部 再生された生成組織
第1章 ネガエントロピー組織
第2章 情報物理
結論 〈自然〉の複雑性から複雑性の本性へ
『方法・2』生命の生命
序文 生命なき生命
第一部 生態学の一般化―オイコス
第1章 生体組織
第2章 自然統合と統合の本性
第3章 生態学的関係(生態→自己=関係)
第4章 一般生態学
第5章 思考の生態学
第6章 科学→生態学的意識
第Ⅱ部 基本的な自立性―自己
第1章 自立性から自己へ
第2章 自己=(遺伝=表現=)組織
第3章 個別性の非本源的な性格
第4章 主体の核心
第5章 第二の型の諸個体
第6章 社会―第三の型の実体の出現
第7章 自己→個体→主体
第三部 生きた活動の組織
単独章 生きた活動の自己組織
第四部 〈再〉―接頭辞からパラダイムへ
単独章〈再〉―接頭辞からパラダイムへ
第五部 生物を理解するために―生命
第1章 圧縮できないパラダイム
第2章 生きた複雑性
第3章 生きること
第4章 生きた人間
『方法・3』認識の認識
総序
第一部 認識の人類学
第1章 認識の生物学
第2章 認識の動物性
第3章 精神と脳髄
第4章 超複雑機械
第5章 計算することと思索することと
第6章 認識の実在性
第7章 認識の二重ゲーム(二枚舌)
第8章 二重思考
第9章 知性ー思考ー意識
第一部のまとめ
『方法・4』観念
第一部 観念の生態学
第1章 文化ー認識
第2章 文化決定論と文化ブイヨン
第3章 知識階級と二つの文化
第4章 認識社会学の複雑性
第5章 自己=横断=メタ社会学
まとめ―ココトイマへの回帰
第二部 諸観念の生命(精神界)
序文 精神圏のルネサンス
第1章 第三界
第2章 観念体系
第3章 精神圏における発生と変身
第三部 諸観念の組織(精神学)
第1章 言語について
第2章 合理性と論理学
第3章 下心(パラダイム学)
総まとめ 思想と人間について
『方法・5』人間の証明
第一部 人間的三位一体
第1章 コスモスへ根をおろすことから人間の出現へ
第2章 人類の人間性
第3章 人間的三位一体
第4章 多様な一者
第二部 個人のアイデンティティー
第1章 主体の核心
第2章 多形態アイデンティティー
第3章 精神と意識
第4章 アダム・コンプレックス―サピエンス=デメンス
第5章 理性と狂気を越えて
第6章 耐えられない現実
第三部 大きなアイデンティティー
第1章 社会的アイデンティティー(1)―往古の核心
第2章 社会的アイデンティティー(2)―リヴァイアサン
第3章 歴史的アイデンティティー
第4章 地球規模のアイデンティティー
第5章 未来のアイデンティティー
第四部 人間複合体
第1章 覚醒せる者と眠れる者
第2章 本源への回帰
⊕ 著者略歴 ⊕
エドガール・モラン(Edgar Morin)
1921年、パリ生まれの社会学者・思想家。パリ大学に学び、大戦中は対独レジスタンス活動に参加。戦後は雑誌編集者、映画評論家として活躍。パリの国立科学研究所(CNRS)の主任研究員として、現代の多元的・総合的な人間・社会・文化の調査研究に成果を上げる。日本語訳に『人間と死』『政治的人間』『カリフォルニア日記』『失われた範列』『プロデメの変貌』『自己批評』『スター』『大いなる女性』『時代精神(全2巻)』『映画』『ソ連の本質』『意識ある科学』『ヨーロッパを考える』『ドイツ零年』『出来事と危機の社会学』『二十世紀からの脱出』『E・モラン自伝』『祖国地球』『方法(全5巻)』(以上、法政大学出版局)、『複雑性とはなにか』(国文社)『オルレアンのうわさ』(みすず書房)、『百歳の哲学者が語る人生のこと』(河出書房新社)などがある。