名人に香車を引いた男
中公文庫 1980
ぼくの将棋の腕はたいしたものじゃない。この30年間、ほとんど強くなっていない。ヘボ将棋もいいところで、せいぜい初段前後だろう。ただし、変なこともある。ものすごく強い者と対局するとなぜか強い指し手が続き、相手がそこそこだと、そこそこになる。昔からこういうふうだった。
ふつう、将棋ではこういうことはありえない。実力差があれば最初から角落ちや香落ちのハンディキャップ戦になる。ぼくは小学校3年のときに父に将棋を教えられたのだが、夏休み中、飛車角落ちだった。これは悔しかった。
升田幸三は「名人に香を引いて勝つ」というとんでもない決意をして広島を出た男である。昭和7年2月の13歳の家出だった。大阪に出て、木見金治郎八段の書生になった。以来、よく知られているように破天荒な将棋人生を送った。だいたい定跡(定石は囲碁)をおぼえない。ろくに知らないといっていいらしい。ではどうしてきたかというと、新手を工夫しつづけた。局面を打開する逆転の独創に賭けた。だから升田の将棋人生は「新手一生」といわれる。
それにしても将棋指しになるという少年の決意が、「名人に香を引く」というものだったというのは、恐ろしい決意だった。
名人に香車を引くということは、絶対にありえない。名人が香車を引くことはあるが、その逆はありえない。
名人は棋界の頂点にいる者で、誰だってその位に挑戦するわけである。そもそもプロの将棋の正式戦はすべて総平手戦であって、ハンディキャップ戦などはない。そういう将棋は門下内の稽古か、素人相手の稽古将棋だけである。そういう場合でも、上の者が香落ちにすることはあっても、下っ端の挑戦者が香を落として臨むなどということは、ない。まして名人を相手に挑戦者が香車を引くことはない。
もし、そういうことがあるとすれば、「一番手直り」の連続勝負が認められたときだけで、これならば負ければたとえ名人でも相手が香を引く。さらに名人が負ければ2枚目の香を引く。さらに負ければ桂馬を落とされる。
俗に「指しおろし」というもので、升田は少年時代にこれを夢見たわけだった。なんとも壮絶な、異常な大望だった。負けん気が強いなどというのではなく、敵に屈辱を強いるという大望である。
本書は「週刊朝日」が連載した自伝で、升田が喋りまくったものを記者がまとめた。昭和54年の連載だから、もう升田は引退していた。
さすがに稀代の名人(変人?)の半生記だけあって、感情を隠さない。黙っていればすむような将棋界の事件もあからさまに喋っているし、相手を睥睨していることも手加減しない。許せないことは癇癪を爆発させてまでも絶対に許さない。不世出の名人といわれた木村義雄の自伝や著作とくらべると、あまりにがさつで、味も素っ気もない。いつも何かに噛みつき、吠えている。感情の言葉だけで綴られた自伝なのである。だから喧しい。
ところが、こういう自伝を読むと、かえって勝負に賭けた人間の機微が細かく伝わってくる。豪気な性格だからポカも多く、自制を失って大事な勝負をよく落とすのだが、いったい何が人間を失敗に追いこむのかが、しみじみよくわかる。その岐路はたいていはごく僅かな局面にある。升田はその僅かな局面に蛮勇をふるって独創を集中し、その僅かな局面で事態を踏みにじってきた。そういう正直なことがすべて書いてある自伝だ。これがあの傍若無人な升田幸三の本音なのかと思わせる箇所も少なくない。
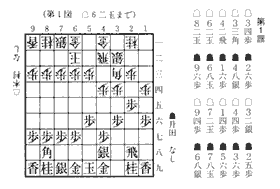
升田はのちに大山康晴と並んで「大山升田時代」を築いた。いったんは升田がリードしたのだが、やがて大山に負け続けた。升田のほうが年上で、同じ木見金治郎門下だった。
その棋風は、同門ということもあって、「攻めの升田、受けの大山」とずっと囃されたのだが、本書では、実は升田は六段のころまではずっと受けの将棋で、大山のほうが攻めの将棋だったと証されている。これは意外なことだった。
きっと同門で互いにそのよさを学んだのだろう、攻めと受けの特色が棋士人生の後半からは逆転していったのである。ということは、大山が強あれほどかったのは、升田の受けを学んでの受けだったからなのである。
升田の時代、最初に棋界に君臨していた名人は東京の関根金次郎だった。この関根の門に入って名をなした実力者に土居市太郎がいた。土居は子供のころのカリエスで片方の足が曲がらない。けれども、その強さは音に聞こえていた。
その土居が老齢となった師の関根に代わって阪田三吉と対戦し、これを破った。だから、升田の青少年期、実力ナンバーワンは土居だろうと言われていた。升田はこの土居の将棋の本に学んで将棋指しを決意した。
大阪の阪田三吉はそのころすでに60歳をこえていて、人気はあいかわらずだったが、もう勝負をしていなかった。将棋連盟とも袂を分かって勝手に名人を標榜していた。暴れん坊のように言われるが、まったくそうではなく、升田に言わせると、その指し手も慎重きわまりない手筋だったという。
本書はそういう升田が木村義雄に挑んで追いつめ、ついに香車を引く寸前まで辿りつきながら、これを実現できず、もはや大望これで潰えるというところで、大山康晴名人に香を引くところまで進むという経緯を中心に語られている。結局、大望はついに果たされたのである。途中、いくつかの名勝負の棋譜ものっていて、升田がどこで「勝ち」を掴んだかが升田の独特の解説で指摘されている。この手筋の解説は、さすがに「ひらめき」がものすごく、他の誰の指摘よりもおもしろい。
しかし、本書のなかの白眉はそういう将棋の話ではなく、升田が敗戦まもなくGHQに呼ばれて“講演”をしたときの顛末である。ここをどうしても紹介しておきたかった。
昭和22年の夏のことだったという。そのころ升田は上京するたびに朝日新聞の業務局長だった永井大三の世話になっていた。あるとき新聞社にいると、業務次長の窪川という男が、GHQに行って将棋の話をしてきてほしいと頼んできた。升田はそういうことなら、大成会の会長である木村義雄が引き受けるべきだろうと思ったが、ふと、むらむらして行くことにした。
いまの第一生命にあった司令本部に行くと、部屋に通された。ベタ金の偉そうな軍人が4~5人と通訳が待っていた。升田は開口一番「酒を飲ませてくれ」と言う。自分は5歳のときから酒を飲んでいて、人と話すときは酒を飲まなかったことがないという理由だ。アメリカ人たちは「わかった、日本酒はないが、ビールとウィスキーならあるが、どっちがいいか」と聞く。ビールを所望した。
これは升田の最初からの作戦だったらしい。迂闊に喋って言葉尻でもつかまれたら、まずい。ビールを飲んでいれば小便に立てるから、そのときに変な質問をかわす時間が稼げる。そういう作戦だ。ところが、いつまでたってもビールが来ないので催促をすると、目の前にあるという。缶ビールなのである。こんなものがあるとは知らなかった。あけて飲んでみると、これがまずい。「まずいビールだ」と大声で言ったら、みんなビクッとした。
質問が始まった。「日本には剣道とか柔道があって、武道とか武士道というものになっている。おかげでわれわれは沖縄の戦いで手を焼いた。武道は危険なものなのではないか」。
升田は答える、「そんなことはない。武道の武は戈を止めると書く。身につけてもやたらに外には向けず、おのれを磨くのが武道なのだ。武士道とは心づかいの道なんだ」。
また質問がある、「日本の将棋はわれわれがたしなむチェスとちがって、相手の駒を自分の兵隊として使用する。これは捕虜の虐待であり、人道に反するものではないか」。升田は、そうら、おいでなすったと腕を撫す。反撃のチャンス到来である。
「冗談を言ってもらっては困る。チェスで取ったら駒を使わないのなんてこそ、捕虜の虐殺ではないか。そこへいくと日本の将棋のほうは、捕虜を虐待もしないし、虐殺もしない。つねに全部の駒が生きている。これは能力を尊重し、それぞれにはたらきを与えようという思想なんだ。しかも敵から味方に移ってきても、金は金、飛車は飛車という元の役職のまま仕事をさせる。これこそ本当の民主主義ではないか」。
なかなかの説得力である。これで升田は勢いがついた。「だいたいあなたがたは、いちいち民主主義をふりまわすけれど、チェスのどこが民主主義なんだ? 王様が危なくなると女王を盾にして逃げようとするじゃないか。古来から、日本の武将は落城にあたっては女や子供を逃がし、しかるのちに潔く切腹したものだ。民主主義、民主主義とバカの一つおぼえのように言ってくれるな。将棋をよく勉強してほしい」。
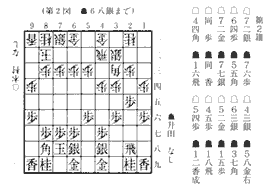
このあたりから升田はまずいビールで酩酊し、しだいに攻撃的になっていく。そのぶん説得力もあやしくなってくる。チェスだけでなく、将棋だって金銀歩兵で王様を守り、すぐに逃げ出すのを忘れている。とくに大山の穴熊将棋など、ただ王だけを守っている。それより、将棋には早々の「投了」というものがあると言えばよかったのである。
しかし、升田の勢いはとまらなくなったようだ。ついに「お前たち」とか「お前ら」とか「おんどれら」と呼び捨てにする。「お前らは、いったい日本をどうするつもりなんだ? 生かすのか殺すのか、はっきりしてくれ。生かすのなら、日本の将棋に習って人材を登用するのがいい。殺すというなら、俺は一人になっても抵抗したい。日本が負けたのは武器がなかったせいだ。俺はよその飛行機をぶんどっても、お前らの陣地に突っ込んでやる」。
通訳は汗びっしょりだったようだ。かれこれ、この調子で5~6時間を喋りまくったらしい。さすがに「もう帰っていい」というので、最後に注文を出した。これが、いい。ぼくはこの一節に唸ったのだ。
「巣鴨にいる戦犯の連中を殺さんでほしい。かれらは万事をよく知っており、連中を殺すのは字引を殺すようなものである。生かして役に立てる道を選んでもらいたい」。
この「連中を殺すのは字引を殺すようなものである」が、泣かせる。戦犯どころか、日本はこのあと、日本人が日本の字引を見捨てていった。これでは経済戦争ですら負けるのは当然である。日本はときに「香車を引く盤面」をつくる必要もある。



