父の先見


その歴史と諸形態
国書刊行会 2010
Ortwin Henssler
Formen des Asylrechts und ihre Verbreitung bei den Germanen 1954
[訳]舟木徹男
編集:伊藤喜孝 協力:阪内紀子・村澤真保呂・信友建志・実川幹朗 装幀:犬塚勝一
アダムとイヴはエデンの楽園を追われたのち、二人の子を産んだ。カイン(Cain)とアベル(Abel)である。兄のカインは土地を耕し、弟のアベルは羊を放牧した。二人がその成果を神なるヤハウェに供物として捧げたところ、ヤハウェはアベルが捧げた羊の初子に目をとめ、カインの農作物を軽視した。これを恨んだカインは野にアベルを誘い出して殺害した。
ヤハウェにアベルの行方を問われたカインは「知りません。私はアベルの番人なのですか」と答えたが、大地に流れた血はアベルの異常な死を示していた。ヤハウェはカインに「おまえは土に呪われている」と告げると、エデンの東にあるノド(ノデ)の地に追放し、耕作による収穫物から遠ざけた。けれどもカインがノドの者たちに殺されることを怖れたので、ヤハウェはカインに「誰からも殺されないための印」をつけ、「カインを殺そうとする者は7倍の復讐を受けるだろう」と告げた。
やがてカインはエノク(Enoch)という子をもうけ、ノドの地にエノクという名の町をつくった。そこはカインのしたいことが許容され、カインの罪が問われないところ(アジール)になった。一方、ヤハウェは子を失ったアダムとイヴを不憫に思い、アベルの代わりとしてセト(セツ)を授けた。時が移り、セトの9代目にノアが登場した。人類が40日40夜におよぶ大洪水に見舞われたとき、すでにノアは年老いていたが、ゴフェルの木で方舟をつくって民と動物を救った。
以上は旧約聖書「創世紀」に出てくるカインとアベルをめぐる有名な話で、日本でも有島武郎(650夜)の『カインの末裔』の素材になっているほどなのだが、この話、よくよく読むといくつもの謎がのこる。
たとえば、なぜヤハウェは土地の収穫物より牧畜に関心をもったのか。あの時代に、農耕民よりも動きまわる遊牧民が重要だったということだろうが、なぜそうなったのか、はっきりしない。「ユダヤの民」という、新たな部族をつくりあげるためには、そういう生産観や労働観が必要だったのだろうか。
カインの働き方が蔑まれたとしても、それだけで弟を殺したくなったのかも、どうにも唐突だ。ふだんから兄弟の仲がよくなかったのか、貢ぎものや捧げものに区別があったのか。きっとユダヤ教の社会の初期制度の何かを暗示しているのだろうが、兄による弟殺しはよっぽどだ。もっと複雑な理由があったのだろう。
もっとも弟殺しはカインだけのことではない。古代ローマを建国したロムルスも、弟ゲタと争ったカラカラ帝も、始皇帝も唐の太宗(李世民)も、頼朝も尊氏も信長も、弟を殺した。逆はあまりない。頼朝の義経への憎悪は、日本人に「判官びいき」をふりまくほど有名になったけれど、その奥の真相や意図には、説明しがたいものがある。
ちなみに動物学や行動生態学では兄弟姉妹殺しを「ジブリサイド」(siblicide)といって、鳥類に多いことがよく知られている。鳥類は成長の途中に兄弟姉妹がひんぱんに殺されてしまうのだ。
追放されたカインになぜ「殺害を逃れるための印」がつけられたのかということも、気がかりないきさつである。その「しるし」はどんなものだったのか。スティグマ(聖痕)のようなものなのか、刺青のようなものなのか、それとも差別的な服装なのか、魔法のような呪いなのか。こういうことも判然とはしない。
カインはノドという町をだんだん都市に仕立てていったと察せられるのだが、なぜそこは罪が問われずにすんだのか。無法都市だったわけではあるまい。当時すでに原始都市っぽいところにはなんらかの免罪力があっただろうと思われる。
これらについての答えは「創世紀」の記述からだけでは推測がつかない。わかることは、ユダヤ社会の初期に労働が分割されていただろうこと(農業と遊牧)、カインが人類最初の殺人者であったこと、そのカインが「しるし」を受けたことはカインが最初の「神から選別された者」になったのだろうということ、そしてカインとともに「聖なる避難所」としてのアジールが生まれたのであろうということである。
そう、カインとアベルの物語はアジール発生の物語としてこそ読めるのである。ただ、そのように理解はされてこなかった。
日本の80年代の話になるが、中世歴史学とその周辺でアジール談義が熱くなったことがあった。
いまは懐しい阿部謹也の『中世を旅する人びと』(平凡社)や『刑吏の社会史』(中公新書)、網野善彦(87夜)の『無縁・公界・楽』(平凡社)や『日本中世に何が起きたか』(日本エディタースクール出版部)、および網野・阿部の対談『中世の再発見――市・贈与・宴会』(平凡社)などが話題になった。そこにはオルトヴァン・ヘンスラーが強調したアジールの議論がしばしば取沙されていた。ただし、原著が翻訳されていなかったせいなのか、ヘンスラーがどのようにアジールを定義したかというようなことは、あまり話題になっていなかった。
早くに西洋社会のアジールを紹介していた平泉澄の『中世に於ける社寺と社会の関係』(至文堂)も、ヘンスラーにはふれていない。そういうことを引き受ければたいていは調べあげてみせるはずの今村仁司も、のちの『排除の構造』(青土社→ちくま学芸文庫)などはそのことに踏みこんでもよかったのに、さらっとしていた。どうしてそういうふうだったのか、そのころの学問事情は知らないが、日本は“インスラー抜き”のアジール議論でずうっと湧いていたということになる。
で、2010年になって、やっと舟木が原著の翻訳に名のり出たわけである。翻訳を買ってでただけでなく、たいへん詳しい解説も付けた。
もっとも、その舟木がヘンスラーの本書のことを知ったのが、小俣和一郎(470夜)の『精神病院の起源』(太田出版)だったというのは意外だった。中世以来の精神病棟がアジールであることについては、小俣以前にアーヴィング・ゴッフマン(1317夜)の『アサイラム――施設被収容者の日常世界』(誠信書房)が記しているのだが、これまたあまり話題になっていない。まあ、それほどに日本の思想界ではヘンスラーのアジール論について疎かったということだ。
原著はゲルマン社会のアジール法についての研究書で、犯罪者や逃亡奴隷などが墓地や教会などに逃げこんだ場合、かれらの権利(アジール権)をどのように処理してきたかをめぐった法制史学の本である。
ヘンスラーは1923年のシュトゥットガルトの生まれで、学者というより司法行政のプロだったようだ。長年にわたってバーデン・ヴュルテンベルク州の司法省で判事などをしているうちに、ゲルマン法に埋もれていたアジール法の実態を明るみに出すことを思いついた。
ヘンスラーによるアジールの定義は次のようになっている。「一人の人間が、特定の空間、人間、ないし時間と関係することによって、持続的あるいは一時的に不可侵なものになる。その拘束力をそなえた形態をアジールという」。
ドイツ語のアジール(Asyl)はギリシア語の「不可侵」「侵すことができない場所」を意味する asylos や asylon から派生して、ゲルマン社会で「庇護」や「避難所」の意味をもつようになった。その地域の統治権力が及ばないところ、そこがアジールとされた。アジールは「カインの末裔」が逃げ切れるところとして歴史化されていったのだ。
なぜ、そうなったのか。古代中世のゲルマン社会には「血讐」の習慣があり、ある者が殺害されると、その血縁者が復讐をはたすことが慣行化していた。国家による公権が確立していない時代では、各地の「血讐」の慣行が自力救済の一助となったからだ。
しかし、これでは復讐の連鎖がおこりかねない。そこでアジール法によってその抑止がはかられた。カインの「しるし」(その実態はあいわらずあきらかになっていないままだが)は、やがてアジール法に取って代わったのだ。
ヘンスラーはアジール法が適用された実態を調べていくうちに、そこにひそむ歴史的意義に気がついた。法制としてのアジール法のあれこれよりも、その裏側に動くアジールの社会文化的な意図に関心をもったのだ。そこでヘンスラーはアジールの歴史を調べあげ、①宗教的・魔術的段階、②実利主義的な段階、③退化と終末の段階、の3段階に分けてあきらかにしていった。3段階について、かんたんに説明しておく。
宗教的・魔術的段階のアジールは、原始古代において恐怖と不安を乗りきるためのものである。原始古代人は自然の脅威、獣類の脅威、病気の脅威、死の脅威などから逃れるため、超越的な霊力を想定し、それにすがるための強力な観念をつくりあげた。ヘンスラーはそれを「オレンダ」という用語で説明する。
オレンダは北米イロクォイ族が信じていた霊力のようなもので、「あらゆる事象を規定する強い効力を信仰する力」のことをさす。ヘンスラーは当時の宗教学者ププィスターがオレンダにもとづく観念状態を「オレンディスムス」と名付けたことを踏襲して、アジールはそうした原始古代特有のオレンディスムスによって発生したとみなした。
オレンディスムスが律する古代社会や未開社会では、祭場・墓地・酋長・祭司・戦士・シャーマンなどがオレンダをもっているとみなされた。そのオレンダに接した者にもオレンダが感染し、転移すると考えられた。「エンガチョ」がおこるのだ。エンガチョによる感染はジェームズ・フレイザー(1199夜)の『金枝篇』以降の人類学では「類感呪術性」などともよばれる。
古代オレンディスムスはオレンダが強くはたらく場所をアジール化し、その前後でのやりとりにタブーを発生させたのである。
やがてアジールは実利主義的な段階にすすんでいく。領主や国王の力が強くなり各地に広まっていくと、それまでのアジールが宗教的な枠組から世俗国家の枠組に組み替えられていった。
これは定住生活が確立していったこと、農耕社会が地域的に確定されたこと、商業圏が発生してその商圏ネットワークと職人ネットワークができあがってきたこと(定期市やハンザ同盟)、特定の家系が力をもつようになったことなどによるもので、ここにアジールは世俗権力のアジール法によって保護され、維持されることになった。
ヘンスラーはこうした実利化したアジールが、犯罪者のためのアジール法、外国人(流民や移民)のためのアジール法、奴隷のためのアジール法などに分かれていったことをつきとめた。
その後、これらのアジール法が法治国家の管轄になり、新たな法制度に切り替えられていくと、アジールそのものが特色を失い、退化と終末の段階になっていく。フランスでは1539年に、イングランドでは1624年に、事実上アジールが廃止されている。
ヘンスラーはこう綴る。「神聖な中心点のまわりに集まった祭祀共同体から、国家的な目的団体が生成し、それが自らの目標実現のために合理的な手段を発達させ、国家の完成度がある段階に達すると、アジール法はその存在理由と意義を失った」。
だいたいこんなところがゲルマン社会における「アジールの発生と退行」のあらましだが、やはり興味深いのはオレンディスムスがどのように網を拡げていったのかということだ。それについてヘンスラーは、オレンダに当たる言葉は古ゲルマン語では「ハイル」(Heil)だろうことを指摘する。
ハイルは「平安、無事、健康、繁栄、幸福」に向かうことを示す言葉で、神的な空間・人物・時間に充ちているものをいう。漢字一字をはめるなら「感!」というあたりだろう。「万歳!」にも近い。ゲルマン社会では、そのハイルに接触したものも軒並みハイルになるとみなされた。強力なエンガチョだ。
ハイルが充満しているところや人が「聖性」(Heiligkeit)をもち、そこに匿われているものを「聖なるもの」(Das Heilige)にしていった。ハイル、ハイリッヒカイト、ハイリゲとみなされたものや場所は「一時の平和」を保証し、血讐を遠ざけるアジールになれたのである。
こうして、森のハイル、氏族のハイル、墓所のハイル、祭場のハイル、集会のハイル、家のハイル、境界のハイル、迷路のハイル、市のハイル、町場のハイルがすだくところ、けっこうな数のアジールがヨーロッパに生まれていった。日本中世でも、網野が挙げたような「無縁」や「楽」が生まれていった。
そうしたアジールでは、たいていは「通過儀礼」や「聖なる犠牲」や「治癒」や「交換・贈与」が生じた。ドイツ語の治癒を意味するハイルンク(Heilung)はハイルの暴走と沈静の様子をあらわしている。
このあたりのこと、ヘンスラーばかりが考察したわけではない。アルノルト・ファン・ヘネップの通過儀礼論、ヴィクター・ターナーのリミナリティ論、マルセル・モース(1507夜)の贈与論、ミルチャ・エリアーデ(1002夜)のイニシエーション論、さらにはルドルフ・オットーの『聖なるもの』(岩波文庫・創元社)、ルネ・ジラール(492夜)の『暴力と聖なるもの』『世の初めから隠されていること』『身代わりの山羊』(法政大学出版局)などにも、それなりの言及がある。
さて本書には、さきほども述べたように訳者の舟木徹男による詳細な解題「アジールの近代」が付いている。ぼくが知るかぎり、いまのところ最も浩瀚なヘンスラー論やアジール論になっている。いろいろ解題されているが、なかで次の流れが重要だ。多少を補って、解題の解題をしておく。
アジールのルーツは原ゲルマン社会にも原ユダヤ社会にもあった(むろん古代中国にも古代日本にもあった)。原ゲルマン社会の原アジールは「森」である。ぼくが阿部謹也さんに会っていたころ、阿部さんは「フランク王国なんてまだおっかない森ばっかりですよ。ゲルマン系のサリ族が占拠した土地です。そこにアーヘンなんていう都を、穴ぼこをあけるようにむりやり穿いたんですよ」と言っていた。
そこはヘンゼルとグレーテルが迷い、長靴をはいた猫やロビン・フッドが君臨し、ファウスト博士の魔術がかかる地域であった。また魔女や七人の小人が棲む森でもあった。
ゲルマンの森は平地との境界領域をかたちづくっていた。共同体から追放された者はしばしばそういう森に逃げこんだ。原ユダヤ社会から追放されたカインの宿命を想わせる。カインはおそらく森の中を穿ってノド(ノデ)をつくったのであろう。こうして古代中世を通じて、森の一隅を穿つかのように点々とアジールができていった。
当初にアジールをつくった者は、ハイルやオレンダを帯びながらも共同体の摂理や機序を破った者だった。それゆえそうした者がつくったアジールでは、不法や犯罪が帳消しにできた。そうすることによって、不法や犯罪の悪しき連鎖が防げるとみなされたからだ。
そのためアジールには第2、第3の不法者や犯罪者が次々に逃げこみ、よりいっそうの避難拠点に足るアジールとしての性格を強めていった。アジールには聖俗両方が流れこんでいったのである。中国では『水滸伝』の舞台にあたる梁山泊などがそういうアジールにあたる(438夜参照)。
日本のアジールについては網野の『無縁・公界・楽』や夏目琢史(1559夜)の『アジールの日本史』(同成社)、また最近の著作だが、伊藤正敏の『アジールと国家』(筑摩選書)などが詳しい。中世の寺社勢力の近辺には、比叡山や高野山や各地の修験の山のネットワークの支点のように、いくつものアジール(無縁所)ができていったのである。そこには「別所」や「散所」や「駆込寺」とよばれるスポットも含まれた。
いま、ぼくは近江の有志たちと「近江ARS」というプロジェクトを準備しているのだが、そこには三井寺(園城寺)のいくつもの別所が息づいている。山科、逢坂山、三井寺一帯は別所だらけだったのである。
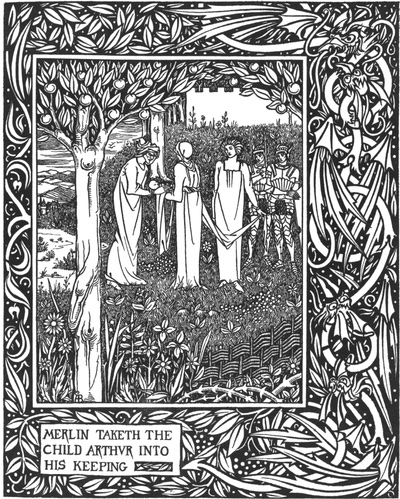
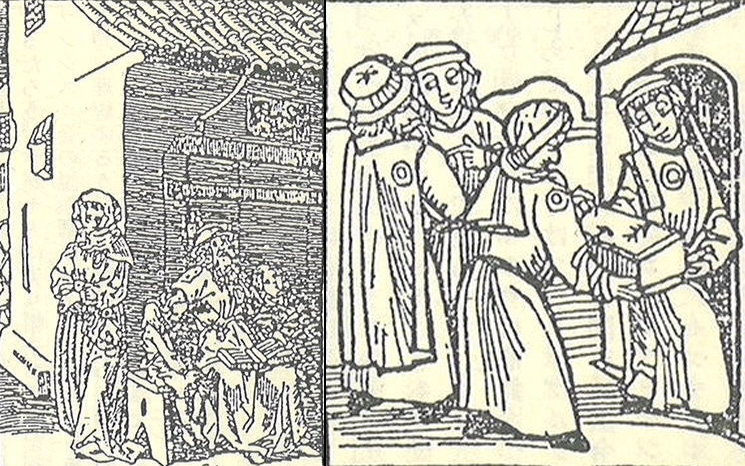

いまさら言うまでもないことだろうけれど、そもそも「聖なるもの」は「正と邪」の両面性や「聖と俗」の両義性をその内側に孕んでいる。ルネ・ジラールはそうした聖性を「人間がそれを制御できると思いこめば思いこむほど、それだけ確実に人間を制圧するいっさいのもの」と定義した。
なかなかうまい言い方だ。これは「聖性」には、邪や俗が最も劇的に加速して「暴力」にいたる力が半ば隠されていたということを告げている。ジラールはこの見方に徹して、社会における犠牲や供犠の本質を喝破した。しかしジラールには見落としていたことがあった。聖性と暴力の両面性や両義性は、二つながらアジールとしていかされていたということだ。
暴力には相互に認証された暴力や、第三者が立ち会う暴力がある。たとえば決闘だ。決闘はその場をいっときのアジールにする。ドイツ語ではこういう暴力のことを「フェーデ」(Fehde)と言った。
たんに暴発した暴力が発端したのではなく、暴力による決着のための措置をみとめることがフェーデだった。したがって決闘では第三者が巻きこまれることがない。フェーデは暴力の波及を抑止できると考えられたのだ。
つまりフェーデは自力救済のための暴力だったのである。10世紀のドイツでは、こうしたフェーデが頻繁におこっていた。
ところがやがて、つまらぬ言いがかりをつけて相手方に決着を迫り、身代金や掠奪を目的とするような、フェーデを隠れ蓑としてつかう暴力行為が目立ってきた。ゆすり、たかり、詐欺が暴力行為を伴うことになった。ヨーロッパに広まりつつあるキリスト教社会においては、こういうフェーデの恣意的な歪曲は「神の平和」(Pax Dei)を乱すものだった。世俗国家としてもこの歪曲は統制すべきものになった。こうしてここに数々のアジール法が関与したわけである。
ちなみに、互いに宣戦布告をしあう戦争も、こういうフェーデ型の相互暴力行為を広域で認証したものだとみなすことができる(今日においてもこの事情は変わらない)。また、戦争における戦場も特別なアジール化をおこしているとみなすことができる。

ヨーロッパではフランク王国の時代とその瓦解分解以降の時代で、歴史が大きく分かれる。アジールの歴史にとってもこの分岐点が大きい。
フランク王国以降、ひとつには、ヨーロッパ各地で自治都市が生まれていった。背景には三圃(さんぽ)農法の普及で農業生産力が高まり、定期市が開かれる場所に集まってきた遠隔地商人たちによって居住区を拠点とした都市が発達してきたことが与かった。
商人たちは聖俗権威の両方から承認をえながら少しずつ発展していったのだが、そのうち税の取り立てなどをめぐって領主と争うようになり、商人が手工業業者や行商人とのあいだに誓約(コンユーラーチオ)を結んで、しだいに自治権を主張する中世都市を形成していくようになった。これは自治都市そのもののアジール化を促進した。
もうひとつの変化としては、フランク王国の分離以降、キリスト教的な「神の平和」ではまにあわなくなってきたということがある。世俗国家による平和、すなわちフェーデを上から制限するか、禁止するかする「ラント平和」が提示される必要が出てきたのだ。1235年のシュタウフェン朝のフリードリヒ2世によるマインツでのラント平和令(Landfrieden)が、ドイツ語による最初のラント平和の文面として残る。
ラントは州単位による国家のことをいう(ブレーメン、ハンブルク、バイエルン、ヘッセンなど)。1495年のマクシミリアン1世の永久ラント平和令は、ヨーロッパの多くのフェーデを完全に禁止に追いこんだ。 ここにアジールは変貌するか、世俗国家の手にわたすしかなくなったのである。
歴史が近代に向かうにつれ、アジールをめぐる約束事にもいくつかの大きな制度変更が加わっていった。
第1には、訴訟裁判が前面に出てきた。それまでは親告訴訟であったのが糾間訴訟になっていった。個人の有責性を問い、治安の確立と犯罪を予防するための刑罰が確立していったのだ。
第2に、市(市場)の充実と貨幣による交換経済がしだいに普及して、それまで贈与や互酬によって保たれていた「ハイルを伴う経済行為」が薄くなっていった。モースの『贈与論』はその経緯をつぶさに綴った。
第3に、このことはけっこう特筆できるのだが、個人や女性が浮上してきた。呪術的な共同体から個人が独立する準備ができてきて、キリスト教社会での「告解」が一般化していったのだ。ヘンスラーは(阿部謹也も)、こうした個人の出現をアイスランド・サガなどを材料にして読み解いた。フーコーはそのへんの事情を次のように説明した。
「個人としての人間は、長らく他の人間たちに基準を求め、他者との絆を顕示することで自己の存在を確認してきた。ところが、彼が自分自身について語りうるか、あるいは語ることを余儀なくされている真実の言説によって、他人が彼を認証することになった。真実の告白は、権力による個人の形成という社会手続きの核心に登場してきたのである」。
女性も特別に議論されるようになった。ヘンスラーはアジールにとっては魔女(Hexen)の強調が重要な事態になったと解釈した。魔女は男性社会には見えない出産力や性的魅力や霊感をもっているとおぼしく、とくに才能あふれる女性には、共同体や都市の中では「森の魔力」が日常社会の真ん中にそのままもちこまれたとみなされた。こうして公権力は「魔女を裁く」という判定機能を発揮するようになった。
こうして魔女狩りや魔女裁判の断行され、多くの魔女狩りがアジールの駆逐に結びついていった。ナサニエル・ホーソーン(1474夜)の『緋文字』はアメリカ前近代17世紀の魔女裁判の悲劇を描いた傑作だった。
各地に主権国家が確立していくにつれ、魔女狩りは終焉し、アジールがなくなっていった。
アジールの後退や終息は、宗教革命の進行や科学の発展とも結びついている。プロテスタンティズムが「天職」や「勤労」を称賛し、それが各地の市場経済の促進に役立っていったことも、アジールの役割を剥いでいくことになった。
各地に収容所や監獄が林立していったことは、アジールを縮めさせた。アジールはたくみに精神病棟(アサイラム)に変更されていったのだ。
それでどうなっていったかといえば、実は「啓蒙」が躍り出た。ルソー(663夜)の啓蒙思想は「自然人」を称揚したが、それはかつての「こわい森」を新たな自然観に切り替え、自然権を社会に導入する装置になっていったのである。
それなら近代国家とともにアジールはなくなったのかといえば、そうではない。近代社会は感性や想像力や文芸や劇場の中にアジールを求めた。舟木はそれを「情緒的避難所」とよんでいる。いまでは、それは心理的避難所ともなって、「うつ」や「トラウマ」を塗り重ねている。
アジールもアジール的なるものも、おそらくなくなりっこないだろう。われわれが空想やフィクションやアイドルに託すもののすべてに、なんらかのアジール性がこびりついているからだ。本書には言及されていないけれど、すでにスポーツ競技にも芸能社会にもサブカルチャーにも、アジールの特異性がさまざまに頻出しているのである。
そこには「カインの末裔」も「魔女狩り」も、今後ともおこりつづけていくだろうとも、言っておかなければならない。今後はネット社会にもアジールや別所が必要になるにちがいない。

⊕『アジール―その歴史と諸形態』⊕
∈ 著者:オルトヴィン・ヘンスラー
∈ 訳者:舟木 徹男
∈ 発行者:佐藤 今朝夫
∈ 発行所:国書刊行会
∈ 装丁:犬塚 勝一
∈ 印刷所:藤原印刷株式会社
∈ 製本:株式会社ブックアート
∈ 発行:2010年7月1日
⊕ 目次情報 ⊕
第一部 アジール法の諸形態
第二部 異教ゲルマン人におけるアジール法の諸形態
解題―アジールの近代―
訳者あとがき
原註
訳註
解題註
文献および資料一覧
索引
⊕ 著者略歴 ⊕
オルトヴィン・ヘンスラー
1923年シュトゥットガルト生まれ。長年バーデン・ヴュルテンベルク州の司法行政に携わり、同州の司法省で判事および省庁ディレクターとして活動。63歳で定年退職を迎え、現在もシュトゥットガルトに在住。
⊕ 訳者略歴 ⊕
舟木 徹男(ふなき・てつお)
1973年石川県生まれ。1996年京都大学文学部卒業。2007年京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程単位取得満期退学。現在、龍谷大学非常勤講師。