ヘンゼルとグレーテル
新潮文庫(グリム童話集II) 1967
Jakob Grimm & Wilhelm Grimm
Kinder und Hausmarchen 1812(第1版)~1857(第7版)
[訳]植田敏郎
おばあさんの腹を裂くオオカミ。
コスプレ・切断・相姦・嬰児虐待。
誘拐・殺人・嘘つき・騙しあい。
グリム童話は残酷なのか。
そうではあるまい。
われわれのほうが残酷になりすぎたのだ。
もう一度、メルヘンに戻りなさい。
セイゴオ流グリム論、初披露。
あるとき、ぼくと妹はつながっていた。
何歳のときだったかは正確に思い出せないのだが、ぼくが9歳前後のころだったと想う。妹の敬子は6、7歳だ。妹とつながっていたといっても、それは虫取りに耽った一夏(ひとなつ)か、何かの他愛もない遊びに夢中になっていたときのことで、その記憶のなかでは二人を分け隔てるものは、なんらなかった。
その後、妹はぼくとつながっていることを、しばしば取り戻そうとした。それはたとえば「お兄ちゃん、お風呂行こうよ」とか、「お兄ちゃん、ライオンになって」といった言葉の口調の甘さでわかった。外に出るとすぐに腕につかまって歩こうともした。それがやけに甘ったるいので、妹が兄にしか放出しないシスター・フェロモンのようなものも感じた。ぼくのほうは、そのたびに照れた。
妹はそういう素振りを思春期になるまで発揮したが、ぼくのほうは、妹を兄の心身が養った季節がすでに過ぎ去っていることを知っていた。何かが幼なごころとともに失われていったのだ。
大正14年の「婦人公論」十月号に、柳田国男(1144夜)がやや長めの『妹の力』を書いた。そこで柳田が日本の村落の兄と妹が見せる独得の親しみ深さに関心を寄せたことについては、第537夜の『ヒメの民俗学』のところで指摘しておいた。
柳田はあるとき岡山の自分の故郷に久々に戻って、家々の妹が村落共同体の場で兄と自由にふるまっていることに注目し、大正時代がそういう光景を許せるようになったのは、日本の家の本来性にまつわるものがやっと回復しているせいだと判断した。兄が男性ゆえにもたざるをえない孤独感や寂寥感のようなものを、妹が快活にふるまうことによって深く補償することが、日本の村落や家族が古代からもってきた「妹の力」だというのだ(このばあいの「妹」は妻のことではなく、まさに妹のことをいう)。
アニマな兄とアニムスな妹が、ときにアニムスな妹とアニマな兄になる。いったいどんな例を思い浮かべればいいだろう?
いまは柳田民俗学の深部には入らずに言うが、これをわかりやすく理解するなら、「フーテンの寅と妹のサクラの関係」なのである。あれが柳田の言うニッポンの兄妹の例なのである。倍賞千恵子のサクラがときおり兄の寅さんの前で見せる、その場を救うような明るさ、寅さんがその妹に託している万幅の信頼、「それを言っちゃおしまいよ」と言う兄を「家庭」につなぎとめていく妹。その関係がニッポンの兄妹が万葉以来秘めていた「もうひとつの家系感覚」というものなのだ。
後日談をしておく。
ぼくは実の妹についてはその親密感を照れて、ひょっとして発展していたかもしれない妹との濃密なコラボレーションを失うようになってしまったのだが、長じてはそのぶん、“仮の妹”がそばにいてくれることを何度も希求するようになっていた。これがぼくの恋学(れんがく)の発祥である。いまでも、それは変わらない。
こんな話を枕にして、では、今夜はグリム童話のことを書く。
枕に続いて兄妹の話から入ってみるが、まずもって『ヘンゼルとグレーテル』というあの童話においては、実はヘンゼルとグレーテルは一人の子供なのだということを言っておきたい。一人の子供が兄のヘンゼルと妹のグレーテルに分身した。
その名もずばり『兄と妹』というグリム童話もあるのだが(新潮文庫版第2巻、岩波文庫版第1巻)、この話でも森に入った兄と妹は、兄が泉を飲んで鹿に変身する役割をもち、妹が魔法を解く役割を分担しながら話がすすむものの、実は兄と妹とで1セットなのである。『六羽の白鳥』は魔法にかけられて鳥になった兄を妹がきびしい試練をうけながら助けるお話だが、結末がそうであるように、この兄妹は中世の分身レプリカントであって、ゲルマニックな合体ロボなのだ。
こういうことはグリム童話のなかではごくふつうのことで、ちっとも驚くにはあたらない。それ以前に昔話や民話を採集したイタリアのジャンバティスタ・バジーレやフランスのシャルル・ペロー(723夜)やヨハン・ムゼーウスなどの再話集のなかの多くでも(この3人がグリム童話の先行者であった)、兄と妹はほぼ一心同体になっている。分身状態だ。
いや、兄と妹だけではない。『ヘンゼルとグレーテル』では継母と森の魔女は同一人物であり、『赤ずきん』では赤ずきんとおばあさんがほぼ同一人物である。それらのキャラクターは口伝えの物語のなかで分かれたにすぎない。
『フーテンの寅』がそうであるように、口伝えを重視する物語(かつてなら昔話や民話や説話)には、こうした「一人で二役」、「二人でひとつ」、「お妃で魔女」ということはしょっちゅうなのだ。そこが口伝えのいいとこだ。寅さんもまた電話や葉書においてもつねに口で伝えられることだけを信じた。伝えまちがいなんて恐れなかった。むしろ口で伝えようとしないことのほうが、寅さんにとってはまちがいなのだ。
いきなり意外なことを示したかもしれないが、こういうことは中世このかたヨーロッパの村落社会がかかえこんだ民衆の口承性にもとづいている“しくみ”だった。“知恵”だった。
そのころの口伝えの昔話や民話では、つねに口伝え独得の編集がなされ(むろん日本も同じだが)、そのなかで最も受け入れやすい「型」に向かって話が定着していくという傾向があった。
その「型」は数え切れないほどあったわけではない。3つとか5つとか7つといった比較的少ない「型」になっていて、その「型」をもとに、話をそれぞれふくらませることにみんなが熱中した(ウラジミール・プロップは魔法的昔話には一つの「型」しかないとまで言い切った)。
ぼくの用語でいうなら、これはさしずめ「物語母型」(ナラティブ・マザー)の作用というものだけれど、それが昔話や民話においてはごく少数の口承用の母型として機能した。口伝えとはそういうものなのだ。複雑すぎるものには向いてはいない。
たとえば、そもそもの話の母型が「一人の女の子が森に行きました」というものだったとすれば(これはとてもわかりやすい母型だ。なぜならヨーロッパの村落では、少女が森に行って日暮れまで帰ってこなかったことなど、いくらでもおこっていたからだ)、そこにお兄さんを加えれば『ヘンゼルとグレーテル』になり、二人の姉を加えると『灰かぶり姫』(シンデレラ)になったのである。おわかりか。
口伝えはさらにヴァージョンをふやす。もっとたくさんの兄と姉をふやせば、それがたとえば『親指小僧』となり、さらに、その女の子を森の小人たちのところに行かせれば『白雪姫』のお話になった。あとはお察しの通り、森の中の女の子がおばあさんのところへ行ってオオカミと出会うことにさせれば、かの『赤ずきん』が仕上がっていく。おわかりか。
昔話や民話や説話は母型(マザー)をもっていただけではなかった。いくつかのごく容易に見いだせる法則性のようなものももっていた。
たとえばアクセル・オールリクは、民話というもの、話の導入部ではたいてい最前部を優位にし、クライマックスでは最後部を優位にする傾向が強いことを発見し、マックス・リュティは別の法則に気がついた。主人公がやたらに小さいこと、容貌や活動が目立たないこと、みんなから馬鹿にされていること、能力が劣っていると見えることといった特徴は、すべてそれがすっかり逆転される可能性をもった仮象であるという法則だ(みなさん、自信をもちなさい)。
むろんそんなことは読者は先刻承知のこと、昔話や童話には「負の作用」が真実の価値のための伏線なのである。
このほかにも数々の童話論者や口承文芸学者があきらかにした法則があるけれど、今夜はそれらにはいちいち触れないことにする。ナラトロジー(物語学)で童話を解くのも一興だが、グリム兄弟にはそういう意図がなかったろうから、ここでは扱わない。
それよりもここでは、1985年を挟んだグリム兄弟生誕200年を記念して世界各地で勃興したグリム童話論がこぞってあげた特徴があったことを指摘しておく。議論するほどのことはない特徴だけれど、一応は書いておく。
それは、ごくありきたりな指摘なのだが、グリム童話には切断、幼児遺棄、嬰児殺害、親殺し、カニバリズム(食人)といった残酷な素材があまりにも溢れかえっているのではないかということだ。
日本でもその手の議論が喧しかった。野村滋のグリム童話論には「子供に聞かせてよいか」というタイトルがつけられたし、池内紀が訳したグリム童話の解説は、イリング・フェッチャーの「グリム童話は完全犯罪の話が多すぎる」の紹介にやたらに徹していた。
たしかにグリム童話には恐るべき犯罪が満ちている。そのため、登場人物はとうてい尋常な日々をおくれない。『灰かぶり姫』のシンデレラの姉たちは鳩に目をつつかれて失明し、『歌う骨』では弟が殺され兄は袋に入れられて水に沈められて水死する。
『白雪姫』だって、毒リンゴを食べさせるという和歌山カレー事件のような他殺計画もあれば、「真っ赤に焼いた鉄の靴で死ぬまで踊らせる」という残酷な仕打ちも計画されている。『なでしこ』では八つ裂きにあい、『十二人の兄弟』では煮え立った油の樽に放りこまれてしまう者たちがいる。『ねずの木の話』では男の子の頭が刎ね落とされ、それを細かく刻んでシチューに煮込んでいる。
いったいどうしてこんなふうになったのか。グリム兄弟の好みだったのではないかという意地悪い指摘もあるほどだが、しかし、これらが残酷だというのなら、マスメディアの報道する20世紀や21世紀のニュースこそ残酷の極みばかりが選ばれているというべきなのである。
そもそも昔話や民話は、村落がのんべんだらりとしている安閑としたところからは発生しない。
洪水や飢饉があったり、疫病が通りすぎたり失火があったり、領主の苛酷な取り立てがあったり、急に牛や山羊がおかしくなったりするうちに、独得のお話のかたちをとった。残酷がテーマになったのではなく、そうしたよんどころない「負の状況」が物語をつくったのだ。
『ヘンゼルとグレーテル』でも、この話はあきらかに樵(きこり)の両親が暮らしていけなくなってわが子を森の中に捨てるという導入から始まっている。「あるとき、国ぜんたいにものすごい飢饉がおそいました」とあるように、この両親からすれば明日のパンも確保できない苦境の日々なのだから、子供が餓死してもしょうがないという判断だ。それならせめて森に放逐したい。森には危険もあるが、ひょっとすると救済力もあるからだ。そういう判断なのだ。きっとそれは中世の村落のやむをえない「間引き」の習慣だったのである。

以上で推測がつくように、昔話や民話のお話の発端の多くは、たいていはのっぴきならない動機が変形したものだった。
しかしそこから先の筋書きは、必ずしも現実や事実にはもとづかない。ヘンゼルとグレーテルを森で待ち受けていた老女が、ヘンゼルを格子のついた小屋に放りこんだのは、お話のなかではヘンゼルをぶくぶくに太らせ、おいしくしてから食べようという老女の魂胆になっているのだが、こんなことは魔女伝説にまつわる想像力がつくりあげたもの、そんな出来事が一回でもおこっていたわけはない。民衆が勝手につくりあげたお話だ。
ましてお菓子の家などあるはずもなく、そこにあるのは「行った者と帰ってきた者の関係」の話とか「行きはよいよい、帰りはこわい」という話とか、「しばらく見えなかった者が成功者になっていた」(三年寝太郎型)という話とかの、物語母型という見方からすれば一種の「往還マザー」をつかっての話がさまざまにヴァージョンを膨らましただけだった。
けれども、そのヴァージョンの荒唐無稽こそが童話というものなのである。そこにはいつもとびきりのアイディアも散りばめられる。
ヘンゼルが森に行くときに小石を落としておいて帰り道の目印にしたという知恵といい、二度目はパン屑を落としたところ鳥たちが啄んで失敗した顛末といい、屋根がパンで窓が砂糖でできているお菓子の家といい、童話というものはずいぶんファンタジックな謎かけとギミックと成功失敗のヤジロベー的な案配(お話の貸借対照表だと思えばよろしい)をうまく採り入れるものなのだ。
だから昔噺や民話では発端と結末は、途中経過とはべつなのである。ぼくの用語でいうのなら、途中経過は「アワセ・キソヒ・ソロエ」になっている。それぞれの土地に長く暮らしてきた者たちが、自分たちの環境と風土と氏神とさまざまな忘れがたい出来事に照らして、お話のためのメイキング(作成)とマッチング(照応)をくりかえしたのだ。
童話とはそういうものである。それゆえ「グリム童話はどうして残酷なのか」ということだけを話題にするのはつまらない。途中経過が残酷でない童話など、日本の昔話の『カチカチ山』や『舌切り雀』や『花咲か爺』がそうであるように、特別に目立ったにすぎないと思ったほうがいい。しかも、多くの昔話を読んでみればすぐわかるように、むしろ残酷ではない童話のほうがずっと多いのである。
別の観点から見ると、ふーん、そういうものかと興味深くさせられることもある。プロの語り手たちの調査によるのだが、子供たちの多くは首が落ちたり、手足が切断されたり、魔女が殺されることをほとんど怖がることがないというのだ。ペローの『青ひげ』をおもしろがる子供がいても、これを怖がった子供はいなかったというイギリスの調査報告もある。
それならグリム童話とは何なのかということだが、これについては、童話のいちいちの内容を問題にするというよりも(それはそれでナラトロジーとしても文化人類学としてもおもしろいけれど)、そもそもグリム兄弟がなぜメルヘン(メールヒェン)を集めて編集することになったのかということを見たほうがいい。
グリム童話は、のちにそのことの理由を指摘するつもりだが、今日なおふえつづけている一般の童話や絵本とちがって、あの時期のドイツに生まれたということが重要なのである(ちょうど大正7年前後から始まった日本の童謡が寂しさや悲しさばかりを歌ったように)。そこに新たな焦点をおけば、そこから出るプリズムに、グリム兄弟はなぜアルニムとブレンターノという二人のとびきりのドイツ浪漫派に出会うことになったのかとか、兄弟はどのようにメルヘンを集めたのかとか、あるいはそのメルヘンにはどの程度手を入れたのか(編集したのか)とか、さらにはそもそもメルヘンとは何なのかということからグリム童話の正体が見えてくる。
それにはグリム兄弟の日々を多少は追ってみることだ。
今夜は詳しいことはともかくとして、ごくかんたんな生い立ちから見ておくが、グリム兄弟はフリードリッヒ大王時代の末期、ヘッセン侯国の官吏の家に生まれた。母親のドロテーアも官吏の娘だった。
6人の子供のうち5人が男で、1785年生まれの二男のヤーコプと三男のウィルヘルムは年子だった(この二人をグリム兄弟という)。晩年の父親が故郷のシュタイナウの裁判官をしたため、一家はしばらく裁判所に住んだ。
兄ヤーコプが11歳のとき、父親が死ぬ。時は1796年、18世紀の終わりのことだ。裁判所に住むことができなくなった一家は小さな家に移り、さらに2年後、ヤーコプと弟のウィルヘルムだけが9年制のギムナジウムに入るため、カッセルに移り住んだ。あの美術祭「ドクメンタ」で有名になったカッセルだ。
田舎から来た子だというので二人は一年下のクラスに入れられるのだが、それがかえってよかったのか、二人はそれを屈辱と感じて猛然と勉強をした。たちまち進級につぐ進級で、ヤーコプは4年で卒業、二人はともにギリシア語・ラテン語を確実に身につけた。この言語技法の獲得がのちのちに生きてくる。
1802年、ヤーコプはカッセルから南に100キロほどのマールブルク大学に入った。法学部にしたのは父親の職能を継ぐつもりだったらしい。1年後、ウィルヘルムもマールブルク大学に入った。

大学での講義は二人を刺激しなかったようだ。よくあることだ。けれどもただ一人、若い助教授のフリードリヒ・フォン・サヴィニー先生が強烈な印象をもたらした。これもよくあることだ。
ちょっと説明をしておくが、当時の法学はローマ法が中心である。ローマ法は、ローマ帝国がキリスト教を奉じて中世ヨーロッパ世界に版図を広げるにあたって中央集権的に構築した厳密な法体系というべきもので、一言でいえば社会人為的な組み立てになっていた。しかし世間にはローマ法以外の規律や習慣や取り決めでおこなわれていることなど、いくらでもあった。
とくにドイツ各地には、キリスト教が広がる前にゲルマン諸民族が長年にわたって築き上げてきたいくつもの慣習法があって、そこには中央集権的なロジックがおよそあてはまらないような価値の取り決めやルールが、さまざまに生きていた。サヴィニー先生はそれを強調した。ヤーコプはそういった先住民族の伝承や語法に関心をもったのだ。
法学から民間伝承へ。
グリム兄弟はサヴィニーの研究室や図書室に入り浸りになる。さかんに古代ゲルマンの伝説・民謡・物語を調べ、ノートにとるようになった。そしてあるとき、サヴィニーの自宅でアヒム・フォン・アルニムとクレメンス・ブレンターノに出会うのだ。
この出会いが決定的だった。いい例がすぐに思いつかないが、本居宣長が賀茂真淵に出会ったものだと思えばいいだろう。
アルニムは後期ドイツ浪漫派を代表する詩人で劇作家で小説家だ。ベルリンでプロシャ貴族の家に生まれてゲッティンゲン大学で法律・科学・数学を学んだのち、3年にわたってヨーロッパ各地を旅行して、1808年に『隠者新聞』を編集した。
この『隠者新聞』はハイデルベルク浪漫派の牙城となった。このときアルニムはブレンターノと新たな仕事を組んだ(ぼくはアルニムでは幽霊とジプシーを描いた『エジプトのイザベラ』を好んでいる)。
ブレンターノも後期浪漫派の詩人で劇作家で小説家だが、ゲッティンゲンでアルニムと出会ってからその創作欲が開花した(異様な叙事詩の『数珠のロマンツェン』やドイツ文学最初の田園小説ともいうべき『けなげなガスパールと美しいアンナール』が出色だ)。ちなみにブレンターノの妹がのちにアルニムのもとに嫁いでいる。
そのアルニムとブレンターノが1805年に、二人で『少年の魔法の角笛』第1巻を刊行した。これが少年少女の世界文学史にとって忘れられないシリーズだ。ドイツ浪漫派がその精神の極みを求めて到達した民謡歌謡集である。ゲーテが激賞し、ヘルダーが構想したドイツ民族の魂がここに結集した。
こうして、グリム兄弟が大学で学んでいたころは、アルニムとブレンターノはちょうど『少年の魔法の角笛』の続巻にとりかかりつつあったのである。『少年の魔法の角笛』は採集によって成り立っている。第2巻にはさらに新たな歌謡群が必要だった。アルニムとブレンターノはサヴィニーにもその素材の応援を頼んだ。「図書館に自由にできる人で、古い民謡があるかどうかを調べる人はいないだろうか」。二人は民謡だけではなく、ドイツ民族に伝わる輝かしい伝説も集めたいと思い始めていたのだ。
ドイツ民族にメルヘンという分野が新たな輝きをもったのは、このときだった。

メルヘン(メールヒェンと発音するのが正しいが、ぼくは昔風にメルヘンとする)とは、「メーレ」という中世の名詞を縮小したもので、当時は「出来事のお知らせ」という意味だった。つまり「情報」だ。
いいかえれば、「よく知られてよい価値があり、それゆえ人々の口にのって伝えられる出来事を知らせる話」というのが「メーレ」であり、それをコンパクトなかたちにしたものが「メルヘン」だった。
けれどもドイツ民族の持ち前の心性は、メルヘンをそのような「お知らせ」として放っておかなかった。「お知らせ」したいために「人々を楽しませるべく考えついたお話」という意味を含ませた。メルヘンは「編集されるべき情報」となったのだ。ちなみにメールヒェンの「ヒェン」は「語られる話のが小さい」ということ、すなわち話の単位がショートだということをあらわしている。
もっともメルヘンはドイツ民族に特有なものではない。そういうものはヨーロッパ各地にあった。フランス語では「コント・ド・フェ」といい、英語では「フェアリーテイル」といった。すでにそうした昔話や民話や説話を集めた先駆的アンソロジーもあった。たとえば、先に名前を出しておいたジャンバティスタ・バジーレが1634年に『あらゆるメルヘンのなかのメルヘン、あるいは子供たちのための楽しみ』(ペンタメローネ)をまとめたとき、イタリアのメルヘンが立ち上がっていたのだし、シャルル・ペローの『長靴をはいた猫』などを集めた童話集もフランスのメルヘンの立ち上がりを告げていた。
しかし、ドイツにはまだそのような覚醒がなかった。アルニムとブレンターノがそこに火をつけたのだ。
すでにサヴィニー先生は大学を辞してパリで研究活動に入っていた。その助手としてヤーコプ・グリムを呼び寄せていた。
サヴィニーはさっそくヤーコプをアルニムとブレンターノに紹介する。ヤーコプもこの仕事をおおいに意気に感じ、ブレンターノはアルニムにヤーコプ青年のことを「たくさんのノートをとり、ドイツ民族の浪漫的文芸に対する多面的な知識をもったすばらしい研究者だ」という感想を送っている。
時はちょっと戻って1805年のこと、ヤーコプはカッセルに帰っていた。母と末っ子のシャルロッテもカッセルに引っ越していた。ヤーコプはそこでたまたま近所のヴィルト家を知ることになった。
太陽薬局という薬屋を営んでいた一家で、カッセルの中央広場に面していた。そこにグレートヘンとドルトヘンという姉妹がいた。この姉妹は近くのハッセンプフルーク家とも親しかった。ハッセンプフルーク家の家人たちも昔話に長けていた。
屈託のない妹のシャルロッテを通してこれらの一家と親しくなったグリム兄弟は、この一家の者たちが昔話にめっぽう詳しいことを知って、聞き書き(ヒアリング)をすることにした。聞き書きはときに一日中、ときに毎晩におよんだ。そこにアルニムとブレンターノの依頼がうまいぐあいに重なった。兄弟はその期待に応える作業に励みを感じた。聞き書きは過熱した。そして、この聞き書きこそがグリム童話の出発点となったのである。
グレートヘンやハッセンプフルーク家から聞き書きした採話は、ていねいにまとめられてブレンターノらに送られた。49篇あった。ところが、ここがグリム童話の“単独誕生”のきっかけになるのだが、待てど暮らせどブレンターノたちからの返事がなかったのだ。


(上・ヤーコプ 下・ウィルヘルム)
ぼくもいろいろの研究書(いいかげんなものも含めて)を読んでみたのだが、ブレンターノらがグリムの貢献と成果に反応しなかった理由は、どうもはっきりしない。
兄弟が集めたいくつかの歌謡は『少年の魔法の角笛』の第2巻と第3巻に収められている(おそらくグリム兄弟の提供だろうと推測されるものが24篇ほど掲載されている)。が、お話(メルヘン)のほうにはブレンターノらはまったく関心を示していない。これは信じがたいことである。アルニムとブレンターノこそはドイツ・メルヘンの凱歌を希求していたはずなのだ。
おそらくは関心を示さなかったのではなく、小さいころから憂鬱と浪漫のあいだを行ったり来たりしていたブレンターノの独得の気質によるものだったろう。世の中には、あれだけ気を乗せて頼んできておきながら、その後は梨の飛礫になる連中はけっこういるものだ(ぼくもそういう何人かや、そういう何社かに出会ってきた)。ブレンターノはついつい返事をしなかっただけだったと思いたい。
そういうこととは露知らないグリム兄弟は落胆した。原稿は送り返されてもこなかった。しばらくは待ち遠しく、しばらくは苛々した。が、それが結局はグリム童話の誕生のためにはよかったのである。兄弟はかつてカッセルのギムナジウムの1クラス下に入れさせられたときに発奮したように、今度も発奮した。念のために原稿の書き写し(コピー)をしていたこともさいわいした。兄弟は自力で聞き書きメルヘンを出版しようと決意する。
この決意が生んだものこそが『子供と家庭の童話』第1版、すなわち“グリム童話第1集”だったのである。86篇を収録した。
グリム兄弟が『子供と家庭の童話』(これがグリム童話集の正式タイトル)を自力刊行することにしたのは、ブレンターノの引きこもりのせいだけではなかった。兄弟自身にも強烈なモチベーションがあった。それはドイツ人の、ドイツ国民のための、ドイツ語の童話を確立したいと願っていたからだ。

(ヤーコプ、ウィルヘルムの弟・ルートウィヒの画)
さて、兄弟がメルヘンの採話に夢中になっていた時代がどういう時代だったかということは、御存知か。そのことが見えてこないとグリム童話の正体はわかせない。
先にも書いたが、グリム兄弟が生まれたのはフリードリッヒ大王末期の1785年あたりだが、このあとドイツはフリードリッヒ・ウィルヘルム2世の治世に入った。そのとたん、隣国のフランスでフランス革命が勃発した。
それでどうなったか、御存知か。自由・平等・博愛が広まったのではない。ナポレオンが台頭して、ヨーロッパは戦場と化したのだ。グリム兄弟がメルヘン収集に乗り出していた時代は、ドイツが各地でそのナポレオン軍と戦闘していた真っ只中だったのである。いっときヤーコプもカッセルの兵站司令部の書記に従事させられていた。ヤーコプがパリのサヴィニー先生のところで助手をしていたときは、英露墺の対ナポレオン同盟が結成された時期だった。それでもナポレオンはアウステルリッツで戦勝し、ドイツはいよいよ風前の灯火にさらされた。
ナポレオンはイギリスを大陸封鎖しておいて、ドイツ領主たちをライン同盟化させると、ついにプロイセンに殴りかかってきつつあった。中世ドイツ人の象徴であった神聖ローマ帝国があっけなく瓦解したのは、『少年の魔法の角笛』第1巻が刊行されたときなのだ。
そういうなか、いや、そうしたなかであればこそ、兄弟は(アルニムとブレンターノもそうだったが)、ドイツ民族の魂のルーツを伝えるメルヘンの収集に乗り出したかったのだ。
ちなみにヨハン・ゴットリープ・フィヒテの熱烈な『ドイツ国民に告ぐ』(390夜)の刊行が『少年の魔法の角笛』第1巻の翌年、ベートーベンの第五交響曲がその2年後、ショーペンハウアーの渋い『意志と表象としての世界』(1164夜)の発表がその3年後のことである。
これであらかた見当がつくように、グリム兄弟のメルヘン採集はドイツ魂の鼓舞とつながっていたわけである。グリム童話の刊行だけのことをいえば、その採集と刊行はドイツ民族の危機の予兆とともに始まって、ナポレオンの退嬰とともに終わったのである。
実際にも『子供と家庭の童話』は1812年から1857年の第7版まで続き、最終的に211話が収録されたところでピリオドが打たれた。途中には削除も補填もあった。こうしてグリムは童話集の編集を終え、あとで少しだけ説明するが、その後はドイツ語やドイツ文法やドイツ英雄伝説やゲルマン神話の研究に向かう。
もはや説明するまでもない。グリム兄弟は祖国愛をもって立ち上がった「母国語の闘士」だったのである。グリム童話は祖国愛と母国語のための下調べだったのだ。
これでぼくが、宣長が真淵と出会ったことをグリム兄弟のアルニムとブレンターノの出会いに準(なぞら)えた意図が少しは伝わったかと想う。グリム兄弟はドイツにおける「からごころ」(漢意)を排してゲルマン民族の「いにしえごころ」(古意)に突入していったのだ。グリム兄弟は“ドイツ国学”のパイオニアだったのだ。
ついでながら、わかりやすいだろうから時代の東西の符牒を言っておくと、宣長が『古事記伝』を完成した寛政10年は1798年のことなのだが、それはヤーコプとウィルヘルムがカッセルのギムナジウムに行っていたころだった。
では、みんなも気になることだろうから、グリムがどの程度にわたってメルヘンに手を入れたかというところを少々点検しておこう。
これについては厖大な研究が微に入り細に亙ってあきらかにしていることなので、そのいちいちにはふれないが、結論を言うなら、兄弟はあきらかに手を入れた。改変した。編集した。聞き書きをそのまま童話として活字にしたわけではなかったのだ。
兄弟が聞き書きした相手は、最初は太陽薬局のグレートヘン・ヴィルトとドルトヘン・ヴィルトの姉妹で、彼女らは『白鳥の王子』『白い鳩』などを語って聞かせた。ついでほぼ同時期にハッセンプフルーク家の娘のマリーたちから『白雪姫』や『長靴をはいた猫』などを聞き書きした。さらにカッセル近郊のドローテア・フィーマンという仕立屋のおかみさんからは(研究者のあいだではフィーマンおばさんとして知られる)、ドイツ農民の独得の語り口というものを知らされ、合計37話を採集する。第2巻のグリム童話集(子供と家庭の童話集)の巻頭に飾られたのが、そのフィーマンおばさんの肖像だ。
そのほか兄弟が聞き書きした相手はかなりの数にのぼる。しかし、昔話を語ってくれる者なら片っ端から聞き書きしたというのではない。各地に赴いたというのでもない。グリムが訪れた近郊の語り手たちが一度語った話を黙ってすべて聞き、二度目あるいは三度目にもその話ぐあいとほぼ同じ話し方ができていたものだけを、丹念にノートしていったのだ。
このような方法に熱中したことを見ると、兄弟には、なんらかのメルヘン編集術に関する信念があったといっていいだろう。
それをグリムが昔話や民話の原型を改変したとも、改悪したとも、また恣意的なドイツ民話を捏造したとも非難することは、できないわけではない。けれども、グリム童話の編集術がどのようなものであったかということに倫理的な判定をえらそうにくだすのは、やめたほうがいい。結局は「なぜ残酷な部分を和らげなかったのか」とか、「結論部に矛盾が多すぎる」とか、「とうてい子供の教育にふさわしいとは思えない」といった揶揄に終始するだけだ。それでは、あんたのお里が知れるだけなんですよ。

(ウィルヘルム・ジンムラー画)
念のため、どのようにグリムが手を入れたのか、いくつかの例だけをあげておくが、これを知ったからといって鬼の首を取ったような気にならないでもらいたい。
たとえば有名なところでは、『白雪姫』では実母を継母に変えた。また、小人(こびと)たちが白雪姫に出した条件を変えた。グリムの当初に採取したノートでは、小人たちは白雪姫に「かくまってやるかわりに、料理をしておくれ」と言っていたにすぎないのだが、『子供と家庭の童話』に入った時点で、「あんたがわしらの家の切り盛りをしてくれ。料理をつくり、ベッドをなおし、洗濯、繕いもの、編み物をして、なんでもきれいにしてくれるんなら、ここにいてもいいよ」となった。
『十二人の兄弟』の初版では、王さまは娘が生まれると考えただけで恐怖をもつのだが、第2版になると、王さまは娘が生まれると思うと夢中になりましたというふうになる。正反対だ。そのため息子たちを犠牲にするというプロットになった。『ヘンゼルとグレーテル』で実母が継母になったことはすでにのべたが、これは第4版になってからの改定だった。
こういう改変や改竄はグリム童話の随所にわたっている。詳しいことはガブリエーレ・ザイツの『グリム兄弟』やマリア・タタールの『グリム童話・その隠されたメッセージ』などを読むといい。いくらでもヴァリアントを示してくれている。しかしだからといって、この改変編集を咎められるだろうか。

(「もっと空想的でメルヘン風でなければならないだろう」という趣旨の、ウィルヘルムの書き込みがある)
そもそも口伝えの何をもって正確な記録というべきなのか。正確な記録ということ自体がありえない。編集なきコミュニケーションなんて、あるわけはない。
グリム兄弟は自分が聞き書きをしているときから、これが別の語り手から聞いたものであればおそらく異なるものになっていただろうことは、十分に予想していた。ヴィルトの姉妹やハッセンプフルーク家の人々やフィーマンおばさんに話を聞いているときも、兄弟はきっとその背後にあるだろう「分母としてのメルヘン」をこそ想定していたのである。
だいたい、メルヘンではしょっちゅう魔女や魔法使いが登場するのだが、その魔女や魔法使いは邪念をもたらすものであって、また恵みを与えるものなのである。メルヘンでは登場人物をこれが善、これが悪とは規定しがたい。正は負であり、負が正なのだ。
かくしてぼくの見方は、こうなのだ。童話というもの、その話を「デジャ・アンタンデュ」(聞いたことがあるような感じ)にすることが役割だと見たほうがいい。これが童話のモダリティなのである。それゆえグリムはおそらくは、「この話はそのようになりたいにちがいない」と思って編集しつつづけたのである。言い伝えられ、語り継がれた物語がこのようになりたいと思っていただろう方向に、グリム童話を夢中でまとめたのだ。
もっとはっきりいえば、内容や筋書きを作り替えたかったのではなかったのだ。そこにひそむドイツ民族のドイツ語による語りの本質を残したかったのだ。
グリムが童話編集のかたわら、何に没頭していたかを、また童話編集後は何に没頭していったかを最後に書いておく。
1816年、ヤーコプとウィルヘルムは『ドイツ伝説集』第1巻を刊行した。1818年には第2巻を、さらにウィルヘルムは『アイルランドの妖精童話』(翻訳)と『ドイツ英雄伝説』を、ヤーコプは『ドイツ神話学』をまとめた。
これでびっくりしては困るのだが、これだけでもグリム兄弟の研究姿勢が只事ではないことが窺い知れるだろう。童話編集よりも“ドイツの記憶の全体像”の編集に乗り出している!
しかもこれらとはべつに、ヤーコプは『ドイツ文法』という大著を1819年に第1巻を刊行して以来、これを1837年の第4巻まで続刊していった。この仕事は文法の解明であってドイツ語の歴史の解明であり、かつそのままがドイツ人民族の思考の歴史であった。そのように確信していたヤーコプは、『ドイツ文法』を哲学的に綴ることを断固として避けた。このことについてはヤーコプは何度も序文や友人への手紙に書いている。
ぼくは、ここを断固として評価する。ドイツ語という母国の言葉の内実を解明するのだから、そのこと自体がドイツ的思考なのである。そこへよそから哲学や理念をもちこむ必要などなかったのだ。
こうしたドイツ研究に人生の時間のすべてを投入したグリム兄弟の志がどこにあるかは、ヤーコプの次のメッセージにあらわれている、「文芸は民族の魂から発し、それが言葉になったものなのです」。
今夜すでに何度もつかってきた「民族」という用語は、ドイツ語では“Volk”にあたる。フォルクスワーゲンの、あのフォルクだ。グリム兄弟はこのフォルクのために口承説話を集め、ゲルマン神話を辿り、ドイツ語の歴史を研究したのだった。これで予想がついただろうが、兄弟がメルヘンを改変したのは、フォルクとドイツ語のためだった。
ちなみにこうしたグリムのドイツ論は、いずれ「千夜千冊」でとりあげるかもしれないジャン・パウル、アマデウス・ホフマン、アレキサンダー・フォン・フンボルトとウィルヘルム・フォン・フンボルトの兄弟、アウグスト・フォン・シュレーゲルとフリードリッヒ・フォン・シュレーゲルの兄弟を熱狂させた。
晩年のグリム兄弟について、二つのことを付け加えておきたい。
ひとつは、ヤーコプがフランクフルト議会に何度も参画して(ときに会議の議長もつとめ)、祖国ドイツのための憲法の試案にとりくんでいたということだ。詳しくはガブリエール・ザイツの『グリム兄弟』に収録されているおびただしい史料や手紙を見てもらうといいが、この憲法試案へのとりくみは、兄弟のヴィジョンがどこに向かって過熱していたかを雄弁に暗示しているだろう。
もうひとつは、『ドイツ語辞典』のことだ。これはヤーコプとウィルヘルムが最後に最も力を注いだ仕事で、第1巻は1852年に、ウィルヘルムの死ののち第2巻が1860年に刊行され、その3年後にヤーコプが死んでからは、実に100年をかけて東西に分裂したドイツがこれだけはドイツ民族のために共同編集しなければならないと合意して、その完成をめざしたものだった。『ドイツ語辞典』が完成したのは、実に1961年だったのである!
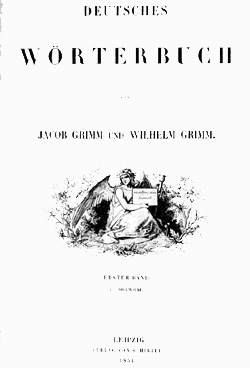

(1829年 ルートウィヒ・グリム画)
グリム兄弟をめぐる評伝・批評・批判書もべらぼうにある。誰もが参考にするのはハインツ・レレケの『グリム兄弟のメルヒェン』(岩波書店)とガブリエーレ・ザイツの『グリム兄弟』(青土社)あたり、またつねに参照されるのはウラジミール・プロップ『昔話の形態学』(白馬書房)、カール・ハインツ・マレ『〈子供〉の発見――グリム・メルヘンの世界』『〈おとな〉の発見――グリム・メルヘンの世界』(みすず書房)、マックス・リュティ『ヨーロッパの昔話』(福音館書店)、マリー=ルイーズ・フォン・フランツ『おとぎ話の心理学』(創元社)などだが、そこにはつねにミハイル・バフチン『ことば対話テキスト』(新時代社)、ロラン・バルトの『神話作用』(現代思潮社)や『物語の構造分析』(みすず書房)、アラン・ダンダス『シンデレラ』(紀伊国屋書店)、ロジャー・セール『ファンタジーの伝統』(玉川大学出版部)などが絡む。日本の研究者では小澤俊夫の『素顔の白雪姫――グリム童話の成り立ちをさぐる』(光村図書)、『グリム童話の誕生』(朝日選書)、鈴木晶『グリム童話』(講談社現代新書)が定番だ。
グリムを批評にさらそうというものも少なくない。とくにグリム残酷説は売れ行きがいいせいもあって、引きもきらない。おもしろい視点のものもある。代表的なのはマリア・タタール『グリム童話――その隠されたメッセージ』(新曜社)、イーリング・フェッチャー『だれがいばら姫を起こしたのか』(筑摩書房)、ジャック・ザイプス『グリム兄弟――魔法の森から現代の世界へ』(筑摩書房)、同じくザイプスの『赤頭巾ちゃんは森を抜けて』(阿吽社)、ルース・ボティックハイマー『グリム童話の悪い少女と勇敢な少年』(紀伊国屋書店)、アン・セックストン『魔女の語るグリム童話替え話』(静地社)など、ほかに野村滋『グリム童話――子どもに聞かせてよいか』(ちくまライブラリー)、金成陽一『誰が「白雪姫」を誘惑したか』『誰が「赤ずきん」を解放したか』(大和書房)などがずらりと控える。
メルヘン研究も多い。なかでぼくはルドルフ・シュタイナーの『メルヘン論』(書肆風の薔薇)、アンドレ・ヨレス『メールヒェンの起源』(講談社学術文庫)、森義信『メルヘンの深層』(講談社現代新書)を愛読した。グリム以前のメルヘンを知るには『もうひとりのグリム――グリム兄弟以前のドイツ・メルヘン』(人文書院)がいいだろう。



