父の先見


河出書房新社 2018
編集:吉住唯 協力:江坂健・村上隆・中山暁
装幀:水戸部功
ヴェネツィアで見て、バーゼルで買う。
これが現代アート業界の合言葉だ。ヴェネツィア・ビエンナーレで品定めをし(隔年開催)、アート・バーゼルでめぼしい作品を手に入れる(毎年開催)。2つのフェアの開催地と開催期が近いこともあって、いつのまにかここにアートビジネスのグローバルな日付変更線だか変動相場制だかが、賑やかに、曰くありげに、生き馬の目を抜くようにできあがっていた。
ヴェネツィア・ビエンナーレは国単位で出展される。各国のパビリオンには毎年コミッショナーやディレクターが選ばれてコンセプトやテーマを設定し、それにふさわしいアーティストたちが制作にあたる。一方のアート・バーゼルには世界中の300近いトップギャラリーが参加するが、招待状がなければ入れない(いまはアート・バーゼル香港、アート・バーゼルマイアミ・ビーチもある)。
どちらも画商とお金が動くが、むろんそれだけではない。アーティストも批評家も、コレクターもキュレーターもオークショニアも、かなりその気になる。本気を出す。パリコレやF1のようなものと思うかもしれないけれど、それはちがう。衣服やクルマは一般消費者のほとんどが手を出すが、アートはそういうものではない。美術は日常的なコモディティにならないようにしてきた。何かを競いあい見せあうのだからオリンピックや万国博のようでもあるけれど、それともちがう。スポーツ界や産業技術界は別の交換市場や見本市をいくらでももっている。
それらにくらべて「ヴェネツィアで見て、バーゼルで買う」ことになったアートワールドには、かなり特別な仕掛けが作動してきた。現代アートという特別な仕掛けだ。まことに特別で、面妖で、けっこうトリッキーなのである。

現代アートはデュシャン(57夜)が男子用便器をさかさまにしてR・マットと署名したときに始まり、ウォーホル(1122夜)がキャンベルスープの缶を並べてシルクスクリーンに刷ったときに事故現場のように確立した。コモディティにならないようにしてきたのが美術の歴史のはずだったのに、現代アートは日用品から始まったのである。この日用品アートは当初は「レディメイド」と呼ばれた。
たとえばリチャード・ハミルトンは雑誌広告のページをコラージュして展示し、リキテンスタインはコミックの一場面を印刷の網点ごと拡大した。これは広告やマンガ雑誌から現代アートが鬼っ子のように生まれたようなものだった。瓢箪から駒だ。ジョセフ・コスースは椅子と椅子の写真と辞書の「椅子」の項目の解説コピーとを並べて飾り、高松次郎は4脚の椅子とテーブルがそれぞれ直角に見えるように錯覚するような仕掛けを見せた。家具屋からアートが生まれたようなものだ。
中原浩大はレゴでフィギュア彫刻をつくり、村上隆はフィギュアの美少女を巨きく再生した。フェリックス・ゴンザレス゠トレスは色とりどりのチョークあるいはキャンディをギャラリーの片隅に山積みした。
いずれも世の中で知られている日用品をなんらかの方法で「変換」して、アートにした。すでに消費されたものがトリックよろしくアートに生まれ変わっていったのだ。消費されたものが対象になるのだから、すぐさまゴミや廃棄物もアートになった。
スージー・ガンシュはプラスティック食器やコーヒーの蓋を素材にし、イギリスのティム・ノーブルとスー・ウェブスターの2人組は家庭ゴミや金属スクラップを組み合わせてシルエットを見せた。最近では長坂真護がガーナの不法投棄された電子製品のアート化をはかって話題になっている。
生理的排泄物もアートになった。テレンス・コーは自分の排泄物を金メッキしたオブジェを出品した。2007年のアート・バーゼルでのことだ。もっと以前、平川典俊は1998年に女性の排泄物が本人とともに展示されるという仕掛けを発表した。平川は女性たちの排泄物を写真にもしていて、ぼくのニューヨークのガールフレンドも「まんまとおしっこしているところを撮られました」と笑っていた。
さまざまな「変換」がアートを生み出した。こういう現代アート作品は「なんでも鑑定団」には出てこない。「なんでも鑑定団」は手持ちの美術作品に相場の値段をつける番組だけれど、現代アートは「変換」という概念制作の行為とその成果物に値段がついたのである。ウォーホルの作品には100億円以上の値がついた。まことに特別で、面妖で、トリッキーだというのは、そこなのである。それでは、なぜそんな「変換」に価値がつくのか。

本書は、そのような仕掛けをつくりだした今日のアートワールドの現状を丹念に炙り出したもので、①マーケット、②ミュージアム、③クリティック、④キュレーター、⑤アーティスト、⑥オーディエンスに分けて、それぞれの特徴を鮮やかに案内しながら、その問題点を少し辛口で掘り下げた。加えて現代アートが確立させてきた美術史的な意味をまとめ、絵画と写真に迫っている危機がどんなものかもレポートしていた。
よくできた1冊で、最近は現代アートについての入門書や解説書はかなりあるし、ときに雑誌でも特集されるようになっているようだが、ぼくはこの1冊をぜひとも勧めたい。
著者の小崎哲哉は世界中の現代アートの実情に詳しいだけではなく、なかなか渋いジャーナリスティックな慧眼の持ち主で、ずいぶん前から現代の社会状況を「狂気の時代」と捉えてきた。この狂気は20世紀がつくってきたものなので(また訂正ができず、その上塗りをしてきたので)、小崎は2002年に『百年の愚行』(Think the Earth)を並べ、2014年にその続編を構成刊行した。2020年には美術展示と政治介入をめぐる『現代アートを殺さないために』(河出書房新社)を上梓した。「ソフトな恐怖政治と表現の自由」というサブタイトルがついている。
本書はウェブマガジン「ニューズウィーク日本版」に2015年秋から不定期連載した「現代アートのプレイヤーたち」がもとになったもので、現代アートに関するゴシップとセオリーとを綯いまぜにしている。以下、メモ書きのようになってしまうけれど、視点と論点と登場人物を紹介したい。

【富豪のマーケット】
大きなアートフェスティバルにはだいたいコラテラル・イベント(同時開催イベント)が付く。2009年にヴェネツィア・ビエンナーレに付随して開館したプンタ・デラ・ドガーナは鳴り物入りだった。スーパーコレクター、フランソワ・ピノーのとびきりのコレクションを展示するためのもので、かつての税関の建物を27億円で改装した(安藤忠雄が設計)。ピノーは、グッチ、サンローラン、バレンシアガ、プーマなどのブランドを統合するファッション・コングロマリット「ケリング」の元会長である(資産1兆7000億円)。コレクションにはジェフ・クーンズ、工藤哲巳、ダミアン・ハースト、リチャード・セラ、ヤン・ヴォー、村上隆、ソフィ・カルなどがずらりと揃う。ピノーは1998年にオークションハウスのクリスティーズも970億円で買収した。
ピノーに現代アートの精髄を揃えさせる手引きをしたのは(たとえばゲオルク・バゼリッツやジグマー・ポルケの新作すべての落札)、パリのギャラリストのエマニュエル・ペロタンだと言われている。
ケリングだけでなく、カルティエ、ルイ・ヴィトン、プラダ、エルメスも、それぞれアートコレクションをしてきた。なかでもベルナール・アルノーを総帥とするルイ・ヴィトンは、セリーヌ、ジバンシィ、フェンディ、ダナ・キャラン、香水のゲラン、宝飾のブルガリ、百貨店のボン・マルシェなどを傘下にLVMHグループを築いて、またたくまに巨大軍団となった。
2014年、アルノーはブローニュの森にルイ・ヴィトン美術館を開館させた(フランク・ゲーリー設計)。ウォーホル、ゲルハルト・リヒター、クリスチャン・ボルタンスキー、ピエール・ユイグ、ドミニク・ゴンザレス゠フォルステルなどが並んだ。シュザンヌ・パジェの構成展示ディレクションだった。
【ギャラリー/ディーラー】
現代アートは大富豪によってコレクションされるけれど、そのマーケット・フィールドを用意してきたのがギャラリストやアートディーラーである。現代アート業界では、ギャラリーはアーティストの代理人として新作を売るプライマリー・ギャラリーと、これらを受けて作品を売買するセカンダリー・ギャラリーでできている。オークションハウスはセカンダリーになる。
この領域も生き馬の目を抜く闘いが連続していて、大きな成果をあげるには実力がものを言う。ぼくがニューヨークでナム・ジュン・パイク(1103夜)や河原温と話しこんでいたころまでは、レオ・カステリがディーラーの帝王だった。ポロック、デ・クーニング、ラウシェンバーグ、ジャスパー・ジョーンズ、フランク・ステラ、ブルース・ナウマン、ジュリアン・シュナーベルの名を世に広めたのは、ほとんどカステリだ。
21世紀になるとラリー・ガゴシアンが帝王になった。世界に15のギャラリーを有して、「アートのスタバ」と言われている。2007年に村上隆がマリアン・ボエスキーからガゴシアンに移籍した。
セカンダリーを構成するのはオークションハウスだけではない。昔ながらの町のギャラリーから地方自治体のミュージアムまで、さまざまなアートフェスティバルの主催者まで、いろいろ混在する。だからアートシーンの評判は、新聞の美術欄の記者、アートマガジンのエディター、批評家、大学の美術研究者、ミュージアムのキュレーター(学芸員)、ウェブのコラムニストまでの混成力なのである。
これらがまとめて「アートワールド」と呼ばれる。アーサー・ダントー(1753夜)が名付けた。この見方については、ジョージ・ディッキー(イリノイ大学哲学教授)が「芸術制度論」をぶつけた。アート作品は知性をそなえたアーティストが特定の社会制度に寄与したもので、その行為によってアートワールドができあがると説明した。ダントーはそれではアートワールドが騎士道の集団になると一笑に付したのだが、アート業界の不正や人種差別問題や政治と芸術の関係を見ていると、この議論はまだ決着がついていないと言わざるをえない。
【迷走するミュージアム】
どうみても美術とミュージアムは切っても切れないように感じるだろうが、実際には本来のミュージアム(ムセイオン)は神との交歓の場であると同時に博物館や図書館であって、また研究施設や資料保管施設でもあったので、また近代美術館がはたした役割には教育や学習機能もふくまれていたので、美術作品を展示していればそれですむというわけにはいかない。
本書では、 2015年の香港のM+(エムプラス)美術館館長ラーシュ・ニットヴェ(テート・モダン初代館長など歴任)の突然の辞任事件、それにまつわるアイ・ウェイウェイ(艾未未)の天安門撮影写真の騒動のこと、2015年のバロセロナ現代美術館のバルトメウ・マリ館長による開幕前日の展覧会中止発表の経緯、同じく2015年のMOT(東京都現代美術館)でおこった会田誠と会田家の作品撤去問題、そしてMoMA(ニューヨーク近代美術館)とテートモダン美術館の迷走ぶりなど、さまさまな難産とボタンの掛けちがいを報告している。
最近はクリス・デルコン(元テート・モダン館長)が「ミュージアム3・0」と言ったように、作品を展示して集客を得るだけのミュージアムではあきたらず、人権や表現の自由や地域貢献を配慮するミュージアムが要請される。こういう騒音や変革提案が目白押しになってきたところを見ると、ひょっとしてミュージアムをつくりすぎたのではないかという気になる。


【お呼びでないクリティック】
アメリカでは1962年創刊の「アートフォーラム」と1976年創刊の「オクトーバー」というアートマガジンが競いあってきた。「アートフォーラム」は初期はクレメント・グリーンバーグがモダニズム論を展開して、展覧会批評も独占気味だったのだが、これに飽き足らないエディターが離れて「オクトーバー」をポストモダン風に編集構成するようになった。
社会学者のサラ・ソーントンは『現代アートの舞台裏』(武田ランダムハウス)で、「アートフォーラム」を「ヴォーグ」や「ローリングストーン」誌に比肩して、コネやカネでは作品を掲載しない方針をもっていたと評した。実はぼくもエイズが問題になったころ、4回ほど原稿を書いた。しかし、その後この雑誌はジョン・シードから専門用語だらけでつまらないと、ハル・フォスターからは美術批評家は絶滅危惧種だと揶揄された。
「アートフォーラム」だけではなく、アート・クリティックが期待されなくなったのである。ジェリー・ソルツは「今日ほどアート批評がマーケットに影響を及ぼさなくなったのは、この半世紀で初めてのことだ」と書いた。
こうして美術批評が危機を迎えた。もっとも今に始まったことではない。ニューヨーク・タイムズのベテラン美術記者が「アートがミニマルになればなるほど、説明がマキシマムになる」と書いたのは60年代後半のことだった。
実はアート・ムーブメントを示す用語も払底している。バロック、ロココ、印象派、キュビズム、未来派、表現主義、アンフォルメル、コンセプチュアル・アート、シミュレーショニズム……といった呼び名(様式についての呼称)がずうっと提唱されないままなのである。なんたらイズムという呼称がいいわけではないものの、あまりにもネーミングがなくなった。
ぼくは村上隆の「スーパーフラット」などおもしろいと思ったけれど、残念ながら継承されていない。小崎は「ソーシャリー・エンゲイジド・アート」、ボリス・グロイスの「セカンダリー共闘作戦」、ニコラ・ブリオーが言い出した「リレーショナル・アート」なども紹介していたが、いまいちだ。ブリオーの『関係性の美学』(「藝文攷」で翻訳)を走り読みしたかぎりでは、「リレーショナル」の意味の追求が甘く、あまり充実していない。
だいたいブリュノ・ラトゥールの「モノ論」や「人新世」の思想から派生した創造性論の多くが貧弱なのである。1766夜(ラトゥール『近代の〈物神事実〉崇拝について』)など読んでいただきたい。ぼくはこれらの美術議論にはフェティッシュが決定的に欠けていると思う。アートはもっとフェチを取り戻さないとまずい。
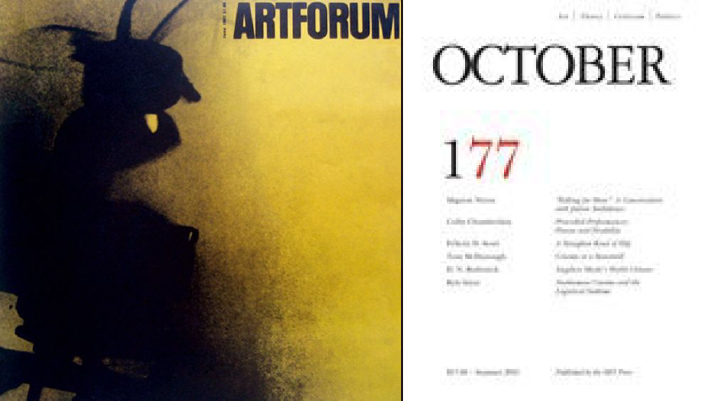
【キュレーターの力】
1986年にベルギーで開かれた「シャンブル・ダミ」展(ゲストルーム展)は大いに話題になった。ジョセフ・コスース、ボルタンスキー、ダン・グレアム、ブルース・ナウマン、ジャン゠リュック・ヴィルムートなど、それにぼくが当時贔屓にしていたパナマレンコらが集められた。ヤン・フートのキュレーションである。50をこえる個人住宅を会場にして、いわゆるサイトスペシフィック・アートの先駆けともなった。そのフートがドクメンタⅨを手掛けたところ、何かに右顧左眄していていまいちだった。ぼくはあまり感心しなかった。
しかしその後のフートは「オープン・マインド」展から亡くなる直前の「ミドル・ゲート・ヘール」展にいたるまで、気を緩めなかった。フートの幅広くてキツツキのような資質がどこからきたのかわからないが、ヨーゼフ・ボイスとの交流が大きかったのではないかと息子が言っている。
1989年、パリで「大地の魔術師」展が開かれた。ポンピドゥーセンターの館長ジャン゠ユベール・マルタンの指揮によるキュレーションだ。欧米のアーティスト50人、非欧米のアーティスト50人が招集された。アジアからはホアン・ヨンピン、河原温、ナム・ジュン・パイク、シェリ・サンバらに声がかかった。アウトサイダー・アートが注目された。ただしこのとき、マルタンは欧米のアウトサイダー・アートを組み込まなかった。
マルタンはインディペンデント・キュレーターに人文科学系を積極的に採り入れることを推奨し、レヴィ゠ストロース(317夜)、マルク・オジェ、ジェームズ・クリフォード、ボードリヤール(639夜)、フーコー(545夜)らの名をあげた。マルタンはその後も「アルテンポ」展(2007)、「世界劇場」展(2012~14)にとりくんで、気を吐いた。
ヴェネツィアで開かれた「アルテンポ」展では、民族人類学的な仮面や石像や木彫品のあいだにジャコメッティの彫像がひっそりと立ち、ハンス・ベルメールの人形、白髪一雄のフットペインティング、ヤン・ファーブルの髑髏、蔡國強の火薬絵画が並んだ。「世界劇場」展はタスマニアのホバートのミュージアムMONAで開かれ、パリのラ・メゾン・ルージュにも巡回したもので、エロスとタナトスに徹したコンセプトが通されていた。ぼくはのちにマリーナ・アブラモヴィッチと再会したとき、「世界劇場」で流されたマリーナとウーライが唇を重ねる映像を見せてもらい、その場で涙ぐんでしまった。マリーナは「マルタンは世界をよく見ているわね」と言っていた。
キュレーターには資質も必要だが、おそらく誰と話しこんだのか、どんな現場を通過してきたのかが問われるのだと思う。

【アーティストの咆哮】
本書の5章「アーティスト」で言及されているのは会田誠、村上隆、アイ・ウェイウェイ、アブラモヴィッチ、ヴォルフガング・ティルマンス、ジェフ・クーンズ、ヒト・シュタイエル、ハンス・ハーケ、アルフレッド・ジャー、ゲルハルト・リヒターたちである。いずれも苦悩し決断し、抗い、投企した。
いちいち紹介しないけれど、小崎はアーティストの肉声もアートになりうること、現代アートがますます政治や社会から切り離せなくなっていることを強調し、1989年に亡くなったベケット(1067夜)の『ゴドーを待ちながら』をボスニア・ヘルツェゴビナの戦火の中のサラエヴォで上演したスーザン・ソンタグの話で結んでいる。
9・11と3・11によって、われわれはディストピアめく現実感覚をどのように表現したらいいのか、いまなお問われている。そうしたなか、小崎は現代アートを構成するものは「インパクト」「コンセプト」「レイヤー」ではないかと提示する。これは写真家の杉本博司(1704夜)が「視覚的にある強いものが存在し、その中に思考的な要素が重層的に入っているということが、現代アートの2大要素だ」と語ったことを、少し分解したものだ。とくにレイヤーが入っているのがいい。
ぼくは実は山本耀司には現代アートの戦略が充実しているとも見てきたのだが、そのヨウジに躍如しているのが「レイヤード」だった。ただしヨウジには、それに加えて「場面」と「怒り」も秘められている。だったら小崎の「インパクト」「コンセプト」「レイヤー」に、新たに「シーノグラフィック」(場面的)と「アングリー」を加えてもいいのではないかと思う。どちらにせよ、アーティストの咆哮はとうてい鳴りやまないものであってほしいと思う。

【現代アートが抱えもつ動機】
現代アートの作家たちは、どんな動機と問題意識で作品をつくるのか。この問いに回答を見せることは、なかなか厄介なことだと思うのだが、小崎は思い切りよく7つのフラッグを提示した。
すなわち、(1)新しい視覚と感覚の追求、(2)メディウム(媒体)と知覚の探求、(3)制度への言及と異議、(4)アクチュアリティと政治、(5)思想・哲学・科学・世界認識、(6)私と世界・記憶・歴史・共同体、(7)エロス・タナトス・聖性、である。
驚くほど、よく配慮されている。説明の仕方にはよるだろうが、そうとうにカバーできている。あえていえば伝統との刺し違え、電子ネットワークとプロトコルのこととハッキングについて、憂鬱と疾病の問題、サル学のこと、ジェンダーのめぐりかた、そして衝動と欲望の問題がどこかに入ってきてもいいのかもしれない。
例示されたアーティストを紹介して一口メモを加えておく。
(1)新しい視覚と感覚の追求は、インパクトをどうするかということだ。巨大でハイパーリアルな人体をつくるロン・ミュエク、複数の乳房をもつ気球を彫刻するパトリシア・ピッチニーニ、極端に小さな作品をつくる須田悦弘やハム・ジン。ここにはヴィクトル・ヴァザルリやブリジット・ライリーらのオプティカルなインパクトや、かつてのルイジ・ルッソロなどのノイズによるインパクトも入ってくるだろう。
(2)メディウムと知覚の探求は、いわゆるメデイアアートともかぶってくるが、スキャナーを通したり、見る角度をマスキングして視野の変換を見せたりするアートとともに、ストッキングなどの伸縮性のある素材に重しを入れたエルネスト・ネト、味覚もとりこむミラルダやシェ・リン(謝琳)、数々のVRやARによる仮想現実アートが例示できる。
(3)制度への言及と異議は、美術館や展覧会そのものへの挑戦から、社会経済制度への挑戦までが入る。
(4)アクチュアリティと政治には、きわどい動機が動く。サンティアゴ・シエラは報酬を与えて失業者に刺青を入れさせたり、移民たち133人を金髪に染めるようなことをした。シアスター・ゲイツはシカゴの貧民地区サウスサイドで廃屋をリノベーションして、コミュニティハウスをつくった。戦争、テロ、貧困、人種差別、いじめ、環境問題につらなるアートは今後もあとを断たない。
(5)思想・哲学・科学・世界認識は、きわめて重大な動機になりうるが、かんたんではないように思う。トーマス・ヒルシュホーンが、スピノザ、ドゥルーズ、バタイユ、グラムシに捧げた作品など、とうてい思想力があるとは思えなかった。ここはやっぱり荒川修作だろう。
(6)私と世界・記憶・歴史・共同体は、文学やマンガならいくらでも例がある。荒木経惟(1105夜)、ナン・ゴールディン、ソフィ・カル、自分が育った家をテーマにしているス・ドホ、母親が集めていた瓶・箱・食器・薬などを展示したソン・ドン(宋冬)などがエントリーする。収容所の記憶をアート化したボルタンスキー、ダニ・カラヴァン、アンゼルム・キーファー、アルトゥル・ジミェフスキなどもこの動機だ。しかし、最も雄弁なのは草間彌生とルイーズ・ブルジョワだろう。
(7)エロス・タナトス・聖性は、永遠の動機である。フランシス・ベイコン(1781夜)やロバート・メイプルソープ(318夜)が圧倒的だが、ぼくも何度かコラボしたビル・ヴィオラ、「私は死にます」と話す世界中の男女を撮影したヤン・ジェンジョン(楊振中)、自分自身の死の姿を何度も展示したヤン・ファーブルの例もある。小崎はブランクーシの「無限柱」シリーズをあげ、さらに内藤礼と西沢立衛の《母型》が嗚咽を誘うほど強烈だったと感想を述べていた。

だいたい以上が本書が伝えようとしていたことのメモである。最後に、現代アートの現状はこんなふうになっているという感想が箇条書きになっている。
①アートワールドは矛盾に満ちている。
②アートマーケットは過熱するばかりだ。
③美術館とアーティストは圧力にさらされている。
④作品の特権的な私有化や囲い込みが進んでいる。
⑤巨大美術館はポピュリズムに陥っている。
⑥批評と理論は影響力を失っている。
⑦自治体は不勉強で不見識だ。
⑧今後のアートはインスタレーションを志向する。
⑨アーティストは「方外」であっていい。
アーティストにとっては③と⑨が、業界にとっては②と④が、文化にとっては⑤と⑦が問題だ。ぼくはひたすら⑨に期待する。ただし、「方外」とともに「数寄」と「作事」にもっと堪能してもらいたい。

⊕『現代アートは何か』⊕
∈ 著者:小崎哲哉
∈ 発行者:小野寺優
∈ 発行所:株式会社河出書房新社
∈ 組版:大友哲郎
∈ 印刷:株式会社暁印刷
∈ 製本:大口製本印刷株式会社
∈ 発行:2018年
⊕ 目次情報 ⊕
∈∈ 序章 ヴェネツィア・ビエンナーレ——水の都に集まる紳士と淑女
∈ Ⅰ マーケット——獰猛な巨竜の戦場
∈ Ⅱ ミュージアム——アートの殿堂の内憂外患
∈ Ⅲ クリティック——批評と理論の危機
∈ Ⅳ キュレーター——歴史と同時代のバランス
∈ Ⅴ アーティスト——アート史の参照は必要か?
∈ Ⅵ オーディエンス——能動的な解釈者とは?
∈ Ⅶ 現代アートの動機
∈ Ⅷ 現代アート採点法
∈ Ⅸ 絵画と写真の危機
∈∈ 終章 現代アートの現状と未来
⊕ 著者略歴 ⊕
小崎哲哉(おざき・てつや)
1955年、東京生まれ。京都在住。カルチャーウェーブマガジン「REALKYOTO」発行人兼編集長。京都造形芸術大学大学院学術研究センター客員教授。同大学舞台芸術研究センター主任研究員。2002年、20世紀に人類が犯した愚行を集めた写真集「百年の愚行」を企画編集し、03年には和英バイリンガルの現代アート雑誌「ART iT」を創刊。13年にはあいちトリエンナーレ2013のパフォーミングアーツ統括プロデューサーを担当し、14年に「続・百年の愚行」を執筆・編集した。