父の先見


河出書房新社 1994
Michele Green
The Dream at The End of The World 1991
[訳]新井潤美・太田昭子・小林宜子・平川節子
ぼくは、この9年間というもの、「未詳倶楽部」という妖しい倶楽部を主宰してきた。ここには紹介者がないと入れないし、ぼくが入会を誘うことはありえない。年に2、3度の例会を各地の某所でこっそりひらくのが目的で、それ以外の目的は何もない。
会員には、ある日、ある刻限、ある場所に集まられたいという通知だけが届き、気の向いた会員がその告知にしたがって、好きな装いに身をやつして集まる。だいたいは25人から40人くらいだ。そしてたいていは、一泊二日をともにする。長崎だったり、伊豆だったり、東京だったり、出雲だったり、山形だったり。ただし、とっておきのサプライズがある。その例会には、会員にはその名をあらかじめ知らされないゲストが必ず、一人か、ときに二人、招かれている。そして、突然、あらわれる。
これまでのゲストには、敬称は省略するが、中村明一・池田美由紀・柳家花緑・山口小夜子・田中優子・内田繁・江木良彦・西松布咏・大倉正之助・美輪明宏・白石加代子・田中泯・あがた森魚・高橋睦郎・岡野玲子・杉浦康平さんたちを選んだ。みんな、ぼくが大好きな「とっておき」だ。
会員は、これらのゲストが誰であったかを、出雲に来て加藤和彦であることを、熱海に来て森村泰昌であることを、会津に来てしりあがり寿であることを、初めて知る。でも、それからは何の隔絶もない。ほたほたとした溶融ばかり。先だっては、小雨降る奈良の柳生街道の人知れぬ店にみんなが三々五々集まると、そこに元権宮司の中東弘さんが待っていて、春日大社の若宮に連れ去り、しばらく由緒など交わしていると、やおら土取利行さんが登場して呪術的パーカッションが始まるという趣向にした。
これからもそのように、忘れたころにみんなで集まって、好きな遊びに耽ろうと思っている。
いや、未詳倶楽部の話をしようというのではなかった。その未詳倶楽部で、ぼくには最後の最後に行きたいところがあって、その話をしたかった。そこは日本ではない。モロッコのタンジールなのである。そのタンジールに集まって、みんなでそのまま消えるか、そのまま暮らしたい(笑)。


本書にはタンジールのことだけが書いてある。あらんかぎりの異国情緒を妄想して、それを猥雑で崇高な現実の街区にあてはめたような街である。本書は、そのノンフィクション・ドキュメントだ。
一応、主人公はいる。主役はポール・ボウルズとその妻のジェインで、そこに、タンジールの国籍離脱者たちの喧噪とエレガントな狂気とイスラミック・ボルテージが待っていて、そのあいまを縫うように、ウィリアム・バロウズ(822夜)からアレン・ギンズバーグ(340夜)までが、テネシー・ウィリアムズ(278夜)からフランシス・ベーコンまでが絡む。
時代は第二次世界大戦後のどさくさと、1950年代が一番おもしろい。著者のミシェル・グリーンはその人物模様をとことん描き出した。しかし、読んでみてすぐわかるのだが、主題はあくまでタンジールにあるという一冊なのだ。
そもそもそこがタンジールでなかったなら、そこにボウルズもジェインもバロウズもいなかった。ボウルズは「タンジールには不吉が金糸銀糸で紡がれている」と感応し、ジェインは「まるでエドガー・アラン・ポオのゴシックでアラベスクな場面を全部集めたようなタンジール」と感想し、バロウズは「あそこは死のスリルの放射能を約束する町だった」と言い、あとからやってきたトルーマン・カポーティは「あんな奇っ怪な督促状をもっているところはなかった」と唸った。そういうタンジールなのである。
ぼくがスーザン・ソンターグ(695夜)に直接に聞いたところでは(スーザンがタンジールに入ったのは1964年だった)、「あそこはね、自分でウィリアム・バロウズになる気がなけりゃ、行ってもムダよ。そう、そうね、セイゴオならそれをやるかもね」だった。

タンジールは北アフリカはモロッコの北の端の、狭いジブラルタル海峡に面した特異で突飛な港町だ。そこから海辺を沿って大西洋岸を走るとカサンブランカで、内陸に向かうとフェズが、さらに奥に入るとマラケッシュがある。
いずれもこの世と隔絶されたようなトポスだが、しかし、なんといってもタンジールが、欧米社会のすべてに最初の幕を下ろす、異様で、セイントで、猥雑で、エロティックなトポスなのだ。
モロッコが1912年にフランス保護領とスペイン保護領に分割されたとき、タンジールは国際管理地帯(インターナショナル・ゾーン)という特別な地域特性をもった。議会はフランス人4人、スペイン人4人、オランダ人1人、ユダヤ系モロッコ人2人、イスラム系モロッコ人3人、アメリカ人2人、ベルギー人1人、ポルトガル人1人で構成された。むろんまだスルタンもいた。これで、突如としてタンジールは、ベイルートと並ぶ一獲千金の夢をおこす街となった。
新聞は「タンジール・ガゼット」のほかに、2種類のスペイン語新聞、3種類のフランス語新聞があり、郵便ポストはアラビア語用とフランス語用とスペイン語用が分かれていた。警察はベルギー人の長官のもと、モロッコ人とスペイン人の警官が飲んだくれていた。そこをモハメッド・タジ陛下の「ブラック・ガード」とよばれる騎馬隊が、頭にターバンを巻いてしゃんしゃん練り歩いた。
タンジールは無国籍な「ザナドゥ」(歓楽宮)になりつつあったのだ。男の大半はバイセクシャルだったので、欧米からやってくる金持ち女はその男たちを巧みに漁った。そのくせ異郷の文化と欧米文化をシェリーで割ることは忘れない。そして大戦があった。
戦争が終わり、戦後になると、誰もがもっと気楽にタンジールを訪れるようになった。1946年9月に、ウルワースの麗しい相続人であるバーバラ・ハットンが、カスバの近くの幻のような豪邸「シディ・ホニス」を買った。噂を聞いた欧米人がこのファンタジックきわまりない異郷の館をよろこんで出入りした。もっとも、「シディ・ホニス」のまわりには実は5000人のアラブ人たちが迷路のような巣窟のあいだを、ターバンを巻いた蟻のごとくに動めいていた。この対比の落差が欧米人をくらくらさせたのだ。
こうして1947年の春、ポール・ボウルズとジェインズがタンジールに移り住んだとき、タンジールはすっかり甘美に堕落した、享楽と自由貨幣と売春と文芸実験とが毎夜とびかう、20世紀最後の無国籍エデンになっていたのである。
ポール・ボウルズがタンジールに何をしにきたかというと、小説を書きにきた。最初の数年間で『シェルタリング・スカイ』を書きあげて出版すると(1949)、世界中に興奮が渦巻いた。
『シェルタリング・スカイ』ほどけったいな小説はない。ノーマン・メイラーはさっそく「文明の終わりを小説にもちこんだ」というふうに、きわどい批評をしたものだ。なぜ、ボウルズがこんな小説を書いたかというか、書けたかということは、いまなお現代文学史の奇矯な謎ベスト5のひとつに入る。
本書はそういうことを意に介していないので、そのへんの文学的分析や芸術的考察にはいっさい寄与していないけれど、また、ぼくも今夜はそんな野暮を書く気はないけれど、もしもカフカ(64夜)やベケット(1067夜)やジュネ(346夜)に、またセリーヌやピンチョン(456夜)やクンデラ(360夜)が気になるというなら、ボウルズを読まない手はないだろう。
ニューヨーク生まれのボウルズはもともと作曲家だった。アーロン・コープランドに師事して、歌劇・ジャズ・管弦楽・ブルースが交じった独特の音楽をつくっていた。テネシー・ウイリアムズの『夏と煙』の舞台音楽なども担当したし、フォークソングの収集にも熱心だった。それがたまさか書いた文学作品を、鬼よりこわいガートルド・スタインに酷評されて、アタマにきて小説に挑む気になった。
それをモロッコに書きにきた。なぜモロッコに来たかといえば、1931年にコープランドと一緒にぶらりとタンジールを訪れたときの印象が抜群だったからだ。コープランドにとっては「精神病院の街」に見えたのが、ボウルズには「過密な想像力の都」に見えたのだ。ジブラルタルやフェズやマラケシュが近いのも気にいった。
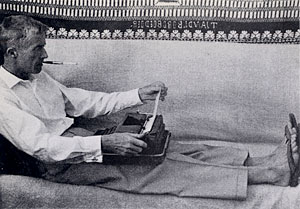
ボウルズの妻のジェインは、ひょっとしたらボウルズよりも才能のある書き手だった。ただし、彼女の神経は「宇宙的な繊細」に満ちていて、結局は神経症に冒されていく。
そうしたなか、ボウルズ夫妻の図抜けた感性に惹かれてか、タンジールの異常に惹かれてか、むろん両方ともが理由だろうが、まずはテネシー・ウイリアムズがやってきた。
次に来たのは写真家セシル・ビートンを伴った、社交界の英雄デイヴィッド・ハーバートだろうか。ペングローク伯爵家15代の次男坊である。世界の王室に通じていたこの男は、たちまちタンジールの夜を一流サロンに仕立てた。「ヘラクレスの洞窟」とよばれた。そこへ時代の寵児トルーマン・カポーティがやってきた。1948年に『遠い声・遠い部屋』を発表したばかりで、ハーバートのサロンに入りびたるようになった。カポーティはたちまち「告げ口屋」のニックネームをあてがわれた。
カスバの「シディ・ホニス」を開いていたバーバラ・ハットンをはじめ、美貌にも肉体にも、エレガンスにも悪魔にも自信のある女たちも、次々にタンジールに入ってきた。カポーティがぞっこんになったのは、痩せぎすで頬紅が濃いエイダ・グリーンだった。象牙のケースからロシア煙草をとりだしては、ひっきりなしに吸っていた。
むろん褐色の娼婦はいくらでもいた。ムスリムの美少年も多かった。ポウルズが惚れたのはアハメッド・ヤクービという17歳の少年で、完璧な美を周囲にふりまいていた。そういうところへブライオン・ガイシンが、そしてウィリアム・バロウズがやってきたのだ。
ガイシンとバロウズについては、その「カットアップ」と「フォールドイン」の魔術的編集術とともに822夜に案内済みだ。また、それがすべてタンジールでおこっていたことも説明しておいた。だからここでは、本書にふさわしいことだけを補うにとどめるが、ガイシンをタンジールに呼んだのは、ボウルズだった。
そのころまだ34歳だったイギリス生まれのガイシンは、すでにパリのソルボンヌに逃れたのち、シルヴィア・ビーチ(彼女についても212夜に詳しく書いた)のクレバーな手配で、エルンスト、ダリ、ピカソらと交わって、当時のアウトサイダーを志すアーティストのすべての慣習になっていた「ガートルド・スタインとアリス・B・トクラスに詣でる」という儀式も終えていた。むろんゲイである。
そこにボウルズから声がかかったのだ。声がかかっただけではない。ガイシンはメディナの家に同居した。メディナというのはタンジール港から一番近い街区のことをいう。言い忘れたが、タンジールにはメディナ、カスバ、オールドマウンテン、新市街というふうな街区があって、取り澄ました連中はオールドマウンテンに、喧噪にも「キフ」という麻薬にも、また男にも女にも自信がある連中は、メディナやカスバに住んでいた。
そのメディナから、ボウルズとガイシンはフェズやマラケシュに旅をしては戻り、タイプライターを打ち、また喧噪の街をうろついた。1954年の冬、ガイシンは「レンブラント・ホテル」の画廊で個展をひらいた。ぼくの好きなカリグラフィック・ドローイングの類いだったろうと思う。ある夕刻、その画廊を閉めようとしても帰らない背の高い男がいた。まるでFBIから追われて仕方なくそこにいるというような、中折れ帽をかぶった風采の上がらないその男は、最近メディナに住みはじめたらしい。
ガイシンはひどく警戒したのだが、その男と喋ってみると、妙に博識、妙に深遠、妙に生臭い。ただし、ジャンキーであることだけはまちがいがない。
これがウィリアム・バロウズだったのである。ニューヨークで妻をピストル誤射し、保釈中にアメリカを脱走することにしていたバロウズは、その途中のどこかで『シェルタリング・スカイ』と『雨は降るがままにせよ』(これもボウルズの奇妙な傑作)を読んで、自分の行き場所をタンジールに決めたらしかった。
かくて、ボウルズ、ガイシン、バロウズが出会う。もう、いちいち経緯を紹介することをやめるけれど、そこにさらに、ギンズバーグやティモシー・リアリー(936夜)が加わったのである。これはとんでもないコンテリジェンスな顔触れだ。とうてい誰が計画しても無理である。まるで“逆上の社会”を代表する「反世界サミット」が、北アフリカの突端のタンジールで、秘密に催されたようなものだった。
これは、もう何も言うことはない。だから、これ以上、「タンジールのその後」について書く気なんてなくなるほどだが、実際には、この顔触れを支えたのが、褐色で献身的で、猥雑でセクシャルなイスラミック・アラベスクであり、数々のタンジールを出入りしたスノッブな欧米人たちの「たまには精神を凌辱されたい」と思う、例外的な気持ちであったわけなのだ。

モロッコは1956年に独立した。が、タンジールの崇高ないかがわしさをめぐる噂は、その後も廃れなかった。
それは、先にも書いたように1964年のスーザン・ソンタグまで続いたし、ローリング・ストーンズがやってきたときは、ブライオン・ガイシンがミック・ジャガーとキース・リチャードをいまだ邪悪な神秘が渦巻く迷路を案内しまくった。さらには、この「タンジールへのやむにやまれぬ衝動」は、これは本書の「あとがき」を担当した四方田犬彦が書いていることだが、レッドツェッペリンのジミー・ペイジの『タンジェリーン』という曲にも、ブライアン・ジョーンズの伝説的なモロッコ収録にもつながっていた。
ポール・ボウルズについては、ほんとうは書きたいことがいっぱいある。とくに『シェルタリング・スカイ』は忘れられないのでいろいろ書きたいのだが、今夜は遠慮しておこう。せめてベルトリッチが映画にしたものでもご覧いただきたい(ただし、あまり出来はよくない)。
というわけで、ぼくは未詳倶楽部の最後の行く先をタンジールにしたいと思ってきたわけである。けれども、そのタンジールは1950年代のタンジールなのである。
