父の先見


人文書院 1984
Joseph Campbell
The Hero with a Thousand Faces 1949
[訳]平田武靖・浅輪幸夫
超有名な本。有名になったのはいろいろ理由がある。
俗っぽいところからいうと、ジョージ・ルーカスが大学でキャンベルの授業をうけて大いに感動し、その英雄伝説の基本構造を『スター・ウォーズ』3部作にそっくり適用して大成功を収めた。何が基本構造であるかは、あとで述べる。
やや学問的なことをいうと、神話学上で初めて「英雄」を規定した。英雄とは「生誕の再現」がたえずくりかえされる人間であり、その生命の啓示がカトドス(上り道)とアノドス(下り道)の交差の上に幾度となく成立するような人間のこと、総じては「自力で達成される服従(自己克服)を完成した人間」のことである。なるほどとおもわせる。
キャンベルはまた、神の造形はあらゆる民族に共通する「欲求」にもとづいているという原理を提示し、どんな神の造形も解読可能であることを示した。さらには「神話の力」を現代に通じる言葉であらわした。すなわち、神話には集約すれば4つの力があって、それは、①存在の神秘を畏怖に高める力(これはルドルフ・オットーが「ヌミノーゼ」とよんだものに等しい)、②宇宙像によって知のしくみをまとめる力、③社会の秩序を支持し、共同体の個人を連動させる力、④人間の精神的豊かさに背景を与える力、というものである。
キャンベルの功績はそのくらいにして、本書のテーマである英雄についてであるが、ルーカスが『スター・ウォーズ』に適用した世界の英雄伝説に共通している構造というのは、単純化すると次のような3段階になる。
(1)「セパレーション」(分離・旅立ち)→(2)「イニシエーション」(通過儀礼)→(3)「リターン」(帰還)。
英雄はまず、(1)日常世界から危険を冒してまでも、人為の遠く及ばぬ超自然的な領域に出掛けるのである。ついで(2)その出掛けた領域で超人的な力に遭遇し、あれこれの変転はあるものの、最後は決定的な勝利を収める。そして(3)英雄はかれに従う者たちに恩恵を授ける力をえて、この不思議な冒険から帰還する。
だいたいこういうことである。ブッダもゼウスもプロメテウスもアイネイアスも、玄奘と孫悟空も桃太郎とイヌとキジとサルも、そしてモーセも大国主命も、みんなみんなこの通りの3段階をへて英雄伝説の主人公になった。
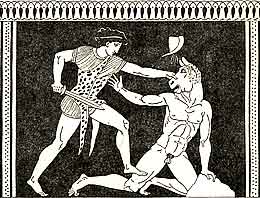
キャンベルはこの3段階をさらに詳しく分析して、それぞれに共通するスクリプトがひそんでいることをつきとめた。
図式的に書けば次のようになる。きわめて興味深い。ぼくなりの解説も加えておいた。
(1)セパレーション
①「冒険への召命」=★出立・分離あるいは冒険への使命がもたらされる。→★あるいは神・老人・特定の声などによる合図がある。
②「召命の辞退」=★しかし、いったんは召命はなんらかの理由によって辞退もしくは理解できないものとなる。→★主人公は神から逃走しようとする自身の愚かさを露呈する。
③「超越的な援助」=★超自然的なるものが思いがけなくも英雄を支援する。→★与えられた冒険を受け入れた者に思わぬ天佑がもたらされる。→★このとき援助者は矮小あるいは貧しい老人や老婆の身なりをしていることが多い。またしばしば助言者は意地悪な妖精になっている。
④「最初の越境」=★こうして英雄は最初の境界をまたぐことになり(バウンド)、そこで境界を守る者との対決を試され、これをなんとか越境する。→★これは異界への突入、限界の突破、異界の守護者(渡守・橋姫・猿田彦など)の認識をあらわしている。
⑤「闇への航海」=★英雄はさらに闇あるいは魔の領域に突入し、いったんはまったく別の負荷状態になる。→★これはしばしば「胎内回帰」とよばれるもので、自己消滅の危機さえ伴う。→★物語のなかではピノキオのように鯨の中などに呑みこまれることが少なくない。いわば、夢を見ているのかと見紛うばかりの「英雄流動」の段階なのである。(2)イニシエーション
①「試練の道」=★ここからは英雄の試練が次々に続く。→★玄奘と孫悟空の試練、あるいは日本神話でいえばイザナギや大国主命の試練などをおもえばよいが、象徴的には主人公が英雄になるべく「転身の門」をくぐるためのプロセスになっている。
②「女神との遭遇」=★英雄はひょんなことから女神あるいはマグナ・マーテルあるいはグレート・マザーと出会い、その力に包まれ、いきさつによっては聖婚(ヒエロス・ガモス)する。→★英雄は慈母・一時花嫁・代母などによって“永遠の幼児”としての至福感を初めて体験するわけである。→★これは主人公のエネルギーの「回復期」にあたるのであろう。
③「誘惑する異性」=★女神による回復をえた英雄は、しばしば誘惑者の快楽を断れない。しかし、このプロセスで英雄は「最大の真相」つまり「オイディプスの謎」を初めて理解する。→★神話上のスクリプトの中でも最も難解なところで、基本的には「父殺し・母との姦淫」が潜在しているのだが(第657夜『オイディプス王』参照)、それ以外にもマグダラのマリアや静御前や吉野太夫のような娼婦・白拍子・遊女との出会い、および悪女からの仕打ちが含まれる。
④「父との一体化」=★畏怖あるいは脅威の対象としての父が「大いなる父」でもあったことをどのように理解したかというドラマが、ここのテーマになる。→★『スター・ウォーズ』における隠れた父ダース・ベーダーとの対立と和解を思い浮かべればわかりやすいだろうが、キャンベルの原型はゼウスにおけるクロノスや、ディオニソスにおけるゼウスなどにあった。→★ここは別の観点からいえば英雄の「成熟」を暗示する。なぜなら英雄はここで初めてこれまでの試練の意味を悟ることになるからである。
⑤「アナザー・ワールド」=★英雄は父の真実の姿を知って驚くとともに、自分にとってはアナザー・ワールドである父がつくった国を体験する。→★この国は、王の国・神の国・ユートピア・アルカディア・老いた国・不老の国・魔王の世界・別世界そのほかの様相を呈する。→★しかしここでは、父に対するアンビバレンツな神格化もおこっている。そのためこの段階では両性具有のキャラクターがよくあらわれる。
⑥「終局の恩恵」=★英雄は大団円に到達する。それは不滅・勝利・獲得・謎解きなどの象徴の終焉であり、前に進む物語の終息である。→★ここで初めて世界模型の全貌があかされることが少なくない。たとえば須弥山、シャンバラ、エルドラドなど。(3)リターン
①「帰還の拒絶」=★英雄は故国への帰還の旅立ちをするにあたって、収穫物(エメラルド板・黄金の羊毛・玉手箱・不老長寿の薬・金銀財宝・眠れる王女など)を持ち帰らなければならないのだが、その困難を予想して責務履行はいったん拒否される(あるいは持ち帰るほど期待される戦利品がない)。→★夢から覚めたくないという本音の気分が報酬の重荷に転移したというふうにも解釈できる。
②「呪的逃走」=★押し付けられた戦利品(たとえば王女)から逃げ出したくなり、主宰の王や管理者からの呪いを振り払って逃走する。→★追跡者の手から逃れる逃走神話には、たいていは残し物・変種の物の散布などが絡む。→★ヘンゼルとグレーテルはお菓子の家に到達したのに、そこが怖くなって逃げるとき、さまざまな呪文と戦わなくてはならなかった。イザナギは冥界からの逃走にあたっては多様な物を投げ捨てながら走らなければならなかった。
③「外界からの救出」=★英雄の逃走が進むには、ときにそこに外部的な超常力が加わる必要がある。→★オズの魔法の国やアリスの不思議の国からの帰還には、外力が手をさしのべる。ダンテが地獄篇の世界を脱出するにも巨人の助力が必要だった。アマテラスの岩戸からの脱出にも外力が加わっている。
④「帰路の境界」=★英雄は彼岸から此岸に戻ろうとして、さまざまな境界を逆方向に、かつ上手にまたいでいかなければならない。それに失敗すると英雄は因幡の白兎か浦島太郎になってしまう。→★ここにはリップ・ヴァン・ウィンクルの原型がある。英雄は最後に「時間の旅」の試練を受けたのである。ここにトランジットの問題の本質があらわれる。
⑤「二つの世界の導師」=★英雄はついに空間と時間の仕切りを越えて帰還に至る。このとき、これまで仮の姿であったすべての化身たちの正体が、輝きあるいは驚きをもって出現してくる。そこに英雄自身が実は神の仮 の姿であったという逆転も含まれる→★英雄クリシュナは実は宇宙神ヴィシュヌであり、助六は実は曽我の五郎だったのである。
⑥「自由と本性」=★こうして英雄が故郷に戻ると、そこは まったく新たな王国・原郷・共同体としての活気に満ちてくる。祭りが挙行され、婚姻が進み、財産が配分される。→★この最後の場面こそ、その後に何度も再現されることになった世界各地の祭りのクライマックスになっていく。
ざっとこんなふうになる。
適当にぼくの言葉を補ってはいるが、重要なのは、このような基本構造が“発見”されたことである。ここでは省いたが、この基本構造の説明にあたっては、世界中の神話伝説のプロットがみごとに引き抜かれ、一人の巨大な英雄のスクリプトの場面を構成するようになっている。その編集性も本書の魅力のひとつなのである。
それにしても、英雄伝説には以上のような基本の流れと基本の特質があるということを知ってみると、物語の母型というものが、いかに多くの物語・小説・オペラ・映画・劇画・マスメディアによる実話再生法などに頻繁につかわれていたか、そのことに驚くにちがいない。
しかしキャンベルはルーカス・フィルムや作家たちを大儲けさせるために、このような分析をしたわけではない。
キャンベルは人間の根本に宿る物語には、「眠り(闇)」と「覚醒(光)」の絶えざる循環という母型が、「実界(此岸・現世)」と「異界(彼岸・浄土)」の境界を告知しつづける母型が、さらには、「父(隠れた力)」と「子(試される力)」の関係の不確定をめぐる母型が、「個体(ミクロコスモス・部分・失われたもの・欠けたもの)」と「宇宙(マクロコスモス・全体・回復したもの・満ちたもの)」との対立と融和と補完をめぐる母型などが、きわめて多様にばらまかれていたことを示したのだ。
いま、このようなことを綴っていて、久しぶりにぼくがいっとき夢中になった「オペラ・プロジェクト」がキャンベルの英雄伝説分析に潜在していた多くの物語母型に着目するところに端を発していたものだったことを思い出して、懐かしい。
その後、佐藤恵子とアメリカに行って、キャンベル亡きあとに設立されたジョセフ・キャンベル・ファウンデーションを訪れたとき、ぼくが子供のように『千の顔をもつ英雄』のコンピュータ化の夢を話しおわると、「日本にキャンベルの申し子がいたんですね!」とホメ殺しにあったことも、いま久しぶりに思い出した。
けれども、これは推測でしかないが、いまキャンベルはほとんど忘れ去られてしまったのではないかとも思う。神話と現代をつなげることなど、映画プロデューサーか劇画家しか関心がむかないことになってしまったのだ。
が、それならば、言っておきたいことがある。
神話というものは、「一」と「多」の間にいかなる危機や裂け目が生じるかという物語なのであるということを――。
ひるがえって、英雄とは、その「一」と「多」の間に出現する危機と裂け目を克服した者であり、その境界がどこにあるかということを告げるために用意された装置だったのだ。
しかし、そこには必ず犠牲が伴い、予期せぬことがおこっていく。もし英雄を待望したいのなら、このことも見落としてはならないことなのだ。そして加えて、思いがけない者こそが味方であって、見かけぬところが境界の秘密なのであり、中心こそが静寂なのであることを知ったほうがいい。われわれが今日、そのような「思いがけない味方」や「静寂な中心」をアメリカにもヨーロッパにも日本にも見いだせなくなっているのは、われわれに極端に神話の力を理解する力がなくなっているせいでもあるだろう。
ところでキャンベルは本書の第2部で、このような英雄伝説がもたらす神話作用の本質をさらに凝縮してみせているのだが、とくに最後に、英雄がときに「世捨て人」や「苦行者」の姿をとること、および英雄伝説が「死と離別」をたいせつにしつづけていることを指摘するのを忘れなかった。ぼくがキャンベルに夢中になったのは、こういうことをキャンベルは絶対に言い忘れない神話学者であったからである。