芸と道
前口上
弾いて哀切、舞って幻、演じて飄々、笑って下げる。
日本の芸事は琵琶法師や世阿弥や説経節に始まった。
盲人が曲と節を案じ、三味線にサワリが生まれ、
浄瑠璃や豊後節あたりで、慟哭のポップスが出現した。
そこから踊りも役者も落語も浪曲も派生した。
この一冊には極め付けの芸道名人たちの「間」が躍る。
(前口上・松岡正剛)
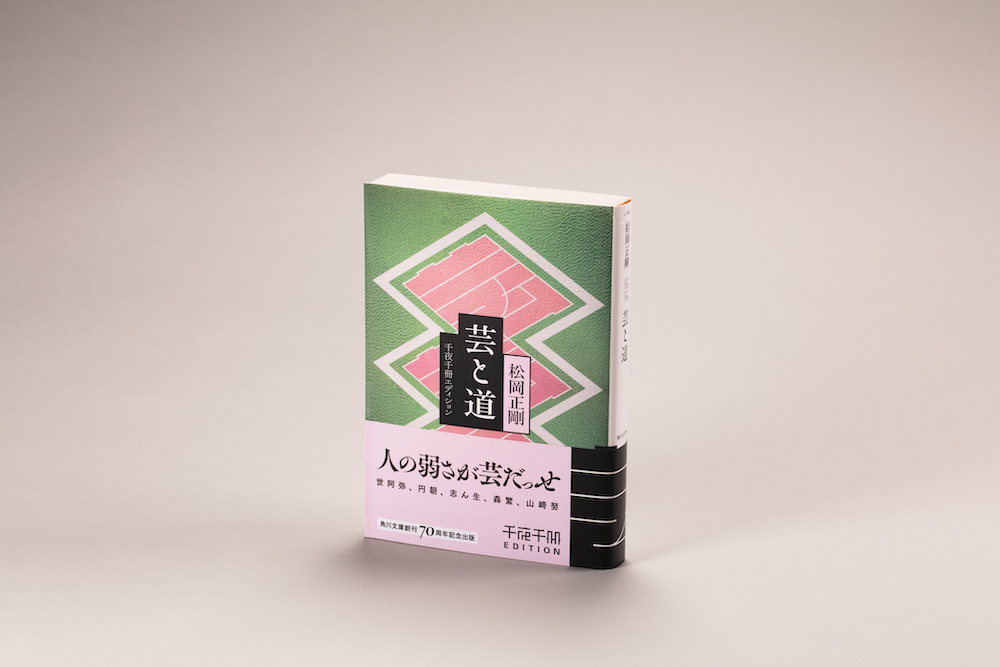
世阿弥の稽古哲学から三味線名人の芸談まで、江戸が胸詰まらせた新内から20世紀の新日本音楽まで、寄席芸人の至芸・粋芸から喜劇の王様・殿様まで。京都の旦那衆だった父から受け継いだ芸道数寄の精神を発揮し、「これでできなきゃ日本は闇よ」と啖呵を切りながら、松岡が格別に贔屓にしてきた名人たちを揃えて見せる、切なくも華やかな一冊。
第1章 世阿弥に始まる
芸能論として唯一無二であるばかりでなく、達人の世界観にして極上の人間観が刻印された花伝書。この世のものならない異界とのあわいに成立する複式夢幻能の構造と、現実世界の人間の愚かさを慈しむ狂言の笑い。能・狂言の天才たちの言葉から、日本の芸能の基本である「うつし」と「わたし」をたどる。
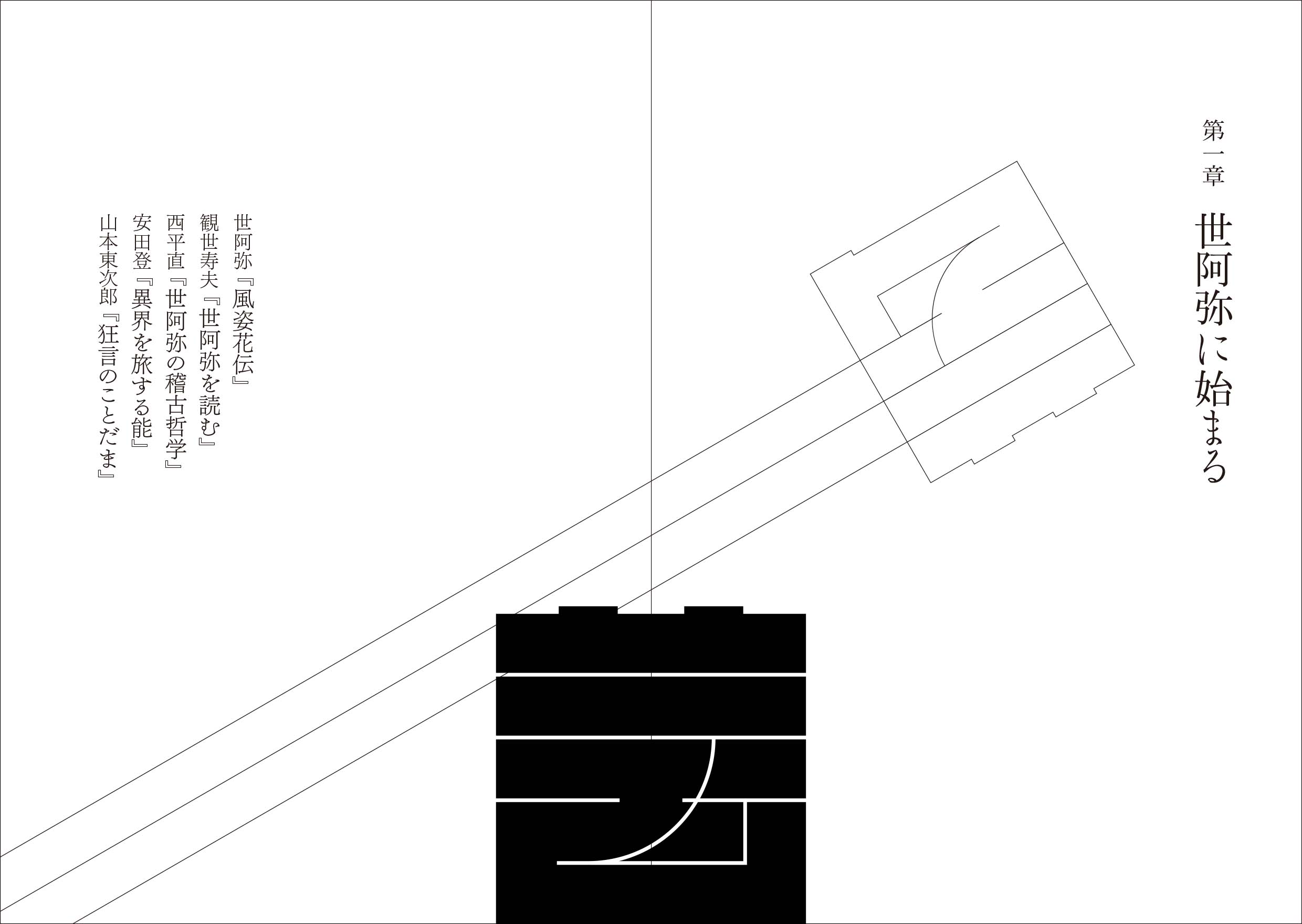
第2章 芸能と音曲
河原者や盲目の漂泊者たちや遊女から始まった日本の芸能文化史を、林家辰三郎と兵藤裕己の名解説に託して説く。江戸に開花し多様化した三味線音楽の真髄は、平岡正明が魅惑された「新内」をもって記す。日本音楽の行方と可能性は、宮城道雄、高橋竹山、本條秀太郎たちの革新性によって示す。
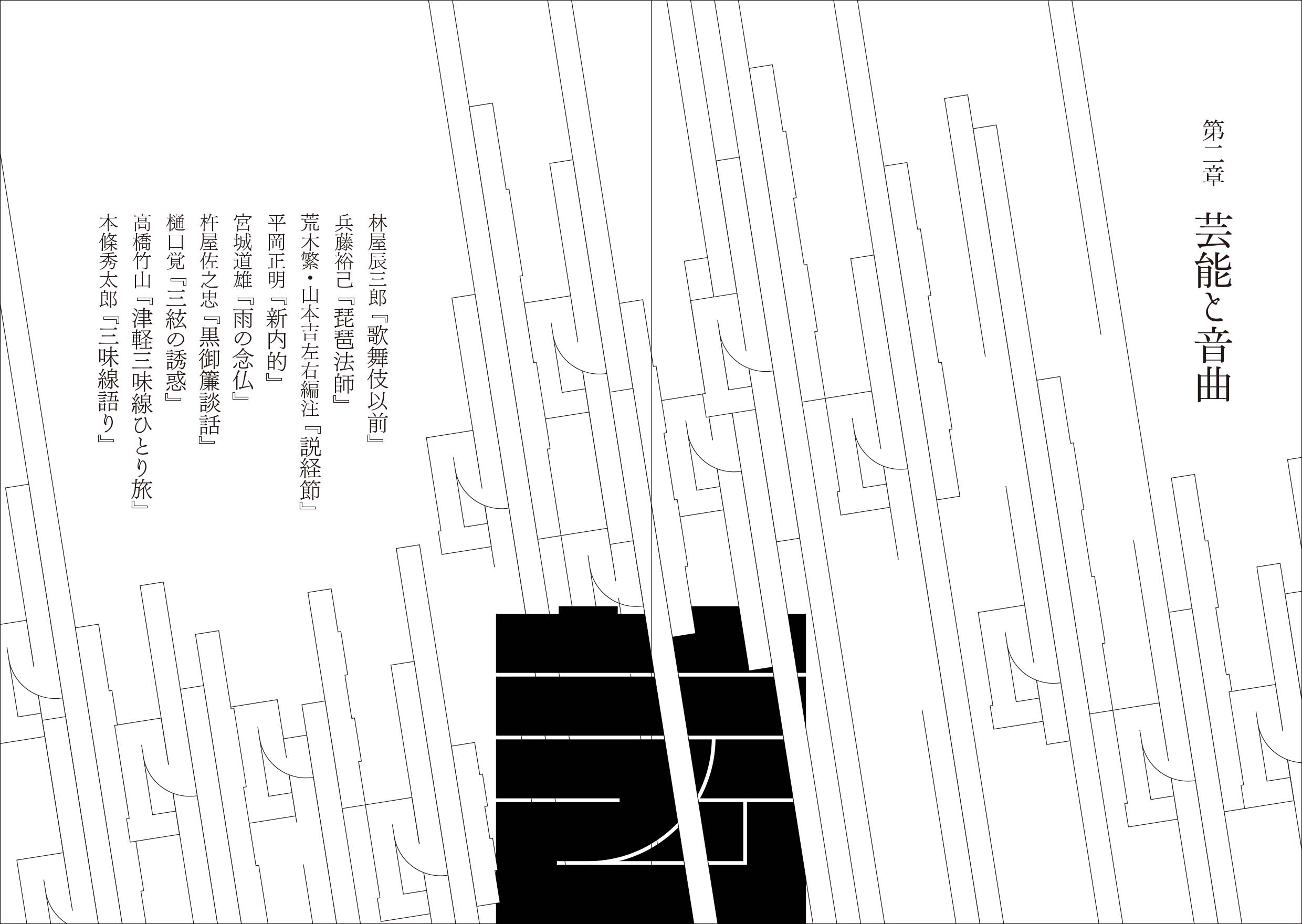
第3章 芸道談義
松岡が最高峰の舞台芸術だと評価する文楽の世界を、有吉佐和子『一の糸』をはじめ安藤鶴夫、吉田簑助の芸談によって案内。そこから、伝統と前衛を相互越境させた演出家の武智鉄二、女形の雀右衛門、黒衣の秀十郎、男装の鶴田錦史、地唄舞の武原はん、徳川夢声の話術、太鼓持あらいの「間」へと駆け抜ける。
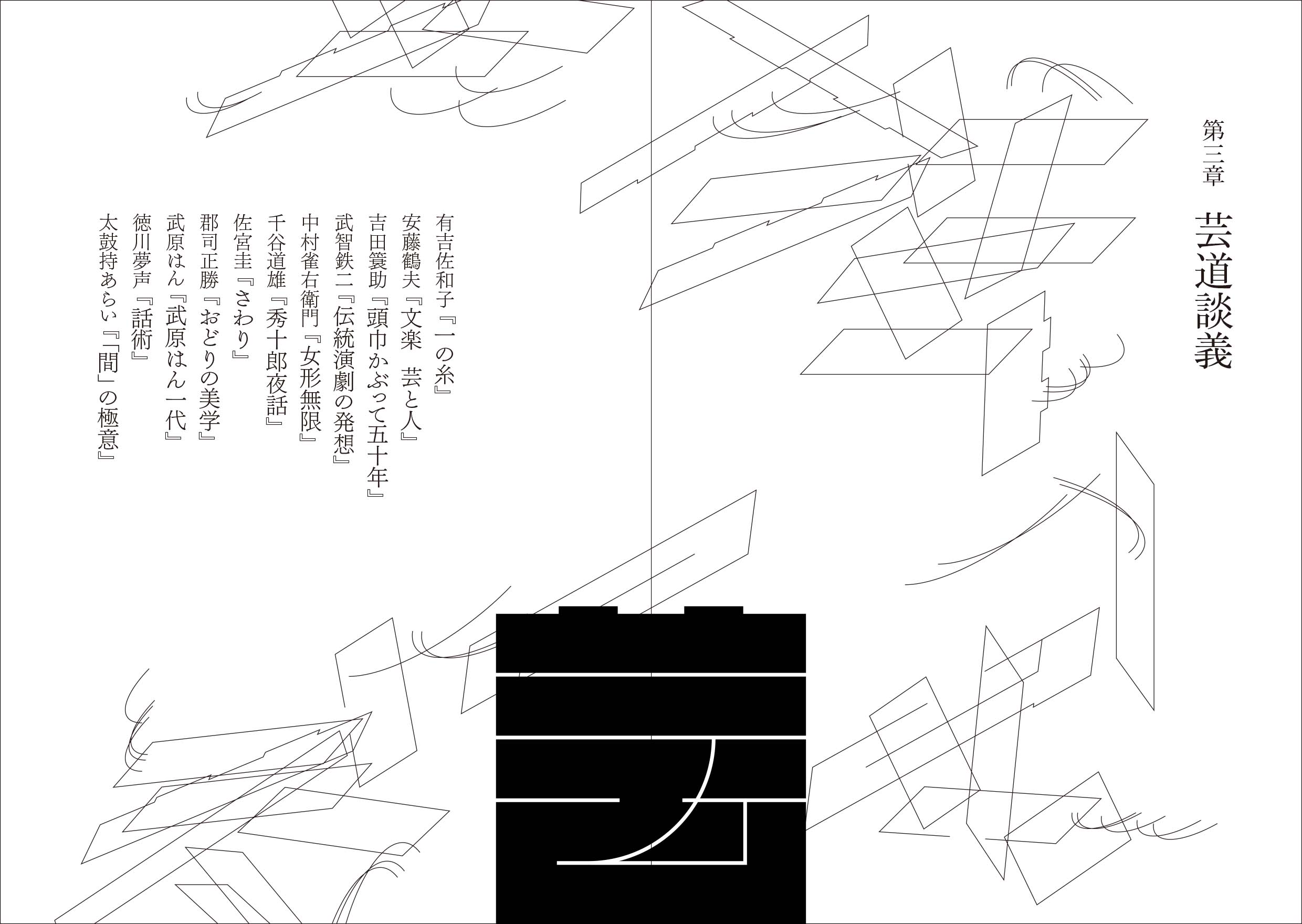
第4章 寄席や役者や
少年期、父に導かれて通った人形町末広亭の思い出もまじえながら、円朝、文楽、志ん生、志ん朝たちの至芸を披露、さらに桂米朝による上方芸能の名案内を紹介する。モリシゲ、伴淳、のり平に泣き笑いした松岡がオオトリに登場させたのは、リア王の狂気を緻密につくりあげていく、山崎努の壮絶な記録。
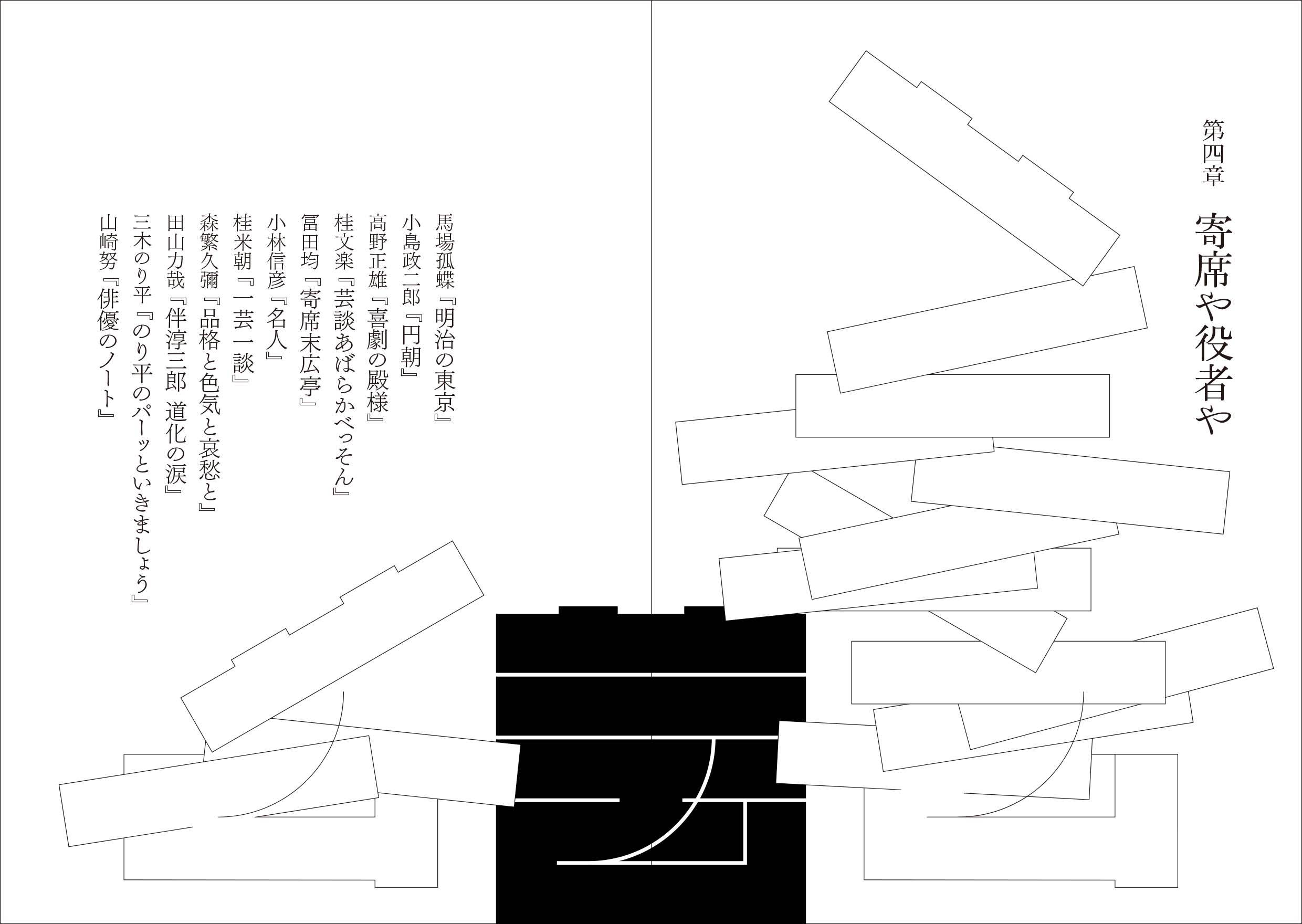
『芸と道』
第1章 世阿弥に始まる
- 118夜 世阿弥元清 『風姿花伝(花伝書)』
- 1306夜 観世寿夫 『世阿弥を読む』
- 1508夜 西平直 『世阿弥の稽古哲学』
- 1176夜 安田登 『ワキから見る能世界』
- 646夜 山本東次郎 『狂言のことだま』




