父の先見


平凡社ライブラリー 2001
[訳]荻原達子
見るといっても、離見の見。花といっても、時分の花。能はひたすら感じるものであるけれど、感じてもなお、能は却来なのである。
観世寿夫はぼくの憧れの人だった。当時すでにして〝昭和の世阿弥〟と呼ばれていた。見て、聞いて、そして接してみて、その深さと前衛性と覚悟と柔らかい高さに、心底、敬服した。以下、失礼ながら「寿夫さん」と言わせてもらう。
いまから30年以上前の1976年8月のこと、寿夫さんの能の取り組みをかたわらで固唾をのんで拝見したことがあった。所は利賀村(富山県)。その年の眩しいくらい暑い夏のなか、鈴木忠志の早稲田小劇場「利賀山房」が開場したのだが、ぼくはその一部始終を映像記録するために数日前から工作舎のスタッフとともに利賀村に入っていた。以前から知り合いのチューさん(鈴木忠志)に頼まれて『劇的なるものをめぐって』(のちに工作舎発行)という本をつくるためでもある。
そこへ、オープニング記念に《経正》(経政)を舞うために寿夫さんが招かれ、農家を改造して醤油などで黒光りさせた変形舞台に向かったのである。
まだ朝の風が静かに吹き通っていた刻限、寿夫さんが誰もいない醤油舞台を前に、静かに考えこんでいる場面に出くわした。しばらく黙って様子を見ていたら、寿夫さんもこちらに気がついて会釈をされた。思わずふらふらと近寄って「この舞台をどういうふうに使われるのですか。経正ですよね」みたいなことを言ったところ、寿夫さんはオールバックの髪に少し手をやって、「いま、その段取りをアタマに踏んでましてね」と言われた。
それだけで何かが痺れてきた。「段取りをアタマに踏む」。もう、これで十全ではないか。それでもぼくは「で、どうですか」とでも、愚かなことを訊いただろうか。そこはまったくおぼえていないのだが、たしか、「音がね、声のことですが、どういうふうに動くかというのが、まだ入っていないのでね」というようなことを言われた。
翌日の《経正》の舞台は圧倒的だった。静かでテンポのよい修羅物だが、熱かった。それから2年後、胃癌が発見され、癌はリンパ節に転移して寿夫さんを蝕み、やはり暑かった夏の一日、青山銕仙会の装束や面の虫干しに立ち会っているとき、激しい腹痛で倒れてしまった。わずか53歳の「闌位の花」だった。
本書は荻原達子さんが、『観世寿夫著作集』全4巻(平凡社)から世阿弥を出入りするエッセイ・講演・論文を絶妙に選抜した1冊である。とてもよくできている。元の著作集はそこそこ読んでいたけれど、どちらかというと早逝した寿夫さんを惜しむように拾い読みしていたので、そこから立ち上がってくる「能の知」に分け入るというような読み方をしていなかった。それが本書ではことごとく動きだし、リンキングし、新たなレティキュレーションとアーティキュレーションが交差した。
いまぼくは、寿夫さんが利賀山房で「声がどういうふうに動くか」と言ったことについて書いたけれど、あのころはその真意がほとんどわかっていなかった。せいぜい舞台の空間を声や囃子の音がどんな反響で動いていくのかということだろうとしか理解していなかったのだが、そんなことではなかったのである。本書にある「無相真如」というエッセイをあらためて読んだとき、やっと了解できた。寿夫さんはこんなことを書いていた。
謡曲《芭蕉》に「それ非情草木いっぱ、まことは無相真如の体、一塵法界の心地の上に、雨露霜雪の象を見す」というくだりがあるとき、これを役者がヒジョーソーモク、ムソーシンニョ、イチジンホーカイ、ウロソーセツと謡っても、とうてい観客はそこに妥当する四文字熟語は思い当たらない。では、どうするか。寿夫さんはそれでいいのだと言う。それが能というものだと言う。何かを呑み込まなければ、能は始まらない。その何かとは花伝書なのである。
能にはたいそうシンプルではあるが、筋書きがある。筋書きがあるから、みんなそこに引っかかる。能楽堂に行くと、これから始まる演目の粗筋をパンフレットなどで読んでいる観客が少なくない。
たしかに筋書きがわからないでは不安になろうけれど、しかし、その筋書きは曲に入るための手掛かりであって(つまりはプロノーム=認知の手摺であって)、曲が進むにしたがってどうでもよくなるし、亡霊になったシテの生前の人生が何であるかもどうでもよくなっていく。シテの正体が芭蕉の精か式子内親王かということよりも、そこで謡われていく言葉と音と律動が呪能的とさえいえるような「祈りの抑揚」になっていくことが眼目なのである。役柄のステレオタイプ(典型)はむろん、能としてのプロトタイプ(類型)さえどうでもよくなって、われわれの奥なるアーキタイプ(原型)が動きだすからだ。
寿夫さんは、そこが大事なんだと言う。声がどう動くかということは、べつだん音の響き方なんぞを問題にしているということではない。利賀村の舞台は初めての空間だから、そのことにも多少の計算はあるだろうが、それよりも、そのような呪能的な声を寿夫さん自身が明日の夜にどのように演ずるか、そのことを思案していたようだった。
本書にはそういうふうに、ハッと思い当たる話がいろいろ詰まっていた。そこには分母としての「能の地」と分子としての「能の図」が仕分けられている。
ぼくは去年(2008年)の晩秋、NHKの教養講座での8回分の話をもとにして平凡社新書に『白川静』を書いた。いろいろのことを案内したが、大きくいえば白川静は「漢字マザー」を発見的に注目したのだということ、東洋的思考にひそむアーキタイプを動かしたのだということ、この2点を特筆しておいた。ぼくなりに白川さんが到達した「東洋日本」の分母に読者を誘うことを心がけたのだった。
観世寿夫も、そうだったのである。世阿弥の「能マザー」を動かして、われわれを「われらが奥なるアーキタイプ」に誘おうとしてくれたのだ。そのごくごく一端が利賀山房の1日にもあらわれていたのだった。

話のついでに、能の声のことを書いておく。
世阿弥は舞台に臨む能の声について、「一調・二機・三声」と言った。能の役者というもの、最初にこれから発する声の高さや張りや緩急を、心と体のなかで整え、次にそのような声を出す「機」や「間」を鋭くつかまえて、そして声を出しなさい。そう、指南した。
こんな演芸的芸術は世界中にもほかにない。まるで禅機を動かすことを要求しているようであり、あたかも裂帛の気合を尊ぶ武道のようでもある。けれども禅や武道が観阿弥や世阿弥の時代に広まっていたわけではなかったし、2人がそのような名人や達人の心や芸に接して何かのインスピレーションをおぼえたのでもなかった。観阿弥親子は自身で「一調・二機・三声」を創発させたのだ。
これを『風曲集』でいえば、「出る息、入る息を地体として、声を助け、曲を色どりて、不増不減の曲道息地に安位するところなるべし」ということになる。まさに「地の能」があって、そのうえに出る息・入る息の「図の能」が動くのだ。
このようなことを、たんに発声にあたっては腹式呼吸を訓練すればいいなどと受けとってはならないというのが、寿夫さんが早くに体得したことだった。「息のつめ」あるいは「体のつめ・びらき」というふうに体得した。息と体はくっついていた。
能には、見たり聞いたりしていればそれなりにわかってくることがある。それには、杓子定規に観能するというのではなく、何でも見るのがいい。ぼくもそう思って、松濤の観世能楽堂から歩いて3分のところに引っ越したことがある。普段着でちょいちょい覗きたかったからだ。50番か60番くらいにさしかかってくると、風味や奥行のようなものがしんしんと伝わってくる。体の動きのキレやタメも見えてくるし、能の声というものも、聞こえてくるというのか、見えてくる。
ときには失望することもある。ぼくの経験では、謡いの1文字ずつの〝字の声〟がのびてしまうのが不満を感じることで、その〝字の声〟が体の弛緩ともなって、鑑賞者にもやや耐えられないときがある。能はすこぶるギリギリの芸能なので、こうした〝字の声〟の扱いは微妙精妙なのである。
世阿弥は『音曲口伝』(音曲声出口伝)に、「惣じて音曲をば、いろは読みには謡はぬ也」と指摘して、1文字ずつを「い・ろ・は」というふうに切って読まないようにしなさいと言いつつ、「まなの文字のうちを拾いて、詰め開きを、てにをはの字にて色どるべし」と書いた。まな(真名)の文字、つまり漢字になっているところを掴まえて発声し、あとを「てにをは」といった活用語尾や助詞で調節しなさい。その緩急自在や縦横呑吐が大事だというのである。

もともと能には「横ノ声」「豎ノ声」「祝言ノ声」「望憶ノ声」という分け方がある。横は出る息、豎は入る息をいう。「横ノ声」は外側に向かって強くなり、「豎ノ声」は内向的で柔らかい。それが原則なのだが、必ずしも内向きの声、外向きの声とは分けられない。世阿弥は「相音」こそ重要で、1句を謡うなかにも横豎を入れこむほど稽古をしたほうがいいと奨めた。
「祝言ノ声」は明るく喜びに満ちた声にする。祝い事や結婚式などでもこの声が活躍する。「望憶ノ声」のほうは遠いところから響いてくる記憶を呼びさますような声をいう。懐かしく、また時を超えるようで、ぼくが大好きな声だ。けれどもこれも、だからといって祝言ノ声が弾みすぎては能にならないし、望憶ノ声が暗く沈みすぎてもいけない。世阿弥は望憶ノ声の調子が下がりすぎることを戒めていた。
寿夫さんのシテとしての声は5、6曲しか聞けなかった。だから生意気なことなどほとんど言えないけれど、いまでもやや高めの艶を思い出すことができる。それが開口ただちに始まって、それから鎮み、横たわり、そうかと思うとたちまち変じて、急激な「声の姿」をともなって動いていく。それでいて全容は一度として激しくはなく、上品で、凜然としつづけている。
そういう寿夫さんに何を感じたかというと、「意味」を感じた。ああ、この人は能のもつ意味を謡っている、ああ、この能には意味が舞っていると感じた。能の風味は意味なのだと思ったのだ。
声のことだってこのように深いわけであるが、能はそれに加えて、そこに拍子や旋律が交じっていく。フシ(旋律)はともかく、なんといっても拍子がまたまた複雑だ。
寿夫さんも「能の拍子は謡いの詞章の字数およびフシによる伸び縮みを基準にして数理的に配分されているので、譜面上の計算は記号(符合)が読めさえすれば可能なわけであるが、音と音との間隔の振幅がはなはだしいため、これを体得することは相当にむずかしい」と書いている。
そもそもは小鼓や大鼓や太鼓といった打楽器の伴奏があっての拍子と、無伴奏のときの拍子がある。無伴奏のばあいは声や足が拍子をとる。打楽器があるときも、打つ手と謡いの拍子が合うところ、合わさないところ、拍子には無関係にするところがある。その案配をいろいろ変えなければならない。
それがいわゆる「ノリ」であるが、そのノリもまた平ノリ、中ノリ、大ノリに分かれていく。平ノリは日本の伝統音楽のなかでも能にしかみられない。七五調12字を8拍子にとっている。しかし詞章の言葉は7・5の句ばかりとはかぎらない。原則としては、たとえば「在原寺の夜の月」であれば、この12字を「あ~・りわ・ら~・でら・の~・よる・のつ・き○」というふうに8拍子にするのだが、それには言葉でも打楽器でもあらわさない拍子を、声と体のリズムとして抱えこまなければならない。そこがとんでもなく複相的で、まただからこそ能らしくなってくる。
中ノリは2字を1拍にあてるので、8・8調が基本になる。「いか・にも・だい・じを・のこ・さず・つた・えて」というふうに、かなりリズミカルになるため、1曲のなかでも多くは曲の終わりでつかわれる。動きもかなりきびきびとする。
大ノリは1字が1拍になる。「さ・な・が・ら・ま・み・え・し」というふうにはっきりしている。西洋音楽にいう4拍子に近く、そのぶん示威的な舞踊性にふさわしい。亡霊や神懸かりした役があらわになるには、この拍子が説得力をもつ。
これらがだいたいの拍子の割り振りではあるのだが、実は能の詞章は7・5調もしくは8・8調でありながら、これが自在に3・5、5・4、ときに6・6、6・8というふうになる。破れるのである。能はこの「破」をうまくいかして、拍子を内外に出入りさせて曲調をつくっていく。とうてい一様ではないのだ。コノテーション(内示性)とデノテーション(外示性)が内外から啄まれているとしか言いようがない。ぼくが「意味」というのは、ここなのである。
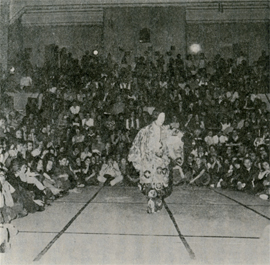
能がおもしろいのは、筋書きや舞の美しさにとどまらないものが、名状しがたく出入りしているからである。
出入りしているものはいろいろある。声や拍子もそうであるけれど、もちろん体にもいろいろの〝もの〟が出入りする。霊やら魂やら気配やら、むろん感情も沈潜も、逆上も思慕も出入りする。それを世阿弥はまとめて「二曲三体」とも言った。
応永27年(1420)、58歳のころの『至花道』にその見方が明示され、翌年には『二曲三体人形図』としても著された。《井筒》などのいわゆる複式夢幻能が完成するのはこのあとだったから、この「二曲三体」は世阿弥の円熟がもたらした「能に出入りするもの」の根底的な決定打であった。序破急でいうのなら序、守破離でいうのなら守であった。
二曲というのは「歌」と「舞」である。その「歌」というのが、これまで少々述べた声や詞章や拍子に依っている。「舞」は体の動きのことで、その根本はカマエとハコビのみに依っている。そのくらいカマエとハコビは徹せられてきた。稽古はそのカマエとハコビを丸呑みに体得してしまうことに始まり、そしてそこに終わる。そのことを寿夫さんがどのように書いているかを、少しだけだが紹介する。
カマエとハコビ。
これは能のからだを動かすうえで最も基本になるパフォーマンスである。能、ことに夢幻能においては、演者はあの吹き抜けの舞台で、一人の生身の肉体であることを超越してそこにいたい。空間というものが演者によって変貌していってほしい。そのために演者の姿は舞台に根が生えたような存在感を伴わねばならない。ただ立っているだけで、ひとつの宇宙を象りうる存在感がいる。どうやってそれを持つか。
舞台で立っているということは、能の場合、前後左右から無限に引っ張られている、その均衡の中に立つということなのだ。逆にいえば、前後左右に無限に力を発して立つことになる。無限に空間を見、しかも掌握する。それがカマエである。
ハコビというのは、歩み、止まり、動き、騒ぎ、ためらい、静まるということだが、それをまたどんどん引き算しきっていく。寿夫さんはそのことについても、「演者は歩くことにおいても、歩くという行為を超越して歩きたい。それがハコビである」と書いている。
世阿弥はカマエとハコビによって「型」が作られ、「型」が動くと考えた。しかし、「型」が歌舞二曲によって能になるには、他方では、そこに「三体」が見据えられていなければならないとした。老体・女体・軍体だ。この三体は世阿弥の「物学」の基本中の基本になっている。かつて世阿弥は『風姿花伝』(花伝書)においては「物学条々」で九種の役柄をあげていたが、晩年になって二曲三体論が確立すると、これを三体に絞りあげた。
世阿弥が三体についてのべたキーワードは、あたかもちりちりと灼けた燠火のようである。めらめらと燃えさかるものではない。それを四文字熟語でいうのなら、老体は「閑心遠目」によって、女体は「体心捨力」で、軍体は「体力砕心」をもって、それぞれ演じなさいというものだ。
二曲から入って三体へ。これが世阿弥が教えた能の稽古の根本だったのだ。そこからあらゆる変化多様が出ていった。
総じて、能にはこういう〝もの〟が出入りしているわけである。この〝もの〟は「霊」という字をあてる。「もの狂しい」「ものめずらしい」「ものすごい」の〝もの〟である。寿夫さんはそこに根を下ろして、そのうえで現代の能の器量を打ち立てようとしたのだけれど、実はこのように「世阿弥に戻る」という姿勢を示したのは、能役者では寿夫さんが初めてだったはずだ。

その時代その時代で、能役者たちがどのように世阿弥の著作を読んできたかという変遷は、わからない。ほとんど読まれてこなかったとおぼしい。能が「式楽」となった徳川時代でも、世阿弥の伝書を見ていたのは観世と金春の家くらいのことで、とくに明和あたりからはその著作の存在すら知られなくなった。
明治に入って文明開化が吹き荒れると、武家の式楽だった能楽界には激震がおこり、茶の湯や歌舞伎とともにその存続が危ぶまれた。このようななかから梅若実・宝生九郎・桜間左陣といった名人が次々に輩出して伝統が復活されていったのだが、名人たちはそのころ続々と〝再発見〟された世阿弥の伝書には目もくれない。そこでは激しい稽古が重視され、「世阿弥を読んだからといって能が舞えると思うな」という体得の道のようなものが先行していた。文字を読むなんてことは〝逃げ〟だったのだ。
昭和に入ってからは、今度は戦争である。世阿弥を読むどころか、日本人は観能の余裕さえ失った。こうして敗戦まもなく、焼け残りの東京の片隅でやっと世阿弥が本気で読まれるようになったのである。その先頭に立ったのが能役者のほうでは、まだ20代半ばの観世寿夫・栄夫・静夫の兄弟だった。
寿夫さんはエッセイ「能と私」のなかで、自分を変えた3つの出来事として、太平洋戦争、世阿弥との出会い、外国人による能の見方をあげている。まさにその通りで、寿夫さんたちが能勢朝次らの能楽論や世阿弥論に教えられ、今日の世阿弥の語り方が定着したといっていい。
というわけで、能と世阿弥は直結していると思われがちだが、それを能楽界にもたらしたのは昭和20年代後半の若き観世寿夫だったのである。
寿夫さんのお父さんは観世雅雪(七世観世銕之丞)といった。おじいさんは名人として知られた観世華雪(六世銕之丞)である。おじいさんをかなり尊敬していたことは、本書でも著作集でもよく伝わってくる。寿夫さんは長男で、すぐ下の弟が現代劇にも映画にもテレビにも活躍した観世栄夫だ。ぼくは栄夫さんのほうに早くに出会えた。その下の弟に幸夫、静夫がいたけれど、幸夫は早く亡くなった。
生まれは大正14年(1925)の11月だから、その生涯はぴったり昭和と重なっている(三島由紀夫ともぴったり重なっている)。幼稚舎から慶應に通い、17歳のときに本格的に囃子の稽古にとりくんだ。太鼓は柿本豊次、大鼓は亀井俊雄、小鼓は大倉流の鵜沢寿と幸流の幸祥光、笛は寺井政数。錚々たる顔ぶれだ。名人の亀井からは《道成寺》を相伝された。シテ方では例を見ない打ち込みぶりである。
この囃子稽古では、太鼓の稽古場で横道萬里雄に出会ったのが大きかった。その後、横道さんとはずっと親交を深め、多くの示唆をうけている。本書の平凡社ライブラリーの解説も横道さんが書いている。きっと寿夫さんの凄みをうかがい知るには参考になるだろうから、その一部を紹介しておこう。
寿夫さんが《野宮》を演じたときの話だ。六条御息所の霊が後ジテになっている。終わり近く、「神風や伊勢の内外の、鳥居に出で入る姿は、生死の道を神や受けずや思ふらん」という詞章がある。ふつうは、「出で入る姿は」というところで、片足を作り物の鳥居から一歩踏み出しかけて、すぐまた引っ込めるという所作をする。これは当て振りで、盛りをすぎた女の心の葛藤をあらわしているといえばそうなのだが、寿夫さんはこれには満足できなかったのか、鳥居の前を左右に行きつ戻りつしてみせた。
これが凄かったらしい。女の心のためらいがバアーッとあらわれた。「型」を守って「型」を出たのである。「破ノ舞」の留メでは、するすると正先に出て片足を踏み出し、すっと引っ込めて後退し、膝をついて合掌した。この「型」は、境界を乗りこえようとして躊躇する心情をあらわしているのだが、それを「鳥居に出で入る」という当て振りに終わらせたくなかったのだ。
そういうことを寿夫さんはさまざまなところで工夫した。武智鉄二が《智恵子抄》を演出したときは、エロティシズム大好きの武智は光太郎と智恵子が肉体的に触れ合うことを要求した。しかし寿夫さんは、光太郎が智恵子と向き合って座したまま、少し左半身をうしろへ引きつつ、右手にもった扇の先をじりじりと体の前に出し、智恵子の扇の先とぴったりくっついたところで動作をとめ、それを見せてから体をゆっくり離していった。ベッドシーンとしては最高の能だったという。
こんなふうに横道萬里雄は盟友観世寿夫の演技を語るのだ。そのほかいろいろ寿夫さんの〝昭和の世阿弥〟ぶりを彷彿とさせるくだりもある。ちなみに、この解説を書いた2001年、横道は何を指摘したかというと、現在の能の盛況があるとしたら、その大半が観世寿夫の遺産で成り立っていて、そう思うと、現在の能楽界の現状はその先が見えず、ただ暗中模索の様相にとどまったままにあるということだった。

寿夫さんが敗戦を迎えたのはちょうど20歳のときである。一挙に真剣きわまりない研鑽と活動を開始した。世阿弥に戻ることを志した。
当初こそ、空襲によって観世の舞台と自宅が焼亡して、自由が丘・大曲の観世会や観世宗家に仮り住まいをしたり、玉川用賀の三井別邸などに身を寄せたりしていたが、昭和21年(1946)からは銕仙会の定式能を再開し、大磯の川崎慶一の家に若手が集まって稽古や談義に励むようになっていく。
能楽塾(初代塾長・桑木巌翼)に入塾して、安倍能成・田辺尚雄・土岐善麿・野上豊一郎・野々村戒三の講義を熱心に聞いたのも大きく、ただちにみずから銕仙会研究会を発足させると、昭和23年には野口兼清・観世華雪の監督のもとに、松本恵雄・波吉信和・三川泉らと多摩川能楽堂で稽古会も始めた。ここには尾上九朗右衛門・南博・藤波光夫・大谷広太郎・中村又五郎たちも加わって、昭和24年に発足した「伝統芸術の会」になっていく。
東京文理科大学に行って能勢朝次の「世阿弥の能楽論」を聴講したのも、この時期である。ぼくはまだ見ていないのだが、浅見真高・喜多節世・橋岡久馬・横道萬里雄らが創刊した「焚火」にも同人として参加している。ともかく研究熱心、稽古熱心、交流熱心なのである。
最も特筆すべきは昭和25年11月に始まった「能楽ルネッサンスの会」で、そこから世阿弥の伝書を読みこむ読書会がもたれた。西尾実をリーダーにおこなわれたこの読書会は5年にわたり、世阿弥の伝書のほぼすべてを読了したようだ。寿夫さんは全回に出席したようで、ほかに栄夫・静夫、野村万之丞・万作兄弟、浅見真高・近藤乾之助たちが、また小西甚一・表章・横道萬里雄らがいた。
こうして昭和26年に催された長老たちの審査による第1回「能楽賞の会」では、寿夫さんがダントツとして称賛をうけ、頭角をあらわしていた。それでも稽古熱心・研究熱心は変わらない。東大の川崎庸之の「日本思想史」を聴講し、田中一松・吉沢忠・宮川寅雄らの「文化史懇談会」では日本美術をしきりに学んでいた。
本書には随所に鋭い世阿弥研究のあとが見える文章が収められているのだが、それが能楽師の現場の勘や直観からくるだけのものでなく、世阿弥のテキストの精査からきていることはすぐわかる。古典文学者の小西甚一がその勉強ぶりをふりかえって感想を述べているが、のちにその小西と吉野の天河神社に古い能面を見に行ったおりには、観世十郎元雅が奉納した阿古父尉を手にして、おおいに感動したという。

寿夫さんは芸の異種格闘技にも果敢にとりくんだ。断絃会が主催したアルベール・ジロー作詞・シェーンベルク作曲の《月に憑かれたピエロ》(武智鉄二演出)に、アルルカン役として出演したのは30歳のときである。さきほど紹介した《智恵子抄》の光太郎には32歳のときに扮して、斬新な現代能を表現した。
草月アートセンターでストラヴィンスキーの《兵士の物語》を作舞・出演し、武満徹や福島和夫のミュージック・コンクレート《水の曲》や《蜘蛛》を作舞・出演をしたのは35歳のとき、フランスで半年間にわたってジャン・ルイ・バローのもとに学んだのは37歳のときである。
ぼくがそういう異種格闘技に挑んだ寿夫さんを最初に見たのは、昭和48年(1973)に「冥の会」がベケットの《ゴドーを待ちながら》を作ったときで、48歳の寿夫さんはウラジミールを演じた。実はさっぱり感動できなかったことを憶えている。演出の石沢秀二のせいか寿夫さんのせいかはわからない。
ついでその翌年、岩波ホールの《トロイアの女》の老人兼メネラオスを見た。鈴木忠志の演出で大当たりした芝居で、2回見た。こちらは世阿弥のいう「めづらしきもの」だった。ただ、いささかチューさんに押し込まれているような気もして、多少の疑問が残った。それよりも最後の年となった昭和53年(1978)1月の岩波ホール《バッコスの信女》のディオニソスのほうが、ぼくには寿夫さんだった。
むろん能にも打ち込みつづけた。寿夫・栄夫・静夫の3兄弟による「華の会」、野村万之丞・野村万作・桜間龍馬・山本真義・茂山七五三・茂山千之丞らとは東西の能狂言師が交じっての「黒の会」をはじめ、さまざまな試みにとりくみ、古典にも根っこを下ろそうとしていた。しかし、その志半ばにして倒れたのだ。
芸事とは、面白くもあるが、また危ういものである。だからこそ世阿弥は芸のための「方法の知」の一部始終を残そうとした。観世寿夫もきっとそうだったろう。本書を含む『観世寿夫著作集』は、他方で忌野清志郎やマイケル・ジャクソンやプロレスラーの三沢光晴を惜しみつつあるわれわれが、そのわれわれこそが格闘してでも読むべきものだと思われる。
先頃、亡くなった夫人の関弘子さんは、夫の著作集が仕上がったとき、概略、こんなことを書いていた。
私は観世寿夫に入門しました。異例の稽古法でした。能の専門家になるのでもない相手にも、大変なエネルギーを注ぎこんでいました。ギリシア悲劇をやるときは、周りが危ぶむなか、ギリシアをやって犯されるような能なら、そんな能は捨てると言っていました。しかし寿夫は、シテを舞った日には、必ず失敗だと言って帰ってきました。
寿夫は能のことしか頭にも体にもない人でした。日常的な事柄や個人的話題やスキャンダルめいた話は嫌いでした。物欲もなく、名誉欲もなく、他人を羨むなどということもありませんでした。そして、いつも、「努力ってものはよろこばしくやるものだと思う」と言っておりました。
まことにしみじみとした哀惜であり、なんとも凜然とした寿夫頌である。ギリシア悲劇をやって犯されるような能なら、そんな能は捨てるだなんて、骨に沁みてくる。今宵、七夕の夜である。叶うことならば諸君を、天なる寿夫に会わせたい。