一千一秒物語
新潮文庫 1969
これまでタルホについては何度も綴り、何度も発言してきた。ぼくの青春時代の終わりに最大の影響を与えたのだから当然だが、最近はタルホを読まない世代というか、稲垣足穂の名前すら知らない連中ばかりがまわりに多くて、いちいち説明するのが面倒になってきた。ふん、もう教えてやらないぞ。自分で辿れ!
けれども先だって鎌田東二君が主宰しているらしい東京自由大学という、名前は凄いが教室は神田のビルの小さな一室というところで、タルホについて話してくれというので、久々に気分に任せたタルホ語りをしてみた。「薄板界」に「AO円筒」というイメージを被せて最初に話してみたら、何人かのタルホ好きを除いて目をまるくしていた。そうなのだ、タルホに目をまるくすること、それこそぼくがタルホを伝えて皆にそうなってほしかったことだった。
だからこのときの語りは、いくぶん気持ちがよかった。よかったのだが、やはりタルホの文章を諸君が読んでいるかいないかということは、ちょっと決定的なのだ。
それは本当に曾て在ったことではないはずのに、なんだかまるで記憶が知覚に追いつくというように、そのことをとっくに知っていたと思えるようなことがある。知っての通り、ぼくはこれをしばしば「未知の記憶」とよんできた。
この感覚を最初に論じたのはベルグソンであるけれど、そのベルグソンの持続と瞬間のエスキースを語った直後、タルホはこんな説明だけではまだ何も説明したことにならないと言って、堤中納言の「みかの原わきて流るるいづみ川いつみきとてか恋しかるらむ」をあげ、さらに六月の都会の夕暮の光景とテニソンの詩を引き合いに出して、そこに自動車のエグゾーストの芳香に青き音楽が交じり、ムーヴィーフィルムの切れっ端がひょぃひょい躍るのはなぜかと問うて、こういう感覚はむしろ「宇宙的郷愁」とでも言わなければ気がすまないことなのではないかと書く。
これは『美のはかなさ』の冒頭に書いてあることで、このエッセイを五分の一ほど読むだけでも、諸君の人生はみごとに一変するはずなのである(『美のはかなさ』は本書に収録されている)。
しかしもうちょっと読みすすむと、その「未知の記憶」あるいは「宇宙的郷愁」ともいうべきものが、そもそも1900年ちょうどのクリスマスが近い12月にマックス・プランクが量子定数“h”を発表したときから突如として六月の都会の夜に広まったもので、それは「世界線の不連続性」にかかわる秘密とともに都会の隅々に「薄板界」として洩れ出していたことが見えてくる。
さらにすすむと、このクリスマス近くの1900年12月某日というのは、実は稲垣足穂が大阪船場に生まれた刻限近くのことであって、この世界不連続性にまつわる消息とは、ここに生まれたタルホ少年がその後に神戸六甲は摩耶山近くの小学校で飛行少年に憧れて、麦藁帽子のリボンの結び目に竹のプロペラをつけて疾走しはじめた夢見心地と浅からぬ因縁をもっていたことに、しだいに気がついていく。
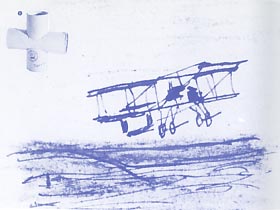
(遊『野尻抱影・稲垣足穂追悼号』より)
やがてタルホ少年はこの消息を求めてRちゃんやSちゃんとお尻遊びをしつつ、本当の宇宙よりも「黒板に描かれた白墨宇宙」のほうを、実在の芸術よりもそれがもたらす「髭のついた印象」のほうを、本物の青いお尻よりも「A感覚の幾何学」のほうを、まるで天体模型のように大切にするのであるが、なぜそのようにするべきなのかということが、その後のタルホのすべての文章の存在学になったのである。
こうして1923年のマニフェストとして『一千一秒物語』が残されることになる。それは銀紙とボール紙で作られた「世界線の不連続性」のための模型細工なのである。
ついでに言っておくけれど、この『美のはかなさ』こそはぼくが最初にオスカー・ベッカーと出会った記念すべき紙碑であり、ぼくが最初にフラジリティの存在学に向かう勇気を与えた香ばしい手榴弾だった。
本書新潮文庫版でいうなら、288ページから「第二部・芸術家の冒険性」が始まるのだが、その冒頭に“fragility”がバヴァリア製の脆うい色鉛筆の赤い芯の“こぼれ”とともに顔を出す。
ここは見逃してはいけない。とくにタルホがカントの「無関心の快楽」を俎上にしながら、シェリングやゾルゲルの「壊れやすさ」をへて、フロイト、ハイデガーを駆使しての「無意識の無限性」をフラジリティに託すあたり、この「よるべなきもの」の「よるべ」を求めるタルホの思索の独壇場を味わうべきである。
さて、『一千一秒物語』である。これはタルホが17歳くらいからちょこちょこ綴っていた「夜景画の黄色い窓からもれるギターを聞いていると、時計のネジがとける音がして、向こうからキネオラマの大きな月が昇り出した」に始まるハイパーコントとでもいうもので、さっきも書いたように1923年に未来派の玉手箱のように上梓された。
これを最初に読んだときは、たまげた。こんなにシャレたものが世の中にあること自体が奇蹟のように思われた。まずは次のハイパーコントの3つ、4つを読まれたい。
ある晩 黒猫をつかまえて鋏でしっぽを切るとパチン! 黄色い煙になってしまった頭の上でキャッ!
窓をあけると 尾のないホーキ星が逃げて行くのが見えた。
「お月様が出ているね」
「あいつはブリキ製です」
「なに、ブリキ製だって?」
「ええどうせ旦那、ニッケルメッキですよ」昨夜 メトロポリタンの前で電車から跳び下りたはずみに
自分を落としてしまったある晩 露台に白っぽいものが落ちていた 口へ入れると冷たくて カルシュームみたいな味がした 何だろうと考えていると だしぬけに街上へ突き落とされた とたん 口の中から星のようなものが飛び出して 尾をひいて屋根のむこうへ見えなくなってしまった 自分が敷石の上に起きたとき 黄色い窓が月下にカラカラとあざ笑っていた
ここは「薄い街」なのである。ここでおこるルールは口元であっというまに移ろっていく。だから自分以外の人間はまったく出てこない。すべては天体と関与して、かつどんなことも一瞬のうちに起承転結になる。誰が「どうして?」と問うても、虚空には笑い声だけが響いて、何も答えはない。
タルホがここでショーイングしてみせたのは、存在学に雲母の音がする自己撞着である。論理学や現代思想がしばしば自己言及系を問題にしてきたなかで、これはこれはなんとも唐突な論理の脱出であり、主体性の打擲だった。ぼくはとりわけ次のハイパーコントを読んで、胸のプロペラが唸り声をあげたのを聞いた。
ある夕方 お月様がポケットの中へ自分を入れて歩いていた 坂道で靴のひもがとけた 結ぼうとしてうつむくとポケットからお月様がころがり出て 俄雨に濡れたアスファルトの上を ころころころころ どこまでもころがっていった お月様は追っかけたが お月様は加速度でころんでゆくので お月様とお月様との間隔が次第に遠くなった こうしてお月様はズーと下方の青い靄の中へ自分を見失ってしまった
この「お月様がポケットの中へ自分を入れて歩いていた」は、これまでのあらゆる哲学と論理学の将来をポンプで圧縮して、フッと紙風船にして飛ばしてしまったような破格の魅力をもっている。
ぼくが「主体性」という用語を極端に嫌ってきたのは先刻ご承知のことだろうとおもうけれど、これほど胸のすく表現で主体性を笑いとばした一文はない。しかもこの主体性はたちまち二つに分かれ、しだいに互いの間隔が遠くなって、結局は自身を見失ってしまうのである。これは、バンザイ、だ。
しかし、バンザイはこれで終わるのではない。知っての通りタルホには「模型少年」「天体嗜好」「飛行家願望」とともに「少年愛の抽象化」という他の追随を許さない“お題”があるのだが、この少年愛議論に先駆的一石を投じた『A感覚とV感覚』(これも本書に収録されている)の、次のような細部に存在の消息を及ばせる一節こそが、タルホの主体性の彼方の存在学の面目躍如というところなのである。
短いコントを散りばめた『一千一秒物語』はこんなふうに続行連打されるのだ。最後の一行まで、ご賞味いただきたい。
例えば、かれらがいましも玄関の上り框に腰をおろし、うつ向いて、新しい編上靴の緒を結んでいるとすれば、かれらは何事を想うであろうか。なんだか靴をおろすのが惜しいと思う。この惜しいという気持はいつかそんな靴の内部に足先を入れて、しかもこんなにまでぴったりと合っているということを自覚している自分自身の問題にまで移行している。ではこの、底部まで艶出しされた新しい靴を穿いた自分はどうありたいと云うのか?
綺麗なリノリュームや坦々としたアスファルトの上にのみありたいのか。コトコトと舞台の床を鳴らして、何か芝居の一段をつとめたいのか。はたまた塵一つない自動車の操縦席に腰をうずめてクラッチの上に載っけてみたいのか? いっそ、この靴をはいたまま何か手荒に取扱われたいのである。
話はたんに靴なのだ。誰もがどこかで感じている靴との出会い。それなのに、その靴と足が出会う一刻だけをここまで念入りに記述する。この尖端の消息に関する記述があってこそ、タルホは靴と足の背後に控える「AとVとP」にまつわる前代未聞の解読を一千一秒間にわたって、展開できるのである。
その議論を一度も読んだことのない読者のために一部を披露すれば、V感覚(ヴァギナ)はA感覚(アヌス)から分離した片割れなのである。Vはその荒々しい扮装にもかかわらず、その一部のKをどこかで問題にしないかぎりは動揺しない代物である。けれども男性が偉ぶるP感覚(ペニス)となると、それ以下のもの、その出来ばえにしてVを裏返して突起されたものにすぎず、いつだって慌ただしい種蒔き器械を任せられているだけの、つまりは肉体の外部に暫定的に取付けられたコックの身分なのである。
これに対してA感覚は、口腔から肛門に突き抜ける無底のAO円筒をきずきあげている存在学そのものである。すなわちAは感覚の感覚であって、存在の存在である。しかもそのAには、つねに失笑がつきまとう。この失笑こそがAを普遍芸能にも、永遠の少年の痒みにもしてくれる。
タルホはこうしてA感覚をその存在学の全域のサドルにし、その自転車に少年と飛行機と彗星を一緒に乗せて、六月の都会の夜を疾走する。
すでに知られているように、タルホは自分が生涯かけて書くものは『一千一秒物語』の脚注にすぎないだろうと予告した。まさにタルホはその予告に違わず、つねにそのようにしつづけた。
脚注か。ぼくもそんなことを言ってみたいと思ったものだ。しかし何の脚注にすればいいのだろうか。タルホは自分のお尻に脚注をくっつけた。では、ぼくは? そのことを考えると、居ても立ってもいられずに、ぼくは京都桃山のタルホを訪れた。
この話はまだ書いたことがなかっようにおもうのだが、ぼくが最初に稲垣足穂を訪れたときのことである。そこでタルホが言ってくれたのは、「ちゃんと準備をしたら、あとは好きなようにしやはったらええんや」ということだった。ちゃんと準備をしたら? そうなのだ、われわれは最初に一番小さな模型をつくることなのだ。その模型をつくらずして、われわれは外出してしまいがちになる。
われわれはどこかに月の人がいると思いすぎている者なのだ。タルホはすでに『一千一秒物語』に書いていた――。
月の人とは ちょうど散歩からかえってきてうしろにドアをしめた自分であったと気がついた

筑摩書房 2001



