父の先見


ぱる出版 2007
Silvio Gesell
Die natürliche Wirtschaftstordnung durch Freiland und Freigeld 1920
[訳]相田慎一
装幀:工藤強勝・渡辺和音
花 このところ「千夜千冊」は貨幣やマネーですね。
松 うん、暑いのにね。ぼくが一番苦手な分野です。沖縄興南高校みたいにはいかない。
花 そうなんですか。
松 うん、苦手。ただ、いつかは取り組もうと思っていた。少なくともフェルナン・ブローデルの『物質文明・経済・資本主義』(1363夜)を片付けたら書こうと決めていた。
花 どんな展開をするのかなと、このところの「連環篇」を読んでいたんですが、まずはジンメル(1369夜)からケインズ(1372夜)ヘ、でした。ここまでは貨幣論の定番で、解読速球勝負。そこから一転してゲーテ(970夜)の『ファウスト』の魔術が説きあかされて、なるほどなるほど、そういうことだったかと納得していたら、そこへビンスヴァンガーと仲正昌樹が挟まって、いったん島田雅彦の偽金つくりの『悪貨』とエンデの『モモ』(1377夜)が並んだでしょう。斬新なリリーフ陣の登板でした。「やったー」って感じで、ちょっとどきどきしてた。
松 それは嬉しいな。
花 そしたら話はモモではなくて、『エンデの遺言』のほうに核心があったんですね。クローザーとしての「エインジング・マネー」がテーマでした。そこにしかもシュタイナー(33夜)がいた。シュタイナーを挟んでゲーテとゲゼルとケインズとエンデが色っぽい折り紙になっているんですよね。これはいよいよ佳境じゃないですか。苦手だなんて思えない。コーチョー、絶好調ですよ。
松 そうか、ぼくが激励されてるのか(笑)。
花 はい、激励してる(笑)。最近、私はそういう役だと気がついたんです。
松 それはもっと嬉しいな。
花 はい、嬉しがってください。それはそれとして、シュタイナーがエンデの気分や価値観やを作ってたんですね。
松 そうだね。エンデがシュタイナー学校に学んだのが大きいね。そうじゃなかったらゲゼルも知らなかったろうね。ゲゼル、シュタイナー、エンデはつながっている。
花 で、今夜は何を千夜千冊するんですか。
松 そのゲゼルの大著。
花 翻訳があるんですか。
松 うん、唯一、『自由地と自由貨幣による自然的経済秩序』という大著がね。試訳はべつにもあるけれど、本格的に翻訳刊行されたのはこれ一冊。おととしのことです。
花 シュタイナーが感じられますか。
松 いや、シュタイナーにはゲゼル的なものが継承されているところがあるけれど、ゲゼルにはシュタイナー的なところはないでしょうね。
シルビオ・ゲゼルの波乱に満ちた生涯については、あらかた前夜に書いた。20世紀初頭の経済理論家があれだけの“経済乱世”をくぐり抜けてきたというのは、めずらしい。
いくつか理由が考えられる。ドイツ帝国の勃興期と多難期のドイツの辺境に生まれ育ったこと、若いころにシュティルナー、マルクス(789夜)、ショーペンハウアー(1164夜)、ニーチェ(1023夜)を読んだこと、南米アルゼンチンで投機とその崩壊のプロセスに立ち会ったこと、すぐれたビジネスセンスとロジカルな理論構築能力に恵まれていたこと、第一次世界大戦前のドイツマルクの狂乱を身近で体験したこと、ロシア革命が勃興して社会主義の成長理論が登場していたこと‥‥。
そうしたことがゲゼルのなかで比類のないかっこうで融合したから、かなり独創的な経済理論や自由貨幣の構想が思い浮かんだのだったろう。そこから協同組合的な理想や農業重視的な理念とともに、ありうべき資本主義の未来像についての構想が浮かんでいった。
そのゲゼルのことを、どこかでシュタイナーは知った。シュタイナーのアントロポゾフィ(人智学)はつねに精神生活と社会生活の深い関係を問うものであるが、そこにはゲーテ譲りの政治経済感覚も去来していた。そこへゲゼルが加わって、生産と生活の直結ないしは循環が理想になっていく。シュタイナーが「貨幣は他人の生産した財貨の“小切手”にすぎない」というふうにみなしていたこと、また、その“小切手”が経済領域においてどのような財貨とも交換しうるのは、社会生活者たちが労働をして生産物を社会に供給する責任をはたしているかぎりにおいてのことだ考えていたのは、多分にゲゼルっぽい。
シュタイナーが「老化する貨幣」を考えて、貨幣に25年ほどの期限つけたいと思っていたのも、きわめてゲゼル的である。シュタイナー的なオーガニック・エコノミーにはそういう貨幣の未来像が必要だったのだ。それが「エインジング・マネー」だった。
花 シュタイナーって日本では神秘学と教育論しか知られてませんね。私はダンスをしていたからオイリュトミーも好きだったけれど、でも、経済社会論のことは知らなかった。
松 日本でのシュタイナーは霊的な思想や教育の革新ばかりだと思われすぎているからね。でもね、アントロポゾフィっていうのは「知」の総合的な編集思想みたいなものだから、当然、そこには社会思想や経済思想も入ってくる。そういえばごく最近、高橋巌さんが『社会問題の核心』と『社会の未来』(春秋社)を新たに訳された。以前はイザラ書房だったよね。
花 シュタイナーといえば高橋先生ですもんね。高橋先生がいらっしゃらなかったら日本のシュタイナー・モードは育まれなかったでしょうね。もう一人は子安美知子さん。
松 実はおととい高橋先生から突然の手紙をいただいてね、松岡さんの『日本流』(ちくま学芸文庫)をテキストに勉強会をしていると知らせていただいた。恐縮しました。
花 あら、それはステキなこと。ひょっとしたらシュタイナー・ファンと松岡正剛ファンはけっこう重なっているのかもしれませんよ。
松 そうかなあ。
花 だって意外な人がシュタイナー・ファンでしょ。マリリン・モンローとかヨーゼフ・ボイスとか。ダンサーの笠井叡さんも。
松 うん、そうだね。プロレスラーの前田日明も『美味しんぼ』の雁屋哲もね。雁屋さんは子供をシドニーのシュタイナー学校に通わせた。
花 はい。それで、シュタイナーの社会経済思想はどこまで書けているんですか。
松 おそらく途中までだろうね。「社会有機体三層論」(三分節論)のプロトタイプはできていたけれど、それを書いたのは第一次世界大戦の途中の56歳くらいのことだったからね。例の「法生活・経済生活・文化生活」を生の三領域に分けたものですね。
花 ミシェル・フーコー(545夜)の「生・政治」とかアントニオ・ネグリ(1029夜)の「ビオポリティーク」の先触れみたいですね。
松 そうだね。そのあと大戦が終結して、シュトットガルトのタバコ工場の研修コースのために自由ヴァルドルフ学校(シュタイナー学校)を開いた。それが58歳だったかな。いずれにしてもこれらは晩年の仕事です。そこから64歳で亡くなるまでに、ドルナッハのゲーテアヌムもシュタイナー医学の提唱も、アントロポゾフィをめぐる著作も、オイリュトミーの開発もバイオダイナミック農業の実験も、みんな一人でやっていたからね。いろいろやることがあったんだね。そのぶん経済学までは手がまわらなかったんでしょう。講演ではときどき話していたようだけど。もしもシュタイナーがあと10年生きていたら、きっとシュタイナー流の自由貨幣を発行していだろうね。
花 シュタイナーはゲゼルとの交流関係はあったんですか。
松 二人は1、2歳のちがいだけど、出会えてはいませんね。ゲゼルはアルゼンチンやスイスに動いていたしね。社会的な未来像のようなものは似たところがあるけれど、感性や思索は違ってるよね。ゲゼルはゲーテというより、プルードン、シュティルナー、ニーチェ(1023夜)のほうだったから、シュタイナーはそのあたりについては異和感を感じていたでしょう。シュタイナーはなんといってもゲーテですからね。
花 ゲゼルってアナキストなんですか。アナルコサンジカリストですか。
松 そう見られても仕方がないところがあるんだけれど、それはアナキズムをどう見るかということや、ゲゼルに影響を与えたプルードンをどう見るかということにかかわってきますね。
ゲゼルは生前もその後も、一貫して異端扱いされてきた。シュタイナーやエンデやビンスヴァンガーが重視したのはめずらしい。
それでもケインズ(1372夜)が貨幣論のなかでわざわざ「将来はマルクスよりもゲゼルが重要になっていく」と予言的に評価した。それにもかかわらず、その通りには評価されてこなかった。やはり特異すぎたのであろう。またケインズの「バンコール」などの提案がアメリカ主導のIMF=世界銀行構想に押し切られたせいだろう。そのあとは、あまりにシカゴ学派と新自由主義がはびこってケインズ主義が退嬰してしまったせいもある。
それでも、それがリーマンショック以降はいささか反転して、少しはケインズ復活の機運も出てきただろうから(1373夜)、これからは多少はゲゼルにも光が当たるかもしれないが、そうなるにはゲゼルがもっと読まれなくてはならず、それがなかなか叶わないままにある。いま日本で読めるのは残念ながら本書一冊きりで、しかも大冊。一般読者には難解でもある。
そもそもゲゼルの思想の立場も実は説明しづらいところがある。たとえば、本書の訳者の相田慎一が「あとがき解説」で最初に断っているように、ゲゼルは「反マルクス主義的社会主義」というレッテルを当初から貼られてしまっていた。ケインズが「マルクスよりもゲゼル」と言ったのも、その見方を踏襲していた。
そうした見方はゲゼルの今日的な意味を取り出すに当たってはかなり狭すぎる。それでもマルクスとゲゼルを比較するのは、ゲゼルを理解するためのとりあえずの入門的な見方としてはわかりやすい窓になるはずだった。とくに資本主義についての考え方はきわめて対比的なのである。
たとえば、マルクスは資本主義の本質が「産業資本主義」にあるとして、そこに資本と生産関係の矛盾が噴き出て、資本家と労働者のあいだに搾取が生じるとみなしたが、ゲゼルは資本主義の本質は「利子経済」にあると見た。そして、矛盾がおこるのは生産過程ではなく、むしろ流通過程であって、搾取がおこるとしたら貨幣所有者と商品生産者のあいだだろうとみなした。
マルクスは市場経済そのものを根底から覆し、プロレタリアートの手による経済社会にするという構想を出し、それがレーニン以降のプロレタリア独裁国家によるソ連の計画経済になったわけだけれど、ゲゼルはまったくそういうことは考えなかったのである。市場経済は個人の自由が守られるかぎりは有効なもので、資本主義も利子経済から脱却できれば何とか軌道修正できるだろうと見ていた。ただし、それには貨幣による経済秩序の統御が障害になっているので、そこにこそ「エイジング・マネー」としての自由貨幣が登場すべきだと提案しつづけたわけだった。
一応はこういうふうに、ゲゼルの経済思想のおおまかな特色がマルクスとの比較によって見えてはくるのだが、ただしそういうふうに見ると、そのぶん、ゲゼルの思想が反マルクス的な自由論をめざしているとも見えるだけに、それが個人的自由主義に与するものともみなされる。そういうふうに見るのがふつうの近代思想史の見方なのである。
しかしながら、実際にはゲゼルの思想は、今日にいういわゆる個人的自由主義とはほとんど交差していない。
というのも、ゲゼルの個人的自由主義はアダム・スミスやスチュアート・ミルの自由経済論から出てきたのではなく、まして今日のリバタリアニズムと直結しているわけでもなく、実はピエール・プルードンやマックス・シュティルナーから出ていたからである。そうだとすると、ゲゼルの思想はマルクス以前のアナキズムこそが思想的背景だというふうになってきて、ふつうの経済学者はむろん、多くの思想家たちも、いささかお手上げになる。そのへんをどう見るかが、ゲゼルの自由地論や自由貨幣論を考えるときの、ちょっとした難関になるわけなのである。
松 だいたいプルードンやシュティルナーなんて、いまはほとんど読まれていないよね。長いあいだ忘れられてしまってきた思想家だもんね。
花 はい、私も読んでない。かなりラディカルな思想なんですか。
松 そうだねえ、二人はひとつには語れないけれど、ラディカルというなら、今日の思想界では考えられないほど根底的だったよね。そもそもプルードンは「所有」という問題を初めて社会哲学したわけで、そこから私的所有財産(私有財産)を問うアナキズムも科学的社会主義もマルクス主義もその後に生まれていったわけだから、近代の反体制思想としてこんなにラディカルなものはないと言えますね。
花 マルクスがプルードンの『貧困の哲学』を『哲学の貧困』にひっくりかえしたんですよね。あれってマルクスがずるいでしょう?
松 まあ、ずるいというか、うまいというか(笑)。マルクスはヘーゲルやフォイエルバッハもレバレッジに使ったわけだから、その点でいえばマルクスは相手のロジックを転倒させるロジックの天才だよね。だから『哲学の貧困』も『ヘーゲル批判』も『ゴーダ綱領批判』も書けた。批判の天才。まあ、そこがマルクスのマルクスたるゆえんなんだけれど。
花 マルクスに優しいんですね。
松 まあ、ぼくには若い頃のちょっとした仁義があるからね(笑)。でも、そのマルクスにくらべたらプルードンはもっと実直でね、職業的には学者ではなくて職工さんです。それも徹頭徹尾の印刷工ですね。それで「多能工」こそが労働者の人間的な成長を促すと確信して、自分でも27歳くらいで印刷所をつくって職工さんたちを雇ってあげるんですが、これは2、3年で経営が破綻した。それでだいぶん借金をした。
花 ずいぶん若いうちからラディカルだったんですね。
松 ラディカルで、かつジェネラルだね。というのも印刷所時代には言語学研究にも関心をもって『一般文法論』を自費出版したりもしている。で、30歳をすぎるとすぐに『所有とは何か』(1840)を書いた。これが有名な「所有とは盗みである」に始まる画期的な本です。
花 はい、「所有は盗奪である」。その通りです。でも、なぜ一気にそこまで言明できたんですか。
松 プルードンってもとはといえばフーリエ(838夜)のアソシエーショニズムを継承して「自由」の問題をとことん突き詰めた人でね。実際にもフーリエにも2、3回会っている。だから“私有の経済”も批判したけれど“共産の経済”も批判したんです。だからこそ無政府主義としてのアナキズムの母型のような思想になったんですね。
プルードンを有名にしたのは1830年の七月革命と1848年の二月革命である。七月革命で仕事を失い、二月革命ではチュイルリー宮の無血占領に参加した。
フランスのブザンソンに生まれ育って、そのブザンソンのゴーチエ印刷所の植字工や校正工になった。1829年、ゴーチエ印刷所にたまたまシャルル・フーリエの『産業的協同社会的新世界』の原稿がもちこまれた。プルードンは校正担当者としてフーリエと接触して、その思想のとりこになった。
そのうちそこへ七月革命の余波が届いた。ナポレオン以降のフランス社会の最悪の混乱と経済的打撃がやってきたわけである。プルードンは“渡り職人”の資格をとってなんとか食いつなごうとするのだが、とうてい仕事はなかった。パリにも出てみたが、何の仕事も得られない。こうしてプルードンは国家というもの、社会というもの、経済というものの成り立ちそのものに疑問をもちはじめる。フランス革命、ジャコバン党の支配、ナポレオン帝国、そしてルイ・ボナパルトの共和政というふうに連打されてきた祖国フランスの右往左往に根底的な疑問をもったせいである。
それは言ってみれば「真の革命とは何か」ということであった。こうして書かれたのが『所有とは何か』(1840)だったのである。所有の起源を辿っていくと、そこには他人のものを収奪するか、徴収することでしか成立していない財産というものがある。そういう所有の制度をこのまま放置しておいてもいいものか。その問題に切り結んでいったプルードンは、かくて「所有」と「私的財産」の根源を歴史上初めて俎上に乗せた思想者となった。
しかしプルードンはそこにとどまらない。1843年には『人類における秩序の創造について』を、1846年には『経済的諸矛盾の体系』を発表し、リヨンの織工たちが蜂起したときはその支援にもまわった。また当時は“ヘーゲル左派”と呼ばれていたルーゲ、グリュン、ハイネ(268夜)、まだ25歳だったマルクス、さらにはバクーニン、ゲルツツェンらと積極的に接触して、その考え方を広めていった。
『経済的諸矛盾の体系』は通称『貧困の哲学』と呼ばれた。いっさいの経済行為を「分業・機械・競争・独占・租税・貿易・信用・所有・共有」に十分類し、それらがことごとく矛盾とアンチノミーの上に成り立っていることを証そうとした社会的快著だった。プルードンは社会の前進の駆動力は、この矛盾とアンチノミーから発進していると見たわけである。
しかし翌年、マルクスはこれを『哲学の貧困』として批判した。プルードンの思想を抉ったというよりも、プルードンが立ったアナーキーな人脈と立場に批判を加えたのだった。これ以降、マルクスはプルードンやバクーニンらを無政府主義者として難詰する。
こうして時代は1848年のフランスは二月革命に雪崩こむ。これが世界史的にどんな意味をもっていたかは説明するとキリがないが、第1には、当時のフランスには50万人を突破する勢いで失業者があふれていた。そのため国立の失業対策のための工場が必要になっていた。第2には、偏向した選挙権をめぐる運動が激化していた。人口170人に有権者が1人という制限に知識人や労働者が不満をぶつけ、各地でいわゆる「バンケ」(改革宴会)が開催されていった。第3に、バンケの中止を求める政府と民衆が激突し、市街戦が激化した。第4に、その運動の渦中に国王ルイ・フィリップが退位亡命して、蜂起した側の労働者の代表やルイ・ブランなどの社会主義者が登場して臨時政府が成立した(これを狭義の二月革命という)。
第5に、臨時政府は21歳以上の男子による普通選挙を敢行するのだが、穏健派が議会の多数を占める結果となり、国立作業場が閉鎖されることになって、ふたたび30万人の労働者が決起(六月蜂起)、多くの犠牲者を出して鎮圧されることになった。第6に、これらの結果、ルイ・ボナパルトが大統領に就任した。第7に、こうして19世紀初頭から続いたナポレオン体制のあとに各国が築こうとしたウィーン体制が音をたてて崩れていき、その余波がベルリンとウィーンの三月革命などに波及していったのである。
プルードンはこうした事態をすべからく「理念なき革命」と断罪し、「人民の代表」と題する新聞を発行したり、選挙に立候補したり、六月蜂起で弾圧された労働者を擁護したりしつつ、議会には所得税に対する改変を迫る提議を案出したりもしていたのだが、ついに業を煮やしてまったく新たな「銀行」の提案に向かっていった。
花 革命家プルードンを、どうして自由貨幣論のゲゼルが評価するんですか。プルードンも自由貨幣のようなものを考えていたんですか。
松 自由貨幣論まではいっていないけれど、新しい銀行を考えていたし、実験しようとしていた。プルードンは二月革命のような政治革命ではダメで、真の経済革命が必要だと見ていたんです。
花 どんな実験ですか。
松 「交換銀行」とか「人民銀行」と称した新しい銀行をつくろうとしたんですね。これは相互主義や連合主義を前提にした銀行で、貨幣が商品に対してもっている優位をなくしてしまおうというものです。
花 というと?
松 Aが貨幣をもっていて、Bが商品をもっている場合、つねに貨幣をもっているAのほうがBよりも有利ですね。これは貨幣が商品に対する交換可能性をもっているからです。今日の用語でいえば、貨幣には流動性がある。商品は売れればいいけれど、売れないこともあるわけだから流動性は極端に落ちる。プルードンは、これは貨幣と商品には同等性がないということだとみなし、貨幣には“王権”があると見たわけです。そこで、このような王権的な貨幣に支配された市場や生活をよくするには、新たな銀行が必要だと考えた。
花 ということは、王権すなわち国家から自立している銀行を発想したわけですね。
松 そう、その通り。資本金もなく営利も目的にしない銀行で、加入者に「交換券」を発行して、それによって生産もしくは保有した商品を流通させようというんですね。だから「交換銀行」なんだね。「交換券」は20フラン、100フラン、500フラン、1000フランなどになっていて、端数だけは通常の通貨で支払われるほかはいっさいの通貨を使用しないという計画です。
花 なるほど、そうすれば、市場で買い手のつかない余剰生産物を交換銀行を介して動かすことができるというわけですか。
松 そうだね。そういう狙いもあった。だからこれは自由貨幣というのではなく、あくまで生産と労働と市場の関係に根底的な流れをつくりなおそうというものです。
花 で、実験は成功したんですか。
松 2700人の加入者が集まって、交換券をもう少し発達させた「流通券」という紙券でいよいよ本格的な活動を開始しようというとき、ボナパルトを誹謗した文章の科で逮捕され、監獄に入ってしまうことになり、計画は挫折してしまいますね。
花 そこで、ゲゼルがその構想をさらに転換させて自由貨幣計画に組み立てていったということですか。
松 おおざっぱにはそういうことだね。ただし、ゲゼルはプルードンの人民銀行(交換銀行)では限界があると見て、もっと根源的な問題にまでさかのぼる貨幣の必要を感じたんですね。そこには「自由地と自由貨幣」という組み合わせもあったんです。
前夜で、ゲゼルがスイスに農場を購入して「土地」のことを考えるようになり、雑誌「貨幣と土地改革」を創刊したということを述べておいた。また、その後にスイスの国営銀行法に介入して『スイス銀行の独占』を書き、1906年には『労働全収権の実現』や『積極通貨政策』を刊行したことも述べた。
ゲゼルは土地にひそむ自由地に目をつけ、しかるのちに自由通貨を構想したのだった。『自由地と自由貨幣による自然的経済秩序』をまとめていくには、この思索のプロセスが前提になっていた。加えて、ゲゼルはこれを書くときにプルードンを批判したマルクスを批判して、マルクスの選択肢がプロレタリア独裁による国家経済に向かったことを非難した。
ゲゼルが考えた「自由地」とは、土地監理局に報告されて労働が許された土地、外国人が侵攻あるいは認定されて居住している土地に対して、誰もが努力しさえすれば開墾できる土地のことをいう。ゲゼルはそれを「第三級の自由地」と呼んだ。
この自由地を、生産と労働の本来的な活動のなかで経済的に有効にするにはどうするか。地主の申し渡した地代を払い、労働賃金を払っているだけでは、そこには経済の自立的自由は生まれない。そこでゲゼルは、ありうべき「自由地」にふさわしい「自由貨幣」がありうるのではないかと考えたのである。
ということで、本書の主だったところだけを抜き書きするが、ざっと次のような部立てと章立てと節立てになった。よくよくこの目次を見れば、ゲゼルが何を構想したか、あらかたが見えてくるにちがいない。
第1部=「財の支配」
第2章 労働全収益とは何か
第3章 地代による労働収益の削減
第5章 生活諸関係が賃金と地代に与える影響
第7章 第三級の自由地という概念
第12章 関税・賃金・地代
第14章 資本利子が賃金と地代に与える影響
第2部=「自由地」
序章 自由地、平和の絶対的要求
第2章 自由地の財政
第4章 土地国有化の諸作用
第6章 自由地では実現できないこと
第3部=「現行の貨幣」(金属貨幣と紙幣)
序章 貨幣という存在はいかにわれわれの前に現れるのか
第2章 貨幣の不可欠性と貨幣素材への公衆の無関心
第3章 いわゆる価値
第4章 なぜ貨幣は紙から作ることができるのか
第6章 貨幣が達成すべき価格とはどのようなものか
第8章 紙幣の価格はどのようにして決まるのか
第10章 貨幣供給(商品需要)
第11章 今日の貨幣流通における法則性
第12章 経済恐慌、それはいかに予防できるのか
第13章 紙幣発行の新条例(発券改革)
第15章 金と平和?
第4部=「自由貨幣」(理想的な貨幣と可能な貨幣)
第1章 自由貨幣
第2章 国家は自由貨幣をいかに流通させるのか
第3章 自由貨幣はいかに管理されるのか
第4章 自由貨幣の流通法則
第6章 自由貨幣はいかに評価されるのか
第7章 世界通貨同盟(国際ヴァルタ同盟)
第5部=「自由貨幣の利子理論あるいは資本理論」
第1章 この理論の試金石としてのロビンソン・クルーソー物語
第2章 基礎利子
第3章 基礎利子の商品への転嫁
第4章 基礎利子のいわゆる実物資本(物財)への転嫁
第6章 これまで資本利子はいかに説明されてきたか
第8章 純粋の資本利子、その不動の大きさ
花 うーん、すごいですね。
松 うん、とても解説する気がしなくなる(笑)。いつか本書を手にとってください。
花 えっ、解説なしですか。
松 はいはい、今夜はとてもそんな気分じゃないね。それにしてもほとんどケインズの直前っていうところだよね。
花 ちなみに、第4部第7章の「世界通貨同盟」というのはどういうものですか。
松 この同盟に参加する国々に「エヴァ」という通貨単位を導入して、国際銀行券ヴァルタを発行し、各国の通貨政策をエヴァの単位のもとでバランスをとろうというものですね。
花 ケインズの「バンコール」みたいなものですか。
松 そっちのほうが厳密だったけれど、大筋はそうですね。でもゲゼルの案もケインズの案も葬り去られてしまった。
花 なんだかいろいろ溜息をつきたくなりますね。うーん、やっぱりいったい「お金」って何なのだろうと思わざるをえません。
松 そうだよね。厄介なもんだねえ。でも、以前から言っているように貨幣は言語と同様に、なくなりっこない。それがいかに地域通貨や並行通貨に代わっても、貨幣そのものの機能はなくならないでしょう。だとすると問題はやはり銀行利子やデリバティブな先物証券のほうだよね。マッド・マネーを食い止めるためにもね。そこで、ゲゼルやシュタイナーやエンデたちは貨幣のほうにこそ「時計」を付けようとしたわけだ。ぼくはこの抵抗はよくわかる。
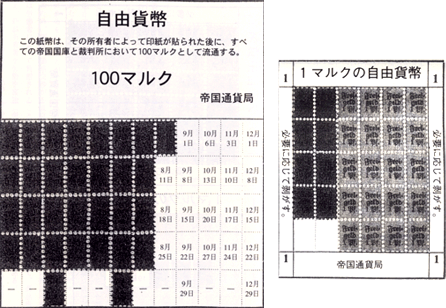
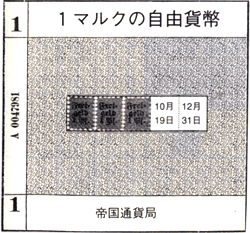
花 自由貨幣あるいはプルードンに戻っての銀行改革が必要だろうということですか。
松 そうだねぇ。銀行を変えるというより、社会における資本の考え方をそもそも変えてみるということかもしれないね。ソーシャルキャピタルの本来は何なのかということ、もう少しべつの考え方をすれば、本来の「価値の交換」とは何かということをもっと考えるということだろうね。プルードンもそこを考えたわけです。
花 そういった考え方は、いまはほとんど再生していないんですか。イスラムの無利子経済やグラミン銀行のマイクロファイナンスの例だって、ありますよね。
松 そうだね。そのへんはいずれ千夜千冊するつもり。それからデヴィッド・フリードマンのアナルコ・キャピタリズム(無政府資本主義)もあるね。これもいずれ千夜千冊します。
花 日本ではどうですか。ダメですか。
松 いや、そんなことはない。ゲゼルについては森野栄一の不断の研究が続いているし、そのほかにもいろいろ新たな思索や実験が試みられていると思いますよ。プルードンについては、柄谷行人が『世界共和国』(岩波新書)のなかでけっこう興味深いことを言っている。鈴木謙介の『反転するグローバリゼーション』(NTT出版)なども、よく書けていた。プルードンについても触れています。そのほか各種のリバタリアニズムやアナルコ・キャピタリズムも芽生えています。一種の最小国家論だね。そのへんもそのうち千夜千冊するよ。
花 お手伝いしたいです。
松 うん、そのつもり。