父の先見


岩波書店 1979
Michael Ende
MOMO 1973
[訳]大島かおり
読書には「ドッキ」というものがある。ドッキは「読機」だ。その本をいつ読んだのかということ、いつ通過したのかということ、そこにその本とわれわれのあいだにひそむドッキがある。
ドッキは容易には掴めない。だからドッキなのである。念のために言っておくが、果物に旬があるようにその本に旬があるのではない。そんなものはない。どんな本もその気になればいつだって旬になる。これはシュンドクというもので、「旬読」という。旬読は版元がそれをこよなく願っていて、その本が時代の中に提示されたときに買って読むことが大いに期待されているのだが、けれども本そのものには、実は旬はない。アリストテレス(291夜)も太宰治(507夜)もつねに旬なのだ。だから本というものはいつだって旬読を待っている。
ところが旬読はなかなかおこらない。それを読み食べるこちら側の時機に問題があるからだ。その本をいつどんな心境やどんな状況で読んだかが、その本についての印象や感想にひどく関係してしまうのに、それがずれるため旬読がおこらない。これはドッキのせいなのである。
ドッキはそもそもが潜在的なものなので、これを制御したり有利にすることはできない。太宰の『女生徒』や『葉桜と魔笛』をぼくが読んだのは高校時代だったけれど、このときはドッキがよかった。だからやたらに感動した。だからといって、こういうことを自慢してもしょうがない。セレンディップな恩恵として有り難く感じるしかない。ドッキとはそういうものなのだ。
日本で『モモ』が岩波から刊行されたのは1976年で、ぼくは「遊」の第2期をぶんぶん編集していた頃だった。寝るなんてことが惜しくて、ともかくいろんなディープで過激なことに挑んでいた。
そんななか、それでも話題になっていた本にはなんとか目を通すという作業だけは欠かしていなかったので、噂の『モモ』も一読した。時間泥棒というアイディアにはなるほど感心したが、全体に寓意が勝ちすぎていておもしろくなかった。ビビガールという“完全無欠な人形”がちらちらと印象に残ったにすぎない。
このころはSFを片っ端から読んでいた。劇画を読んだのもこの時期だったが、これは勢いで読んだにすぎなかった。なかでJ・G・バラード(80夜)やレイ・ブラッドベリ(110夜)にはついに会いたくなってロンドンやロスアンジェルスにまで行った。きっとチャンスがあればアーサー・クラーク(428夜)やフィリップ・K・ディック(883夜)やトマス・ピンチョン(456夜)とも会っていただろう。
そういう時機に『モモ』を読んだのだから、いけない。きっと劇画のように読んでしまったのだろう。実はトールキンの『指輪物語』やC・G・ルイスの『ナルニア国ものがたり』もこのあとしばらくして読んだのだが、残念ながらつまらなかった。いずれもドッキが悪かったのだ。『指輪物語』は別役実に薦められたので読んだのだけれど、やはりその一定した寓話力や寓意力に、どうしても感心できなかった。
というわけでぼくはエンデを旬読すらできなかったのである。それからずいぶん時間がたった。『モモ』を再読したのはごく最近のことで、10カ月ほど前なのである。
きっかけは河邑厚徳らがまとめた『エンデの遺言』(NHK出版)を読んだせいだった。その『エンデの遺言』を読んだのは反グローバリゼーションの見解を片っ端から読んで、その傍らでハイエク(1337夜)の貨幣論、たとえば『貨幣発行自由化論』(東洋経済新報社)を知り、さらにケインズの『雇用・利子および貨幣の一般理論』(岩波文庫)にとりあげられているシルビオ・ゲゼルの「スタンプ付き貨幣」のアイディアに、エンデがひとかたならない関心をもっていたことを知ったからだった。
そこからはジグザグとした読書が数カ月ほど続いて、一方では経済学の本を啄(ついば)みながら、エンデの『遺産相続ゲーム』や『鏡のなかの鏡』を遊ぶというようなことの“折り紙読み”が、あれこれ前後したと思われたい。こういうことはぼくにはよくあることで、新たな集中ドッキをつくりながら世界読書の渦中に自分でどんどこ入っていくという読み方になる。
ともかくはこうして、ひとつにはゲゼルの自由貨幣論が、もうひとつにはエンデの「お金」に対する思想の片鱗が手元に残ったのだ。ゲゼルのほうのことについては、このあとの千夜千冊にまわすとして、今夜は初読のドッキをまちがえたぼくが、あらためてエンデに“再会”できた感想を、以下、ごくかんたんに披露しておきたい。
まず、『モモ』である。
物語はよく知られているだろうから紹介しないが、モモという少女が大きな街の古びた廃墟のような円形劇場に住み着く。モモには人の話にじっと耳を傾けるだけで、人々に自信を取り戻させるような不思議な力がそなわっているらしい。
そのモモのところに「灰色の男」たちがあらわれる。「時間貯蓄銀行」からやってきた灰色の男たちは、人々から時間を奪っていくのが専門の職業になっている。時間を節約して、時間貯蓄銀行にその時間をせっせと預ければ、利子が利子を生んで人生の何十倍もの時間をもつことができるというふれこみだ。モモはこれは時間泥棒だと思う。
けれどもその街の人々は時間泥棒たちの言葉巧みな説得に誘導されて、しだいに余裕のない生活に追い立てられていく。気がつくと時間とともに人生の意味も失っている。モモは盗まれた時間を人々に取り戻すため、カメやカシオペイアとともに灰色の男たちとの戦いに挑んでいく‥‥。ざっといえば、そういうお話である。
モモは孤児に設定されている。身寄りのない「みなしご」だ。「棄人」や「みなしご」や「孤児」は内村鑑三(250夜)や野口雨情(700夜)が最も重視した社会存在のモデルだった。「歌を忘れたカナリア」を連れてモモのところにやってきた少年も出てくる。
そんなモモにも親友が二人いる。道路掃除夫のベッボ爺さんは自分で建てた煉瓦とブリキの小屋にいる。どんな話にもにこにこ笑えるが、自分ではほとんど喋らない。観光ガイドの若者ジジは何でもよく喋る。けれどもほとんどが空想で、この街の神話を勝手に作っている。つまりはこのモモを含めた3人は、何も所有していない無所有者たちなのである。当然、無産者でもあった。
そこへ時間貯蓄銀行の灰色の男たちがやってきて、「みなさん、時間はどこから手に入れますか」と聞き、「それは倹約するしかないでしょう」と説得しまわっていく。たくさんの計算と数字も見せる。すべてを損得勘定で説明できる連中である。時間銀行の銀行員は「時間をあずけてくれたら5年で同額を利子として払う」と言い、時間の節約の仕方を説明する。
仕事はさっさとすます。老いた母親は養老院に入れて、自分の時間を大事にする。役立たずのセキセイインコの世話の時間ももったいないから、捨てる。とくに歌を唄ったり、友達と遊ぶのを避ける。このようにして時間を節約したぶん、幸福が確実にたまっていく。そう、言うのだ。住人たちは次々に時間が倍になって戻ってくることに狂喜する。
いったいこのお話は何を書いたのか。
失った時間を取り戻したという話ではない。「時間」を「幸福」と見立てたのでもなかった。エンデはあきらかに時間を「貨幣」と同義とみなしたのである。「時は金なり」の裏側にある意図をファンタジー物語にしてみせたのだ。ドッキを失うと、こういうことすら読めてこなかったのである。
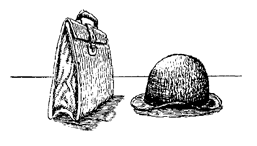
さて、あらためてエンデの作品群をつらつら読んでわかったのは、エンデは同じことを『鏡のなかの鏡』でも、また初期の戯曲の『遺産相続ゲーム』でもメタフォリカルに書いていたことだった。同じことというのは「お金」をめぐるということだ。
『鏡のなかの鏡』(丘沢静也訳)はカフカ=アインシュタインふうの一種の迷宮小説で、モモに代わってホルという少年が主人公になるのだが、『モモ』よりもずっと挑戦的である。文字だけでできている紳士、デュシャンのガラス絵のような花嫁と花婿、売春宮殿、部屋になっている砂漠、貧しい女王、輪郭を溶かせる男、伝達力を問うブリキ缶、格子のある螺旋階段、市街電車に合図をする白髭‥‥。
なんともいろいろなものが出てくるが、エンデはこれらを巧みに組み合わせて話を進める。とくに「列車の来ない駅カテドラル」の全面が紙幣でできていることを証かすと、この街のどこかで「奇蹟の金銭増殖」がおこっていることを仄めかす。
どうやらカテドラルの祭壇がお金を増殖させているらしい。案の定、祭壇についている説教師は大声で「真なるものも商品である!」「お金は万能である!」などと叫んでいる。その意味するところは、「われわれは永遠にわれわれ自身の債権者(グロイビガー)であって、かつまたわれわれ自身の債務者(シュルドナー)である」ということだった。
なるほど、われわれは何かの債権者であって債務者なのである。何を担保に債権し、債務を感じているのかといえば、生命と社会がもたらすイレギュラーなものいっさいに、債権し、債務を感じているのだ。セイゴオ流にわかりやすくいえば、われわれは生と死という両端の無明(むみょう)に挟まれて危険な日々を生きる不断のリスク・テイカーなのである。いや、そのはずだったのだ。
ところが「お金」が発達するにつれ、われわれのリスクはすべからく値段に換算されることになった。いまや出産も葬式も、結婚も病気も、洗濯も食事も、教育も音楽も、おいしい水も山の空気さえ、マネーゲームに関与しないものはない。リスクはすっかり貨幣に乗っ取られてしまったのだ。
エンデが『鏡のなかの鏡』で現代の貨幣経済の陥穽を突いていると最初に指摘したのは、おそらくは『金と魔術』で『ファウスト』の錬金術の近代的意味を解剖してみせたビンスヴァンガー(1374夜)だった。
ビンスヴァンガーはエンデの遺作となった『ハーメルンの死の舞踏』でも、その問題がとりあげられていると見た。金貨の報酬を得られなかったハーメルンの笛吹き男に子どもたちが誘い出されたことを、エンデは資本主義社会からの次世代の救済というふうに読み替えたというのだ。
ぼくはエンデが救済の物語を書いたとは判定しないけれど、多くの作品に貨幣経済の影を描こうとしていることは明白だった。
こうしてやっと『遺産相続ゲーム』を、3ヶ月ほど前に読むことになった。エンデが36歳のときの戯曲処女作である。『モモ』が発表されたのは43歳のときだから、その10年前の作品だ。フランクフルトで上演されながらさんざんな酷評に見舞われたことで有名になった。
岩波のエンデ全集(9巻)の解説では、平田オリザがなぜに『遺産相続ゲーム』が失敗作なのかをしつこく書いていたが、それは上演上の問題にすぎない。むしろ興味深いのは、エンデはこの戯曲ですでに貨幣経済社会の矛盾を暴こうとしていたということにある。
そもそも、いったい何がその人間の財産目録かということは、時代によっても社会によっても異なるはずである。15世紀のロンドンの貴族にとっての財産目録とドゴン族の財産目録は一致しっこない。かつては田畑を保有すればそれが石高になったわけだが、いまでは日本の農民の財は土地ではなく農協の作物買い上げ額によって決まる。
もっとはっきりいえば、財産目録なんていっときの国家の管理物にすぎないともいえるわけで、そのリストと価格には何の普遍性もない。それが今日の社会では、税務署や金融機関が認定する価値判断によって財産が規定されていくばかりなのである。たとえばぼくの財産なんて金高にすればおよそ知れているが、しかし「誰によってもとうてい算定できないもの」とも言えるはずなのだ。
エンデはこの財産目録が明示できるということに疑問をもった。そのため作品の中では、財産をとりまく人物たちを異様にも、多様にも仕立てた。
この戯曲の第3幕には、保険会社の社長エーゴン・ゲーリュオンが財産目録を作成している場面が出てくる。思考磁石、星時計、ミツバチの天の梯子、精霊の卵の殻といったわけのわからない財産ばかりが並んで、ゲーリュオンは多幸感に酔いしれ、そのくせそれがどのような値打ちになるのか、焦燥感を禁じえない。ゲーリュオンという名はダンテの『神曲』(913夜)の冒頭近くに出てくる地獄の番人、ジェリオーネのことである。ダンテは「堅気の顔をした竜」と書いたが、エンデはこの人物をブレヒト流の「搾取する者」になりすぎないように設定した。
もっといろいろな人物が出てくる。公証人のレーオ・アルミニウスは義務を忠実にはたすことでいっさいの紛争に巻き込まれないようにしている。女教師のクララ・ドゥンケルシュタインは論理的なシステムが大好きで、「公平」とは何かということをつねに主張する。年輩の前科者ヤーコプ・ネーベルはどんなときでも大儲けをしようとしている。ゲーリュオンの妻はどんな難問からも逃れてばかりいる。将軍マルクス・シュヴェーラーは全員の幸せのためには暴力が必要だと考えている。
こんな連中によって遺産相続ゲームはとんでもなく頽廃的になっていく。誰も、何が本当の遺産であるか、わからない。そういう物語なのだ。ここにはエンデがその後に書き綴っていこうとした“モモ的なるもの”がすべて用意されていたわけだった。
諸君、ドッキとは掴めぬものなのだ。
よほどにセレンディップでないかぎり、本は2度目の読みに入ったほうがいい。ぼくにとっては『モモ』とはそういう物語だったのである。
では、エンデのドッキが次に何を呼びこんだかということについては、次夜に説明したい。エンデは長らく「老化する紙幣」や「時計がついた貨幣」を夢想しつづけたのだ。それをシルヴィオ・ゲゼルやルドルフ・シュタイナー(33夜)に学んでいたのだ。これ、「エイジング・マネー」とは何かという、とんでもなく大きな問題である。
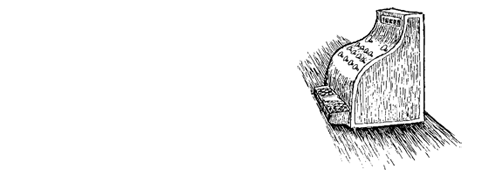
【参考情報】
(1)ミヒャエル・エンデについて、その略歴を感想を交えて書いておく。次夜の千夜千冊の下敷きとされたい。
エンデは1929年に南ドイツのバイエルンに生まれた。父親のエドガーは画家で、初期にはエンデのための挿絵も描いた。母親はレース・アクセサリーの店を開いていた。子供時代は父親の絵がよく売れていて、ミュンヘン郊外のパージングに住んだりしていて、そこでエンデのメルヘン風の気質も育まれた。そのころまでは街にやってくるサーカスの一団とも存分な交流をしたようだったが、やがて父親がナチスの文化政策を拒む姿勢を見せたため、経済状態がたちまち悪化していった。のみならず、あろうことかミュンヘン美術館は父親の絵を「無用の長物」と断罪した。
小学校時代のエンデはあまり勉強をしていない。両親も諍いが多くなり、その仲裁をするような子供になっていた。親友も肺炎で死んだ。太っちょのこの親友の死はそうとうに衝撃だったようで、のちに『はてしない物語』のバスチアンとなった。こうなれば、魚やトカゲやカメを飼って遊ぶしかなくなった。そのせいか、10歳前後には「ドリトル先生」シリーズ(55夜)を全部読破した。あっぱれ、あっぱれ。家計は母親が医療体操とマッサージの免許をとって支えるようになっていた。しかしドイツは第二次大戦に突入、生活はとてもひどいものになっていた。エンデはヒトラー・ユーゲントを逃れ、馬との日々を選んだ。
以上の日々の一端は、『ものがたりの余白』(岩波現代文庫)に切々と語られている。インタヴューを担当した田村都志夫は、エンデにおける「負の余白」こそがエンデを形成したと見ている。
(2)エンデが14歳のとき、ミュンヘンの空襲が激しくなった。夏休みにハンブルクの伯父を訪ねると、そこでも大空襲に会った。翌年はついにカウルバッハ通りの住まいが爆撃され、父親の油絵800点がすべて焼失した。
父親がこのように「社会的に傷めつけられる」ということが、少年の心に何をもたらすかは、ぼくには十分な予測がつかないが、もしも「アンチアンチ・オイディプス」ということがあるのなら、きっとそういう擦傷こそがおこったことだろう。召集令状を受け取ったエンデがそれを破り捨て、ガルミッシュからミュンヘン郊外プラーハに疎開していた母のもとに80キロを歩き続けたというのは、そして「バイエルン自由行動」という反ナチス抵抗組織の16歳の伝書係りとなって爆撃の町々を走り抜け続けたというのは、社会的軍隊性というオイディプスに対する反撃でもあったにちがいない。
戦後がやってきた。ひどいドイツの戦後だ。17歳のエンデはシュタイナーの「キリスト者共同体」に出入りするようになった。そこで3年歳上の少女に恋をするのだが、その仲を少女の両親が裂くため、エンデはシュトゥトガルトのシュタイナー学校に転校させられた。その両親が授業料を負担したらしい。しかし、ここはエンデの才能を開花させる編集学校だった。たちまち演劇に傾倒し、友達と屋根裏を借りて「屋根裏劇場」をつくると、コクトーの『オルフェ』を翻訳上演したり、ヒロシマに捧げる処女戯曲『時は迫る』を書いたりした。
こうしたなか、敗戦ドイツに通貨改革が施行されるのだ。一方で、エンデは働いてその通貨を受け取り、他方では社会がもたらす貨幣価値の変転に疑問をもっていく。もっと表現を過激にしたくなったエンデは、19歳でオットー・ファルケンベルク演劇学校に進み、ブレヒトの演劇理論を浴びた。このころ、ラジオで聞いたインゲボルグ・ホフマンの朗読を聞いて魂が震えた。インゲボルグはのちのエンデの伴侶となった。8歳の年上だった。
(3)23歳から26歳まで、エンデはミュンヘンのキャバレー(97夜)に出入りして、歌やコントを書いて糊口をしのぎ、さらにバイエルン放送局で6年にわたって映画批評の番組をもった。黒沢明や溝口健二に惹かれたのはこのころだ。のちにラフカディオ・ハーンの怪談にも魅せられ、『牡丹灯籠』をラジオドラマに仕立てたりもしている。
しかし、精気を取り戻した父親にはてこずった。エンデと同年代のロッテ・シュレーゲルと同棲を始め、母親を絶望させた。母は父の絵にナイフを入れ、自殺をはかったが、エンデがなんとかこれをとりなした。やっとの思いで、エンデはイタリアのサンアンドレアを旅行する。27歳のときにはどうやら父との和解をはたしたようだ。
28歳はひとつの転機になっている。ひとつにはブレヒト理論に見切りをつけた。リアリズムでは自分の表現がまとまらないと見通したのだ。もうひとつはグラフィックデザイナーになった友人から絵本の共同制作をもちかけられて、筆に任せて書いたところ500枚の大作となった。これが『ジムボタン』のプロトタイプで、その後に『ジムボタンの機関車大冒険』になり、ドイツ児童文学賞を受賞した。
30歳代、エンデはインゲボルグと結婚、『遺産相続ゲーム』を組み立てた。上記にも書いたように、この作品はフランクフルトで初演されたのだが、さんざんな酷評にあった。演出家がまったく戯曲を理解できなかったという、お寒いマッチングだった。そんなところへ西ドイツ放送局からテレビ・ドラマの依頼がきた。そこで構想されのが『モモ』である。1966年、37歳のときだ。このあたりのことについて、エンデは井上ひさし(975夜)と『三つの鏡』(朝日新聞社)と語りあっている。
(4)『モモ』は1972年に完成出版された。センダックの挿絵を希望したが果たされず、やむなく自分で絵を描いた。どうもエンデのやることは計画通りにいかない。しかし、それでも少しずつ根底にひそむものが起爆していった。翌年、母親が死に、次の表現作品に向かうことになった。
それは3年がかりで50歳のときに脱稿する『はてしない物語』なのだが、そのため、エンデは日本を訪れている。約半月にわたる滞在で、佐藤真理子の案内のもと、能・歌舞伎・禅寺・弓などを堪能している。『M・エンデが読んだ本』(岩波書店)には、『荘子』(726夜)とともにヘリゲルの『弓と禅』が大事そうにとりあげられている。
ちなみに『M・エンデが読んだ本』には、ノヴァーリス、ゲーテ、シラー、マイリンク、グリム兄弟、ドストエフスキー、カフカ、リルケ、ストリンドベリ、ボルヘス、シュタイナー、ガルシア・マルケス、ルネ・ホッケ、トールキンなどが挙げられている。
実はエンデの名が世界的に知られるようになったのは、やっと『はてしない物語』のあとからで、このときついでに『モモ』がベストセラーになった。1980年、51歳のときだ。いくつかの賞も受けたが、ポーランドのヤヌシュ・コルチャック賞は全額を児童施設に寄付した。ナチスの犠牲になった子供たちのために自身の命を懸けたヤヌシュを記念した賞であったからだ。
『はてしない物語』は映画化にも着手された。しかしエンデは自分が指定した脚本と監督ではないチームによって映画化が進行していることを知らず、抗議のために撮影所に駆けつけるのだが、入所を拒否される憂き目にあっている。なんともいつもバツが悪いのだ。やむなくエンデはタイトルロールから「原作者」の名を削らせた。こうしてエンデが10年来の鬱屈を作品に昇華したのが、タルコフスキー(527夜)ばりの『鏡のなかの鏡』なのである。
しかしこのころ、エンデこそ時間を泥棒されていたのだろう。63歳には食道炎に罹り、翌年には胃潰瘍となり、65歳でウルム大学病院でガンを発見され、抗ガン剤治療に入ったのだが、1995年8月28日、65歳で亡くなった。モモは駆けつけなかったのだろうか。