ヴァリス
サンリオSF文庫 1982
Philip K. Dick
VALIS 1981
[訳]大滝啓裕
SFにどっぷり溺れていたのは70年代と80年代の20年間ほどだ。ブラッドベリとバラードの衝撃を受けて以来、数々の驚嘆と感嘆に見舞われてきたが、構えて取り組み読みをしたのは、ディックのものが多くなっていた。取り組み読みというのは、暗号解読者のように読むということだ(ピンチョンなどもそのように読んだ)。なかで深くて速い過呼吸に襲われ、構えも崩れそうになったのが『ヴァリス』だ。
そこには、情報ネットワークがもたらす知の能動性についての、最も幽遠か、もしくは最も忌まわしい妄想と哲学が滾っていた。
どうしてあんな異様な話が書けたのか。フィリップ・キンドレッド・ディックであるからだ。これでは何も説明したことにならないけれど、そう言うしかない。それほど卓抜きわまりない作家だった。だから評判も尋常じゃない。
ブライアン・オールディスは早々と「ディックとバラードだけが読むに足る作品を書いている」と言っていた。アーシュラ・K・ル・グィンは「わが国のボルヘス」という最大級の賛辞をつかった。ティモシー・リアリーは20世紀をとびこえて「21世紀の大作家」と名付け、さらには「量子時代の創作哲学者」と褒めちぎった。
ボードリヤールは「現代の最も偉大な実験作家である」と書いたし、アメリカのSFが大嫌いなスタニスワフ・レムですらディックだけは褒めたあと、「アメリカのペテン師に囲まれた幻視者」と評した。みんなメロメロなのである。
ディックにメロメロなのは『ヴァリス』のせいではない。ずっとそうだった。アート・スピーゲルマンは「20世紀前半におけるフランツ・カフカと20世紀後半におけるフィリップ・K・ディックは同じように重要だ」と評した。きっと1963年にヒューゴー賞を受けた『高い城の男』(ハヤカワ文庫)のことだろう。
あれは哲学的迷路というものが初めて稠密なSFになった記念碑だった。舞台は第二次世界大戦後にアメリカの西部が日本によって、東部がドイツによって分割統治されるという、とんでもない設定のネーベンヴェルト(パラレルワールド)になっていた。いまおもえば、『高い城の男』の主人公ホーソーン・アベンゼンこそ、その後のディックの作品に繰り返しあらわれる社会的共有世界観と個人的幻想世界観との対決を辞さない男の原型だった。
みんなメロメロだったが、しかし長いあいだ、ディックが宇宙や世界の何かの原型や母型を求めているとは思っていなかった。ディックはもっとずっと多様な才能の持ち主だと信じられていた。「ロンドンタイムズ」が「あらゆる種類の文学を試みたディックこそが欧米の前衛作家の全員の顔色をなからしめている」と書いたのもそのせいだ。スラヴォイ・ジジェクがジャック・ラカンの鏡像思想を説明するたびにディックの短編をいろいろ持ち出すのには驚いたけれど、これはディックの錠剤をラカンの症状にあわせて処方したにすぎなかったのかもしれない。
こういうぐあいにディックをめぐる評価には尖ったものも、その才能に脱帽しきっているものもあるのだが、しかし、いまなおその真骨頂が文学としても思想としても申し分なく語られているとは見えてはこない。とくに『ヴァリス』においては――。
Vast Active Living Intelligence System.
これがVALISの正式名称である。
本書を最初に訳した大瀧啓裕の訳以来、「巨大にして能動的な生ける情報システム」と訳されている。ディック得意の知的トリックだが、架空の『大ソビエト事典』第六版には、VALISについての次の説明があるという。「巨大にして能動的な生ける情報システム。アメリカの映画より。自動的な自己追跡をする負のエントロピーの渦動が形成され、みずからの環境を漸進的に情報の配置に包摂かつ編入する傾向をもつ、現実場における摂動。擬似意識、目的、知性、成長、環動的首尾一貫性を特徴とする」。
小説『ヴァリス』の中でVALISの名は、これまたディック得意の仕掛けによって、同名のSF映画として登場する。ロックグループ「マザー・グース」のエリック・ランプトンが監督・脚本・主演している映画だ。
エレクトロニクスの天才が経営するレコード会社とホワイトハウスの二つを舞台にした映画で、どうもニクソンの陰謀と失脚がVALISとおぼしいシステムによって動かされていたという筋書きになっているらしい。らしいというのは、こうしたことは小説『ヴァリス』の登場人物たちの断片的な会話によってしか語られていないので、映画の実態はわからない。ようするにVALISはこのSFの題名であって、架空の映画の題名でもあったのである。
こういうことだから、話の中味を案内するのは並大抵ではない。メタフィクショナルな多重構造になっているなどというよりも、メタフィジカルな多重の構想が錯綜していて、こう言っていいなら、古代の集合脳に未来のネットワーク脳を引き取って進捗しているかのようなのだ。要約はほとんど不可能に近い。
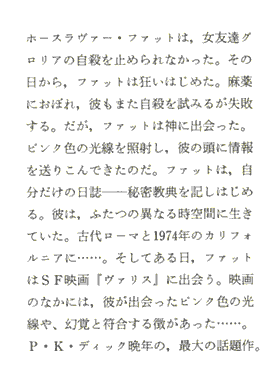
主人公ホースラヴァー・ファットは親しいガールフレンドのグロリアの自殺を止められなかった。これが一応の発端である。ファットはこのことに耐え切れず、自分が自殺を幇助したのかとか贖罪をどこに求めるのかといった葛藤と苦痛によって、だんだん狂い始める。ファットの妻もドラッグのせいか、前年に精神病で死んでいた。
主人公が狂い始めたのだから、このさき、いったい何が実際に進行したストーリーで、何が妄想によって語られたものなのかは、読み手には判別しがたくなってくる。時代は1960年代後半から70年代にかけてのこと、事態の進行はファットの友人の「わたし」によって報告されていく。そこにファットの日誌が絡む。日誌にはたいてい「宇宙が情報で構成されている」とか、「脳はその情報の配置の一部しか感知できない」だとか、「世界は理性によってはとうてい理解できない」といったことが、やや錯乱ぎみに断片的に綴られている。ただそこには、どうも「宇宙的知性」とでもいうものが関与しているらしい。
ファットはこのような知性を最初は「ゼブラ」と名付けた。それがシマウマの縞のような混合的な“Active Living Intelligence”と見えたからだ。やがてファットは「神」に出会い、ピンク色の光を体験し、完全な死をめざす。
一応、物語はこのように展開するのであるけれど、ディックが死んでからのちに判明したように、この物語に始まった“ヴァリス三部作”(『聖なる侵入』『ティモシー・アーチャーの転生』)には、それまでディックが書いてきたディストピア・オデッセイとは決定的に異なるものが発散していた。
ディックはこの三部作を書いて1982年に死んだ。53歳の早死にだった。死因はよくわかっていないが、おそらく三部作は遺言だったのである。実際にも作品には死を予感したディックがそれまで紆余曲折を見せつつ人類の宿命を問題にしてきた多様なテーマを、一種の黙示録めいて提出しようとしたようなところがあった。
なぜディックがそのような試みに突入していったのか、それがなぜ「巨大にして能動的な生ける情報システム」の宿命になっていったのかは、おそらくまだほとんど議論されないままにある。というのも、このヴァリス三部作によって、ディック自身が発狂してしまっていたのではないかという憶測が流れ、そっちの話題に作品が包まれてしまったからだった。この憶測はいまなお否定されていない。
わざわざ紹介することもないだろうが、たとえばこういう憶測だ。ディックのファンにはすっかりお馴染みになった「2―3―74」は、1974年2月から3月にかけて、ディックが不気味で異様な夢や幻覚や音声に見舞われたときの体験を示す符号をあらわしている。
ディックはこのときフィボナッチ数列の光の放列の奥にグノーシス的な叡知のときめきを感じた。そのあと数年間にわたってグノーシス主義やクムラン宗団の文献を読み、その周辺を探索し、そして『ヴァリス』を書いたのであろうとおもわれる。執筆は1980年に突入していた。続けさまに『聖なる侵入』『ティモシー・アーチャーの転生』を発表した。これがヴァリス三部作になった。やっぱりディックはおかしくなったのではないか。そういう勝手な憶測だ。
思い出してみると、ぼくが『ヴァリス』を読んだのは翻訳が出てまだ数日もたっていなかったころだった。渋谷の大盛堂で買った。一読、5分の1ほど進んだところで、「エントロピーによる虚無」って文学になるのかと驚いた。そして、この奇怪な物語装置は太古から続いているある種の神秘宗教の総決算なのであろうこと、それにしては、ディックの科学主義はそれを十全に処理しきれなかったのであろうことが、すぐに残骸のように見えてきた。
宇宙の大エントロピーから生まれた生命という小エントロピー(負のエントロピー状態)が、生命誕生以来の何事かの「情報システム上のいたずら」を数十億年にわたってしてきたことはわかっている。それが遺伝情報における誤植という事件であったことも、わかっている。さまざまな突然変異がおこったのだ。その途中で人類という別の知性が派生して、その知性が個体としてはたかだか数十年でおびただしい死を数珠つなぎに経験してきたこともわかっている。言葉や道具や絵画や機械はその途中にもたらされた「いたずら」による産物だったのである。
しかし、これらのことを宇宙の「知性」による情報システムの誤作動によるものとみなし、その誤作動を一部の人類が解読しようとしたと想定することは、いささかやりすぎだった。ディック自身もあきらかに自分が突入してしまった問題に決着をつけかねているようなのだ。
作品が半ばにさしかかると、ファットは宇宙の一部ないしはホロニックな全体のそこかしこに「生ける情報」(Active Living Intelligence)があるとみなすようになっていく。そして、その情報の一部が生命情報システムとして人類にさしかかったものを「プラスマテ」と名付けるようになる。特別のものではない。一般にはプラスマテは「精神」とか「魂」とよばれている。人類とはそもそもの本来がホモ・プラスマテなのである。
ディックは、宇宙の情報エントロピーはまわりまわってこのプラスマテの形態になっていると考えたのだ。進化したのではない。プラマステがヒトに異種共生したということなのだろう。
が、こういうことは、とくにディックだけに特有な独創ではないだろう。プラスマテと呼ぶかどうかをべつにすれば、ほとんどの哲人や宗教者はそういうことがありうるだろうと考えてきた。ぼくのようなぼんくらにも、そんなことは20代の後半にほとんど見えていたことだ。そのあたりのことは『自然学曼陀羅』(工作舎)にも書いたし、その後の『遊学』(中公文庫)にも散らしてある。
だからこうした展開は、宇宙生物学、遺伝情報論、ヘラクレイトス、ゾロアスター教、ジャイナ教、インド六派哲学、新プラトン主義、カバラ文献、パスカル、スピノザ程度を読むだけでも十分に見当がつく。いや、古代宗教者の大半がプラスマテに近いことを、アヌやらヌースやら般若やら六現観(6つの直観)といった言葉であらわしたからといって、それが物語に組みこまれたからといって、それは哲学がまじっただけなのだ。
ところが、ディックはこのプラスマテはごく一部の人間にしか感知できなかったと考えたのである。そして、その一部の人間に預言者エリヤや医術者アスクレピオスやオリエント神テレピヌスや、そして魔術師シモンやイエスやクザーヌスやヤコブ・ベーメを充てたのだ。
こうなると、これは「菩薩はプラスマテの受信者であった」とか「グノーシスは宇宙情報システム解読の記録であった」と言っているようなもので、ここからはディックの狂気と妄想なのである。PKDカルトなのである。PKDはフィリップ・キンドレッド・ディックの頭文字のことをいう。このPKDカルトがヴァリス三部作を記述させた。そうでなければ、悔しいけれども、こんな“傑作”は生まれない。
そうなのだ。おそらくディックは作品の後半にさしかかって、ついに長年にわたった「コイノス・コスモス」と「イディオス・コスモス」との対決に決着をつけたくなったのだ。しかしながらそれだけに、そういう決着の経過を描いた『ヴァリス』の後半を読むことは、人類が総じて受容した情報システムの正体と向きあうことを読者に強要することになり、ぼくから見ると、こういう対決を読者が引きかぶるのはあまりに気の毒のようにもおもえるのである。
つまりは、最期のディックはあまりに真剣すぎたのだ。きっと「もどき」が「もどき」でなくなったのだ。そして、その後の世の中の事態がVALISを宇宙というより地球に引きずりおろしてしまったことを、ディックは予感できなかったのだ。インターネットの出現によって「巨大にして能動的な生ける情報システム」はみんなのものになってしまったのだ。もちろんやむをえないことだろう。
それなら『ヴァリス』はつまらないのかというと、まったく逆だ。いくらだって愉しめる。たとえば、人称のトリックを読むのはおもしろい。『ヴァリス』の語りでは、主人公フィル(ディック自身)が友人ファットと一緒に行動しているようになっているのだが、物語の終盤になって救世主めく少女ソフィアに「フィル=ファット」と指摘されて、ファットが消える。二人は別人ではなかったのだ。
このカラクリは冒頭で「ぼくはホースラヴァー・ファットだ。ぼくはこれを三人称で書く」という“仕込み”に暗示されていた。一人称フィルの三人称化が、何かを可能にしたはずなのである。これについてはジョン・C・リリーが『サイエンティスト』(平河出版社)で「一人称を三人称にすることで、一人称では思いつけないことが浮かんでくるものだ」と言っていたことを思い出させよう。
むろん極端に知的な読み方をするのもおもしろい。それには翻訳者の大瀧啓裕も試みていたように、頻繁に登場してくる神秘思想をディック以上に複合賞味することだろう。とくにシモンの知やグノーシス思想について、ディックほど熱心にとりこんだものはなかったのだが、これはその気になればもっと深まるものになる。たとえばシモン(Simon)の知では、キレネのシモン、熱心党のシモン、ハスモン朝のシモン、シモン・マグス(魔術師シモン)、サン・シモン伯爵のすべてを引き取れば、母型としてのシメオン(Simeon)がさらに騒然と立ち上がってこよう。
なんだか面倒な話にしてしまったが、それはそれ、もっと気楽に読むのも、他人頼みで読むのもありである。
たとえば『フィリップ・K・ディックのすべて』(ジャストシステム)というノンフィクション集成が刊行されているので、ここに収録されているディックの文章を遊ぶのもいいだろう。リドリー・スコットが『模造記憶』と『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』を下敷きに、かの《ブレードランナー》として映画にしたのはよく知られているが、ディックがこの原作が映画になりうることを一九六八年にとっくにノートとして発表していたことなどは、この集成でなければわからない。
以上はむろん老婆心である。ディックはカフカともル・グィンとも違うし、ボルヘスやエーコほどの幻想制御もしていないということを、また、ティモシー・リアリーやデレク・ジャーマンのポスト・ジェンダーふうの陽気をもちあわせていないということを、老婆心から語ってみたにすぎない。
けれども、どんな読み方をしようとも、『ヴァリス』(と、その続編)が、今日考えられるかぎりの「宇宙と脳と神秘哲学をめぐる情報システム」を扱った最初で最大の唯一の文学思想的な試みであったことからは、読者は逃れようはない。面倒なのでここには書かないが、カルトを脱出するのはそんなに困難なことではないけれど、そんなことを考えるより、やはりいったんはディックの周到で狂気に満ちたPKDカルトに浸ることである。そうすれば、これだけは請け合うが、読み終わったのちに何が何だかわからない自分がそこにぽつんと取り残されるのを感じることだろう。
が、そのぽつんとした自分こそ、死を前にしたディックが入念に仕上げたディックその人の虚無そのものだったのだ。あれっ、こんなことでよかったのかな。ま、ディックだから許してもらえるか。



