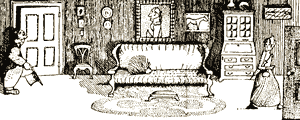父の先見


岩波少年文庫 1951
Hugh Lofting
The Story Of Doctor Dolittle 1920
[訳]井伏鱒二
この本のことをおもうと、最初に京都河原町の志津屋で食べたシュークリームのほわほわとした幻想的な味を思い出すように、胸の奥がなつかしい。
あまりになつかしくて、ぼくがどれほどドリトル先生の物語にいそいそしたか、とうていうまく説明できそうもないほどだ。
そこで、このシリーズができた背景について書いておくことにする。
ドリトル・シリーズは全部で12冊ある。だいたい似たようなファミリーが登場する。
中心人物はイギリスの田舎バドルビーに住んで医者をしているジョン・ドリトル先生で、ある日、百歳をこえるオウムの「ポリネシア」からどんな動物にもちゃんとした言葉があるんだということを教えられ、勇躍、動物語の研究にいそしむ。
動物語を話せるようになると、その噂を聞いて世界中からドリトル先生に病気をなおしてもらいに動物たちがやってくる。
ところが、先生と一緒に住んでいた妹のサラは、動物ばかりに囲まれるのにうんざりして出ていってしまう。そこでメスのアヒルの「ダブダブ」が代わりの家政婦の役を買ってでる。フクロウの「トートー」は知恵があるので、先生の参謀役になる。犬の「ジップ」は先生の助手をつとめながら、ホームレスになった犬たちのホームをつくって管理人になる。
このほかブタの「ガブガブ」は食いしん坊で愛嬌をふりまく役を、頭が長い胴体の前後についている「オシツオサレツ」は先生が疫病をなおしたアフリカのサルたちがお礼に送ってきた珍獣で、どういうわけかいつもはにかんでいる。
こうした連中にかこまれながら、ドリトル先生は大冒険をしつづける。ともかく、動物語の研究はいくらでも奥が深いので、魚語や虫語にとりくむたびに、冒険が広がっていくのである。
こういう愉快な設定を作者ができたのは、ロフティングがそもそもこのような物語を生み出すにいたった事情によっている。
ロフティングはアイルランド系のイギリス人で、アメリカに渡ったのちはMITをへて土木技師や鉄道技師をしている。結婚後、第一次世界大戦がはじまるとアイルランド軍の将校として招集をうけ、フランダースに赴いた。このときロフティングの幼い二人の子供たちが戦地のお父さんの便りをほしがった。
戦地では子供に聞かせる話はない。そこでロフティングは日頃感じていることをなんとか物語にして書くことにした。
日頃感じていることというのは、戦争では兵隊ならばケガや病気をするとちゃんと扱われるのに、人や荷物を運ぶ馬などはケガをしたら捨てられる。ロフティングはこれはおかしい、馬にも同じような看護をしてやるべきだと思っていた。
が、そのように馬を看護してやるには、人間が馬の気持ちを察する必要がある。それには馬語も話せるようにならなければならない。
そのようなことを夢見ていたロフティングは、これをふくらませた話を子供たちへの便りにして、お父さんの戦地での夢物語を伝えてあげようと考えた。ついでに絵も入れた。
子供たちはロフティングの話にとびついた。
おまけにロフティングが負傷してアイルランドに送還され、家族がふたたび顔をあわせるようになってからというものは、子供たちは毎晩この話のつづきをせがむようになった。
こうしてロフティングのドリトル先生が誕生していった。知り合いはこの話を聞いて出版を勧めた。その本が『ドリトル先生アフリカゆき』である。
その後、ドリトル・シリーズは大当たりする。
ロフティングは次々に趣向を変えてドリトル先生に冒険をさせた。2作目はクモサル島を探検する『ドリトル先生航海記』、3作目は黒人国の郵便局長になる『ドリトル先生の郵便局』、4作目は『ドリトル先生のサーカス』で、いろいろ動物助けや人助けばかりしている先生が貧乏になってサーカス団に入るのだが、やがて自分でサーカス団を結成するという話になっている。
ぼくがいちばん熱中したのは『ドリトル先生と月からの使い』とその続篇の『ドリトル先生月へゆく』『ドリトル先生月から帰る』だったろうか。
これは先生が、格別に複雑なしかけの聴音器というものをつくって、ガチョウ・アリ・ハチ・トンボのたてる音を研究しているうちに、ある夜、巨大なガが訪ねてケガをなおすことになる。
どうも変なガだとおもってあれこれ研究してみると、そのガは月からやってきていたらしいということがわかる。そこで先生はガの背中に乗って月に行く計画をたてるという話である。ぼくの月狂いを準備したファンタジーだった。
この巨大ガは「ジャマロ・バンブルリリイ」という名前をもっている。ぼくはこの名前のリズムが好きで、何度も口にしたものだった。
ところで、本書は井伏鱒二が訳している。
それどころか、ドリトル・シリーズの大半が井伏鱒二訳になっている。なぜ、そうなったのか、その背景にすこしだけふれておく。
そこには一人の女性の乾坤一擲があった。『ノンちゃん雲にのる』の石井桃子の乾坤一擲だ。
昭和15年のこと、石井桃子は文芸春秋社をやめた退職金で白林少年館をつくり、当時の暗い世相を打ち破る少年少女むきの出版に単身でのりだした。その第1弾が本書であった。石井は翻訳(下訳)を自分でやり、そのブラッシュアップを、当時、近所に住んでいる井伏鱒二に頼んだ。
井伏のブラッシュアップはすばらしいものだった。翻訳というより、ほとんど日本語の文章をこしらえた。たとえば、ドリトルもふつうに訳せばドゥーリトゥルで、あえて訳せば「薮博士」というところだが、それを日本の子供の発音でも親しめるドリトル先生にした。そのほか「オシツオサレツ」「アベコベ」などの動物たちの名前や冒険先の国の名前にも工夫を凝らした。
ところが出版されたのはこれ1冊きりで、時代はどんどん戦火のほうへ巻きこまれていった。
戦後、石井はふたたび決断をして、岩波書店にドリトル先生シリーズを出させる約束をとりつける。井伏にも翻訳をひきうけさせた。岩波もこれに応えて全12巻の刊行をひきうけた。
ちなみに石井は、さらに独力で「かつら文庫」という貸本型の児童図書館をつくっているが、そこで最も読まれたのはドリトル先生シリーズだっという。子供たちは一冊読んだらやめられなくて、途中で放棄する子供は一人もいなかったともいう。
そんな背景があったのである。
さて残念なことに、アメリカでドリトル・シリーズを出してきたリッピンコット社では、いま『アフリカゆき』と『航海記』の、たった2冊だけしか出ていない。
これは、本シリーズには黒人問題をはじめとする差別問題にかかわる部分が少なくないという理由によっている。アメリカらしいことだ。ただし、イギリスでは全巻が刊行されている。日本でいえば、アメリカからのクレームによる「ちびくろサンボ」や「ダッコちゃん」の禁止にあたる例なのだが、はたしてこのような問題をすべて差別問題にしてしまってよいのか、いささか複雑な心境になる。ドリトル先生にはやはり月まで行ってほしいのである。