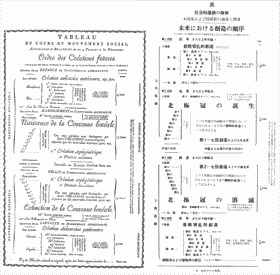父の先見


現代思潮新社 1970・2002
Charles Fourier
Theorie des Quatre Mouvements et des Destinees Generales 1808
[訳]巖谷國士
パレ・ロワイヤルの狂人と言われていた。晩年はパレ・ロワイヤルのカフェや読書室で風変わりな常連として知られたせいだろう。その狂人フーリエが書いた『四運動の理論』が奇書でないはずがない。奇書なのだ。まさに奇書、それもとびきりの奇書である。ただし奇書というと、ふつうは書物の中に「奇」があるということになるのだが、フーリエの奇書は社会に実在する「奇」を企てたという意味では、活きた奇書だった。
もっともフーリエ自身は「奇」とは思っていない。『四運動の理論』がめざすもの、それは新しい社会モデルの実験だったのである。
結論からいうと、この社会モデル「アソシアシオン」(協同体)は、中心に「力」をもっている。その力は「関係」である。フーリエはそれを「情念引力」とよんだ。それゆえフーリエの理論は万有引力論ならぬ情念引力論となる。「愛の重力理論」などともよばれた。フーリエが考え出した基礎の情念は12を数えた。五感にあたる5つの「感覚(贅沢)情念」、友情・恋愛・野心・家族愛の4つの「感情情念」、そして密謀・交替・複合の3つの「配分情念」。これらが前後左右にマトリックス状につながって、系列(serie)と群(groupe)をつくっている。その相互関係を引きつけているのが情念引力である。
なんだこれはというほどに、抽象的か観念的か、もしくはわけがわからないものに見えるだろうが、フーリエは大真面目にこれらの充実した組み合わせを組織化することで、社会モデルとしてのアソシアシオンができあがると確信していた。それが「ファランジュ」というものだった。のちにフーリエ協同体ともよばれた。
アソシアシオン「ファランジュ」は1500人から2000人で構成される。理想的には1620人だというのだが、これは810におよぶ情念素が完全なシステムを形成するのに必要な人数の、2倍にあたっているらしい。フーリエが1819年に確立した理論にもとづくものだったのだが、その後にフーリエ自身が「縮小規模実験体」を発案して、80家族・400人でも「試験ファランジュ」が設立できるとした。このようなファランジュの中心には、その建物だけでも自生自立しうる「ファランステール」という集合機能と集住機能をもったパビリオンが設定された。
それにしても、こういうことを聞かされただけでは、これはただの理念の弄びか、数字の遊びにすぎないとしか思えないだろう。ぼくもながらくそう思っていた。むしろフーリエの奇抜な文章と重力感覚の横溢をおもしろがって読んできただけだった。
しかしあるとき、下河辺淳さんや金子郁容さんらとの仕事で近代の“プレボランタリー組織”の歴史を調べているときに(幼稚園・YMCA・赤十字・動物愛護協会・ボーイスカウト・慈善団体その他)、そうだそうだ、あれも見ておこうと思ってフーリエが提唱した共同体「ファランジュ」の周辺を追いかけてみたところ、その意外な実際的広がりに驚いた。
発祥のフランスにはコンデシュール・ヴェグルのコロニー建設をはじめとして、ギーズのファミリステール、サン・ドニの農業共同体、リーの農村児童の家、ドーフィネのポリモンドー協同体などが次々にできていて、イギリスでは農学者のヤングが参画して資金提供してからいくつものファランジュが生まれていた。
ロシアでは、ペトランシェフスキーがフーリエ主義運動の旗手となったことも手伝って、ここにはドストエフスキーも参加した。時期は遅れたが一番広がったのはアメリカで、マサチューセッツだけで30におよぶフーリエ協同体が出現し、コンシデランが移住してからはテキサスに多機能型のファランステールが建てられた。
いったい、これは何なのか。何の魅力が人々を引き付けたのか。なぜフーリエの「奇」はこれほど受け入れられたのか。それがどうして短期間に各地に広がっていったのか。これは腰をすえて、いつか考えなければなるまいと思ったものである。
では他方、それほど実践的だったファランジュやファランステールを作り上げたフーリエが、なぜにまた「パレ・ロワイヤルの狂人」などとよばれたのか。やっぱりフーリエはおかしかったのか。そこも改めて視点を変える必要がありそうだ。
いや、そもそもフーリエはいったいどういう理由でアソシアシオン「ファランジュ」を発想し、そこに情念と引力などを持ちこもうとしたのか。これまた、考えこまざるをえなくなってきた。
英語のアソシエーションには結社とか協会とか組合という意味がある。もともとアソシエーションは「組み合わせること」をいう。そのような意味と形態の原型は、実はフランスに発芽していた。それがアソシアシオンである。協同体とか協同組織と訳している。
フランスの産業革命が本格化したのは、1830年代である。これによって都市問題・労働問題・交通機関問題・工場問題などが一挙に噴き出てきた。アソシアシオンはこれらの問題を克服するために発想された協同活動単位のことで、日本でいえばかつての生協がさまざまな運営法や流通問題にとりくんだように、また今日のNPO法人がそれぞれ独自性を誇ろうとしているように、そのころのアソシアシオンもそれぞれが競いあっていた。フーリエはこれに着目したわけなのである。
つまりすでにアソシアシオンはあったのだ。
が、このままではバラバラになる。フーリエはこのような情勢のなか、のちに「空想的社会主義」とよばれることになる“空想”をした。いや、それは空想ではなく、きわめて社会的なアソシアシオンの実践的改革だったというべきである。
だいたい空想的社会主義という呼称はまったく実態にあわないもので、これは実証主義とプレ社会主義と産業的生活主義が出会ったものといったほうがいい。シャルル・フーリエもサン・シモンも、まったく“空想的”ではなかった。これはのちのマルクスやエンゲルスが打ち出した社会主義から見て、かれらが“空想的”ではあれ先駆していたという意味でつけられた呼称にすぎない。
それはともかくも、フーリエはこうした時代情勢のなか、いったいどのような理念で、どのように組み立てれば、新たな協同組織(アソシアシオン・ヌーボー)が産業革命社会の只中でできあがるのか、そこに着手していくことにした。すでに具体的な組織は見えていた。改善点は見えている。けれどもフーリエは、のちにのべる理由によって、自分の仕事を厳密に組み立てたいと考えていた。
そこで最初に理念をたてた。
バラバラな活動をつなげるためにはいったい何が必要なのか。フーリエは考える。必要なのは、いわば引力である。互いを引きつけ、互いを引きあう引力がほしかった。しかし人間は物体ではないので、何をもって引力のはたらきと見ればよいのか、そこがわからない。フーリエは人間の感覚や活動から、質量や速度や位置や摩擦にあたる人間力学的な要素を導き出していくことにする。
こうして最初に着手したのが厖大なノートであった。これはのちに『大論』になる。フーリエ協同体のためのマスタープランといってよい。これでおよその骨格が見えてきた。そこで人々にプランの一部を話しかけてみると、予想以上の反応がある。フーリエは自信を深める。しかしまた、まったく理解されないところがあることも見えてきた。
そこでフーリエは具体的な説得対象としての男女にむけて、そのマスタープランの一部を切り出すことにする。それが『四運動の理論』なのである。読めばその法外な内容とともに、フーリエが「普遍のためのアナロジー」に徹していることがすぐ伝わってくる。
フーリエがとりくんだのは、デカルトの『情念論』では語りきられなかった情念の性質をあきらかにすること、その情念に運動を与えること、情念の型を分類してそれらを配置させること、それらが引きあう可能性を予想すること、そのうえで調和や親和の本質を突き出すこと、こういうことだった。
しかし他方で、フーリエはそのようなことが理論化されても(徹底的に理論化したのであるが)、働く民衆たちに理解されるとはかぎらないことも知っていた。かれらは毎日肉体を酷使し、毎日欲望に飢え、毎日喜怒哀楽を表現しているものたちだった。かれらに新たなアソシアシオンを感じさせるにはもっと肉体的で、もっと欲望的で、もっと喜怒哀楽的な説得が必要だということを知る。
そのためにフーリエが採った方針は、肉体も欲望も喜怒哀楽も抑制しないということを強く訴えることだった。こうしてフーリエは「愛」と「性」を積極的にもりこんだ説明に傾いていく。この傾きは度が過ぎたといえるほど、フーリエ自身の肉体や欲望をめくれあがらせたようだった。このためフーリエは、のちのちにも「性の享楽」を煽ったのではないかと責められる。
いったいフーリエがどういう人物だったかということを書いておく。フーリエの理論は、フーリエの人生と切っても切れないものをもっている。
シャルル・フーリエはブザンソンの織物や香料を扱う富裕な卸業の家に生まれたわりに、父親の死などの不運がつづいて、20歳には商業の見習をし、そのあとは商人になっている。商人としてはフランス全土ばかりかヨーロッパ中をまわっていた。その後にリヨンに落ち着いた。この、フーリエが商人であったということがことのほか大きい意味をもっている。
ミシュレの『フランス革命史』には、「誰がフーリエを作ったのか。ランジュでもバブーフでもない。リヨンだけがフーリエの先駆者なのだ」という一節がある。それほどリヨンという土地がフーリエに与えた影響が大きかった。1784年には、魔術師カリオストロがリヨンにあらわれて秘密結社のロージュを開いた。1793年にはフーリエ自身が商取引上のことで逮捕と疑獄を体験した。19世紀になると、リヨンはある意味でアウトサイダーが群をなし、屯(たむろ)して、ありとあらゆる犯罪と欲望を吸収するような都市になっていた。
しかしこのリヨンの喧噪と闇こそがフーリエに新たな見通しをもたらしたのだった。フーリエは商業や交易の裏の意味を詳細に知っていく。のみならず、大半の商業や交易に欠けているものを発見する。それは、すべては「計算方法」によって、どのようにも社会と人間の価値が変わっていくということだった。フーリエはしばらく“ニュートン的な計算”に没入し、その引力を人間社会にあてはめても十分に活用できると考え始めたのである(フーリエの計算好きや数学好きには呆れるばかりだ)。
このあとのフーリエの活動は省くけれど、フーリエは緻密な計算を使いさえすれば、人間の情念は司ることが可能だというところまでのぼりつめていった。社会は情念引力が司ることによって均衡と安定を保つのではないかとも、結論づけた。しかし、リヨンを見ているうちに、そのような理想社会は少人数によるモデル的社会にしておくべきだろうということも、見えてきた。
こうしてアソシアシオン「ファランジュ」が誕生していったのである。『四運動の理論』にフーリエは書いている、「発見はどんなやりかたで予告されてもかまわないのではないか」。
なるほど、フーリエは新しい社会の単位を発見したかったのである。この単位、その後すべての社会組織の単位となったものが多い。協会、組合、協同組合、労働組合……これらはみんなフーリエの子供たちだった。
では、それなのになぜフーリエは「パレ・ロワイヤルの狂人」だったのかといえば、フーリエ自身は予告者であり発見者であって、“参加する一人”
ではなかったからである。それに「情報引力」の質量源であるシャルル・フーリエという太陽だか地球だかが、そんなに動きまわっては、おかしくなる。ただフーリエはちょっとばかり街をうろつきすぎて、狂人扱いをされたのだった。