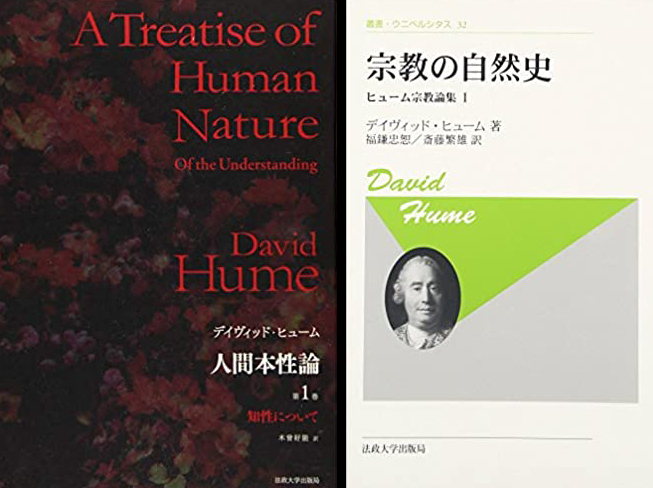フェティシュ諸神の崇拝
叢書ウニベルシタス 法政大学出版局 2008
Charles de Brosses
Du Culte des Dieux Fétiches ― Ou Paralléle de l'ancienne Religion de l'Egypte Actuelle de Nigritie 1760
[訳]杉本隆司
編集:平川俊彦・勝康裕 協力:石塚正英
フェティシュ(fétiche)という言葉は18世紀のド・ブロスの造語だ。ポルトガル語のフェイティソ(feitiço)から転用したもので、もともとは護符とか呪符とか、魔法とか呪いとかを意味していた。さかのぼれば、ラテン語の「制作する」にあたる facere の形容詞 facticius(人工の)からフェイティソが派生した。日本では「物神崇拝」などと訳される。
シャルル・ド・ブロスはブルゴーニュで高等法院評定官の仕事をしながら、歴史や民族にひそむ人間の思考形態に関心をもって、サルティウス(古代ローマの政治家)の研究をし、『カティリーナの反乱』や『ユグルタの戦争』を書いていた。イタリアを旅行して『イタリア便り』『火山の噴火によって埋没したローマ年の現状』などを発表し、ウォーバートンの『古代エジプトの象形文字』に刺激されて『言語のメカニズムと語源学の自然法則』を刊行した。
歴史に埋もれ、起源がわからなくなった「何か」を発見するのが好きだったようで、1760年に『フェティシュ諸神の崇拝』を著して、ついに誰もが着目できなかった「心の宗教」以前に「物の宗教」が先行していたことを仮説した。

フランス啓蒙主義時代の思想家。ブルゴーニュのディジョンに生まれ、21歳でブルゴーニュ高等法院の評定官に就いた後、歴史・地理・言語とともに、ラテン文学を含む古典の研究にいそしんだ。1739-40年にイタリアを旅行し書いた紀行文は文芸・建築等における中世原理の軽視とヒューマニズムの礼賛で特徴づけられる。
どうして宗教が発生したのか。宗教がその後の数千年をこえる影響を文明・社会・制度・生活習慣にもたらし、さまざまな文化様式と表現形態を営々と構築形成しながら、かつまた個人の内奥にひそむアディクションを時代ごとにそのつど喚起してきたのかということは、まだよくわかっていない。
ふつうは、宗教の起源は「心」の中を説明のつかない何かが占めてきた現象だとみなされている。そうした心の現象に神やオーバーマインドや象徴物に対する崇拝が生じ、それが信仰となり、信仰集団(教団)になっていったと解釈されてきた。ところが、ド・ブロスはこの通念を打ち破ったのである。
話は逆ではなかったか、というのだ。最初に「物」に対するなにがしかの崇拝がおこっていて、あるとき或る集団(クランなど)がその崇拝にもとづく超越的な教えや超常的なものに曰く言いがたい信仰をもつようになったとき、そこに特定の神や象徴物に対する崇拝が生まれていったのであろうと推測したのである。「物」が先行して「心」がそれに従ったと見たのだ。ド・ブロスはそのようになることを「フェティシュ」と名付けた。
あとで説明するけれど、このような見方は一般に想定されている信仰や宗教心にあらわれる「無限の感情」にくらべて、一段も二段も下位の「こだわり」のように思われてきたものだったが、フェティシュはそういう見方をくつがえすものになっていった。
画期的な見解の登場だった。その影響はそうとう大きいものになった。たとえば、ド・ブロスと同時代のヒューム、ディドロ(180夜)、その後のコント、マルクス(789夜)、フレイザー(1199夜)、デュルケム、フロイト(895夜)らを次々に驚かせ、やはり「信仰の芽生え」よりも「物の崇拝」がずっと原初的で力強い起動力をもっていたのではないかと考えられるようになったのである。
それなら、その後はフェティシュ宗教学やフェティシュ文明論とでもいうべきものが宗教学や人類学の基礎になっていったのかというと、必ずしもそうではなかった。
ひとつにはフェティシズムがアニミズムやトーテミズムとどのように異なるのかということが、もうひとつにはフェティシュをめぐる性向に心理的ないしは精神的な「歪み」や「倒錯」や「偏向」がおこっているのではないかということが、新たな議論を巻きおこしたからだ。

左上からデイヴィッド・ヒューム(1711-1776)、ドゥニ・ディドロ(1713-1784)、オーギュスト・コント(1798-1857)、ジェームズ・フレイザー(1854-1941)、エミール・デュルケーム(1858-1917)、ジークムント・フロイト(1856–1939)。
すこし話が前後したので、問題別、時代別に多少の順を追って整理していこう。まずド・ブロスはフェティシュを次のように説明した。
(1)多種雑多な「もの」がフェティシュの対象になる。木、山、海、木片、小石、貝殻、植物たち、花、塩、ヤギ、オオカミ、象、ライオンの尾、動物の牙などなどだ。(2)フェティシュになった「もの」はどの地域でも他愛ないものだったが、集団の中で呪物あるいは物神として神聖視され、厳(いかめ)しくも恭(うやうや)しい格別の崇拝の対象になった。(3)そうした各地のフェティシュは必ずしも共通しない。多様である。即時的なものもあり、公時的なものもあった。おそらくフェティシュは公的なものと個的なものが二重に認知されていったのだろうと思われる。(4)フェティシュはその地の集団に禁忌(タブー)の体系をもたらした。アフリカのグリグリ(魔除け)に代表されるのは、崇拝と禁忌の両方の作用である。(5)このような作用は、日月や星に対する畏怖と本質的に変わらないが、各地に生ずるフェティシュの雑多性がその後の信仰と宗教の独特の多様性をつくっていった。
こういう説明をするにあたって、ド・ブロスはエジプトなどの古代信仰の形態やギリシア神話に出入りする「もの」たちが「物神化」されていることに気がついたのである。神がそういうものを選んだのではなく、人々の生活の中でおこる「もの」への執着が、神々に託された出来事の物語性を生んだのだろうことにも気がついた。
アフリカの土俗も調べたド・ブロスは「崇拝されるもの」が必ずしも「神の象徴」ではないことを重視した。石ころでも根っこでも崇拝された。それらはのちに「神の代理物」に昇格することがあったとしても、当初はフェティシュとしてのみ認知されたものだったとみなした。フェティシュ(物神崇拝)は宗教的な偶像崇拝(Idolâtrie)より早かったというのだ。
ド・ブロスはこれらの発想を独自に得たのだろうか。実は同時代のデイヴィッド・ヒュームの人間本性論との共鳴関係をもっていた。

エジプト神話では、ホルス神の左目を「ウアジェトの目」という。全てを見通す知恵や癒し・修復・再生のシンボル。ホルス神が癒された目を父オシリス神に捧げたというエピソードから、供物の象徴ともされ、ミイラに添えられることもある。ツタンカーメンの「ウジャトの目の胸飾り」が有名。
ヒュームはエディンバラ大学にいるころから、すべての知識が知覚(perception)との関連でできあがっていて、そこに印象(impression)と観念(idea)がつくりあげられるのだろうという見当をつけていた。
そうした見方を総合的に組み立てて、大著『人間本性論』(全3冊・法政大学出版局)を出版したのは1739~40年である。執筆はその前に訪れていたパリやランスで始めていた。ただこの大著は懐疑論や無神論に傾いたものだと解釈され、エディンバラ大学の教授への道をとざすものになった。
そこでヒュームは1757年にあらためて『宗教の自然史』(「ヒューム宗教論集」1・法政大学出版局)を書いて、フェティシュという用語こそ使わなかったものの、自然宗教の発生が教祖的ではなく多神的であり、さまざまな自然物の崇拝からおこっているだろうことを推理して、原始古代人たちの日々の「驚き」や「不安」や「好奇心」がその後の信仰の重要なトリガーになっていたことをあえて強調した。
おそらくド・ブロスはこうしたヒュームの論考をリアルタイムに読んでいただけでなく、フランスに来た本人とも出会っていたのではないかと思われる。本書の訳者の杉本隆司や、ポール=ロラン・アスンの『フェティシズム』(文庫クセジュ)は、ド・ブロスは実際にもヒュームやディドロとフェティシュをめぐる議論をしたのではないか、往復書簡を交わしていたのではないか、のみならずアダム・スミスもフェティシュという見方に惹かれたのではないかと憶測している。
そうだとすると、ド・ブロスの着目はその当初からヒューム的な広がりやアダム・スミスの市場的な物品交換幻想についての構想を秘めていたということになる。このことはのちのフェティシズムをめぐる思想を豊饒にした。

イギリス古典派経済学の創始者。資本主義の古典とされる『諸国民の富(国富論)』を著した「経済学の父」。富の源泉を労働に求めるとともに、「見えざる手」による予定調和を唱え、重商主義・重農主義を批判した。
ド・ブロスのフェティシュ(物神)についての見方は人間と社会の内奥にひそむであろう「フェティシズム」(fetishism)の分析理論として、しだいに伝播していった。
カントは『たんなる理性の限界内の宗教』でフェティシュを採り上げて、フェティシュには神に嘉(よみ)するような道徳性がないにもかかわらず、それにまつわる妄想のすべてを付随させるものだとみなしてその異能性に驚き、ヘーゲル(1708夜)はアフリカの宗教に言及した『歴史哲学講義』で、従来の宗教解釈では説明できなかった現象が、フェティシュという魔術的心性によって解読できる可能性をもつことにふれた。
社会学の基礎をスタートさせたオーギュスト・コント(1798~1857)も『実証哲学講義』に、フェティシズムは滑稽で哀れな現象だとしながらも、ひょっとするとしっかりとした神学的な発想の初期段階をあらわしているのかもしれないと述べた。
フェティシズムが「アニミズム」の形態のひとつだと見たのは、エドワード・タイラー(1832~1917)の『原始文化』(上下・国書刊行会)だ。
タイラーは原始文化がアニミズム(魂の発露がとった原始信仰)によって成立しているとみなして民族学を立ちあげたのだが、フェティシズムがその一角を占めていたことを認めた。タイラーはフェティシズムを「木や石の魂に関する信仰」だろうと捉えて、こう書いている。
「アニミズムという用語は、人間精神の教義一般をあらわすのに用いられるのがいいだろう。フェティシズムという用語は、この偉大な教義のなかでも、何らかの対象に神々が具象化されている信仰、対象に結びついている神々がその対象を介して作用する場合に、限定して用いたほうがいいと思われる」。
一方 宗教的感情の起源をヒンドゥイズムの研究によってアプローチしていたマックス・ミュラー(1823~1900)は、フェティシズムは原始宗教の形態としては認められないとして、フェティシズムを人間精神としては格下の信仰であると規定した。しかし『金枝篇』のジェームズ・フレイザー(1854~1941)は、その格下の物神力こそが格上の上位社会の「力の交代」を動かしたのだと説いた。
これらはド・ブロスの見方に準じて原初の習慣と信仰をめぐるものだったのだが、フェティシズムが産業革命以降の近代社会の人間の問題の根底につながっているとみなした思想者が、やがて登場した。マルクスとフロイトである。

近代ドイツ最大の哲学者として、ドイツ観念論を集大成した。フランス革命への共感にもとづいて、自由主義的な神学観を抱き、聖職に就くことを断念した。哲学者となってベルリン大学教授として生涯を終える。
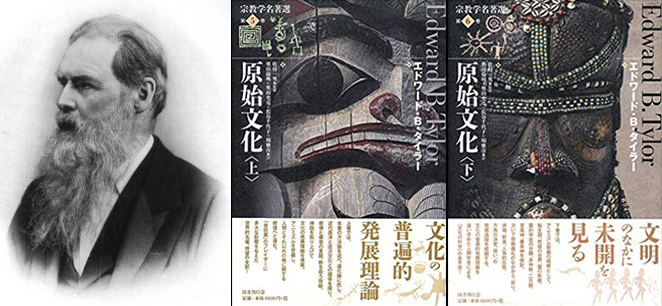
文化人類学の父と呼ばれ、1861年、結核の転地療養のためのアメリカ、キューバ旅行の体験に基づいた「アナウァク」を発表。1871年に「原始文化」を発表し、文化の概念を初めて明らかにするとともに、文化に関する科学的研究の基礎を築き、一躍彼の名を高めた。元オックスフォード大学教授。

ドイツに生まれ、イギリスに帰化したインド学者(サンスクリット文献学者)、東洋学者、比較言語学者、比較宗教学者、仏教学者。イギリス首相を4度務めたウィリアム・グラッドストンとは親友であり、ヴィクトリア女王とも親交があった。
物神としてのフェティシズムを近代産業社会にもあてはまるものとして最初に深く捉えたのは、カール・マルクスの『資本論』だった。第1巻第1章第4節の「商品の物神的性格とその秘密」に明示されている。
マルクスは1842年にド・ブロスの『フェティシュ諸神の崇拝』ドイツ語訳を読んで、ライン新聞に物神的人類学をヒントにした経済学的な論考を書くようになっていた。マルクスはたんに森にはえている樹木が材木となって取引され、木製商品になって価格競争を生んでいく理由を考えた。
なぜ木は材木となり、材木は商品になって売り買いされるのか。商品になると、なぜ貨幣による売買が可能になるのか。そこには労働という作業が関与したはずだが、その労働の価値はどこに転じていったのか。マルクスはこのことを究極的に考えぬくにはド・ブロスの物神崇拝(Fetischismus)という見方が有効だと合点した。
こうして「商品の物神的性格」が『資本論』冒頭の有名な分析に浮上することになった。マルクスは「もの」が商品という物神性をもったことだけを説明したのではなかった。「もの」が商品という物神性を得たぶん、労働をする人間が疎外されて物象化(独Versachlichung 英reification)を余儀なくされていること、貨幣も物神化されていることを痛烈に告示した。
マルクスの経済学は商品にひそむフェティシュへの着目で仕上がっていったのである。こうした「もの」によって全社会史のプロセスを解明する立場は「唯物史観」と呼ばれた。まさしくモノ史観というものだ。
『資本論』第1章第4節には、こう書かれている。「人間の頭脳の産物は、それ自身の生命を与えられて、相互に関係し、また人間とも関係する自立的な姿をそなえているかのように見える。商品世界では人間の手の産物がそれと同じふるまいをする。私はこれをフェティシズム(物神崇拝)と名付ける。フェティシズムは、労働生産物が商品として生産されるとたちまち生産物に貼りつき、商品生産から分離できなくなる。商品世界のこのような物神的性格は(‥)商品を生産する労働がもつ独特の社会的性格から生じるものである」。
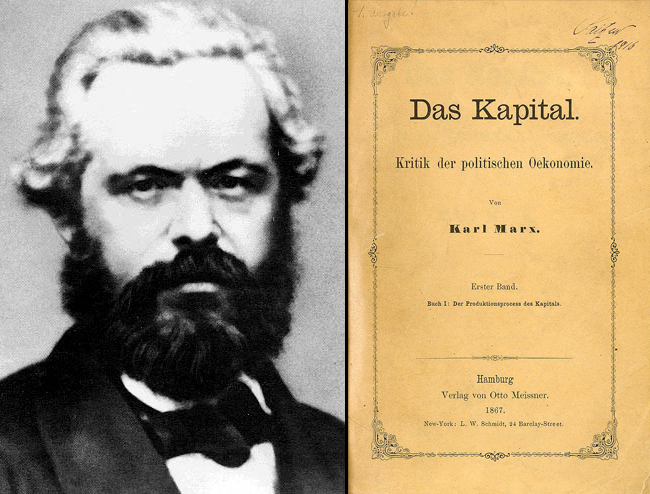
ヘーゲル左派として出発し、エンゲルスとともにドイツ古典哲学を批判的に摂取して弁証法的唯物論、史的唯物論の理論に到達した。これをもとに、イギリス古典経済学およびフランス社会主義の科学的、革命的伝統を継承して科学的社会主義を完成。共産主義者同盟にも参加し、のち第一インターナショナルを創立した。
マルクスが「商品」や「貨幣」にフェティシュの動向を発見したのに対して、アルフレッド・ビネ、クラフト=エビング、ハヴロック・エリス、そしてフロイトは「心」の奥の「性」の動向にフェティシュを発見した。
ビネはソルボンヌ大学でフランス最初の実験心理学をおこした生理心理学研究者で、アソシアシオニスム(連想連合主義)を提唱した。心的現象を観念の連合によって説明しようとするものだ。そのビネが1887年にフェティシュが性科学の分析に有効であることを提唱した。愛が倒錯するとき、そこにフェティシュが認められるとした。
続いてクラフト=エビングが『性の精神病理』(Psychopathia Sexualis)を書いて、サディズムやマゾヒズムでもなく、露出狂でもないものとしてフェティシズムをとりあげた。胸・鼻・手・おさげ・足首などの体の一部、ハンカチ・靴・ナイトキャップ・下着などの衣類や布地などに執着する、一見風変わりな心理傾向が、精神病理としてのセクシュアル・フェティシズムと認定されたのだ。
ハヴロック・エリスはそれらには「フェティシュとしての象徴的記号性」があると見た。
こうしてフロイトがこれらを承けて、『性欲論三編』『フェティシズム』『トーテムとタブー』『文化への不満』などの論文著作で、次々にフェティシュによる精神分析を全面展開していったわけである。もっぱらリビドー(libido 性衝動)の欲動力学にもとづいたもので、「性の倒錯によるフェティシュ」「ファルス(男性器)を愛着するフェティシュ」「愛好物に惹かれるフェティシュ」などを、実際の症例に言及しつつ解いてみせた。
その仮説的分析がもつ説得力は、いささか強引なところがあったにもかかわらず、たちまち心理学界から文学界や思想界に及んでいった。
マルクスの社会分析にはまだド・ブロスがちゃんといたが、フロイトの精神分析にはもうド・ブロスはいない。フロイトは大半のフェティシュ(物神)をファルス(phallus)の代理物や代替物とみなしたのだ。そこに一人の体と心がありさえすれば、フロイトのフェティシズム論は成り立った。
フロイトは、今日俗にいう足フェチや下着フェチに類する「フェチ」の症例ばかりを列挙した。そのフェチがことごとく性的な歪みにもとづいているというフロイトの結論は、かなり偏った見方であった。なにもかものフェティシュが男のペニスに結びついているとはとうてい考えにくい。
考えにくいのではあるが、しかし、フロイトのフェティシズム論は文化人類学がとりあげる去勢の問題や成人規定の問題、精神医学(心理学)がとりあげるエディプス・コンプレックスの問題や自我分裂の問題を説明するのに、意外な効力を発揮することになった。20世紀の物神文化論はマルクスとフロイトにどっぷり依拠したのだった。
フロイトのフェティシズム論は女性にも転用された。女性の下着フェチは「男性から見られることをとりこんだフェティシュ」だとみなされ、自分の子を可愛がりながら支配するファリック・マザーはわが子をフェティシュにしているとみなされたのだ。
フェティシズムと社会文化をつなげる考え方は次々にあらわれた。エミール・デュルケーム(1858~1917)は『宗教生活の基本形態』や『自殺論』で、フェティシズムはもはや宗教の起源にまつわっているというより、集団のトーテムを個人が獲得するときの物神性の出現ではないかと推測した。集団社会に埋没したり見逃されがちになる個人がトーテムをもとうとするとき、フェティシュが必要になるのだろうと見たのである。
マルクスとフロイト以降、近現代社会におけるフェティシュがどんな意味と役割をもっているのかをめぐっては、きわめて多彩な議論が交わされてきた。現代思想を十把一からげにいえば、ほぼフェチをめぐる議論だったというほどだ。
代表的な例を紹介する。ベンヤミン(908夜)は、グランヴィルらの幻想的なアート作品をとりあげつつ、「無機物的なものにセクシャリテイを感じるフェティシズムこそがモードの生命の核である。商品崇拝はフェティシズムをみずから使うことによって成立する」と述べた。モードとフェティシズムを結びつけた最初の議論だった。テキストそのものにフェティシュな快楽を忍びこませるのが好きなロラン・バルト(714夜)は『モードの体系』では明るいフェティシズムをモードのコノテーションから導き出した。
ボードリヤール(639夜)のシミュラークルの議論は、そのほとんどが商品の物神性に着目していた。『物の体系』(法政大学出版局)はまるまる一冊が物神交換論であり、『象徴交換と死』(ちくま学芸文庫)はまるまる一冊を通して、本来は可逆的な象徴価値の贈与的な交換が、資本主義社会においてはフェティシュなほうへ向かって価値を堆積していく謎を解こうとしたものだ。

ドイツの思想家・評論家。ユダヤ神秘思想とマルクス主義とを背景とする思想を展開し、神秘的洞察力に満ちた多くのエッセーを書いた。1933年、ナチスに追われフランスに亡命。ピレネー山中で自殺した。

フランスの批評家、記号学者。歴史家にとどまらないミシュレの活動に着目した『ミシュレ』、『作者の死』の一編を収めた『物語の構造分析』、フランスのさまざまな文化・慣習を分析した『神話作用』、バルザックの中編を過剰に詳細に分析した『S/Z』を著した。
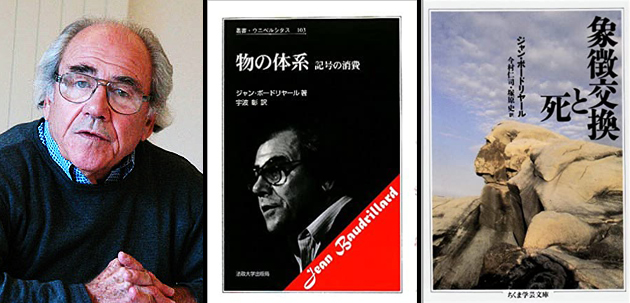
フランス生まれ。ジャーナリストからパリ大学ナンテール校教授.社会学記号論専攻を経て、思想家活動に至る。経済学およびマルクス経済学を継承批判、これを超えようとする試みを展開する。とくに記号消費をめぐる考察は有名で、現代消費社会の特質を考える上で重要とされている。
言語のフェティシュをとりあげた思想者はめちゃくちゃ多い。なかでミハイル・バフチンは言語はその内側にフェティシュなカーニバル性をもっていて、カニバリズム(食人行為)がそうであるように、われわれは自分たちと同類の肉身を食べるために言語をつかっているのかもしれないとみなした。
大胆な見方のようだが、そうでもない。たとえばジャック・ラカン(911夜)は言語体系(ランガージュ)そのものがフェティシュでできているとさえ見ていた。そうだとすると、われわれが言葉をつかっている以上、人間はいつだってフェティシュの体系のどこかを追走しているということになる。ジュリア・クリステヴァ(1028夜)は、だからわれわれは言語から脱走できっこないと言った。
言語が物神性をもっていて、貨幣と商品が社会の物神に陥っているなら、文明や文化の変遷はフェティシュの変遷だったというふうにも言える。ソシュール言語学を研究した丸山圭三郎は『文化のフェティシズム』(勁草書房)、『フェティシズムと快楽』(紀伊国屋書店)を書き、フェティシュがわれわれの無意識に巣くっているのではないかと説いた。だからこそ、われわれはフェチな夢を見ているのかもしれない。

ロシアの文芸学者。ポリフォニー論の提唱者として知られる。バフチンは、ドストエフスキーの小説が作者が登場人物を意のままに操る既存のヨーロッパ小説とは対照的に、登場人物たちのイデオロギーや階層の差異を前提としつつ、融合しない複数の声や意識が織りなす対話的関係によって高度な統一を実現していると指摘し、「ポリフォニー小説」「カーニバル文学」と定義づけた。

フランスの構造主義、ポスト構造主義思想に影響力を持った精神分析家として知られる。フロイトの精神分析学を構造主義的に発展させたパリ・フロイト派のリーダー役を荷い、「フロイトに還れ」と主張。ドゥルーズ&ガタリらポストモダンの哲学者から、理論も振舞いも父権的であるとして、痛烈な批判を受けた。

ブルガリア生まれ。1966年、なかば亡命のようなかたちでフランスに渡る。初期には雑誌『テル・ケル』を中心に活躍し、ロラン・バルト、フィリップ・ソレルスらとともに現代フランス思想の潮流をになう一人となる。哲学、言語学、精神分析を大胆に応用し、「文学の記号論」を根本的に革新する。
だいたいがこういう感じなのだが、フェティシュについてやや皮肉な見方をするのはスラヴォイ・ジジェク(654夜)だった。『ポストモダンの共産主義』(ちくま新書)の第6章は「二つのフェティシズムのはざまで」と題されている。
この二つとは「症候」(symptom)と「フェティシュ」(fetish)のことで、われわれが何かから抑圧されているとき、ひとつはなんらかの心理的身体的な症状が出るほうに傾き、もうひとつはなんらかのフェチに託すほうになるのだが、そこをどう見るかという議論になっている。ジジェクはフェチを生じさせるほうがずっと理性的で、抑圧からの脱出がはかれると見る。マルクスは貨幣に物神性を見いだしたが、社会の多くの人間が貨幣に引き込まれるのはそのフェティシュには心理的身体的症候からの脱出感があったからだった。
しかし、フェティシュな脱出にもいくつもの分岐がおとずれる。ジジェクはAの対策をポピュリズム的で原理主義的なフェティシュと呼び、Bを買い物主義と呼び、Cをシニカルなフェティシュと呼んだ。Aは成長神話に走る企業家やビジネスマンたち、Bはバーゲンセールやネットショッピングに興じる消費者、Cがリチャード・ローティ(1350夜)やイアン・ハッキング(1334夜)やフレドリック・ジェイムソンなどだ。ジジェクもCだと言いたいのである。
以上、ド・ブロスの画期的な切り込みに発したフェティシュ談義をざっとしてみたが、今夜はこのくらいにしておく。まだまだ紹介したい見方がいろいろあるけれど、それは別の千夜千冊でとりあげたい。
実は数年前から若い諸君に「フェチ」を白状してみないかと誘ってきたのだが、なかなか乗ってこないのだ。さもなくば上っすべりになる。なぜなのか、わからなかった。ぼくのジンセーのほとんどが「好奇心あるいはフェチの編集工学」の徹底だったので、できれば一緒にフェチ語りをすれば、もうすこしぼくの考え方と若い諸君の感じ方が交差できると思っていたのだが、なかなかそうならない。
照れくさいのかと思ったけれど、べつだんフロイトっぽい下着フェチや靴フェチを話題にしたいというのではない。好きなスタジャンや使い古した鞄でもいいし、デヴィッド・ボウイの服装をフェチしたというのでもいい。子供のころに何がとんでもなく好きだったのか、机の抽斗にこっそりしまっておいたものは何だったのか、友達が持っているもので羨ましかったのは何だったのか、そういうことを白状してほしかったのである。
青年時代、ぼくは古本屋に入ると、なぜか惹かれる本がおいでおいでと訴えてきた。お金がないので買えないのだが、何度もその本を手にとっては棚に戻し、また手にとってはフェチした。ぼくの読書はフェチ読書なのである。
こういうことはいくらでもあるはずだ。フェチを封印したままでは、編集はダイナミックに開展しない。意識にも、無意識にも届かない。ときにわれわれはいったんド・ブロスの物神に戻るべきなのである。そうしたほうが信仰や思想や仕事も動きだす。

書物フェチの松岡は、とくに小口にめっぽう弱い(上)。紙たちが断裁されて束ねられているのを見ているだけで、本を読んだ気になる。下は全集の函を猫たちが引っ掻いた跡。
撮影:小森康仁(編集工学研究所)

⊕『フェティシュ諸神の崇拝』⊕
∈ 著者:シャルル・ド・ブロス
∈ 訳者:杉本隆司
∈ 発行所:財団法人法政大学出版局
∈ 印刷:三和印刷
∈ 製本:鈴木製本所
∈ 発行:2008年11月1日
⊕ 目次情報 ⊕
∈ 第1部 黒人やその他野生民族に現存するフェティシズムとはどのようなものか
∈ 第2部 古代民族のフェティシズムを現代人のものと比較してみる
∈ 第3部 これまでフェティシズムの起源はどのように説明されてきたか
⊕ 著者略歴 ⊕
シャルル・ド・ブロス(Charles de Brosses)
1709年、ブルゴーニュの首府ディジョンに生まれる。コレージュでビュフォンと親交を結ぶ。1730年に高等法院評定官に任官。41年部長評定官(プレジダン)、75年院長。39年のイタリア旅行後、『イタリア便り』(1799)を執筆。ヴォルテールとの大喧嘩でアカデミー・フランセーズに2度落選。77年、パリで客死。
⊕ 訳者略歴 ⊕
杉本隆司(スギモト・タカシ)
1972年生まれ。明治大学政経学部卒。現在、明治大学政治経済学部専任講師。DEA(哲学、ナンシー第二大学)。博士(社会学、一橋大学)。著書に『社会統合と宗教的なもの』(共著、白水社)、『共和国か宗教か、それとも』(同)、訳書にマチエ『革命宗教の起源』(白水社)、コント・コレクション全二巻(同)、ド・ブロス『フェティシュ諸神の崇拝』(法政大学出版局、日仏社会学会奨励賞)他。