父の先見


インターシフト 2012
Guy Deutscher
Through the Language Glass 2010
編集:真柴隆弘 協力:矢沢聖子・千勝泰生・佐々木啓
装幀:織沢綾
ユダヤ人はこう言う。「この世界には使うに値する言葉が4つある。詩歌のためのギリシア語、戦いのためのラテン語、悲嘆のためのシリア語、日常会話のためのヘブライ語だ」。このことは『タルムード』に書いてある。
神聖ローマ皇帝カール5世は、こう言った。「神にはスペイン語、女にはイタリア語、男にはフランス語、そして馬にはドイツ語だ」。なんとも乱暴で横柄な言い草だが、スペイン王にしてオーストリア大公で、イタリア=ドイツ領土に君臨した神聖ローマ皇帝ならではのジョークだ。
日本人には、なかなかこういう危うい比較を先行させる歴史的人物がいない。新羅・高句麗・百済の三国人とわたりあい隋の皇帝に譲歩しなかった聖徳太子も、スペイン・ポルトガル・イタリアの宣教師の相手をしたはずの信長も、外国人の捕虜を審問していた新井白石も、日本語と朝鮮語と中国語とヨーロッパ語の特色を比較できたわけではないし、英仏の政商を天秤にかけてあしらった龍馬や日中を横断した宮崎滔天の三兄弟や、ユダヤ宗教やエスペラント語にも通じた大川周明が、日中韓の言語文化の気質を巧みに言い当てたなんてことは、聞いたことがない。
しかし実際には、日本人の多くは映画やテレビや街頭で朝鮮語と中国語を聞いて、自分たち日本人とは何かがかなり違っているだろうことを実感しているはずなのだ。実感してはいるけれど、では耳に騒ぐその言葉づかいから何かの文化的特質を言い当てられるかというと、そういうことはさっぱり苦手だ。そこは、ヨーロッパや西アジアの地続きの文化を長らく経験してきた言語文化知の歴戦の士たちのほうに、かなりの「歩」や「分」がある。けれども、かれらの「歩」や「分」が言語学的にいつも当たっているかというと、けっこうあやしい。
国民と言語については、昔から諸説紛々だ。フランシス・ベーコンは「民族や国民の特質はかれらが話す言葉から推論できる」と見ていたし、のちの言語学の基礎をつくったコンディヤックやヘルダーも「どんな言葉からもその民族や国民の知力と文化が窺い知れる」とみなしていたが、そういう観察がどこまで当たっているかは、とうてい証明しがたいことだった。
なぜなら、どの民族や部族も他の集団語にはない語彙や言葉づかいや言いまわしをもっていて、それを別の言語文化が理解できるかどうかということ自体が、けっこうきわどい問題であるからだ。ダンテは『俗語論』のなかでイタリア各地の言葉づかい(いわゆる方言)を比較して、「ローマ人の言葉は崩れきっていて下品なもので、そのことはかれらの醜いふるまいからも推してはかれる」といったことを書いていたけれど、この判定はかのダンテにしてあまりに狭隘だった。

或る民族言語に或る単語が欠けていることは、いくらでもあることだ。「パパイヤ」や「琥珀」や「図書館」や「娼婦」がその地になければそれに当たる言葉はその地になく、「南十字星」「トナカイ」「コンドル」「クリームソーダ」「携帯電話」を見たことがなければ、そんな言葉を思いつくことはない。日本語の「納豆」「十二単衣」「切腹」「コギャル」「ゆるキャラ」は他のどこの国語にも入っていない。
しかし、こういうことから何を導き出すかということは、なかなか厄介なのである。キケロはギリシア語にラテン語の「イネプトゥス」(無礼、ぶっきらぼう)に当たる単語がないことを知って、それは古代ギリシアに無礼な態度が蔓延しすぎていたからだと結論づけたのだが、これはムリがある。
どんな意味のどんな言葉がどこの国語にあるかどうかということは、その国語の自慢にはならない。ヴォルテールはフランス語は明快さと秩序力がとびぬけてすばらしいと自慢していたけれど、だからといって「フランス語はどこにもないほどの言語力に富んでいる」とは言えない。英語には「エスプリ」に当たる言葉はないが、フランス語には「エスクワイア」や「ジェントル」に当たる言葉はなかったのである。
逆に、アメリカ人が「ヒップ」や「クール」に特別な意味をもたせたからといって、その感覚を言い当てる言葉が他の民族文化や国民文化に育っていないことを、非難はできない。ぼくは「コギャル」という言葉はよくできていると思うけれど、これを「あはれ」と「あっぱれ」をフランス人の前で講演したように説明できるかというと、とても自信がない。「小さいギャル」だと説明しても、そんなチビ少女の何がおもしろいのか、フランス人は理解しない。
本書の著者のガイ・ドイッチャーはこの綴りの名前からは出自がはっきりしないのだが、職能者としてはケンブリッジ大学のれっきとした言語学者である。オランダのライデン大学で古代近東語を研究し、マンチェスター大学で言語文化の表象論をコーチして、ドイツ語圏を母語としながらもヨーロッパの各言語に通じたようだ。国籍はおそらくイギリスなのだろう。
そういう知的経歴のあるドイッチャーから、たとえば古代バビロニア人はドストエフスキーの『罪と罰』を読んだらしかめっ面になるだろうと言われると、なるほど、そうなんだろうなどと頷ける。バビロニア語では「罪」と「罰」とは1つの単語で言いあらわしているからだ。
外国人にとって、その土地の母国語(母語=マザリーズ)がどんな特徴をもっているかは、なかなかわからない。たとえばアジア人やスペイン人からはノルウェー語とスウェーデン語とオランダ語の区別はつきにくい。それは北欧人からはモンゴル語と中国語と朝鮮語と日本語の区別がつきにくいのと同じだし、タイ語・ビルマ語・インドネシア語の区別が西欧人や日本人につきにくいのと同じだ。
もっとも何かに慣れてくると、その区別が“耳の似顔絵”のようにわかる。ドイッチャーによると、ノルウェー語は切り立った岸壁のようで、スウェーデン語はどこまでもつづく平野のようであり、勤勉なプロテスタントである民衆がつくりあげたオランダ語は、海からの風がたくさんの子音を削ってしまったかのようであるらしい。われわれは中国語、韓国語、日本語の“似顔絵”をこんなふうに説述できるだろうか。
言葉には、気候風土や「なり」「ふり」にもとづくニュアンスや、伝達意志力がしからしめる言いまわしがある。そこには必ずやソージ(相似)とルイジ(類似)の特色がある。
ずっと前、タモリを伴ってイタリア大使公邸でのパーティに出たとき、タモリにイタリア映画の会話の真似や、中国人・イタリア人・ドイツ人・韓国人のマージャン議論のパロディを即興で演じてもらったことがある。そこにはレオ・レオーニや谷川俊太郎なども招かれていたのだが、イタリア大使のビアンケリもイタリア出身のレオーニも、タモリのいんちきイタリア語がそっくりだと言って大笑いしていた。
いまどき、こんな余興はできないだろうというような、懐かしいエピソードだが、こんなふうに「言葉の特色」は「聞き耳」のなかでソージやルイジが大いに強調されたり歪曲されたりするものなのだ。けれどもその違いが感じられるからといって、その言葉の意味が理解できることは、ほとんどない。同じ日本語でも津軽弁と茨城弁と名古屋弁の意味がとれないことは、しょっちゅうだ。

ドイッチャーが本書で主張したことは、言語はすべて相対的にしか理解できないということである。わざわざその程度のことを主張したのかと思うかもしれないが、言語学の歴史ではこのことを実証的に主張するのは案外に大変なことだった。
なぜなら言語学の仮説には長らく「言語起源論」というものが君臨していて、レオン・ポリアコフが『アーリア神話』で暴いたと同様の「言語単一起源説」がずっとはびこってきたからだ。その神話を破るのが大変だったのだ。しかし言語の起源なんて、もとより一つじゃなかったのである。民族や部族の言語はその数がわからないほどに複数発生的で、かつ複合発生的だった。
キリスト教言語圏からすれば、オリゲネスやアウグスティヌスやセビリアの司教イシドールスが主張したように、ヘブライ語がただ一つの起源言語で、上代のあるときに「バベルの塔」が崩壊し人々が四散して、世界各地にさまざまな言葉がばらまかれたというふうになるけれど、決してそんなふうにはならなかったのだ。一部の「アダムの言語」がそうなっただけだ。

いやいや、バベル神話だけではなかった。なんらかの普遍言語や世界言語のようなものが、歴史の起源のどこかにあったはずだという逞しい想像は、なかなか潰えなかったのである。
たとえば、ジョン・ウィルキンズの『マーキュリー、あるいは秘密にして迅速なる使者』(1641)、サイモン・ベリントンの『モザイク状の世界創造、大洪水、バベルの塔建設、そして言語の混乱に関する私論』(1750)、ジェームズ・ハリスの『ヘルメス、あるいは普遍文法についての哲学的探求』(1751)といった謎のような本が次々に登場して、どこかに起源言語があるという万余の想像力をかきたてたのだった。
そうしたなか、言語文化を洞察したコンディヤック、モーペルテュイ、ルソーをへて、本書も注目したヴィルヘルム・フォン・フンボルトが議論を深めていくようになると、やっとインド=ヨーロッパ語族の全貌や言語系統樹の青写真が見えてきて(これもあくまでヨーロッパ語からの比較推論だったが)、そこからソシュールの『インド=ヨーロッパ諸語における母音の原初体系に関する覚書』(一八七八)のような、今日の言語学の基盤が用意されるようになったのだった。
しかし、それでも、まだ言語には「共通する普遍性」があるという見方は強い仮説力をもっていた。その代表的な仮説がノーム・チョムスキーの生成文法論という言語理論である。
チョムスキーは、すべての言語がその深いところで普遍文法と基本的概念とを共通させていて、それゆえ体系としての複雑さがどんな言語にもあらわれたのだと見て、譲らなかった。人類の心身に言葉の原型がひそんでいたというのだ。ただし、その延長の研究に勤しんだスティーブン・ピンカーの『言語を生みだす本能』(NHK出版)などをもってしても、このことはいまだに実証されてはいない。
まあ、言語学史の話は本書の主題ではないので、今夜は追いかけないことにするが、ガイ・ドイッチャーの言語相対説はどこから来たかといえば、エドワード・サピアとベンジャミン・ウォーフの仮説にもとづいたのである(言語学ではサピア=ウォーフ仮説とよばれる)。それが蓋然性に一番富む言語理論であるかどうかは、まだはっきりしない。

ところで本書の後半には、今日の言語社会が乗り上げつつある暗礁についての議論が展開されている。それは「なぜ言葉は差別感をもつのか」ということだ。とくにジェンダー語の事情に分け入った。少し、とりあげておく。
日本には新聞禁止用語や放送禁止用語がある。ここで例を出すこと自体が憚られるほどなので例を書きづらいのだが、たとえばわかりやすいところでも「おまわり」「運ちゃん」「お給仕」「芸人」「百姓」「人夫」「線路工夫」「郵便屋」「興信所」「名門校」「未亡人」は自粛されている。ぼくはいつのまにか「婦人」という言葉が差別語扱いされるようになっていて、びっくりしたこともある。「婦人科」はともかく、「婦人警官」とか「看護婦さん」と言えなくなっただけでなく、明治以来の「婦人社会運動」も語りにくくなってしまった。
ぼくにはいまもって何がどう差別されているのか、そのリクツがよくわからないままなのだけれど、「婦人」や「OL」がダメで、「オヤジ」「おっさん」「女」「ガキ」はいいらしいと聞くと(いずれもテレビ番組のタイトルにも使われる)、いささか困惑させられる。
こうした風潮はアメリカのPC運動から広がった。PCとは「ポリティカル・コレクトネス」(political correctness)によってコミュニケーション用法を制御しようという運動のことで、初期には人種差別(アパルトヘイトなど)からの脱却をめざして大きな成果をあげたのだが、それが差別用語の粛正やジェンダー語にまで広がって、いつのまにか「言葉狩り」にもなった。けれどもジェンダー語によって差別の度合いをはかるのは、歴史的にはかなり乱暴なことなのである。
だいたい「ジェンダー」(gender)という言葉は、もともとは「タイプ」「種類」「種」のことだ。genus(種類)や genre(ジャンル)と同じ語源なのだ。古代ギリシアの哲人たちが「ゲノス」(種族・類型)の基準を、①男性=人間・動物、②女性、③無生物という三つに分けたのが、ジェンダーの始まりだった。
このジェンダーが各地で別々の分類価値観で使われるようになったのである。アフリカのマリ地方のスピレ語には「人間、大きなもの、小さなもの、集合体、液体」という5つのジェンダーがあり、スワヒリ語には10のジェンダーがある。オーストラリアのガンギテメリ語にいたっては「男、女、犬、犬以外の動物、植物、飲みもの、槍のあれこれ」など、15のジェンダーを数えた。
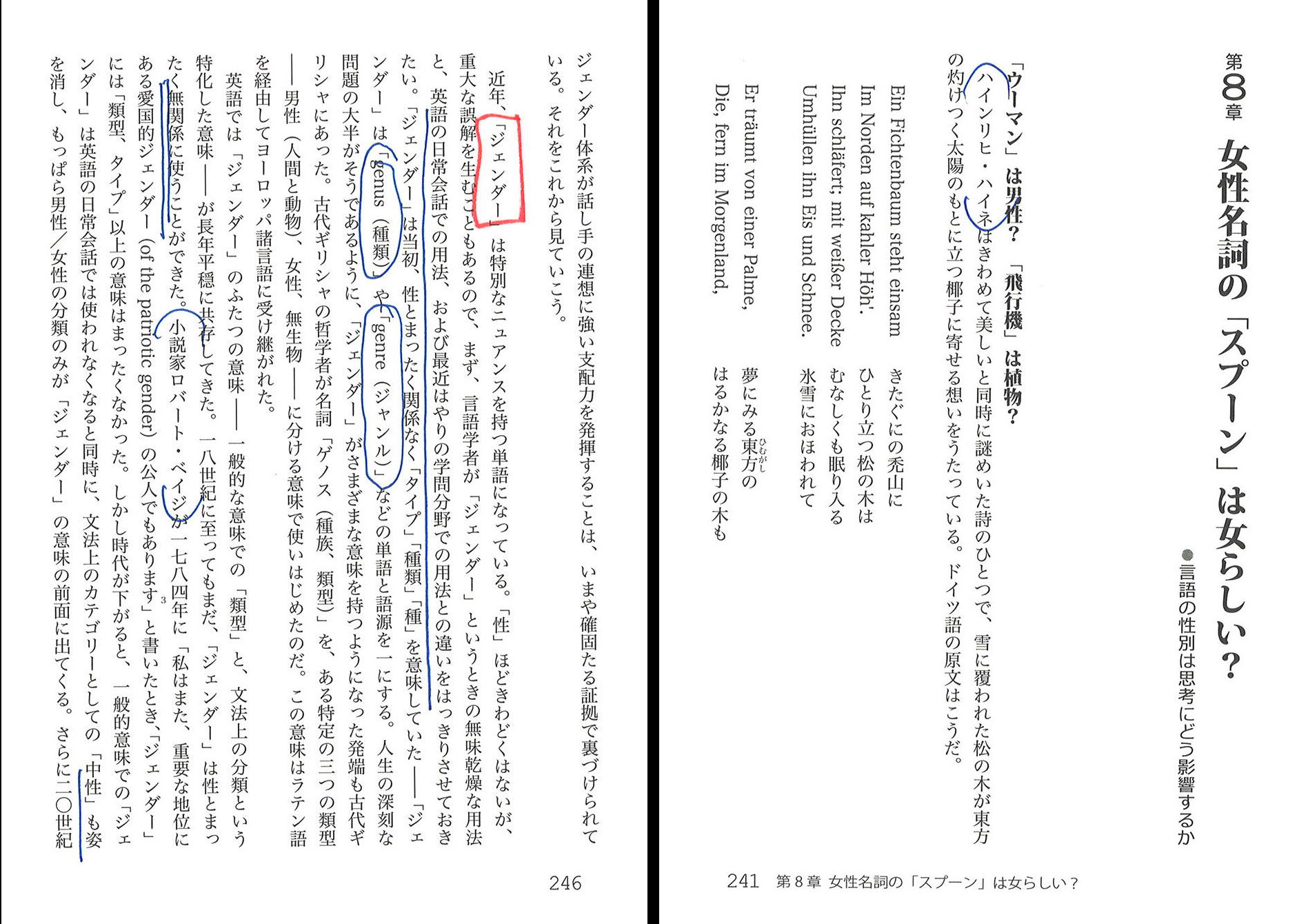
民族や国語や方言によっては、男性名詞と女性名詞の使い方もまちまちである。男性名詞や女性名詞や中性名詞が生ずることを、言語学では「文法的ジェンダー」とか「性文法」というのだが、その分類は各国語・各民族の歴史や習俗やマナーによってかなりの違いが出る。
たとえば、ロシア語では「雑誌」が男性名詞で、「新聞」が女性名詞、「家」が男性名詞で「学校」が女性名詞になる。「紅茶」が男、「水」が女、「ワイン」は中性名詞なのだ。この感覚はよほどロシア語やスラブ文化に詳しくないとわからない。
パプアニューギニアの各言語では、おおむね「大きくて長いもの」が男性で、「小さくてまるいもの」が女性とみなされる。これはなんとなく納得できそうであるけれど、ジェンダーがまったく逆になることもある。ドイツ語ではスプーンが男性、フォークが女性、ナイフが中性なのに、スペイン語ではフォークが男性で、スプーンが女性名詞になる(フランス語はフォークが女性名詞)。統一ルールなんて、あるわけがない。
おまけにトルコ語、フィンランド語、エストニア語、ハンガリー語、インドネシア語、ベトナム語、日本語には、そもそもジェンダー名詞の区別がほとんどない(日本語は一人称を「俺」や「あたし」に変化させる)。その理由も研究できていない。けれどもそこにジェンダー語が割り込んだ。しかも「ジェンダー」という言葉が「性」(sex)の婉曲表現となったのはやっと20世紀になってからのことで、性別や性差別の意味として使われるようになったのは20世紀半ばからのことなのである。
ドイッチャーはこうしたジェンダー語があらわす意味の違いは、各民族の言葉が「青」や「緑」などの色について、どの色をどのように呼んできたかということにも似て、一概には確定できないはずだと主張する。
最近はジェンダー・マーカーについてもいろいろ喧しくなっている。ジェンダー・マーカーは、接尾辞や接頭語の変化でジェンダーを示す言葉上の形態素のことをいう。
ところが、これもまちまちなのである。「男らしさ」や「女らしさ」ははっきりしない。デンマーク語では dag(日)と hus(家)は名詞としてはジェンダーをもたないのに、冠詞をつけるとジェンダー・マーカーが作動する。それにもかかわらず、ジェンダー・マーカーはしだいに肩で風を切るようになった。トルコ語から日本語まで、ジェンダー名詞の区別がほとんどない国でも、どんな言葉づかいが女性蔑視になるのかだけはどんどんリストアップされているのだ。
英語が“he”や“she”などの代名詞にしかジェンダーをあらわさないのはよく知られている。それなのに(いや、そうであろうから)、そういう英語圏のアメリカからこそ性差別をする言葉に対してのポリティカル・コレクトな「言葉狩り」が始まったのだった。けれども、自分たちの国語はジェンダー区別をしない言葉になっているからといって、他の言語にも性差別をしないように奨めるのは、無理強いに近いものだった。
かくて本書は、各国語がどのように色彩語やジェンダー語を決めてきたかという研究を通して、そもそも言語は文化背景によって異なる複雑性に達するものであって、その点からするとどんな言語も相対的であるということを主張した。
しかし、以上のことは、言葉の秘密のまだまだごく一部の問題だった。ぼくが思うに、言葉は「漬物」のようなところがある。糠床と塩加減と食べ方の関係を問題にしなければ、柴漬けも千枚漬けも野沢菜も、ない。言語の糠床はまだまだ探求しきれていない。

⊕ 言語が違えば、世界も違って見えるわけ ⊕
∈ 著者:ガイ・ドイッチャー
∈ 訳者:椋田直子
∈ 装丁:織沢綾
∈ カバー・扉・表紙:人物シルエット shutterstock.com
∈ 発行者:宮野尾充晴
∈ 発行所:インターシフト
∈ 発売:合同出版
∈ 印刷・製本:シナノ印刷
∈∈ 発行:2012年12月5日
⊕ 目次情報 ⊕
∈∈ プロローグ 言語と文化、思考
∈ 第Ⅰ部 言語は鏡
∈ 第1章 虹の名前
ホメロスの描く空が青くないわけ
∈ 第2章 真っ赤なニシンを追いかけて
自然と文化の戦い
∈ 第3章 異境に住む未開の人々
未開社会の色の認知からわかること
∈ 第4章 われらの事どもをわれらよりまえに語った者
なぜ「黒・白、赤…」の順に色名が生まれるのか
∈ 第5章 プラトンとマケドニアの豚飼い
単純な社会ほど複雑な語構造を持つ
∈ 第Ⅱ部 言語はレンズ
∈ 第6章 ウォーフからヤーコブソンへ
言語の限界は世界の限界か
∈ 第7章 日が東から昇らないところ
前後左右ではなく東西南北で伝えるひとびとの心
∈ 第8章 女性名詞の「スプーン」は女らしい?
言語の性別は思考にどう影響するか
∈ 第9章 ロシア語の青
言語が変われば、見る空の色も変わるわけ
∈ エピローグ われらが無知を許したまえ
∈ 謝辞
∈ 原注
∈ 参考文献
∈ 補遺
∈∈ 解説
⊕ 著者略歴 ⊕
ガイ・ドイッチャー(Guy Deutscher)
言語学者。ケンブリッジ大学(セント・ジョンズ・カレッジ)の特別研究員、ライデン大学の古代近東言語学科の教授を経て、マンチェスター大学の言語・言語学・文化学部の主任研究員。本書を含め、3冊の著作がある。本書は、多数の年間ベストブックを獲得している(エコノミスト誌、フィナンシャルタイムズ誌、ライブラリージャーナル誌:いずれも2010年度)。英国ロイヤルソサエティによる年間ベスト科学本・最終選考賞(2011年度)、ニューヨーク・タイムズ紙のエディターズ・チョイスも獲得。