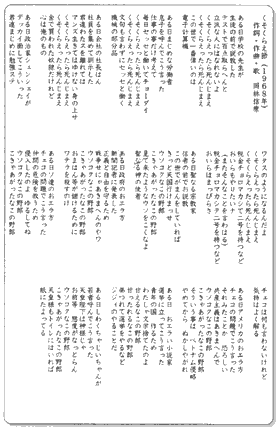父の先見


光文社 2003
美輪明宏さんに「長いあいだ、『ヨイトマケの唄』が流れなかったでしょう。どうしてですか」と聞いたことがある。美輪さんが吐き捨てるように言った、「あれね、ほんとにバカな話なのよ。“土方”っていう言葉がダメだっていうのね」。土方が差別用語だというのだ。「聞こえてくるよ、あの唄が、働く土方のあの声が、貧しい土方のあの声が」という箇所だ。
早川義夫のジャックスの名曲『からっぽの世界』も、突然、レコードからもラジオからも姿を消した。「ぼく 唖になっちゃった」の「唖」が差別用語だという理由である。フォーク・クルセダーズの『イムジン河』は南よりの歌詞だというので、朝鮮総連からの抗議があって自粛された。『イムジン河』が復活したのはごく最近のことである。
実はぼくが作詞して、小室等が作曲してくれた『Zの挽歌』も受難した。「きのう 佐世保の商店街で 催涙弾を投げられた べつに日本が嫌いじゃないけれど あすの ゲバルト やれはせぬ」という1番の歌詞だが、ラジオで小室が歌ったところ、そこがカットされた(3番か5番まで作ったが、いま思い出せないでいる)。翌日、電話がかかってきて「松岡さん、あれ、放送禁止ですって」と小室が言った。やっぱり、そういうことがあるのかと思った。1969年だったか。
本書はよく書けている。構成もうまい。テレビのディレクター出身だけあって、カットも編集もズームも効いている。しかし、ここまで読ませたのはやはりテーマがよかった。
放送禁止歌の謎を追求してドキュメンタリー番組をつくろうとしている著者が、その紆余曲折の経緯を再現しながら、いったい放送禁止歌って何なんだという“事実”に迫ろうとしているのだが、しだいにあきらかになる放送禁止歌をめぐる事情に、著者自身が呆然としていく姿が如実に伝わってきた。
このドキュメンタリーは2年前にフジテレビの深夜に放映され、ぼくも偶然に見た。ただし見たのはその後半だけで、エンディングに岡林信康の超A級放送禁止フォーク『手紙』が流れた。「わたしの好きなみつるさんは おじいさんからお店をもらい 二人一緒に暮らすんだと うれしそうに話してたけど 私といっしょになるのだったら お店をゆずらないと言われたの」で始まる。黒画面にタイムコードだけが動いていた。
3番になって「もしも差別がなかったら 好きな人とお店が持てた 部落に生まれたそのことの どこが悪い なにがちがう 暗い手紙になりました‥‥」というふうに進む。名曲である。本書によると、著者はこれを3分にわたって何もない黒画面だけで流すつもりだったらしい。それをタイムコードを入れたのは局側の注文だったようだ。
本書にはぼくが知らなかったこともたくさん書いてある。目からウロコが落ちることも多かった。それにしても、このテレビ企画はよく通った。
だいたい放送禁止歌があることは誰もがうすうす知っているはずだが、それがどこでどのように“禁止”されたかなどということは、誰も知ってはいない。それを取材してドキュメンタリーにすること自体がタブーを犯すことになるのだから、どだいこの企画は無理なはずなのである。
ところが本書がしだいにあきらかにするように、放送禁止歌というものは「幻想」だったのである。「実在」しないのだ。そのような事情があったからこそ、このドキュメンタリーは成立し、本書が読ませるものになった。しかし「実在」しないなら、どこで放送禁止歌はつくられたのか。
放送禁止歌になった“理由”にはいろいろのものがあるのだろうと“憶測”できる。
高田渡の『自衛隊に入ろう』は自衛隊からは使いたいと申し入れがあったらしいのに、各局が自粛した。高田は自衛隊をからかったのに、これは二重の過誤がおこったのである。同じ高田に『スキンシップ・ブルース』がある。「いつものように いつもの夜に 頭に帽子をかぶせてしまいましょ 僕と君との岡本利研ゴム」という1番だが、いまならエイズ対策で奨励されそうな歌も、固有名詞が入っていては無理がある。
なぎら健壱の『悲惨な戦い』は、巨漢の雷電と地獄の料理人若秩父が相撲をとっていると、マワシがほどけたという歌で、「さすが天下のNHK すぐにカメラを消せと命じたが 折も悪くもアルバイトを使っていたために アップで放映してしまったのだ」、「さすが天下の国技館 すぐに照明を消せと命じたが 折も悪くもパートタイムを使っていたために スポットライトをあててしまったのだ」とえんえん続く。これも“理由”はわかる。
山平和彦は白井道夫作詞によるその名も『放送禁止歌』をつくって放送禁止になった。「世界平和支離滅裂 人命尊重有名無実 定年退職茫然自失 職業軍人時節到来‥」というふうに、これも四字熟語がえんえん続き、「奇妙奇天烈 摩訶不思議」のフォーク囃しが何度か入る。
こういうものは気にすれば気になるだろうが、ジョークソングやプロテストソングとしてはそれほど“罪”があるとは思えない。まあ、気の小さな放送局が自粛したのであろう。けれども『ヨイトマケの唄』や『からっぽの世界』は差別用語が一カ所入っているだけで、禁止になった。やはり高田渡の『生活の柄』は沖縄詩人の山之内獏の有名な詩をフォークにしたものだが、「秋は 秋からは 浮浪者のままでは眠れない」の「浮浪者」がひっかかった。いまホームレスの歌というのがあるかどうか知らないが、そういう歌があったなら禁止か自粛がおこるのだろうか。
ところが、そういう“理由”が見当つかないものもある。たとえば『竹田の子守唄』。この名曲はどうして放送禁止になったのか。
著者はこの疑問をきっかけにタブーに挑む。1971年、コーラスグループ「赤い鳥」がシングル『お父帰れや』のB面に入れた子守歌で、爆発的にヒットした。森山良子や加藤登紀子もよく唄っていた。それがあるときからこの歌は消えたのである。こういう歌詞だった。
守りもいやがる 盆からさきにゃ
雪もちらつくし 子も泣くし
盆がきたとて 何うれしかろ
帷子(かたびら)はなし 帯はなし
この子よう泣く 守りをばいじる
守りも一日 やせるやら
はよも行きたや この在所こえて
向こうに見えるは 親の家
この歌詞のいったいどこがタブーを犯したのか。この歌を唄っていた「赤い鳥」の後藤悦治郎は、この「竹田」は大分県の竹田だと思っていたそうである。そうであるならそこは滝廉太郎の故郷であり、「五木の子守歌」にも近く、なんとなく日本の子守唄の原郷のように聞こえる。実はぼくもそう思っていた。
しかし、そうではなかったのだ。竹田は大分県ではなく、京都の被差別部落の竹田だったのである。そしていつしか部落解放同盟からの圧力がかかって、この歌が放送禁止になっていったという噂が流れた。
そこで著者はこの経緯を追う。テレビ局を調べ、「赤い鳥」を尋ね、解同(部落解放同盟)に出向いた。意外な事情が見えてきた。もともとは尾上和彦が竹田地区で老婆が唄ってくれた唄を採譜したのだという。そのころ尾上は奈良の被差別部落を描いた住井すゑの『橋のない川』を舞台上演するときの音楽監督で、なんとか部落内に伝承されていた曲をモチーフにしたかった。それが舞台に流れ、解同の竹田深草支部の合唱団「はだしの子」がこれをレパートリーに入れた。
それをどこかで聞いた関西フォークの連中、たとえば高石友也らがめいめいで唄いはじめ、それをステージかフォークジャンボリーで聞いた後藤が注目し、アレンジを加え、「赤い鳥」ふうのファルセットを入れてレコーディングした。そういう経緯だった。
では、部落を唄ったからタブーを犯したのか。たしかにそういう“認識”はメディア全体がもっていた。いっとき『五木の子守唄』も流れなかったことがある。O157問題が話題になってカイワレダイコンが“犯人”扱いされたとき、著者のかつての仲間だった放送記者は、「どうも、あれは肉だったんじゃないか」と言い出していた。著者が「調べたのか」と聞くと、ほら、同和問題にひっかかるからと逃げ腰だったという。『竹田の子守唄』もどうも解放同盟が圧力をかけていたようだ。
しかしよく考えてみると、この子守唄は竹田深草支部の合唱団さえ唄っているのだから、これがタブーになるとは思えない。そこで解放同盟を取材すると、案の定、禁止を申し入れた事実は絶対にないと言う。
それならどうして『竹田の子守歌』は放送禁止歌になったのか。著者はしだいに、これらは差別と糾弾と非難を惧れるメディアがしだいに「みずからの陥穽」を広げていったのではないかと思うようになる。そうだとすると、これはメディアやアーティストたちの勝手な思い込みで、数々の名曲、たとえば『夢は夜ひらく』や『網走番外地』や『チューリップのアップリケ』が消滅させられたことになる。
調べてみると、そもそも「放送禁止歌」という言葉などなかったのである。正式には「要注意歌謡曲」という用語が紙の上にあるだけだった。民放連が1959年に「要注意歌謡曲指定制度」というものを決め、これに各局が従っているだけのこと、べつだん法律でもなんでもない。たんなるガイドラインなのである。
しかしそれにしては次から次へと放送禁止や放送自粛がおこってきた。しかもいったんそうなると、二度とその歌はメディアのどこにもにあらわれなくなっていく。禁断される。けれどもその禁断はメディアの共同幻想らしかった。著者はそのことを伝えたくて、番組をつくりたかったと書いている。
『竹田の子守歌』で“問題”になったとされたのは、「在所」という言葉だった。1986年のフジテレビの議事録にも、「在所=未解放部落」の注意書きが残っていた。
そうなると、「はよも行きたい この在所こえて」は、「早く行きたい この部落を越え 向こうに見える 親の家へ」と解釈できることになる。けれどもそれなら、この子守りの少女は被差別部落の出身ではないことになる。部落の外に生まれた少女が部落で子守りをしていて、早く親の家に帰りたいという意味になる。この疑問をもって著者は竹田を訪れる。京都市のやや南部にあたる。
著者はまず竹田の解放同盟の関係者たちから、「子守唄」と「守り子唄」の違いを聞かされる。「子守唄」は幼児を寝かしつけるための歌だが、「守り子唄」は労働歌。『竹田の子守唄』はその「守り子唄」なのだという。そのうえで原曲を聞かされた。原曲の歌詞は「赤い鳥」のものとはずいぶん違っていた。しかしどこが差別かはわからない。さらに「在所」という言い方も、京都では部落をさすことが多いらしいのだが、大阪では逆に部落ではないところをさすことが多いとも聞かされた。
これはいったいどういうことなのか。どこに「差別」や「禁止」のマークがついているのかが、わからない。少なくとも『竹田の子守唄』は、メディアが勝手に「差別」と「禁止」に躍っていたとも見えてくる。本書はこうした大きな「謎」を投げかけて、最後に岡林信康を追いつつ、終わっている。
岡林は近江八幡の牧師の家に生まれた。ぼくが『比叡おろし』をつくったころ、颯爽とデビューして、『山谷ブルース』が大ヒットした。「今日の仕事はつらかった あとは焼酎、くらうだけ」という、あの叩きつけるようなフォークは、いまでもぼくがカラオケで唄う数少ないレパートリーのひとつになっている。
ぼくがフォークギターで遊んだ新宿番衆町のころは、大半が岡林のものだった。ちなみに傍らの戸田ツトムは「キャロル」だった。ぼくに作詞を頼んでいた六文銭の歌も唄ってみたかったが、あのコード進行はぼくにはお手上げだったのだ。
こうしてぼくには岡林信康時代というものがはっきりあったのである。とくに『チューリップのアップリケ』は聞くたびに涙が溢れていた。その岡林がしだいに過激な歌を唄うようになっていった。『くそくらえ節』はその典型である。
ある日 聖なる宗教家 信者の前でお説教
この世でがまんをしていれば きっと天国行けまっせ
ウソコクな この野郎
見てきたようなウソをこくなよ 聖なる神の使者
ある日 アメリカのおエラ方
チェコの問題でこう言った それみたことか 恐ろしい
共産主義はあきまへんで
ウソコクな この野郎 こきゃあがったな この野郎
そういうことは ベトナム侵略やめてから
ぬかしやがれ
ある日 おエラい小説家 選挙に立ってこう言った
青年の国 作るため わたしゃ文学捨てたのよ
甘えるなこの野郎 甘ったれるなこの野郎
弟つれて選挙をやるなど ジジイのやることだ
いまこそブッシュや石原慎太郎に聞かせたいが、最後には天皇も出てくきて、そうとうに過激な内容になっている。が、岡林はこのような歌をその後はステージでも歌っていないらしい。
著者は岡林に取材を申し込むが、成立しなかった。岡林は竹田も訪れて、同盟主催のコンサートもしたらしい。そこでも『手紙』も『チューリップのアップリケ』も唄わなかつたという。
こうして本書は、放送禁止歌ではなくて、時代と社会とメディアの中で生まれ、沈んでいった歌というものの不気味な本質を告げ、終わっていく。なかなか読ませた。考えさせられた。ぜひとも1時間のドキュメンタリー『放送禁止歌』の前半も見てみたい。そのうえで、いったいぼくの『Zの挽歌』のどこかが自粛の対象になったのか、いつか調べてみたい気にもなってきた。きっとなんとなくヤバイと思われただけなのだろう。