父の先見


筑摩書房 2005
41歳で急逝した早坂文雄が昭和28年の手帳に残したメモに「端的只今の一念」とあって、さらに「現在尊敬セル人々」の名があげられている。和辻哲郎、坂本繁二郎、永井荷風、鈴木大拙、斎藤茂吉、前田青邨、幸田露伴、柳田国男、会津八一、クレー、モジリアニ、そして映画では黒澤明。
実にいい顔触れだ。なかなかこんなリストはつくれない。荷風や大拙が入っても、そこに八一や青邨が並ぶことは、ふつうはできない。「端的只今の一念」がよくあらわれている。早坂は30代後半から汎東洋主義(パンエイシャニズム)を標榜して西洋音楽との訣別を宣言し、最後の最後に『ユーカラ』を完成させた。「端的只今の一念」を貫いたのだ。『ユーカラ』を聞いた武満徹は「音楽を聴いて、あれほど涙が出て感動したことはなかった」と言った。
黒澤は芥川龍之介や山本周五郎の素材や武士道の宿命を描きつづけて、あれだけ国際的な受賞歴を誇ったにもかかわらず、「ぼくは日本人として言いたいことを言っているだけだ。外国に受けようなんてことはいっぺんも考えたことがない」と言い切った。『夢』の公開のあとには「最大の夢は日本を作り直すことだね」と言って、電通などが日本アカデミー賞を企画したことについて、「なぜアメリカの猿真似をするのか、ばかばかしい」と吐き捨てた。
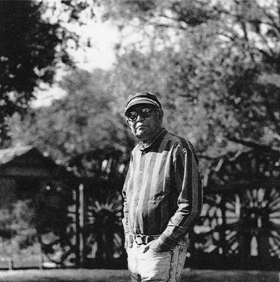
本書はそのような黒澤明と早坂文雄が『七人の侍』を完成させ、被爆者を描いた『生きものの記録』の制作途中で早坂が死ぬまでの日々を追っためずらしいノンフィクションである。黒澤と早坂の少年期から壮年期までを交互にオムニバスしつつ、二人の周辺の人物、たとえば植草圭之助、山本嘉次郎、清瀬保二、伊福部昭、本多猪四郎、高峰秀子、武満徹、橋本忍たちを鮮やかに描き出している。
どちらかといえば早坂の短い生涯が映画音楽にもたらした独創的な成果に重点がおかれているのだが、これは著者の西村がすでに『黒澤明・音と映像』とか『黒澤明を求めて』といった黒澤についてのいくつもの濃厚な著作を発表してきたからで、ぼくにはこのように早坂がクローズアップされたことに感謝しながら読めるものが横溢していて、むしろありがたかった。


黒澤については『全集黒澤明』をはじめ、佐藤忠男の『黒澤明の世界』から三国隆三の『黒澤明伝』まで、いくつもの評論や評伝があるので、それらを補えばいい。
ただし、そういうものを読んでみると、黒澤をめぐる周辺の毀誉褒貶がはなはだしく多いことにぶつかる。黒澤作品は『姿三四郎』から『まあだだよ』まで全部で30作品があるのだが、たとえば石堂淑朗は『乱』『夢』『八月の狂詩曲』を「耄碌を絵に描いたような失敗作」と書き、獅崎一郎は『黒澤明と小津安二郎』という本のなかで『影武者』も『乱』も人間を描けなくなった観念だけの作品になっていると指摘し、緒方邦彦は『黒澤伝説』に「黒澤の作品は『赤ひげ』で終わってしまったのか」と書いて嘆いた。最近は『黒澤明の精神病理』というきわどい本も刊行されている。二人の精神科医が黒澤の記述や映画からエピレプトイド(癲癇症)を推測したもので、当たっているかどうかは、まったく保証のかぎりではない。
むろん絶賛は数知れない。サタジット・レイ、フェリーニ、タルコフスキー、コッポラ、スピルバーグ、ルーカスをはじめ、褒めない映画関係者のほうが断然少ない。樋口尚文が『黒澤明の映画術』で「黒澤は映画になることと映画にならないことを知り尽くしていた」というような言い方をしていたが、黒澤を評価する者の気持ちはほぼこの言葉に集約されているだろう。
そういう評価をべつにしても、とかく「クロサワ天皇」とか「鬼のクロサワ」とか「完全主義者」よばれた"人柄"についても、そういう噂のわりには逆の感想が多い。『天国と地獄』と『赤ひげ』に出た山崎努は「あの深くて優しい眼ですべてが許されるんですよ」という感想をのべているし、『どですかでん』と『まあだだよ』に出演した松村達雄は「愛嬌があって大雑把で無邪気だった」と言っている。これが意外な感想なのか、それとも黒澤の実像を伝えているのかは、ぼくにはわからない。黒澤自身は「映画は監督の人柄が出るもんだ」と言っていた。
そのように黒澤については多くの著作や言述が出ているのだが(黒澤自身の『蝦蟇の油・自伝のようなもの』もある)、しかし黒澤と早坂の紐帯に入りこんだものは、本書一冊だけなのだ。まことに貴重な一冊だ。
黒澤は明治43年の東京生まれで、父親の故郷の秋田を背負っている。青年時代はプロレタリア美術に惹かれて絵を描きたかったらしいのだが挫折して、そこへ兄の自殺も加わって、しばらくは根無し草として野良犬のように喉が渇いた青春をおくっている。
それがPCL映画撮影所(のちの東宝)の助監督募集になんとなく応募して、そこで山本嘉次郎のサードについたのが黒澤をめざめさせた。大器晩成というのは当たらないが、原作にもロケ地にも俳優にも、ともかく新たに出会うと、そこから急激な集中力と持続力と爆発力を発揮するタイプだった。
早坂は大正3年に仙台に生まれて幼児期に札幌に移り、そこで伊福部昭と同じ学校で切磋琢磨した。北の大地が早坂の背景なのである。これは早坂がずっとアイヌの『ユーカラ』を交響曲にしたがっていたことにもあらわれている。伊福部は『ゴジラ』の作曲家として一般には知られているが、昭和の作曲界を早坂とともに雌雄を争ったユニークな音楽者だった。
早坂も伊福部も清瀬保二に憧れた。第1033夜にも書いたけれど、昭和の現代音楽にとって清瀬保二は神様だったのである。もっとも早坂も早熟で、早くからその才能が輝いていた。そこが黒澤とは異なっている。

5歳ちがいのこの二人が出会うまでには、本書がそれをこそ詳細にあかしているのだが、さまざまな有為転変があった。
しかし『酔いどれ天使』で出会ったとたん、二人は人が羨むほど尊敬しあい、互いにその才能を評価しつづけた。『野良犬』『醜聞』『羅生門』『白痴』『生きる』『七人の侍』まで、すべて連打して早坂の音楽である。そして次の『生きものの記録』の途中で早坂が41歳で死んだ。黒澤は早坂が急逝したことを断腸の思いで噛みしめ、「あんな音楽家は日本にもう出ない」と呻いた。
早坂は早坂で、黒澤の音楽に対する勘の鋭さにずっと舌を巻いていたようだ。とくに『羅生門』のときに、この監督は「画のマチエール」とまったく同様に「音のマチエール」がわかる人だということに驚いたという。
早坂は『七人の侍』のとき、一方で溝口健二の『雨月物語』の音楽も引き受けていた。
もともと『七人の侍』は黒澤が脚本家の橋本忍に、「侍の一日をものすごくリアルに描いてみよう」と言った一言から始まったプロジェクトだった。朝起きて、城へ上がった侍が些細な失態で切腹にまで追いこまれる流れを克明に映画にしようというものである。
このアイディアはそのときは実現せずに、そのかわりにさまざまな剣豪や剣客たちのエピソードを独自につなげようということになった。ところがその調査をしているうちに、多くの武者修行の侍たちが、各地で野武士の襲撃のために村に雇われていたことがわかった。黒澤はとっさにそれがいける!と叫んで、それをモチーフに小國英雄と橋本忍にストーリーを組み立てさせた。ソ連作家のファジェーフの『壊滅』も組みこんだ。当初は『武士道時代』というタイトルにもなっていたらしい。侍が一日のなかで切腹していくというほうのアイディアは、その後も橋本がゆっくり暖めて、結局は小林正樹の『切腹』と今井正の『仇討』になった。
早坂は出来上がってきた脚本を見て、ワグナーが楽劇をつくるために小さなライトモチーフを構成していった手法を援用しようと思いつき、「侍のテーマ」「野武士のテーマ」「百姓のテーマ」「志乃のテーマ」「菊千代のテーマ」などのデッサンを始めた。なかで「志乃のテーマ」が一番早坂らしいと、のちに黒澤は述懐した。
そのころ、『雨月物語』がヴェネチア映画祭の銀獅子賞をとったという報告が入ってきた、早坂は『羅生門』に続いて賞をとったことになる。戦後の日本人が輝いていた瞬間だ。溝口は次の『山椒太夫』も早坂に頼んできた。早坂は気合を入れて、黒澤と溝口という日本を代表する二人の監督の映像の音楽化にとりくんだ。
しかし、『七人の侍』の圧力と重量はさすがにものすごいものだったようだ。早坂はついに喀血して酸素ボンベを編集機のそばにおいて、仕上げるしかなくなっていた。あの頑強な三船敏郎でさえ、野武士の襲来のクライマックス・シーンの撮影のあとは倒れて慶応病院に入ったのである。

こういう話が本書は連続している。終盤、早坂が一枚の写真を病床に飾ったまま死んでいく場面が描かれている。その写真には「昭和二十九年四月二十一日。『七人の侍』完成試写の日」とあって、右に黒澤、左に早坂が写っていた。それから1年少したって早坂は死ぬ。
黒澤明はその後、早坂の弟子にあたる佐藤勝を起用した。『蜘蛛巣城』『用心棒』『椿三十郎』『天国と地獄』『赤ひげ』である。それで足りないときは、早坂を慕ってやまなかった一番若い武満徹を起用した。『どですかでん』である。黒澤は映画でもっとも大事なのは編集と音楽だと言っていた。
黒澤はつねづね言っていたそうである。「映像と音楽の関係は、映像プラス音楽ではなくて、映像かける音楽なんだ」というふうに。
だから黒澤は、ジョージ・ルーカスの『スター・ウォーズ』にも注文をつけた。あれは音楽が多すぎるというのだ。ルーカスが「子供が見るのでわかりやすくした」と言ったところ、黒澤は「子供を侮辱しちゃいけない。子供はそんなことをしなくてもちゃんとわかるんだ」と窘めたという。
いま、ちょうど公開されているスティーブン・スピルバーグの『SAYURI』のことを生前に聞いていた黒澤は、スピルバーグにFAXを送って「日本で撮るなら日本語にしたほうがいい」と助言したようだ。黒澤久雄によると、その話題が父と交わした最後の会話だったという。スピルバーグは黒澤の助言を守らなかった。
しかしそのような黒澤の卓見にくらべると、いま早坂文雄の卓見が何であったかを、われわれは忘れすぎている。早坂は西洋音楽が「幅」と「量」に依拠しているのに拮抗して、日本音楽が「線」や「余」によって成立しうることを訴えていたのである。
その早坂の葬儀には、黒澤のはからいで『七人の侍』の「侍のテーマ」が流された。「風のように侍は、大地の上を吹きすぎる」、二番は「旗のように侍は、嵐の中にひるがえる」。この歌詞は早坂自身が書いたものだった。それを、そのころはイサム・ノグチ夫人だった山口淑子が歌った。みんな泣いたという。