父の先見


岩波新書 1940
[訳]北川桃雄
手元の岩波新書の第19版奥付は昭和35年。高校2年のときにあたる。ボロボロだ。そうだった、これを布製のナップザックに入れて鎌倉を歩いた。このとき居士林や覚園寺で座禅などに遊び、大量の鎌倉の写真も撮った。
この年頃に禅を知ったこと、ほぼ同時に大拙を読んだこと、それが英文で書かれたものの対訳版であったこと、これらはいまふりかえるとかなり濃厚な大拙禅ミームをぼくの体に染みこませていた。それとともにやっと日本文化の入口に気がついた。京都の呉服屋に育っていれば日本文化なんて勝手に身についていてもおかしくないはずだが、残念ながらそうはなっていない。日本文化の奥に手が届くのはずっとあとだ。その踊り場がこの一冊にあったということが、のちにわかった。
その後、禅語録にあれこれ目を通し、禅の歴史にも禅の美術にも禅の庭にも、ようするに禅林文化のあれこれに遊ぶようになったのだけれど、最初期の大拙禅ミームそのものはいまもって生きている。ミームはちっとも廃れない。これが、青き時代の読書というものの影響の大きさをあらわしているのか、鈴木大拙という特異な禅学者がもたらす言葉の象徴作用の大きさなのか、そもそも禅というものはそのように最初のインプリンティング(刷りこみ)の体験に左右されるものなのか、いまとなってはそのあたりは因数分解しがたい。
ひょっとして本書が英文和訳の一冊だったことに何かの染め色の秘密とでもいうべきものがあるように惟われるのは、ぼくが岡倉天心(75夜)の『茶の本』や小泉八雲の『怪談』に同様の染め色ミームを感じたからでもあろう。ときに英語で日本文化を読むのはいいものだ。いや、実際にも本書は他の大拙の著作にくらべて、けっこうバイリンガルな禅味に富んでいた。
いまでもよく憶えているのは、こういう語り口だ。あえて当時の大拙の英語の言いっぷりをまじえて紹介しておこう。
禅というのはブッダの精神を直截に見ようとするもので、何を見ようとしているかというと、「般若」と「大悲」なのである。それを英語でいえば、般若はトランセンデンタル・ウィズダムに近く、大悲はとりあえずコンパッションといえるであろう。この「超越的な智恵」たる般若によって、禅者は事物や現象の因果を超えるために修行をする。そうやってやっと事物や現象にとらわれなくなったあるとき、ふっと大悲が自在に作用する。それは自分にまつわるコンパッションではない。そのコンパッションの作用は禅仏教では無生物にさえ及ぶのだ――。
こんなことを感受性の高い高校生が初めて聞いたら、ちょっと身震いするのは当たり前のこと、すぐさまラルフ・エマーソンの超絶主義につながったり、ティヤール・ド・シャルダンの精神圏仮説と見くらべたりしたが、大拙はそんなことはおかまいなしに次のように畳みかけたものだった。
人間はそもそも「無明」と「業」の2つの密雲にはさまれて生きている。禅はこの密雲に抗って、そこに睡っている般若を目覚めさせる方法なのである、トランセンデンタル・ウィズダムはその間隙に出現する方法の智恵なのだ。その方法を知りたいなら、まず学校で習ったような順で物事を考えることをやめなさい。あれはレッスンにすぎない。ラーニングではない。なぜなら禅は「認識のコースを逆にした特別のメソッド」をもっている。そう言って大拙は突如として、だからこそ、「禅は夜盗が夜盗に学ぶようなものなのだ」と言った。
これはのちにぼくも読むことになる『五祖録』からの引用だったのだが、突然に夜盗になれと言われても戸惑うだろうから、説明しておく。
ある夜盗の父親が息子から夜盗のコツを教えてほしいと言われ、2人して目星の屋敷に忍びこんだ。父親は大きな長持を開けて息子にこの中の衣服を取り出せと言っておいて、そのまま蓋を閉め、庭に出るとやにわに「泥棒だ、泥棒だ」と大呼した。
家人があわてて起き出したが泥棒はいない。困ったのは息子のほうで、長持から出るに出られない。そこでやむなくネズミが齧る物音をたて、家人が長持を開けたとたんに飛び出し、命からがら逃げ出した。這々の体で息子が戻って父親にひどいじゃないかと言うと、まあ憤るな、どうやって逃げたか話してみろというので、息子が一部始終を話すと、そう、それだ、お前はこれで夜盗術の極意をおぼえたのだ、と。
こういう奇想な話を紹介し、大拙はすかさず「禅は不意を打つものだ。それが禅の親切というものだ」と説いたのである。親切が不意を打つことだなんて、これはエマーソンやカーライルやコールリッジとはちがう。アメリカの超絶主義とはちがう。わーっカッコいい、ものすごい。こんなことニヤリともせずに茶碗を片手で出すように言われれば、一介の青年、すぐに禅や禅林に憧れる。
大拙が禅を英文で説いたことが世界に禅を広めた。それが同時にその後の昭和の日本人にやっと禅の入口と出口を指し示す好機ともなったことは、いうまでもない。ちょうど英語にも夢中になっていた高校生には、禅と英語が一緒にやってくるのは、なおさらにどぎまぎする未知の魅力になった。たとえば、こうである。
禅では、スピリットとソウルの行方だけが、ようするに気分の行方だけが焦点の課題なのだ。それゆえ世間で通用するフォーマリズム(形式主義)、コンベンショナリズム(慣例主義)、リチュアリズム(儀礼主義)などをすっぱり捨てるところをもって自己の精神を裸出させる。そうすれば、その本来にひそむアローンネス(孤絶性)とソリタリネス(孤独性)に裸形のものが還ろうとする。このアブソルートな孤絶が禅独得のアスセチシズム(清貧と禁欲)の精神となるはずだ……云々。
英日両用のチャンポンな禅の説明は、当時、ぞくぞくするほど痛快だった。とくにぼくは本書によって、禅というものの本来が「一即多、多即一」であることを刷りこまれたために、こうしたグローバルでローカルな禅の説明が効いた。
もうすこし続けると、大拙はこう言った。禅が「一即多」になるのは、一方ではプリミティブ・アンクースネス(原始的無骨)やライフ・インパルス(生の衝動)を好むからである。けれども他方で、たえず師家が雲水たちをダイナミック・アイデンティフィケーション(動態的同一作用)の動揺に導き、たえず陥りがちになる論理的袋小路を突破させている。この苛酷な稽古がやはり必要なのである、と。そこでは自分が「一」に着こうとすると「多」が暴れ、「多」を引き取ろうとすると、それが奪われる。こういうことをくりかえしていると、「一が多であり、多が一であること」など、至極当然になる。それでいて一切が本来無事である。そう言うのだった。
こういうぐあいに、本書が鎌倉に遊んでいた高校時代のぼくに与えた一陣の風濤は、まことに迅速、待ったなしの趣きだった。よくぞこの一冊をナップザックに放りこんだとおもう。しかしところが、のちに禅林文化に分け入り、大拙の著作を次々に読んだうえでふたたび本書に戻ったとき、なんだ、ぼくはまったく本書を読みこんではいなかったと痛打されたのである。
読みこんでいなかったことはいくつもあったのだが、いまは2つに絞れば、そのひとつは、華厳哲学と禅の著しい親近性をすでに大拙が指摘していたことだった。華厳(1700夜)と禅とは互いに「アマルガメーション=合金作用」の関係になっていると大拙は本書で書いていたのである。これについてはぼくもずっとあとになって「華厳から密教へ」「華厳から禅へ」という二つの変化の研究にとりくんだ。その一部の成果が『空海の夢』(春秋社)の第26章になっている。
もうひとつは、大拙が能・水墨画・茶・俳諧・日本刀などを例にして、日本文化のエステティック・アスピレーション(美的思慕)をずいぶん踏みこんで解明していたことだ。『禅と日本文化』という本書の表題からして、こんなことは当然に予想されることなのに、なぜかぼくは禅そのものの唐突で根本偶然に満ちた未知の魅力に関心をもったにもかかわらず、本書に日本文化の美にひそむ禅を嗅ぐということをしなかった。けれども、この一冊が踊り場だったのだ。
改めて読んでみて、そのことに気がついた。能も水墨山水も茶の湯も刀も日本仏教だったのである。とくに俳諧と禅の話がヒントになった。
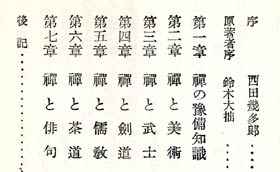
いささか大拙の作り話めいてはいるが(大拙はこういうことをよくする)、芭蕉(991夜)のエピソードにこういう話がある。仏頂和尚のもとで参禅していたときのこと、和尚が突然に芭蕉の庵を訪れ、「近頃はどうしておられるかな」と問うた。それがきっかけで「今日」(today)とは何かという話になった。
芭蕉は「今日」とは「雨が通り過ぎて青苔が潤っているようなもの」と答えた。和尚は「その青苔がまだ芽も生えていない時も、いま、あろう」と突っこんだ。ここまではよくある禅の公案に近い。が、このとき芭蕉がぽつんと放った言葉が、「蛙とびこむ水の音」だった。大拙はこのエピソードについて、キリスト教なら「アブラハムの生まれ出でぬ前より、我はいる」という基督の回答に芭蕉がぶつかったようなものだと説明する。そして、キリスト教ならばここできっと「我は在るなり」(I am)ですむかもしれないが、禅仏教ではそうはいかない。その〝am〟の未生以前が問われる。それに応えようとしないかぎりは禅にならないと言う。
キリスト教はどこかでポラリゼーション(分極)をおこせばよい。神と人とは結局はどこかで分離する。だからこそ絶対唯一なる神がいつまでも残る。けれども禅はそうはしない。神も人も青苔も水音もたちまち一緒になって、またそのそれぞれの元々の時に戻ってくる方法をもつ。これが道元の「有時」である。そう説明していた。もっとも、ここまではへぼな説明だ。
けれども大拙はここから転じていく。俳諧には禅の方法に達していることがしばしばおこっている。それは、禅や俳諧が最初から「不確実性」ということを体現しているからである。だから禅はけっしてディスクリミネーション(分別)にはとらわれない。
そう言って大拙は、やおら芭蕉の「やがて死ぬけしきは見へず蝉の声」と、蕪村(850夜)の「釣鐘にとまりて眠る胡蝶かな」とをあげた。大拙は、茶や能や俳諧が思想の表現に進まずに、直観の提示に徹したことを評価したのである。日本文化に出入りするワビ・サビ・シオリは禅定の同意語だろうと見たのである。それゆえ「寂び」を試みに〝tranquility〟とも訳しているのだが、これをもう一度日本語にあてるなら、きっとそれは「妙」とか「三昧」になるのだろうとも言っている。
このセンスこそ大拙であり、日本文化はこのように扱うべきだったのである。日本仏教はここから説明されてよかったのである。
以上、ここではただひとつのこと、ぼくが最初に出会った一冊とのかかわりだけを書いたにとどめたが、鈴木大拙についてはいくらでも書いてみたいことがある。
大拙は明治初期の生まれだが、金沢の四高や東京帝大選科の途中から禅に関心をもちはじめて、早々に鎌倉円覚寺で今北洪川や釈宗演についたのがよかった。宗演は日本初のコスモポリタン型の禅僧で、青年期に福澤諭吉(412夜)や山岡鉄舟(385夜)に学んで20代後半にセイロン(スリランカ)やインドに入ってパーリ語を修め、32歳で円覚寺派の管長につくのだが、1893年のシカゴの万国宗教会議に出席したのを機縁にまた一念発起して、水夫となって世界一周を企てた。
その宗演が帰国して建長寺派の管長を辞して1905年に渡米をしたとき、宗演の推薦により大拙が通訳を担った。大拙のセンスはこのときの宗演のアメリカでの講演通訳を通して磨かれた。けれども大拙の「大乗禅」の研究もすでに本格的で、『大乗起信論』の英訳や英文による『大乗仏教概論』をものして、独得の禅思想の開示に向かっていた。とくに華厳と禅の関係は大拙の初期に宿っていた炯眼で、その後のぼくはこのヒントにどれほど鼓舞されたものだったか。
いや、それ以外にもたくさんの叱正と示唆と振動をもらってきた。いずれそれらをダルマの話や『臨済録』(550夜)『無門関』(1175夜)の禅語録体験や五山僧たちの数々のエピソードなどとともに、まとめたい。
ただし、ちょっとした問題もある。大拙の英語力やセンスがアメリカに独得の仏教感覚や禅感覚を広めることになったのは、国際宗教力の只中に投げこまれた近代仏教にとって大きな福音となったのだが(日本の禅ブームにとっても)、そのぶんアメリカ禅が自己実現禅のほうに転回していったのだ。このへんが気になる。大拙の英語による解説力がそうさせたのか、のちにケネス・タナカが説明するように、アメリカ仏教が瞑想主義とマインドフルネスを好んで大乗禅から遠ざかったのか。どうも功罪相半ばするところが交じっていたのである。そのうちゆっくりと考えこみたいことだ。
大拙と西田幾多郎(1086夜)の関係のこともいずれは深く突っこんでみたい。同じ金沢の生まれで、同じ明治3年の生まれだ。
西田の『善の研究』は、大拙が好んで色紙に書く次の英文の3行そのものである。“To do good is my religion; The world is my home”そこから大拙は「霊性の自覚」を言葉にすることを試みて、いわゆる「即非の論理」を提唱するに至った。「即非」は『金剛般若経』にひそむ東洋独自のロジックで、「AはAでない、故にAである」というもの。「AはAでない」の前半の自律の推論と後半の「故にAである」の相対化の推論が、ワンフレーズのなかで高速で進行するものである。ここには日本文化を説明するときの格別のロジックがあった。このロジックはいわゆる論理ではない。アナロジックともいうべきものだ。わが編集思想にとって、アナロジックはどうしても欠かせない。
べアトリス・レーンのことも気になる。学習院と東京帝大で英語を教えていた大拙は渡米してベアトリスに出会う。のちの大拙夫人である。ベアトリスがいなかったら、大拙はリアルタイムの速度で世界に届かなかったろうし、ぼくもここまで大拙に溺れなかったかもしれなかった。
きっとエーリッヒ・フロムを大拙の側から批判しておくことも必要なのだろう。いまはそのような作業をする気はないけれど、いっときぼくはフロムによって禅とフロイディズムに傾倒していたのだから、ここはいつまでも放っておけるものでもなくなっている。ようするに、いったい内なるレヴェレーション(啓示)とは何かということだ。外なる啓示なら天使ガブリエルさえ必要なのに、禅者の天使は「カラスがカー」だけでいいのはどうしてなのか。そこをフロムにもフロイト(895夜)にも、さらにはユング(830夜)にも突き付けなおしてみることも、そろそろ必要なのだろう。
天龍寺管長や花園大学学長を務められた高歩院の大森曹玄老師との日々について、とくに「書禅」をめぐって話しておくことも必要だろう。そのときは寺山旦中さんに教えられたことも外せない。
まあ、いつしかぼくも好きなことだけを三昧する日々もあるかもしれない。そのときはまた大拙を思い出し、「そこ」を一言、“totality itself”とよべるのかもしれない。いまはともかくも、さて真空妙用、無効用行。用事をつくるのが無事なんである。