父の先見


岩波文庫 1990
今夜は愉快だ。陶淵明が書ける。「万化は相尋繹す。人生、豈に労せざらんや。古(いにしえ)より皆没する有り、之を念(おも)えば中心焦(こ)がる」である。陶淵明が45歳に詠んだ重陽の日の詩の一節だ。405年のこと、5世紀に入ったばかりの詩人の洞察だった。
このように「之を念えば中心焦がる」と言い放てる者とともにあると、そう思えるだけで、ぼくは心が躍り、気分はいやましに痛快なのである。
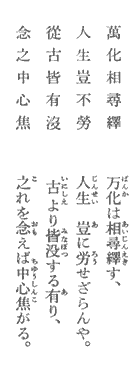
49歳のときの陶淵明に『形影神』という、とんでもなく大胆奇抜な詩があった。「形」と「影」とが「神(しん)」をめぐって問答をしでかすという内容だ。形は肉体、影は精神と見立ててよいが、そういう解釈はともかくとして、言いっぷりがいい。
長い漢詩を引くわけにもいかないから、つまみ食いでお目にかけるしかないが、まず「形」が「影」に向かってこう豪語する。「天地は長(とこし)えに没せず、山川は改まる時なし」「人は最も霊智なりと謂うも、独り復(また)茲(か)くのごとくならず」。すると「影」が「形」に応えるのである。
|
生を存することは言う可からず、 |
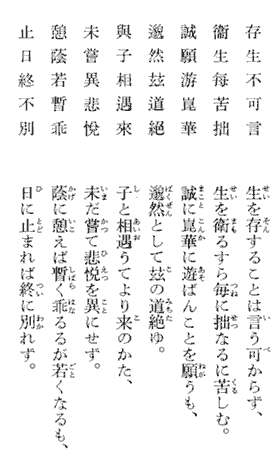 |
いつまでも生きていたいなどというのは論外、もってのほかのこと、当方、生を養うことすら拙劣で、いつだって困っている。こう言い放つのだ。
これはぼくがずっと感じてきたことである。まったく生活なんて困ったもので、どうしてこんなものを上手に充実させられるだろうか。いつだって皆に助けられてかつかつ生きているだけなのだ。だからこそ、一木一草に突如に感慨を疾走させられるのだし、突然に芭蕉とヴィトゲンシュタインとマーク・ボランを一口にほおばりたくもなるわけなのだ。
陶淵明はすでに5世紀にして、このことを喝破した。しかし、これはまだ「影」のセリフだったのである。ここでやおら「神」が口を開くのだ。これが、さらにいい。
|
大鈞無私力 大鈞は力を私(わたくし)すること無く、 |
大鈞は轆轤(ろくろ)のことである。その大鈞は力を私(わたくし)していない。回せば、おのずと何かができてくる。萬理はもともと独創的なものとして現れていたのであって、何も誰かがオリジナリティを競ったわけでも、威張ったわけではなかったのだ。だからこそ天地の間に位置する「人」は(三才とは天地人のこと)、「中」を求めていまここにある。これらがこのようにあること自体が、ほれ、「神(しん)」というべきことではないか。
ざっとこんな意味である。陶淵明がこのような『形影神』を綴ったのは、そのころ深い交流のあった慧遠との問答のせいだった。やっと中国に慧遠による浄土教が芽生えた瞬間のことである。
しかし慧遠は新たな浄土教のイデオロギーと修行の仕方に邁進したのだが(だからこそこの流れが日本にも届いて浄土信仰となったのではあるけれど)、陶淵明はこれに半ばは興味を示しつつも、悠然とこれを見送った。その気概が『形影神』には残響する。
陶淵明が仏教の台頭を見送れたのは、老荘思想に存分に遊んでいたからであり、すでに栄達や成功にまったく関心をもてなくなっていたからだった。
あらためていうまでもないが、陶淵明は41才のときすべてを投げ擲って故郷の廬山の麓に帰ってきた。このときの詠嘆が、「帰りなんいざ、田園まさに蕪れんとす。なんぞ帰らざる」に始まる、かの有名な『帰去来辞』というものだ。この「蕪れんとす」は日本人ならすぐに「荒れんとす」と読めなければいけない。これこそが“蕪村”の名の由来そのものだから。
その蕪(あ)れた廬山に発祥したのが、一方では慧遠の浄土感覚であって、他方が陶淵明の山水感覚だったことは、この時期の中国の一郭(六朝時代)が、よほどの文化の根底に戻れていたことを物語る。しかも、浄土感覚は仏典の翻訳による力もあずかったわけであるが、陶淵明の山水感覚は陶淵明自身の存在の投企がなければおこらなかった。なにしろ、短期間ではあれ彭沢県の県令(町長)すら務めた者が、いかに世渡りがへたとはいえ、あるときすべてを打擲して、こんなふうに山水だけを求めて田園に戻るなどということは、かつてなかったことなのである。
この山水感覚の“発見”については、むろん『帰去来辞』の発揚もいいのだが、『帰園田居』(園田の居に帰る)三首こそがもっと故淵に戻った草莽からの発想を思わせて、ぼくは何度もこれをうろついた。ここには「一切合財」と「たった一個の山水」とを平然と取り替えっこしている陶淵明の気分が、一語一句一聯によくあらわれている。
山水感覚は、そして山水思想というものは(『山水思想』を読んでください)、その端緒においてすでに「引き算」をもってスタートしていたものだったのである。
ところで、この漢詩については、もうひとつ、別の感想がある。「一去十三年」(一たび去って十三年)の一聯に、かつてたいそう感じたことがあったのだ。
いったん何かに迷ったら十三年はたちまち過ぎ去るということである。ああ、そうだろうな、そういうものなんだろうなと、大いに感じた。そう感じてから、ぼくはおそらく十三年の迷妄には入っていない。だいたい十七ヶ月くらいの単位で、自分の執着を変えてきた。しかし、何かがごく僅かでも狂っていれば、いつだって十三年の徒花に入りこんでいただろうとも回顧できることがある。このことは、ときどき我が身を振り返って慄然とする。
『帰園田居』四首目の、「一世、朝市(ちょうし)を異にす、此の語、真に虚ならず。人生、幻化に似たり、終に当に空無に帰すべし」も、そこをまさに衝いていた。
陶淵明の詩は120篇ほどのこっている。何度かにわたって読んできたが、ぼくはもともとは杜甫が好きで、ついで李白や白楽天、いったん屈原や李賀にさかのぼって惚れ、ふたたび『唐詩選』『宋詩』をめぐったあとから、やっと陶淵明をゆっくり読むようになった。
残念ながら、最初のうちは酒の詩人だという印象があった。『文選』を編集させた梁の昭明天子蕭統は、陶淵明を初めて世に知らせた天子としても知られているが(それまで陶淵明はまったく知られていない無名詩人だった)、その陶淵明伝の序文には「篇篇有酒」とある。どの詩にも酒の香りがしているというのだ。陶淵明はある年齢に達してみないとわからないのであろう。
むろんこれは中国独特の誇張であって、陶淵明には淡々とした田園詩もファンタジックな幻想詩も、また官能に心を寄せている詩もあって、李白ではあるまいにすぐに酒と結び付けるわけにはいかないのだが、それでも最初は酒気を帯びた詩人であるという印象が強かった。それが、『連雨獨飲』だか『止酒』だかを読むようになってから、だんだん変わっていった。
とくに『止酒』はおかしくて、二十行のすべての句に「止」という文字を使って、酒を止(や)めようとしているのだが、最後に「今朝、真に止めたり」と結ぼうとしているのに大笑いできて、これで陶淵明にゆっくり浸れるようになった。
陶淵明は『山海経』をそうとうに好んで、耽読していたふしがある。広く「異書」も好んだふしもある。フィクショナルな人物の探玄を好んだふしもある。
空想癖があったといえばそれまでだが、ぼくには陶淵明のイメージマップには、つねに幻想の山水郷がことこまかに生きていたと見えるのだ。これはひとつには陶淵明が実在者としての自分をこてんぱんに放棄していたことと関係がある。『五柳先生』を読めばすぐさまわかるように、陶淵明はすでに廬山に帰った自身の存在がフィクションだったのである。
またひとつには、陶淵明はつねに「別界」にいて、別界の物語をつねに語ろうとしていた。それを誰かに伝えるのではなく、むしろ「伝えられない物語がある」ということを物語に綴りたかった。この趣向がぼくを陶淵明に走らせたのだ。とりわけ『桃花源記』はとびきりの傑作で、桃源郷の物語として、あるいは山水ファンタジーとしてはもちろんのこと、別界物語の香り高い嚆矢としても、世界の文学史上で最も早い到達を示している。
こんな物語だ。
あるとき、ある男が谷川に沿って舟を漕いで上っていくうちに、どれくらい先のことだったか、突然に一面に桃が咲き乱れる林に出会った。桃以外の木々は一本もなく、すべて桃なのだ。
その「芳華鮮美」で「落英繽紛」の光景に驚いた男は、その林の奥を見届けたくなって入っていくと、林は水源で尽きて、そこに一山が開けた。その「山に小口あり、髣髴として光あるが如し」。男は夢中になってその口に入っていくと、はじめのところは狭かったのだが、しばらく行くと「豁然として開朗」となって、なんとそこに光に満ちた村落が出現した。家屋も厳然としているし、池も田も桑竹も美しい。しかもそこに行き交う人々はことごとく異邦人のようであって、微笑を絶やさない。
あまりに不思議なので会話をしてみると、「先世、秦の時の乱を避け、妻子邑人を率いてこの絶境に来り、また焉(ここ)より出でず」という。いっさい外界と絶縁したままだというのだ。実際にもこの人達は漢の帝国があったことさえ知らなかった。
数日滞在して、いよいよそこを去ることになったところ、皆は口々に「こんなことはたいしたことではありません」と語る。男は思いを残しながらも“そこ”を去って、以上の話をいろいろ伝えたところ、多くの者が興味をもって“そこ”を訪れようとしたのだが、ことごとく迷って辿り着けなかった。それだけのことである‥‥。
この桃源山水からタオイズムや神仙思想や「桃と棗の時間」を牽強付会するのは、ここでは遠慮したい。いま、陶淵明を感じるとはそういうことではなくて、ただ陶淵明に向き合って愉快であるという、そのことだけなのだから。ひたすら気分がいいのだから、何も説明はしたくない。
そのかわりに、古来の評価が分かれる陶淵明屈指のエロティックな官能山水を放って、しめくくりとしたい。
これは『閑情賦』というもので、かつてはこの官能山水がさっぱり理解されなかったものだった。やっと魯迅によって脚光が浴びせられ、これを魯迅から教わった盲目詩人エロシェンコを動かした。
きわめて長い作品なので、またまたそのごく一部を掲げるにとどめるが、この漢詩は陶淵明の心に棲んだ絶世の艶色と隔世の有徳をもった美女を想って綴った極上の思慮なのである。ところどころを抜くので、陶淵明の理想の女性についての語りっぷりを聞かれたい。
このあと、詩は襟になって香しいものに染み、帯となってその腰を締め、眉墨となって視線となり、靴となって素足に添いたいというふうに、しだいにきわどくなっていく。
さすがにこれでは、甚だ耽美にすぎるというと思ったのだろうから、このあと陶淵明はさらりと風や桐や舟となって、みずから名状しがたい風情の形影に変化しつつ、この世のものとつかぬ女性の「精」なるもの、「神」なるものに溶融してしまう。そんな詩である。
まあ、こんな女がいれば男は夢中になるが、こんな詩を書く陶淵明こそ、いまはもっと夢中に読まれるべきである。よって官能山水と名付けることにした。