父の先見


雄山閣出版 2000
編集:野口鐵郎・三浦國雄・堀池信夫・大形徹
装幀:熊谷博人
番匠 このところついに「千夜千冊」に待望の道教関係の本が登場してますね。シルクロード仏教や魏晋南北朝から漢訳仏教の案内になって、そこで仏教に対する道教の存在が浮上してきました。
校長 そうだね。ほんとうは儒教の歴史も扱いたいんだけれど、中国で新参の仏教に煽られるように浮上したのは道教のほうだったからね。
番匠 われわれもタオイズムや道教はずっと気になっているんですが、ちゃんとした道教研究書を読むことなく過ごしてきて、でもなんとなく親近感をもってきたものですから、あらためて老荘思想と仏教の関係とか『淮南子』(1440夜)から入ってもらったのは、助かります。
校長 そんなに読みにくいかな。日本でもずいぶん道教関係の本は出てるけれどね。
番匠 ちょっとはその手の本を見るんですが、自分らが手にとりやすい道教ものはどうも堅かったりオカルト寄りだったりして、いまいち本格的に取り組めないんです。今夜の本は難しくないんですか。
校長 雄山閣出版が平成12年(2000)から刊行した6巻シリーズの一冊だけれど、やっぱりまだ堅いかな。ただ、どんな未知の分野の「知」も「行」もね、一度は堅い書籍の洗礼を浴びたほうがいい。ぼくはマスペロの『道教』と吉岡義豊さんの研究書からだったけれど、たしかにぎくしゃくしたような案内を読んでいたという感じはありました。でも、そこをいったんは通過しなくちゃね。一方、研究者のほうも、道教論を現代の思索者たちがとりあげたくなるような魅力にもっていくべきですね。最近になって、本シリーズや春秋社の「道教の世界」シリーズが出たので、かなり広くも柔らかくもなってきたけれど、どちらも多数の研究者が分担執筆しているから、全貌を明確につなぎきるのはまだ難しいかもね。
番匠 今夜の雄山閣シリーズは出来はどうですか。
校長 6巻にわたって、視点や問題点はだいたい俯瞰されているのだけれど、突っ込みぐあいは巻によっても論稿によってもマチマチです。
番匠 それでも今夜は『道教の生命観と身体観』だから、われわれにとってもかなり身近かです。だって道教って導引などの呼吸法や本草や漢方などによる養生法が前提になっているから、東洋人には馴染みやすいですよね。
校長 馴染みやすいといいんだけれどね。いまの日本人はタオを本格的に見るというより、健康術や神秘学の一環のように見るからね。そうでなければ風水の親戚みたいに思っている。
番匠 日本人には印象だけは馴染みやすいんじゃないでしょうか。でもそれらがどこからタオイズムという思想になったり、道教という宗教システムになっていったかというと、わかりにくい。
校長 そのうち見えてくるよ。
番匠 基本的なことを聞きますが、やっぱり古代中国人は「老荘のタオ」に発した生命身体哲学を前提にしてきたんですか。
校長 いや、その前がある。老荘以前の歴史がある。導引や漢方も老荘以降です。そもそも殷周時代までの古代中国人の思考に著しいことはね、「生と死」「心と身」とが二つの別々の世界に属すると感じていたことなんです。人は生まれたからには死ぬもので、死ねば肉体は滅んで、精神や霊魂は別の世界で彷徨しているとみなしていた。そのため、そこから二つのプリミティブな考え方が生じていったと見るといい。ひとつは、「生きているあいだにできるかぎり生命と身体の神秘をしっかりつなげておこう」というもので、もうひとつは「心身が分断された死後においてもなんらかの方法で、その分離をくいとめよう」というものです。
番匠 後者の、死後においても分離をくいとめようというのは「尸解」(しかい)などの考え方になるわけですね。
校長 そうだね。当時の古代中国では亡霊にすらも何かにくっつく形代(かたしろ)、つまり「尸」(し)がないと、死者の魂魄がさまよって安定しないという見方をしてたからね。ところがその後の春秋戦国期、とりわけ戦国期になると、生と死や、心と身をつなげている根源的なものとして「気」が想定されるようになってきた。そうすると生と死の奥を握る生命の力そのものが気の集散によって維持されているとみなせるようになったわけです。
番匠 なるほど、そこからが老荘ですか。
校長 そうだね。そこで、『荘子』(726夜)の知北遊篇に「人の生や、気の聚(あつ)まれるなり。聚まらばすなわち生と為り、散ずればすなわち死と為る。ゆえに万物は一なり」というふうに説明されるわけだ。では、この「万物は一なり」の「一」とは何なのかというと、それこそがその前後に老子(1278夜)によって「道」(タオ)と称ばれたものだったわけです。ここから古代中国思想がおおいに変化し、やっと多様になっていく。
番匠 そこに神仙思想や陰陽思想が重なっていった?
校長 いや、それももう少しあとのことだね。まずは、気を操って生をぎりぎりいっぱい延ばすことを夢想して、独特の長寿幻想をつくりあげた。『詩経』の頌歌には「眉寿」という言葉がよく出てくるんですが、これは当時すでに長寿が人生最大の関心事であり、そのことを詩歌に託することが重要だったことを暗示しているんだね。次に、この長寿幻想がやがて不老不死の強調というふうになって、そういう長寿や不老不死を実現している者がどこかにいるとしたら、それは山野の人跡未踏のところの仙境にいる者だろうというので、だんだん神仙思想が芽生えるんです。
番匠 「気」って古代インドのプラーナや古代ギリシアのプネウマと同じようなものですよね。
校長 うん、ずっとのちにはプネウマとかプラーナとかとみなされるけれど、古代中国の気は世界や生命や身体の構成要素そのものじゃありません。生命も人体も気によって支えられているとは考えたわけだけれど、ギリシアの自然哲学のようにそれを世界元素的には見なかった。タオイズムにおいては世界元素は一元的で、それは「道」です。
番匠 はい、なるほど、なるほど。
校長 古代インドのプラーナは「気息」というもので、それがマクロコスモスとミクロコスモスを出入りするんだが、中国の場合は本書の葛兆光さんも書いているけれど、たしかにマクロコスモスとしての世界とミクロコスモスとしての人体は気によってつながっているんだけど、タオイズムではそこには同源的で、同構造的で、相互感応的なのものが動いているという見方がはたらいて、それが身体的な循環系をつくりあげていると考えたわけです。そこを堀池信夫さんは「気は身体の構成要素であるというよりも、げんにある身体という形態に統括してる機能、あるいはそういう機能をもつ何者か」なのだなんて言っている。
番匠 ということは、道教では気は身体に特化されているんですか。
校長 そうだね。儒教や儒学の気はもっと普遍的で世界要素的だけれど、タオイズムではずっと身体的になっていった。そこがまた、タオイズムの生命主義的なところで、その生命主義があからさまに中国の民間信仰を覆ったのが道教というものなんです。
番匠 そうすると古代中国人は要素的なものは何によって見ていたんですか。
校長 陰陽や五行だね。陰陽説と五行説とはちがう出自だけれど、時代的には陰陽五行という見方の発生はやっぱり春秋戦国時代のことです。
番匠 陰陽が要素ですか。
校長 陰や陽は要素ではなくて様相です。五行が要素。白川静さんも書いていることだけれど、もともと陰・陽っていうのは「陰」も「陽」も光が当たったり陰ったりすることでしょう。だから陰陽は気候や気象や季節や地勢や方位の説明に使っていた様相上のカテゴリーなんです。一方、五行は「木火土金水」(もっかどこんすい)の5つの世界要素のことで、こちらは素材論であって要素論です。陰陽は様相論。
番匠 五行には「火は木に勝ち、水は火に勝つ」というような優劣の順序がありますよね。
校長 うん、相生説や相勝説ね。
番匠 最初から「木・火・土・金・水」の順だったんですか。
校長 文献的な初出でいうと『尚書』の「洪範」では「水・火・木・金・土」になってるね。その説明は「水は潤下し、火は炎上し、木は曲直し、金は従革し、土は稼穡する」という程度のもので、まあ、それぞれの属性を世界要素の説明に使っている段階です。ところが最近の研究で、春秋末期に「五声」という考え方も芽生えていて、これが『春秋左氏伝』に「気は五味となり、発して五色となり、章ありて五声となる」というふうに説明されている。このことと春秋期のものとして発掘された編鐘という楽器の音律と調べて比較してみると、どうも五声と五行が対応していたらしいというんだね。そこで「洪範」の「水火木金土」という順は、5・6・7・8・9というふうにきれいに並ぶものとして設定されたということになった。
番匠 へえ、音楽論やリズム論と結びついていたんですか。
校長 そうみたい。しかもここで水がトップにきているのが春秋戦国的なところなんだね。それがやがて「木火土金水」の五行相生説や「土木金火水」の五行相勝説になっていくんだけれど、これはどうも戦国末期以降、とくに秦漢時代になってのことで、あとからカテゴリー編集されて理論化された。そのとき初めて気の思想と交じっていったらしい。ということは何を意味するかというと、初期においては「光を重視した陰陽カテゴリー」と「水をトップにおいた五行カテゴリー」とがあって、それらを気の思想がだんだん包含していったということです。
番匠 水と気のコスモロジー。
校長 そうだね。本書の中でも堀池信夫さんのそういう一章がある。で、このあたりから今度は身体そのものの養生法が絡んでくるわけだ。これは『神農本草経』や葛洪の錬丹術の世界ですね。
番匠 身体重視のタオイズムにおいては、漢方的ないつごろから絡んでいくんですか。
校長 これも話しだすとキリがないけれど、かんたんにいうと古代中国医療は、もともと「巫術系」「鍼灸系」「湯液系」という3つの流れをもっているんだよね。巫術系はアニミスティックでシャーマン系のもの。祈祷や呪術による観念技術的な医療です。鍼灸系は最初は瀉血や切開のための骨鍼・竹鍼・石鍼による医療が先行していて、それがだんだん刺法に転化していった。このとき「気血」を決め打ちしていくということが始まって、これがいわゆる「経穴」や「経絡」の発見になっていく。いわゆるツボですね。ここにお灸が加わって鍼灸医療が発達していった。でも、これはかなりあとのことです。初期の中国医術はまだまだ今日の漢方医学のようなものではなくて、多分に神仙道的で、まあ仙人に近づくための技みたいなものだったということです。だから服餌や辟穀(へきこく)や導引、あるいは錬丹術が中心でしょう。
番匠 千夜千冊478夜に呉澤森の『鍼灸の世界』を紹介されていますよね。あれもかなり近代的な漢方でした。
校長 そうね。だから古代中世で目立つのは本格的な医療ではなくて、むしろ房中なんです。「接して漏らさず」という閨房術だね。
番匠 一方の湯液系は南方で発達したわけですよね。
校長 そうですね。薬草生い茂る地域に発生して、それらを煎じて服用するという方向に発達していった。いわゆる「本草」(ほんぞう)です。伝説的な神農さんが書いたという『神農本草経』がバイブルになるわけだけれど、誰が書いたかは詳細はわからない。おそらく後世の編集でしょう。もっとも陶弘景の『神農本草経集注』ができたころに、『神農本草』という4巻本があったらしいから、似たようなバイブルはあったのだと思いますね。陶弘景の『神農本草経集注』のほうはちゃんと敦煌から出土したものです。
番匠 水銀を使った錬丹術はいつごろからですか。
校長 「丹」ねえ。これもすこぶるあやしい世界だね。『山海経』にも葛洪の『抱朴子』にも、それから『管子』にも「丹」のことがしっかり出ているから、後漢のころには一部で流行していたんだろうね。ただ流行したのはそのころだとしても、漢の武帝の方士の李少君が武帝に丹砂(丹)を操って黄金を見せたとか、『淮南子』(1440夜)に方士が「黄白術」を操って「白金」を生成したというような話が載っているんで、実際にはもっと前から神秘的に錬丹術めいたことを先駆していた例はあったんでしょう。
番匠 金丹も水銀作用ですよね。
校長 『抱朴子』に金丹篇がありますね。「丹」というのは丹砂を焼いて採れる水銀のことですが、常温で液状であることがたいへんめずらしいので、金を生成するといった特殊な力を秘めていると見られたんだろうね。もっともそのころは水銀とともに王水や苺子(いちご)も使っていたらしい。苺子というのは未成熟の時期はシアン化水素酸(青酸)を含むから、金を溶かすことができたみたい。
番匠 よく「内丹」と「外丹」といいますが、あれは何ですか。内丹って内観ですよね。
校長 そうなんだけれど、内丹はけっこう生理的です。正確な定義はないようなんだけれど、「丹」を水銀や薬草などを使ってつくっていこうというのが外丹で、それを体内につくりだそうというのが内丹というふうになっている。でも内丹とか内修という用語そのものは南岳慧思の『立願誓文』で初めて使われ、内丹思想も隋の蘇元朗によって組み立ってきたというんだから、やっと唐代で広がったものなんですね。それまでは「陰丹」と言ってきた。
番匠 それって房中術じゃないんですか。
校長 陰丹も内丹も房中での精気を蓄えたり強くしたりするものだよね。
番匠 セックスの方法。
校長 というより、道教はセックスをする方法とセックスをしない方法を組み合わせていったと見たほうがいいかもしれない。
番匠 精をためる。
校長 気と精をためるためだね。
番匠 そのために「接して漏らさず」を実行するというのは、かなりアクロバティックな感じがするんですが、そんなこと可能なんですか。
校長 ぼくに聞いてもらっても困るけど(笑)、道士たちの房中ではそこを最も重視しているね。
番匠 どうやるんですか。
校長 だからぼくに聞いてもらっても困る(笑)。ぼくは接するとすぐに漏れる(笑)。最近はそれすら地味になっている。
番匠 それじゃタオイズムが泣くじゃないですか。
校長 しょうがないね。もはや老年だしね。強く長生きしたいと思わないかぎり、房中術なんてマスターできないでしょう。ぼくにはそういうサバイバル意志が根本において欠けているからね。
番匠 なんだか諦めているようですね。
校長 なるようにしかならないと思っているのかな。まあ、その話はまたにしよう。
番匠 はい。追求しません(笑)。ところで、道教の閨房術というと男性中心のパトリズムが強いというふうに思うんですが、道教ってやっぱりマッチョなところがあるんじゃないですか。
校長 パトリズムでもマトリズムでもないと思うね。道教にはそもそも「胎」という考え方があって、本書では加藤千恵さんが担当しているけれど、これは男女が交合することで生じる小さな世界そのものなんだね。
番匠 受胎の胎ですよね。
校長 そうだけれど、おそらくもっと普遍的なものだろうね。道教では男女が接すると「胚」「胞」「胎」「肌」というふうな世界充実があると見るんです。六朝のころに『胎精中記経』、正確な名称は『上清九丹上化胎精中記経』というテキストがつくられているんですが、そこでは男女の交わりによって大宇宙の陰陽が交合して、人の胞胎の中に気を降ろすというふうにあってね、それが受胎でもあるとともに、世界との交信ともなっていくと考えられている。こういうものを含めて「内丹」と捉えてきたんだと思う。
番匠 たんなるセックスの仕方でも快楽肯定主義でもない?
校長 むろん快楽を肯定しているよね。ただ、そこに古来からの思想が絡んでいる。もともと古代中国では老荘のように「無」を重視した思潮があったわけですね。それで「無為自然」というような考え方も出てきた。これは「何もしないほうがいい」という極のほうに振った思想です。いわば「無に戻る」。これに対してタオイズムや道教は「無」に発していながらも、そこから生命力が生まれていくという方向になっていった。いわば「無から生む」。この「無から生む」が外丹によって自信をもったタオイストたちが、次に陰丹や内丹に向かっていった原動力になっていったんだろうね。
番匠 内なるエネルギーの開発ですね。
校長 それをきわめて特徴的に象徴するのが「存思」です。

番匠 「存思」って修行法ですか。
校長 観念や思想であって、修行にもなっている。だいたいタオイズムはすべて観念イコール修行ですよ。
番匠 何を観念して何を修行するんですか。
校長 「胎」を感じるための修行でしょうね。『胎精中記経』では存思法は体内の「結」を解くためだというふうに書いている。結というのは人体には受胎とともに幾つもの結び目が出来上がって、これが十二結と十二節をつくる。それが成長しながら「胞」や「胎」になっていく。それらを内観して“解結”していくのが存思だというんです。
番匠 結を解いたらヤバイんじゃないですか。
校長 解くというのは「感じる」ということでしょう。つまり内観です。しかし体内の具体的な部位を実感するというんだね。
番匠 そんなことできるんですかねえ。
校長 タオイストになってやってみなけりゃわからない(笑)。もちろん簡単なことじゃないから、当時もいろいろ体内に神々を想定してそれを観法するようにしたようだよね。『太平経』にすでにそういう五臓六腑の体内神がいろいろ出てきます。
番匠 ああ、そうすると「守一」というのと「存思」は似たものなんですね。
校長 そうです。守一、抱一、存思はつながっている。さっきも言ったように、その「一」というのがタオですよ。
番匠 セックスだけでなく、そこに「胎」を想定して、そこに外なる丹と内なる丹を重ねていくというのは、世界宗教的にもかなりめずらしいですよね。
校長 そうだねえ。これほど古代において「からだ」というものを科学や医学ではなくて思想したというのはめずらしいよね。ただ、それについてはヨーガや密教についても議論しておかないと道教のオリジナリティを特定できない。そういう意味では、まだ道教を世界思想の中で捉えるという作業は本格的なものにはなっていないということです。しかも、そうした道教独特の内丹や内観の修法は随唐期よりずっとあとに発達したものだから、仏教と相い並んでいた道教思想のレベルとなると、いまのところはこのあたりまでのことでしょう。
番匠 ユング派が道教思想を東洋全般の中で位置づける研究をやったんじゃないですか。
校長 ユング(830夜)たちの研究はほとんど近代道教の観察だから、あそこには老荘すら入ってないよね。
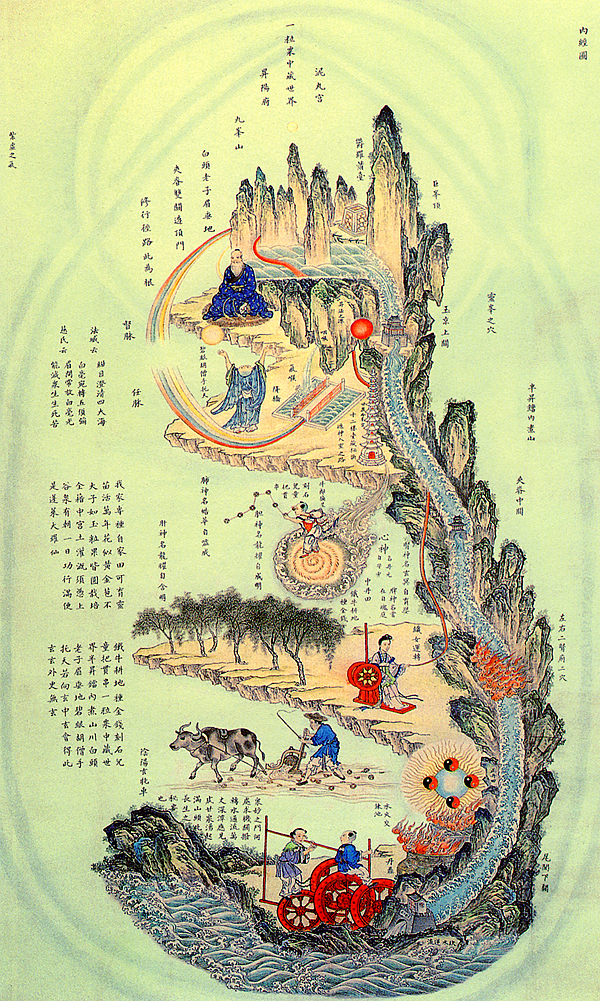
番匠 校長! 結局、校長はタオイズムや道教をどう見るんですか。
校長 ずいぶん端的なことを聞くね。それをちゃんと言うには、いろいろ準備がいるんだな。まず第1にはこれらの背景にある「気」の思想の流れをどう見るかということから評価しなおす必要があるね。そこに東洋思想の大きな底辺を見るべきだからね。第2にそれとともに、インドの「プラーナ」思想とも比較しなくちゃいけない。そこにヨーガも密教もタントリズムも出てくる。もうひとつは第3に、禅と比較する必要があるよね。禅は多分に道教的なるものと共鳴しているからね。でも禅もまた随唐以降に発展するので、これは東洋史がモンゴル帝国をとりこんでからどう変わっていったかということに大きく関係してくるわけです。そのへんのことは、もう少し連環篇がすすんでから話していこう。
番匠 そうですか、待ち遠しいです。だって校長が90年代半ばに「編集八段錦」を提唱されたのって、導引の八段錦を意識されていたからでしょう? 身体派のわれわれとしてはその説明をいつかしっかり聞きたいんです。
校長 うん、そうだよね。きっと導引術や胎息法と情報編集術とをまぜたふうに感じるだろうね。
番匠 そうじゃないんですか。
校長 いろいろです(笑)。導引術や胎息法というのは服気・行気・練気を基本にしているんだけど、情報編集も「服する」「行く手」「練り方」を基本にするからね。まあ、このへんのこともそのうちね。

雄山閣出版
『講座道教 第三巻 道教の生命観と身体論』
著者:金谷治
2000年2月5日 発行
発行者:長坂慶子
発行所:雄山閣出版
装幀:熊谷博人
【目次情報】
凡例
はじめに
Ⅰ 道教の生命観
第1章 道教の生命哲学 ―宇宙・身体・気―(葛兆光・池平紀子 訳)
生命観の変遷/生命の永遠性/身体の永遠性/感応から転用へ/むすび
第2章 気と水のコスモロジー ―中国古代の身体観と医学観―(掘池信夫)
医療と文化的多様性/気の身体観/水のコスモロジーと身体/
気の医療/水の医療
第3章 医書と道教(林克)
はじめに/目録学的に見た医書と道書/房中・神仙と医術/おわりに
第4章 薬物から外丹へ ―水銀をめぐる古代の養生思想―(大形徹)
はじめに/古代の生命観にみる血と丹砂の赤色/
治病薬としての丹砂・水銀/墓と水銀/
水銀と金/淮南王劉安と丹薬/『抱朴子』金丹/おわりに
第5章 本草と道教(松木きか)
問題の所在/これまでの論考/漢代の<本草>/六朝の<本草>/
隋唐の<本草>/仙薬と医学/宋代の<本草>と方薬/
宋代以降の<本薬>と道教/医学と道教と<本草>と
Ⅱ 内丹説の成立
第1章 胎の思想(加藤千恵)
古代人の懐胎十月観/胎の再構成/内丹への展開/結び
第2章 存思の技法 ―体内神の思想―(垣内智之)
序/存思の源流/「一」と「多」/存思の諸相
第3章 唐代の内丹思想 ―陰丹と内丹―(坂内栄夫)
はじめに/陰丹―房中から内丹へ―/唐代の内丹思想/おわりに
第4章 黄婆論 ―『老子』から『悟真篇』へ―(三浦國雄)
黄婆は人か/黄婆の祖型/沖気考/黄婆の性格
Ⅲ 内丹説の展開
第1章 全真教と南宗北宗(横手裕)
はじめに/全真教の成立と展開/初期全真教の教説/
いわゆる南宗の人々/江南における全真教の変化/
道統説の統合/おわりに
第2章 陸西星の内丹思想(秋岡英行)
はじめに/陸西星について/陸西星の内丹の基本的原理/
陸西星の内丹のプロセス/おわりに
第3章 「張三峯」の房中術(猪飼祥夫)
はじめに/房中術の展開/「張三峯」と「張三丰」/
「三峯採戦の術」と張三峯/「三峯」は人か/
虚構としての「張三峯」/おわりに
第4章 道教内丹説のエピローグ ―陳攖寧「仙学」小論―(沈恩明・畑忍訳)
序/「仙学」唱道者 陳攖寧/陳攖寧の「仙学」論/
「仙学」の歴史的位置づけ
編集担当・執筆者紹介