父の先見


東京大学出版会 1998
Norbert Bolz
Die Sinngesellschaft 1997
[訳]村上淳一
装幀:鈴木堯・瀧上アサ子・光川裕介
いま、世界が病気にかかっているとしたら、それは「意味」が失われているからだ。いま、世界が再生しようとしているなら、それは新たな獲得の方法によって「意味」の意味が捜し求められているからだ。
ドイツ語の「意味」(Sinn)はもともとは「旅する」とか「進路をとる」という古語だった。だとすると、まさに「新たな方向を示す意味」が、いま見失われたままなのだ。
これを「ヴィジョンの喪失」だと思ってはいけない。ヴィジョンはさまざまな「思考」のフィギュアやプロフィールを組み合わせなければ、まず生まれない。その思考は何によって支えられるかといえば、時間の旅をしてきた「意味」によって支えられてきた。その意味は民族や風土や歴史といっしょくたに育ってきたものだ。
ところがそれが、いつのまにか消されたか、何かによって取り替えられたか、どんどん忘れられたか、軽々しく扱われるようになった。意味で「価値」を示せなくなっていた。企業も学校も国家も共同体も家族も、気がついてみると「組織化された無知」のフリをするようになったのだ。あるいはグローバリズムがもたらしたギョーカイ用語だけで価値の説明をすますようになったのだ。
これは「組織化された無責任」と言ってもいい(ベック:1347夜参照)。ノルベルト・ボルツはそのことをまとめて「意味社会の喪失」あるいは「意味に餓える社会」と名付けた。
この意味喪失社会では、それなら意味に代わって何が浮上しているのかというと、それが「リスク社会」(ベック)や「スポーツ社会」(ナイトハルト)や「体験社会」(シュルツェ)なのである。
本書はドイツ・ポストモダン派の旗手が綴った一滴の快著だった。ボルツは本書の前に『仮象小史』『批判理論の系譜学』『カオスとシミュレーション』『グーテンベルク銀河系の終焉に』(いずれも法政大学出版局)、および『制御されたカオス』『カルト・マーケティング』といった著作などをものしていたらしいのだが、ぼくは前2冊以降のものは読んでいない。本書のあとに何を書いたかも知らない。
しかし本書や『グーテンベルク銀河系の終焉』を読んだかぎりは、なかなかの腕前だ。ポストモダン議論についてはフランス派やアメリカ派にばかり付き合わされてきて、少々うんざりになっていて、なかでデイヴィッド・ハーヴェイの経済地理学的なポスモダニズム論くらいが勝ち残ったように見えていたのだが(そのうち千夜千冊します。もうちょっと待ってね)、どうしてどうしてドイツ派も、ボルツを見るかぎりは、骨がある。とくにハーバーマスに噛みついているところは、おもしろい。
それは、そうかもしれない。なにしろこの国にはマルクス(789夜)、ニーチェ(1023夜)、カフカ(64夜)、マッハ(157夜)、ハイデガー(916夜)、ハイゼンベルク(220夜)、ベンヤミン(908夜)、アドルノ(1257夜)がいて、それからハーバーマスやウルリヒ・ベックやニクラス・ルーマン(1349夜)に及んできたのだ。意味と思考のフィギュアとプロフィールを生産しつづけたのは、なんといってもドイツだったのである。
それがナチスと敗戦でしばらく控えていただけなのだ。そこには思想のリスクと戦争のリスクがたっぷり用意されていた。ボルツのような快速の走破者が出てきても当然だった。
ありていにいえば、今日の社会の特質は「複雑性」と「不確実性」(または不確定性)と「不透明性」にある。この3つは今日の社会だけではなく、近代社会が確立した当時からの特質だ。
社会が複雑になったというのは、事態やシステムがこみいってきたというだけのことではない。そこに自分が組みこまれて自己包摂的で自己準拠的になったため、自己と事態の見分けがつきにくくなったからである。GPSとネットにつながったケータイが、そのことをよくあらわしている。そのため、なんであれ「編集なき情報」(意味を問わない情報)に頼ったまま、その複雑性のなかにぷわぷわ浮かんでいるしかなくなったということが、複雑な社会の属性になってしまったのである。
仕事も複雑なものに向かうしかなくなっている。一番わかりやすいのは電子システムを設計する仕事と、そのミスをデバッギングする仕事が、ほぼ等量のお仕事になっているということだろう。これを、精神的障害の数のぶん、それを知ってもらうための情報とそれを手当てするための人間の数とがだんだん等量に向かっているという例におきかえてもいい。
なぜこんなふうになるかといえば、世の中の複雑性は不確実で不確定なものによって律せられているからだ。ということは、そこには必ずや「偶然」が出入りするようになったということで、そこにリスクとオプションが名状しがたく抱き合わせになっているということだ。つまりはどんな仕事でも、「偶然が必然になっている」。
本書ではこの不確実性や不確定性や偶然性のことを、まとめて「コンティンジェンシー」と呼んでいる。コンティンジェンシーについては、ここ数夜にわたってあれこれ角度を変えてスケッチしてきたので、もう説明はいらないだろう。
複雑なしくみにコンティンジェンシーがはたらいているということは、複雑で不確実な事態やシステムには“自分入り”のコンティンジェンシーが動いているということだ。ボルツはそこからこそ「意味」が生まれるとした。「意味は複雑性の自己記述だ」ともみなした。
すでに前々夜でも説明したように、ルーマンもまた同じことを見抜いていた。そこにはオートポイエーシスがはたらいて、社会システムがコンティンジェンシーに出会うたびに意味を生成していると考えた。いずれも高度な社会学だった。
しかし、このような見方は容易にはとりにくい。難解でもあろう。そこで、複雑な社会に誰彼なく組みこまれることになった多くの者たち(国家・企業・経済機関など)は、ごくごく安易な二つの“逃げ”を打った。
ひとつの“逃げ”は、統計や確率によって複雑性を少しでも解体し、コンティンジェンシーに目をつぶるか、これを平均化することだった。あるいはこれを巧みにリスクヘッジすることだった。もうひとつの“逃げ”は、何らかの規約やルールやレギュレーションを外から導入して、これを内部統制にまで持ちこむことだった。これがグローバル・ルール主義の蔓延になった。またコンプライアンスの蔓延になった。
いずれにしても現代のシステム社会では、国家も組織も経済も、自分ではコンティンジェンシーから「意味」を生み出せなくなったのだ。そのかわり、コンティンジェントなリスクだけを相手にぐるぐるまわりに押しつけた。
かつて「意味」は聖なるものの顕現によって示されていた。これがルドルフ・オットーやミルチア・エリアーデ(1002夜)の考え方である。この考え方は、いまでも宗教や神学や民俗学に綿々と生きている。
この考え方が生きているところでは、不確実性も不確定性もそのまま承認される。そこでは、信仰者は自分がコンティンジェントであることを疑いもしない。そもそも宗教というもの、世と人のあいだに出入りするいっさいのコンティンジェンシーを承認してあげる“魔法の学校”なのである。
こうしてユダヤ=キリスト教は、世界で最も強力な「意味の市場」をつくりあげるにいたったのだ。ところがそういう宗教でも、一番重大なところは「意味」に転化できないできた。ヌースとか福音とか真如とかマンダラとしか言うしかなかった。
そのうち近代国家が確立してくると、その歴史的コンティンジェンシーと近代的個人のあいだの認知ギャップをめがけて、機能や統計や自己責任や代理業務や機械が次々にさしはさまれていった。それがいつのまにか拡大拡張し、そのままコンピュータ時代に突入することになった。ついでに“救済のふりをした民主主義”や“人間の顔をした社会主義”が綿密に組み立てられていった。けれども、なかで最も巨大化したのが「意味を失った市場」なのである。
むろんそういう市場のような装置に、本来の意味の歴史があるはずはない。意味喪失社会に代わるものばかりが、体よく、効率よく、確立されていったのだ。
しかも、この装置の担い手は「はいはい、あなたは、みなさんという個人というものですよ」と信じこまされた。この不幸で、新たな宗教者扱いをされる担い手は、こともあろうに「インディビデュアル」(分割できないもの=個人)とさえ呼ばれ、すっかりおだてあげられることになったのだ。
かくしてもはや、世の中から意味のカリスマも意味のスターもいなくなった。もしもそんなことを標榜する者がいれば、たちまちカルト主義者とか狂信者とか変人とかと例外者扱いされた。
けれども社会というものはこれでは困るから、そこで新しいカリスマやスターをつくりあげることになった。たとえば映画スター、たとえば経営者、たとえばスポーツマン。かれらは新たな意味実現のためのシンボルなのである。これなら他の多くのインディビデュアルたちも、この新たなシンボルをめざして自己努力してくれる。
が、こうなると、もう、本来の意味なんてどうでもいいわけだ。サクセスと成長と個性化だけが、「意味がつくる文脈」に代わるあらゆるシナリオのプロットになればいい。マスメディアはこれに乗っかった。
さすがにハーバーマスやルーマンらはコミュニケーションの本来と行為の本来に意味を取り戻そうと考えたけれど、事態はとまらない。かえってコミュニケーションは通信の自由の、行為は経営や自己の、実現のためのパフォーマンスだとみなされるばかりとなったのだ。
知覚にはゲーティングというものがある。知覚が刻みこまれるたびにゲートを通って、印象が強調されることをいう。
かつてウンベルト・エーコ(241夜)は、知覚が思考や意味を獲得するプロセスにも、このゲーティングがあるはずだと主張した。そのゲートをちゃんと組み立てなおしさえすれば、世界はいつだって世界像(ワールドモデル)を取り戻せると主張した。その通りであろう。
一方、今日の社会にも今日のシステムにも今日のネットワークにも、いろいろなゲーティングが設(しつら)えられている。ただしかし、この社会やシステムやネットワークの中のプロセスのゲートでは、何かが必ず「意味の身代わり」をする。また「肩代わり」をする。問題は、その身代わりの「身」、その肩代わりの「肩」は何なのかということだ。
これをたんに手続きとかオペレーションとかマニュピレーションというふうに見てはいけない。それはデジタル・エンジニアが打つアルゴリズミックな“逃げ”の説明だ。そんなバカなことはない。どんなゲートも、本来の意味の代わりのエージェントか、擬似エージェントになっているはずなのだ。
そうであるにもかかわらず、これらの「身」や「肩」をいくら集めても世界像を再構成してはくれない。してくれるのは、高速の検索だけなのだ。このことをアルノルト・ゲーレンは「こうして意味への問いは棚上げされるのだ」と言った。ニクラス・ルーマンは「かくて意味喪失を克服したいという要求だけが残った」と言った。
もっともずっと前に不思議の国のアリスは、こう言ったものだ、「もしもしそこに意味がないのなら、ずいぶん仕事の節約になるわ。だってそれなら意味を捜さなくていいんだもん」。
そうなのだ。意味を問いかけるなんて、このポストモダンな世の中では、自分は迷い子になりましたと言っているようなものなのだ。意味や思考は、とうてい外部に委託できるものではなかったのである。
ボルツは本書の後半ではメディア社会をとりあげる。その見方は少しおっちょこちょいではあるけれど、一貫している。テレビもウェブも、意味と無意味を、同意と反意を、質問と解答を区別なく運ぶということだ。
いくらテレビがクイズ番組で「知識」を提供しようとしても、視聴者はそこに提示された「正しい」と「まちがい」を憶えてはいられない。コンピュータもネットワークも、どれが質問でどれが解答であるかを、自分ではゼッタイに見分けない。コンピュータが得意なパターン・マッチングには「意味」は置き去りにされているからだ。
しかしそれでもなお、デシタル・メディアは意味社会を変えていく。高速・大容量に加えて、そこにはインタラクティビティがあるからだ。互いに情報をやりとりさえしていれば、それで仮構の意味社会が維持されていると思いこめるようになったのだ。
けれども、このインタラクティビティは実はつながってはいない。たとえば、至便性と安全性を求めるユーザー、個人データの軌跡を知りたがる企業、規制をめざす政府(とくに中国のような政府)、ウィルスを恐れないハッカー、ネットオークションに大事なものを売り出すお母さん‥‥。これらはズレあっている。決してつながらない。
これは、今日の社会が本当の「意味」で社会を築いてはいないということなのである。共通項はグローバル・ルールだけ、あとはローカルな才能とローカルな技術が沸騰していながらも逼塞しているということだ。
でも、だからといって寂しくはない。ケータイとノートパソコンとアイパッドくらいがありさえすれば、「意味」でつながらなくたって、どんな情報にも困らないからだ。システムやネットワークは、決して難問な「お題」など出してはこないのだ。
それゆえ、もしも今日の社会に本当の「意味」の担い手たちがいるとしても(当然、人間に心や意識や言語があるかぎり、本当の担い手はいくらでもいるのだが)、その担い手はネットによってかえってもっと見えないところに引き下がらざるをえなくなったのだ。じゃあ、諸君、どうする?
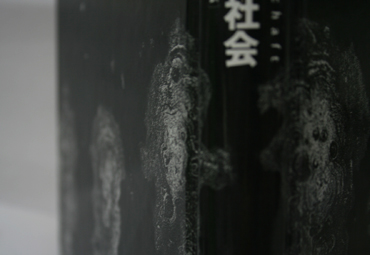
【参考情報】
(1)ノルベルト・ボルツは1953年の生まれ。ベルリン自由大学のヤーコプ・タウベスのもとで宗教哲学を修め、自身はアドルノ美学で博士号を取得した。両大戦にはさまれた時期の哲学的ロマン主義の研究で著作テビュー(『批判理論の系譜学』)したのちは、上記に紹介したような著作をたてつづけに書いたようだ。1992年からはエッセン大学のコミュニケーション学の講座を担当した。
ちなみにボルツの考え方の多くは、ぼくにはベンヤミンこそが先取りしていたと思われるのだが、ボルツ自身はそのベンヤミンをアドルノが引き取った方法(否定の弁証法)が気にくわないらしい。
(2)上には書かなかったが、ボルツのポストモダン論は、ポストモダン社会では既存の理論が“製作”した「モダンな意味」に足をとられないほうがいいというふうにもなっている。それよりむしろ徹底的にネットで言葉を交わして、加工・訂正・編集をしていったほうが、かつての「本来の意味」に近づける可能性があるというような、そういう判断にもなっている。
しかし、デジタル・メディアやコンピュータ・ネットワークの現状からすると、これだけでは足りないだろう。ぼくの考えでは、システムやネットワークにも、そろそろメタテキストかワールドモデルが装填されるべきなのだ。ただし、それは必ずしも公開されたり商用される必要はない。クラブ財になったままでもいい。
(3)ボルツとともに、ひとつはヴィレム・フルッサーの『サブジェクトからプロジェクトへ』『テクノコードの誕生』(いずれも東京大学出版会)を読まれるといい。
また本書の訳者の村上淳一は法学史を専門とする法学者だが、めっぽう柔らかい。『仮想の近代』『現代法の透視図』『法の歴史』(いずれも東京大学出版会)を覗いてみられるといい。