父の先見


現代企画室 1996/松籟社 1998
René Schérer
Zeus Hospitalie 1993/Utopies Nomades 1996
[訳]安川慶治 [訳]杉村晶昭
編集:太田昌国・向井徹 協力:鵜飼哲・篠原洋治 装幀:有賀強
編集:竹中尚史 協力:鵜飼哲・篠原洋治 装幀:有賀強
いまさら言うまでもなく、ぼくの仕事は編集工事だが、そのために何をしてきたかというと、しばしば「概念のマッピング」をする。新しい本から気になる概念を抽出したり、それにまつわる既存の概念をあれこれ連想したりしつつ、それを一枚の紙の上に並べる。並べるときに組み立てをする。
一枚の紙というのは当面向かってみたい「世界」にあたる。その「世界」に出会いたくて、そういうマッピングをするのだが、いつもわくわくする。そういうことを30代に始め、40代になってからはそのリメークや転換をルーティンのように準備運動にしてきた。
概念を並べていくと、遠近、前後、吐呑、重畳などの関係が出てくる。並べてみないと、関係の立体性や多層性はなかなかわからない。どこにシソーラスが潜んでいるかも、わからない。「概念とは来たるべき出来事の輪郭、形状、布置である」とドゥルーズ=ガタリが『哲学とは何か?』に書いていたが、まさにその通りなのだ。概念たちの一群をそのように「来たるべき出来事」に向けておくために、編集がある。そんなふうに仕事をしてきた。
ホスピタル、ホステス、ホテル、ホスピタリティ、ホスピスはほぼ同じ概念の中にある。ここには、よく知られたシソーラスがある。旅する者を泊め、傷ついた者を癒し、遠方の友を労い、酒肴を振る舞い、ときに語らう。これらは広い意味で「歓待」あるいは「もてなし」だ。そこには迎える者と迎えられる者がいる。主と客がいる。
歓待は予定されていることもあるし、不意に始まることもある。しかし、ここが重要なところだが、たいていは一時的である。だからこそ出入りが頻繁なホテルも病院も成立する。茶の湯もホスピスもボランティアも成立する。それなのにカントが『永久平和について』のなかで「普遍的歓待」(allegemeine hospitalität)を望んだのは、意図はわかるけれど、ぼくには肯んじられない。
歓待は一時的なので、主客が問われることもある。問われるのは「身元」だ。このことがのちに宿泊や病院や店舗や遊興におけるレジストレーションを発達させた。いまではそれがネット社会のIDになった。
こうして世の中のホスピタルな出来事の大半が、実は大きなノマドな出来事の一部であったろうことがあきらかになっていく。歓待はノマドの多様性がもたらしたそのつどの主客の関係の突起なのである。
ルネ・シェレールの『歓待のユートピア』(現代企画室)と『ノマドのユートピア』(松籟社)を続けさまに読んだとき、以上のような感想をもった。20年ほど前のことだ。2冊ともにぼくには馴染みのトレース思想的な愛嬌があって、どこか懐かしい読後感だったが、いささか悩ましい本でもあった。
歓待とノマドをユートピックに捉えたいというところが悩ましく、少しおめでたいと思ったのである。ただしなぜそうなるかは、よく伝わってきた。シェレールは、研究者としてのルーツからいうとシャルル・フーリエ(838夜)の「ファランジュ」にぞっこんなのである。
それはそれで大いに結構なことで、ぼくもフーリエにはいっとき恋闕(れんけつ)のようなものを抱いたものだが、シェレールの2冊の本がトレース思想としての愛嬌があるのに、悩ましく、また少しおめでたいと感じたのは、いくらフーリエ主義者だからといって歓待やノマドを理想化しすぎているのではないかという心配が過(よぎ)ったからだった。
シェレールとしては理想化したい事情があった。理想化のための研究もしていた。トゥール大学でフッサールの現象学やハイデガー(916夜)の存在学への傾斜を通して、「アソシアシオン」(協同体)の夢を掲げたフーリエについての執拗な研究で名をあげていたのである。
けれどもそれだけなら、フーリエ主義と歓待思想やノマディズムが結託していくことはなかったかもしれない。シェレールは途中から変わったのだ。その変わり方が悩ましい。
1968年のパリ5月革命の機運が弾んで、翌年、実験大学としてのヴァンセンヌ大学(CUEV)が誕生した。それまでトゥール大学の助教授だったシェレールはそこに呼ばれた。1969年のことである。シェレールを呼んだのはフランソワ・シャトレとミシェル・フーコー(545夜)だ。この年、ジル・ドゥルーズ(1082夜)がフェリックス・ガタリと出会っていた。ドゥルーズ=ガタリが始まったのだ。
シェレールはその後、CUEVがパリ第8大学になったのちの1991年まで名物教授として名を馳せた。CUEVにはリオタール(159夜)やミシェル・セールが加わっていった。

こうしてシェレールのフーリエ熱にドゥルーズ=ガタリのノマディズムが二重焼きされ、その印画紙の上に思想のガーデニングが施されていったのである。
ロラン・バルト(714夜)の『サド、フーリエ、ロヨラ』が、ドゥルーズ=ガタリのノマドロジーをめぐる議論が、ジョルジョ・アガンベン(1324夜)の「来たるべき共同体」が、次々に挿し木されたり、植え替えられたり、プランター化していった。一種独特のノマディック・ホスピタルな歓待をめぐる思索が、シェレールなりに育まれていったのである。
きっとそういうことだったのだろうと思う。そして、ここまではたいへん香ばしい。すぐれて編集的でもある。ところが、どこでそのようになっていったのかはわからないが、やがてシェレールのノマディック・ホスピタルな歓待思想は「ユートピアの事例」として恒常化されていくようになった。ここからは、ちょっと待ってほしいというところだ。
フーリエの『四運動の理論』や2000人社会「ファランジュ」をめぐる理想主義的な仮説と構想は、そうとうユニークである。ヘルメットをかぶって連日デモをしていた学生運動時代のぼくも、いっときかなり浸ってみた。その構想はいまふりかえっても妙に懐かしく、またなんとも悩ましい麻薬のような魅力をもっていた。
19世紀初頭、フーリエは同時代人たちから「パレ・ロワイヤルの怪人」と呼ばれていた。その怪人が「情念引力」によって構成される「アソシアシオン」(共同体というより協同体=アソシエーション)を構想した。
大略、人間社会には大きくいえば四つの運動(社会的・動物的・有機的・物質的な運動)が絡んでいるが、それらは情念引力(感覚情念・感情情念・配分情念など)によって相互的な関係を動かせるはずなのだから、その案配を最大公約数ないしは最小公倍数にした機構をちゃんとつくれば、新たな世界単位が生まれるという構想だ。
まさに麻薬か神酒のような魅力を放つ構想だが、『四運動の理論』(現代思潮社)を読んでみるとどこにも疚(やま)しいものがない。たいそう敬虔で、愛に充ちている。実践性ももっていた。よく知られるように、フーリエはマルクス(789夜)によってサン・シモン、オーエンらとともに空想的社会主義者のレッテルを貼られたけれど、空想に耽っただけではなかった。実際にファランジュの稼働実験にとりくんだのである。
それがどういう経緯だったのかは、838夜にも書いたことなので今夜は省くけれど、一言でいえば「概念と理念による理想的組織生成のアジェンダ」が実社会に向かって発動されたのだった。ファランジュの中心に予定される生-活動の建物を「ファランステール」と呼ぶのだが、ファランステールっぽいものも各地に建設された。
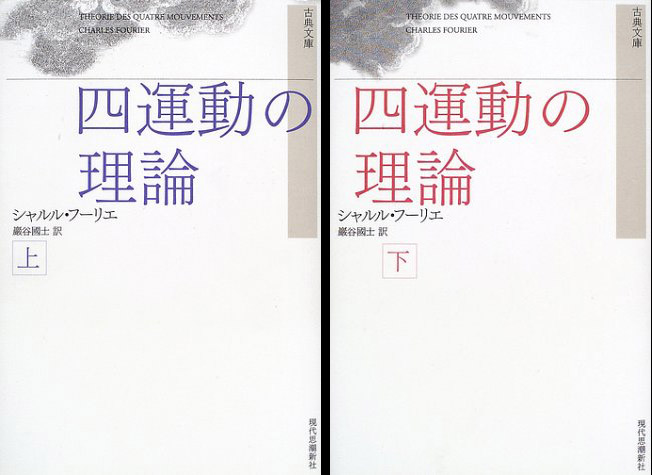
シェレールはこのようなフーリエ的協同体をめぐる夢想テキストに、さまざまなガーデニングを施していったのだ。さぞかし愉しい思想ガーデニングだったろうと思う。そこにはもちろん方針がある。それが「歓待」もしくは「ノマド」をもってガーデニングするということだ。
が、ぼくが思うに、そのような思想印画紙上のガーデニングは「数寄の行為」であるべきなのである。マッピングの痕跡を残したままにしておくべきなのだ。理想化や文脈の完成に向かってしまっては野暮なのだ。ぼくは『歓待のユートピア』と『ノマドのユートピア』を読んだとき、そう感じたのだった。
ここで少しばかりぼくの見方の話をしておくけれど、もともと「歓待」(ホスピタリティ=もてなし)も「ノマド」(ノマディズム=一所不在)も、ぼくの長きにわたった思索的的実践のための主題のひとつだった。
ただ、ぼくにとってはそれらは必ずしもユートピックなものではなく、すぐれて夾雑的であり、決してセンタリゼーションをおこさない遍在的なものなのである。理想があったとしても、部分理想であり、隙間や不足さえあるものなのだ。またカント的な永久を誇ってはならないもので、たえず出たり入ったりしているべきものなのだ。
ぼくがナム・ジュン・パイクと「ノマド」をめぐっていろいろ語りこんだのは、パイクが白川静の漢字観と「遊」の編集方針に関心を寄せたときからだから、かれこれ40年になる。ぼくはそのころパイクが口にしていた「遊牧的定住民」という言い方が気にいっていた。
その後、1978年の「遊」10・11号に書いた「存在と精神の系譜」という大部の原稿を、あらためて『遊学』(大和書房→ちくま学芸文庫)にまとめたとき、「142人のノマドロジー」というサブタイトルをつけた。ピタゴラスからマンディアルグまでの東西の遊学趣向の142人を採り上げたものだが、見直してみると、自分がほとほとノーマッドな思想者や表現者に惹かれてきたことがよくわかったからだ。
けれども、ぼくのノマドロジーは遊牧論でもディアスポラ論でもなく、また撒布論や撒種論でもなかった。遊民遊学的な「数寄の感覚」というものに近かったのだ。トレースや転移やスクリーニングやリミックスを極めること、それがぼくにとってのノマディックな数寄なのである。
当時の白川さんは白川さんで、「あんなあ、ノマドっちゅうものは出遊(しゅつゆう)のことやで」と言っていた。ノマディックな概念の見取り図を「おでかけ」状態にすること、それが「遊」であり「数寄」なのである。
歓待についてはどうだったのか。ぼくが「もてなし」を重視したのは平安建都1200年を記念するプロジェクトの企画委員になったときである。このとき委員会に請われて、京都千年を一貫して象徴する三つ揃えとして「もてなし・ふるまい・しつらい」という言葉を提案した。
これらは平安期以来の古語で、漢字で綴れば「持成・振舞・室礼」になる。今日と意味合いがやや違っていて、「もてなし」は『源氏』に「撥(ばち)を持て成す」とあるように、実際に楽器や道具をどうやって使ってその場の者たちを感じ入らせるというスキルのことで、当初はホスピタリティ(歓待)という意味はなかった。
「しつらい」(室礼)は調度を揃えること、それも有職故実にもとづいた調度を用意することで、それが「支度」(したく)だったのである。そのうちインテリア一般を整えることが「しつらい」になった。「ふるまい」も、本来はフリ(振り)とマイ(舞い)によるもので、一さし舞ってみせることが振る舞うことだったのだが、やがて大盤振舞というように料理や御馳走をふるまうことにもなって、振舞い酒などにも転化していった。
とにもかくにもこれらのこと、すなわち「出遊」「もてなし・しつらい・ふるまい」「数寄」が、ぼくの「ノマドロジー」の原点であり、「歓待」の本来の姿恰好なのである。だから、それらをユートピアや理想に結び付けてみたいとは、毫も感じてこなかった。
それなのになぜ、シェレールは歓待もノマドもユートピックに仕上げたかったのだろうか。なぜ一時的な香ばしさにとどめておけなかったのだろうか。なぜ不足があってもかまわないと思えなかったのか。そうしておいたほうが、曇天の海辺の花のように、もっと懐かしいものになっていたはずなのに。
歓待やノマドの議論は、シェレール以外の場面でもいろいろ議論されてきた。
たとえばジャック・デリダの『歓待について』(産業図書)は、ソポクレス(657夜)やプラトン(799夜)やクロソウスキー(395夜)を引き込んでいた。八木茂樹の『「歓待」の精神史』(講談社選書メチエ)は、北欧神話のオーディンの歓待を端緒にしてフーコーやレヴィナスに及んでいた。
シェレールにも『ドゥルーズへのまなざし』(筑摩書房)があってノマドロジーの検討をしていたし、これがシェレール入門だと自負していたマキシム・フェルステルの『欲望の思考』(富士書店)は、シェレールがなぜノマディックな歓待に溺れていったのかを検討していた。
これらを読んでとくに盛り上がったわけではないが、あらためてシェレールがフーリエとドゥルーズを重ねていった事情に関心が出てきた。なんといっても当時のノマドロジーといえば、ドゥルーズ=ガタリの『千のプラトー』(河出書房新社)がノマド思想の母体になっていたのである。
しかし『千のプラトー』は実は理想には走っていない。ぼくからすると、あれこそは数寄っぽい。シュレールはそこが甘かったか、読みまちがえたのだ。
話を戻して、おそらく歓待はもともと擾乱的で、反時代的なのである。また、なによりも国家理性(レゾン・デタ)に抵抗するものなのである。歓待は「おもてなし」でないことはないが、国家理性にべったりなどしない。してほしくもない。
といって、ノスタルジックな過去の遺物なのではない。ホスピタル、ホテル、ホステス、ホスピタリティ、ホスピスは、いずれも歓待行為の持続性や現在性をあらわしている。
しかしながら、歓待は収入と支出のバランスからはずれたものでもあろう。ヨーロッパの例でいえば、十字軍の遠征騎士たちを街道の住民たちがもてなしたとき、ホスピタリティとホスピタル性やホテル性やホスピス性がつながった。
やがてヨーロッパが産業革命を通過すると、工場に出向く市民たちがふえてきた。家で仕事をしているわけではない。畑で何かを耕しているのでもない。多くの老若男女が工場に出掛けていくのだ。
働いて帰ってきて、また翌日も働いて帰って、一定の賃金をもらう。いったい、この「工場」とは何なのか。出先機関であるのに、そこには生産も利潤もあった。マルクスはそこには搾取がおこっているのだと断じたが、そのようにみなされるまでは、工場をこそなんとか理想化する必要があった。そこで、フーリエが工場に代わるファランジュを構想したのだった。
けれども、こうした工場の理想化は、やがて企業の側こそが心掛けるものになっていった。しばらくはそれこそマルクスが言うように苛酷な労働と搾取が続いたのだが、しだいに工場は企業家の勝手な思惑ではあったにせよ、それなりに理想化されたのだ。少年労働や女工哀史は少なくなっていた。
もちろん、こんなことが「歓待のノマドロジー」になるはずはない。そうだとすれば、今日の社会思想として、フーリエの理想をあらためて過剰に理想化するのは、やっぱり変なのである。まして「そこ」をノマドにしたければ、むしろファランジュは個々の参加がもう少し自由なスタイルに変じていったほうがよかったのである。
それがいま、PCやスマホになっていきつつあるとは言わないけれど(ネットの中のフーリエ幻想はグーグルやフェイスブックこそが振りまいているのだから)、そろそろノマドロジーも新たな意匠に着替えるべきだった。
ところで余計なことかもしれないが、シェレールには変わった兄貴がいた。長らく「カイエ・ド・シネマ」の編集長をしていた映画監督のエリック・ロメールが実兄だ。
ロメールはヌーヴェル・ヴァーグの最後の旗手で、「獅子座」「コレクションする女」「四季の物語」「聖杯伝説」などを演出して、理想的な映像美を追った。『美の味わい』(勁草書房)などの著書もある。シェレール兄弟は二人が二人して「理想を語るに足りる変わった兄弟」だったのである。それはそれでバルテュス(984夜)とクロソウスキー兄弟のように、羨ましい。

⊕ 歓待のユートピア ⊕
∈ 著者:ルネ・シェレール
∈ 訳者:安川慶治
∈ 装幀:有賀強
∈ 発行人:北川フラム
∈ 発行所:現代企画室
∈ 印刷所:中央精版印刷株式会社
∈∈ 発行:1996年10月30日
⊕ ノマドのユートピア ⊕
∈ 著者:ルネ・シェレール
∈ 訳者:杉村晶昭
∈ 装幀:有賀強
∈ 発行者:相坂 一
∈ 発行所:松籟社
∈ 印刷所:亜細亜印刷
∈∈ 発行:1998年4月20日
⊕ 目次情報 ⊕
∈∈ 第1部 星雲(間隙の徳
∈ 公的な歓待―カント『永久平和のために』
∈ アナーキーの連合主義―古代ローマの歓待・プルードン『連合の原理』
∈ 客の席)
∈∈ 第2部 星座(両義的な客―アイスキュロス『救いを求める女たち』・ホメーロス『オデュッセイア』
∈ もろ手で迎える女主人―クロソフスキー『歓待の掟』・フーリエ『愛の新世界』
∈ 行きずりの客―パゾリーニ『テオレマ』
∈ 二人の守護聖人―ジュネ『恋する虜』・フローベール『聖ジュリアン伝』)
⊕ 目次情報 ⊕
∈∈ 輪郭
∈∈ 生活態
∈∈ 文化
∈∈ 四つの肖像
∈∈ 後書き―フーリエ横断
⊕ 著者略歴 ⊕
ルネ・シェレール(René Schérer)
フランスの哲学者、パリ第八大学の名誉教授であり、とりわけ、シャルル・フーリエの研究者として彼の『愛の新世界』に基づいて著された歓待論の古典『歓待のユートピア』、およびジル・ドゥルーズの概念を援用してフーリエの世界を描いた『ノマドのユートピア』で知られる。