コンセプチュアル・アート
岩波書店 2001
Tony Godfrey
Conceptual Art 1998
[訳]木幡和枝
コンセプチュアル・アートはデュシャンの『泉』ではなくて、レンブラントの『聖家族とカーテン』(1646)に始まっていた。のみならず、マネの『フォリー=ベルジェールのバー』(1882)もマラルメの『骰子一擲』(1897)もコンセプチュアル・アートだった。いや、芸術がつねに概念(コンセプト)であるとするのなら、コンセプチュアル・アートは芸術の開闢とともに始まっていた。
しかし、1967年にソル・ルウィットが『コンセプチュアル・アートに関するパラグラフ』で、また1969年にジョセフ・コスースが「哲学のあとの芸術」でコンセプチュアル・アートの定義を初めてしようとしたことに従うなら、その前哨戦はさかのぼってもキュビズムまでということになる。


ピカソが『籐椅子と静物』(1912)でプリントのオイルクロスをそのまま貼って、JOUという文字を描きこんだとき、次の4点においてコンセプチュアル・アートは萌芽したのだ。
すなわち、①レディメイドの先触れとして日常のイメージや事物を導入した、②認識論つまり表象と、われわれが何を知っているかという問題に公然ととりくんだ、③見る者の期待を裏切ろうとしている、④街のなかの生活と密室的なアトリエとの融合をはかった。
あとはデュシャンの二人の兄貴がキュビズムの申し子だったことを付け加えればいいだろう。むろんデュシャンもキュビズムの絵を描くことからアーティストとしての出発をした。
そのデュシャンが『階段を降りる裸体No.2』(1912)をアンデパンダン展に出品したとき、審査委員会が「裸体はけっして階段を降りたりしない」とバカなことを言ったこと、キュビストたちすら「多少見当ちがいの作品ではないか」と言ったこと、二人の兄に「せめて題名を変えるように進言してくれ」と言ったキュビストがいたことが、デュシャンを心底呆れさせた。デュシャンは何も変更せずに作品を撤去し、二度と絵を描かなくなった。それがデュシャンに「レディメイド」を発想させた。


デュシャンが次にしたことまで話しておけば、もういいだろう。デュシャンは、便器をさかさまにして"R・マット"と署名した作品『泉』が展示拒否にあったとき、アルフレッド・スティーグリッツの291画廊にその作品を運んだのである。
のちにジョージア・オキーフの夫となった写真家のスティーグリッツが、それをマースデン・ハートリーの『戦士』というタブローを背景にパシャリと撮った。デュシャンはそれで何かを"完成"させた。美術をもって美術界から去ることを決意した。
しかし、こんなことはカジミール・マレーヴィチが1913年に黒の正方形をカンバスに描いたときに、みんなが気づくべきことだったのである。あるいはアレクサンドル・ロトチェンコが1921年に純粋な絵の具の色を塗っただけの三部作を発表したとき、みんなが悟るべきことだった。あとはダダが何をしたかということ、シュルレアリスムがどれほど勝手なことをしたかということを、思い出せばいい。
そこで本書の話は、戦後にとぶ。レトリストのイジドール・イズーや舞踊家のマース・カニングハムやジョン・ケージが「偶然性」に着目したところから再開する。
けれども、そんなことを説明してもしょうがないだろう。これらはダダとシュルレアリスムのアメリカ的な再現なのである。ただし、問題があった。イヴ・クラインやネオ・ダダやダニエル・スポエリやヌーヴォー・レウリストやギー・ドゥボールがしたことは、新たな芸術への挑戦だったのだ。
ここにコンセプチュアル・アートの終生にわたる問題が噴き出た。デュシャンがレディイメイドを十数点しか作らなかったのに対して、コンセプチュアル・アートの前哨戦を担った連中は「過度の反復」と、いまならさしずめ"ユビキタスな"と言いたいところだが、誰でもどこでもいつでも作れる芸術をめざしてしまったのだ。
アーティストたちはそんなことに「退屈なよろこび」と「説明できない哲学」を見いだしてしまったのだ。デュシャンは芸術にそっぽを向いたのに、新たな運動主義者たちは芸術を生み出そうとしたのだ。
こうしてあの60年代が始まった。R・D・レインの言い草を借りるなら「ニセ自己」のアートが怒涛のように、そして意味でも無意味でもないものを求めて、美術界を席巻しはじめたのだ。
その象徴はエドワード・クーンホルツの「概念タブロー」の提出(1963)と、アンディ・ウォーホルのフィルム『エンパイア』(1964)に端的である。それにくらべれば、クレス・オルデンバーグの仕事など面倒くさくて忌まわしい。
その面倒くささを取り除いたのが、カール・アンドレやドナルド・ジャッドのミニマル・アートだった。アメリカではしばしば「コンセプチュアル・アートはミニマル・アートから直接分娩された」というのだが、それはこのあたりの事情をさす。のちにダン・グレアムがこのあたりの事情を、ちょっとヨーロッパ型にひねって、ミニマル・アートは幻滅を味わった実存主義に近いと言い、ベケットやサルトルのアート化の進捗があったと指摘した。
まあ、どちらでもいいだろう。もはや美術観念のマスターベーションは止まらなくなったのだ。
こうして60年代後半は米ソ対立とベトナム戦争があやしくなるにつれ、世界中で同じ症状による発病が蔓延することになる。急性環境反応病、信頼性崩壊前兆病、発話婉曲話法病(ユーフェミズム)、言語戦争病、略号普遍化病である。アーティストは「物質から脱する」か、「自然を加工しつづける」か、それとも「観念で勝負をする」か、選択を迫られた。結局、これらをごっちゃに表現することになったのだ。いまでもこの病気は治っていない。ただしアートだけではなく、どの社会の、どの世代の、どの生活にも蔓延した。
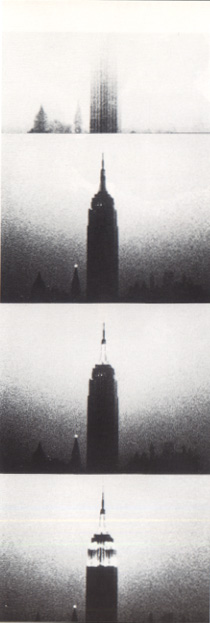
以上、ここまで書いたことは著者のトニー・ゴドフリーが"解説"していることばかりではない。ぼくが勝手に付け加えている。
それもぼくが思いついたことばかりではない。たとえば河原温とずっと語りあったことにももとづいている。河原温は、ぼくが認めている数少ないコンセプチュアル・アーティストなのである。1966年1月4日から、デイト・ペインティングを始めた。作品はそれが制作されたその日の日付で構成されていて、1日に3点を上回らず、深夜12時で完成さなかった作品は破棄される。
細部まで手のこんだ作品で、絵の具を4層か5層重ねているのだが、個人的表現のいっさいの痕跡が消去されている。唯一、その日の新聞の切り抜きが添えられるだけだ。1971年には過去100万年を1年ずつタイムアウトして10巻の書物を仕上げた。写真を撮られたことも、インタヴューをうけたこともないアーティストなのである。
ソーホーにずっと住んでいるが、ぼくも河原さんとは将棋をするか、哲学談義をするか、アメリカ批判しかしない。
もう一人、ぼくが語らってきたのはナム・ジュン・パイクである。が、パイクについては明日の夜に書くのでふれないでおく。
ということで、ふたたびコンセプチュアル・アートの現代前史に戻ることにするけれど、ここに河原とパイクに匹敵する年長の一人のアーティストが登場した。ヨーゼフ・ボイスだ。多くのコンセプチュアル・アートが英語圏でラッシュされたのに対して、ボイスはデュッセルドルフで講義と口論するだけでアートしつづけた。第二次世界大戦でナチスのドイツ空軍に編入されて、クリミアで追撃されるという戦歴をもっている。
この追撃のあと、ボイスは負傷しただけではなく凍死しそうになり、現地の遊牧民に助けられた。そのとき動物の脂肪とフェルト布がボイスを治癒した。ボイスの彫刻に動物脂肪とフェルトがつかわれるのはこのせいである。その後、パイクらとともに「フルクサス」に参加してハプニングやオブジェ活動をするのだが、やがて鈍重で暗冥な作品を残してデュッセルドルフの美術学校の教師に徹していった。
1972年、その美術学校ですべての受講希望者をうけいれたため職を追われ、自由国際大学を創設、まさにシャーマン的な教示活動ばかりを展開するようになった。いっさいの美術活動に不協和音をもたらす者として、本書においてもほとんどボイスの活動は言及されない。しかし、この不気味な存在こそ、コンセプチュアル・アートが早々に切り結ぶべき相手だったとおもわれる。
ボイスは「ドクメンタ7」で『七千本の樫の木』を植えている最中に、死んだ。
コンセプチュアル・アートは、以上の前史を知ってか知らないでかべつとして、ニューヨークの画商セス・ジーゲローブが企画した『1969年1月5-31日展』をもって離陸する。
ロバート・バリー、ダグラス・ヒュブラー、ジョセフ・コスース、ローレンス・ウェイナーの「観念」が展示されたのだ。この展示で一番重要だったのは、当然ながらカタログだった。
これでコンセプチュアル・アートは自分で自分の息の根をとめたのである。離陸して、直後に墜落したのだ。それから数年(あるいは十数年?)、コンセプチュアル・アートといまはよばれている季節があいかわらず続きはしたのだが‥‥。
それでもぼくには気になる一連の動向があった。1973年にルーシー・リパードが「c.7500」という26人の女性アーティストによる巡回展をしたときからのことだとおもうのだが、アナ・メンディエタやハンナ・ウィルケやマーサ・ロスラーらの活動が、キュビズムやデュシャンやミニマリズムとはまったく別個の意思を発揮しはじめていたのである。フェミニズムとして括る気はない。何というのか、ジェンダーを含んだ起源に奇妙なフィードバックを駆けたのだ。それは臨床性にも富んでいて、ハンナ・ウィルケのフェティッシュとの闘争、マーサ・ロスラーの擬似テレビ、アネット・メサジェの施術性の暴露をやってのけていた。とりわけエレナ・アルメイダの『住みつかれた絵』(1976)は婉曲な儀式のようでいて、絵画の本来とのかかわりを告示した。
ちなみに本書には日本および日本人アーティストの動向は「具体」と久保田成子と草間弥生をのぞいて、まったくふれられていない。千葉成夫の『現代美術逸脱史』や安斎重男・篠田達美の『現代美術トーク』などで補われたい。




