父の先見


ミネルヴァ書房 2001
ありがたい研究本である。近代以降の絵本の歴史をほとんど検証して、その特質を浮き彫りにした。さすがに執筆者は多いが、記述にムラがなく価値の視軸がぶれていない。編者の鳥越信の力なのだろう。
明治以降の絵本は、最初のうちは赤本の系統のもの、外国絵本の輸入や翻訳、それに「ちりめん本」が並立していた。「ちりめん本」は縮緬状の和紙をつかっていたためそういう呼称になったのだが、弘文社をおこした長谷川武太郎が英文の「日本昔噺シリーズ」を刊行して、特異な位置を占めた。ぼくはこの袖珍本のセンスを買う。小泉八雲を縮緬絵本にしたのも弘文社だった。
絵本の普及と幼稚園の創立ラッシュは軌を一にしている。明治10年に幼稚園規則が制定されると、「物品科」「美麗科」「知識科」の3つが保育科目とされ(いまならこれこそ知育科目だろうが)、これにあわせた絵本も出回るようになって、春陽堂はさっそく「幼稚園」という絵本シリーズを刊行した。やがて続々と翻訳されたフレーベルの幼児教育思想やモンテッソーリ教育法もこれらの歯車を加速し、のちのちの倉橋惣三によるフレーベル館の「キンダーブック」などにつながっていく。
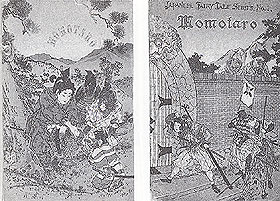
一方、町には絵草紙屋が賑わいを見せはじめた。谷崎潤一郎の『幼年時代』には、人形町の清水屋に3枚続きの水野年方や尾形月耕や小林清親の錦絵が並べられ飛ぶように売れていた光景が語られている。これがのちの竹久夢二とたまきの「港屋」につながった。
そこに加わってきたのが日清日露戦争による戦記絵本の大流行である。和田篤太郎、北沢楽天、石原和三郎、一条成美が腕をふるった。森桂園が文章を書き、かの尾竹竹坡・国観兄弟が絵を描いた『征露再生桃太郎』など、まことに傑作だ。お爺さんはエイゾー、お婆さんはオアメ、それぞれイギリスとアメリカの国旗を意匠にした恰好をし、悪者ロスケがおシナちゃんとおチョーちゃんを攫うという御伽噺なのだ。したい放題だったといっていい。
坂本嘉治郎の冨山房と大橋佐平の博文館が絵本にとりくむのも、日露戦争前後からである。それぞれ「帝国画報」や「幼年画報」も出版した。この時期で、われわれがいまも知る桃太郎・金太郎・カチカチ山から曽我兄弟・源義経・太閤記まで、文明開化物語から東郷平八郎物語までの、典型的な話のパターンがほぼ確立された。さらに金井直三の金井信生堂が山本笑月・大和田建樹・熊田葦城を擁して絵本シリーズを量産し、そこに赤穂浪士・楠木正成・加藤清正が加わった。これで、ようするに日本の英傑と豪傑が「お話の型」をもって出揃ったのだ。本書では、この時期に「絵本はメディエーションされた」と見ている。その中心にあったのは桃太郎主義である。
第一次世界大戦をはさんだ大正文化のなかの絵本というと、乗物絵本の隆盛が目立っている。汽車・飛行機・飛行船・汽船・自動車・観覧車の乱舞である。こうして絵本はまさに加速する。
それとともに中西屋が台頭して「日本一」シリーズを蔓延させていった。『日本一ノ画噺』である。巌谷小波が文章を、小林鐘吉・杉浦非水・岡野栄が絵を描いた。絵本史では、近代日本の創作絵本の母型をつくったものとしても、シルエットを導入したものとしても、またアールヌーボーの先駆けとなったものとしても、評価している。またこのシリーズによって、ウシワカマルやウラシマは、ヘイタイゴッコやシマメグリと同じ趣向、同じ主題、同じ重要度になっていったともいえる。
中西屋は丸善を創業した早矢仕有的が個人経営ではじめた子供向け版元で、とくに巌谷小波に全権を委任して画期的な絵本時代をつくりあげた。川端竜子や竹久夢二が抜擢されたのは、早矢仕と巌谷の先見の明による。
その竹久夢二が登場し、また鈴木三重吉が「赤い鳥」を創刊し、そこへ「おとぎの世界」「金の船」「童話」「コドモノクニ」などの絵雑誌がぞくぞくと加わって、大正絵本文化はまったく新たな様相を呈する。ここではそのフラジャイルな中身よりも「童画の誕生」に注目しておきたい。とくに「赤い鳥」の清水良雄、「金の船」の岡本帰一、「おとぎの世界」の初山滋、「まなびの友」の村山知義、「童話」の川上四郎だろう。そこに大正11年に「コドモノクニ」が参入して武井武雄が登場してきた。絵本というより、日本イラストレーション史としての画期があった。
もうひとつ注目したいのは夢二の「どんたく絵本」である。夢二は最初、恩地孝四郎・久本信夫らを同人にして「どんたく図案社」と雑誌「図案と印刷」を計画するのだが、これが関東大震災にあって壊滅した。ようやく気をとりなおして作ったのが『どんたく絵本』の3冊だった。千駄ケ谷の金子書店が引き受けた。これはまったく文字がない絵本で、いま見るとデザイン的イラストレーションの先駆体といえるものになっている。

戦争中の絵本にはひとつの大きな変化がおこっている。十五年戦争戦時下、「コドモノクニ」と「コドモアサヒ」を除いてほとんどの絵本雑誌が休刊もしくは廃刊していたこと、そのため絵本作家や童画家たちは一斉に単行本に向かったということである。
これによって絵本の作品性や長編性がいちじるしく増した。また自立性も増す。しかしその一方、戦時統制と絵本の関係はいくつもの問題をかかえた。作家や画家たちは挙国一致のための絵本づくりを版元を通して強力に要請され、内務省図書課の「指示要綱」に従う本づくりを余儀なくされた。浜田広介、与田準一、坪田譲治、百田宗治らがこの統制のなかで、想像を絶する苦闘にまみれる。なかでもぼくが注目するのは吉田一穂である。
戦時下、吉田一穂は金井信生堂で36冊の絵本を編集担当した。一穂を金井信生堂に紹介したのは内務省図書課の佐伯郁郎で、寡作と極貧をもって知られる一穂をなんとか生活させたいというのが最初の動機だったようだが、生真面目にこの計画にとりくんだ一穂は、一方で未曾有の創作性を発揮しつつも、他方で国家精神と版元経済のあいだに挟まれて、ぼくなどが安易に説明しがたい壮絶な日々をおくったようだ。
こうしたなか、逆に「愛国・皇道・忠義」を真っ正面にかかげて一挙に絵本の世界を席巻していったのが大日本雄弁会講談社の新シリーズ「講談社の絵本」である。すでに大人向けの大衆大量販売雑誌「キング」と、「少年倶楽部」「少女倶楽部」「幼年倶楽部」の青少年3大誌を当てていた講談社は、野間清治の決断で戦争賛美の絵本づくりに突き進んでいった。絵も名画主義と写実主義で、「ハワイ大作戦」「ツヨイ日本軍」「支那事変美談」などが連打された。
田中日佐夫の『日本の戦争画・その系譜と特質』(ぺりかん社)には矢崎泰久・今井祥智・司修らの当時の回顧も収録されているのだが、それぞれがいかに講談社の軍国絵本に大きな影響をうけたかを強調している。あれで愛国少年にならないわけはなかったというほどの影響力だった。べつのところで、山藤章二もやはり「徹底した写実描写で見る者をすべてねじ伏せていた。ただ不幸はすべてがカーキ色の絵であったことだ」と感想を述べた。

戦後の絵本は仙花紙からの再開である。そこに新潮社が「世界の絵本」シリーズをカラーで出版し、岩波書店が「岩波の子どもの本」シリーズにとりくんだ。
それからはありとあらゆる絵本が試みられたといってよい。が、まあ、そういう事情はこれくらいにして、ぼくが本書の第3巻において、ついに子供時代に夢中になった絵本の一冊に再会したことをちょっと付け加えておきたい。失ってしまった片っぽの手袋にやっと出会えたようだったのだ。
それはウェズレー・デニスによる『フリップ物語』という絵本だった。子馬のフリップが夢の中で翼をはやし、ついに自由に空を飛んで冒険するというお話で、夢中に読んだ。ところが題名も作者名も思い出せなかったのだ。本書によると、GHQ占領下でどっと入ってきた欧米絵本の翻訳もののひとつだったらしく、当時としてはきわめて珍しいことに横組で、しかも英文併記になっている。もっと驚いたのは翻訳者が桜沢如一だったことである。マクロバイオテックを提唱し、世界中に玄米レストランを波及させた、あの桜沢如一なのだ。
詳しいことはまだ見えないのだが、どうやら桜沢は、この『フリップ物語』にこれからの日本の社会が進むべき進路を感じて訳したらしい。そういうことを縷々語りあげた100ページ以上の解説書もあるらしい。どこかで入手したいものである。その名もかわいいコンパ出版が発行元になっている。
もうひとつ、本書によって再発見できたのは、ぼくがやはり子供時代に何度もひっくりかえして読んでいた『家なき子』『フランダースの犬』『ピノキオ』『世界一づくし』『夕鶴』『アラビヤンナイト』などは、どうやら新潮社の「世界の絵本」シリーズだったろうということだ。石川光男が企画していた。『家なき子』や『フランダースの犬』が林芙美子、『アラビヤンナイト』が与田準一の文章だったことも、今度初めて知った。
セイゴオ少年としてのぼく自身の絵本体験は、このあたりで終わった。ぼくは絵本から離陸してしまった。そのまま長じて子供をつくらなかった人生を歩んできたため、その後はついに本気で絵本と交わらないままにきた。ときどきは大人の目で童話や絵本を眺めてきたものの、それは小学校の教室の椅子になつかしくなって坐ってみたようなもの、どうしてもあの時期の読書感とはちがっている。
子供に戻りたいのではない。子供の絵本を作りたいわけでもない。きっとその両方ともぼくの手にあまることである。そうではなくて、盗み見をするように、どこにもない物語がそこに世界の裂け目のようにあることを知って、自分でその裂け目に落ちたいと思うのだ。きっと手遅れだろうけれど――。
