父の先見


岩波書店 2002
柏木博の本はみんなとりあげないと、そのデザイン思想はわからない。それほど広いし、それほどデザインを一つの大きな脈絡に入れようとはしてこなかったということである。
この姿勢はデザイン史を研究している者が選んだ方針として、敬服に値する。ウィリアム・モリスから説いてバウハウスに及び、アールデコやスティルや流線型を見ながらアメリカのポッブデザインにも目を配って、そこから60年代や70年代を一挙に観測するというのがわかりやすい常道なのに、それをあえてしないというのは、柏木博にはデザインの進歩とおもわれている大きな流れに対するラディカルな批判精神があるからなのだ。
本書はそういう意味では柏木らしい一冊だ。本としての出来栄えからすれば『家事の政治学』や『普請の顛末』のほうがコクがあるけれど、このようにモダンデザインを例証をもって批評できる者が、では誰か他にいるかといえば見当たらないわけで、やはりこの一冊はもっと読まれるべきなのである。
柏木がモダンデザインを批判しなければなるまいと思ったのは、ポストモダン思想とそれがもたらすデザイン風潮にうんざりしたからだったろう。
だいたい資本主義市場が完全に蔓延した社会では(日本がまさにそうだし、いまや韓国も中国もそうなっているが)、どんな「もの」も均質化してしまう。そこに違いを見いだそうとすれば、アンドレ・ルロワ=グーランが言うように「文化の差異」を抜き出すしかなくなっている。「もの」は人間生活の外化(エクステリオリゼ)なのである。と同時に「クレオール」なのだ。つまりは言語と同じものなのだ。だから「もの」がコミュニケーションのプロセスから跳び抜けてあるときは、まだ「もの」は言葉や音楽ではあらわせない価値をもっていた。たとえば利休時代の茶碗やポール・ポワレの洋服がそういう「もの」だった。
しかし、このあとのべるように「もの」はそのような跳び抜けた価値を欲しなかったのである。それだけではない問題もそこには噴き出していた。ヴィレム・フルッサーが指摘したように、「もの」は「神」に代わったのだ。
そうなると何が問題になるかというと、コミュニケーションすら問題になってくる。コミュニケーションの本質はいろいろ説はあるけれど、とりあえずはユルゲン・ハーバマスがいうように神を抜いた社会での人々の「合意」をめざしているのだとすると、その合意の行く先の証拠がほしい。ひとつは訴訟や裁判だろう。そこには妥当かどうかはべつにして、ともかくも価値の決定というものがある。もうひとつは、おそらくは精神や意識というものだろうが(それを最近は「安心」とか「安全」というつまらない言葉にしているが)、これはいまのところまったく証拠にはならない。道徳や倫理はとっくに社会から撤退させられてしまったのだ。
そこでコミュニケーションの価値を示す端末に厖大な「もの」が浮上してくることになった。つまりはどんな証拠も「もの」が示す以外にはなくなってしまったのである。財産も株価もステータスも、店舗も料理も美の感覚も。「もの」を介在させない価値の合意は、「神」はいないかわりに「もの」のほうに移行しきってしまったのである。
もっとわかりやすくいえば、こうだろう。すでに資本主義社会のコミュニケーションの半分は電子化されて、いまや会話すらメールやブログになっているのだが、ということは、パソコンの市場やケータイの行く先で何かを掘り当てるということが電子社会の一番てっとりばやいコミュニケーションであるのだろうが、そこには「もの」しか待っていないということなのだ。
しかし、これで「もの」が大手を振れるかといえば、そうともかぎらない。鳥インフルエンザがそうであるように、コンピュータ・ウイルスがそうであるように、賞味期限がそうであるように、たえざるチェックを欠かせば、「もの」はすぐにダメになる。だから、「もの」の価値は破棄されたもの以外の「もの」に集中する。逆にいえば、「もの」はどんどん捨てなければ、価値が残らない。それなのに、何を破棄するかという哲学や何を引き算するかという思想や美学なんてものは、誰も学んでこなかった。ましてデザインの大半は破棄や消尽など考えないで作られてきた。
いったい、こんなことを近代の理性は期待していたのだろうか。そうではあるまい。だとしたら、では、視点を変える必要があるのだろうか。そもそも近代においてコミュニケーションが理性的な合意をめざしたこと自体が問われなければならないのだろうか。
ひょっとしたら、そうなのだ。そこが問われる必要があったのである。誤謬はかなり以前から始まっていたわけなのだ。バーバラ・スタフォードが『アートフル・サイエンス』で喝破したように、実は近代社会で「もの」がどのようにあろうとしていたか、商業者もデザイナーも研究者もろくすっぽ見ても考えてもいなかったのだ。デザイン史の研究とは、そこを塗り替えることなのである。
モダンデザインとは、一言でいうなら19世紀の技術革新を延長拡張した社会運動のことである。
スティーブンソンやブルーネルやロックが蒸気機関を鉄道にすることをおもいついた瞬間に、モダンデザインは時間と経済のコストを前提とした軌道路線を走りはじめたのだった。
もうひとつ、出発点があった。健康で豊かで快適な生活をすべての人々がおくる権利があるという幻想が、モダンデザインの底辺にも表面にもあったということだ。人々の生活権利のために、モダンデザインはその改良計画に着手するべきだと考えたのだ。
いや、このことはモダンデザインだけが責任を負うべきものではない。1899年の横山源之助の『日本の下層社会』や1909年の石川天涯の『東京学』は、エンゲルスが『イギリスにおける労働階級の状態』に描いた1840年代の社会とそっくりなのだ。この社会を改革するための計画は、近代社会の矛盾にめざめた者なら、どうしても考えたくなることなのだ。バクーニンのアナキズムと藤村の『破戒』とユゴーの『レ・ミゼラブル』と百貨店の誕生とモダンデザインは、当初においては別物ではなかったのだ。
エンゲルスとモダンデザインは、こうしてエベネード・ハワードの田園都市構想とともに軌道をひとつにしてしまったのである。資本主義が生み出すシステムの矛盾としての貧困が問われるかぎり、モダンデザインはその路線で進むしかなかったのである。
かくてモリスもバウハウスも蔵田周忠の「型而工房」も、タトリンのロシア・アヴァンギャルドさえも、「生活の進歩」を掲げて造形と生活と「もの」とを一緒くたにしていった。ワルター・グロピウスがバウハウスの精神に掲げたのは、フォードの量産システムのモデルとそれほど変わりはしない。柏木はそこに、1920年に文部省が組織した「生活改善同盟」の趣旨と同じ年に結成された森本厚吉の「文化生活研究会」の動向をぴったり重ねて見ている。モダンデザインは最初から「もの」の普及のための戦略だったのだ。

このような150年にわたったモダンデザインのコンセプトをさがすことは、けっして難しくない。「みんな同じものが手に入ります」ということに尽きている。それによって「生活が便利にもおもしろくもなります」というメッセージに尽きている。近代資本主義がつくった「もの」は最初から「広告」なのだ。
いや、それは「すばらしい生活」だとも勘違いされたのである。1879年にキャサリン・ビーチャーがボストン料理学校を開校したこと、そのあとの校長のファニー・ファーマーが「すりきり一杯の計量」を提案したこと、そのあとの化学者のエレン・リチャーズがアメリカ料理を工夫して「ランフォード・キッチン」を提案したこと、一方でミース・ファン・デル・ローエが年の均質空間を求めてユニバーサル・スペースを計画したこと、ヘンリー・フォードがT型フォードを実現したこと、そしてハーバート・バイヤーが「ユニバーサル・タイプ」というタイプフェイスを発表したこと、これらに共通するものがモダンデザインのコンセプトなのである。
もうひとつ加えよう。フランクリン・ルーズベルトがロシア人に贈りたい本があるとしたら何でしょうかという質問に答えて、そりゃあ『シアーズ・カタログ』だよと答えたということを――。
モダンデザインの価値観とは、デザインの意味を生成させる社会システムを信じるということなのである。それは欲望のデザインがどれだけ社会システムと連絡をとりあえるかということである。ブランド商品もきっかりその延長線にある。

もっとも、モダンデザインが資本主義社会のすべてにゆきわたっていったとはいえない。たとえばカウンター・カルチャーが志向したデザイン感覚や、エコロジーや産業廃棄物批判が求めたデザイン思想や、ときにはフェミニズムが模索したデザイン社会は、一時期ではあったけれど、モダンデザインの進歩思想と激突する面をもった。それがロックの波及とともに目立ってきたことについては、サイモン・フリスが『サウンドの力』で適確に説明してみせた。
そこにはアメリカがベトナム戦争で行き詰まったという情勢も関与した。後進国の産物が、あたかも柳宗悦が民芸に注目したような意味で、またこれは日本でもおなじみの流行になったけれど、エスニック料理や無国籍料理が話題になったような意味で、着目されたということもある。
そういうことも手伝って、アメリカにおけるベトナム戦争の矛盾はデザインの矛盾を直接にはあらわしはしないけれど、カウンター・カルチャー世代はそこに工業社会総体の究極の矛盾を感じたわけである。ダニエル・ベルが『脱工業社会』を著したのは、そうした背景に衝き動かされたせいだった。
しかし、70年代が終わってアメリカがふたたび復権してみると、実はカウンター・カルチャーのエコロジカル・デザインもまた、ジャン・ボードリヤールがいう過剰消費社会の「シミュラークル」(もどきのもの)になっていたと言わざるをえなかった。いっさいの「もの」たちが、民芸品もエスニック料理もが、実物まがいを辿るための記号の系譜になっていた。このことは、コンビニエンスストアとインターネットとケータイ文化によって、いったん「情報化」されたかのように見えたネットワーク社会のコミュニケーションが、その後は徹底的に「もの化」されていったプロセスを見れば、一目瞭然である。
かつての均質な夢をばらまいた『シアーズ・カタログ』は、いったんはスチュアート・ブランドによって意識的な『ホールアース・カタログ』に対抗化されたのであるが、それもこれも何もかもが電子貯蔵されてみると、結局は電子マウスのクリック先の宛名にすぎないものにさせられていた。そういうことだった。
こうしてそこに、強引な意匠をもって登場してきたのがポストモダンな動向だった。もう「大きな物語は終わった」「それぞれに適切なディコンストラクションをおこそうよ」というものだ。たしかに、そのように言いたくなる季節に、資本主義市場は突入していた。
本書はとくにポストモダン思想をこきおろしてはいない。また、そこに咲いた徒花ともおぼしいエットーレ・ソットサスらのデザイン活動に新たな意味を付与もしていない。柏木は、そんなことはとっくにアンリ・ルフェーブルや、もっと以前にはヴァルター・ベンヤミンが見抜いていたことだと示唆するにとどめている。
しかしながら、ポストモダンの体たらくは、モダンデザインの根本的な矛盾をこれ以上は許容してはいられないものを反射的に掴み出したはずなのである。柏木の言葉でいうなら、資本主義消費社会とモダンデザインがおこした"脱臼"は、80年代から90年代にかけて鎌鼬のように世間を走りまわったポストモダン現象によって、その病状をあきらかに悪化させたのだ。
デザインはモダンデザインであれポストモダンデザインであれ、ようするに一緒くたになったのだ。それをポストモダンが促進したとさえいえる。ロンドンとミラノと上海と福岡がそうであるように、そこにはルロワ=グーランの「文化の差異」すらなくなったのだ。

いったい、これはどういうことだろう。モダンデザインが出発点から矛盾を孕んでいたことが、ここまで病状を悪化させたのか。それとも、それを批判するデザイン批評やプロダクト思想や、もっとはっきりいえば企業とデザイナーと学者がダメだったのか。
いまのところ解答はない。処方箋もない。柏木はやむなくリサイクルやリストレーションを持ち出してはいるのだが、つまりはデザインにおける「編集」の可能性を提言してはいるのだが、これはぼくのような編集派が擁護したくても、とうていまにあいそうもない。それくらいポストモダン以降の「もの」は欲望の構造すらのりこえてしまったのだ。
なぜなら、これらの「もの」たちはその大半がすでに情報化をおえて、ただ都市店舗の棚と電子端末との棚で「待つだけのもの」にまで"化けもの進化"してしまったからだ。
これではリサイクルもエディティングもまにあわない。破棄がおすすめだ。そんなところを覗かないようにするしかない。
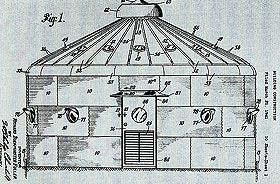
というようなことを、本書は感じさせた一冊だった。できれば、いささか編年的な『デザインの20世紀』や『20世紀はどのようにデザインされたか』から読むのがわかりやすいだろうが、問われるのは結局はわれわれの社会と諸君自身なのである。