父の先見


東京経済 1998
大正12年に丸ビルが竣工したとき、最初のテナントで入ったのは米田屋洋服店だった。1階の101号室。岩崎小弥太が三菱地所に用意させた836室もの部屋の第1号である。米田屋洋服店はこれで日本一の老舗となった。
米田屋の歴史は百年をこえている。そんな洋服屋はいまは一軒もない。本書はその米田屋の二代目夫人の柴田和子さんがわが家史のように、わが店舗史のように、わが銀座史のように資料をかき集めて綴った長大なドキュメントである。大判で600ページ近くある。ずっと気になっていて、ちょびちょび読んでいた。
米田屋をおこしたのは仙台出身の柴田光之助である。明治初期に尾張町2丁目(いまの松坂屋のある銀座6丁目)の山岸民治郎がはじめた大民(だいたみ)洋服店の下職をしながら、銀座通りで唐物(舶来品)を売って鍛え、明治15年に日本橋蛎殻町に「柴田洋服店」を構えた。それが米田屋になったのは、姉のフミが当時有名な新橋の料亭「湖月楼」の女将をしていて、光之助が手狭になった店を銀座に移そうとしたとき、フミの実家が米屋であったところから名付けた。
このフミのことから話せばわかりやすいのだが、多賀右金治という傑物に嫁いで、「湖月楼」だけでなく、これも銀座竹川で有名になった「花月楼」にもかかわった。女傑であった。吉井勇が「大観が酔ひて描きたる絵に似たる花月の塀の春の泥かな」というとんでもなくうまい10歌を詠んだ。
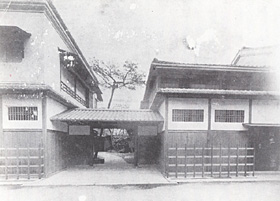
そのころの花柳界といえば明治初期は隅田川両国橋近くの柳橋が中心だったのだが、銀座の興隆とともにしだいに新橋へ移ってきた。華族や政財界の連中が新橋を好んだためである。それに比していえば柳橋のほうは大商人が遊んだ。だから「御前の新橋、旦那の柳橋」などという。
実は、銀座の隆盛はそれらのあとなのだ。それが明治5年の大火に業を煮やした東京府知事の由利公正が「不燃都市宣言」をして銀座を舗装して煉瓦街にする計画をたてた。まず明治5年9月に新橋ステーションができて、7年に舗装が完成、ガス灯がついて、鉄道馬車が往来するようになった。これに夜店が出た。のちに服部時計店となる服部金太郎は夜店で舶来物の時計を売っていた父親の稼業を受け継いだものだし、池田弥三郎の生家の「天金」や菓子の「青柳」などもこの夜店から発した。柴田光之助もそのでんで、唐物を売りつつ、仕立ての技術を磨いて洋服屋をおこしたのである。
銀座に煉瓦の建物が並ぶのはそれからである。
明治21年、三越洋服部が三越洋服店に拡張されたとき、柴田は招かれて従業員を引き連れ生地の裁断を担当した。これで柴田の腕が有名になった。そのあとの三越の仕立て担当になった名和小六はやがて"裁縫の神様"とよばれるほどなのだ。
とはいえ洋服の仕立てはまだ始まったばかりだった。もともと日本の洋服の歴史は種子島に鉄砲がわたったときにスタートを切ったようなもの、最初は南蛮服とよばれ、鎖国してオランダとの交易が中心になると紅毛服とよばれ、さらに筒服、戎服、異人服などとよばれて、せいぜい軍服や蘭学者につかわれる程度だった。下のズボンにあってはずっと段袋としかよばれていない。
では、その洋服にどういう職人がかかわったかというと、着物の仕立て職人が引き継いだろうと予想できるのだが、実は足袋職人に期待が集まった。着物は平面的だが、足袋は立体的だったからである。けれども足袋と洋服ではずいぶん差があった。
明治5年11月12日、明治政府の太政官布告令は「爾今礼服ハ洋服ヲ採用ス」と決めた。さあ、これで大変になった。冠婚葬祭にすべて洋服がいる(おかげでこの日は洋服記念日になった)。柴田はだから張り切ったのである。
たちまち米田屋に華族や政財界の者たちからの注文が殺到した。歴代の首相はほとんど米田屋の顧客だったようだ。柴田もいいかげんなことはできなくなって、軍艦浅間に便乗させてもらって武者修行のためにロンドンに渡った。それが明治35年のことだというのだから、漱石がロンドンで憂鬱になっていたころである。ロンドンから帰ると米田屋の評判がまた上がった。しかし柴田はそれに甘んじない。ロンドンで既製服を売っていることを知って驚き、それと同じスタイルの店をつくることを思い立つ。なかなか抜け目がなかった。それが神田神保町に出店した「日の出屋」である。

こういうふうに洋服のことだけで近代日本を見るというのは、なんだかぼくのような者には妙な気分になるのだが、けれども日本の近現代史というのは、こうして一軒ずつの「店」がつくりあげた歴史だったともいえるのである。とくに銀座にはその歴史が高密度に集中していた。
いまは銀座もどこも似たような風情で、しかもそこにはシャネルやディオールやプラダやグッチがひしめいていて、とても老舗の銀座とはいえなくなっているように見えるけれど、どっこい、銀座にはそこかしこに、まだまだ近代日本が凝縮して喘いでいるはずなのだ。
そうしたなか米田屋が長命を誇ったのは、柴田和子さんによると幸運もあったからだと謙虚である。それというのも大正12年の丸ビル出店がついていたというのだ。その直後の9月、東京は関東大震災で壊滅し、炎上したのである。銀座の米田屋も神田の日の出屋も灰燼に帰した。それが丸ビルの米田屋と工場が残ったのである。
結局、米田屋は昭和8年4月に地上5階地下1階の秀麗なビルとして蘇る。著者の家族もそこに住む。1階がマホガニーやチークで造られた重厚な売り場、2階が仕事場とストレージ、3階はホールと店員の寝室、4階が裁縫工場、5階が住居となった。日本間には犬養木堂の「無欲則剛」の額が掛けられた。この言葉、柴田米田屋にぴったりである。
銀座米田屋は銀座2丁目、向かい側にはカフェ「黒猫」があった。なるほどこのように銀座に寝起きする華族が当時はたくさんひしめていたのであろう。
本書を読んでいると、近代の日本人がよほどハイカラやモダンが好きだったことが皮膚感覚のように伝わってくる。たんに煉瓦街がハイカラで、洋服を着て万年筆を胸にさしてソーダ水を飲むというのがハイカラ・モダンだったのではないのである。
このこと、おそらく外国人にはわかりにくいことだろう。たとえば明治17年に来日したフランス海軍士官で作家でもあったピエール・ロチは、その『秋の日本』で初めて見た銀座煉瓦街の印象を書くのだが、それは「こんなものはヨーロッパの美の踏襲じゃない、アメリカの醜悪な模倣だ」というものだった。のちに『お菊さん』などを書く日本贔屓のロチですら、こうだった。
けれどもロチの見方と日本人の見方はちがうのだ。日本人には築地ホテルの擬洋風建築やカフェ・パウリスタの名前もハイカラ、滝廉太郎の『箱根八里』や北原白秋の南蛮趣味もモダンなのである。しかもそのように思えるのは、これらがずっとこのまま続いていくだろうなどと思っていないからなのである。どこかで壊れてしまうかもしれない、いつかちぐはぐになるかもしれない、きっと無くなってしまうだろうと思えるから、ハイカラ・モダンなのである。
さらにもうひとつ加えておくと、ロチには見えなかったろうけれど、「今日は帝劇、明日は三越」と思っていそいそ着飾ってそこを訪れる日本人の手元は、実は風呂敷を持っていたり、その足元は草履を履いていたりするわけなのだ。もっとわかりやすくいうのなら、荷風がいくら汚い恰好でカフェ・パウリスタに寄っていても、荷風の心はハイカラ・モダンで澄めるわけなのだ。
銀座米田屋の長い日々の細部を読めば読むほど、この近代日本人が入手したハイカラ・モダンというものが、まるでミシン目や襟の折り返しのように伝わってきた。もう一度、花月楼の風情を詠んだ吉井勇を引いておく。
はかなさは花月の門につるしたる
金燈籠の灯より来るらし