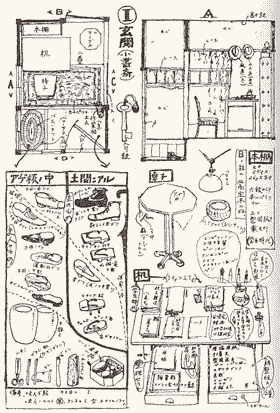父の先見


ちくま文庫 1987
変な文章である。『ブリキ屋の仕事』は関東大震災で壊滅した帝都を建て直そうとする自力のブリキ屋のことを書いた一文だが、こんなふうにある。
「らい年、さらい年あたりから、いよいよ恋の願いとでもいうべきものがかなって、帝展の玉の御座に、工芸美術も出陳されるめでたい御代となるだろうと想像しても、そう目ざとい奴だなんていわれる気づかいはあるまい。そうなるのがいまの世の有様では、至当でほんらいなことなのである。(中略)ペンキ屋やブリキ屋たちも、そこで昇格運動でもはじめることになるのかもしれない。皆昇格して、流行のいわゆる真剣な製作ばかりに努める時代になるのかもしれない。私の目には涙が流れる。本来気が弱くて、そんな人ごみのなかでの競争に耐えられないような魂を背負わされている私には、悲しくて涙が流れる」。
これでも少しはわかるように、今和次郎はあきらかにアナクロニズムに徹しているという抵抗や自覚のようなものがある。そこに感動や涙が入っている。けれども他方では、生活や風俗を研究するには、流行を追っていただけでは何も記録できないのではないかという民俗学者の目もあった。
その「はざま」に考現学という変なものが生まれていったということなのだ。
いってみれば、「考現学」は「考古学」に対する逆襲である。だから、それなら「考今学」と名付けられてもいいのだが、今和次郎はそういうところは屈託がなく、最初に「考現学」という名称を思いついたまま、ずっとこの名称を使ってきた。
あまり使われていないようだが、一応は、れっきとした英名もある。“Modernology”(モデルノロジー)という。ただ今和次郎らは、エスペラント風にこれを「モデルノギオ」というのを好んだ。
考現学の命名者ははっきりしないが、今と仲間の吉田謙吉・新井泉男・小池福太郎らの相談の結果だったようだ。あるいは嶋中雄作あたりの入れ知恵だったかもしれない。今はそのころ、喜多川守貞の『近世風俗誌』などの継承も頭にあったようだが、むろんそれよりはずっと分析的になっている。
今が、考現学の作業を始めたのは、大正12年の関東大震災の直後のことだった。しばらくは「死の帝都」を前に呆然としていたのだが、やがてぽつりとぽつりと都市の各所が復興されるのを見て、「新しくつくられていく東京はどういう歩み方をするものかを継続的に記録する仕事をやってみたくなった」。
この一念発起を励ましたのは『婦人公論』の嶋中雄作だった。編集部に一斉に調査作業の協力をさせた。こうして昭和に切り替わった年、“銀座風俗調べ”が始まった。
つづいて本所深川の貧民窟の調査が、さらに山の手の郊外の調査がおこなわれた。今はこう書いている、「それらの仕事に従事したことからわれわれはつぎのように意識することができた。すなわちすべての風俗は分析されてはじめて、それぞれの意義がはっきりするものであるということを」。
調査の結果を紀伊国屋書店で展示することになった。これはのちに名物店主として名を馳せた田辺茂一の薦めだったようだ。このとき「しらべもの展覧会」では面白みがないので「考現学」という名称が“発案”された。
これらの成果は春陽堂から『モデルノロヂオ』一冊にまとまって刊行される。かなりの反響があったようで、今自身の言い方によると、「この一冊を備えない新聞雑誌編集室がないといわれるほど」にメディア業界に浸透していった。気をよくした今は第2弾『考現学採集』をまとめる。
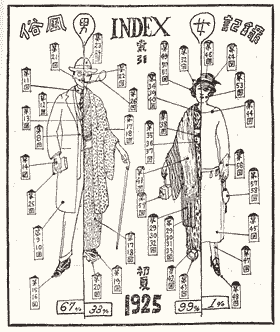
考現学の武器は、わずかなものである。歩くこと、観察してメモをとること、採集収集すること、これだけだ。いまなら電子カメラもビデオもテープレコーダーも携帯カメラもあるが、それらがないぶんだけ、考現学には今和次郎のナマの感覚が生きている。そこが変な文章にもつながっていく。
しかし考現学の本当の武器は、目のアングルに収まったすべての対象を列挙して一言説明を加えたいという、その執拗な視覚的記述願望にある。
ともかく商店街を片っ端から記述する。家人の一日の行動をことこまかに表にする。エプロン(前掛け)というエプロンを一人一人にはずしてもらって、それを並べ立てる。センチも型も調べる。押入れの中でも抽出しの中でも、なんでも克明にスケッチをして、その一つずつの事物に引き出し線を入れてメモを加える。銀座を歩く着物の柄はもちろんのこと、スカートの長さもいちいち物差しをあてて測っている。かつてぼくが感心したのは、襖や障子の汚れや破れの位置を克明に記録していたことだった。
この執拗はときに異様ですらあるが、人間には少年少女の時代から、このオールオーバネスとでもいうべき「全部記述願望」というものがひそんでいるのであって、今和次郎はその願望をついに現存生活のすべてに及ぼそうとしたのである。
ISIS編集学校の「編集稽古」には、「自分の部屋にあるものを列挙しなさい」という問題があるのだが、これは考現学からのヒントによったものだった。部屋にあるものなんて人によってそんなには変わらないと思うだろうが、これが細部にわたると大変な差異なのだ。
もともと今は、柳田国男に弟子入りした青年だった。高校受験に落第して、ここで美術学校に切り替えて絵を修行しようとした。
ところが、静物や女体をデッサンするのがどうにもおもしろくない。勝手に学校を抜け出して、動物園に行ったり浅草公園をぶらついてばかりいた。もともと何かの変化を観察するのが好きだったわけである。その変化も、似たようなものの動きの中からちょっとした変化を発見するのが好きだった。
そのうち早稲田にできたばかりの理工学部の建築科で小使い兼助手の口をえて、生まれてはじめて月給をもらった。しばらくすると月給も上がる。しかし大学の建築アカデミズムにはまったく馴染めない。
ぐずぐずしているところへ、建築家の佐藤功一教授が柳田国男らとつくった「白芽会」に入るようになり、柳田から「君、田舎を一緒に歩こう。私にはパスがあるから君の汽車賃は払ってあげよう」と声をかけられた。図工や絵描きには多少の腕はあったので、そういう面で「先生の役に立つぐらいはつとまると考えた」。これで農家の見方や農民の暮らしぶりを観察する目が備わってきた。
このときの成果が『日本の民家』(1922)である。日本最初の民家研究書となった。
が、ここで今は柳田にちょっとした不義理をしてしまう。農林省の農政課長だった石黒忠篤が旅費を出すから、もっと農村調査をしてほしいと頼まれ、引き受けてしまったのだ。石黒の依頼は農政調査だったから、柳田の民俗学調査とはおのずとインディケーターが変わってくる。柳田は今には民俗学の仕事が頼めないと見るようになった。
そこへ関東大震災である。焼け野原になった東京のそこかしこを見ていると、そこに草の芽のようにできてくる「現代」の芽吹きに関心をもった。今の目はここで考古から考現に切り替わる。そしてあえて「考現学」の狼煙をあげたのがいけなかった。「柳田先生から破門の宣告を頂戴してしまったのである」。
今を動かしたのは考現学だけでなく、焼け跡に次々に粗末に建っていくバラックだった。これを見ると矢も盾もたまらずに、今は美術学校の後輩を集めて「バラック装飾社」をつくり、ハシゴをかつぎ、ペンキ缶をぶらさげてブリキやトタンや板っきれに「絵」を描きはじめたのだ。銀座のカフェー・キリンがその代表で、そこには原始人まがいの、いわばオートバイ族が壁にペンキスプレーで描くような奇怪な「絵」が出現していった。
考現学はいまなお生きている。すでにお気づきのことと思うけれど、ぼくはこの手の見方や記録の仕方が大好きなのだ。注意深い読者なら、さらに気づいていることだろうが、「千夜千冊」でもあえてこの手の報告書や解読書を意識的に採り上げてきた。
参考までに、その一部をあげておく。意外にその数が多いことに驚かれるにちがいない。ぼくは、この手の成果は断固として軽視されてはならないと思っている者なのだ。とりあえず番号の若い順にあげておく。
イアン・ビュルマ『日本のサブカルチャー』(30)、米川明彦編『集団語辞典』(37)、永沢光雄『風俗の人たち』(115)、田村紀雄『電話帳の社会史』(135)、三好一『日本のマッチラベル』(144)、奥成達『駄菓子屋図鑑』(208)、尾佐竹猛『下等百科辞典』(303)、石井忠『漂着物事典』(339)、村松貞次郎『大工道具の歴史』(379)、竹中労『ルポライター事始』(388)、井田真木子『フォーカスな人たち』(396)、金子雅臣『セクハラ防止マニュアル』(411)、林忠彦『カストリ時代』(421)、明田鉄男『日本花街史』(494)、イアン・アーシー『怪しい日本語研究室』(579)、溝江昌吾『数字で読む日本人』(662)、香取俊介・箱石桂子『テレビ芸能職人』(740)、秋山祐徳太子『泡沫桀人列伝』(818)、等々。
考現学は、いまも生きている。テレビのワイドショーやタレントのルポ番組など、すべて考現学といってよい。
それなのに、メディアと都市論と建築家たちは今和次郎をいまだに大事にしていない。