父の先見


動物行動学が教えてくれること
紀伊國屋書店 2010
Frans de Waal
The Age of Empathy―Nature's Lessons for Kinder Society 2009
[訳]柴田裕之
装幀:芦澤泰偉・五十嵐徹 解説:西田利貞
類人猿を研究している者なら誰でも知っている「2動作パラダイム」という動物実験がある。チンパンジーの群を使ってやる。
まず若いメスのヴィッキーにパズルボックスのAB二つのやりかたを教える。Aの成功は棒を差し込むとバナナが転がり出てくる。Bによる成功はその棒でレバーを押し上げるとバナナが転がり出てくる。
どちらもおいしい結果を得られる。少しは試行錯誤するが、チンパジーの知恵をもってすれば、バナナにはABどちらの試行錯誤でもありつける。そこで今度は十数匹のチンパンジーを集めて、ヴィッキーにAの方法でバナナを獲得してもらう。しばらくするとこの群では、すべてAの方法が流行する。別の十数匹を呼んで、今度はヴィッキーがBをしてみせる。するとこちらの群ではBが流行する。
これはいったい何を示唆しているのだろうか。「模倣」とはどういうものかという実験だ。
模倣がいかに社会的にも人間的にも本質的なものであるかということは、誰もがなんとなく知っていることで、その理論的な理由付けについても、すでにガブリエル・タルド(1318夜)の『模倣の法則』があきらかにしている。ぼくもさんざん解説しておいた。この本についてはジル・ドゥルーズ(1082夜)が自分が再発見したんだということを自慢気に書いてもいた。
とはいえ、この実験から「そうだろうね、模倣はやっぱりサル真似に始まっているんだよね」とか「ようするに模倣も本能なんだろ」とかといったことだけを反応していてはいけない。サルにはミラーニューロン(1469夜)があるというような話でもない。模倣で重要なのは、何が感染しやすいのかということだ。上の実験では動作が真似されたのではなく、ヴィッキーに感染したのだった。
本書の著者は、ここには「共感」(empathy)という、われわれ人間の社会にとって最も重要な生物学的行動がチンパンジーを始めとした動物たちに芽生えていると示唆した。
エンパシー(共感:empathy)という言葉は、そもそもはカントの人格哲学を継承したテオドール・リップスが流行らせた用語だ。ギリシア語の“empatheia”をもとにした。「感情を何かに移入する」という意味だ。ドイツ語にはさらに“Einfühlung”というぴったりした言葉もある。
もともとエンパシーという言葉は、シンパシー(同情)が感情をダイレクトに交流させるという意味をもつのに対して、「何かを代行してそれをものにする」という意味をもっていた。アダム・スミスが言うようにシンパシーが道徳にもとづくところがあるとすると、エンパシーはむしろ「その場」でおこっていくハイパーコミュニケーションなのだ。
とはいえ、このチンパンジーの実験だけで、はたしてかれらの行為がたんなる模倣ではなく「その場」に生じた共感(エンパシー)によるものだなんてことが、わかるのか。むろんこれだけではわかりはしない。
そこで、ここにもう一つの実験を加える。
これは「ゴーストボックス」を使うもので、誰も何も手を加えないでも、ボックスがさまざまなパーツによって魔法のように開いたり閉じたりして、そのたびにバナナやリンゴがあらわれるというものだ。
チンパンジーたちがこのボックスの仕掛けをよく見ていれば、おやつは自在に取っていける。ところが意外なことに、どんなチンパンジーも「ゴーストボックス」の魔法を学ばなかったのである。かれらは、別の本物のチンパンジーが何をしているかを目にしなければ、模倣すらできなかったのだ。
チンパンジーが別の仲間の行動を見て模倣のトリガーを引いたというのは、サル学になじんでいない者にとっては驚くべきことだろうが、ふだんから模倣や認知やコミュニケーションに関心をもっている者にとっては、ピンときたかもしれない。
が、次はどうか。チンパンジーはもっと意外な学習能力ももっていた。
互いが見える隣り合った檻にいる二匹のチンパンジーに、左のサルには石ころを渡してそれを戻させてからあまりおいしくないキュウリを、右のサルには同様に石ころを授受させてから甘いブドウをあげるという、いじわるな実験がある。
この実験では、最初は左のサルはキュウリを齧るのだが、右のサルが石ころを授受するたびにおいしそうなブドウを食べているのを見ているうちに、何の変哲もない右側の石ころが「おいしさ」と関係していることを察知して、ついにキュウリにしかならない石ころを突き返してしまうのだ。
つまりこのチンパンジーたちは、石ころがトークンであることに気がついたのである。わかりやすくいえば石ころが代行している価値のようなものを見抜いたのだ。
ぼくはこの実験の映像をTEDで見たのだが、虚を突かれた。それから、悪知恵があるのはサルではなくて、サル学者なんだとも知った。そして、そのうち深く頷けるようになっていた。うーん、これは半世紀以上も前に今西錦司(636夜)が言ったこと、「動物にだって文化があるんや」そのものではないか、と。
このような実験を次々にやってみせたのが、著者のフランス・ドゥ・ヴァールとその仲間たちだった。ぼくより少し年下だ。
ドゥ・ヴァールはオランダ人で、しばらくアーネム動物園で動物生態の研究と調査をしたあと、アメリカのヤーキーズ国立霊長類研究所に移り、リビングリンクスセンター所長となった。もともとは心理学者でもある。
ヤーキーズというのは世界の霊長類研究の泰斗ロバート・マーンズ・ヤーキーズのことで、1929年にフロリダでイェール霊長類研究所を設立し、動物学習のヤーキーズ・ドットソンの法則を発見したりした。この研究所がのちのちアトランタに移転してヤーキーズ国立霊長類研究所となった。ヤーキーズという研究者はなかなか愛嬌がある学者で、晩年にはボノボの「プリンス・チム」君を飼って、この子を世界一かわいがった。
ちなみにオランダというところは、動物行動学ではニコこと、ニコラス・ティンバーゲンという巨人を生み、その弟子筋に秀れたチンパンジー研究者の、アドリアン・コルトラントとヤン・ファン・ホーフという二人のエソロジストを生んだ国だ。
ティンバーゲン(ティンベルヘン)はアメリカで猛威をふるいつつあった行動主義に反旗をひるがえした鳥類研究者で、コンラート・ローレンツ(172夜)、ミツバチの8の字ダンスの研究で有名なフォン・フリッシュとともにとともに1973年にノーベル賞を授与された。1973年は動物行動学(エソロジー)の輝かしい出立だったのだ。
そのわりにはティンバーゲンは日本ではローレンツほど知られてない(兄はヤン・ティンバーゲンでノーベル経済学賞の初代受賞者。兄弟のノーベル賞受賞はめずらしい)。ぼくもずっとローレンツばかり読んでいた。しかし、その『足跡は語る』(思索社)を読んで大いに啓発された。ティンバーゲンには問題を掴まえる大きな翼と姿勢が備わっていた。
たとえば、動物に接する者は次のような「問い」とともにあるべきだというのだ。①どのように行動が引き起こされるのか(仕組み)、②どのようにその行動は発達してきたのか(発達の要因)、③それはどんな意味や効果があるのか(適応の意義)、④それらはどんな進化のプロセスをへてきたのか。
しばしば、①至近要因、②究極要因、③発達要因、④系統進化要因、と言われるものだ。このところぼくがぞっこんの長谷川真理子さんは、このティンバーゲンの「4つのなぜ」こそが生命と進化にかかわる者がつねに背負っているべき見方だと、その『生き物をめぐる4つの「なぜ」』(集英社新書)に書いている。
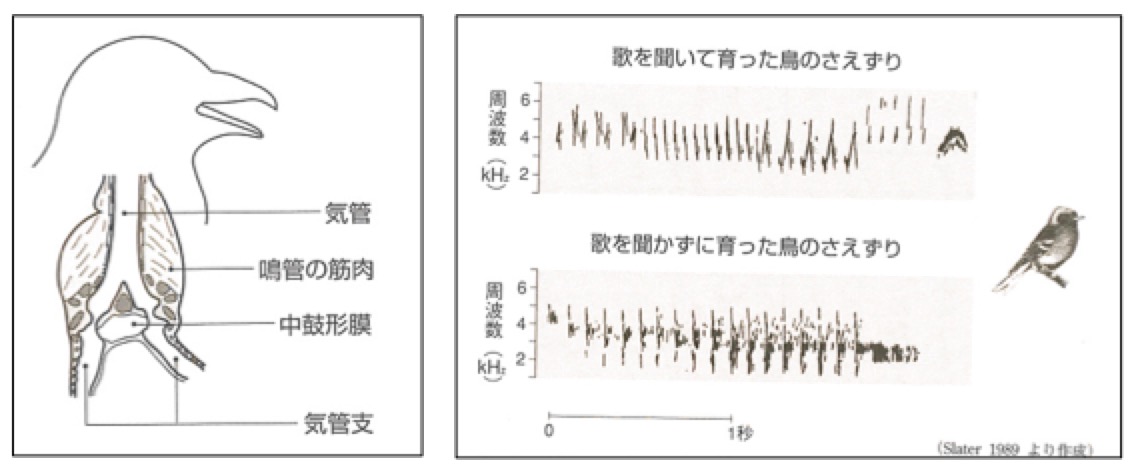
ティンバーゲンはこういう巨人だったから、その影響を受けた弟子は多かった。
その一人コルトラントは、世界で初めてチンパンジーがゴリラよりも人間に近いことを示した。ファン・ホーフは人間の笑いの“smile”がサルの恐怖を示すグリマス的な表情筋の動きに近く、“laugh”が格闘遊びでのオープンマウス・ディスプレーにもとづくことを仮説した。
これらオランダのエソロジストたちはローレンツ派とは一線を画して、多元的に動物文化をとらえようとして世界を引っ張ってきた。
本書のドゥ・ヴァールはそのファン・ホーフのほうの弟子で、のちにアメリカに渡ったオランダ移民なのである。ここがミソだ。オランダ人はアメリカについては、ニューアムステルダムがニューヨークになった一事にもあらわれているように(アムスの名は消されたのだ)、複雑な気持ちをもっている。
それかあらぬか、ドゥ・ヴァールは最初の著書『チンパンジーの政治学』(産経新聞出版)でオランダ譲りの多元的動物文化についての見方を披露し、返す刀でアメリカの一国中心型の善悪二元論(二値思考)を非難した。これがバカ当たりした。
その後も勢いがあった。『利己的なサル、他人を思いやるサル』(草思社)、『仲直り戦術』(どうぶつ社)、『あなたのなかのサル』(早川書房)、『政治をするサル』(どうぶつ社→平凡社ライブラリー)を続けさまに当てた。
なかでも傑作は『サルとすし職人』(原書房)で、愛すべき一冊は『ヒトに最も近い類人猿ボノボ』(阪急コミュニケーションズ)だろう。
前者の『すし職人』は今西錦司・河合雅雄・西田利貞といった日本のサル学に心からの敬意を表したもので、日本人にとってはくすぐったいほど嬉しい。後者の『ボノボ』は「何がなんでもボノボは最高」という賛辞で埋めつくされていて、これでボノボが好きになれなかったら、人間として最低だということを刻印される。これまたとても嬉しくなる本だった。ぼくのアシスタントをしつつ、いまはプロデュースやディレクターの仕事をこなすようになった和泉佳奈子は、大学時代にはサルの行動観察をしていた子だが、あるときボノボを見て「私はこのボノボに何かを捧げたい」と思ったそうである。
いずれにしてもドゥ・ヴァールの著書は、豊富な事例と人間社会に対する鋭い分析力と闊達な文章によって、またときおり見せるアメリカの利益主義に対する辛口によって、カネよりも気持ちを大事にしたいと思っている読書界の連中を満足させた。
こうしてドゥ・ヴァールは、2007年にはタイム誌の「世界で最も影響力のある100人」に選ばれた。TEDにも何度か呼ばれて大ウケした。
が、どんな本でも、ドゥ・ヴァールが書きたいことは一貫していた。極端にいえばただ一つの流れのことだ。それは動物たちには見逃せない「共感」(エンパシー)があるということ、その共感は動物社会の重要な場面でおこっているということ、だったら人間社会はもっともっと共感にもとづく社会になってもいいのではないかということ、この流れだ。
本書はこの共感をめぐる動物行動学を、ときどき人間社会(とくにアメリカ社会)に対する文句と期待をまじえて書いたもので、里山の暮らしやコミュティやネット社会や、さらには企業力やプロジェクト力の参考になるところも少なくなく、これまでの著書のなかで最もアップトゥデイトな出来になっている。
さて、では、動物(そして人間)は、はたして「共感」と言うにあたいする絆を、あるいはその絆をつくりうる鍵を、本来的にもっているのかどうかという問題だ。そこを検討しなければならない。
まず、まったく逆の見方が世に跋扈してきたことをふりかえっておく。逆の見方とは、動物と人間の区別なく、世界はそもそも競争や対立でできているという見方だ。
トマス・ホッブス(944夜)は人間の本性を「ホモ・ホミニ・ルプス」と呼んだ。「人間は人間にとってのオオカミ」であるという意味だ。戦争の歴史や企業競争の実態や学校での「いじめ」の報告に付き合わされていると、たしかにそういう気がしてくる。
ダーウィンは進化には生存競争があり、そこには自然淘汰がはたらいていることを実証した。これをハーバート・スペンサーが「適者生存」と言い換えて社会にあてはめ、社会進化論にした。アジアと南半球を除く列強世界は、この適者生存を掲げ、地球を欧米化することに邁進し、たちまちアフリカ分割に群がった。こんなところに共感があるはずがない。
20世紀に入ると、社会の進歩と「弱肉強食」とがもっと重なってきて、それを実証するかのように、フォードを先頭にビッグスリーをつくったアメリカの大企業が大成長をとげた。アメリカ企業はコングロマリットとして世界を荒らしまくったのである。そのため資本主義市場においての熾烈な「自由競争」のもとにこそ、健全な所有と分配が進行できるという勝ち組たちによる勝手な考え方がまかり通るようになっていった。そこから経営学も誕生した。
他方これとは逆に、クロポトキンはシベリアの動物たちを観察して相互扶助論を提出し、エドワード・ウィルソンは「社会生物学」を提案して、動物社会には利他的な行為があることを主張して、人間どもも弱肉強食ばかりに熱中することを控えさせようとした。
しかし、こうした「競争」よりも「協力」を重んじた見方に対しては他力本願だとの謗りが向けられ、生物学界でも社会学界でもなかなか認められなかった。それにもまして、二度の世界大戦、原爆投下、米ソ対立、冷戦、アメリカの帝国主義化などが次々に連打されると、利他的であることより利己的であることのほうが、ずっと「富」も「安心」も得られるという価値観が欧米を覆い始めたのである。
それだけではなく、続いてミルトン・フリードマン(1338夜)らがこの考え方を極度に発展させ、それを金融界がとりこんで、マッドマネーの活用も辞さない「新自由主義」化をはかることになった。
こうして、まことしやかな「啓発された利己主義」ともいうべきものが、今日における最も“正当”なバランス感覚だというふうになった。行動主義の父ジョン・ワトソンが提唱した「効果の法則」も、まわりまわってこれらのことを支援した。
このような流れのなか、いつのまにか「利己的な遺伝子」のようなものが拡大解釈されて、社会経済的な大活躍をするようになっていた。
とはいえ、このようなシナリオはいつも満足をもたらさないこともはっきりしていた。少数の勝ち組と、そして多くの負け組をつくっていくだけであるからだ。富はやたらに片寄るのだ。いま話題のトマ・ピケティの『21世紀の資本』(みすず書房)は、今日の富の大半が僅か1パーセント以下の者たちによって独占されていることを、厖大な歴史データによって実証した。
その僅かな勝ち組にだって落とし穴が待っている。たとえば、エンロンの有名CEOだったジェフ・スキリングは、ドーキンス(1069夜)の『利己的な遺伝子』の忠実なファンとして、社内に「ランク&ヤンク」(ランクを付けつつ首にしていく)を導入し、あっというまに成長したのだが、その実、内部ではぞっとするような不正行為をはびこらせ、外部に対しては情け容赦ない搾取力を敢行したため、2001年にがらがらと内部崩壊していった。成績主義の敗北だった。それも利益を唯一の価値とした度過ぎた成績主義だった。
エンロンは崩壊したが、成績主義のほうは大半の企業がいまでも積極的にとりいれている。人事考課を工夫して、なんとか利益貢献度だけで仕事を見ないようにしている企業も少なくないが、それでもどんどん収益重視・成績重視が主流になっている。
問題は、この風潮が一人一人に投影されビルトインされていくようになったということだ。そんなことがすすむとどうなるかといえば、社内に「うつ」や「ジコチュー」(自己虫)がはびこり、社会の最も重要な紐帯ゾーンが回復しがたく傷ついていく。
ドゥ・ヴァールはこうしたアメリカ的企業社会の「共感欠如の病理」を心配しつつ、これはひょっとしてサル社会やチンパンジー社会で観察できたことが、どこかで人間社会で薄れてきてしまったせいなのではないか、いや傷ついてしまったのではないかと考えたのである。
たとえばモーリス・メルロ=ポンティ(123夜)は「私は他者の表情の中に生きているし、他者も私の表情の中に生きているような気がする」と書いていたが、そういう見方が欠けてきたのではないか。
むろんこのような危惧については、反論がある。そんなことは取越し苦労だとか、チンパンジーの共感力なんてその場かぎりのもので、人間社会はずっと高度な「助け合い」をしている、いちいちサルと人間を較べるなんて愚の骨頂だといった反論だ。
もっと踏みこんだ反論は、そもそもサルやチンパンジーこそ他の哺乳動物にまして権力競争をしているではないか、バナナほしさの成績主義に陥っているではないかというものだ。いわゆる“競争本能論”である。
が、ドゥ・ヴァールも再反論する。すでに『チンパンジーの政治学』や『政治をするサル』でも書いていたことだが、高度なサルたちはたんに競争本能にかまけているのではなく、ある種の行動や価値観をフォーマライズ(儀礼化)し、かつそれをパターンとして記憶・再生・反復することにより、いたずらな過剰競争を回避していると見られるという反論だ。
仮に競争を煽られてしまった場合でも、かれらは「宥和」や「慰撫」や「仲直り」の行動文法を知っていて、エンロン社のような集団にならないようにする。ドゥ・ヴァールは数々の野生チンパンジーの集団観察をへて、このような判断をすることに自信をもったのである。
ところで、ぼくは『チンパンジーのなかのヒト』(1544夜)でもお里が知れただろうように、チンパンジーのことはよく知らない。また立花隆のようにはサル学にも詳しくない。そのくせ、サルや類人猿や霊長類にたいへん関心がある。隠れファンなのだ。だからいつも揺れ動いている。
どう揺れ動いてきたかというと、最初にグドール女史の『森の隣人』(平凡社)やそのドキュメントに刮目したときはチンパンジーにぞっこんになり、その子殺しの習性を知ったときは、さすがに目を背けた。
次に、イモ洗いで有名な幸島の「100匹目のサル」の話については、この話を冒険に採り入れたライアル・ワトスン(101夜)の『生命潮流』(工作舎)の翻訳を手掛けたこともあって最初は大いに惹かれ、ついで疑問をもつようになった。
一方、加納隆至の『最後の類人猿:ピグミーチンパンジーの行動と生態』(どうぶつ社)や山極寿一の『ゴリラ:森に輝く白銀の背』(平凡社)を読んだときは、心の底から誇らしいものを感じた。ゴリラやボノボの本なのに誇らしい感じをもったのが不思議だった。ピグミーチンパンジーとはボノボのことだ。スー・サベージ・ランボーらが飼っている「カンジ」のNHKスペシャルで、パックマンをするカンジを見たときは、こみあげる微笑にさえ誘われた。
ところが松沢哲郎さんとシンポジウムに出て、比較認知学から「アイ」というチンパンジーの能力の話を聞いたときは、理由はさだかではないのだか、どうも納得しきれないものが残った。一方その後、「チンパンジーにはおばあさんがいない」という話になったときは、妙に得心した。その手の話とともに佐倉統さん(358夜)とはときどきチンパンジーの道具使いの話を交わすことがあったのだが、こちらはたいてい納得できた。しかしサル社会のなかで、その道具が進歩していかない理由はわからなかった。
あとは摘まみ食いだ。ビルーテ・ガルディカスの『オランウータンとともに』(新曜社)は大著だったけれど、オランウータン派に染まっていったし、『ヒトのなかのチンパンジー』でも書いたように、今西錦司(636夜)や西田利貞の考え方にはあいかわらず惹かれたままにある。ちなみに和泉佳奈子のサル先生は、下北半島のサル観察から始めてアマゾンの熱帯雨林のサルを30余年にわたって調査した伊沢紘生さんである。
そんなこんなで、いったいどのように類人猿の研究成果を評価してよいのか、ぼくは行ったり来たりなのだ。

サル学は難しい。微妙な問題をいっぱい抱えている。そのことはそのままわれわれヒト学の微妙に結びついている。
ゲノムの解析が進んで、ヒトとチンパンジーのゲノムの違いは2パーセントほどしかないことが判明した。ということは、ヒトは98パーセントのチンパンジーであり、チンパンジーは98パーセントのヒトなのである。とはいえ、それにしてはヒトとチンパンジーはあまりに違いすぎている。両者を比較するには何か別の視点が必要なのだ。
あれこれの先達の本を読みながらそのように感じていたところに、一連のドゥ・ヴァールの著作群が入ってきたのだった。読んでいるうちに、いわばチンパンジーの右の「はしっこ」に共感的利他行動があり、ヒトの左の「はしっこ」にその残響があるように思えた。二つは連続してつながっているのではない。けれども、ずっと遠くから眺めるとつながっていく。そこをどう見ようかという気になってきた。
ソーシャル・スクラッチというチンパンジーの行動がある。マハレの調査研究で注目された(マハレについては1544夜を参照)。一頭のチンパンジーが別のチンパンジーに近寄って、手の爪で何度か相手の背中を勢いよく掻いて、それから座りこむと相手をグルーミングするという行為だ。
チンパンジーが自分の体を掻くのはいつもしていることだから、この行為にはめずらしいものはない。ただ、自分で掻くのはかゆみを紛らわすためだが、別のチンパンジーのかゆみをまぎらわしてあげるメリットは、どこにあるのかというと、これはにわかには結論が出ない。
ドゥ・ヴァールはここにはきっと「他者の受容」や「社会的な慣習」が芽生えているのだと見て、自分たちで飼っているオマキザルが「他者の欲求」を感知できるのかどうか、さまざまな実験と観察をくりかえしてみた。ドゥ・ヴァールたちは二つのグループに分けたオマキザルを飼っていたので、この二つをときどき交ぜて、かれらが食べ物を他者にあげるかどうかを調べた。
そこでわかってきたことは、オマキザルが他者に食べ物をあげているときは、直前にその相手が食べるところを見ていたかどうかにディペンドしているということだった。さらに観察を進めると、食べ物をほうばっているところを見かけた相手よりも、さっきはほうばっていたのにいまは食べ物を口にしていない相手に食べ物を渡すオマキザルがいたということだった。それも何度も観察できた。
ドゥ・ヴァールはこれらを通して「他者の福利に対する関心」あるいは「向社会的な行為」というテーマを掲げて、その後の観察研究をしていった。
本書はこれらの観察や洞察を通して、チンパンジーやサルには「共感」がどのように行動化されているのかを“推測”したものである。
ただし、サルやチンパンジーばかりの観察では推測は前に進まない。イルカやゾウやオオカミなどと比較する必要もある。もっと重要なのはヒトの幼児がどんなふうに共感を示すかだ。ドゥ・ヴァールは他の意欲的な研究者たちによるヒトの共感発生を暗示させる実験や研究を集めまくっていった。
なかに「同時創発仮説」があった。スイスのドリス・ビショフ=ケーラーらが仮説したものだ。
このもともとの実験では、幼児は大人と一緒に生クリームに似たチーズを食べる。大人は途中で自分のスプーンが折れたので、ちょっと困った顔やがっかりしたポーズをとるように仕組まれている。そうすると、どうなるか。多くの幼児がテーブルに置かれた別のスプーンを差し出したり、自分のスプーンを押し付けたりしたのである。なかには折れたスプーンでチーズを刺し、大人に食べさせようとした子もいた。
似たような実験もいろいろ試みられた。おおむね幼児は“人助け”をしてみせたのだ。
結論は必ずしも決定的なものではない。しかし、このような観察研究をいろいろ合わせていくと、そこには「温情」や「援助」や「利他性」を通してかれらなりの未知の報酬快感が動いているだろうことが推測されるのである。
ここまでくると、ぼくもなんとなくそんな気がする。バーバラ・スマッツはマントヒヒが「背中を貸す」という行為をしばしば見せることに気がついた。ロバート・サポルスキーはオランウータンが子供が危難を切り抜けたときに「ホッ」という声を出すことを知った。多くの哺乳動物に、集団が危機に直面するとそのうちの何匹かがやや激しい「ヘッド・フラッギング」(首振り)を見せることがわかってきた。ケイティ・ペインは幼児が大人のおどけたそぶりに反応するのは、同時創発のリハーサルになっているのではないかと考えた。
おそらく、われわれは何かに引き寄せられたがっている動物なのである。その何かとは「協力」だ。その奥にある「共感」だ。でも、ちょっぴり怖いのだ。
ルイス・トマス(326夜)が喝破したように、われわれには「役に立ちたい衝動」というものが潜んでいるはずだ。けれども、社会や組織を形成していくにつれ、何が「役に立つ」かについて、慎重になっていった。こんなこと、役に立つのだろうか、こんなことで喜ばれるだろうかと、思うようになっていった。これが近代社会でピークに達してしまったのだ。われわれは「フラジャイル・スピーシーズ」でもあったのだ。
おそらくは、われわれの脳には「温かい視点」と「冷たい視点」のボタンがあるのだろう。そして、いつもそのどっちを押そうか、天秤にかけているのだろう。それがあるとき、他者や相手が困っているので温かいボタンを押す気になってみたとき、その社会や集団が愉快になったのだ。いや、自分も愉快になれたのだ。それがドゥ・ヴァールの言う「共感」のスウィッチが入ったときなのだ。
人間社会においては、共感力はどこかで道徳と結びついている。ただし、道徳はかつての道徳哲学とか倫理学がそうだったように、かなり優勢と劣位をつくるものでもあった。そこには嘲笑的な価値判断にもとづいているところも少なくなかった。そのうえ道徳はとっくに有償的にもなってきた。いまや「ケア」は同情や共感だけでは成立しないのだ。
しかしチンパンジーやわれわれの共感力には、必ずやもっと低コストの道徳ボタンもいっぱい付いているはずなのである。これを何かの折りに押してみない手はないだろう。
現在社会はいつのまにか異質を排除して、何が何でもハラスメントだと規定するようになってきた。けれども、これまでの多くの動物行動学が示してきたように、人類がもっている共感のリリースボタンはけっこう複雑にできている。だとしたら、チンパンジーのそのボタンが愛と暴力を混在させているように、われわれの共感力も矛盾を孕んで成立したものだと思われる。
おそらく、サルもヒトもとくに利他的な動物ではないはずなのだ。それが集団内や家族間の何かの矛盾の受容を引き受けたとき、本人のほうも得がたい「共感」を受けとるのだったろう。同時創発とはそのことだ。
ただし、ドゥ・ヴァールが「共感の時代」をさらに強調したいなら、そこに「矛盾を編集したくなる動機」を加えるといいのではないかと、ぼくには思える。
そう思っていたところ、ドゥ・ヴァールは新著『道徳性の起源』(紀伊國屋書店)を上梓した。ボノボが教えてくれた道徳的なるものの起源が述べられていた。道徳は上からではなく、ボトムアップで回復するしかないだろうというのだ。

⊕ 『共感の時代へ―動物行動学が教えてくれること』 ⊕
∃ 著者:フランス・ドゥ・ヴァール
∃ 訳者:柴田 裕之
∃ 解説:西田 利貞
∃ 発行者:神田 明
∃ 発行所:株式会社紀伊國屋書店
∃ 印刷・製本所:図書印刷
∃ 装丁:芦澤 泰偉+五十嵐 徹
⊂ 2010年4月22日発行
⊗目次情報⊗
∈∈ はじめに
∈ 第一章 右も左も生物学
∈ 第二章 もう一つのダーウィン主義
∈ 第三章 体に語る体
∈ 第四章 他者の身になる
∈ 第五章 部屋の中のゾウ
∈ 第六章 公平にやろう
∈ 第七章 歪んだ材木
∈∈ 謝辞
∈∈ 解説 西田利貞
∈∈ 注
∈∈ 参考文献
⊗ 著者略歴 ⊗
フランス・ドゥ・ヴァール
動物行動学者。霊長類の社会的知能研究で世界の第一人者として知られている。現在、ヤーキーズ国立霊長類研究センターのリヴィング・リンクス・センター所長、エモリー大学心理学部教授。2007年には『タイム』誌の「世界で最も影響力のある100人」の一人に選ばれている。著書に『利己的なサル、他人を思いやるサル』『あなたのなかのサル』などがある。