父の先見


インピタス 1984
音楽、とりわけロックは、そこに去来する暗喩と影像がもたらす母型の流出なのである。ちょっと付け加えれば、そこにはたいていメランコリアの逆説とノスタルジアの逆転が仕組まれている。けれどもその二つの出所は、意識とも無意識ともつかないあたりの出所そのものが漂泊するのであって、だからこそそこに、聖痕とも病根とも感じられる対立物の合致が高速で動いていく。
阿木譲は『イコノスタシス』(iconostesis)で、こんなことを綴りながら、さらに「あとがき」で次のように告白した。「愛を信じたいといつも思いつづけてはきたが、果たされない。それはやさしい母なる容器がいつまでも僕を包容したまま呑みこんで離さなかったからだ。そんななかで、ドストエフスキーやニーチェ、イーノやジャン・ピエール・タメール、イアン・カーチスなどにみられる個人主義とニヒリズムの哲学や思想に魅かれつづけてきた。それはなによりもかれらには嘘がないということにつきるだろう」。
そして、重ねてこう告白した。Aのメッセージは「ロックは聖なる病いだ、この暗闇の時代の心の空洞を埋める絶望的で潜在的な精神欲求なのだ」、Bのメッセージは「音楽が脳のなかで描く視覚的で抽象的なパータンという暗号を読み、魂という無意識から生み出された記憶に耳を澄ますことこそ、音楽体験だ」。これはまさしくミルチャ・エリアーデがたどりついたエピファニックな両義具有のメッセージであった。
阿木譲の本なら"世界で一番早すぎたロックの遺書"たりえたと評されるべき引き出物『ロック・エンド』(工作舎)でもよかったのだが、これはぼくが執筆依頼をし、ぼくが編集したので遠慮しておく。それで阿木君が自分でおこした出版社インピタスで作ったB5判の函入り『イコノスタシス』にした。カバー折り返しに、ぼくと阿木君の共通の友人・能勢伊勢雄のオマージュが刷られている。
能勢君は岡山大学の向かい側で「ペパーランド」という30年以上も続くライブハウスの超店主であって(こういう長命のライブハウスはいま日本には2軒しかない)、70年代初期には映像作家として先駆的に鳴らし、その後はハイパージッピーとしてラジオのDJをはじめ、すこぶる広域脱境界の表現活動やディレクション活動を静かに展開してきた。
2004年11月から2カ月は、『スペクタクル能勢伊勢雄1968-2004』という、轟音をもって半開しながら無音に向かって凝集するといったカウンター・エクスクロージャーふう展覧会を、倉敷市立美術館と岡山市の複数会場で開いた。これは恐るべき観念をいっときだけ実在化させる遊学展示の集大成ともいうもので、ぼくとの約30年にわたる交流交配の残響がそこかしこに断層されていたこともさることながら、それとともに阿木譲がもたらした多種多彩なサウンド・ミームも、見えない鉄条網をやすやすと破って会場のそこかしこを走っていた。
その能勢君がカバー折り返しに何を書いていたかというと、「阿木譲は喪失した母性への転生としてイコンを欣求している」と書き、そこへそっと1980年5月に自殺した「ジョイ・ディヴィジョン」のイアン・カーチスの死を阿木譲が全身の波動で受けとめようとしている奇蹟を記念して、喝采を添えていた。
本書の半ば、「アイソレーティブ・チェインジ」という数ページが挟まれているのだが、それは阿木君がイアンに捧げた小文字の黙示録になっている。
さて、ぼくがどのように阿木君に出会ったのか、さだかなファーストコンタクト・シーンが蘇らない。きっと30年前に大阪新町で会ったのだとおもう。いまは失踪したまま消息が見えないEP4の佐藤薫がそこに同席していたのかもしれない。
が、会ってその次の機会には、第Ⅱ期が始まろうとしていた「遊」に『ロック・シーン』という連載と新たに始まるレコード批評を頼んでいた。いまでもよくおぼえているが、『ロック・シーン』の連載第1行目は「僕は複製人間。」で始まったものだ。
レコ評のほうは「ディスクリッピング」という二人ずつがノートを担当する人気爆発の企画ページで(このページのレイアウトは羽良多平吉君に頼んだ)、一方は土取利行・秋山邦晴・佐藤聡明・間章などが入れ替わり執筆したのだが、阿木君だけはずっとレギュラーでロングランのチョイス&クリティックを手掛けてくれた。これもよくおぼえているが、第1回目はフィリップ・グランシャーとZAOたちだった。そのノートに、デーヴォ、クラフトワーク、エルビス・コステロらが揃って眼鏡をかけていることを指摘し、「眼鏡をかけたロックが自分は好きなんだ」と書いていたことも、なぜか忘れられない。
そのあいだに、ぼくも阿木君が1976年から創刊していた「ロック・マガジン」(日本で最も過激な深層意識をゆるがす音楽雑誌だった)に、『逆音記』というへなちょこな短期連載をした。
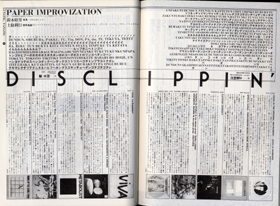
それから数年というもの、二人はのべつ話しこんできた。たいていは阿木君が上京したときに松濤の工作舎に寄ってくれたのだが、阿木君はいつも、いましがたロンドンのボヘミアンカフェから帰ったばかりという風情の黒の皮パンと白いワイシャツを着けていた。上のボタンは必ず二つあいていた。
だいぶんあとになって、ああそうか、ブライアン・フェリーが阿木譲のファッションを真似ていたのだと、お里が知れた。ついでに当時の話をすると、そのフェリーが東京公演に来たとき、必ずメークアップとフェイスマッサージを頼んでいたのが川邊サチコだった。コシノジュンコとともにキラー通りでマリー・クワントのミニスカートを流行させた張本人で、繰上和美がロックをかけながら撮影するモードを定着させたのも彼女だった。彼女は高橋靖子とともに、デヴィッド・ボウイの額に銀色の三日月を化粧させるのも得意だった。
ぼくの周辺には阿木君とともに、そんなパンクでバロックでストーンな老若男女が頻繁に出入りしていた70年代後半の話である。ときおりスーザン・ソンタグや横須賀邦光やボブ・マリーとウェラーズにとりまぎれて、山崎春美のような怪物が遊塾にも工作舎にももぐりこんでいた。
本書には、500以上のバンドやアーティストのディスコグラフィが(それを本書はイコノグラフィと名付ける)、ライナーノーツに似た短いコメントとともにカタログされている。すべて80年代初期のサウンドだ。
こんな紹介では阿木君のとっておきの感覚のごくごく一端しか伝わらないだろうけれど、わが阿木譲が毎夜放っていた言葉の放射圏のメモリアル・ノートとして、以下に紹介する。残念ながらごくごく一部だ。最初と真ん中と最後あたりのアルバム評を、摘まんでしるしておく。やや仮名づかいと言葉をいじった。
FAST PRODUCT=無名時代のジョイ・ディヴィジョン、ヒューマン・リーグ、ダフ、テッド・ケネディズのアルバムである。「80年代音楽はパンクから始まったと言う連中がいるが、パンクは70年代音楽の終焉なのだ。80年代はインディーズから発表されたオルターナティブ・ミュージックあるいはインディヴィデュアル・ミュージックを起源とする」(これは阿木君の持論)。ヒューマン・リーグについては「エレクトロニクスを使用するアーティストはなぜこうも暖かい人間性をいつも歌いあげるのだろうか」(ときどきこういう音のまなざしを阿木君は投げかけるのが好きだった)。「セックス、バイオレンス、ロマンス、アクション、キャッシュ、ヒストリーがファースト・プロダクトの精神支柱だが、キャッシュだけが縁がなかったようだ。ダフの曲も最高にヘヴィだ」。
ALTERNATIVE TV=「オルターネイティヴ・ティヴィはジョイ・ディヴィジョンやスロッピング・グリッスル以上に重要なバンドだった」「共同体の最後の夢を、かれらは実行し音楽化している」(そう、この言い方だ)。ついでさらに「マーク・ベリーとデニス・バーンズの曲にジェネシス・P・オーリッジが参加してバスウェイ・サウンドスタジオで収録されたこのアルバムこそ、名盤と呼ばれるものだ。普遍的な時代を超した音楽だ」と言っておいて、「ジェネシス・P・オーリッジはステージ上で割れたガラスの破片の鋭い先を顔に近づけ、そして口を開き、吸いはじめる」という、まるでトルーマン・カポーティの冷房装置のような一言がコーダに入る。
TUXEDOMOON=ぼくも引っかかっていたアルバムだが、ここは阿木節独壇場のセリフに耳を傾けられたい。「すべての芸術のごとく、タキシードムーンの音楽は、音楽という形象において、表現不可能なもの、禁じられたもの、忘れ去られたもの、脅迫観念なものを表現し、物質化する。しかしそれは、不穏な透明感を従え、エクトプラズム現象を喚起するという明確な性格をも含んでいるのだ。これがタキシードムーンの特異性であり、グループ全体の主題の疑うべくもない無意識の基石(奇跡)である」(うーん)。また、「ヴァイオリンへの絶大な哀悼、憑かれた音楽、滴下する恐れと激変、空虚なヴォイス、息つく間もない多様性、封鎖された喉からいかなる音を発音しようとも、そこには莫大な困難が伴う。しかし知覚可能な限界においては、幻覚こそが現実であり。だからこそそれは遍在するノスタルジアとして漂流できるのである」(また、うーん)。
THE CHURCH=「シーアンスとは呪術的な神降ろしの集会を意味するのだが、このザ・チャーチはもちろんジョイ・ディヴィジョンの精神を受け継いでいる。とてもシンプルでソフトな語り口ではあるけれど、決してあなどってはいけない。こういう音楽こそロックの主流であり、われわれの必要としている象徴というイコノグラフィを最も多く描きだしてくれる」(本書のサブジェクトに沿った解読だ)。
SOFT CELL=音もアンドロギュヌスしたり、シネモゲネシス(相補的分裂生成)するのかとおもわせたバンドだった。「両性具有者としてのソフトセルは、男と女に分離させられた人間こそ、生まれながらにして堕落した存在であり、奇形だというのだろう。このマーク・アーモンドの歌こそ80年代のポップミュージックにまちがいはない。この歌こそわれわれの絶望の時代の愛だ」(この、愛と絶望のトランジションあるいはコンバージョンがめっぽう速いのである)。
COCTEAU TWINS=コクトー・トゥインズのヘッドオーバー・ヒールについて。「夢を追いつづける存在孤児。見たこともない美しくも稀なイメージ。エリザベスとロビンの構成は壊れやすくて月のダンディズムでいっぱいだ」。フラジリティとルナティシズムは、おそらくぼくと阿木譲の共生遺伝子だったのだろう。
THOMAS DOLBY=デビュー作をXTCのアンディ・パートリッジ、ブルース・ウーリー、ダニエル・ミラー、矢野顕子などとマルチート・パフォーマンスを虚構してみせたトーマス・ドルビーの4作目のアルバム「フラットアース」(地平球)。「緻密にコントロールされた非常に幅広い音楽性をもったものに成長している。東洋音階、中近東の民族音楽、レゲエやカリプソ、ファンクが交じってあらゆるジャンルを超越する」。
ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK(OMD)=阿木譲独得の体感反逆の叫びを秘めたニュークリティシズムの声が聞こえてくる。「眩惑船は記号化していく人間性を電子律動にのせて謳歌する」、「プラスティックな人工物や機械に囲まれて生きるほうが、どんなに人間の肉や血を愛おしく思えるか」、「文化とは決してアカデミックな世界から生まれるでるものではなく、がらくたな俗っぽいものなのだ」、そして「最近のイギリスの動向にはアート・オブ・ノイズやフランキー・ゴーズ・ハリウッドなどの最も新しいポップな人間超越主義が見られるが、OMDもこのアルバム(ジャンク・カルチャー)で古い倫理を克服した。が、これは70年代のジャーマン・エクスヘリメンタル・ミュージックの世界なんだ」。ガーン。
ぼくが阿木譲にぞっこん惚れていたことは、多言を要しない。そうでなければ執筆を頼まないし、本を書いてももらわない。
しかしなぜぞっこんだったのかということを、いまはなんとか伝えたい気分になっているのに、やはり言葉にしきれないでいる。それは1976年から数年だけ鳴っていたエジソンの精神ラジオが、なぜかあのときだけ格別実況してくれた名状を許さないシーンだったのである。ひたすら、そのことを日本の1980年前後を疾駆したイコノグラフィック・シーンだったと思い出すばかりである。
けれども、3つだけはっきりしていることがある。第1、阿木譲が参加していなかったら「遊」はあそこまで精彩を放たなかっただろうということ、第2、阿木譲のロックをめぐるクリティックは能勢伊勢雄・間章と並んでつねに当代随一であったということ(中村とうようや田川律や渋谷陽一は問題にならなかったということ)、第3、阿木譲の愛はいまなお君の言葉に接した者の胸でプラチナ製の扇風機のような唸り声をあげているということだ。