父の先見


藤原書店 1999
Emmanuel Todd
L'Illusion Économique 1998
[訳]平野泰明
類書がない本だ。家族人類学や歴史人口学の成果からグローバル経済のサド・マネタリズムを告発した。告発しただけではない。その資本主義的ルーツがアングロサクソン型家族制度にこそもとづいていることを証した。
それとともに、ドイツや日本の社会はこれらに本来はあてはまらないだろうことを暗示した。これはいったい何を意味しているのだろうか。反グローバリズムの狼煙が、このような思想によって議論されることは、少々ながらユニークである。
本書は、大著『新ヨーロッパ大全』(藤原書店)で斯界を唸らせたフランスの若き人類学者エマニュエル・トッドによる、次々にグローバル経済主義の軍門に下っていった各国についての、文句たらたらの問題提起書である。フランス語ではグローバリズムのことを「世界化」(モンデュヤリザシオン)と言うのだが、そのモンデュヤリザシオンに対処しきれなかった自国フランスの単一思考にも、点数が辛い。
1998年の執筆だから、グローバリズム批判としてはとくに先駆的ではない。けれどもトッドは専門が歴史人口学や家族人類学なので、叙述の仕方も経済書とはかなり異なっていた。視点が変わっている。だから本書はたんなる市場原理主義批判や新自由主義批判の本ではない。並みで凡庸なアングロサクソン型の経済学者たちに、私がひとつ人類学的な見方を教え諭してしんぜようというようなムキがある。
経済学、とりわけ新古典派の経済学は、「最小の費用によって最大の利益を求める人間社会」というものがありうると思いこんでいる。これがホモ・エコノミクスによって経済社会を説こうとする連中の理屈だ。けれどもトッドは、それはおかしい、経済は社会や家族の中にあるはずだという見方をしつづけた。まとめていえば「経済はもともと社会に埋め込まれている」という思想だ。そこにフランス人類学独特の構造主義的な見方がまじっているところが、なかなか憎い。
とはいえ、トッドの思想はカール・ポランニーの経済人類学のようなものではない。といってその歴史思想はアナール学派っぽくもない。またフランス人の市場原理主義批判だからといって、ジャック・アタリが9・11の年に刊行した『反グローバリズム』(彩流社)の主張とも、かなりちがっている。アタリは市場主義を批判して「フラタニティ」を持ち上げたのだ(余談だが、こちらは鳩山由紀夫の「友愛」に近いようでいて、近くなかった)。
そういうわけで、グローバリズム批判をめぐった本としては本書に似た類書はあまり見当たらない。いわばトッド主義、トッド流とでもいうものだ。だからこそ一度は覗いておいたほうがいいと思い、千夜千冊に入れることにした。
トッドは、この本のあとに『帝国以後』(藤原書店)を発表してさらにアメリカをこてんぱんに斬ったので、またそのあとに『「帝国以後」と日本の選択』(藤原書店)で対米追随主義を打ち砕いたので、そちらに喝采をおくった読者もいるだろうが、ぼくは本書のほうを推す。
ただし、あらかじめ言っておくけれど、ぼく自身はトッドの図式的で比較を重視した文脈に必ずしも全面賛成はしていない。けれどもこういう見方があることは、知っておいたほうがいい。実にユニークなのだ。ユニークであることには、いったんは敬意を表するべきなのだ。
歴史人口学や家族人類学が世界をどう見るのか、とりわけ冷戦終結後の帝国アメリカの姿とグローバリゼーションに席巻された現代世界をどう見ているのかということが、本書を読むおもしろさである。
トッドは90年代の高度資本主義社会を「たえまない後退の悪夢」とみなした。とりわけ9・11以降のアメリカを「無力感に襲われた国」と観察し、そこには「世をすねた観客」ばかりがいると評した。また、今日の世界を覆っている国際経済は「プラグマティックな経済観」と「スコラ的な経済観」の組み合わせにすぎないと見た。
前者はアメリカのビジネススクールが教えることができる程度のもので、「有用な連鎖」ばかりを重視し、後者は事実が理論と異なればただちに理論が示すほうを選ぼうとする経済観で、現実を理論のほうにねじまげていく。
この2つの経済観が奇妙にまじりあっているのが、21世紀初頭のアメリカ型経済社会の現状だとみなすのだ。したがってトッドは、ケインズにもフリードマンにも与しない。ホモ・エコノミクスの合理性に絡めとられている経済理論そのものに、「ああいう理論は合理的というより、場所も時も選ばない形而上学だ」と文句をつける。
とくにアメリカがシカゴ学派とウォール街によってマネタリズム(新自由主義)に暴走していったことについては、辛辣だ。EU統合後の共同通貨ユーロの導入がいいと言うのではない。アメリカ式マネタリズムもヨーロッパ式共同通貨も、その根っこは“貨幣神秘主義”というべきものであるが、プロテスタンティズムの歴史的伝統から発展して金融工学に及んだマネタリズムと、ヨーロッパの人類学的な資質から生じた「マーストリヒトの通貨」とを、同じ思想で考えるべきではないというのである。
たしかにそうだろう。WASPがもたらしたマネタリズムは、スーザン・ストレンジが言ったとおりのマッド・マネーだったのだ。もっともトッドは、これをマッド・マネーとは言わずに「サド・マネタリズム」(加虐的マネー主義)と揶揄してみせた。
これまでグローバル経済主義や新自由主義のイデオロギーは、たとえ疑似的ではあれ、「平等」観や「自由の再生」観と結びついて肥大化していったと考えられてきた。だから仰々しくも「自由」などという言葉がマッド・マネーにもサド・マネタリズムにもくっつきまわっていた。
つまりは、マネタリストにも自由志向があったのに、それが行きすぎになったのだと好意的に解釈されてきた。しかしトッドは、とんでもない、そうではないと声を上げた。むしろ自由や平等の価値が資本主義社会のなかで下落していったから、そのためグローバル金融主義が自由や平等の“嘘の衣”を着るようになり、それを標榜するようになったのだと見た。
ヨーロッパ近代(18世紀)がつくりだした理性主義は、もともと二重の公理を隠しもっていた。ひとつは「個人」には人格と欲望があって、その長所と欠陥は合理的な計算能力によってなんとか統一できるというものだ。もうひとつは、その個人も「集団」なくしてはありえず、それゆえ生活や言語や習慣はその集団によってこそ保証されているというものだ。2つの公理は互いに互いを補完しあっていた。
トッドは後者から前者を切り崩そうとした新しいタイプの研究者である。そのための武器が歴史人口学と家族人類学なのである。どういうふうにその武器を使うのか。
たとえばアメリカについては、なぜアラブ・イスラム圏と癒しがたい敵対関係に入ったのかという問いを立てる。トッドによれば、この敵対関係は原初的で人類学的なのである。アメリカの家族は核家族で個人主義的で、女性に高い地位を保証する。一方、アラブの家族は父系による拡大家族で、女性を最大限に依存の立場におく。いとこ同士の結婚はWASPのアメリカではタブーだが、アラブ圏では優先される。
こうした背景のもと、レギュレート(統制)された多様性を管理するアメリカは、世界の多様性に対してはしだいに不寛容にならざるをえない。とくに一夫多妻のテロリストを生み出すしくみをもっているアラブ・イスラムの過激主義に対しては。
そうだとすると、アメリカの家族帝国主義性がアラブ・イスラム圏との紛争をおこすことは、トッドふうに言えば「ある意味ではプログラム化されている」わけなのだ。
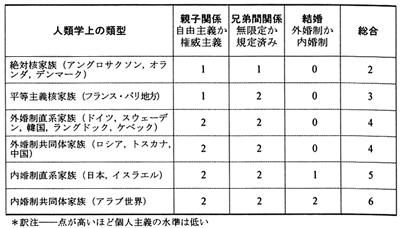
トッドは、合理性と効率性を金科玉条にしたグローバリゼーションはアングロサクソンの思考と習慣が生んだものだと見ている。それがアングロサクソン的家族制度からの派生だとも見た。そして、そういうものがグローバルな価値観になるなんてことはどう転んでも「幻想にすぎない」と見切ったわけである。本書に『経済幻想』というタイトルが使われているのは、そのせいだ。
ホモ・エコノミクスのような平均的で統計的な個人などいるはずもないのに、そんなものを想定したアングロサクソンは、やがて個人主義を強く市場主義と結びつけた。トッドは、それがどうして普遍的な自由主義のよそおいを発揮しながら全世界を席巻する勢いをもてたのかを、心底、訝ってきた。それゆえ、そういう怪しげな自由主義を、トッドはシカゴ学派のように「新自由主義」とは言わずに、あえて「超自由主義」(ウルトラリベラリズム)と名付けた。
ふりかえってみると、イギリス・アメリカ・フランスはその国民性がもっている自由主義的で非平等主義的な「エリートたちの反国民主義」によって、この超自由主義の勢いをやすやすと受け入れてしまっていた。ただし、英米とフランスでは解釈がちょっと違っている。
イギリス的なるものは、その旧植民地がもたらした絶対核家族性から派生する。この家族制度は核家族を原則として、親と子供を早期に分離し、自立させていく。そのため遺言はいちじるしく非平等になる。当然に、このような習俗からは独特の個人主義観念と経済観念が生まれる。ここからアングロサクソン独特の「短期利益の最適化」という価値観が確立していった。ロジックの内的一貫性はあるものの、つねに過剰消費を生みかねないものなのだ。
一方、フランス的なるものは、最初はパリ地方に支配的な平等主義的核家族性から派生して、南北イタリア、ポルトガル中心部、中部・南部のスペイン、ポーランドというふうに波及した。イギリス型ほど個人主義的ではないが、フランスふう単一思考であることは変わらない。ヴォルテールの『カンディド』のパングロスなのだ。熱狂的受動主義なのだ。
ぼくには以上のような家族人類学が指し示すイギリスやフランスの特徴が当たっているのかどうかは、わからない。いかにも図式的であるようにも思えるが、本書および『新ヨーロッパ大全』を読んでいると、なるほどそうかもしれないとも思える。
そもそもトッドがこのような見方をするのは、その家族制度研究にもとづいた歴史人類学によっている。ほとんどヨーロッパの家族社会文化の研究で、大きくは次のような分類をした。
絶対核家族……最初のカップルが子供をつくり、その子供たちは成年に達すると独立世帯を構成する。親の遺産は子供たちのあいだで分けられるが、そのやりかたは厳密ではない。親子間は自由主義的で、兄弟間では平等が軽視されている。
平等主義核家族……最初のカップルが子供をつくり、子供たちは成年になると独立の世帯をもつ。親の財産は子供たちのあいだで細密に分けられる。独立世帯は自由主義を、財産分配は平等主義を反映している。
直系家族……最初のカップルが子供をつくり、そのうちの男子の一人が成年に達して結婚すると、当初の家族を離れることなく生活をともにする。他の子供は出身家族集団に独身のままとどまるか、あるいは家を出て結婚し、新たな世帯を形成する。遺産の多くは家を継いだ男子(あるいは跡取りとなる婿をとった娘)の家族を中心に分与される。親子間は権威主義で結ばれ、兄弟間は不平等。
共同体家族……最初のカップルが子供をつくり、成年に達するとすべての男子が結婚することができ、妻を親の家に入れて住まわせる。息子たちが子供をもつようになると三世代で同居し、大きな家族共同体を構成する。遺産はおおむね兄弟間で分けられる。親子間は権威主義的だが、兄弟間は平等。
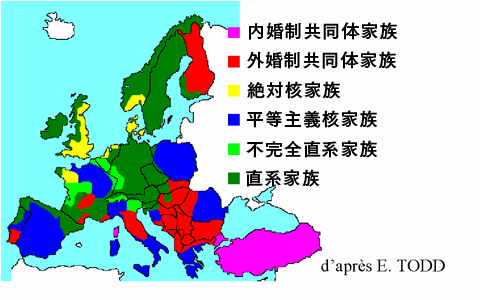
この大まかすぎる分類は、さらに(1)外婚制共同体家族、(2)内婚制共同体家族、(3)非対称共同体家族、(4)権威主義的家族=直系家族、(5)平等主義家族、(6)絶対核家族、(7)アノミー的家族、(8)アフリカ・システムというように分けられるが、ここではその理由と説明は省く。
ともかくもトッドは、このような家族制度の傾向が歴史的な背景をもっていることについて研究し、そこから今日のグローバル資本主義の着床の仕方を論じたのである。
たとえば、平等主義核家族がローマ時代の継承で、イタリア北西部・南部、北フランス、パリ盆地、スペイン中心部、ポルトガル中心部などに顕著になっている。絶対核家族の代表はイギリスである。他にオランダの一部、デンマーク、ノルウェー南東部が入る。直系家族はゲルマン民族の色彩が濃いもので、ドイツ全体を覆っているとみなし、この類型が世界で韓国と日本に残っていることを重視した。共同体家族は西ヨーロッパには少ないが、ロシア、東ヨーロッパ、中国、ベトナムには顕著であると見た。
興味深いのは、このような視点で各国各民族の社会史を見ると、フランスが「自由」「平等」を謳うのは北フランスの家族制度から出てきたものであるだろうこと、イギリスが「自由」を絶対核家族の親子関係にもとづいて採用していながら、兄弟間の不平等にもとづいて競争を許容していて、それが資本主義のイギリス的発達を促したであろうこと、ドイツがライン型資本主義ともいうべきシステムを根強く発揮しているのは直系家族型の権威主義が生きつづけているからであろうこと、共産主義がロシアや中国で植え付け可能になったのは共同体家族を維持していたからであろうことなどを、説明することができそうだということである。
ぼくはそのような説明が歴史的事態の本質の多くを理論化できているのかどうか、ましてそこからグローバル資本主義のルーツをイギリス型アングロサクソン主義に帰一させられるのかどうか、いまもって自信をもって賛同しきれない。
とくに、このような見方が「アングロサクソン型の個人主義的資本主義」と「ドイツ=日本の直系家族資本主義」の“説明”になるというふうに及んでくると、そしてそれゆえにドイツや日本のような国民国家には「超自由主義」や「サド・マネタリズム」は根付かないとなると、さあ、どうなのかと思う。しかしトッドは、ドイツが族外婚的であるのに対して、日本は族内婚的であるからその相違が資本主義にもあらわれるだろうとも踏みこんでいて、そこまで言われると、うーん、なるほどと、半分頷きたくもなってしまうのだ。
先にも書いたように、トッドの独特の見方は『帝国以後』ではさまざまな現状分析に進んで、グローバル資本主義の質感のようなものがどのようにアングロサクソンから発信されて世界に流れていったのか、地域によってはそれがどうして定着しなかったのかという分析にまで達した。
そこには、アングロサクソンはなぜフェミニズムを称揚したのかとか、ロシアはどうしてウクライナ問題を抱えざるをえないのかといった、文化的にも地政学的にも説得力のある予想的分析も含まれていた。
とはいえ一方、トッドの世界史における資本主義の分類については、やや古い感じもする。ぼくも千夜千冊してきたハムデン=ターナーとトロンペナールスの『七つの資本主義』(日本経済新聞社)やヤーギンとスタニスローの『市場対国家』(日本経済新聞社)などにも依拠しているようで、そうだとすると、もっと本格的な制度分析をした資本主義類型論やレギュラシオン理論による分類などともぶつかり稽古をしたほうがいいようにも思われる。
たとえばブルーノ・アマーブルの『五つの資本主義』(藤原書店)では、アングロサクソン型、大陸ヨーロッパ型、社会民主主義型、地中海型、アジア型という分類になっていて、このあたりの分析とどう“辻褄”を合わせるのかという課題がのこる。
ドイツと日本を重ねる「日独型資本主義」という見方についても、たとえば日本のコーポラティズム(協調主義)などに注目すると、いちがいにドイツと同じには見えてこないものがあるわけで、そこを家族制の特質だけで解読突破するわけにはいかないところもある。ロナルド・ドーアの『日本型資本主義と市場主義の衝突』(東洋経済新報社)などは、そこを拾った。
しかしながら、それらをあれこれ考慮してなお、やはりトッドの見方は二度、三度は覗いておくべきである。今夜はそのことを示しておきたくて、反グローバリズムの狼煙の上げ方の一端として紹介した。

【参考情報】
(1)エマニュエル・トッドはポール・ニザンの孫である。1951年生まれで、25歳のときに『最後の崩落』を発表してソ連体制の内部崩壊を予言した。ケンブリッジ大学のピーター・ラスレットのもとで歴史学を学び、パリ政治学院で人口統計学を修めた。
この手の論客としては若い。若いだけではなく、研究の方向がぶれないし、問題を抉る視点がつねに新鮮でもある。32歳のときの『世界の多様性』(藤原書店)はコミュニズム、ナチズム、リベラリズム、イスラム原理主義を同じテーブルで論じ、『デモクラシー以降』(藤原書店)では協調的保護主義の問題点を突き、『移民の運命』(藤原書店)では多文化主義の問題点を浮上させた。
トッドの家族人類学を見るには『ヨーロッパ大全』が最も基本になるが、なにしろ大著。わかりやすくはトッドを多く翻訳している石崎晴己が編集構成した『世界像革命』(藤原書店)などのほうが便利かもしれない。また歴史人口学については、ピエール・グベール『歴史人口学序説』(岩波書店)、速水融の『歴史人口学の世界』(岩波書店)、カルロ・チポラ『経済発展と世界人口』(ミネルヴァ書店)などがある。
(2)トッドの著作をあらかた翻訳刊行している藤原書店はたいへんユニークな版元だ。1990年から出版を始めたニューウェーブだが、その当初から出版業界の不況や黄昏の状況不安をものともしない凄み、深み、広がりがある。たとえばフェルナン・ブローデルの『地中海』全5巻、『石牟礼道子全集』全17巻、『正伝後藤新平』全8冊をはじめ、アナール派の歴史書、レギュラシオンの理論書、ピエール・ブルデュー(1115夜)、エマニュエル・ウォーラステイン、アラン・コルバンなどの著作をかなり刊行してきた。バルザックやゾラのセレクションもある。きっと売れないものも多いだろうに、まったくその負荷を感じさせないのは、立派だ。オルハン・パムクの『わたしの名は紅』(1234夜)にお目にかかれたのには驚いた。
その全貌は、藤原書店の本を買うとたいてい挟みこみになっている「機」という小冊子か、季刊の機関誌「環」をご覧になるといい。刊行著作をかなり大事に扱っていることがすぐ伝わってくる。とくに強調したいのは、出版物を単著として刊行するだけでなく、その周辺をシンポジウム、フォーラム、研究会、インタヴューなどで“支援”していくというやりかただ。ぼくはかつて「エコノミスト」誌上で藤原良雄社長と対談したことがあるのだが、そのときこの版元は日本の出版界の新しい力を示すだろうという印象をもった。装幀もほとんど藤原さん本人か、社内で手掛けるらしい。