父の先見


使命と誤算
中公新書 2009
情報の経済学者として知られるジョセフ・スティグリッツの『世界を不幸にしたグローバリズムの正体』(徳間書店 2002)が告発しているのは、IMF(国際通貨基金)と世界銀行(IBRD・IDA)と世界貿易機関(WTO)だった。とくにIMFである。
スティグリッツは1997年2月に世界銀行の上級副総裁に就任し、2カ月後にエチオピアに行って、かつてはゲリラ戦を指揮していた首相メレス・ゼナウィがIMFと闘っているのを見て、この世界機関が何か恐ろしい正体をもっていることを直観したという。
他の国ではあてはまるかもしれないが、エチオピアではゼッタイに行使してはならないプログラムを押し付けているのだ。スティグリッツには、「説明責任」と「結果による判定」だけをふりまわして、ひたすら教条的な自由主義経済の政策を相手国の事情におかまいなしに耕運しようとしている巨大トラクターが、いままさにエチオピアを蹂躙しつつあるように見えたのだ。
いったい、こういうことをやってのけるIMFとは何か。
教科書的にいえば、IMFは第二次世界大戦後の世界経済の安定的発展をはかるため、国際収支の困難に直面している国々に対して資金支援をおこなうために設立された国際機関である。これによってIMFと世界銀行の二枚看板による、いわゆるブレトンウッズ体制が発動した。
その当初の目的は国際的な通貨の安定をめざすためのものだった。それゆえIMF(International Monetary Fund)は名目上はあくまでも「国際通貨基金」なのである。
しかし、IMFは世界の資金難を救助する公平な国際機関というより、アメリカのドル基軸体制を支える強力な装置であり、とりわけワシントン・コンセンサス(後述)を掲げて世界に市場原理主義とグローバリズムを広げる“主役”になってきた協力機関であった。
実際にも時がたつにつれ、IMFはしだいに途上国・新興国に対する金融面での支援出動が頻繁になり、IMFプログラムが実施される国々の政治経済社会を根底から脅かすようになった。IMFが融資を受ける当該国に対して、融資と引き換えのコンディショナリティ(融資条件)として、きわめて多くの困難をともなう政策的な構造改革を要求しつづけた。エチオピアはそのほんの一例にすぎない。
だいたい支援を受けなければいけないような国々がひどい財政ピンチになっているのは、その政治体制がピンチになり、農業も工業も企業もあやしくなっていたからである。そうに決まっている。
そんなときにIMFプログラムが財政支出削減のための緊縮政策を融資国に要求すれば、公的支出が大幅に削減され、急激な民営化やリストラをせざるをえなくなる。たちまち政権交代を余儀なくされること、火を見るよりも必至なのである。
スティグリッツの本を読んで、ぼくはIMFの実態に呆れた。しかし、この本が書かれた2002年からこっち、その後の世界は金融同時危機さえ迎えるようになったのだ。グローバリゼーションの影の主役はIMFばかりではないことも知れわたったのである。
では、その後のIMFはどうなったのか。そこであれこれ関連本を読んでみたのだが、ジョージ・ソロス(1332夜)のものを除いては、どうもぴったりとした本がない。IMFや世界銀行のことなんて、どんな現代経済史の本にも現代経済学の教科書にも載っていて、その概要がわかるようになっていると思うかもしれないが、どっこい、実はそうではなかった。
日本の書物でいえば、90年代に本間雅美の『世界銀行の成立とブレトンウッズ体制』(同文館出版)、大野健一・大野泉の『IMFと世界銀行』(日本評論社)があったくらいで、ほとんどが21世紀になってからやっと“解説”されたという現状なのだ。ぼくが見たかぎりは、毛利良一の『グローバリゼーションとIMF・世界銀行』(大月書店)が早かったと思う。
そうしたなか、本書はIMFの歴史と将来について、慎重ではあるものの、最もうまく書かれた一冊だったのである。さまざまな問題をコンパクトに割り振りながら、あまさず正確に扱っている。スティグリッツのような激しい告発力はまったくないけれど、そのぶん淡々とIMFの狂った体質が伝わるようになっている。
本書刊行ののちのIMFについていえば、ごく最近の2008年秋のリーマン・ショック以降の例だけをあげても、アイスランド、ハンガリー、ラトビア、ルーマニアが、IMFプログラムを受けてあっというまに政権が崩壊するか、交代してしまったのだ(アイスランドにいたっては、その後に国そのものが経営破綻した)。ジョージ・ソロス(1332夜)の“悪名”を高めたアジア通貨危機のとき、インドネシアでスハルト政権がもろくも崩壊したのも、まさにIMFプログラムの導入が引金になっていた。
この20年ほどのIMFプログラムの大要は、緊縮政策によって財政支出を削減し、金利を引き上げ、輸入を減少させて、経常収支を改善させるというお決まりのメニューになっている。
短期で経常収支の均衡を達成させるために、国内景気を冷えさせて輸入受容を抑え、中央銀行(日本なら日銀)によるマネーサプライ(ハイパワードマネー)のコントロールと金利引き上げをさせるというメニューである。これによって貿易・経常収支を均衡化するという方針だ。
しかしIMFが出動すると、たいていの国では景気悪化にともなって税収が激減するから、財政支出は逆に悪化する。国が危機的な状況に陥っているときに、短期間の政策転換を求めること自体が、どだいムリなのだ。これについてはスティグリッツも告発しているが、しかしながら性懲りもなく、これを2002年以降もくりかえしてきたのがIMFだった。
これって何に似ているかといえば、小泉構造改革が財政緊縮政策をとって、社会保障・医療・教育への支出を削減し、地方自治体向け支出を絞っていったことに似ている。いや、そっくりだ。ただし日本は経常収支が黒字の国で、対外借入をしていない。だからIMFプログラム受け入れ国のような最悪の事態はおこらなかった。それどころか、当時の小泉改革をIMFの幹部たちは称賛さえしていた。しかし、そのことこそが問題だったのだ。
もっともごく最近になって、国際的な金融取引に対する監督規制の必要が叫ばれるとともに、こうしたIMFの金科玉条プログラムが問い直されるようになったらしい。しかし問い直されるようにはなっても、改善には着手していない。IMFは新古典派が大好きなマクロ経済しか相手にしていない機関なのである。そこには実は本来のグローバリゼーションに対する見解も、むろん各国のミクロ経済に対する哲学も、からっきしなかったのだ。
1332夜にもあらかたのことを書いておいたけれど、1944年7月、IMFは世界銀行とともに生まれた。
ニューハンプシャー州ブレトンウッズで連合国45カ国が通貨金融会議を開き、二つの大戦の間にブロック経済が膠着状態に達したため、世界の貿易と経済が縮小したことを転換するために設立された機関だった。理念的な方針は「保護・差別・双務主義」から「自由・無差別・多角主義」への転換である。
しかし設立当初から、方針と具体案をめぐっての大きな対立があった。イギリスが提出したジョン・ケインズ案とアメリカが提出したハリー・ホワイト案の対立がおこっていた。
ケインズ案は「国際清算同盟案」にもとづいて、貨幣創出機能と信用創造機能によって国際的な財政収支の不均衡を是正しようとするもので、国際決済通貨「バンコール」を発行するという独創的なプランになっていた。黒字国に黒字をためこませず、赤字国にも制限を設けて、黒字国から1パーセントずつを徴収して、その基金でバンコールを発行すれば、それがいずれ世界の基軸通貨になるだろうというシナリオである。
これに対してホワイト案はその後のIMFそのものに近く、「短期的な外貨流動資金の提供」に目的を限定した基金主義を提案していた。今日から見ればケインズ案が断然すぐれていたが、しかしアメリカはケインズ案では赤字国に一方的な支出を迫られること、ドルを基軸通貨としたいこと、戦後社会でヘゲモニーを握りたいことなどなどの理由で、ケインズ案を退け、ホワイト案を採択するように工作した。
こうしてIMFは「金1オンス=35米ドル」という固定相場制をもってスタートし、世界に金ドル本位制を定着させた。
60年代までは融資国もほとんど先進国ばかり、コンディショナリティ(融資条件)もスタンドバイ取極(SBA)がある程度で、融資期間中の引き出しにも審査がなかった。
それが60年代後半に長引いたベトナム戦争どろ沼化の影響で、アメリカの軍事費拡大による財政収支が悪化し、ドルの信認低下が著しくなってきて、たまりかねたニクソンが1971年に「ドルと金の交換を停止」を発表(ニクソン・ショック)、翌年から各国が変動相場制に移行するようになると、IMFは急激にアメリカに好都合なコンディショナリティの強化に向かうようになった。そこに、石油価格の変動に対処するという名の緊急融資の導入という手も加わった(オイル・ショック)。
IMFは80年代に入ると、中長期の構造改革を迫る融資期間に変貌していった。これこそはスティグリッツが告発するIMFプログラム「構造調整政策」の押し付けになっていく。ラテンアメリカ諸国がその実験的な対象になったことは、すでによく知られている。
IMFプログラムが本格的にその金融資本主義の片棒をかつぐような正体をあからさまに見せはじめたのは、ワシントン・コンセンサスの前後からのことである(この名称は、IMF、世界銀行、アメリカ財務省がいずれもワシントンに所在するところから付いたニックネーム)。
もともとは1985年10月にアメリカのジェイムズ・ベーカー財務長官が発表した「ベーカー・イニシアティブ」が発端で、ここにはラテンアメリカの経済救済を名目に、こうした諸国を支援するには公的資金や国際機関からの援助だけでは不足があるので、民間に応分の負担を求めるという“要請”が含まれていた。これはいまでは、日本やヨーロッパの銀行に資金を分担させる狙いだったことがわかっている。
ここに1989年、シンクタンク国際経済研究所(IIE)のジョン・ウィリアムソンによる「自由主義経済拡大の方針」が加わった。まとめれば、次の10項目で、これをIMFが踏襲することになった。
①財政赤字の是正、②財政支出の変更、③税制改革、④金利の自由化、⑤競争力のある為替レート、⑥貿易の自由化、⑦直接投資の受け入れ促進、⑧国営企業の民営化、⑨規制緩和、⑩所有権法の確立。
これでバレバレなように、ワシントン・コンセンサスには「小さな政府」「規制緩和」「市場原理」「民営化」がズラリと並んでいる。まさに小泉・竹中の構造改革のお題目だった。あのときの日本はいまさらIMFメニューの真似などしてはいけなかったのである。
ワシントン・コンセンサス以降のIMFが、メキシコのテキーラ危機で最初におこした資本収支危機、ブラジル危機の際に導入したレアルプラン、アルゼンチン危機のときのカレンシーボード制の導入などが、ことごとくうまくいかなかった例については、ここでは省く。
また、1997年から翌年にかけて襲ったアジア通貨金融危機において、タイ、インドネシア、韓国に対してIMFが打った手が、またぞろことごとく各国事情をかえって悪化させたことについても、ここでは省く。このあたりのこと、ソロスがIMFと闘っていた時期にもあたるので、1332夜を参照されたい。
でも韓国の例だけをスケッチしておけば、韓国はアメリカにとっても“重要国”であったにもかかわらず、それゆえ外貨流動性の供給をこそおこなえばよかったのだが、金利の大幅引き上げ、財政緊縮措置、金融機関の整理統合、企業のリストラ、金融規制の撤廃、財閥の信用保証の解消などの“構造改革”を急激に求めたため、かえって韓国の経済危機に拍車をかけたのだった。
このようになってしまうのは、IMFの分析シートが経常収支を抑制するというフレームワークばかりを重視しているからである。この分析シートはIMFのフィナンシャル・プログラミング(FP)と呼ばれる。これが各国の実体経済を無視した、新自由主義的な、つまりはワシントン・コンセンサス型の押し付けをばらまくことにもなったのだった。
いま、さすがにIMFプログラムは見直しを迫られている。2008年秋のリーマン・ショック以降の世界金融危機後の世界を前に、現状のIMFプログラムのままではこの危機を対処しきれないからである。とくに途上国や新興国を潰してしまう。
第1に、資本取引や金融自由化を早期に実施するのは、経済変動リスクを高めるばかりで、その国にふさわしい安定的な経済成長にはならない。第2に、株式や債権などの証券投資を促して、かえって短期流出を誘ってしまう。第3に、途上国や新興国では国内貯蓄率がしっかりすべきなのに、その風潮をぶちこわしてしまう。
しかしながらIMFは、いまだに自身の改革に向かっていない。IMFのスタッフにあいかわらず新古典派的な「自由化」を信奉するエコノミストが集中しているらしいこと、いまなおアメリカ金融界の利害が組みこまれていることなど、根深い体質に問題があるようなのだ。スティグリッツがさんざん文句をつけた体質だ。まあ、治らないのかもれない。
このため、最近ではIMFにはもう頼らずに、「通貨スワップ」で経済危機を国際的にのりこえる方式が検討され、この方式が一部では各国間に導入されるようになってきた。2007年12月にはFRB(アメリカ連邦準備制度)とECB(ヨーロッパ中央銀行)とスイス中央銀行が通貨スワップを決め、2008年10月にはブラジル・メキシコ・韓国・シンガポールとFRBがスワップ協定し、その2カ月後には日本も中国・韓国との3カ国スワップ協定の拡充を決めた。中国は韓国・香港・インドネシア・マレーシア・ベラルーシと通貨スワップを締結した。
IMFがいまだにコンディショナリティに「貿易自由化、民営化、公共部門の賃金抑制」などを謳っているのは、かなり実情とそぐわなくなっているはずなのに……。
【参考情報】
(1)著者の大田英明は2005年からは愛媛大学の総合政策学科の教授を務めているが、1984年には国連工業開発期間(UNIDO)の本部で途上国・新興国の支援プログラムに従事し、その後は野村総合研究所(NRI)でアジア調査部や経済調査部に属して、各国の経済調査に従事した。とくに資本の急激な流出にともなう通貨下落の調査研究、いわゆる「資本収支危機」の調査研究が、著者の目を鍛えたようだ。
IMFの今後についても、大田は独自の改革案を用意している。詳しいことは知らないが、ケインズ案がもっていた信用創造機能をもつ「世界中央銀行」のようなものをつくって、融資機能をIMFから切り離すというアイディアのようだ。以下の図が概念図になっている。
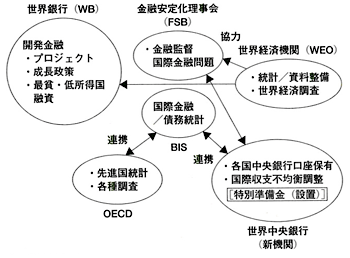
(2)IMFにはSDR(特別引き出し権)という制度がある。SDRは利付きである。これをどのように使うかは、実は新しい国際援助資金の活用になんらかの展望を与える可能性がある。ジョージ・ソロスがSDRを国際協力のために「贈与」すべきだと言いだしたのは、そのひとつだった。1332夜を参照されたい。
(3)ジョセフ・スティグリッツの『世界を不幸にしたグローバリズムの正体』(徳間書店)の原題は“”Globalization and Its Discontents”。2001年にノーベル経済学賞を受けた直後の著作だった。
スティグリッツは1943年の生まれで、アマースト大学、MIT、ケンブリッジ大学をへて、エール大、オックスフォード、プリンストン、スタンフォードなどで教鞭をとったのち、いまはコロンビア大学教授。早くから「50年に一人の逸材」と言われ、「情報の非対称性」に注目して数学モデルに頼らない経済学を研究しつづけた。1993年にはクリントン政権の経済諮問委員会(CEA)の委員長もしている。
邦訳には『新しい金融論:信用と情報の経済学』(東京大学出版会)、『人間が幸福になる経済とは何か』『世界に格差をバラ撒いたグローバリズムを正す』(徳間書店)、『スティグリッツ教授の経済教室』(ダイヤモンド社)などがある。
(4)世界銀行は正式には「国際復興解発銀行」(IBRD)という。ブレトンウッズ体制とともに設立され、当初は第二次世界大戦で疲弊したヨーロッパや日本の「復興」に重点がおかれた。ただし復興援助にはマーシャル・プランなどの発動もあったため、約10年でその任務を終了し、60年代からは途上国の開発支援が主要目的になった。それとともに低所得国向けの低利融資と無償融資を業務とする国際開発協会(IDA)を設立し、その後は世界銀行はIBRDとIDAの両方を総称する。
ところでIMFがワシントン19番街の本部中心の組織であるのに対して、世界銀行は世界各地に事務所をもっていて、その職員数も1万人を超える。各国のミクロ情報を調査研究するためである。それにもかかわらず、80年代まで世銀はIMFと似たようなプログラムで運営されてきた。これを新たに転換したのが、1995年に総裁に就任したウォルフェンソンと、その2年後に副総裁になったスティグリッツだったのである。けれども、この二人をもってしてもワシントン・コンセンサスにもとづくグローバリゼーションの波には抗しきれなかったようだ。