父の先見


市場主義的リベラリズムの限界
新書館 1999
装幀:ADR
2007年8月のパリバ・ショック、2008年9月リーマン・ショック以降、グローバル経済と先進資本主義各国の国内経済の痛手はまだまったく癒えてはいない。
やっと国民医療保険の議案を成立させたオバマ・アメリカも、その実情はそこらじゅうで倒壊や火災がおきている。この2年で1万2000軒の店舗がクローズし、シャーパーイメージやリネンズ&シングスといった小売業が倒産していった。ソニーやパナソニック商品を扱ってきた最大手のサーキットシティが連邦破産法による手続きに入って事実上倒産したことも、まだ最近のニュースだ。
それなら日本はどうか。いったい「二番底」はどこにあるのか、それともひょっとして「底抜け」こそが待っているのか。それともゆっくりと回復していくのか。エコノミストたちの議論はいまだ右顧左眄がかまびすしい。すべてはマッド・マネーと金余りによる金融危機がもたらした傷痕である。いや、次から次への病巣の転移だった。資本があたかも意思をもったかのように自己増殖しつづけたことが、こうした異常事態をいまなお続行させているわけだ。
問題は、この事態は修復可能だろうと思いすぎていることにある。さまざまな手を打ちさえすれば、きっと元にあった状態に戻るはずだと想定していることにある。ヘッジファンドやプライベート・エクイティファンドが健康を取り戻せば大丈夫だと思いこんでいるのだ。えーっ、そんなわけはないじゃないか。これは資本主義が抱えた本質的なビョーキの露呈だったのだから、もっと根本的な問題を切開しなければならないはずなのだ。元に戻ってはだめなのだ。
それにしても、なぜこんなことが気がつかなかったのか。そんなにもグローバル・キャピタリズムの猛威はウィルス並みだったのか。
表題はいささか気負っていたが、金子勝の『反経済学』(新書館)にはそうとうの先見の明があった。刊行は1999年、所収論文はそれ以前の数年間のものだ。海外では主張こそあれこれ異なってはいたものの、スーザン・ストレンジ(1352夜)、ポール・クルーグマン、ハイマン・ミンスキー、ジョセフ・スティグリッツ、エマニュエル・トッド、ジョン・グレイなど、いくつかの先駆的研究は出ていたのだが、このころ、のちに市場原理主義と一括されることになった動向に、いちはやく批判的洞察をもたらした日本人はあまりいなかった。
ふーん、あっぱれだな。こういう経済学者が日本にも出てきたのかと思った。かつての岩井克人(937夜)とはまた別種の路線をつくりつつあるようだった。ぼくは慌てて『反経済学』の原型となったらしい『市場と制度の政治経済学』(東京大学出版会)をさっと読んでみた。やっぱり早い。その先見にまずは敬意を表したい。
その後、金子はたくさんの著書やエッセイをものした。かつて「朝まで生テレビ」で田原総一郎の乱暴をかいくぐって鳥めいた発言をしていた姿は、その後は自身で司会をするCS番組を持つようになった。はあ、はあ、ふーん、姜尚中(956夜)とは好一対だな。それにしてはいささか似た本を書きすぎじゃないか、焦っているのじゃないかと気になったが、読んでみるとそれぞれどこかにヒントが勃発していて、悪くない。
加えて経済学者としてはちょっぴり異端の香りがするのが、カワイくていい。それが“反経済学”というタイトリングにもあらわれたのだろう。異分野との接し方も好感がもてた。たとえば大澤真幸(1084夜)との対話『見たくない思想的現実を見る』(岩波書店)も脂が乗っていた。八面六臂の大澤君の見方に引きずりこまれていなかった。
ということで、いつか金子勝をとりあげようと思っているうちに、ここまで引っ張ってしまった。今夜はとりあえず記念すべき『反経済学』にしておいたけれど、この本がベストだということではない。もう少し最近のものならば、『閉塞経済』(ちくま新書)とか、アンドリュー・デウィットとの共著『世界金融危機』や『脱「世界同時不況」』(ともに岩波ブックレット)あたりのほうが、入門にはわかりやすいかもしれない。
とくに旧著『反グローバリズム』を改編した『新・反グローバリズム』(岩波現代文庫)は書き下ろしに近く、最近の金子の考え方を最もインテグレートしているようにも思う。というわけで、以下は金子の見解を上記のいろいろの本からまたいで、その先見の明のごく一角を紹介する。
金子がずっと訴えつづけていることは、日本経済が閉塞感をもっているのにその危機の正体が見えていないのはどうしてか、そのことはなぜ気がつきにくくなってしまったのかということだ。その原因は日本の経済社会にも政策にもあるが、グローバル経済が向かっている考え方や勢いそのもののなかにもある。
金子がそういう問題意識で「経済」を問いはじめたとき、日本はどういう状況にあったかというと、1997年11月に北海道拓殖銀行・山一証券・三洋証券などが連続的に経営破綻した直後だった。政府は翌年に1・8兆円の公的資金を導入したがまにあわず、中谷巌(1285夜)や竹中平蔵が主導した小渕内閣の経済戦略会議の中間報告にもとづいて、1999年に7・5兆円を注入し、日銀はゼロ金利に踏み切った。
むろんすべては焼け石に水。金融機関は粉飾決算にまみれ、日本経済が内部から腐っていることはあきらかだった。こうしてバブル崩壊の傷はとんでもなく深いものだということが知れてきた。そこで海外のエコノミストたちは、日本の金融機関がBIS規制型の自己資本率やペイオフ実施や時価会計制度を「グローバルスタンダード」として早急にとりこみ、不良債権を一掃すべきことを口を揃えて提案した。
これで日本はグローバル病院の患者になった。2002年末、小泉政権は不良債権査定をすることにしたけれど、株主価値を毀損しない程度の実質国有化の方針をとった。日銀は銀行から大量の国債を買いつづけ流動性を供給しようとしたものの、銀行は損失処理に追われるばかりで、結局、ゼロ金利による円安政策と雇用流動化政策がカップリングされて、輸出依存型の景気回復に走らざるをえなくなっていった。
金子の“反経済学”は、こういう状況の只中からアタマをもたげはじめたのである。
いまでもそうだが、財政再建か景気対策かという方針は、つねに右に左に揺れ動く(いまでも自民党は谷垣派と与謝野派で割れている)。小泉・安倍・福田・麻生時代は、景気のほうにとりくんだ。しかし、景気回復をするには体力がなければならないのに、そのときすでに日本企業は3つの変更を余儀なくされていた。
まずは、①国際会計基準(IAS)を導入していた。企業の所有資産は時価評価され、時価会計主義になってしまっていたのだ。これで、ときにはリーズナブルだったはずの過剰債務・過剰設備・過剰雇用のすべてが問題になった(IASはのちにIFRSに発展した)。
次に、②単独財務諸表から連結財務諸表の重視に慣らされていた。子会社に隠れていた不良債権がこれで次々に表面化した。これで、それまでケーレツ維持のために相互持ち合いになっていた株式は時価会計にさらされるので、「含み益」を自己資本に表面化させるには、自己資本そのものを急激に増加させるしかなくなった。
さらに、③キャッシュフロー表の提示が義務づけられて、四半期ごとに継続的なキャッシュフロー上の“改善”ばかりを、バカの一つおぼえのようにめざすようになっていた。キャッシュフローの最初の項目には「税引き後営業利益」があてられているのだが、これを引き上げるには在庫を削るか人員整理をするか、企業合併を模索するしかなくなったのだ。
そんな右往左往のもと、2007年には派遣労働者の数はまたたくまに320万人に達し、34歳以下のフリーターは200万人を前後した。この格差社会をどうするのか。問題は景気どころではなくなっていった。
こうして、真綿で首をしめつけられるようにして、日本の経済社会の全体がウォール街の市場原理主義と新自由主義の渦のなかにとりこまれるようになっていったのである。そんなところへ世界金融同時不況が直撃した。あとは、みなさんご存知のとおり。
ざっとは、こういう流れだ。いったい日本のエコノミストは何を考えるべきだったのか。
本来ならば、冷戦が終結し、バブルが崩壊した1990年代のはじめに日本はなんらかの“change”をするべきだったのである。ところが冷戦終結は自由主義体制による「市場原理の勝利」になったと勘違いした。
その後の「失われた10年」はずるずると「失われた20年」に向かって漂流することになった。これをさらに迷走させたのが、日本の場合は小泉構造改革である。ただし、そこには、日本経済がそれ以前から陥ってきた万年病があった。①輸出依存体質からの脱出をいつも失敗している、②政官財の癒着体質がなかなか変更できない、③国の予算組みと財政投融資政策と地方財政策がどうしてもちぐはぐになる、という症状だ。
これらを“清算”しようとして、たとえば小泉内閣による郵政民営化というおかしな決断がなされてしまったわけだったけれど、こういうビョーキは市場万能主義でもグローバリズムでもゼッタイに乗り切れない。乗り切れないのにもかかわらず、日本はこの時期に新自由主義のバスに慌てて駆け乗った。これではうまくいくはずがない。
金子はこのような日本の状態を「閉塞経済」とも言っている。その名もずばりの『閉塞経済』という著書もある。
閉塞経済がおこってしまったのは、経済がマネーを中心に動くようになり、マネーは「信用というしくみ」を利用して動くようになってしまったからである。金融資本主義である。あげくに時間を超えて未来の決算を取引するようになった。未来の利益を先食いし、未来のリスクを回避するような、そんな証券で経済社会がまわるようになってしまったのだ。その頂点にデリバティブ(金融派生商品)があった。
かくて、リスクを負わない逃げ足のはやい投資スタイルが大流行しまくった。本当のリスクから身勝手なリスクだけを切り離して、金融業界は逃げきろうとしたのだ。これで“信用バブル”がおこるようになった。1987年のブラックマンデー、1998年のLTCM(ロングターム・キャピタル・マネジメント社)の破綻、同じ年のロシアのデフォルト(債務不履行)危機、2000年末のITバブルの崩壊はその先駆けで、これがそのまま2007年のサブプライム・ローンの破綻に突入していった。いずれもマネーの過剰流動性が引き起こした病巣の転移であった。
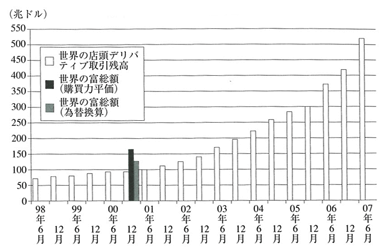
まあ、ここまでの議論は市場原理主義批判というもので、いまではジョーシキになりつつあろうから、いまさら金子の先見性を感じないかもしれないが、金子が警鐘を鳴らしていた問題には、もうひとつ見逃せない指摘があった。今夜はそちらのほうのことを強調しておきたい。
それは、グローバリズムの受容とナショナリズムの高揚とは裏腹の関係にあり、社会民主主義ともリバタリアニズムの一部ともきわどい関係にあるという指摘で、かれらの「市場原理主義批判・グローバリズム批判・新自由主義批判」をめぐる議論にはそうしたナショナリスティックな偏向や社民やリバタリアニズムの傾向がまじっていることが少なくないので、そこに注意すべきだというものだ。
このような偏向は、日本ではすでに10年以上前から連打されていた。たとえば、1998年の佐伯啓思の「シビック・ナショナリズム」論、同年の経済戦略会議(樋口廣太郎議長)の「日本リベラリズム」論、1999年の二十一世紀日本の構想懇談会(河合隼雄座長)の「富国有徳」論、2000年の西部邁の「国民の道徳」論などなどだ。
これらは表向きは市場原理主義を批判していて、それに対するに道徳や徳を持ち出しているのだが、それはサッチャーが「強い国家」や「ヴィクトリア朝の美徳に戻れ」と主張したこととあまり変わらない。つまりは市場原理主義の対抗策になどなってはいない。まさにサッチャリズムやレーガノミクスの裏返しなのである。
思想戦線においてはもっときわどい議論もまかり通っていた。『反経済学』でとりあげているのは、たとえばイマニュエル・ウォーラースティーンの世界システム論の考え方だ。
1989年にベルリンの壁が崩壊して、近未来社会についての構想力の喪失がおこった。そうしたなか、ウォーラースティーンの世界システム論ははからずも社会学・経済学・歴史学の左派知識人たちに“安全なシェルター”を提供してきた。参加者にならずに観察者でいられるというシェルターである。
多くの知識人がアングロサクソン型資本主義、ライン型資本主義、日本的資本主義、はてはイスラム経済論や儒教資本主義などの多様性を、それぞれの国民経済の形状のもとに解こうとしているとき、ウォーラースティーンは資本主義のすべてを、世界システムという“たった一回のロングタームな出来事”のなかにフロートさせたのである。それが、現在社会に対するモラトリアムを許容するパスポートになってしまったのだ。
これはまずかった。金子は早くからそのへんのことについても警鐘を鳴らしていた。
EU諸国に社会民主主義が広がったことも、グローバリズム批判めいていて、実はそうではなかった。アメリカ民主党、イタリアのオリーブの木、フランス社会党、イギリス労働党といった政権力をもつ政党の動きのことだけをさしているのではない。「社民」という思想がケインジアン政策や所得再分配政策を謳っているようで、そうはなっていないところが問題なのである。これらは、ちっともリスクテイクなどしていないのだ。
さらに金子が問題にしたのは、『閉塞経済』第3章に詳しいのだが、「正義」と「社会」と「経済」をめぐる議論の仕方だった。
今日の日本もそうであるけれど、いま、格差社会や貧困問題が世界的にクローズアップされている。このとき格差の是正と所得の再分配が俎上にのぼる。ヨーロッパ近代社会にはこの問題を救済するロジックや制度はなかった。パターナリズム(父性的温情主義)や博愛主義があるばかりで、あとは「自由」と「正義」が論じられるだけだった。
主流派経済学もホモ・エコノミクスという架空の人間行為を“自由の単位”と見るのだから、それがおこす格差や貧困を吸い上げてはこなかった。むしろサッチャリズムやレーガノミクスは「新自由主義」を標榜することで反動ともいうべき政策に走ったわけである。
むろん経済学者が何も考えなかったわけではない。たとえばピグーをはじめとした「厚生経済学」という領域もあった。効用が可測性(計算可能性)をもっていて、個人間の比較が可能になるというロジックで、そう考えれば貧者のほうが富者よりも所得単位あたりの限界効用が高いので、富者から貧者への所得再配分をすることが社会全体の厚生を高めるはずだというものだ。
これは“功利主義の社会化”という実験性をそれなりにはらんでいたのだが、実際には効用を本当に測れるのか、個人間の効用を比較できるのかという疑問に答えきれず、ここからライオネル・ロビンズらの「パレート最適」の考え方にシフトした。パレート最適とは、「これ以上に誰かを不利にすることなく、誰かを有利にすることはできない」という最適点によって社会経済を見ようというもので、ここにおいて、所得の分配論は後退して資源の有効配分論になっていったのだった。「合理的な愚か者」ばかりが経済社会にまかりとおっていると見抜いていたアマルティア・セン(1344夜)が、これらの議論を見てさっそく「パレート伝染病が流行している」と非難したのは当然だった。
こうしたなかから、一方ではシカゴ学派型の「自由」が浮上して、これがネオリベラリズム(新自由主義)になっていき、他方ではアイザィア・バーリンの『自由論』(みすず書房)やノージック(449夜)やロスバードの自由論から、さらに多様なリバタリアニズムの議論になっていったことは、いまはとりあげない(このあとしばらくの千夜千冊で集中してとりあげる)。
そこへもうひとつ、浮上してきたのが、それなら社会にとっての「正義」とはいったい何なんだという議論だった。とくにジョン・ロールズの『正義論』(紀伊国屋書店)がもてはやされたのである。金子はこの議論にもはやくに注文をつけていた。
近代ヨーロッパはいろいろな難問を今日に積み残してきた。そのひとつに、「自由と平等はトレードオフなのか、どうなのか」という問題があった。
ヨーロッパのキリスト教民主党や保守党やアメリカの共和党は、市場の自由にもとづく「機会の均等」を重視して、そこに自由と平等があると言う。ヨーロッパの社会民主党や労働党やアメリカの民主党リベラル派は、「結果の平等」を重視して、格差の是正こそが必要であると説く。
しかし、誰もが同じスタートラインに立てる「機会の均等」がやがて「結果の平等」を踏みにじる格差社会になるなんてことは、説明するまでもないほど自明な歴史的現実だった。自由と平等はトレードオフを超えられない。
そこで、ここに「正義」の規準をもちこもうということになった。その先頭に立ったのがロールズだった。ロールズは社会の原初の状態を想定し、誰もが国家や政府や自治体と社会的な契約を結べばいいと考えた。そのばあい、二つの原理が順に作動する。第1の原理は「平等な自由の原理」というもので、すべての人間が政治的自由や精神的自由といった基本的自由を平等にもてるようにするというものだ。けれどもそのような権利が保証されたからといって、その後の社会経済的な不平等や格差が生じないとはかぎらない。
そこで第2の原理として「公正な機会均等の原理」が動きだす。不平等や格差については最も不遇な状態から是正されなければならないが、そこには機会均等を破るものがあってはならないというのだ。
詳しいことは省くけれど、このようなロールズの正義論に多くの社会学者や経済学者が足をとられてしまったのである。しかし、どう見てもこのような正義論にはアメリカ的な新自由主義を乗り越えるものはないし、グローバリズムの矛盾を突く考え方があるはずはなかった。金子はそのことも長らく指摘しつづけてきたのである。
そのほか金子の指摘には、ときに勇み足や過剰な発言があるとはいえ、いろいろ興味深いものが多かった。とくにセーフティネットによる社会経済については、いくつもの政策的提案もした。
たんなる公共経済論に陥らない提案もあった。たとえば『新・反グローバリズム』の第8章で、「第三者評価」の機能をもったアソシエーションの組み立てこそが重要であるという提案をしているのは、ぼくには共感できた。社会的な交換力をもったネットワークが、評価機能を発揮したほうがいい、そこから新たな独自の資格者や規準が生まれていったほうがいいという提案で、そこにマーケット・メカニズムに頼らない多元的価値の創生を期待したいという見方だ。
今日の産業社会や企業では、自身のコンプライアンスの金縛りにあって、新たな価値の創出はきわめて遅くなる。たいていは「合理的な愚か者」になって売上げと利益と株価上昇にばかり走っていく。それよりも、これらの産業界や企業や地域社会や自由業を、大胆に横断したネットワーク・アソシエーションが出現して、新たな評価基準や価値観をめぐるスコアをつくっていけば、どうなのか。このようなアソシエーションの動きと知と編集力が一定のレベルに達すれば、そこからはおそらく新たな才能も芽生えるし、そこには次世代の市場がほしがるようなビジネスモデルも胚胎するにちがいない。金子はそういうアソシエーションの必要性を説いたのだ。
ここで唐突ながら、少々おまけの話になるのだが、実はぼくが10年ほど前に、ISIS(Interactive System of Inter Scores)というしくみのありかたを思いついたときは、そこに、公民でも私民でもない“兼業的第三者”の登場と、相互に“インタースコア”しあう小さな評価創発機能の出現とを想定したのだった。
いまではそれがイシス編集学校という相互学習型のネットワーク・アソシエーションになっているけれど、そこには金子が提案しているようなアソシエート・ヴィジョンも含まれていたのである。
いやいや、こういうことを金子がどう思うかはわからない。しかも最近の金子がどのような思想的現在に立っているのかはちゃんとフォローしていないのでよく知らないのだが、なんとなくここには交わるものがあるのではないかと感じて、ここにISISの話を入れてみた。あしからず。
というわけで、とりあえずもっと早くに評価しておきたかった日本の経済学者のありかたのひとつとして、今夜は金子勝という先見の明の一端をごくかんたんに紹介をすることで、出し遅れの証文としたかったわけである。
【参考情報】
(1)金子勝は1952年生まれ。東京大学大学院の経済学研究科で博士課程を終了したのち、法政大学教授から慶応大学教授へ。専門は財政学や地方財政論や制度経済学。著書はかなりある。『市場と制度の政治経済学』(東京大学出版会)、『反グローバリズム』『市場』(岩波書店)、『経済の倫理』(新書館)、『日本再生論』(NHKブックス)、『長期停滞』『経済大転換』『セーフティネットの政治経済学』『閉塞経済』(ちくま新書)、『粉飾国家』(講談社現代新書)など。
共著もいい。共著がいいのは実はめずらしいのである。大澤真幸と『見たくない思想的現実を見る』(岩波書店)、アンドリュー・デヴィットと『反ブッシュイズム1・2・3』『世界金融危機』『脱「世界同時不況」』(岩波ブックレット)、児玉龍彦と『逆システム学』(岩波新書)、高端正幸と『地域切り捨て』(岩波書店)など。
(2)上に書いたように新自由主義(ネオリベラリズム)についての議論や問題点についてはあらためてとりあげる。またリバタリアニズムについては、金子はかなり批判的であるようだが、いろいろ見るべきものは少なくない。いずれぼくなりにとりあげて、そのパースペクティブから紹介しておきたいと思っている。そのときロールズの正義論にもあらためて言及したい。ウォーラスティーンは、もういいだろうね。
(3)第三者によるネットワーク・アソシエーションの創成については、これから大きな課題と期待が寄せられると思う。さまざまな関連思想や関連制度、たとえば大澤真幸の「第三者の審級」や「新しい公共」論や金子郁容の「ボランタリー経済学」などとも関係してくるが、ぼくはそこにやっぱり“編集的アソシエイツ”を加えたい。そこからはきっと新しい「複業社会」や「ポリロール的才能」の出現がありうると思うのだが、さあ、どうなるか。そのうちちらちらご披露したい。