父の先見


講談社学術文庫 2009・作品社 1996
装幀:蟹江征二
赤坂憲雄の東北学はディープである。軽々しいものがない。そう言ってまずければ、ラディカルで、かつきわめて丹念だ。
ぼくが赤坂の著作を読み始めたのは、ごく初期の著作『異人論序説』(砂子屋書房1985→ちくま学芸文庫)や『排除の現象学』(洋泉社→ちくま学芸文庫)のころからだが、そのときからすでに赤坂は調査と思索と表現にまたがる独特のスタイルをもっていた。細部からしか全貌は立ち上がるまい、という頑固な方針だ。大いに共感した。
ちなみに『境界の発生』(砂子屋書房→講談社学術文庫)はぼくが『フラジャイル』(ちくま学芸文庫)を書くときに、『子守の唄の誕生』(講談社現代文庫)は『日本流』(ちくま学芸文庫)を書くときにずいぶん参考にした。
だいたい赤坂には、自分がかかわる民俗学的な調査研究の仕事をあえて「野良仕事」などと綴って“フィールドワーク”とルビを打ちたいというような、そういう感覚がある。
会って話してみるとわかるが、シャイでもある。ぼくが最初に会ったのは恐山の取材のときだった。そのときも「できれば静かに東北を見てほしい」というような眼をしていた。
本書のもとになった「忘れられた東北」と名付けられたフィールドワークとしての野良仕事は、もともとは山形を拠点として岩手・秋田の僻地にひたすらかかわっていくという2年にわたる旅にもとづいていた。歩き方はすこぶる宮本常一(239夜)っぽい。静かなのだ。
むろんたんなる旅人の眼ではない。そこには、「日本」および「日本人」をまとめて記述しようとしてきた柳田国男(1144夜)このかたの「一つの国家観」に対する反発がある。既存の民俗学の見方に対する注文がある。その注文は静かではあるが、激越だ。「忘れられた東北」の旅が始まった動機にも、そこに貫かれていた思想も、柳田の『雪国の春』に向けた徹底した批判の眼にもとづいていた。
柳田が東北をどのように見たのかというと、家の軒まで積もる東北の雪国のそこかしこに“稲作の民”のよろこびを見いだし、その経緯を昭和3年の『雪国の春』に書いた。
柳田にとっては最果ての東北にも、南方からやってきた稲作日本人が北上して培った“瑞穂の国”があったという発見だったわけだ。
しかし赤坂は「いや、ちょっと待ってほしい、それだけではヤマト王権が東北を支配した思想と同じままなのではないか」と思い続けてきたようだ。それは王化思想そのままの民俗学じゃないか。東北を“瑞穂の国”として十把一からげにしていいのかという思いだ。
日本の民俗学の事情が疎い諸君のために言っておくと、柳田の民俗学は「一国民俗学」とも「常民民俗学」とも言われてきた。わかりやすくいえば稲作社会の生活と信仰と祭祀と言葉づかいの広範な調査研究と洞察と推理であり、それを通してコメの文化に育まれた日本人の精神構造を解読してきたというものだ。柳田のいう常民とは瑞穂の国を支える稲作民のことであり、その生活なのである。
その成果は体系的ではないもののまことに夥しい成果をもたらした。ほぼ日本列島各地の実情を網羅したとおぼしかった。日本人の忘れられた生活文化は柳田民俗学によって取り戻されたとも見えた。また柳田国男という存在も巨大で、人脈も広く、柳田の学問人生はそのまま日本の民俗学の方法論ともなったのである。
とくにその出発点が明治43年刊行の『遠野物語』に始まっていたということは、それが佐々木喜善からの聞き書きにすぎなかったとはいえ、柳田こそは日本の辺境の理解者であり、東北の村落生活の底辺の発見者であるともくされることともなった。
ぼくの読書体験でいっても、26歳から27歳にかけて折口信夫(143夜)にぞっこんになり、そのあとしばらくしてから柳田をぽつぽつ読み始めたのだが、そんな折口かぶれの眼で読んでも、初めて読みすすむ柳田の分析や推理にはずいぶん頷いてしまったものだ。
しかしそのような柳田民俗学について、赤坂は『山の精神史・柳田国男の発生』(小学館ライブラリー)や『柳田国男の読み方』(ちくま新書)などで、柳田はあまりに「稲と常民と祖霊の三位一体をなす民俗学」で日本のすべてを解こうとしすぎたのではないかと述べ、その過誤をいくつもの記述の検討を通して解説してみせたのだ。
こうして赤坂の東北フィールドワークは、しだいに柳田的なものではなくなっていった。宮本常一同様に、柳田的な常民のカテゴリーに入らない生活者を訪ね歩いたのだ。とくに東北である。
だから、われわれは柳田の民俗学の射程に入らなかった東北を、赤坂憲雄から学ばなければならないのである。本書はそのような赤坂が試みた最初の東北論になっている。
赤坂が最初に東北に入ったのは、北上山地山麓の九戸(くのへ)群の木藤古(きとうご)という村だった。わずか9戸の集落だったというが、ヒエやアワをつくり、炭焼きで暮らしを立てていた。雑穀の民だ。
このような雑穀の村が東北から消えていったのは、昔のことではない。ごくごく最近のこと、1960年代の高度経済成長期のあとからのことだ。東北は原発開発計画が俎上にのぼったころから、かつての東北を失っていったのだ。もしも東北を復旧するというなら、ほんとうはそこまでさかのぼることが復旧なのだろう。
赤坂はその後も早池峰や男鹿半島や大湯や月山を訪ね、柳田的常民では東北が支えられてこなかったというエビデンスを収集していった。そこには沢内マタギ、木地屋、鉱山で働く者、サケを追う川の民など、とうてい常民とは呼べない者たちの姿があった。とりわけ赤坂の心を打ったのは「箕つくり」の民の実態だった。尾花沢近くの次年子(じねご)という村の実態だ。
江戸時代の次年子には90数戸の家があり、そのほとんどが箕つくりをしていた。1万枚ほどの箕がつくられていた。「箕の定め」という文書ものこっていて、そこには、次年子は昔から田畑が少なく飯米にも不足するので、年貢上納のたしにもなる箕つくりに徹したい。ついては他村に出た者がこの技を広げたりしないように、それを守れぬ者には箕つくりをさせないという「悲しい決め事」が記されていた。
次年子に箕つくりが伝えられたことについては、いくつかの伝承が残っている。そのひとつに、秋田からお里という女がやってきて、村を開き、箕の作り方を伝えたのだという話がある。それが大同2年(807)のことになっている。東北にとって、この大同という時代は実はきわめて象徴的であり、忘れがたい時代なのだが、そのことはこのあとふれるとして、赤坂はこの箕を手にとりながら、東北日本と西南日本が別々の歴史をもってきたことを裏付けていく。
東北の箕は「片口箕」で、西南の箕は「丸口箕」である。のみならず東北の片口箕は樹皮でつくるが、西南の箕は大半が竹製だ。のちに赤坂は『東西/南北考』(岩波新書)というユニークな一冊を上梓するのだが、そこにもイロリとカマド、両墓制、背負子(しょいこ・オイコ)と天秤棒の比較などとともに、箕のちがいをあげ、東西と南北を分ける生活文化の境界の重要性を多様に示している。
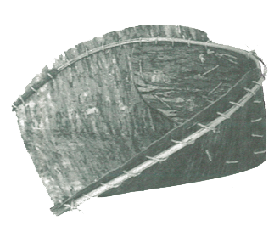
さて、こうした赤坂の眼が東北に注がれるにあたっては、東北独特の歴史的な背景も見ておかなければならない。
本書はそうした歴史をあまり追ってはいないのだが、それでも第5章「大同二年に、窟の奥で悪路王は死んだ」に扱われている話は、東北の歴史特色を憤然とあらわしている。
いったい「大同二年に、窟の奥で悪路王は死んだ」とは何のことなのか。このおどろおどろしいヘッドラインは何をあらわしているのか。お里が大同2年に次年子に来たという話とは何の関係があるのか。
まず大同であるが、これは延暦(782~805)に続く平城天皇から嵯峨天皇即位におよぶ806年から809年までの年号であるとともに、この年号には象徴的な歴史社会がこびりついていた。
7世紀から8世紀にかけて、古代ヤマト朝廷は東北の「まつろわぬ民」を制圧するために何度にもわたって、蝦夷(エミシ)に攻撃を仕掛けていた。詳しい古代東北史のことは別に千夜千冊するが、東北に「道奥国」の名が付けられたのが斉明天皇の659年で、それが天武天皇976年までに「陸奥国」になった。これが「みちのく」の発生だ。
ついで大宝律令・養老律令が制定されると、8世紀には陸奥鎮守将軍や按察使(あぜち)などが派遣されるようになった。このとき東北は律令の用語でいう「化外」「境外」「外蕃」とされた。ヤマト朝廷が辺境の東北経営に乗り出したわけである。
しかし実際の事情はきわめて複雑で、蝦夷(=東北在住者)はいっこうに治まらない。巨勢麻呂や佐伯石湯らが次々に鎮東将軍や征蝦夷将軍として派遣され、大伴旅人や家持の一族までかりだされるのだが、それでもうまくいかない。
宝亀8年(777)には蝦夷の連合軍が出羽国に押し入り、宝亀11年(780)には伊治のアザマロが反乱をおこし、東北が騒然となってきた。
「まつろわぬ民」の動向だった。折からの道鏡の乱行で国政コントロールを欠いた光仁天皇とその側近の力では、とうていそういう東北にまで手がまわらない。
そこに登場してきたのが勇猛なアテルイとその一党である。アテルイは胆沢(いざわ=現在の水沢市・胆沢郡・江刺郡)の豪族だったようで、延暦12年(793)には中央から派遣されてきた大伴弟麻呂の一軍と戦ってこれを破り、平安遷都の渦中の朝廷を大いに動揺させた。こうして桓武天皇期、坂上田村麻呂が征夷大将軍となり、延暦21年(802)に胆沢城を築き、ここでやっとアテルイの軍勢を蹴散らした。
もっともアテルイが首を刎ねられたからといって、蝦夷の反乱は収まったわけではなかった。征夷将軍となった文室綿麻呂が事態を収拾する弘仁2年(811)まで、余波は続いた。これを総称して歴史家たちは「三十八年戦争」という。古代王権と辺境東北とのあいだの、38年にわたる「東北王化の戦争」だった。
これでざっとしたことがわかっただろうが、「大同2年」とは、坂上田村麻呂がアテルイ(およびモレ)を捕まえ、さらに胆沢周辺から東北平定をめざしていた時期にあたる。
もうひとつの「悪路王」とは、のちにアテルイのことを『吾妻鏡』がそのように呼んだことから発した俗称で、正確にはアテルイ=悪路王かどうかはわからないのだが、しかし、ヤマトの中央からみれば、アテルイこそは悪路を仕切る悪路王の一味の頭目だったのである。
一ノ関近くの「達谷(たっこく)の窟(いわや)」に毘沙門堂がある。ぼくはまだ訪れたことがないが、その縁起由来には、征夷大将軍坂上田村麻呂が達谷の窟にたてこもって抵抗する悪路王らの夷族をことごとく打ち破り、田村麻呂は多聞天の加護で蝦夷平定を果たしたことをよろこんで、ここに毘沙門堂を建立したと書いてあるらしい。
この由来どおりだとすれば、もはや東北は9世紀において悪路王が破れた地で、中央政府の管理がゆきとどいた地だとみなされたのだった。
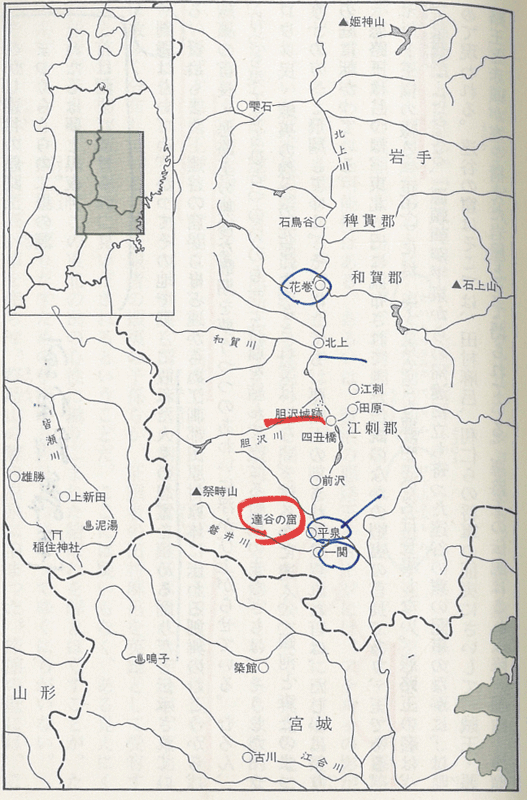
以上が「大同二年に、窟の奥で悪路王は死んだ」の意味だ。実は柳田の『雪国の春』にも「坂上田村麻呂が悪路王を征討したいわゆる大同二年頃」とあって、田村麻呂と悪路王の戦いがこのちの伝承になっていたことを心に刻んでいた。
赤坂はこの話にこそ、「闇に散った負の悪路王」と「光に包まれた正の田村麻呂」という対比が象徴されていると述べ、さらにここから「大同」という年号が“東北の負の歴史”の象徴にもなっていったのではないかと話を広げていった。
それは、またしても柳田が『遠野物語』に書いていたことでもあるのだが、遠野には大同という家名をもつ家が多く、その家々では正月の門松を片方だけ地に伏せて注連縄をわたすらしいとあったことである。
遠野の草分けの家は、きっと大同年間の田村麻呂の制圧の名残りで発祥していたのであろう。そればかりか早池峰神社や六角牛山善応寺なども大同年間の建立の言い伝えをもっていることからすると、この「大同」という響きにはまさに東北そのものの「負」が刻印されているということになる。お里が次年子に来たのが大同2年だというのも、王化された東北がこの年から始まったという“時合わせ”だったのであろう。
赤坂はこれらのことをまとめて、こんなふうに書いている。
ところで、本書にもごく一節だけが引用されているのだが、宮沢賢治(800夜)の『春と修羅』に『原体剣舞連」(はらたいけんばいれん)という詩が入っている。
「こんや異装のげん月のした 鶏(とり)の黒尾を頭巾にかざり 片刃の太刀をひらめかす 原体村の舞手(をどりこ)たちよ」で始まる詩で、勇壮であるが、どこか闇と闘っているように綴られている。原体は江刺郡田原村の原体(はらたい)という部落のことで、剣舞連はそこに伝わる剣舞のことをいう。その中ほどに「達谷の悪路王」が出てくる。
この詩は「消えてあとない天のがはら 打つも果てるもひとつのいのち」と結んでいて、大同2年の背後の闇に散った「いのち」の伝承が告げられる。
賢治がどのように東北を見ていたかということは、何か適切な本を選んでいずれ書いてみたい。いまは赤坂の野良仕事は賢治の思想や表現ともつながっていることを指摘するにとどめよう。
こうして赤坂は柳田の陰に隠れた「もうひとつの東北」を探しながら、その後は「いくつもの日本」が語れるような、そういう日本民俗学が必要だというところへ向かっていったのだ。
その赤坂がいま、3・11以降の東北復興のために設けられた「東日本大震災復興構想会議」のメンバーになっている。今日の政府や政権にかかわって、一人の研究者が何かをもたらすのは至難の業ではあるが、せめてこれを機会に多くの日本人が赤坂の「東北学」や「いくつもの日本」を感じてほしいと思うばかりだ。ぼくも、東北復興には「失われたジャパン・マザーの発動」が必要になるだろうと思っている。
(1)赤坂憲雄は1953年生まれ。1992年以来山形の東北芸術工科大学で教え、東北文化研究センターを設立して所長となり、「東北学」を創刊して、広く東北研究のリーダーをつとめた。今年から学習院大学文学部の日本語日本文学科の教授に移った。福島県立博物館の館長も務める。
(2)赤坂の著書は、上記にあげたもの以外は次の通り。『王と天皇』(ちくま学芸文庫)、『象徴天皇という物語』(ちくま学芸文庫)、『結社と王権』(講談社学術文庫)、『漂泊の精神史』(小学館ライブラリー)、『遠野/物語考』(ちくま学芸文庫)、『物語からの風』(五柳書院)、『東北学へ』1・2・3(作品社)、『山野河海まんだら』(筑摩書房)、『海の精神史』(小学館)、『一国民俗学を越えて』(五柳書院)、『岡本太郎の見た日本』(岩波書店)など。編著だが、『東北ルネサンス 日本を開くたるの七つの対話』(小学館文庫)が、今後の東北の参考になる。