父の先見


古代東北人の歴史
中公新書 1986
編集:並木光晴
装幀:白井晟一
ウサマ・ビンラディンがアメリカ軍によって爆殺された。イスラマバード郊外の隠れ家が襲われたという。まだ何も詳細が伝わっていないけれど、これでアルカイダが壊滅するとは思えない。何人・何百人・何千人のビンラディンが密かに継承されていくだろう。
それはそれ、このところのぼくは頻りに東北を思っている。陸奥を想い、日本を惟(おも)い、母国を念(おも)う。その歴史と現在をあれこれ胸中に感じている日々が続いている。どうしたら自分がそのような思念や思惟を継続できるのか、深められるのか、あるいは囚われた思考から脱することができるのか。それとも東北や日本と刺し違えることができるのか。
さまざまな気分で、ちょっとずつ何かを試みている。高橋秀元ともそのことを「北方文化」として交わし、岩手県の達増拓也知事とも復興対象だけではない「東北」を交わしている。

そんななか、この1カ月ほどのあいだ、多くの連中に“あること”を次々に訊いてみて、驚いた。がっかりもした。エミシという呼称が「東北の民々」のことであることを、大半が知らなかったのだ。「蝦夷」はエゾのことで、それは北海道アイヌのことだろうとほとんどが思いこんでいた。
そうではない。これでは「東北」はなかなか見えてこない。詳しいことはあとで説明するが、北海道アイヌが蝦夷と呼ばれたこともあるものの、蝦夷はエミシ、エミス、エビス、またエゾなどと訓まれ、多くが東北民のことをさしていた。越蝦夷(こしえみし)、出羽蝦夷(でわえみし)、東蝦夷(あずまえみし)、都加留蝦夷(つがるえみし)という言葉も古い。大宝令には「夷人雑類」の項目がある。
「えみし」という呼称や綴りも、漢字では「夷」「狄」「蝦夷」「毛人」などと宛字で綴られてきた。さらには「俘囚」「夷俘」「田夷」「山夷」などとも綴られた。
むろん、東北民が自分たちのことをこのように自称したわけではないし、この呼称を好んでもいない。ヤマト朝廷によってそのように名付けられたのだ。賤視蔑称だった。このことを象徴する意味ありげな歴史記事がある。二つ、あげておく。
ひとつは『日本書紀』景行天皇40年の7月の条で、景行天皇がヤマトタケルに向かって蝦夷について次のように説明しているくだりだ。
ずいぶんひどい批評だが、この文章自体は『史記』『礼記』『文選』などの漢籍を借りているところもあるので、実際に蝦夷をこのように形容していたかどうかは画然とはしない。
もうひとつは『日本書紀』斉明天皇5年(659)の条だ。「道奥の蝦夷(えみし)男女二人を以て、唐の天子に示(み)せ奉る」というふうにある。
道奥は「みちのおく」と訓み、このあとの天武朝で「陸奥」(みちのく)というふうに改められた。“道もない”当時の東北のことである。天子は唐の高宗のことをさす。記事は、遣唐使が蝦夷二人を同行させて、洛陽で高宗にこの二人をご覧にいれたのだと言っている。
『日本書紀』斉明天皇5年の条にはこれだけが書いてあるのだが、このときのことを、遣唐使船に乗っていた伊吉連博徳(いきのむらじはかとこ)と難波吉士男人(なにわのきしおひと)らが航海日誌につけていた。それらによると、洛陽でこんな高宗の下問があって、使者が次のように答えたということになっている。
天子 これらの蝦夷の国は何(いずれ)の方にあるぞや。
使者 国は東北(うしとら)にあり。
天子 蝦夷は幾種ぞや。
使者 類(たぐい)三種あり。遠き者を都加留(つかる)と名(なづ)け、次の者を麁蝦夷(あらえびす)と名け、近き者をば熟蝦夷(にぎえびす)と名く。今此は熟蝦夷なり。歳毎に、本国(やまとのくに)の朝(みかど)に入り貢(たてまつ)る。
天子 その国に五穀ありや。
使者 なし。肉を食ひて存活(わたら)ふ。
天子 国に屋舎(やかず)ありや。
使者 なし。深山の中にして、樹の本(もと)に止住(す)む。
天子 朕(われ)、蝦夷の身面(むくろかお)の異なるを見て、極理(きわまり)て喜び怪(あやし)む。
まさに古代蝦夷の異様な姿を言いたいほうだいに伝えている。その蝦夷は北が都加留(つがる)蝦夷で、その下が麁蝦夷(あらえびす)、もう少し下が熟蝦夷(にぎえびす)になっているという。『日本書紀』は、このうちの熟蝦夷(にぎえびす)の二人が中国まで連れていかれたというのだ。熟蝦夷はおそらくは岩手県南部か宮城県北部あたりの蝦夷であったのだろう。
古代ヤマト朝廷がどのように蝦夷の地を分国的に見ていたのかは、このような記録以外にあまり正確な記述がないのではっきりしないのだが、いずれにしても蝦夷が当時の東北民を賤視蔑称していた呼び名であったことは、はっきりしている。しかもこのような見方は古代を通じ、さらには中世・近世にまで及んだ。
なぜ、そんなふうになったのか。「東北」を思うには、ここから視座を構えておかなくてはならない。
そこで今夜は、そのような古代東北の日本列島ならびに日本人における位置と役割と意義と、日本中央が「蝦夷としての東北」をどのように扱ってきたのか、東北民はそれに対してどのような対抗を見せたのか、総じて古代東北とは日本の何であったのか、そのあたりの相貌を急いでふりえっておくことにした。いや、ビンラディンのこととつなげて何かを語りたいわけではない。
思い返してみると、ぼくが東北を意識するようになったのは高橋富雄の『辺境』(1979・教育社歴史新書)を読んだころからだった。とても凄い本だった。
この本には「もう一つの日本史」とサブタイトルがついていて、「あずま歌・みちのく歌」の意味、大化改新以前の東国観念のこと、「東の鄙・奥の鄙」の背景、そして最後に日本国家論の原点としてエミシ論がなくてはならないことが綴られていた。
ぼくはそのころ、日本が東国と西国に分かれて発達していたということを知らなかった(網野史学も知っちゃいなかった)。のみならず、蝦夷が「東国・ひな・あずま・みちのく・蝦夷・日高見・日の本」などと多様に呼ばれてきたことも知らなかった。
その後、気になって『遠野物語』やアラハバキ伝承を綴った『東日流外三群誌』(つがるそとさんぐんし)や、福士幸次郎が鉄の東北と朝鮮半島を結びつけた『原日本考』を読み耽り、また菅江真澄や吉田松陰の東北旅行記を渉猟した。
そこには宮沢賢治(900夜)や太宰治(507夜)や土方巽(976夜)や寺山修司(413夜)にひそむ謎が、所狭しとびっしり埋まっていた。
しかしエミシのことはいっこうにわからない。そのうち田中勝也のサンカ中心の『エミシ研究』(新泉社)や礫川全次が解説した菊地山哉の『蝦夷とアイヌ』(批評社)などを読んだせいで、ぼくのエミシ観はいささか右往左往させられたのだが、やがて佐々木高明の『縄文文化と日本人』(1986・小学館)や中西進(522夜)がまとめた『エミシとは何か』(1993・角川選書)あたりで、軌道が調整できた。
また、上田正昭・田辺昭三・上垣外憲一・千田稔(881夜)らがあげる縄文文化やアムール北方文化圏との関係、粛慎(みしはせ)や靺鞨(まかつ)や朝鮮半島文化との関係などを知って、やっと大局の見地からの眺望が見えてきた。
これで、ふたたび高橋富雄の『蝦夷』『古代蝦夷を考える』(吉川弘文館)などに目を通せるようになったのである。
こうしてそのあとは、今夜のテキストにした高橋崇の本書『蝦夷』や『蝦夷の末裔』(中公新書)、おそらくは最もこの領域を深く研究した工藤雅樹の『古代蝦夷の東北学』『蝦夷と東北古代史』『古代蝦夷』(吉川弘文館)などを読めるようになっていた。途中に、赤坂憲雄(1412夜)の東北学との出会いがあったことについては、前夜にしるした。
けれども、実はこれらはエミシについての“共読”ができるようになったというだけで、それ以上でもそれ以下でもない。
たとえば大伴家持がなぜ王朝政府から奥州に派遣されて失意のうちに亡くなっていったのかというような、井上ひさし(975夜)がどうして吉里吉里国の独立を執拗に描いたのかというような、そういうようなことはまだ感得していない。
それでも今夜はこれまで“共読”してきたものに、武光誠(1157夜)の『古代東北・まつろわぬ者の系譜』(毎日新聞社)、熊谷公男の『蝦夷の地と古代国家』(山川出版社)、河西英通の『東北』『続・東北』(中公新書)、さらには関裕二(1209夜)の『消えた蝦夷(えみし)たちの謎』(ポプラ社)なども参照して、以下、ざっと古代東北でのアテルイ登場までの出来事を略述することにする。
とうていうまくはまとまらないだろうが、おおむね次のようになっていたとおぼしい。どこか家持、どこか土方巽、どこかアテルイ、どこかビンラディン‥‥。
弥生時代以降の3世紀から6世紀にかけて、日本列島の北には注目すべきことが連続しておこっていた。
当時の東北地域の生活の下敷きになっていたのは、三内丸山遺跡で知られるような縄文文化であり、亀ケ岡式土器などを使っていた縄文的生活である。それが3世紀くらいにはこの地に稲作が北上し、驚くべきスピードで津軽平野まで届いた。「北の稲」の発端だ。青森県田舎館の垂柳(たれやなぎ)遺跡や弘前の砂沢遺跡の水田跡などがそれを物語る。
ところがその後、東北北部(青森・岩手・秋田)の水田跡が激減していった。なぜなのか。
一方、この時期は北海道から続縄文文化が南下した。3世紀に北海道の道央(石狩低地帯)で生まれた後北C2・D式土器が津軽海峡を渡り、ブラキストン線を越えて東北北部に降りてきたのだ。この続縄文文化は、狩猟と採集と漁労による生活、および土器・土壙墓(どこうぼ)・黒曜石石器の使用などを特色とするのだが、これらの前期遺物が能代市寒川Ⅱ遺跡、盛岡市永福寺山遺跡に、後期遺物が青森県七戸森が沢遺跡、宮城県大崎市木戸裏遺跡、横手市田久保遺跡などに見られるのである。
他方、それとともに東北には南方のヤマト文化、つまりは「倭国文化」「倭人文化」が次々に浸透していった。和習(わじゅう)というべきか。岩手県奥州市には角塚古墳などの前方後円墳もあり、宮城県北部の大崎平野あたりまでが古墳文化地域になっていった。永福寺山遺跡にも土師器や鉄器が見られる。
加えてここに北海道からオホーツク型の擦文文化が入りこんで、東北から北海道への東北的擦文の逆波及もおこり、7世紀にはこれらがすっかり混成していった。
前夜に赤坂憲雄によって批判された柳田国男(1144夜)が『雪国の春』で東北の稲作のよろこびをかみしめたことを紹介したが、以上のような動向からみてもこの柳田の観察はたしかに中途半端な観察ではあったのだが、とはいえ稲作はごく初期にいったんは東北一帯から津軽にも伝わり、それが古代蝦夷の時代になぜか途絶え、その後にふたたびヤマト政権文化の北上とともに復活していったのである。
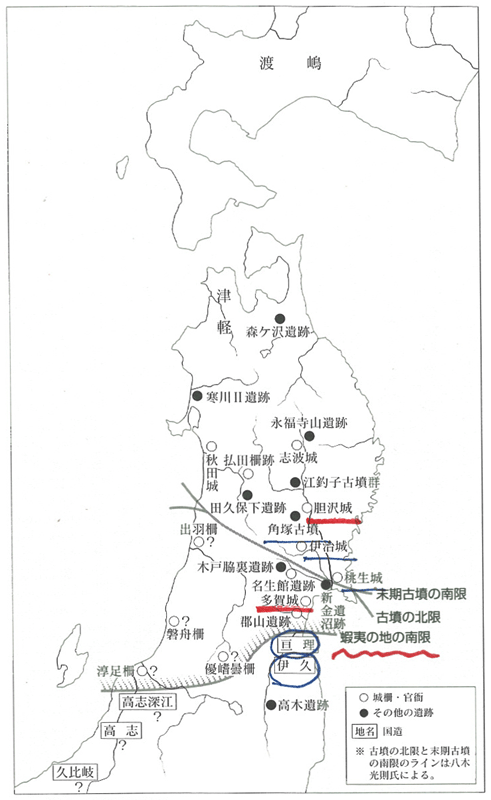
ともかくも、こうして東北各地に拠点集落ができていった。岩手県では石巻の新金沼遺跡、奥州市の中半入遺跡、宮城県は大崎の名生館遺跡、多賀城市の山王遺跡、仙台の南小泉遺跡、名取の清水遺跡などが有名だ。いずれもけっこうな数の須恵器の出土が見られる。
当然、さまざまな“道”も生まれていった。仙台平野から大崎平野をへて北上盆地に向かっては「山道」(さんどう)と呼ばれた幹線道路があったことも知られている。「道奥」は“道がなかった”わけではなく、中央ヤマトがそのようにみなしただけだった。
このような背景のなか、列島南北の生活文化や技能文化をさまざまに習合しつつ、6世紀末までに続縄文文化の痕跡が消えていくのに代わるように、ここに「蝦夷」(エミシ)が形成されていったのである。
この「蝦夷」とは、ヤマト政権が東北北部の続縄文文化を基層とする集団、新潟県北部の集団、北海道を含む北方文化圏の集団などを乱暴にまとめて「蝦夷」と一括してしまった種族概念であった。
つまりは「まつろわぬ者たち」という位置づけで総称された地域であり、そういう「負の住民たち」のことだった。だからエミシは自生したのでも形成されたのでもなく、逆形成されたわけである。
『古事記』景行天皇紀にははやくも、東方十二道に「荒夫流神、及び麻都楼波奴人」がいるなどと記されている。
荒夫流神は「あらぶる神」、麻都楼波奴人は「まつろわぬ人」と読む。初期ヤマト朝廷はそのような“まつろわぬ蝦夷たち”がたいそう気掛かりだったのだ。
それはまた、『宋書』東夷伝の有名な「倭王武の上表文」の中に、「昔より祖彌(そでい=父祖)、躬(みずから)甲冑を擂(つらぬ)き山川を跋渉し、寧処に遑(いとま)あらず、東は毛人(えみし)を征すること五十五国、西は衆夷を服すること六十六国、渡りて海北を平ぐること九十五国」と誇らしげに綴っていることに暗示されているように、王権はこうした“まつろわぬもの”を服属させているという自負のあらわれでもあった。これがだいたい478年あたりのこと、倭王武は大王ワカタケルで、雄略天皇だったろう。
つまり蝦夷は5世紀から6世紀にかけては、ヤマト朝廷の管理下に置かれるべき地域であり、服属すべき辺境民だったのである。
敏達天皇紀には、おそらくは581年前後のことと思われるのだが、数千の蝦夷が辺境を侵犯したので、天皇が蝦夷の魁師(ひとこのかみ=首長)である綾糟(あやかす)らを召して、これをいたく叱責したという記事もある。綾糟は「大毛人(おおえみし)なり」などと注記されていた。
6世紀に入って、大伴金村に擁立された継体天皇が即位すると、倭国政府は任那四県を百済に割譲して、国内の安定をはかるようになっていた。地方に国造(くにのみやつこ)、屯倉(みやけ)、部(べ)を置いて、中央の「氏」との関係を築こうとしていった。
このようになっていったのは、直接には527年に九州で筑紫の君の磐井の反乱がおこったせいだったろう。さっそく大連(おおむらじ)の物部麁鹿火(もののべのあらかい)が大将軍として派遣され、磐井を斬った。
以降、地方における国造の地方官としての力が増大し、①吉備臣・出雲臣・上毛野臣といった臣・君のカバネ(姓)をもつタイプ、②凡河内直(おおしこうちのあたい)・紀直(きのあたい)のようにアタイ(直)をもつタイプ、③日下部直・檜前(ひのくま)舎人直などの名代・子代の設定にともなうタイプが生まれた。そして、どのタイプの国造においても、その領内には必ずヤマト政権の屯倉と部が設置されたのである。
屯倉が設置されたということは、そこに朝廷の直轄領や収穫した稲の収納機構が生まれたということだ。またそこに部としての部民(べのたみ)がいたということは、部民は大王(おおきみ)家やその一族や氏族に属して生産物や労役にかかわるということだから、その地こそが「王民」が住む地域とみなされたのである。
このことを歴史記述の鍵と鍵穴をとりかえた見方からすれば、国造の任官が及ばず、そこに屯倉もなく部民もいなければ、そこは「王化されていない地域」であり、「王民のいない辺境」とみなされたということになる。
当然のこと、蝦夷(エミシ)はそうした王民のいない“化外の民”の地とみなされた。“化外(けがい)”とはなんとも恐ろしい。何かがおこれば磐井のように殺害されるか、さもなくば服属の礼をとらなければならない。敏達天皇の581年前後、数千の蝦夷が反乱して首長の魁師綾糟らが服属儀礼をさせられたというのは、こういうせいだった。
7世紀に入ると、わが列島に仏教も海外技術も流れこんできた。蘇我馬子が君臨し、聖徳太子の摂政が試みられ、遣隋使や遣唐使が派遣され、東アジアを見据えたヤマト政権の海国としての安定が追求か試みられるようになった。
とくに645年に乙巳のクーデターによって蘇我の権力が潰え、大化改新以降になると、斉明天皇の政権は一方では東アジアとのパワーポリティックスを動かしつつ、国内の支配態勢の強化に向かわなければならなくなった。
しかし海外政治は白村江の海戦で失敗し、百済との同盟関係はあえなく水泡に帰した。日本は自立せざるをえなくなっていく。
斉明女帝は阿部比羅夫に北方の守護と服属を任せ、655年には「津刈蝦夷六人」を朝廷に連れてこさせ服属の儀式をおこない、659年(斉明天皇5年)には、先に示したように唐の高宗に男女二人の熟蝦夷(にぎえびす)を見せに連れて行かせもし、ついで659年に「道奥国」を指定した。
阿部比羅夫については、もっと知られてよい。越国(こしのくに)の長官で、180艘の船団で日本海を北上し、秋田・青森から北海道をも遠征して、現地の産物には「沈黙交易」によって交渉したことがわかっている。比羅夫は秋田・淳代(ぬしろ=能代)の蝦夷を服属させ、渡島(わたりしま)蝦夷(北海道の蝦夷)を征討して粛慎(みしはせ)との和解をもたらした。
阿部比羅夫の群を抜く活躍によって、ヤマト政権は初めて東北の社会とその実態を知るようになったといってよい。
そこで政府は「道奥」(みちのおく)を「陸奥国」(みちのく・むつのくに)と改名し、さらに「出羽国」を設け、服属者には位階を授与もした。のみならず、かつての国造の管理外の地域に、むしろ移民を送りこむ方針をとるようになっていったのだ。
これを中央ではしばしば「柵戸」(きのへ)とか「編戸」といった。王化政策が積極的にとられていったわけだ。養老年間には「柵戸一千人」を陸奥鎮処に廃したという記録がある。
こうして天智時代には屯倉・部民が廃止され、国造は国司・群司となり、国と評(こおり=群)が設置されていく。しかし、そのころ「陸奥国」はわずかに仙台平野と大崎平野のあたりに特定されたにすぎず、それより北の岩手や青森はあいかわらず広大な「蝦夷」のまま、北の「大辺境」のままだったのである。
さて、8世紀、壬申の乱をへて皇位についた天武天皇以降のヤマト政権は、いよいよ「日本」の確立を意図するようになり、律令国家の道を歩みはじめる。
その突っ先の平城京が造営されている渦中の和銅2年(709)、蝦夷の一団が反乱をおこし、これを制圧するために巨勢麻呂が陸奥鎮東将軍に、佐伯石湯が征越後蝦夷将軍として北に向かうという事件がおこった。この事件は詳細がまったく不明なのだが、これをきっかけに中央政府は東北にそれなりの任官を置き、城柵を設けるようになった。
その先蹤は、神亀1年(724)に大野東人(あずまびと)が陸奥守となって多賀城(多賀柵)を築き、その功績で天平年間に按察使(あぜち)鎮守将軍になっていることだ。秋田城も大野東人の発案だとされる。神亀1年は聖武天皇の即位の年だった。
東北任官の者たちはそれなりに東北経営に乗り出した。むろん生産力と交易のためだった。天平9年(737)には多賀城から出羽柵へ通じる直通幹線の開削計画もおこったが、これは途中で中止になっている。

このような事情のもとでは、当然に東北出身や東北移民者の出世頭も登場する。一獲千金を狙う者もいる。
牡鹿群の出身の道嶋宿禰嶋足(丸子嶋足)は丸子一族を従えて陸奥においても中央においても活躍をして、奈良の都では橘奈良麻呂の乱を抑えた功績で、その名が坂上苅田麻呂と並ぶほどだった。苅田麻呂は坂上田村麻呂の父である。一族の道嶋三山は宮城県栗原に伊治城(これはりのしろ)を築いた。伊治城はこのあとの東北戦乱の火種になる。
このような動きは藤原仲麻呂(恵美押勝)の専横時代におこっている。仲麻呂が中央と陸奥・出羽を直結して統治権力を伸長しようとしたせいだったろう。そのため、いつの世にもあることだが、陸奥や出羽の任官たちが仲麻呂にとりいった。道嶋嶋足もその一人で、そのため橘諸兄の子の奈良麻呂は失脚させられた。
ところがここに大事件がおこる。中央政府の東北最前線の最大の拠点であった多賀城が、宝亀11年(780)に焼き打ちされたのだ。伊治公(これはりのきみ)アザ麻呂の決起だった。
アザ麻呂は栗原の蝦夷の族長で、中央からも信頼が厚く、部課を率いて胆沢(いさわ=岩手県奥州市)や志波(しわ=盛岡市周辺)に対する蝦夷征討に加わってもいた。胆沢と志波は当時の東北エミシの「まつろわぬ者」の二大拠点だった。アザ麻呂は当初は中央政府の意図に沿ってそこを落とそうとした。
けれども、それが寝返ったのである。伊治城では牡鹿の大領の道嶋大楯や按察使の紀広純が殺された。アメリカのアフガン解放を信じて与したビンラディンが、その後にアメリカに反旗をひるがえしたことが思われる。ちなみに伊治はイジとも読んで、武光誠は「夷中の夷」をあらわす「夷種」がもともとの意味だったのではないかと言っている。
こうして、古代東北戦争の火ぶたが切って落とされる。高橋崇はこれを、国家と蝦夷との「三十八年戦争」と呼んでいる。
ヤマトや奈良の朝廷が東北の蝦夷を支配する戦略とは、おおむね次のようなものだった。
まずは親政府的な蝦夷の集団に対して影響力を強くしていく。それでその地域が中央の直轄支配に組み入れても大きな問題がないと判断できれば、柔順な蝦夷と移民とを動員して城柵を設置し、それが完成したところへさらに移民を導入して、群を置く。この連中を「にぎ蝦夷」とも呼んだ。もしも強硬派の蝦夷がいるのなら、これを巧みに他の地域に強制移住させる。こちらは「あら蝦夷」と呼ばれた。それでも反乱するようであれば、これを武力で制圧する。この制圧された反乱分子のことを「夷俘」(いふ)とも「俘囚」(ふしゅう)ともいった。のちにエミシの異名にもなっていく。
だいたいこういう手順だった。伊治城のときも大量の移民を送りこもうとしていた。しかしアザ麻呂はおそらくは政府側のなんらかの手口の強引などが理由でこの組み立てが気にくわず、反旗をひるがえしたのだ。そこには夷俘が結集しているようだった。
光仁天皇の朝廷はただちに藤原継縄(つぐただ)を征東大使に、大伴益立と紀古佐美を副使に任命したのだが、まったく現地の事態は進捗しない。
藤原小黒麻呂が持節征東大使になった。持節は天皇の権限が代行できる役職である。けれどもそれでも混乱は収まらない。伊治城以北はすっかり反乱軍(あら蝦夷)の手中にあったのだ。ここで天皇が光仁から桓武に代わるのだが、桓武天皇は紀古佐美を陸奥守に任命し、さらに若手を登用して事態を打開しようとする。菅野真道、秋篠安人、坂上田村麻呂、藤原種継らが抜擢された。
しかし夷俘の力は侮れない。藤原小黒麻呂は「われわれが相手にしている夷俘はたいそう始末が悪い。ときに蜂のように集まり、ときに蟻のように群がる」と言って、まるでゲリラのごとき夷俘たちの活況の様相を報告している。吉侯伊佐西古(きみこのいさしこ)、諸締(もろじめ)、八十嶋(やそしま)、乙代(おとしろ)などの猛者の名前もあがっている。
延暦元年(782)、ついに大伴家持までもが駆り出され、陸奥按察使・鎮守将軍になり、2年後には持節征東将軍にもなった。これは実は藤原一族による大伴氏追い落としの計略だった。このことについては、家持の歌と生涯を千夜千冊するときに、あらためて話したい。
家持が失意のうちに東北の露と消えたのち、「三十八年戦争」の最大の主役であるアテルイと、これを征伐する坂上田村麻呂が登場する。そのあらかたは前夜の「悪路王」の伝説とともに紹介しておいた。
アテルイと征討群との戦いは3度に及んだ。延暦8年(789)の紀古左美との戦い、12年の大伴弟麻呂との戦い、16年、20年の征夷大将軍となった坂上田村麻呂との戦いである。アテルイは古左美を叩き(古左美は耄碌将軍と揶揄された)、弟麻呂とは引き分け、肝沢城を築いた田村麻呂には敗れた。いずれも肝沢や衣川が象徴的な戦場になっている。
アテルイは都に引き連れられ、首を刎ねられた。田村麻呂の名声は頂点に達した。では、これで万事が収まったかといえば、まったくそうではなかった。詳しくは次夜以降の「番外録」に続けたいので、ここではこれ以上のことをのべないが、このあと平安王朝は東北とのあいだに壮絶な歴史を展開するのである。
それにはアテルイの背後関係のこと、田村麻呂のその後のこと、そのあとの藤原緒嗣の東北経営の問題、文室綿麻呂の遠征の意味、さらには元慶の乱から東国武士の魂胆を連続的に語りあげ、安倍一族や清原一族のことに言及しなければならない。そしてそのうえで、前九年・後三年の役から奥州藤原氏の例外的台頭の意味までを問わなければならない。
これらはひとつながりなのである。東北をエミシの歴史として浮上させ、それが実は「もうひとつの日本」の根本問題にかかわることとして見えてくるには、このひとつながりを、あえて3・11後の東北の明日ともつなげていかなければならないのだろうと思われる。