父の先見


不確実性とリスクの本質
ダイヤモンド社 2008
Nassim Nicholas Taleb
The Black Swan 2009
[訳]望月衛
装幀:重原隆
著者のナシーム・ニコラス・タレブは、帯では「不確実性科学の大学教授にして、トレーダーの鬼才」というふうになっている。いささかあやしい経歴だが興味をそそる。すでに『まぐれ』(ダイヤモンド社)で大当たりをとった。
付け加えると、タレブはレバノンでギリシア正教の家に生まれ、ウォートンスクールに入った。MBAを取得後、パリ大学、ニューヨーク大学で確率論のリスク管理応用を研究、デリバティブ・トレーダー兼クォンツとしても活躍した。いまはMITに移っている。クォンツとは、不確実性を扱う数理モデルを金融データや金融商品に応用するプロ中のプロのことをいう。
それにしても、そんなトレーダーやクォンツを専門職とした大学教授が、よくもまた『まぐれ』(Fooled by Randomness)のような本を、鮮やかな構成と適度に乱暴な文脈で書けたと思う。タレブは、ウォール街のトレーダーたちがしばしばバカ勝ちしたとしても、それはほとんど「たまたま、まぐれ」のせいだと理詰めで詰ったのだ。
それが話題になった。さあ次の手をどうするのかとぼくも見ていたのだが、本書『ブラック・スワン』は前著を質量ともにはるかに上回る奔放なものになった。さらに推理が乱暴にもなった。奔放、乱暴、おおいに結構だ。そこに哀感がありさえすれば、だ。案の定、本書の献辞には「ブノワ・マンデルブロに捧ぐ」とあって、「誰も彼もがローマ人の中にあって、マンデルブロは一人ギリシア人である」と付け加えているのが、泣かせた。マンデルブロはフラクタル理論の発明的提唱者で、その理論による投資活動にもかかわった幾何学者だ。『禁断の市場』(東洋経済新報社)という共著もある。
この著者、きっととんでもなく感受性が豊かな文芸の享受者なのだろう。でも、何かのきっかけでトレーダーになったのだろう。そのぶん、理屈で現実を支配しようとする連中が大嫌いなのだろう。タレブの味方は、むろんラプラスやベルヌーイやコルモゴロフではあろうけれど、同時にポオやボルヘスでもあるようだ。
本書で「ブラック・スワン」と呼ばれるのは、人のことではない。集団でもない。金融界や証券界のことでもない。かなり異常であって、それが大きな衝撃を与えるにもかかわらず、またそのことを“あと知恵”でしか説明できないにもかかわらず、それなのにそれはあらかじめ予測していたんだとまことしやかに説明してしまうような、そんなブラック・スワンな恣意的現象のことをさす。
タレブが言いたかったことをあらかじめ一言でまとめれば、「人間には大きなランダムネスは見えないものだ、とくに大きな変動は見えないものだ」ということである。ところがあの当時、金融証券業界のポートフォリオ・マネージャーやリスク・マネージャーたちは、その見えないはずのランダムネスをあたかも訳知りに織り込んだかのような確率計算書にして、たくさんの白鳥を大きなブラック・スワンにしてしまった。トレーダーたちが金科玉条にした金融工学の半分は、実は白鳥に黒いペンキを塗ったニセ科学であったのだ。

そのことを、当時のトレーダー実務にもかかわっていたタレブが、苦みをもって自戒して、「まやかしの不確実性に惑わされるな」と言い出したのである。
それなら本書は業界告発書なのかといえば、そういうものではない。かつてジョージ・ソロスが多少はそういう転換をして新たな社会科学の“創成の試み”に向かっていったように、タレブもまた、金融界や証券界に手を出したトレーダーとして社会を操った者だけが、ひょっとして独自に思索できるかもしれない編集的世界観の一端を、なんとか紡ごうとしたものだと見てあげたい。
ベトナム戦争や文化大革命やイラン・コントラ事件に携わった者たちだけが紡ぎ出せる展望がきっとあるように、リーマン・ショックに及んだ出来事から学べる者は、その渦中にいた者であり、失敗者であり、慚愧に堪えぬ者であることが少なくない。そこには新たな展望に向けて這い出す者がきっといるはずなのだ。エコノミストではあるが、日本では中谷巌さんが、そういう一人だった。
もっとも本書の段階では、そういうせっかくの試みにとりくむニュートレーダーとしてのタレブの展望や方針は、まだまだ明確には出ていない。タレブが言いえたことは、「世界は非対称に生まれ、いままた非対称に向かっている」という、ひたすらそのことだけなのである。
とはいえ、どんな本にも、その本が用意した“下敷き”というものがある。また、その本が提示した内容から延長できる“行方”というものがある。一冊の書物に読みごたえがあるのは、この“下敷き”と“行方”の2つが相互につながっているときで、本書の場合はそうなっている。
そういう本書を読むには、さしあたって2つのことを理解しておいたほうがいい。ひとつは、「社会はリスクを分離分担しあっている」ということ、もうひとつは、「リスクについてのわれわれの直観や思考は、もともと非線形的なことにはからっきし向いていない」ということだ。
かつて人類が原始的な生活を営んでいたときは、自分の家族と仲間の体とその周辺事情を頼りにあらかたの判断をしていた。どんな予測も判断もソマティック(身体的)だった。そういうときは身体や知覚にとって、変化することや新しいことが、すなわち衝撃的なことこそが、大事なことだった。
やがて社会がルールをつくり、国家が法によって現象の過剰や過小をコントロールするようになると、大事なことと衝撃的なことが分離されるようになった。そのぶん、大事に守るべきことも別のものになり、別のところで守るようになった(たとえば貯金や不動産や保険)。こうしてリスクが分断されたのだ。あるいは分散するようになっていった。そのための技術も工夫された。
以来このかた、現代社会というもの、リスクを分散管理するシステムでつくりあげられていく。そのぶん、責任も分担されるようになった。どんな事故の原因も分けられるようにした。いまではコンビニの漬物にさえ消費期限のラベルが貼ってある。消費期限のラベルは、メーカーと販売者とユーザーを区分けして、責任とリスクを同時に分担しあうための、つまりは消費者やユーザーに責任を負わせるための無責任なラベルなのである。
一方、古代も中世も近代も現代もまったく変わっていないものがある。それはあいかわらずの「欲望」だ。物欲も性欲も、競争欲も私有欲も、権力欲も消費欲もほとんど変わってこなかった。
そこで問題は、その変わらない欲望社会に向かって、リスクを分担しないでもすむシナリオなど書けるのかということだ。また、そんな今日の社会で、「満足度」や「安心」や「安全」を証明したところで、何になるのかということだ。とっくにジョルジュ・バタイユや松本清張が暴いていたことである。
天気の予想やオッズの予想には計算が動く。たいした計算ではないのだが、そのモデルは自分と社会との関係、あるいは「自分から発するもの」と「状況がもたらすもの」との関係が前提になる。そのため、われわれは非線形的な関係で価値を感じるようになっていて、線形的なことは不得意だったはずだということになる。
もともと非線形な関係は日常生活では、いくらでもあらわれる。喜びと水を飲む関係は、苦しいくらい喉が渇けばコップ1杯の水でもおいしいし、プールに入っていたり滝に打たれていれば水なんて飲みたくなくなっていく。日常生活では、いつも質(定性)と量(定量)とは相対的で、説明がつかないような非線形的な関係になっている。
これに対して、「銀行に預けた金を10パーセントふやせば金利による収入が17パーセントふえる」といったことは、ずいぶん非日常的で、そのくせはなはだ線形的なのである。だから水を飲んで喜びに浸れるという現象と、預金と金利の関係などということは、まったく別々に感じる(知る)べきことになる。
ところが、この2つを巧みに結びつけて、幸福感と金儲けをつなげるビジネスが大手をふって世の中を賑わせることになった。それでも世の中しばらくは、銀行利子とギャンブルとはまったく別のコースウェアで用意されていて、「自分から発するギャンブル」と「状況がもたらす銀行利子」とは截然と分かたれていた。
けれども、どうか。これがしだいに混じってきたのだ。さらには、「状況がもたらすもの」としてのランダムネスがそこに加わるようになってきた。いや、そういうフリがまかり通ることになった。それを派手に喧伝したのが金融商品や金融派生商品(デリバティブ)を巧みに売りに出す連中だったのである。リスク・ヘッジなどという、とんでもない魔法を使いだし、線形を非線形の計算でまぶし、非線形な生活の中に線形をもちこんだ。そこには投資ユーザーが責任を負う金融消費期限のラベルが貼ってあった。
本書には、確率論や統計学の記述はほとんど出てこない。そのぶん巻末にシャレた用語集と注解がついていて、「ベル型カーブ」(ガウスの正規分布)だの「中心極限定理」だのを数行ずつ説明をしているのだが、これは不親切である。
もっともタレブはすでに『まぐれ』を読んだであろう読者を想定しているようで、専門用語からタレブ自身もできるだけ自在になって、好きな文脈で本書を書きたかったのだろうと思われる。というのも『まぐれ』ではすでに所得や資産のこと、ポートフォリオのリターンのこと、本の売上げといった集計量を予測したいなら、ガウス流のベル型カーブによる分布を使うのはやめなさい、それではまちがいばかりがおこるという暗示的結論を示していたからだ。
それならタレブは本書の中で最終的に何が示したかったかというと、ブノワ・マンデルブロのフラクタル分布に戻りなさいと言いたかったのである。それをタレブは「マンデルブロ的ランダムネス」と呼んでいる。
マンデルブロの幾何学は、現象が「でこぼこ」で「ぎざぎざ」で「こなごな」の世界のためにつくられた。そのため、フラクタル分布では、現象の大小や変遷にかかわりなく、そこに自己相似性があらわれることになった。これならブラック・スワンはつくれない。かんたんには隠せない。どの部分も全体の特色をコンシステントに(一貫して)投影しているからだ。それがフラクタルという特色なのである。ガウス分布と違って世界を測る比率が一定なのだ。
タレブはそこが気にいったわけである。そうだ、富がスケールに対して自立できるのかもしれないという見方が、ここにあったじゃないか、これならブラック・スワンはつくれまい、というふうに。
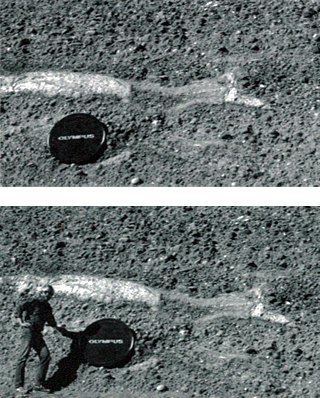
ふりかえって、これまでウォール街のアナリストがやってきたことは、バックテスト用のプログラムを使って、過去のデータベースの数字を並べ替えて目的に応じてあてはめていくというデータ・スヌーピングを作成してみせることだった。そのうえで、その計算グラフを抱えて企業に乗り込み、企業が杜撰につくってきた会計を打倒する。
こういうことにはアナリスト(とくにMBAの取得者)は徹底的に訓練されている。けれども経済社会のランダムネスを考慮するようなことは、まったく訓練されてはいないし、その価値観を保持することもできないだろうと、タレブは自戒をこめて告白している。相手企業の数字をまず1回目に増益に変えさせ、それを3度つづけて出させてみせることだけ、ただそれだけがミッションなのである。そのあとは、どうなってもかまわない。トレーダーとはそういうものなのだ。
結局、かれらが何をしているかといえば、数理モデルによってオッズを計算し、多数の企業にこれを恣意的に分配して、あたかも金融市場のリスク・ヘッジを相手にもたらしているかのような“リアルな幻想”と“説明可能な錯覚”をつくること、やっていることはこれなのだ。そこには真の金融市場のランダムネスと闘っているという姿は、まったくといっていいほどない。
こんな事情の上にトレーダーやクォンツ担当者(金融工学を駆使する者)が成り立っているのだとしたら、これはとんでもないマッド・マネー資本主義(新自由主義)が悪質に続いていたということになるのだが、幸いなのか、不運なことなのか、いまだブラック・スワンの親分の隠しどころが割れていないとはいうものの、状況はいまゆっくりと軌道修正に向かっているようだ。
いやいや、きわどい話だ。これでもしもサブプライム・ローンの破綻やリーマン・ショックがおこらなかったら、どうするつもりだったのか。
それにしても問題は、この程度の議論ではおさまらないだろうということだ。いろいろ考えなければならないことが、わんさと残っている。
とりわけ、いったいリスクとは何かということ、情報の非対称性とは何かということ、それを操ってきた確率論的統計感覚とは何かということ、そこになぜ多くの擬似科学めいたものが介入してしまったのかということなどは、いまなお本格議論には突入していない。
それまでにはまだいくらか時間があるだろうから、まずはムダを見極め、事業仕分けをしておこうというのが、民主党政権だ(これはまた、突然の“線形回帰”に突進したものだ)。
まったくもって、めんどうなことばかりが、残されてしまったものである。こんなことになったのは、そもそも一極的グローバリゼーションがおこしたことなのか、そのため世界がフラット化したことが問題なのか、それともそういう世界を見るための道具や方法がめっぽうちゃちだったのか。いまとなっては、そのことも見極める必要がある。もうすこし、“下敷き”と“行方”がつながっている問題を考えてみなければならない。
文字も思考も非線形にジャンプするセイゴオの赤
【参考情報】
(1)本書に寄せられた賛辞と批評がおもしろい。「エコノミスト」や「フィナンシャル・タイムズ」や「ビジネスウィーク」は例によって「きわめて知的で刺激的な本」「ものすごく楽しめる。説得力がある」「重要なメッセージを含んでいて味わい深い」といった無責任な賛辞だが、『ヤバイ経済学』のスティーヴン・タブナーは「無作法で、居丈高で、愉快で、頑固で興味をそそる」、「ワイアード」編集長で『ロングテール』の著者であるクリス・アンダーソンは「歴史と経済学と人間の欠陥を叩いてまわるドタバタ娯楽大作」、ハーバード大学のニール・ファーガソンは「驚くほど風変わり」と、それぞれ変化球で褒めた。
(2)タレブがレバノンのギリシア正教者であることは、最初に紹介したことだが、実は第1章の「実証的懐疑主義者への道」がタレブの生い立ちになっていて、1000年にわたるレヴァント地方の歴史とともに自身を位置づけていた。ヘレニズム文化に浸ったこと、文化も宗教もつねにモザイク状だったこと、ビザンティン宗教とイスラム宗教が混淆したこと、そして15歳で警官に挑んで監獄の日々をおくったこと、レバノン内戦という先進国の現代世界史からは無視されている体験のなかにいたこと、哲学者になりたかったが、ウィリアム・シャイラーの『ベルリン日記1934-1940』を呼んで衝撃をうけたこと、そしてウォートンスクールに入ったことなどだ。
(3)タレブはもっとチャールズ・パース(1182夜)とピエール・ブルデュー(1115夜)に共感していることを書くべきだった。本書ではそのことを数行しかふれていない。次の本がそのようになることを期待したい。