父の先見


勁草書房 1985~1989
Charles Sanders Peirce
Collected Papers of Charles Sanders Peirce 1935, Science and Philosophy 1958
[訳]米盛裕二・内田種臣・遠藤弘
これから書くことは、ぼくが長らく温めてきたきわめて重要な仮説のひとつを、チャールズ・パースに託して遊学してみるものになる。「パースの編集工学」と「アブダクションの編集工学」の遊学だ。
千夜千冊のルール上、一応は該当書籍としての『パース著作集』(1「現象学」・2「記号学」・3「形而上学」)を掲げたけれど、そしてこれはこれで恭々しいほどすばらしい編集構成になっているのだが、その収録文章のすべてにも言及されていなかったことや、「世界の名著」に入ったパースの『論文集』や岩波文庫に入っている『連続性の哲学』の文章にさえ記述されてはいないパースの推論思想を、ぼくなりにまぜまぜすることを狙っている。以下、強調点を入れたところが編集工学の説明におきなおしたところにあたる。うまくいったら、おなぐさみ。
参考にしたものはパースの著作以外にもかなりの数にのぼっているはずだが、もはやそのいちいちをおぼえてはいない。ずっと以前に、北大の計算機科学者の田中譲さんと夜っぴいて話していたとき、「やっぱりパースのアブダクションに尽きるよね」に二人のすべての議論が帰着したとき以来、ぼくのなかで「アブダクションの編集工学」がふつふつと煮え滾ってきたわけで、そのなかでさまざまな書物と出会うたびに考えてきたことが、なんとか結像してきたところを少々馬車を仕立てて取り出してみるわけなのだから、ここはご勘弁いただきたい。
文中、(3-206)のようにカッコ内で示したのはパースの文章からの引用で、パース研究者たちの慣例にしたがって、原典のパース・コレクションの巻数とパラグラフ数をさしている。
まずはおおざっぱなスケッチをざっと書いておくが、哲学の中心の問題はすべて「推論」の問題にあると喝破したのが、チャールズ・パースだった。
これは論理の問題も認識の問題も表現の問題も、換言すればすべて推論の問題になるということで、もうちょっと正確にいえば、思考のすべては「推論のプロセス」の問題になるということを言っている。デカルトが「懐疑」を哲学の中心に据えて物心を二分してこのかた、こんなに痛快な結論を放った哲学者はいなかった。パースほどデカルトに反旗をひるがえした者はいない。これがパースの出発点なのである。
世間の哲学史や思想史で、パースを哲学者とよぶことにためらいがあるのは、よくよく承知している。パースはふつうは記号学の確立者とか論理学者とか、そうでなければ「プラグマティズム」の提唱者とか数理論理学の先駆者とかとよばれてきた。いわゆる「セミオティクス」(semiotics 記号学)を最初に構想したのがパースであって、のちにウィリアム・ジェームズがプラグマティズムを哲学したのは、パースの天才的示唆によるものだった。
けれども、このあとさんざんのべるように、パースはその程度の男ではなかった。すでに五〇八夜(『シャーロック・ホームズの記号論』)に書いておいたことだが、パースは「アメリカが生んだ最も独創的で、最も多彩で、しかも二位以下に大きく水をあけた唯一無比の知性」であった。記号学や論理学だけでなく、天文学・化学・分光技術・数理経済学・測地学・地図製作・辞書編集・エジプト学・マーケットリサーチ・文献学・シェイクスピアの音声言語研究・戯曲・アガペー研究……等々、なんでもこなした。
こんな男は、まずいない。これらがひとつの文脈に入るというわけでもなかった。棘皮動物のようにそれぞれが突起した。
あとでその特異な生涯を少々紹介するけれど、これだけのことに手を出したパースは実は二十世紀の人ではない。生まれが一八三九年で、リンカーンによる南北戦争がおこったのはパースが二一歳のときだ。
二五歳のときに南北戦争が終わり、三七歳のときにやっとグラハム・ベルが電話を発明したばかりだった。かのエジソンが電球を発明したのはパース四十歳のとき、ダーウィンの『種の起源』ですら二十歳のときだ。驚くべき時代的早熟なのである。
時代的なだけでなく、個人的にもそうとうに早熟だった。父親のベンジャミン・パースがハーバード大学の数学教授だったので、八歳で化学を教えられ、十二歳のときには個人用の化学実験室をもっていた。父親の勧めだか強制だかによって、ホイートリーの『論理学の要項』(昭和堂)を読んだのはわずか十二歳である。
こうした異能を早くから開花させていたにもかかわらず、パースはどんな自分の業績にも主語をおこうとはしなかった。だいたいパースが先駆した記号論でも、パースは「記号とはそれを知ることによってもっとほかの何かを知るためのもの」という見方をしていたのだし、ジェームズのプラグマティズムについても、その進展ぐあいがおおいに不満であったため、パースはわざわざ「プラグマティシズム」という用語に変更して自分の見解をのべたほどなのだ。
そういうパースが「推論のプロセス」にすべての思考の重心を見たことは、哲学史にとっても画期的なことだった。これはどんな思考にも仲介的なプロセスがあり、どんな思考も補正的であるということを示していた。つまり、どんな思考も編集的であることを示していた。もっと強烈な言い方でいえば、パースは「直観は自立などしていない」と言ってのけたのだ。
おとなしい思想家もアヴァンギャルドな思想家も、また中立的な思想家も、人間の思考には「直観」(intuition)としかよべないものがあるだろうということには、ほとんど反論しない。説明がつかない発想のようなものがパッと思い浮かんだり、由来があきらかではない想像力がサッとアタマを横切ったりすることを、否定していない。
しかし、パースは「非仲介的な直観などありえない」と言ってのけたのである。正確には、こう言った。「先行するいかなる認識とも関係なく、また記号からの推論とも関係なく、認知についてたんに考えるだけでも、その認知が先行の認知より限定されたか、その対象を直接参照しているかを、われわれは正しく判断できる」(5-213)。
これは非仲介的な思考が直観で、仲介的な思考が認識だという区別をしていることに対する痛烈な異議申し立てである。哲学史的にいうのなら、デカルトがわれわれには生得的な直観がそなわっていて、それを基底にして他のすべての認識が展開するとみなしたり、カントがわれわれには空間や時間などの非媒介的な直観の形式があるとみなしたりしたことに対する、世界哲学史上最初で最大の強烈な異議申し立てだった。そこには、すべての推論は必ずや先行する認知になんらかの関連性をもっているという確信があった。
パースはどんな経験や思考にも「瞬間的なものがないはずだ」とみなしていた。「(いかなる経験も)瞬間的な事柄ではなく、時間を要する事象であって、ひとつの連続的なプロセスとして生じている」(5-284)。
パースはこう考えたのである。瞬間はない。瞬間は数学的なフィクションである。一方、過ぎ去った認知だって記憶や残像として瞬時に消えるわけでもない。しだいに消えていくか、消えたと思ってもどこかにひっかかったままになっていることも多い。
つまり、どんな認知も認識も、そのすべてが直観だというならまだしも、どこかだけに瞬間的に直観がはたらくわけではない。パースは、すべての認知と認識のプロセスが相互に連携的で、総じて連合的で、すこぶる関係的であることに、すなわち編集的であるということに確信をもっていたのだった。
このことをパースは思考における「シネキズム」(synechism 連続主義)とよんだ。これは思考の連続性を重視したパースの哲学の底層にある考え方で、その一部は『連続性の哲学』に語られている。パースはこのシネキズムの核心に、大半の認知や認識には(むろん表現にも)時間がかかっているという大前提をおいた。どんな認知活動も時間をともなうプロセスから派生するという見解を貫いたのである。そして時間がかかっているぶん、そのプロセスには必ずや推論がおこっているとみなした。
これで見当がついたかと思うけれど、パースの関心は一から十まで、「推論」(inference)の正体を見極めることにあった。パースは自意識や心というものさえ、複雑な推論プロセスと捉えるしかないだろうとみなした最初の哲学者だったのだ。
パースは推論という基本作用を大きく三つに分けた。「演繹」「帰納」「仮説形成」である。三つに分けたのだが、パースはこのうちの「演繹」(deduction)を人間理性の発展から見て後発的なものだとみなすことで、推論にはむしろ「帰納」(induction)や、それに先立つ「仮説形成」のほうがずっと本質的な作用をもたらしていると考えた。この仮説形成のことをパースの用語で「アブダクション」(abduction)という。
パースによれば、三つの推論方法は別々にはたらいているのではない。別々のときもあるが、本来は総合的にはたらいている。わかりやすくいえば、われわれが何かを発想したり仮説したりしようとするとき、つまりは思考を開始するとき、まず先行的にアブダクションをしているのだろうとみなした。しかるのちにその第一次的なアブダクションによるおおざっぱな仮説が、それと関連するであろう観察事実とどのくらい近似しているかを帰納させ、そこに必然的な帰結がありそうならば演繹的分析をおこなっていくと見た。
しかしパースは、そのような帰納も演繹も実はアブダクション(第二次アブダクションや第三次アブダクション)にもとづいているのではないかと考えた。つまりはすべてはアブダクションに始まり、アブダクションに包まれていると見た。
アブダクションという用語そのものについては、あまり詳しいことを解説していない。言っていることもときどき曖昧になる。
もともとはアリストテレスが分析論に用いた“Apagoge”の英訳語が転じて、デダクション(演繹)やインダクション(帰納)にあわせて造語したもので、日本ではこれを「仮説形成」とか「仮説的推論」と訳してきた。
パースはのちにアブダクションよりもひょっとしたら「レトロダクション」(retroduction)という用語のほうがよかったかもしれないとも言っていて、その用語の厳密性にはこだわっていない。ぼくはのちにものべるように、アブダクションは推感編集というふうに見たらいいのではないかと思っている。
またアブダクションには「拉致する」「誘拐する」という意味もある。ぼくはこのことがアブダクションの作用を暗示していておもしろいと思っているけれど、研究者たちは少々困っているようだ。まあ、用語の由来や定義はともかくも、パースがすべての思考の初源と帰結にアブダクションの起動と作動をおいたことに注目した。
「演繹」「帰納」「アブダクション」はいずれも推論の方法である。推論(inference)は、与えられたものから与えられていないものに向かって進んでいく思考のプロセスのことをいう。たんなる〝おしゃべり〟ではないし、たんなる〝ものおもい〟でもない。多くの推論は先見的で予見的な思考に向かう。
しかし、ただやみくもに結論に向かうわけではないし、ゴールに向かってパパッと魔術的に飛び移ろうというのでもない。与えられたものから与えられていないものへ進む道筋について言及する。観察する。言葉にしていく。したがって、このような推論のプロセスでの思考は、先行した思考が後続する思考によって解釈されていく。その解釈のプロセスが推論なのである。
このときわれわれは、さまざまな手立て、たいていは「思考記号」(thought sign)を使っている。その思考記号によってさまざまな関係づけや連合をおこしながら、推論はそれらを適宜消化しながら進んでいく。そのプロセスはあくまで関係的なのだ(それゆえパースの論理学はしばしば「関係の論理学」とよばれている)。
パースは推論には、感覚や知覚が必ずや「注意」(attention)によって編成され、再編成されていくことを重視した。編集工学ふうにいえば、推論では注意のカーソルがたどるダイナミックな編集プロセスを観察するという作業がおこっているということだ。だから注意の能力がパースの推論の基礎になる。パース自身が、ずばりこう書いている。「こうしてわれわれは、注意がたしかに後続する思考に大きな影響をおよぼすことを知る」(5-295)。
かくてパースは、推論の中身は注意のカーソルの動向が示す多焦点によって姿をあらわしてきた「解釈思想」(interpretant)だろうというふうに捉えた。そのプロセスの途中のすべてにおいて、思考記号もさまざまな多焦点をもって動いていると捉えた。安易な直観的思考によって推論が成立するなどということは、パースにとってはありえなかったのである。
推論のプロセスをおおざっぱに想定したとき、そのなかで思考が論証的に進む方法のほうに加担していったばあい、これを演繹的であるという。
演繹は解明的であり、分析的であり、ときに図式的である。演繹は与えられている情報が次に進むたびに、次々に論証されていく。いわば必然が取り締まられていく。そこではオッカムの剃刀が光っている。前提と帰結のあいだに正しい論理関係があるだろう、つくれるだろうと思って進める推論が演繹法である。しかし演繹は論証的であることをめざしはしても、その論証が正しいかどうかを検証する力はもってはいない。よく知られているように、三段論法は最も有名な演繹的推論であるが、前提が誤っていたりすることも多く、演繹的であるから正しい帰結が得られるとはかぎらない。また、そこから新たな情報がもたらされるということも確定されない。
これに対して、帰納は個々の事実や経験から出発して、それらを集めながら、しだいに拡張的に進む推論である。「個別から一般へ」、これが帰納というものだ。演繹が論証的であるのなら、帰納は検証的なのだ。アリストテレスやキケロは「枚挙法」というふうに考えた。さまざまな似た事例を枚挙していくことが帰納なのである。したがって枚挙が少なすぎるときは、その結論に信頼性が乏しいともみなされてきた。
パースはこの帰納法に強い関心を示した。そして帰納的検証は「似ているものをさがす」という方法をとるのだとみなした。帰納エンジンに類似性や近似性が入っている。それが新たな帰結を生み出していく。いや、新たな仮説の可能性を生み出していく。そう、みなしたのだ。
実際にも、科学的な帰納法ではたいてい分類や法則が生み落とされるのだが、パースはそこに仮説の創成の糸口を見たわけである。ここはパースがすこぶる好意的に帰納を見ているところで、その見方にこそパースがアブダクション(仮説形成)を最も重視した特徴があらわれていく。
ざっと以上のような考え方によって、パースのアブダクションは、帰納法をとりこんだ仮説形成型の推論の総体を示していった。与えられているものから与えられていないものに思考が進むのが推論であるのだが、アブダクションはそのプロセスを順逆両方に動きまわり、「本来はこのように与えられていた仮説があったのではないか」という方向を仮想的に樹立してしまうのだ。そのためパースは、アブダクションにはレトロダクション(遡及的推論)の特徴が濃くあらわれるというふうに見た。
たんなる推論の理論ではあるまい。むしろ「発見のための推論」というべきだろう。実際にもパースはアブダクションこそが「発見の論理」ではないかと考えた。ぼくがもっとはっきりさせるなら、アブダクションは仮説の創発なのである。パースも、こう書いた。「アブダクションは説明的な仮説を形成するプロセスである。それは新しい観念を導く唯一の論理的操作である」(5-171)というふうに。
かくしてパースは後期においてはアブダクションを「総合的推論」というふうにもみなす。新しい認識はアブダクションによってこそもたらされるという可能性を示したのである。それならアブダクションとは総合的な推感編集なのだ。そしてそうだとすれば、演繹や帰納はそのアブダクションの出来映えをテストする役目をはたしている助さんと格さんということなのだ。
一般にわれわれは外界の何かの刺激に応じて何かを感じ、何かを発想する。そこには感情とか心理が作用していると信じられている。そこには記号など介在しないだろうともみなされている。もっと直覚的なのではないかと思われている。
パースは、そんなことはまったくないと考えた。感情(feeling)ですらアブダクションの作用のなかに入っていると考えた。そしてそうであるのなら、感情も記号的なものを活用していると考えた。アブダクションにもとづく記号的思考なら、感情や感覚や知覚の充実をももたらすと考えたのだ。
この点については、ヘレン・ケラーの有名なエピソードを思い出せばいいだろう。事物の名前と文字の綴りとイメージと意味とを結びつけられなかったヘレン・ケラーは、家庭教師があるときヘレンの手を水につけ、その手のひらに“WATER”という綴りを筆圧させたとたんに、それらの関係性のいっさいを了解したものだった。ヘレンは狂喜してそこらじゅうを跳びまわり、そこにある物体を次々叩いて、家庭教師がその物体の名前の綴りを手に示すまで叩くのをやめなかった。
われわれの知覚と推論はいつだってヘレン・ケラーの断片の再現なのである。新しい世界や未知の現象や知らない言葉に出会うたび、われわれは小さなヘレン・ケラーを通過させているはずなのだ。
このことは、パースのアブダクション理論には、知識というものの本来の謎を解こうとする計画があったということを示唆している。パースは知識がどのように連環的な総体に向かっていくのかということを研究したかった哲学者なのである。パースはいつからか、ヘレン・ケラーのようにひとつずつの記号と知識がアブダクティブに統合されていくならば、どんな断片的知識もやがてそれらが連合して確固たる世界観を形成するはずだという計画を思いついていたのだ。これは編集的世界観はどのように形成されうるかというプログラムの確立にあたっている。
パース学の基本はセミオーシス(semiosis 記号過程)にある。すべての認識や認知の推論のプロセスに記号的なるものがかかわっている。「われわれは記号を使わずに思考することはできない」(5-265)、「すべての思想は記号である」(5-314)、「最高度の実在は記号によってのみ到達される」(8-327)といったパースの言明を見れば、その主張しようとしているところの意図は十分に伝わるだろう。
しかしここであらかじめ理解しておくべきなのは、この記号とは、ソシュールの言語学や記号論(セミオロジー)にいう記号とは異なっているということだ(記号学や言語学の研究者たちは、ソシュールの思想を記号論=セミオロジーとよび、パースのほうを記号学=セミオティクスとよぶ)。
ソシュール記号論(ソシュール言語学)についてはここではごく単純に説明するしかないが、その基本は二項間の対応がパラダイムになっているということにある。たとえばラングとパロール、コードとメッセージ、意味するもの(シニフィアン)と意味されるもの(シニフィエ)、送り出すものと受け取られるもの……。ソシュールはこれらのそれぞれ二項のあいだにさまざまな対応の行き違いやそれぞれの自立性があることから、その言語学や記号論の枝葉を広げていった。また言語や記号の本質に降りていった。一言でいえば、ソシュール記号論は「差異を生むコードとメッセージの記号論」なのである。
ところがパースの記号学は、そうではない。ぼくが大胆に定義するのなら「類似を生む解釈と仲介の記号学」なのだ。記号はコードそのものではなく(コードも含むが)、解釈内容も仮説候補そのものも、記号になりうるようになっている。いわばモードもテクストも、プロセスも仮説も記号なのである。いや物理的な指示作用だけでなく、図表的なものや図像的なものまでも記号と認めた。
すなわちパースは記号を一種類の作用にはしなかったのだ。では、どのようにしたかというと、まずは記号を「類似記号」、「指標記号」、「象徴記号」に分けた。類似記号がイコン、指標記号がインデックス、象徴記号がシンボルである。

パースが記号をその作用の特異性によって、①「イコン」(類似記号)、②「インデックス」(指標記号)、③「シンボル」(象徴記号)に分けたことについては、ソシュール記号論にどっぷり浸かっている者でなければ、それほど説明を要さないのではないかと思うが、念のため、かんたんに解説しておこう。
①「イコン」(iconic sign 類似記号)は、記号の性質がその対象の性質と類似しているものをいう。「これは富士山の絵だ」「これが新築のビルの青写真だ」「これは東京の地下鉄の路線図だ」「あのギャーギャーという声はうちの猫の鳴き声だろう」というときの、「絵」「青写真」「路線図」「ギャーギャーという鳴き声」がイコンにあたる。パースは「事物としてそれが有している性質が記号となるのにふさわしい。何ものでもそれと似ているあらゆるものの代用物になる」(2-276)、「その記号自体の性格によってその指示対象に言及する記号」(2-247)と説明している。この代用物というところがミソだ。
したがってイコンには、メタファーや見立てや見本も入る。メタファーや見立てを成立させる作用をもつものもイコンなのである。そこでパースは、イコンをさらに三つに小分類して、類似記号には「イメージ」(images)、「図式」(diagrams)、「隠喩」(metaphors)があることを指摘した。
②「インデックス」(indexical sign 指標記号)は、その指示対象と特別な類似関係をもっていないにもかかわらず、その対象と物理的な対応関係をもつ記号のことをいう。たとえば、寒暖計は気温の高さを示すインデックスであり、ある化石はある地質年代のインデックスなのである。パースは「その対象によって実際に影響され、そのことによってその対象の記号として機能するもの」(2-248)と説明した。
風見鶏は風そのものとなんら類似関係をもたないけれど、いったん風向きをあらわすものとして認知されたとたん、風向きの代用記号として機能しつづけるインデックスになるわけだ。ドアをノックする音も来客という対象性をなんら示していないけれど、それが来客のインデックスになりうるわけなのである。
こうした見方からすると、編集工学的にはうまく参照系(reference)や見本帳(repertory)を作成しておくことが、推論にとってはきわめて有効であることが見えてくる。また、たとえそのようなレファランスやレパートリーの準備がなくとも、アブダクションにおいては自動的にレファランスやレパートリーが形成されつつあると見るべきなのである。また、これはぼくが感心したことであるのだが、パースは「そこ」「ここ」「あそこ」「いま」といった前置詞句や方向代名詞などもインデックスになっていることを示唆していた。
③「シンボル」(symbolic sign 象徴記号)は、観念や習慣が結びつきを作りだした記号性である。それ自身が類であって個物ではない記号性である。ピラミッドはクフ王らの、鏡餅は正月の、鯉のぼりは五月の節句の、シャネルのマークはココ・シャネルの、それぞれシンボルである。パースは、「それを使用する者の観念を媒介にしてその対象と結びつけられていて、この連結はその媒介者なしには存在しえない」(2-299)と説明した。まさに解釈内容が記号化したものだ。
アブダクションがこれらの三つの記号性をもって駆動しているという光景を描いたパースは、次に、これらの作用がどのような場面で活動しているかという観察にとりかかった。とくにめずらしい観察分類ではないけれど、ところどころに編集工学的に光るものがある。
イコン、インデックス、シンボルがどのような場面で活動しているかというと、「名辞」(rheme/term)、「命題」(dicisign/proposition)、「論証」(delome/argument)において活動する。これをパースは推論の場面における第一次性、第二次性、第三次性というふうにとらえた。
「名辞」が記号的言明の第一次的であるだろうということは、どんな記号論者も疑わない。けれどもだからといって、名辞によって何かが確定することはめったにない。「名辞はその対象をそのままにし、ましてその解釈内容をいっそう不安定のままに残す記号」(2-95)なのである。そのような記号をあえて名辞記号ということもある。
「命題」は推論における問題様式を整えたところにやってくる。しかしこれまた、やってくるだけであって、その言明を完了するわけではない。それは未発展の推論の状態なのだ。すなわち「命題はその主語とよばれる指示対象を明確に指定するが、その解釈内容はそのままにしておく記号」なのである。
そこでパースは、この中途半端な命題状態を二つの方向に分けた。ひとつは経験的な知識を広げていこうとする「拡張命題」(ampliative proposition)、〝AはAである〟ことを決定づけたくて進む「解明命題」(explicative proposition)だ。この区分けはとくに新しくはないのだが、ぼくはこの「解明命題」にパースが「写し」を含ませたことに驚いた。「~は~である」には「写し」(replica)の推論が含まれていると喝破したのだ。これはぼくが九三〇夜の『インダクション』で注目した「準同型」(homomorphism)や「擬同型」(quasi-homomorphism)の見方を先見しているようで、はなはだ興味深かった。
「論証」は記号的思考の第三次性をあらわす場面である。パースはこの段階でやっとアブダクションがその真の姿をあらわすと考えた。こう、説明している。「論証は、その解釈内容にとってある法則の記号であるような記号である」(2-252)、「論証の解釈内容は、その論証を諸論証の一般的クラスの一例として表意するが、そのクラスは全体としてつねに真理に到達しうる可能性をもっている」(2-253)、「論証は解釈内容の対象を未来指示的に記号に表意する」(2-263)。
このような視点に立って論証の推論的様式を整理すると、パースの言うアブダクションをともなう論証が、おおむね次の五段階になっていることを窺うことができる。(イ)前提(premisses)、(ロ)指導性(leading priciple)、(ハ)言辞合成(colligation)、(ニ)関係包含(involvement)、(ホ)結論(conclusion)、だ。
なかで仮説的言辞を見くらべて「合成」するところ、前提と結論の相互作用に推論が動いているところが、きわめてアブダクションの特徴を発揮する。
パース記号学の要約はこの程度で十分だろう。イコン、インデックス、シンボルが、前提・指導性・言辞合成・関係包含・結論に向かって順逆いずれにも動きながら、名辞や命題を、演繹や帰納をゆさぶっている。それが仮説形成プロセスとしてのアブダクションなのである。
これらの一連の脈絡をまとめているパースの説明はないのだが、たとえば次のようなところにだいたいの意図があらわれている。
「アブダクションは驚くべき事実を説明するためにある理論が必要であることを感ずるところから誘発されるが、しかし最初は特定理論を考えずに、その驚くべき事実から出発する。帰納は、その理論を支持するための事実の必要性を感ずるが、しかし最初は特定の事実を考えずに自己の心理をひとりで主張しているように思えるある仮説から出発する。アブダクションは理論を求める。帰納は事実を追求する。アブダクションでは事実を見当することによって仮説が提案される。帰納ではその仮説の検討からまさにその仮説が指し示してきた事実そのものをあきらかにするような実験が提案される」(7-218)。
パースが示したかったことは明白だ。すべての記号的思考こそが知的活動の総体であり、そのプロセスを観察できさえすれば、デカルトのような「疑念」や「自我」を持ち出さずとも、どんな合理的な推論も可能になるということなのだ。もっと端的に結論づけてもいい。パースにとっては意識とは推論そのものなのであると。

それにしてもパースがどうしてこんなだいそれた計画をたった一人で完遂しようとしたかということは、いまもって十分には検討されていない。
ソシュール記号論が繁栄したこと、ウィリアム・ジェームズのプラグマティズムと同一視されたこと、チャールズ・ウィリアム・モリスらのパース以降の記号学が別途に発展したことといった要因があれこれ考えられるのだが、その大きな原因はパース自身がもっていたといわざるをえない。しかしそれを批評するには、パースはあまりにも時代に先んじていた。そうしたパースの日々に戻って、今夜の感想をまとめたい。
さきほどちょっとふれたように、チャールズ・サンダース・パースはアメリカが植民地から脱却している時代に生まれ育っている。パースの同時代人物は、エマーソンやポオやホーソンやホイットマンやメルヴィルである。これらがすべて文学者であることで察知できるように、この時期はアメリカにはまだ本格的な科学がほとんど芽生えていなかった。
そうした時代でパースがどのように才能をひらめかせ、その大半の業績の着手に周囲が理解を示せなかったか、想像するにあまりある。ぼくは有馬道子さんが訳したジョゼフ・ブレントの大著『パースの生涯』(新書館)やバーンシュタインが編集した他方面からのパース論が収録された『パースの世界』(木鐸社)を読んで、あまりにパースが例外者、いや異例者であったことに、ほとんど胸が痛くなるほどだった。発想において異例、生活において異例、人づきあいにおいて異例、生活状態において異例だった。とくに四十代からはめちゃくちゃな経済状態だった。
一言でいって、パースの生涯は不運だったのだ。ケンブリッジ(ボストン)の名門に生まれた。幼少年期に化学や美学にふれた。数学教授の父に徹底した英才教育をほどこされた。ハーバード大学では古代哲学にもアガシの進化論にも通暁した。アリストテレスとドゥンス・スコトゥスとシェイクスピアを研究し、文明にも言語にも論理にも人類の展望をもった。これだけでもパースが比類のない才能の持ち主であったことは誰にも見当がつく。
しかもデカルトとカントとヘーゲルを読み耽って、その限界に気がついたというのだから、ほとんど一人で全哲学史を止揚しようとしているわけなのだ。だからきっと、これらの背景をもって「関係の論理学」を樹立し、独自に記号学という新しい分野を切り拓いたことは、パースの計画からすればほんの一部分の成果であったのだ。ましてプラグマティズムを提唱したことなどは、パースにとっては一瞬の閃光のようなものだったろう。
後世、なぜパースの全領域の思索は理解されなかったのだろうか。なぜパースは編集的世界観の壮観を提供したと理解されてこなかったのだろうか。たとえパースが周囲からの安易な解釈や理解を拒否したとしても、パース没後(一九一四年の死)からすでに一〇〇年近くがたっている。どんな思想家だってこのくらい時代がすぎれば理解されるはずである。まして記号学や論理学の分野では、かなり多くのパース研究が発表されたのだ。
けれども、パースはいまだほとんど理解されていないといっていい。たとえば『連続性の哲学』には、パースによるリスティンク数研究の一端がふれられている。これはのちのトポロジーの予告にあたるもので、そのことについてはパースの功績が一部認められているのだが、それだけではなく、そこには「弦」(フィラメント)と「帯」(フィルム)という物質現象についての究極像の言及がある。これなどいまならスーパーストリング理論の一部になってもおかしくないものなのである。
『連続性の哲学』には「類似による連合」についての天才的な記述がいくつか含まれている。類似性とは観念の連合がつくるものだという洞察だ。パースはそこから「価値」とは類似性を発見すること以外のなにものでもないのではないかということを暗示した。これは「問題の急所」はつねにアナロジーこそが占めているという、とんでもない指摘なのである。しかし、こうしたパースの言及は、「パース学」の全貌ではめったにとりあげられてこなかったのだ。
すでに書いておいたように、こうした事情を招いたことについては、パースに多くの原因があることは、否めない。
今夜、パースを書いてみて、あらためていくつかの感想をもった。パースはあれほど仮説的論理の解明に長けていたにもかかわらず、まるでヴィトゲンシュタインのようにわかりにくいのだ。その構想はホワイトヘッドに匹敵するところがあるとおぼしいのだけれど、まとめてロジックを公表しているところが、驚くほど少ないのだ。つまり断片的であり、示唆的なのだ。分裂的で、連想的すぎるのだ。
それゆえパースを敷延するには、パースに入ってパースに出ていくしかなく、そこでパースからの逸脱をせざるをえない。パースの文章に依拠するのではなく、そこから新たな組み立てに向かう。けれども、そのためこれでパース学がふつつかなものになる場合も多い。これでは、まるでパースが自分の思想の継承をできるだけしにくくさせているかのようなのだ。
三十代になったパースが絶頂期に達したころ、パースは「形而上学クラブ」というものをつくった。チョンシー・ライト、ウィリアム・ジェームズ、ジョン・グリーン、フランシス・アボットらが参加した。その談義はのちの「ウィーン学団」に継承されたといっていい(「ウィーン学団」の前後の事情については一〇五八夜のゲーデルの項目を参照してほしい)。
パースは「形而上学クラブ」において溢れるような示唆と暗示をもたらした。しかしそれにもかかわらず、自身では重力に関心を寄せていた時期であったせいもあって、自分が一番言いたいことが誰にも伝わらないと感じていた。パースの重力研究は振り子の研究に発して地磁気の測定におよび、重力の本来をヴィジョンすることに発して、光の本質(光速度測定の研究をしていた)の確定に至ろうとしていた。しかし、こうしたアイディアや仮説を語りあい、発表してみると、誰もその重要性に気がつかない。
しだいにパースは世間と没交渉になることが自分の研究や思索の重要なスタイルなのだというふうに思いはじめた。四十代、パースはジーナという妻と別れ、父を失い、ジュリエットと再婚し、コカインを服用しはじめた。その間、アメリカ社会はパースをどんな正業にも(とりわけ大学教授に)就かせなかった。こうしてパースの生活はまたたくまに行き詰まっていった。
それでもパースの独創は衰えてはいない。ただしパースが原稿を書けるのは、ポール・ケーラスが編集していた雑誌「モニスト」だけになっていた。けれどもパースの原稿に注目する者はいなかった。このころのパースはとっくに記号学や論理学の先駆的研究をおえていたので、もっぱら「理論とは何か」「必然性とは何か」「連続性とは何か」「愛とは何か」「精神とは何か」という問題にとりくんでいたのだが、それがかつてのパースのプラグマティックな思考の先駆性のどこに関係するのか、周囲はまったく理解できなくなっていたのだ。
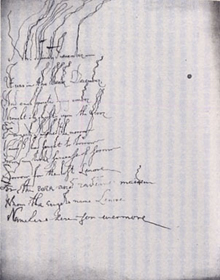
こうして五五歳のころ、パースは餓死寸前に追いこまれた。栄養失調から重病にかかったまま、治療もままならない。このような危機をジェームズらは何とか救おうとしたものの、そしてハーバード大学における論理学の特別講義などをあてがったものの、パースの窮状と健康は回復せず、一九一四年の第一次世界大戦開幕前夜、七五歳でまるで横死するかのごとくに没した。
最後の最後まで文章だけは書いていた。出版のあてもない校正もしつづけた。「神の実在に関する怠惰な論証」という遺稿に近いものも残っている。
ぼくがパースをどのように見ているかは、以上の書きっぷりでほぼ見当がつくだろう。いや、ちゃんと書いたというつもりはない。ぼくもパースの全貌を伝えきれなくて困っているといったほうがいい。
しかしながら、パースから継承すべきものが何であるかは、まことにはっきりしている。アブダクションの哲学の総体を継承すべきなのだ。類似性の編集工学をパースから受け取るべきなのだ。そして、パースの用語にとらわれることなく、パースを現在的に読みなおすべきなのだ。こんな文章がある。
「感情(フィーリング)、他者についての感覚、そしてこれらに媒介すること。この三つのほかに意識の形式はない」(7-551)。いったいこのメッセージに何を加える必要があるだろう。これで十分なのだ。「知覚者によって知覚されていないことがある。それは知覚者が何を知覚しているかということである」(5-115)。
まさに、この通りだ。この問題以外に、脳科学者や認知科学が考えることがあるのだろうか。「思惟と論理は不可分の関係にある。なぜなら人間の思惟は類似を通して前に進んでいるからだ」(5-108)。
そうなのだ、われわれはアナロジカル・シンキングをしている動物であって、どんなときもつねにメタファーをさがしている存在者なのである。
チャールズ・サンダース・パース。あなた自身が壮大なアルス・コンビナトリアそのものだったんですね。連想は一度として欠かせてはならなかったのです。ぼくはそう確信して編集工学を始めたのでした。そして『知の編集術』(講談社現代新書)に「編集は連想と不足に始まる」と書いたのです。ところで、あなたは左利きでした。それって、世界を表象するのに何かの暗示だったのでしょうか。
