父の先見


もうひとつの世界システム
岩波書店 2001
Janet L. Abu-Lughod
Before European Hegemony 1989
[訳]佐藤次高・斯波義信・高山博・三浦徹
編集:杉田守康
装幀:中島かほる
この数週間で、チュニジアのジャスミン革命を筆頭に、エジプト、リビア、イェーメン、バーレーンなどのアラブ中東イスラーム社会が、次々に火を噴きはじめた。執拗で強引で小心だった大統領フスニー・ムバラクも、わずか数週間の民衆暴動の波及によって、退陣を余儀なくされた。
チュニジア革命がフェイスブックのせいだなどと言っているのは日本のジャーナリズムと電子オタクだけで、そこには二一世紀に入ってますます怪獣リヴァイアサン化しつつあるグローバリズムのなかで、アラブ・イスラーム社会に沈殿してきた世界史的なマグマがゆっくり噴き出ていたわけである。
このマグマは厄介だ。かなり深いところから胎動している。それなのに、オイルマネーやイスラーム原理主義や9・11以降のイスラーム・テロばかりに目を奪われて、われわれは「中東」や「マグリブ」(北アフリカ)の現代史がどんな世界史のマグマを孕んできたのかを、すっかり忘れていた。
いまさら言うのもなんだけれど、チュニジア、リビア、エジプト、イェーメン、バーレーンは人口の過半数がムスリムである。加えて東アフリカと北アフリカと西アフリカの、モロッコ、モーリタニア、セネガル、ガンビア、ギニア、アルジェリア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、チャド、スーダン、ソマリア、ジブチも、イスラーム諸国だ。
これに地中海と紅海を挟んで、サウジアラビア、シリア、ヨルダン、レバノン、クウェート、オマーン、カタール、UAE(アブダビやドバイ)、トルコ、イラク、イラン、アゼルバイジャン、アフガニスタン、パキスタン、バングラディッシュ、ブルネイ、マレーシア、インドネシアというふうに、イスラーム圏がアラビア海・ペルシア湾・インド洋・ベンガル湾・南シナ海に向かってびっしりつながっている。
さらにイラン高原やパミール高原の向こうにはトルクメニスタン、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス(以前はキルギスタン)、タジキスタンがタン・タン・スタンと広がっていて、そこはマルコ・ポーロたちが動いた内陸イスラーム圏だった。このうち北アフリカ(マグリブ)は八世紀の後ウマイヤ朝以来の骨太のイスラーム社会であって、今日出回っている『アラビアン・ナイト』は、そのエジプトのカイロでほぼ全面的な編集がされたとおぼしい。だからチュニジアやエジプトの動乱といっても、この巨大イスラーム・ベルトの中の出来事というべきだった。
ぼくは二〇〇六年のサッカーのワールド・カップの決勝戦で、フランス代表のジダンがイタリア代表のマテラッツィに頭突きをしたとき、この大イスラーム・ベルトが何かに向かってコツンと頭突きをしたのだと感じた。ジダンはアルジェリア移民のムスリムの家に育っていて、一説には姉を侮辱されたので思わず試合中の頭突きに及んだというのだが、それはウンマ(イスラーム共同体)への侮辱であったはずだった。このあたりの事情については内藤正典さんの『イスラムの怒り』(集英社新書)が詳しい。
ムハンマド・アブドゥフという近現代エジプトの改革思想のルーツをつくった知の巨人がいる。一八四九年生まれのウラマー(イスラム法学者)で、カイロのアル・アズハル大学でアフガーニーの思想に共鳴して、一八八二年にウラービー革命にかかわった。いずれ何かの千夜千冊の中で紹介したい。エジプトの現在を語るには欠かせないルーツ的人物である。
このところの報道で、「ムバラクは去れ」「ムバラクを倒せ」という怒号が飛びかっている。エジプト群衆の背後にはムスリム同盟とかムスリム同胞団といった正体不明の「堅い絆」が動いているのですというニュース解説があったけれど、これは正体不明どころか、祖国(ワタン)と民族(カウム)と信仰(ウンマ)を一緒にすべきだというムハンマド・アブドゥフの思想を下敷きにしてきたものだった。このあたりのマグマの動向も大事だ。加藤博さんの『「イスラムvs.西欧」の近代』(講談社現代新書)が詳しい。
事態は明白きわまりない。ここにきて、西洋中心主義の歴史観と欧米型資本主義の経済観が「世界の解明」には必ずしも役に立たないことが、あられもなく露呈しているだけなのである。
けれども、そのことを身をもって知るには、ひとつには、中東や南米や東アジアの劇的な変化の意想外の現実に次々に出会ってみることが必須で、もうひとつには、そもそもこのような現代史のマグマが“本来の世界史”のどこから対流をしてきたのか、それがどんな裂け目で噴き上がってきたのかを知ることが重要になる。しかしながら、その“本来の世界史”というものが、われわれには見えなくなってしまったのだ。

たとえば、では、モンゴルの疾風怒濤の歴史とはどういうものだったのか。それはどんなふうに十三世紀の世界史を誕生させたのか。おおざっぱなことくらいは、ほかならぬ東洋人である日本のわれわれは、歴史の血液感覚としてもそこそこ見えていてよさそうなはずだが、はたしてそうなっているのかといえば、かなり心もとない。だからこのことについては、いずれ別の機会に千夜千冊したいけれど、いまはとりあえずその前代未聞のモンゴル軍によるユーラシア制覇の十大ステップとでもいうべきを参考までにまとめておく。ざっと次のようになっている。
①一二〇五年にチンギス・ハーンがゴビ砂漠の南の西夏王国に侵入しはじめて、一二二七年に西夏を滅ぼし、翌年にはモンゴル帝国の第一歩が踏み出された。
②一二一一年に天山のウイグル王国がチンギス・ハーンに投降し、ついで西遼(カラ・キタイ)が帰順して、ここにモンゴル帝国の激越な第一弾が発射された。
③チンギス・ハーンは一二一〇年に金と断交して、翌年からは内モンゴルと華北に侵入を開始、一二三四年にはこれをオゴタイ・ハーンが受け継いで金を支配した。
④ついで一二一一年、ナイマン王の息子クチュルクがカラ・キタイに亡命し、一二一八年、モンゴル軍はクチュルクとともにカラ・キタイ王国を撃破し、その最前線はカザフスタン東部にまで進出した。
⑤一方、セルジューク・トルコの王朝が一一五七年に断絶すると、ここに新たにホラズム・シャー朝がおこり、これを一二一九年にチンギス・ハーンが全軍を指揮してシル河を渡り、七年の遠征によって掌握した。一二二〇年代前半のことだ。
⑥そのころチンギス・ハーンの長男のジョチはカザフスタンを任されていた。オゴタイ・ハーンは一二三六年にジョチの次男のバトゥを総司令官としてウラル以西の諸国の征服に乗り出し、キプチャクの草原とコーカサスの諸種族をまたたくまに制覇すると、一二四一年にはポーランド王国に入ってポーランド軍とドイツ騎士団を粉砕していった。その勢いはハンガリー王国やアドリア海にまで達した。
⑦オゴタイ・ハーンが一二四一年に死去すると、モンゴルの大遠征軍は東経一六度線で突如としてヨーロッパ進軍を中止して引き上げてしまった。総司令官バトゥは方向を転じてヴォルガ河畔、北コーカサス、ウクライナ、ルーシなどを支配して「黄金のオルド」を築きあげた。
⑧他方、一二五三年、チンギス・ハーンの孫のモンケ・ハーンは弟のフレグを西アジア方面に派遣して、バグダードを攻略させ、一二五八年にアッバース朝を滅ぼした。
⑨フレグはさらにシリアに侵入、そのままエジプトに進軍して一二六〇年にマムルーク朝を襲うも失敗、フレグはタブリーズを拠点として南アゼルバイジャン、西トルキスタン、アナトリア、コーカサスに及ぶ広大な領域を支配する。これがイル・ハーン国ことフレグ・ウルスだった。
⑩かくて一二七九年、フビライ・ハーンが派遣したモンゴル軍は杭州を占領、ここに南宋が滅亡した。フビライは一二五三年に雲南のタイ人の大理王国を、一二五九年には韓半島の高麗王国を降伏させ、それらの中核たる中国全土をモンゴル支配による元朝に染め上げていった。

こんなにも凄まじいことが十三世紀前半にあっというまにおこっていったのである。東は日本海・東シナ海から、西は黒海・ユーフラテス河・ペルシア湾にいたる東アジア・西アジア・東ヨーロッパに及ぶ大アジアのほぼ全域が、大モンゴル帝国の版図となったわけである。これをしばしば「パクス・モンゴリカ」という。
とはいえ、「パクス・モンゴリカ」のこんな粗筋だけをもって、それで十三世紀のすべてが説明できるわけではない。ここにはウマイヤ朝とアッバース朝以来のイスラーム諸国の大胆緻密な動向と、『クルアーン』と『ハディース』にもとづいたウンマ・ネットワークの網の目とが、まことにダイナミックな多発多様なエンジンとなって形成されてもいた。十三世紀は「アラビアン・ナイトの人々」と「シンドバードの海」と「チンギス・ハーンの国々」と「マルコ・ポーロの道」とで相互複合的にできあがり、そこへヴェネツィアやジェノヴァが繰り出す「地中海の交易商人」とがさまざまに交じりあっていたという、そんな構図だ。
今夜は七、八年前から気になっていた本書『ヨーロッパ覇権以前』を選んだ。それほどの大著とはいえない程度の、けれども中味がけっこう濃い二冊組だ。内容はきわめて明快、表題通りのヨーロッパが覇権をとる以前の、その“世界”とはどういうものだったのかということを問うた。
覇権とは「ヘゲモニー」の訳語だが、つまりは十三世紀(正確には十三世紀半ば)には、世界のヘゲモニーはアラブ・イスラームで、かつモンゴリアン・アジアで、かつ中東的で東洋的なしくみが、その大半を握っていたということをあらわしている。念のためもうひとつ言っておくと、ぼくにとっての本書はアンドレ・フランクの『リオリエント』(藤原書店)とぴったり一対につながっていて、そこに岡田英弘と宮崎正勝の二冊の『世界史の誕生』ものがくっついているというふうになっている。
本書とフランクの関係については、アブールゴド(アブー゠ルゴドと表記されているがアブールゴドにさせてもらう)の先駆的な本書が先に刊行されて、これを受けてフランクが大著『リオリエント』を著したという順になる。(注=フランクの『リオリエント』は本書『大アジア』の第四章のラストに収録した)
本書におけるアブールゴドの主張は、多少は慎重なところもあるものの、全体としてはアジア・ラディカルである。ブローデルやウォーラーステインが近代資本主義の基本となる「世界システム」は十五世紀のヨーロッパでほぼすべて成立していたという見解に立ったのに対して、いやいや、それ以前の十三世紀後半にはすべての準備がほとんど用意されていたじゃないかというものだ。
これはヨーロッパ中心主義の文明史観に強くクレームをつけたもので、けっこう激しい主張だ。彼女は、一二五〇年から一三五〇年のあいだに東地中海とインド洋を結ぶ中東に世界交易システムの新たな心臓部が確立していたということ、すなわちイスラームの経済社会の拡大期こそがその後の世界大のシステムの基本を確立していたということを、終始一貫して主張した。
この「一二五〇年から一三五〇年のあいだ」のまさに開幕にあたる一二六〇年は、マルコ・ポーロの父ニコロと叔父マッフェオがコンスタンティノープルから旅立って、広大なアジア・イスラームの土地に踏み入り、ついにフビライ・ハーンの国に入った時期にあたる。さきほどモンゴル軍の進軍として一〇個のステップを列挙しておいたけれど、マルコ・ポーロ一族の大旅行の前後には、そのような大変化がユーラシア全域において連続しておこっていたのだし、同時期にヨーロッパ側でも看過できないことがおこっていたのだった。
たとえば、一二五〇年のルイ聖王による十字軍の手痛い失敗、一二五八年のモンゴル帝国のフラグによるバクダードの征服とイル・ハーン国の成立、一二六一年のコンスタンティノープルのラテン帝国の陥落、エジプトにおける一二五〇年から六〇年のあいだのマムルーク朝の樹立などなど‥‥。
本書のアウトラインを少々ながら眺めておきたい。アブールゴドが一番言いたかったことは何かといえば、世界交易システムの新たな心臓部は「東地中海とインド洋を結ぶ中東にこそあった」「それはイスラーム社会とモンゴル社会と地中海社会のあいだにあった」ということである。
これは、たんなるユーラシア・アジアの勢力地図がそうなっていたということではない。経済社会が「世界システム」のレベルに達していたということだ。十三世紀後半に、あらかた次のようなことがおこっていたということだ。①貨幣と信用取引のしくみがだいたい発明されていた、②資本蓄積とリスク分散のメカニズムがほぼ確立していた、③富についての大半の集積方法がおおむね用意されていた。
この通りなら、世界の経済史を総覧しようと思う者にとってたいへん新鮮なことになるが、それが決してオリエンタリズムによる誇張や贔屓目ではないことを、アブールゴドは執拗に立証している。
当時の「世界」は、(A)西ヨーロッパ、(B)中東、(C)東方アジアという三システムに大別できるものになっていた。そこに二つか三つのサブシステムがそれぞれ内属して、独特の外向けの回路を形成しつつあった。
(A)の西ヨーロッパには、三つのサブシステム回路があった。①東フランス・中央フランス、②フランドル地方の織物生産地帯、③ジェノヴァとヴェネツィアだ。
①のフランス回路では、トロワ、プロヴァンス、バール・シュール・オーブ、ラニィの四都市がシャンパーニュの大市などを形成していた。②のフランドル回路の中心になったのは、商業面と金融面でのブリュージュと、工業面でのヘントである。③のジェノヴァとヴェネツィアの回路では、ジェノヴァがコンパーニャなどの商業的自治組織でムスリム諸国と争って西洋的な動力源になっていたのに対して、ヴェネツィアはコンスタンティノープルの庇護をいかした東洋寄りの商業都市国家になっていた。だからこそここからマルコ・ポーロ一族が東への旅を意図できた。
(B)の中東には三つのサブシステム回路が動いていた。①黒海沿岸では、コンスタンティノープルがセンター機能をもち、②パレスティナ海岸地帯ではここに十字軍の活動が加わって、内陸路によるバクダード回路と北東に進む中央アジアの隊商を包みこむ回路が発動した。③ペルシア湾とインド洋を媒介にした回路ではホルムズやシーラーフなどの交易拠点が含まれて、大量の商人が入り乱れた。
(C)東方アジアにも三つのサブシステム回路が躍動していた。①アラブ世界と西インドを結びつける回路、②南東インドとマラッカ海峡を結ぶ回路、③マラッカ海峡と中国の東端を結ぶ回路、である。
これらのうち興味津々なのは、(C)の東方アジア・システムなのだが、マルコ・ポーロ的にいうならこれは、(A)の③回路のヴェネツィアを発して、(B)の①コンスタンティノープルを介し、さらに②バクダード回路、③インド洋のホルムズ回路をへて、すべての流れが(C)に至ったというふうになる。
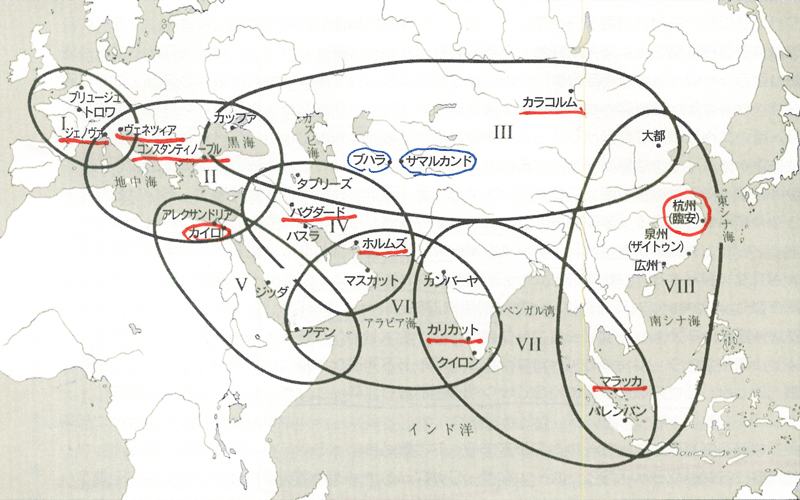
そこで、以上の俯瞰された(A)(B)(C)の十三世紀世界システムを、今度はマルコ・ポーロふうに西から東へ向かうルートで表示してみると、別のネットワークが見えてくる。そこには、(a)北方ルート(コンスタンティノープルから中央アジアの陸路を横切るルート)、(b)中央ルート(地中海とインド洋をバクダード・バスラ・ペルシア湾を経由して結ぶルート)、(c)南方ルート(アレクサンドリア・カイロ・紅海をアラビア海とインド洋のほうに結ぶルート)、という三つのルートが浮かび上がってくるのだ。
これが当時の「東方幻想」を満喫させるルートであった。修道士カルピニやマルコの一族たちも、まさにこの「東方幻想」ルートにかきたてられていた。そしてここにこそ“本来の世界史”が十三世紀に誕生していった背骨が如実に見えてくる。
十三世紀の(a)北方ルートを仕切っているのはモンゴル帝国だが、そこには前史もあった。すでにアッティラ麾下のフン族がローマ帝国崩壊直後に内陸ルートをドイツ地域にまで進出していたし、トルコ系の民族であるセルジューク族が西に向かい、十二世紀までにはイラク全土と肥沃な三日月地帯とエジプトにいくつものルートをつくっていた。また、別のトルコ系のホラズム・シャー朝はトランスオクシアナ(中央アジアのオクサス川以東のオアシス地帯)を押さえていた。
このようなモンゴル前史に対して、さきほど一〇のモンゴリアン・ステップに紹介したような、モンゴル軍の未曾有のユーラシア撃破が連打されたわけなのである。とくに一二二五年までに、チンギス・ハーンのモンゴル軍先鋒隊がホラズム・シャー朝を破り、ハンガリーにまで進攻していったことが大きかった。
しかし、ここでチンギス・ハーンはなぜかくるりとヨーロッパに背を向けたのだ。これは世界史上のグランドシナリオにとってきわめて大きな“方針変更”なのだが、ここではその点には立ち入らない。チンギス・ハーンにとって、ヨーロッパは魅力のある征服対象ではなかったということなのだろう。
ともかくもこうしてモンゴル帝国はヨーロッパを捨てて、朝青龍や白鵬クラスの兵士を何万人も用意した戦線を東に大きく切り返し、今度は中国に向かったのである。一二二七年、チンギス・ハーンはその途次で病没した。けれども、このことがまわりまわって、十三世紀ユーラシアにモンゴル型の(a)北方ルートを確立させたということ、いくら強調しても強調しすぎることにはならない。
チンギス・ハーンの死後、世界制覇の野望は四人の息子たちに委ねられた。ジョチとバトゥはロシアと東ヨーロッパを、チャガタイはペルシアとイラクのほぼ全域にわたるイスラーム地域を、トルイにはモンゴルの本土が任せられ、それらすべてをオゴタイ・ハーンが統率した。
その後、オゴタイが死に、次をモンケが継いだのち、モンケの兄弟であるフレグが一二五八年にバクダードを征服して、そこにフレグ・ウルス(イル・ハーン国)を創設した。もう一人のモンケの兄弟のフビライのほうは中国北部を任されて元朝(大元ウルス)を確立した。バクダードと元の上都・大都こそは、マルコの一族が東へ東へ向かったルートと目的地だった。
(b)の中央ルートのほうは、シリア・パレスティナの地中海沿岸部に始まり、メソポタミア平野を通ってバクダードに入り、そこで陸路と海路に分かれた。
陸路というのはペルシアからタブリーズに至り、そこから二つに分岐して、南東へは北インドに向かい、東にはサマルカンドから西域をへて中国に進路をとるというふうになるルートである。海路のほうはティグリス川に沿ってペルシア湾に下り、バスラの港からオマーン・シーラーフ・ホルムズ・キーシュというふうに進んだ。大量の商品が運ばれたのはこの海路のルートだった。
(c)の南方ルートは、カイロと紅海とインド洋を結ぶルートのことで、これは一二五〇~六〇年のエジプトに出現したマムルーク朝の影響がすこぶる大きい。
このエジプト地域はアラブ・イスラーム史としては、後ウマイヤ朝(七五六〜一〇三一)やファーティマ朝(九〇九~一一七一)がいたところで、そこが十字軍に攻められると、それを十二世紀のクルド人の兵力がサラディンのもとで撃退したことによってアイユーブ朝(一一六九~一二五〇)となり、そのアイユーブ朝がさらにエジプトの国土を実質的に守ってきた奴隷軍人たちによってマムルーク朝(奴隷王朝)に切り替わったことで、新たな世界史の踊り場になった地域なのである。
それゆえこの南方ルートは、その中心のカイロが「世界の母」とよばれてカリフ制を再興したこと、ついでは初代のスルタンになったバイバルスが一二六〇年にシリア・パレスティナを制圧したこと、さらには後続の十字軍を撃退しつづけたこと、これらの流れの出現がつくりだした世界史上の新規ルートだった。いわば十字軍とモンゴル帝国の挟撃によって出現したルートだ。
以上、十三世紀世界は三つの(A)(B)(C)システムと、八つか九つのサブシステムをもつ回路の相互複合的な組み合わせによって説明できると、アブールゴドは見たわけである。
本書は後半にさしかかって、「シンドバードの道」と「モンゴルの道」に分け入り、いよいよ「インドと中国が呼応しながらつくりあげた十三世紀東方世界」の牙城に向かっていく。「シンドバードの道」とは、まさにアラビアン・ナイトな広大な領域のことである。かつての古代ペルシアの商圏がどのようにアラブ化され、イスラーム化されていったかということが証かされる。「モンゴルの道」のほうは十三世紀においては、それこそぴったりマルコ・ポーロの東方への旅に重なっていた。
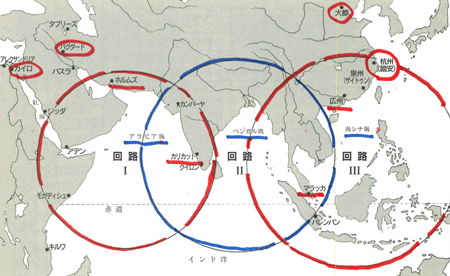
こうして最後に注目されるのが、紅海・ペルシア湾・アラビア海・ベンガル湾・南シナ海をまたいで形成された「インド洋交易圏」と、フビライ・ハーンの中国支配によって頂点に達した「モンゴリアン・チャイナ交易圏」である。
「インド洋交易圏」を制したのはアラブ・イスラーム商人だ。かれらは西側の海路では紅海・アラビア半島・ペルシア湾岸・インド西南を交易し、中央の海路ではインド東南・マラッカ海峡・ジャワを動きまわり、東端の海路ではそのマラッカ海峡からスンダ海峡・東インド諸島をへて、ついには中国華南をめざした。
このような実情をアブールゴドは、十五世紀に書かれたイブン・マージドの航海記などを克明に調べて再生させている。
この商人たちは単独の族派など形成していない。それぞれ独自の商人組織をつくりあげていた。共通の言語や共通の通貨で取引していたわけでもない。それでもアラビア語はギリシア語や口語ラテン語と同様にかなり広い地域で用いられていたし、北京語はすでに東方アジア諸国の共通語になっていた。
通貨はヨーロッパでは銀が価値をもち、中東では金がそれにあたり、中国ではそのころは銅貨が好まれていた。けれども、そういうことはこのアラブ・イスラーム商人たちの何の支障にもならなかった。どんどん両替をすればすむからだ。ようするに、かれらは資本主義の先駆者で、かつ非ヨーロッパ的な主役たちだったのだ。
ちなみにアラブ・イスラーム商人の前身の、そのまた前身はなんとシュメール人である。そこには商業民族の歴史があった。それがササン朝ペルシア期で「銀行・小切手・為替手形」の原型を生み、これをイスラーム商人がコンメンダによる契約商業に発展させていった。
この契約商業はシャリカ・アルミルク(所有権上の協業)とシャリカ・アルアクド(契約による商業上の協業)によって発展したもので、労働すら投資行為とみなされる。このあたりのことは、櫻井秀子さんの『イスラーム金融』(新評論)が詳しい。つまりは、こういうところにもヨーロッパ的な契約とはまったく異なる“世界史”が登場していたわけである。このアイディアはのちにインドネシアのスカルノやマレーシアのマハティールらが、二十世紀に復活させている。
ヨーロッパとアジアを結びつけた地理中心は、中東と中央アジアとインド洋だった。なかでもインド亜大陸が、すべてのユーラシアの動きの波動力となった。
南インドは大半の航海者が出合うところで、西海岸にはアフリカやメソポタミアから来た船が着岸し、東海岸には中国・インドネシア・マレーシア・タイなどの船が西に向かうために寄港する。西側がマラバール、東側がコロマンデルだ。マラバールの中心はカリカット(現在はコジコーデ)やゴア、その背後に発達したのがグジャラートやシンド(今のパキスタン)である。コロマンデルのインド商人はもっぱら東に向かって活動した。
インド亜大陸に次ぐのは東南アジアと、その海だ。
そもそも東南アジアは十世紀と十一世紀に、南インドのチョーラ朝、クメールのアンコール朝、ビルマのパガン朝、北ベトナムの黎朝、中国本土の宋朝などの新たな動向によって勃興していったところで、海に向かってはいわゆる「都市の多島海」を形成していった。
そこからしだいに中核的な“海のブリッジ”となっていったのがマラッカだ。今のマレーシアにあたるが、ここの海峡は一五一一年にポルトガルの征服者カブラル艦長の一行がイスラーム商人の船舶を襲撃して捕縛するまで、ずっと東西の要衝をつなぐ“海のブリッジ”として守護されつづけた。マラッカ海峡はスンダ海峡とともに最も広域の東西のルートをつなぐ最も狭い海峡だったのである。
これでやっと東アジアの帝国、中国の話になる。
もともと中国の人口分布の重心は六世紀までは内陸部にあって、外国交易もシルクロードを中心とする内陸交易中心だった。それがローマ帝国の没落とともに、人口重心が南方に移動して、海洋交易が活発化した。それとともに十二世紀末には人口が一気に七三〇〇万人に達した。その一世紀後の、つまりフビライ・ハーンの時代には、全人口の八〇パーセントが中国南方に居住したのだった。
これは今日の北京型の中国からは想像がつきにくいだろうが、この南がかった中国こそ、十三世紀世界システムに大きく寄与したのである。マルコ・ポーロは北の中国を「カタイ」と呼び、南の中国を「マンジ」と呼んだ。
南のマンジの蠢動を体現したのは、広東・泉州・杭州だ。マルコ・ポーロの時代でいうと、広東はカントン、泉州はザイトゥン、杭州はキンサイになる。とてもエキゾチックだった。これらの港町の繁栄は一三六八年の元の滅亡後も続いた。もっともアブールゴドは、どうも中国についてはあまり冴えた分析をしていない。のちに『リオリエント』のアンドレ・フランクからそこを批判された。そこはむしろ明治・大正期の日本の大アジア主義者のほうが詳しかったろう。
ごくごくおおまかな紹介をしたにすぎないけれど、十三世紀の世界システムは以上のような地理と勢力とネットワークをもって形成されたことが浮上したと思う。
ところがそれらの大半が、十五世紀にはヨーロッパによってしだいに分捕られていったのである。そこでは、東方寄りのヴェネツィアよりも大西洋寄りのジェノヴァが活躍し、そのジェノヴァにコロンブスが登場した。またポルトガルが「旧世界」を乗っ取り、スペインが「新世界」を合併したことが、十三世紀世界システムに変容を生じさせたのだった。
いったいなぜこんなふうになったのか。このことについては、本書には述べられていない。この問題に入るには、いったんアラブ・イスラーム社会の歴史を離れ、ヨーロッパとイスラームの相克の歴史を近代にまで突き進み、一方で中国がノンチャイニーズの清王朝になってのたうった理由と、鎖国を破られた日本が一挙に明治維新をおこしてアジア進出に転じたことを、あらためて俎上にのせることになる。舞台はヨーロッパによる東アジアと東南アジアの植民地化に、どのように日本とアジア諸国が対峙しようかというほうへ移ることになる。