ホワイトヘッドの哲学
講談社選書メチエ 2007
ホワイトヘッド哲学に本格的にとりくんだ人がいた。
おおいに責任を感じるとともに、なんだか嬉しい。
今夜は、ホワイトヘッドをめぐるふりをして、
世界の見方って、ときに
こんなふうにつながっていくという話を、
ちょっとしてみたい。それは、
世界もわれわれも、非連続の連続だということだ。
本書の内容に入る前に、著者の中村昇さんについて書いておきたい。いまのところ個人的にはまったく面識がないのだが(近々出会いたいと思っているが)、中村さんのほうはぼくのことをよく知っているらしい。なぜそんなことがわかったかというと、本書の冒頭近くにぼくが登場する。
「1978年だから、もう30年近く前になる」とあって、予備校の友人におもしろいところがあるから行かないかと誘われ、当時、ぼくがやっていた工作舎のスペースで開いていた無料の「遊学する土曜日」に中村さんがちょくちょくやってきていたというのだ。そこではぼくが、稲垣足穂(879夜)をちょっと涙を浮かべながら話したり、荒俣宏君(982夜)や吉野裕子さんと対談したり、量子力学や相対性理論について語ったり、吉田一穂(1053夜)の詩を読んだりしていたのだが、その「遊学する土曜日」に何度か通っているとき、中村さんはぼくが話すホワイトヘッド(995夜)の話に強烈な印象をもったのだという。
中村さんは1957年の佐世保の生まれで、いまはレッキとした中央大学の哲学教授である。「遊学する土曜日」に来ていた当時は意気軒高な浪人だったらしい。受験中の浪人ではさすがにホワイトヘッドについては何も知らなかったようだけれど(というよりも当時の知識人でホワイトヘッドをちゃんと読んでいるのは、ご老体の市井三郎ほか日本全体で10人未満しかいなかっただろうと思う)、よほどぼくが熱心に話したとみえて、ホワイトヘッドをそうとう別格に扱っている松岡正剛の口吻から、何かピンとくるものを感得してくれたようなのだ。
その後、中村さんはホワイトヘッドを含む現代哲学を、たとえばヴィトゲンシュタイン(833夜)やベルクソン(1212夜)などを専門的に研究するようになった。本書の前には『いかにしてわたしは哲学にのめりこんだのか』(春秋社)なども書いている。大学で哲学を研究する前は、土方巽(976夜)のところで暗黒舞踏のレッスンも受けていたらしい。
なぜ暗黒舞踏などに関心をもったかということは、うすうす見当がつく。中村さんを「遊学する土曜日」に誘った予備校の友人は加藤博という青年で、のちにぼくが「遊塾」を開いたときに参画した青年でもあり、その彼がそのころは暗黒舞踏に親しんでいたということを聞いていたからだ。それにしても親友が暗黒舞踏しているからといってそこに顔を出すというのは、やはり中村さんも変わっている。きっといまなお、そういう風変わりな趣きをもつ哲人なのだろう。もっともそういう哲学研究者こそ、ぼくには信用できる。
だいたいアカデミズムの畑では、暗黒舞踏に関心をもったり、『いかにしてわたしは哲学にのめりこんだのか』といった長ったらしいタイトルの本を書く研究者には、ふつうは眉をひそめる。ちなみに、タイトルがやたらに長い本は業界では書評欄にとりあげにくく(記事スペースが決まっているためです)、それだけでも損をしているのじゃないかと心配するのだが、たとえ長くともこういうスバリの表題をもった書物は、中身の見当がつかなくとも覗いておいたほうがいいとも言いたい。たとえば内村鑑三(250夜)の『余は如何にして基督教徒となりしか』だ。ぼくはこのタイトルで内村を読み始めたのである。
こういう例もあるのだからタイトルはいくら長くたっていいのだが、そんなことはともかく(笑)、そういういささか風変わりな中村さんが、当時、ぼくが『遊学』に書いた30年ほど前のホワイトヘッドについての文章を、本書では次のように評してくれていた。「この書きだしは、いま読んでもうまい。ホワイトヘッドの哲学の特徴を、短い文章で射抜いている」。
書きだしというのは、『遊学』(いまは中公文庫)のホワイトヘッド論の書きだしのことで、ぼくは次のように書いていた。
いろいろなものがピッチング・マシーンで投げられたように次々にむこうから飛んでくる。われわれはこちらにいて、その飛んでくるものが何であるかを見ている。飛んでくるものがあまりに速くあまりに多ければ、そのいちいちを識別することが不可能となり、ただおおざっぱな差異を見るにとどまり、それらが比較的緩慢に飛んでくるばあいは、そのすべてに命名を与える余裕すら生まれる。
われわれが「自然」に対してとっている立場はこのようなものだろうか。ポンポンと飛び出してくるリズムのみを「自然」と見る立場もあれば、そのひとつひとつのもつ様態や飛び方を見て、そこに「自然」を思う立場もある。いくつかのパターンやグループに分けて、これを「自然」と見る立場があってもおかしくはない。
しかし、この比喩は完全にまちがっている。われわれ自身もその飛んで来ているものの一部であり、われわれは自身飛びつづけている状態のままに首をひねって周辺を眺めようとしている――このようになっているはずなのだ。つまり、われわれはピッチング・マシーンのこちら側でバットを構えているのではなく、一個のボールとしていまなお空中にあるままなのである。
中村さんは、「その通り。ホワイトヘッドは、観察者も流動しつづけるものとして世界のなかに放りこむ」と書き、さらに「ホワイトヘッドの哲学の本質を、当時これだけ深くえぐるのは、並大抵の力量ではない。ほかの思想家や哲学者や芸術家についてもそうだが、松岡は、本質を見抜く独特の能力をもっている。これは、かなり驚くべき力だ」とも付け加えた。たいへんありがたい鑑定だ。
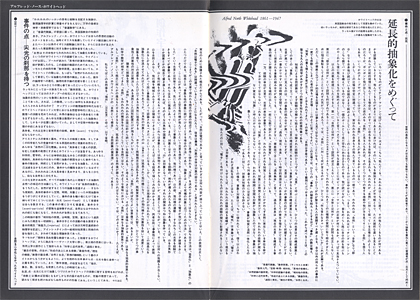
第Ⅰ期『遊』9+10号「存在と精神の系譜」
(『遊学Ⅰ・Ⅱ』中公文庫)
というわけで、本書を以上のような誼みもあってのうえ、少々紹介しようと思うのだが、ところで、またまた寄り道になるのだけれど、本書を紹介したいのは、むろんぼくのホワイトヘッド説明よりずっと正確でタメになるものがあるからなのだが、もうひとつは、ぼくがこの「ピッチング・マシーンの比喩」をごく最近、あるところで30年ぶりに話したばかりだったということが手伝っていた。
あるところというのは、イシス編集学校の「離」でオフ会「表沙汰」というものを催したとき、その30人ほどの離学衆たちとの宴がいよいよ暁方に及んだとき、ぼくはその場を締めるために立って、「ぼくたちはピッチング・マシーンのこちら側にいるのではなく、ピッチング・マシーンとそのボールとともに世界を飛んでいるのだ」とやったのだ。今年の5月17日の夜明けのことだった。
みんな水を打ったようにシーンと聞いていてくれていたが、どんな気持ちで聞いていたのかはわからない。それがぼくのホワイトヘッド論の一部であったことは伏せたので、ただふわふわとした飛行感覚に乗っただけかもしれないし、午後1時からの「表沙汰」にみんなそうとう疲れ切っていただろうから、まさに“上の空”だったかもしれない。しかしあのときぼくは、この話をどうしてもしたくなったのだった。
そういうときって、あるものだ。誰にも多少の経験があるだろうが、とくにぼくにはしばしば「嗚咽」や「間歇泉」のように“或る話”がビデオ再生するごとくに突如として噴出することがあって、それがいつどこでどのような場面に噴出してきたかということ自体が、何かの“解錠(リリース)”になる。
つまり、どこで何をどのように言い放つかということが、おおげさにいうのなら、ぼくの存在学の深化の、契機あるいは再契機になるわけだ。“解錠”と言ったのは、そのことが昔のことゆえ錠を降ろしていたままになっていて、それが何かのきっかけに解錠され、リリースされてくるからだ。
こういうときは、内容よりも、聞き手とともに自分がどんなふうに存在学的な再契機に出会えたかということのほうが重要だ。ヴァレリー(12夜)ならさしずめ「雷鳴の一撃」というところだが、それが5月17日の夜明けでは、ホワイトヘッドについて30年前に話した場面状況の急激な再現だったのである。
そしてそれは、きっと中村さんが本書『ホワイトヘッドの哲学』を書こうとしたときに蘇ってきた「松岡正剛との出会い」の再生噴出でもあったにちがいない。こういうこともあったので、そのうち機会がくれば、本書のことを紹介しなければと思っていたわけである。
前置きが長くなった。
それでは、中村流のホワイトヘッド哲学の要点だけをざっと紹介する。ぼくのホワイトヘッド論の一端は995夜にも、『遊学』にも、書いたことなので、ここではくりかえさない。
中村流ホワイトヘッド論は、木村敏の『時間と自己』とジル・ドゥルーズ(1082夜)の『襞』を補助線にして案内される。これはうまい案内の仕方だった。なぜならホワイトヘッドはその哲学の一部始終で、たえず「出来事」(event)を重視していて、木村敏もドゥルーズも世界や自己が「こと」や「もの」を組み合わせた出来事によって織り成されているとみなしているからだ。
おおざっぱにいえば、ホワイトヘッドもそのように世界を見ていると思えばいいだろう。すべては関連しあっている「過程」(process)であって、その過程そのものが「実在」(reality)なのである。過程が実在なのだ。実在は過程なのである。したがって「出来事」はやがて『過程と実在』という大著のなかでは「アクチュアル・エンティティ」(actual entity 活動的存在)と呼称を変える。
出来事とかアクチュアル・エンティティというのは、ホワイトヘッドが「こと」や「もの」を、とりわけ「こと」の本質を徹底的に絞りこんで仕上げた概念である。世界というものを見極めるための究極の相手のことだ。それゆえアクチュアル・エンティティには世界最小のプロセスも含まれている。いや、そのプロセスを見ているのは観察者であるわれわれなのだから、実はわれわれも過程的実在として“そこ”に“いる”わけだ。
そのように世界を見極めること、またそのことを抽象化して唯一無二に仕上げてしまうという見方そのものを、ホワイトヘッドは「抱握」(prehension)というふうに名付けた。
われわれは知覚するとか、認識するということをいつもおこなっているけれど、とくに知覚や認識がないばあいでも、世界が漠然とであれこんなふうになっているのだろうと思うこともおこっているわけで、そのように世界をどこかで感知していることが、そもそも「抱握」の大前提なのである。ということは、どんな出来事も世界も、実は「抱握の関係のありかた」だというふうにもなる。
今日、世界をどのように見るかということは、すなわちどのように抱握するかということは、社会観においてはかなりめちゃくちゃになっている。
アメリカが扇動してイギリスがこれに追随した金融ゲームによって、この20年ほどで多くの社会的価値観の規範がずたずたになり、とくにビジネス社会に携わっている者の思考力と行動力は、すっかり一様になってしまった。頼るのはコンプライアンスばかりという有様だ。
しかし、そういう社会観を含んでのことであるが、世界の本質というものは、もともと「非連続の連続」なのである。これはもとをただせば「場」の本質からきていることで、科学観でいうのなら、ファラデー(859夜)やマックスウェルが「電磁場」を“発見”してからこっち、ずうっとそうなっている。電場がプラスになったり、マイナスになったり、磁場が揃ったり、揃わなかったりするという、この「場」のほうに、世界のポテンシャル(つまり可能性)というものがある。
電磁場だけでなく、われわれがすっぽり包まれている重力場まで考えてみれば、このことはすぐわかる。世界はその「場」において、もとから出たり入ったりなのである。
ホワイトヘッドもこのような世界の見方(抱握の仕方)を一貫して採ってきた哲人で、「場」のことを「延長連続体」などと言うこともあるが、世界の流動的現象のいっさいが、この「場」のほうから出来(しゅったい)するというふうに見てきたのだった。物質も生命もわれわれも経済も、この「場」のほうに本来を出所させ、その動向を陥入させている。
中村さんは、これをまとめてホワイトヘッドは「関係性の森」を考えたのだというふうに解説した。関係の究極がアクチュアル・エンティティであり、そのように関係を見るように、われわれは関係づけられている。まさに、その通りだろう。これをネクサス(網の目の世界)との関係と言ってもいいはずだ。
ということは、ようするに、世界は「かかわり方」なのである。「場」とのかかわり方なのである。「関係性の森」なのだ。ネクサスなのだ。それが世界というものの本質であって、それ以外の世界は世界観には入らないということなのである。(仮にどんな宇宙がパラレルに併存しようとも)。
というようなわけで、ホワイトヘッドはそのような「かかわり方」の一番小さな単位をアクチュアル・エンティティと呼んだわけである。そして、このアクチュアル・エンティティが「縁起する」というふうに考えた。
縁起というのは仏教用語だから、ホワイトヘッドはそんなふうには言わずに、「経験の生起」とか、「アクチュアル・オケイジョン」(actual occasion)と言った。アクチュアル・オケイジョンは「活動的生起」などと訳す。まあ、用語はどうであれ、世界はそこに、そこから、いつでも、急速に、われわれのかかわり方を巻きこんで、生起しているわけである。
こういう見方を総じて「ホワイトヘッドの有機体哲学」という。ぼくも何度も説明してきたが、中村さんはこれを「フィーリングの渦巻く海」についての哲学というふうに解説した。これも当たっている。ここでフィーリングとはまさに「感じ」(feel)ということで、それが何を意味するかは446夜のベイトソンのところで説明したので省略するが、一言でいえば、出来事とわれわれの「あいだ」は、必ずやフィーリングをともなっているということだ。
しかし、たんなるフィーリングだとは思わないほうがいい。このフィーリングは世界の本来とのべつ交感しているフィーリングなのだ。つまりは、抱握である。だからこの“抱握フィーリング”には肯定的な感じもあれば、否定的な感じもある。この正と負の両方を含んでフィーリングなのである。ベイトソンはそれを「相補的分裂生成」と言ったけれど、ホワイトヘッドは「合生」(concrescence)と言った。
ここから先、中村さんは主にベルクソン(1212夜)との比較を通して、またときどきヴィトゲンシュタイン(833夜)を引き合いにして、さらにホワイトヘッドの有機体哲学の核心に入っていくのだが、今夜はこのくらいにしておこう。ヴァスバンドウの『倶舎論』も出てくる。ぜひとも本書を手にとることを勧めたい。
ついでに、中村さんがこのような考え方をもったことのメタレベルな思考については、『いかにしてわたしは哲学にのめりこんだのか』(春秋社)を読まれるといい。めったにお目にかかれない説明が随所に出てきて、きっと示唆をうけることだろう。実はその「あとがき」にも、ぼくが出てくる。
ヴィトゲンシュタインという名前を知ったのも、松岡正剛の「遊学する土曜日」だったというのだ。これまた、なんとも懐かしくも、嬉しいことである。
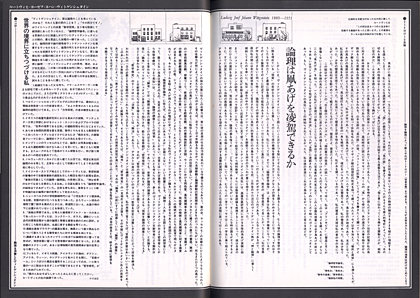
第Ⅰ期『遊』9+10号「存在と精神の系譜」
(『遊学Ⅰ・Ⅱ』中公文庫)



