父の先見


MONETIZE OR DIE?
東洋経済新報社 2013
編集:黒坂浩一
装幀:金子千鶴
現状は、こうだ。2012年の年の瀬、80年にわたって世界に君臨してきた「ニューズウィーク」(NW)が「紙」を放棄した。最終の12月31日号は、象徴的な特集名「ラストプリント・イシュー」というオールドファンの涙を誘うものだった。
NWにはオンラインにせざるをえない辛い事情が続いていた。2005年に300万部だった部数が2012年に入ると半減した。広告量も80パーセントほどダウンして、年間4000万ドル(40億円)の赤字。「紙」メディアの金科玉条を支えていた広告プレミアム神話がばらばらと剥げ落ちていったのだ。
NWだけではない。華々しく見えていたアメリカのメディア各社の苦境は軒並みひどい。新聞社のフルタイム職員数は2000年の5・6万人から2012年には一挙に4万人にまで減った。慌ててオンラインを走らせてみたものの、オンライン広告の単価はあまりに安くてワリに合わない。紙の広告が100万円なら、オンラインは10万円、モバイルでは1万円。アナログ・ドルはデジタル・ペニーなのだ。
各誌紙はデジタル転換をはかろうとしたが、容易ではない。戦場がすっかり違う。かつては紙のメディア企業のライバルは同業の紙のメディア企業だったけれど、デジタル・メディアではマイクロソフト、AOL、グーグル、ヤフー、フェイスブックといったIT企業との闘いになる。太刀打ち不可能だ。
これまで紙メディア業界は限られた同質のプレイヤーとばかりシェアを分け合ってきた。しかし辛うじて苦境を乗り切り、なんとか転換をはかりつつあるのは、FT(フィナンシャル・タイムズ)、NYT(ニューヨーク・タイムズ)、雑誌の「アトランティック」「フォーブス」くらいだった。どんなふうに窮地を脱したのか。
FTは無料と有料を組み合わせたメーター制(フリーミアム)を導入して、購読料収入をアップさせた。メーター制は、①1ヵ月だけ一定本数(たとえば10本)だけ無料で記事を読める。②一定本数をこえると、有料会員にならないと次は読めない。③有料会員は読み放題で100本でも1000本でも読めるようにする。④検索エンジン、ソーシャルメディア経由で拡散された記事も無料で読み放題にする。⑤デジタル版は紙の購読料より安くする、という作戦だ。
FTがB2B(法人向け)を強気に重視したのもよかったようだ。スタンダード会員の年会費を350ドル、レックス・コラムが読めるプレミアム会員は年会費450ドルにした。やってみると、プレミアム会員が3分の1をこえた。功を奏したのは、無料会員500万人の属性データを徹底分析したからだった。
NYTはこの数年で30億ドルの売上げを20億ドルに落とし、広告収入は半減していた。やむなくリストラを断行した。2010年に100名を切り、翌年には20名に遠慮してもらった。苦しんだのは、当初のオンライン化がうまくいかなかったせいである。記事の無料化をやってみたのだが、さっぱりだった。
そこで方針を転換、FTとは少し違うのだが、メーター制を導入してユニークユーザーの獲得に乗り出した。動画コンテンツの充実、『フラット化する世界』のトーマス・フリードマンらをホストとした高額フォーラムの開催、年会費40ドルのクロスワードパズル・プロジェクトの展開なども併用した。
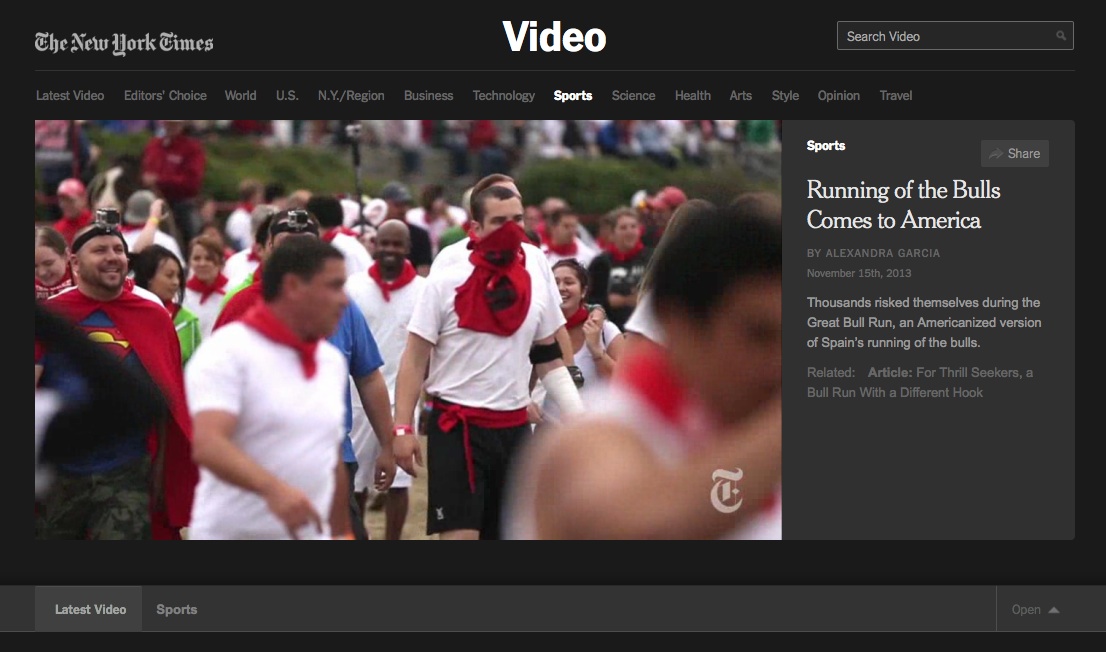
1857年創刊の「アトランティック」の凋落は2005年に向かって、目を覆いたくなるものだった。赤字は3000万ドル。ジャスティン・スミスが社長になって、反撃を開始した。チームづくりに取り組み、編集者とビジネスマンをぐちゃぐちゃに交ぜた。次にコンテンツをデジタルと紙に分けないようにした。
そのうえでメインサイト以外の、ニュース&オピニオンの「アトランティック・ワイアー」、都市・旅行に特化した情報サイト「アトランティック・シティ」を立ち上げ、2012年からは20人のジャーナリストを新規雇用して、徹底したグローバルエリート向けのスマホサイト「クオーツ」を組み上げた。ブランドコンテンツによる広告ビジネスを「クオーツ」を中心に推進したのである。すでにボーイング、ソニー、キャデラック、クレディ・スイスなどがブランドコンテンツの顧客になっている。
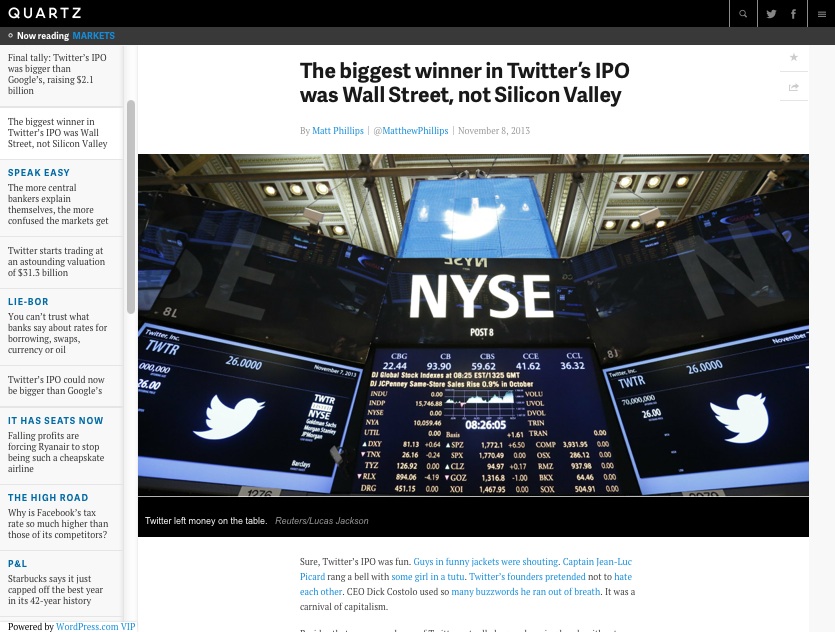
92万部を誇ってきた「フォーブス」は、ドットコム・サイトのCPO(チーフ・プロダクト・オフィサー)のルイス・ドヴォーキンが早々に抜け目ない戦略を行使した。ビジネス誌の編集記者として名をあげてきた男だ。
ドヴォーキンは「徹底オープン戦略」と「データカルチャーの駆使」を敢行し、オープン化にはビジネスジャーナリスト以外の書き手をどんどん登用した。いま100人の書き手のうち、半分がビジネスパーソンや学者やフリージャーナリストになっている(2013年現在)。ユーザーの声に応えるためだ。それには職業記者にこだわらずに、適材適所の目利きが必要なのだ。
データカルチャー化は書き手と読者のあいだを、さまざまなフィードバックのしくみでつなごうというものだった。たとえば原稿料をユニークビジター1人につき数セントとし、もしそのビジターが同じ月に同一筆者の別の記事を読んだ場合は、20倍のボーナスを支払うようにした。これはページビューのデータに原稿料とビジターの「関係」を反映したもので、なるほどと思わせる。
デジタル・メディアは紙メディア以上に目利きの獲得と選抜が重要になるのだが、そこにはそれなりの報酬体系が機能するべきなのだ。
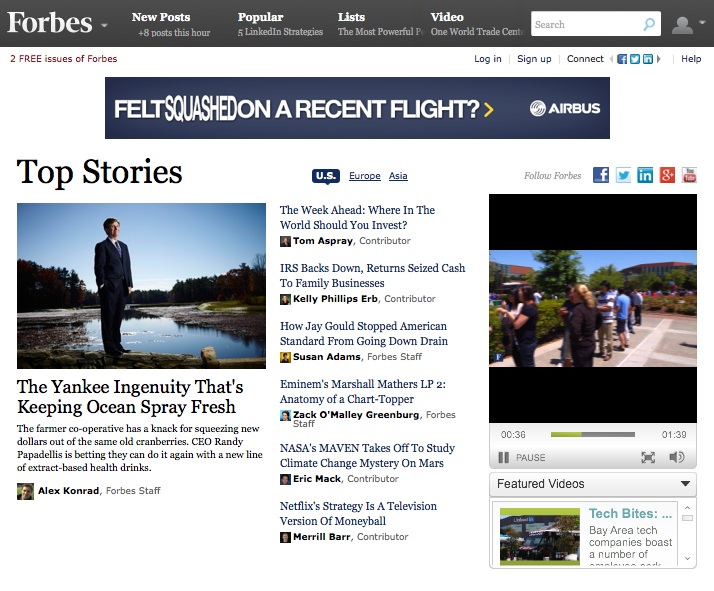
本書は小ぶりのトレンド本だが、この手の本としてはめずらしく快速で、説得力がある。今後のメディアの方向選択にひとつの風穴をあけた。
著者の佐々木は雑誌編集をへて2012年冬に「東洋経済オンライン」の編集長になると、すぐさまリニューアルにとりかかり、きっとすぐれたチームを促成栽培したのだろうが、僅か4ヵ月で5300万PVを達成して、ビジネス系サイトのナンバーワンになった。その後は「ニューズピックス」を立ち上げて、これまたナンバーワン・メディアに育て上げた。
が、それが自慢でこの本が書かれたのではない。「週刊東洋経済」という現場でビジネスの最前線を追いながら、自身が所属するメディア業界やジャーナリズムが日に日に古色蒼然となっていくのを渦中に実感していて、この変革期を首尾よく脱出突破するにはどうすればいいのかという「やむにやまれぬ事情」から書いたのが、よかった。とくに日本のメディア業界の慣習と現状をどう見ればいいのか、いろいろ参考になる。ぼくも岡島悦子の紹介で本人と話してみて、この男は「やれる」と感じた。

どう転んでも、今後のメディア業界は「紙」からデジタルに移行していくしかないようだ。すでに印刷とテレビがすっかりデジタル化された。そこへSNSだ。「紙」はそれらのあいだで三方挟撃されて方針転換を迫られている。
こういう状況では、競争力はコンテンツだけでは決まらない。それなのに単行本や雑誌や新聞をつくってきた連中は、この新たな戦場のことが理解できないでいる。
事態ははっきりしている。「読み」はアクセスであり、アクセスのしくみに「読み」が出入りするべきなのである。それゆえユーザビリティをよくするためのテクノロジーとクリエイティブが要求され、PDCA(計画→実行→評価→改善)をのべつくりかえさなければならない。ユーザーの興味や関心が向く記事と広告とをマッチングする技法をつくり、日々のサービスをリニューアルしつづける機動力もいる。
紙の旧世界ならコンテンツは売りっぱなしでいい。発行発売された本や紙誌は、単立したパッケージ商品であるからだ。そのかわり書籍では売れない本はすぐに返本され、絶版扱いになる。雑誌は特集コンテンツで売るのだが、版元の収入はもっぱら広告だ。だから書籍や雑誌がどんな理由で売れたのか、売れなかったのか、結局のところわからない。とくに書籍は初版部数を少なくして、売れ出したら増刷をくりかえすという“潜水泳法”的な手法以外のどんな作戦も、もっていない。
電子メディアはそうはいかない。「出っぱなし」「見えっぱなし」なのである。すべてのデータはウェブ・ネットワーク上に開陳され、1秒単位でアクセスの動向がわかっていく。どの記事が読まれたか、どのページに離脱がおこったか、すべてはデータにのこる。そのデータの起伏こそコンテクスチュアルなのだ。
ということは、そうしたビッグデータから読者の動向が分析できるのに、旧世界の連中はこのことをめんどうくさがって、対処しようとはしなかったのだ。
旧世界から新世界への転換は、何をもたらすのか。めぼしい変容をまとめると、次のようになると佐々木は言う。
①紙からデジタルに変わったことで「コンテンツ+α」の時代になった。
②文系の人材と理系の人材とが手を組むようになってきた。
③ビッグデータを分析して活用する必要がある。
④作家の力よりも、個人のキャラを大いに活かすときが来ている。
⑤メディア会社は社内での競争が激しくなっていく。
⑥識者も読者もビジネスマンもみんなが書き手になりうる。
⑦編集とビジネスがどんどん融合していく。
佐々木は⑦の「編集とビジネスの融合」によって、これからはきっと「編集力を身につけたビジネスマン」が劇的にふえていくだろうと予想する。企業とメディアがコラボするブランドコンテンツの創出にも、オウンドメディアを運営する企業のコンサルティングにも、編集的ビジネス感覚が要請されていくだろうとも言う。
事態は明白なのだから、早々に対策に着手すべきなのである。どうするか。佐々木はひとまず、次の9つの「稼ぎ方」を試みるべきですよと忠告している。
①広告。ウェブサイトの主軸となる収益モデルで、バナー、テキスト、メルマガ、タイアップがあるが、新たなブランドコンテンツの手法が有力になりそうだ。
②有料課金。コンテンツの閲覧に対する課金が中心になっているが、やはりメーター制の導入をはかったほうがいい。
③イベント。セミナー開催ならリアルとオンラインの両方が必要だ。FTは年間200のイベントを開催して、合計1万7000人を掴んでいる。
④ゲーム。NYTのクロスワードパズルのように、オンラインのゲームをいくつか用意する。
⑤物販。「ほぼ日刊イトイ新聞」が2012年の「ほぼ日手帳」を46万冊売り上げたような例がある。
⑥データ販売。さまざまなデータをパッケージにまとめて、各機関やユーザーに販売する。USニューズ&ワールド・リポートなどの例。
⑦教育・学習。カリキュラムをオンラインで配信・学習する。大学や予備校もこの方法が可能だ。ワシントン・ポストは大学・予備校と組んでいる。
⑧マーケティング支援。ビッグデータを分析活用して、企業にコンサルティング・サービスをする。
⑨コミュニティ経営。エイベック研究所のように企業各社のネット・コミュニティを代行運営する。
これらのうち、意外に悪戦苦闘するのがネット広告だ。実際には現在の日本の広告収入は、テレビの49パーセントについで、ウェブ広告が24パーセントに達した。2012年はまずまずの8680億円。しかし、如何せん収益率が低い。ネット広告は単価があまりに安く、バナー広告のクリック率もどんどん下がっている。おまけに画面の小さいスマホではバナー広告を出せるスペースも限られる。
だからネットの広告取りなどに営業力を使えない。それならアドネットワークで広告枠のすべてを売ってもらったほうがいいということになるが、このしくみによるPV当たりの広告収入はせいぜい0.1〜0.3円なのである。
新手の広告ビジネスも、少しずつ登場してきている。たとえば、広告のリアルタイム入札だ。これは、広告の在庫と広告主をコンピュータ・プログラムによって自動的にマッチングさせるサービスをいう。株式市場でトレーダーが株を売り買いするように、広告の売買をしてもらおうというものだ。「アドエクスチェンジ」と言われている。

こうしたことが成立するには、「読者データ」を豊富にもっていること、その動向の分析に余念がないということ、的確な判断を次々にくだしていくことが、ゼッタイの条件になる。
ゼッタイの条件ではあるのだが、問題もある。配信業者や一部の広告主がウェブメディアに広告をだすときは、一緒にトラッキングクッキーと呼ばれるテキストデータを送っている。ユーザーを“追跡”してアクセス履歴を調べるためのツールで、これらがしだいに蓄積されてくると、ユーザーと広告をマッチングしやすくなっていく。たとえばユーザーがホンダ・アコードのサイトを見たという履歴がデータベースにのこっていると、そのユーザーが何かのニュースサイトを読んでいるとき、その記事の隣にホンダ・アコードの広告がふいに出てきて微笑むというふうになる。
これは配信業者や広告主にとっては効果的なしくみだが、メディア側はたまったものじゃない。どれだけ読者やユーザーをサイトに集めてきても、貴重な読者データを吸い取られてしまう。しかもメディア側は自社の読者データしかもっていないのに、配信業者や広告主は無数のメディアのデータを組み合わせることができる。まことに癪にさわることだけれど、グーグルとフェイスブックが強いのは、ここなのだ。
というようなアンビバレンツな問題もあるのだが、とはいえメディアが読者データから離れてしまったら、そこでいっさいの話はおしまいだ。なんとかメディアも工夫して、そのデータを第三者のデータと“組み合わせ編集”するべきなのである。さらには、メディアが広告主に「場所貸し」をするほどに強気になるべきである。
ところで、この数年間、日本の出版界はずうっと「本の世界も電子書籍に変わるんじゃないか」と戦々兢々としたままにある。ぼくもしょっちゅう、この恐怖の解消の仕方について意見を求められてきた。だが、ここで慌ててはダメである。この変化はアメリカと日本ではだいぶ異なるので、まずそのことを認識する必要がある。
日本の書籍はすぐに衰退するはずがない。アメリカは書店の数が少ない。国土は日本の25倍あるが、書店の数はせいぜい3分の2以下だ。それに、ペーパーバックはべつにして、アメリカの本はやたらに重い。それゆえアメリカでは、仕事帰りに駅のそばの書店にぶらりと立ち寄るというリーディング・ライフスタイルがとりにくく、そのぶんブッククラブやギフトブックがこれを補填していた。
そこに電子書籍が登場した。だからアメリカではキンドルが一気に広まった。けれども、こんなことをすぐに日本にあてはめる必要はない。もっと版元と書店が工夫するべきなのだ。
新聞や雑誌はどうかというと、こちらのほうは日本でもどんどんひどくなる。日米ほぼ同様の宿命を負っている。紙メディアは単立の書籍とちがって、あまりにウェブに似てきたからだ。佐々木によれば、いま日本で部数を伸ばしている雑誌は「週刊現代」(講談社)と「BAILA」(集英社)くらいのものだという(2013年現在)。
ただし、アメリカの雑誌が長らく定期購読によって維持されてきた(店売りはわずか20パーセント)のに対して、日本はフリーで買う客が圧倒的に多い。ということは、販売チャネルを独自に工夫していくべき余地がまだあるということである。それには書店や書店もどきのスペースに足をはこぶ文化をもっと拡張すべきなのだ。話題を別立てでつくるべきなのだ。いまさら言うのもなんだけれど、丸善ジュンク堂が松丸本舗を閉めてしまったこと、まことにもって最悪の判断だった。
本書は最終章に向かって、俄然、言及力が濃くなっていく。大前提になっているのは、「これからは編集の力がビジネスを開いていく」ということである。佐々木はさらに、次のようなことを勧める。
①メディア(媒体)を使い分けなさい(そしてマルチロールプレイヤーに、多面的になりなさい。そのほうが抜け道も見えてくる)。
②テクノロジーに対する造詣を深めなさい(技術に精通できなくとも、勘所がおさえられるように)。
③どこからでも「起業」がありうると思いなさい(ビジネスモデルの発見がほんとうの編集力である)。
④スーパーゼネラリストか、スーパースペシャリストか、どちらかを狙いなさい(得意分野は最低でも三分野)。
⑤地域と国家を越えなさい(アメリカ、アジア、ヨーロッパという外から日本を見るべきだ)。
⑥どんなときも孤独に耐える気持ちと力をもちなさい(これがリーダーシップの最大の条件だ)。
⑦教養を広くもちなさい(教養とは価値の遠近法に自在になることで、そのための読書とは他人のアタマでものを考えられるということだ)。
ずいぶんザツな案内をしたけれど、この男、けっこう「やれる」のだから、信用したほうがいい。ぼくはこの男のエディターシップがこれからの日本には絶必だと思っている。

⊕5年後、メディアは稼げるか⊕
∃ 著者:佐々木紀彦
∃ 編集:黒坂浩一
∃ 装幀:金子千鶴
∃ 発行者:山縣裕一郎
∃ 発行所:東洋経済新報社
∃ 印刷・製本:丸井工文社
⊂ 2013年8月1日 第1刷発行
⊗ 目次情報 ⊗
∈ 序章 メディア新世界で起きる7つの大変化
∈ 第1章 ウェブメディアをやってみて痛感したこと
∈ 第2章 米国製メディアは稼げているのか?
∈ 第3章 ウェブメディアでどう稼ぐか?
∈ 第4章 5年後に食えるメディア人、食えないメディア人
⊗ 著者略歴 ⊗
佐々木紀彦(ササキ・ノリヒコ)
1979年福岡県生まれ。慶応義塾大学総合政策学部卒業後、東洋経済新報社で自動車、IT業界を担当。2007年9月より休職し、スタンフォード大学大学院で修士号取得(国際政治経済専攻)。2009年7月より『週刊東洋経済』編集部に復帰し、『30歳の逆襲』『非ネイティブの英語術』『10年後に食える仕事、食えない仕事』『女性はなぜ出世しないのか』などの特集を手がける。2012年10月より現職。著書に『米国製エリートは本当にすごいのか?』『5年後、メディアは稼げるか』。