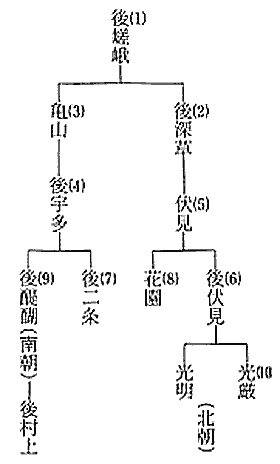父の先見


教育社 1980
[訳]松村武夫
北畠親房が『神皇正統記』を書いたのは、常陸の筑波山麓にたつ小田城の板の間でのことだった。同じころ吉田兼好が『徒然草』を書いていた。二人の執筆の姿勢はまことに対極的で、親房は日の本を背負い、兼好は草の庵を背負っていた。14世紀になってしばらくのこと、内乱の時代の只中である。
しかし、親房と兼好とがまったく逆の世界を見ているのかといえば、そんなことはない。二人とも同じ社会の流れを凝視した。同じ日本人の気の振舞を凝視した。二人とも日本の将来を憂い、二人とも無常をぞんぶんに知っていた。
ただ、二人には大きな違いもあった。親房は動きまわった人であり、兼好はじっとした人だった。親房は権力の側にいて、兼好は権門に背を向けた。
親房が『神皇正統記』を筑波くんだりで書いたというのも、このとき親房が小田城を拠点にして、南朝のための東国工作に従事していたからだ。そのころ南朝の勢力はそうとうに逼迫しつつあって、なんとか常陸や下野を傘下におさめようとしていたのだが、北朝は足利氏を軸に高師冬をさしむけて、南朝切り崩しにかかっていた。関東での戦端もしばしば開かれ、親房はその合い間をぬって『正統記』を書いたのである。
鎌倉南北朝時代の200年(150年+50年)は、日本を知るうえでわれわれが想像する以上に重要な時期になる。まことに異様な構造変化のおこった時代だった。
また、われわれはついつい「倒幕」(討幕)というと江戸の幕末だけを思ってしまうけれど、実は最初の倒幕運動は鎌倉末期にこそおこったのである。ただ、江戸幕末を勤皇佐幕とか公武合体というのに対して、この鎌倉幕末は「公武水火の世」というふうにいう。
そもそも源氏将軍の支配力がわずか三代で終わったことが、あまりに早すぎる挫折であった。すぐさま北条執権政治による得宗体制が引き継いで、幕府の体制は強化されるけれど、それで安定したかとおもうまもなく在地名主層が急成長し、社会構造が大きく変質していった。幕府はしきりに御家人を保護しようとしたにもかかわらず、御家人たちは所領を失い、多くが食えなくなりつつあった。
そこへ二度にわたる元朝モンゴル軍の襲来である。北条幕府はこれを機会に国土防衛政策を打ち出し、本所一円地を中心にそれぞれの兵糧徴収を試みるが、残った有力御家人は得宗政策とは対立しはじめる。
そういうなかで、突如として立ち上がってきたのが江戸幕末同様の京都の朝廷勢力なのである。後醍醐天皇を中心におこったこと、その最初の事件を正中の変というのだが、それこそが日本史上最初の倒幕運動の烽火であった。
つづいて元弘の変では、いったん隠岐に流された後醍醐が、名和長年を頼って伯耆の船上山に移ってみると、各地の武将が次々に起ち、そこへ足利尊氏・新田義貞らの有力層がこれに呼応することになった。これはさしずめ公武合体の先駆というものだった。こうなっては鎌倉幕府はあっけなく瓦解する。
このとき北畠親房は41歳になっていた。
翌年、後醍醐は建武と改元し、かつての院・摂政・関白をおかない天皇親政政治、いわゆる「建武の中興」を開始する。王政復古の断行である。
解決しなければならない問題が山積していた。とくに問題は論功行賞と土地にある。後醍醐政府はさっそく記録所、恩賞方、雑訴決断所、武者所などを次々に設置して、明治の維新政府さながらの処置にあたっていく。諸国には国司・守護をパラレルに置き、奥州には義良親王(のちの後村上天皇)と北畠顕家(親房の子)を、関東には成良親王と足利直義をそれぞれ派遣して、東国経営にあたらせもした。
あとは敗退した北条与党の連中以外の所領の安堵をどうするかということになるのだが、そこでしだいに現実社会との適合を見失った。とくに武家階層の不満を抑えるにはいたらない。後醍醐は理想を求めすぎたのである。準備も足りなかった。岩倉具視や西郷隆盛や大久保利通もいなかった。政治というもの、プラトンのイデアだけではやはり途中から進まなくなっていく。
新政権は行き詰まる。親房もこの新政権に参加したのだが、すぐに息子の顕家の後見として奥州に派遣されていた。
この弱体化した新政権を見て、すばやく反旗を翻したのが関東武士の足利尊氏である。1335年(建武2)、後醍醐政権はたった2年あまりで崩壊した。尊氏が最初にしたことは、光明天皇を擁立して京都に凱旋することで、それが1336年の8月だった。
これを見て後醍醐が怒る。11月には吉野に遁れて、ただちに皇位の正統(レジティマシー・第796夜参照)を主張し、ここに南北朝50年の互いに譲らぬ前代未聞の両統対立の時代が始まった。
ここまでが、親房の『神皇正統記』という書名に「正統」の二文字が入っている理由の背景になる。
南北朝の皇統対立がどうしておこったかということについて、少し付け加えておくが、実は天皇の血統については、日本はここまでの歴史ですっきり落ち着いたことはない。
継体天皇の就任をはじめ、兄弟ながら天智系と天武系の皇統が長らく別々に進行していたことなど、その血脈にはさまざまに複雑な輻湊関係がある。
それゆえ両統(大覚寺統・持明院統)迭立の気運も、後嵯峨天皇のあとに二人の兄弟皇子が即位したことにすでに始まっていた。兄の後深草天皇(持明院統)が即位し、ついで弟の亀山天皇(大覚寺統)が即位するのだが、亀山が後宇多天皇に譲位したときに、両派の対立が剥き出しになっていた。
かくていったんは、後宇多(大)→伏見(持)→後伏見(持)→後二条(大)というふうに交替が進んだ。けれども、これは単線的な交替による就任であって、複線的な両立平行交替まではいたっていない。しかもこの交替劇には公家貴族のほとんどが巻き込まれたとはいっても、まだ朝廷公家内の対立である。
しかしそこに、尊氏の光明擁立の挙動が出た。尊氏は朝廷とも公家ともまったく関係のない武家である。後二条のあとを継いだ後醍醐としては、ここで引き下がるわけにはいかなかったのだ。
二項対立としての南北朝が勃発し、それが長引くことになったについては、もうひとつ原因がある。
南北朝の対立は皇統からみれば両統の抗争なのだが、そこには武家勢力における主導権争いとトラタヌ(とらぬタヌキ)の目論みが絡まっていた。当時は乱世がまだ続いているなかで、のちに足利将軍による室町幕府が確立するというような見通しなど、誰も予想するだにできなかった状況である。武家たちも、ただただ必死に有利な情勢につこうとしていただけだった。
そのため武家勢力の一方が北朝につけば、他方は南朝についた。南北朝が長引いたのは、こうしてつねに南朝側にもくっつく勢力が絶えなかったからでもあった。
それでやっと親房のことになるが、親房の家は村上源氏の血を引いていた。親房は父の源師重が後宇多天皇出家に従って剃髪し、そのとき北畠の家督を継いだ。15歳である。
このとき親房は自分が大覚寺統に属することを強く意識する。親房の生涯にはずっと村上源氏と大覚寺統のシンボルを背負っているという矜持があった。
親房はそうとうの才能の持ち主でもあった。もともと北畠家そのものが「代々和漢の稽古をわざとして」というような家であったけれど、親房はそれだけでなく、学問・和歌・管弦・神仏・宋学のいずれにも通じ、のみならず記憶力が群を抜いていた。冒頭にもふれたように『神皇正統記』は陣中で書かれたもので、きっと参考書などほとんどなかったにちがいないにもかかわらず(簡潔な『皇統記』が一冊あっただけと本人は記している)、それなのに『神皇正統記』には夥しい知識が披瀝されている。記憶力が抜群だったとしかおもえない。
また親房は行く先々でかなり深い学習をしたふしがある。なかで最も有名なのは、宗良親王を奉じて伊勢に下ってこの方面の工作にあたったときに、外宮の禰宜の度会家行について徹底して度会神道の精髄を学びとったことである。
こうした親房が『神皇正統記』をなぜ陣中で急いで書いたのかというと、これは東国武士に南朝への参加を説得するための分厚い政治パンフレットだったのだ。かつては後村上天皇のために書いたとされていたのだが、いまでは関東の“童蒙”(かんぜない君主)、すなわち結城親朝の説得のために書いたというのが定説になっている。
けれどもその効果は出ずに、説得工作は失敗をする。しかもその直後に後醍醐の崩御を聞いた。親房は傷心のまま吉野まで帰ってくることになる。まだ十代の後村上天皇はさすがに親房の労をねぎらい、准大臣として迎えるのだが、親房は静かに黙考して、動かない人になっていた。つまり『神皇正統記』は後醍醐存命中にこそ流布されるべきレジティマシーのための一書パンフレットだったのである。
それゆえ、あそこまで書き尽くしたものなら、その後も書写され配布されてもよかったのに、親房はいっこうにこの一書に継続的な関心をもたくなっていた。一度手を入れただけである。
そこであえて言っておきたいのだが、こうした事情を看過して、親房の著作をいたずらに神国思想の吹聴のために議論するのは無理があるということだ。のちのち『神皇正統記』はさかんに大日本帝国の宣伝パンフレットのごとく利用されるのであるが、実は親房にはその用途は東国工作の失敗とともに終わっていたのだった。
このまま親房の最後まで見取ることにする。正平2年(1347)、楠木正行が河内で高師直の大軍とぶつかった。親房はここでふたたび動いて河内に赴いた。
けれども翌年には正行は四條畷で戦死、高師直は吉野にまで進んで行宮を焼き払うにいたる。後村上は大和の賀名生(あのう)に退き、親房を頼ったため、ここに親房の果たすべき役割が久々に大きなってきた。
歴史の舞台では、このあと南朝と北朝は尊氏と直義の対立と宥和の度重なる入れ替わりを反映して、めまぐるしいシーソーゲームを演じていくことになる。親房がそこで動いたことも、もはや有効なものとはならなくなっていた。政治的には過剰になったり臆病にもなっていた。なかで16年ぶりに京都に入ったことが、唯一の親房の宿願とも思想の実践ともいえるもので、このときばかりは胸中さぞかし、なにものかが漲ったのではないかとおもう。
が、そのあとまもなく親房は死ぬ。それもふたたび退却を余儀なくされての、賀名生あたりでの客死だったと伝えられている。62歳であった。
さて『神皇正統記』天地人であるが、これは神話的神代から後村上天皇までの事績を天皇中心に順番簡潔に述べたもので、要約すればただそれだけである。
ぼくなどは「天」では『古事記』の焼き直しかと思い、ついで欽明天皇にはじまる「地」は日本古代史のトレースかと思い、やっと鳥羽天皇からの「人」で、親房の意図が少し見えてきたかというのが、最初の印象だった。しかし、これはまだ20代のころの読書のことで、それ以前に頼山陽の『日本外史』を齧っていたのがかえってアダとなったふしがある。
あらためて日本について多少とも深く考えるようになってから読み直したときは、まったく別の感想をもちながら読めた。
いろいろ感想はあるが、第一には上記にも述べたように、北畠親房を歴史に生きた姿ととして捉らえながら読めた。
第二には、明治以降のナショナリストたちの『神皇正統記』の読み方を知ってのうえでこれを読むと、いかに八紘一宇型にこれを読むのがまちがっているかということが、よく見えた。
親房は良くも悪くもナショナリズムを把握していないし、それを日本を超えたウルトラナショナリズムにするような思想も、まったく持ち合わせていなかった。近代日本がうっかり北畠親房を読み違えたことは、かなり決定的な過誤であったろう。
第三に、『神皇正統記』は文化論としても読めた。文章が簡潔であることも手伝っているが、どこか花伝書の趣きがある。むしろ世阿弥がこれを読んで花伝書を綴ったのではないかと思わせた。
それに関連して気がついたことは、おそらく日本の文化論はときどきこのように、神話を説き起こし、天皇の聖断と失政を問い、神仏の加護に配慮しているうちに、突如として新たな構想に達するのではないかということだ。『正統記』はそのような文脈的な「たどり」のすえに、新たな日本の創発の日を願う「方法の提示」であったようにもおもう。
第四に、『神皇正統記』はむろん天皇の正統を議論するためのものであったわけではあるが、同時に初めて神道の立場を入れながら天皇を論じた最初の試みでもあったということである。
親房の皇統正統の証しは三種の神器にあった。それゆえ、神器をもたないものには「偽主」の烙印を押している。しかしそれだけで帝王としての正統が完熟しているかといえば、親房はそうは考えなかった。たとえば後醍醐天皇にはその政治に対して批判した。親房には摂関政治のほうがよかったと考えていた傾向もあったのだ。
では、そんな親房がわざわざ“神皇正統”を執拗に持ち出したのはなぜだったかといえば、ひとつはすでに述べたように東国の説得のためであったのだが、もうひとつは日本の皇統の奥にひそむ「何がしか」ということを、慌ただしい「公武水火の世」のなかで考えたかった。それが神道とは何かという問題だったのである。
それを親房は伊勢の度会家行から学んだ度会神道(伊勢神道)に求め、さらに独自に外宮信仰の特色にふれようとした。残念ながら『神皇正統記』ではその神道思想は開花にまではいたっていないけれど、この神道に着目した親房を考えることが、今後は日本の歴史思想の問題を解くうえでのひとつの課題になってくるのではないかとおもわれた。
第五に、いったいわれわれは『神皇正統記』のような著作を、これからどんなふうに書けばいいのだろうか、もし書き直すとすればどのように書けばいいのかという気分をもちながら読んだことが、いまは思い出される。
おそらく、いまぼくが述べたような感想を、近現代史に立つわれわれは正直に問題にしてこなかったのではないかとおもう。われわれはどこかで『神皇正統記』の余韻のすべてを隠している者ではあるまいかということだ。
この最後の感想については、ぼくのなかで少しずつながら深いものになっているのだが、「千夜千冊」においてもすでに、プラトン『国家』(第799夜)からミラン・クンデラ『存在の耐えられない軽さ』(第360夜)に及んで、また、猪野健治の『ヤクザと日本人』(第152夜)、滝沢誠『権藤成卿』(第93夜)、安彦良和の『虹色のトロツキー』(第430夜)として、さらには高取正男『神道の成立』(第409夜)、海津一朗『神風と悪党の世紀』(第109夜)、黒田俊雄の『王法と仏法』(第777夜)などをめぐって、そのつど議論の端緒にふれてきたので、ここではくりかえさないことにする。