父の先見


フェミニズムとアイデンティティの攪乱
青土社 1999
Judith Butler
Gender Trouble 1990
[訳]竹村和子
編集:津田新吉
装幀:高麗隆彦
高校時代にダイヘンがあった。ふーん、その手があったのかと思った。ダイヘンは「代返」である。授業の冒頭、担当教師が名簿の名前を次々に呼び上げて出欠をとるのだが、本人の出席を装うために欠席者に代わって「はーい」と返事をしてみせる。これが代返だ。大学になると、一人で何人ものアブセンスをプレゼンスに変える代返のセミプロがいた。
千夜千冊を書いていると、ときどき奇妙な「代返」をしているような感覚に陥る。千夜千冊はできるかぎり著者の意図にどう乗れるかを自分に課しながら書いてきた。そういうことをしていると、著者の代弁をしているのか、不在の著者の偽装をしているのか、あるいは不足を補っているのか、一緒にどこか遠くへ行こうとしているのか、書いているうちにいろいろなモードが混ざっていくのだが、これが「複合代返」っぽいのである。
千夜千冊はたんなる書評ではなく、また批評(批判)をするというのでもなく、その書物や著者に出会って自分がいくつもの仮想状態の織り目をくぐることをできるだけ重視しているので、この代返的な行為はある意味では必須作業であった。ぼくなりの編集的プレゼンスもそこで試される。
ところが代返がなかなか利かない相手が稀にいる。当人がすでにプレゼンスとアブセンスの検討を思想的に済ましているような、そんな用意周到な状態にある相手だ。ジュディス・バトラーがその代表的な一人だった。試しに次の文章を読んでいただきたい。
‥構造主義には「法」を単数とみなす傾向がある。レヴィ=ストロース(317夜)の影響だ。『親族の基本構造』では、親族関係を強化すると同時に差異化する役目を担う交換の対象は、女である。女は結婚という制度を通じて、父系的な氏族から別の父系的な氏族へと贈与される。
‥ここには交易をスムーズにする機能的な目的もあるが、この贈与を通して差異化される各氏族の内的結束を強めるという象徴的で儀礼的な目的もある。花嫁は、男によって構成される集団の関係項として嫁ぐ。花嫁はアイデンティティ不在の場所となることによって男のアイデンティティを反映する。
‥レヴィ=ストロースにとっては、男性的な文化アイデンティティは父系氏族のあいだの差異化という目にみえる行為をつうじて確立されると解釈されるのだろうが、すでにイリガライ(1127夜)が指摘したように、この男根ロゴス中心主義による機構が依拠しているのは、表にはあらわれない否認された差延の機構なのだ。父系氏族関係の基礎にあるものは、抑圧されたホモソーシャルな欲望なのである。
‥「象徴的な思考が出現するには、女が言葉と同じように交換される事物となることが必要なはずだった」というレヴィ=ストロースの悪名高い主張は、この文化人類学者が現在から過去をみるという無色透明な観察者の立場に立って想定されただけの文化の普遍性から導き出されたものにすぎない。ラカンがレヴィ=ストロースをとりこむときに焦点としたことも、文化を再生産するときにはたらく近親姦の禁止と族外婚の規則だった。
これはバトラーの主著『ジェンダー・トラブル』第2章「禁止、精神分析、異性愛のマトリクスの生産」の冒頭節「構造主義の危うい交換」のごく一部を、ぼくがひとまず編集要約してみたものだ。
読んでもらって感じられたと思うが、おもしろい代返にはなっていない。すでにバトラーが構造主義からポスト構造主義にかけての代返をいくつもの織り目をもってなしとげてしまっているからだ。
バトラーを代返しにくい理由は、それだけではなかった。こちらのほうがずっと重要な理由になるのだが、バトラーがフェミニズムとジェンダーをめぐる社会スクラムを自身で突破して、その突破のプロセスでフェミニズムとジェンダーをめぐるトップレベルの議論をなぎ倒し、それで勝ち誇るというのではなく、そのため生じるだろう軋轢の残滓を、バトラー自身のアイデンティティを語るうえでのトラブルにしてみせているからである。
『ジェンダー・トラブル』というタイトルの「トラブル」とは、そういう意味だ。これはおそらく、バトラーがレズビアンとしての自分の存在の語り口をあえて「クィア」(queer)にもちこんでいると同時に、LGBTQをめぐる議論のアリバイをLGBTQ+の「+」にまでぎりぎりに押し切っているせいでもあった。L(レズビアン)でありながらLにとどまっていないのだ。
トラブルを辞さないというより、自身のアイデンティティはもちろん、あなたがたもトラブルをもってしか語れませんよということを迫るのだ。
『ジェンダー・トラブル』の第2章はこのあと、「ラカン、リヴィエール、仮装の戦略」「フロイトおよびジェンダーのメランコリー」「ジェンダーの複合性、同一化の限界」「権力としての禁止の再考」というふうに進む。
レヴィ=ストロースの短慮が告発されているだけでなく、ラカン(911夜)もフロイト(895夜)もちょいちょい手玉に取っていく。第3章ではクリステヴァ(1028夜)も俎上にのせる。
もっとも、ポスト構造主義に対する短慮の攻め方や手玉の取り方は、必ずしもうまくない。英語圏で「ジュディスの悪文」と言われてきたような、パイ捏ねめいた書きっぷりのクセがある。ぼくはポスト構造主義に加担しすぎて書いているとも思うのだが、これはフーコー(545夜)とデリダに本気で加担したことがフレンチセオリー(ポスト構造主義フランス派)全体の検討に及びすぎたせいだろう。
なぜバトラーは代返を許さないのか。「女というカテゴリー」を安易につかってきた歴代数々の言説を問い上げ、フェミニズムが陥った狭隘な思想状況を問題にするときの、その自分の立場そのものを安全なところにおかないようにしたからだ。バトラーはLのようだが、その言説はLGBTQ+の「Q」(クィア)を深掘りした「+」(プラス)に向かっているからだ。これでは誰もバトラーの代返はできない。そんなことをすると、当人たちのプレゼンスとアブセンスがどんどん嘘くさくなっていく。
本書は、バトラーが誰にも勝手な代返をさせない存在の根拠を提示した一書だったのである。レジーナ・マーラーが、『ジェンダー・トラブル』を「ジェンダー学の最高の入門書」と称え、「大学のカフェではこれしか読むな」と言ったというのも頷ける。

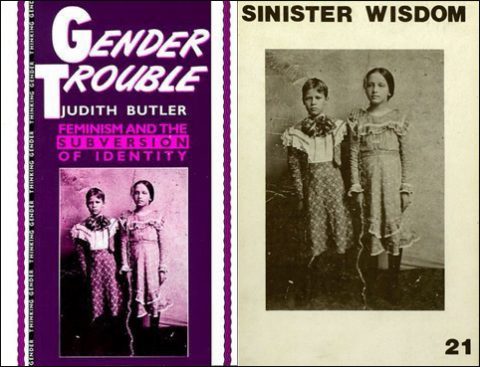
ジュディス・バトラーのことは本書を読むまでほとんど知らなかった。その後、いくつかの著書や論文を読むうちにその生い立ちや生き方も少しは知るようになったのだが、そのたびに関心が募った。
少女時代のジュディスは生家近くのシナゴーグで、ラビが導く言い分に親しんでいたようで、うっすらとではあろうが、スピノザ神学がもたらす魅力についてもそのとき知ったらしい。ユダヤ教改革派の熱心な信者であることは、その後もずうっと続いているようだ。
ベニントン・カレッジ、イェール大学ではスピノザ、カント、ドイツ観念哲学を専攻し、途中フルブライト留学によってドイツに滞在したおりに、ハイデルベルク大学でガダマーの講義を受けている。かなり難解なコースを選んだものである。
けれども一方、在学中からフェミニズムをめぐる言説、とくにポスト構造主義のフェミニズムを「わかったふり」をして扱う言説に真っ向から疑問を向けていた。そこには自身がレズビアンであることが如実に投影していた。いつから、どんなレズビアンであったのかはわからない。
博士論文は『欲望の主体:ヘーゲルと20世紀フランスにおけるポスト・ヘーゲル主義』にまとまった。なんともガチガチな主題を扱ったものだ。1987年にプリンストン高等研究所に入ったのちにジョージ・ワシントン大学の哲学准教授になったころ、『ジェンダー・トラブル』を書いた。
それからはジョンズ・ホプキンズ大学をへてカリフォルニア大学バークレーだ。いまでもバークレーで教えているのではないかと思う。ご覧の通り、アカデミシャンとしてはピカピカのキャリアであるが、そのアカデミックな鎧が自分の身を語るにはなんの力ももっていないばかりか、ジェンダーにまつわるどんな思想の鎧もジュディス自身の「性」(sex)にまつわる説明になりえないことを感じて、デビュー著書に『ジェンダー・トラブル』という穿ったタイトルを選んだにちがいない。自分のプレゼンスとアブセンスのアリバイ議論を勝負無用の「トラブル」に持ち込む方法をもって、自身がかかえる存在の問題の説明に挑むことにしたわけだ。
このことはサブタイトルに「フェミニズムとアイデンティティの攪乱」というフレーズを付したことにも、端的にあらわれている。
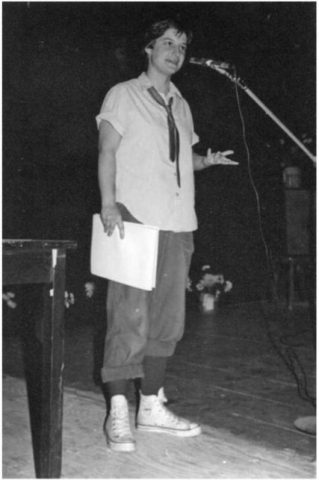
あらためて言うまでもなく、シモーヌ・ド・ボーヴォワールが1949年に『第二の性』(新潮文庫・全5冊)を問うて、「ひとは女に生まれない、女になる」と書いたことは、時代を画する乾坤一擲だった。これで、ジェンダーは構築されるものか、もしくは可変的な自由意志で入手できるかもしれないものとなった。
この乾坤の装置をめぐって、多くの共感とともにいくつかの疑問がフェミニズム思想として提出されてきた。ボーヴォワールの議論だけでは、なぜ男性的なものが身体をもたない普遍性を騙り、女性的なものは否認されてもかまわないような肉体性を付与されていくのか、明確にはならないからだ。そこで、こうした見方を乗り越えるべく議論がさまざま提出されたわけである。
ベティ・フリーダンの『新しい女性の創造』(1963・大和書房)の刊行を合図にして、70年代になるとケイト・ミレットの『性の政治学』(1970・自由国民社)、シーラ・ローバトムの『女の意識・男の世界』(1973・ドメス出版)、ジュリエット・ミッチェルの『精神分析と女の解放』(1974・合同出版)、エレーヌ・シクスーの『メデューサの笑い』(1993・紀伊国屋書店)、リュス・イリガライの『ひとつではない女の性』(1977・勁草書房)などが、連打された。
これらを通しておおざっぱには、第1波はリベラル・フェミニズムの議論を生んで、女性の権利の保護や女性差別の改善や撤廃を訴えた。第2波はウーマンリブの運動である。ウーマニズムとも言われ、いくつもの波頭が立ち上がった。アリス・ウォーカーは「フェミニストはラベンダー、ウーマニストはパープル」と言った。ブラック・フェミニズムも台頭した。第3波ではインターセクショナリティや多様性が主張された。キンバリー・クレンショーが黒人の女性同性愛に対する差別をとりあげ、レベッカ・ウォーカーはこのままではセクシュアル・ハラスメントがなくなりっこないと訴えた。
こうしたなか、リュス・イリガライの見方がとくに戦略的だった。イリガライの言い分は、われわれは女性器をもつ女性にしか担えない「女性的なもの」(féminin)を放てばいいじゃないかというものだ。
バトラーはボーヴォワールとともにイリガライの言説を点検し、ジェンダー概念を根本的に問いなおした。一言でいえば、われわれがセックス化され(性別を受け)、ジェンダー化され(男女の文化性を付与され)、人種化されたアイデンティティをもつようになった理由を、根本的に問いなおしたのだ。

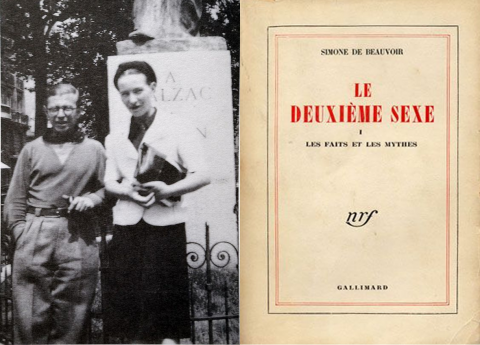


問いなおしの作業は容易ではなさそうだった。問いなおすにあたっては、すでに多くの男性的ロジックによって確立されてきた「主体」「自己」「言語」「精神」「身体」「性」「欲望」「社会」「結婚」といった概念とその影響範囲でぬくぬくと棲息している思考癖の数々を、できるかぎり洗いなおす必要があった。
この男根ロゴスっぽい思考癖は一夫一婦制を保持し、同性愛を差別してきたものだ。ジェンダーやセックスの通念を頑なに守りぬいているものだ。ゲイやレズビアンを異常扱いしてきたものだ。それが社会哲学的な「言語」「自己」「身体」の隅々にまでこびりついている。
だからできれば一新したいけれども、なかなかそうはいかない。これらは文明や社会によって裏打ちされてきたからだ。根こそぎ洗い落とせば、まるごと底が抜ける。ここは脱構築するしかないと思われた。
そこで、その作業にあたってはポスト構造主義がもたらした思想の意匠を借りたのだが、さきほども示唆しておいたように、大著『性の歴史』(新潮社・全4冊)を綴りつづけたゲイの思想家フーコーへの深い共感はべつとして、そんなことを細部にわたってしないでもよかったとも思う。
それはともかく、バトラーはボーヴォワール、イリガライ、ポスト構造主義を次々に脱構築するうちに、新たなジェンダー思想の新境地をもつに至ったのである。それは「パフォーマティヴィティ」(performtivity)によって性の行為遂行性を前面化するという試みだった。

日常言語学の研究者ジョン・オースティンは『言語と行為』(大修館書店)を著して、言語行為論(スピーチアクト理論)を提案していた。言語は状況の言明や事態の記述のために発達しただけではなく、依頼や警告や拒否を告げる「行為の遂行」をもたらそうとするものとしてパフォーマティヴに発達したという考え方をまとめたものだ。
たとえば「早くおいでよ」「明日は用事があるんで」「それ、取ってくれますか」といった言葉は、その場の状況を説明しているとともに、その言葉によってなんらかの行為が生じることを示している。「ここに第15回高校ラグビー全国大会の開会を宣言します」という言明は、「宣言します」と言うこと自体が「宣言する」という行為そのものなのである。
かねてジェンダーが言語や言説で組み上がってきたと実感していたバトラーは(いいかえれば、文化的な書き込みに先立つ「自然な身体」は存在しないとみなしてきたバトラーは)、このオースティンの見方をジェンダー思想にあてはめ(デリダも『言語と行為』を脱構築する試みをしていた)、ジェンダーは言語そのものの呪縛から脱出して、むしろパフォーマティヴィティ(行為遂行性)として認識されるものになるべきだとみなした。
このアイディアは、本書の第1章に初めて出てくる。「ジェンダーは結局、パフォーマティヴなものである。つまり、そういうふうに語られたアイデンティティを構築していくものである。この意味でジェンダーは“おこなうこと”であるが、しかしその行為は“行為の前”に存在すると考えられる主体によっておこなわれるものではない」というふうに。
わかりにくい説明だったが(翻訳もややわかりにくいが)、あらかじめ“行為の前”に用意をされているのではないものが、行為遂行に向かってあらわれることがあるもので、そこにはジェンダーの本質に近いあらわれ方が出ているというのである。ジェンダーがパフォーマティヴに議論されるべきだというのは、ここだった。
バトラーはジェンダーやセックスの議論は、「言語」や「身体」や「自己」についての従来の男性的な扱い方を離れて(この「離れて」のために脱構築のプロセスを踏んだ)、自分がパフォーマティヴになっていくときをめがけて、持ち出すべきだろうと決断したのだった。

バトラーはオースティンから言語にひそむ「行為遂行性」という視点を借りながら、「ジェンダーを行為として語る」という可能性を示唆し、それをもって「ジェンダーとセックスの非自然化」を企てたのである。またそれによって、ジェンダーが長らく「セックスの文化的解釈」のほうへ押しやられてきたことを砕きたかったのである。
この試みは成功したのだろうか。半分半分というところだ。本書からだけではこのことは見えてはこない。議論は続く著作『問題=物質となる身体』(1993・以文社)、『触発する言葉:言語・権力・行為体』(1997・岩波書店)、さらには『自分自身を説明すること』(2005・月曜社)などに少しずつ継承されていったのだ。
これらを通して、バトラーはケリをつけた。とくにジェンダーとセックスが何かを奪われたものになっていることに、ケリをつけた。もしくはたいていのジェンダーとセックスは誰かによって模倣されたものが投影したものであるかもしれないことにケリをつけた。加えて、そうしたジェンダーやセックスは二重の分断を受けたアレゴリーになっているのではないかということを示唆した。このアレゴリーはLGBTQ+の「Q」と「+」のところで“おこなわれる”ように仕向けて、バトラーが示唆したものだった。
なぜ「Q」や「+」にアレゴリカルなことがおこるのか、ここが残されたテーマだが、それを理解するにはクィア・スタディーズがどういうものであるのかを覗いてみる必要がある。
TOPページデザイン:富山庄太郎
図版構成:寺平賢司・上杉公志・梅澤光由・大泉健太郎
・桑田惇平・中尾行宏

⊕『ジェンダー・トラブルーフェミニズムとアイデンティティの攪乱』⊕
∈ 著者:ジュディス・バトラー
∈ 訳者:竹村和子
∈ 編集:津田新吉
∈ 装幀:高麗隆彦
∈ 発行者:清水一人
∈ 発行所:株式会社青土社
∈ 印刷所:三協美術印刷、方英社
∈ 製本所:小泉製本
∈ 発行:1999年
⊕ 目次情報 ⊕
∈∈ 序文
∈ 第1章 〈セックス/ジェンダー/欲望〉の主体
∈∈ 一 フェミニズムの主体としての「女」
∈∈ 二 〈セックス/ジェンダー/欲望〉の強制的秩序
∈∈ 三 ジェンダー――現代の論争の不毛な循環
∈∈ 四 二元体、一元体、そのかなたの理論化
∈∈ 五 アイデンティティ、セックス、実体の形而上学
∈∈ 六 言語、権力、置換戦略
∈ 第2章 禁止、精神分析、異性愛のマトリクスの生涯
∈∈ 一 構造主義の危うい交換
∈∈ 二 ラカン、リヴィエール、仮装の戦略
∈∈ 三 フロイトおよびジェンダーのメランコリー
∈∈ 四 ジェンダーの複合性、同一化の限界
∈∈ 五 権力としての禁止の再考
∈ 第3章 撹乱的な身体行為
∈∈ 一 ジュリア・クリステヴァの身体の政治
∈∈ 二 フーコー、エルキュリーヌ、セックスの不連続の政治
∈∈ 三 モニク・ウィティッグ――身体の解体と架空のセックス
∈∈ 四 身体への書き込み、パフォーマティヴな攪乱
∈ 結論――パロディから政治へ
∈∈ 原註
∈∈ 訳者解説
∈∈ 索引
⊕ 著者略歴 ⊕
ジュディス・バトラー(Judith Butler)
1956年、アメリカ生まれ。政治哲学・倫理学から現象学まで幅広い分野で活動するが、とくに現代フェミニズム思想を代表する一人とみなされている。カリフォルニア大学バークレー校での修辞学/比較文学の教授。哲学専攻。主な著書に『欲望の主体』(堀之内出版)、『問題=物質となる身体』(以文社)、『権力の心的な生』(月曜社)、『触発する言葉』(岩波書店)他。
⊕ 訳者略歴 ⊕
竹村 和子(たけむら・かずこ)
1954年生まれ。日本の英文学者。お茶の水女子大学教育学部卒業。お茶の水女子大学大学院および筑波大学大学院修了。専門は英米文学、批評理論、フェミニズム思想。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科教授(刊行時)。主著に『フェミニズム』『愛について - アイデンティティと欲望の政治学』(岩波書店)、『彼女は何を視ているのか - 映像表象と欲望の深層』(作品社)、訳書に『女性・ネイティヴ・他者 - ポストコロニアリズムとフェミニズム』(トリン・T・ミンハ、岩波書店)他。