父の先見


天に思いを馳せる支配者たち
三田出版会・出版文化社 1998
E.C.Krupp
Skywatchers, Shamans & Kings―Astronomy and the Archeology of Power 1997
[訳]田川憲二郎
編集:林美樹
装幀:福田和雄
最近、アメリカで「nones」(ノンズ)という言葉が動き出している。ミレニアルズ層を中心にバズっているようだが、その多くが無神論者や不可知論者たちで、その数は全米のカトリック人口に迫っているらしい。2021年には宗教社会学者ライアン・バージの“The Nones”という本が話題になった。
かつて教会主義者のあいだではnonesはやや侮蔑をこめてノーネスと発音されていた。それがいまではノンズだ。「ない派」「なし派」とでも訳せるか。かれらは教会には行かないのに、スピリチュアルにはぞっこんで、瞑想・ヒーリング・ヨガ・セルフケア・占い・魔法・メンタリストが大好きだ。シャーマンになりたがっている動向もある。
そういう女性たちのあいだでは、仕事の帰り際に「ねえ、これからシャーマンしない?」が合言葉になっているのだという。隠れシャーマンになることが流行しているらしい。
ほんとにそんなふうなのかと思ったが、ぼくが読んだ「Style Rituals」(スタイル・リチュアルズ)のレポートでは、その発信者は元ファッション・スタイリストが開いたシャーマン・スクールだった。ニューヨークのキャリアウーマンや東海岸のママたちが押しかけて、シャーマンめくことを愉んでいた。
何? シャーマン・スクール? いったい何がおこっているのか。こうした気運が最近のスピリチュアリズムに統合しつつあるというのなら、よくある話でつまらない。最近のスピリチュアリズムはそのルーツである近代英国の心霊主義運動など振り返ろうとしないし、歴史的な占星術や錬金術の意味も継承していないだけでなく、カウンターカルチャーにもなっていない。「なんとなく癒し系」なのだ。
けれども21世紀初頭のコロナ・エピデミックな世の中が女性たちを「今夜のシャーマン」に駆り立てている理由は、回りまわってわかる気がする。
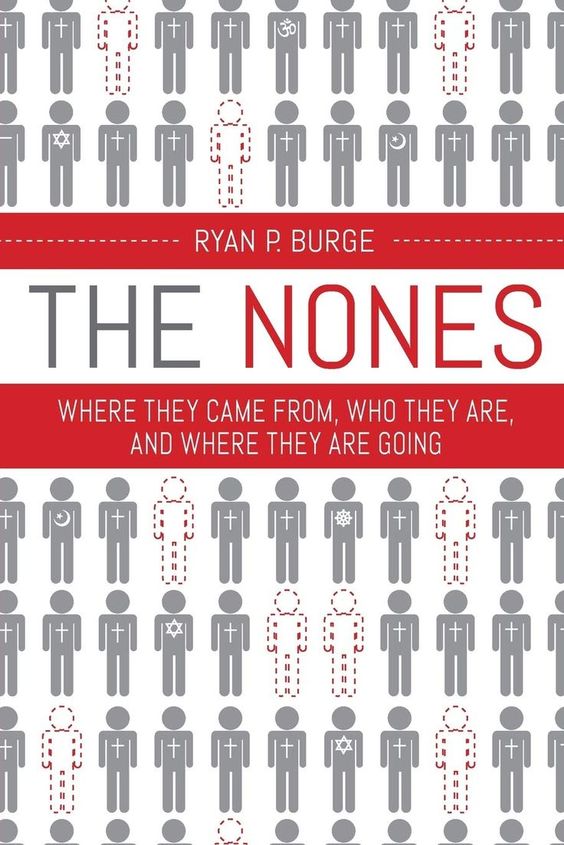
「今こそ訊こうじゃないか。シャーマンに精霊を呼んでもらって道を尋ねようじゃないか。モンゴルの大地が大丈夫かどうか、借金や抑圧がなくなるかどうか、訊ねようじゃないか。泥棒は誰なのか、尋ねようじゃないか」。
モンゴルのヒップホッブグループ「Ice Top」(アイス・トップ)の《Am Asuuya》(2011)のリリック&ヴァースの一部だ。目の前のシャーマンに迫るような荒々しいヒップホッブで、こんな歌詞をシャウトするのは日本のラッパーにはいない。
さすがモンゴルのシャーマニック・ラップと言いたいところだが、ラッパーがシャーマンだというのではない。シャーマンたちに尋ねてみようじゃないかというのだ。なぜ、昨今の世の中の実情をシャーマンに尋ねるのか。どこにシャーマンがいるというのか。理由がある。
実はいま、モンゴルにはシャーマンが激増している。人口約320万人のうちのなんと2~3万人が自称シャーマンだという。オンゴドとよばれる精霊を憑依させて何かを告げるシャーマンが多いと聞いた。
かつてのモンゴルのシャーマンはダルハドやブリヤート(バイカル湖周辺)などのマイノリティに限られていた。それが最近は首都ウランバートルに次々に登場している。それも貧困層の多いゲル地区だ。親分シャーマンもいるし、なんちゃってシャーマンもいる。きっとそうなんだろうが、とはいえ現代社会の告発をシャーマンにまで戻って世を憂えたり、それをラップするというところがなんともイミシンである。深い背景もありそうだ。島村一平や関根康正が「ストリート人類学」としてさまざま報告しているので、覗いてみられるといい。


誰にもそこそこ思い当たることかもしれないが、若いころのぼくの周辺にはシャーマンっぽい男たちや女たちがいつもいた。むろんシャーマンではない。擬似シャーマンないしは擬態シャーマンとでも言う雰囲気で、その多くは対抗文化的で、反宗教的ですらあった。
誰某(だれそれ)がこれこれだとは言えないが、次のような顔ぶれだ。ジャズメン、ヒッピー、「遊」の愛読者、トランスジェンダー、土方巽(976夜)や唐十郎や寺山修司(413夜)の取り巻き、チャネラー、新興宗教の末端信者、同時通訳者たち(多くは女性)、コンテンポラリー・アーティスト、田中泯の踊りのファン、電子派、シュタイナー主義者。
タルホ(879夜)やシブサワ(968夜)好き、DJ、武道家、現代思潮社の本の愛読者、ロックンローラー、マンガ家、ドラッグ派、感性アナーキスト、変わった僧侶たち、新左翼、神秘学おたく、トランス・パーソナル志向、デザイナー、陰陽タオイスト、若い投資家、パンク・ミュージシャン、写真家、タントラ主義者などなど……。
かれらを「シャーマンっぽい」とか「擬似シャーマン」と見立てるのがいいかどうかはわからないが(むろん当てずっぽすぎるけれど)、とはいえ「おかしな連中」とも「あやしい一族」とも片付けられないので、当時はお互いに70年代シャーマンあるいは浪漫派シャーマンとみなしていた。「遊」では「魔術的リアリスト」と名付けたこともあった。
かれらの言動は、そのファッションを含めて現実の日々のなかでは「逸脱の象徴」で、ひどくセンシティブで、かなり目立ちもした。60年代末から70年代全般にかけて、新宿のマット・グロッソや松原のキッド・アイラック・ホールに行くと、そんな連中がいつも屯(たむろ)していた。ツバキハウスにはアン・ルイス、戸川純、坂本龍一、町田町蔵がいた。クラブ・シーンの3割くらいがその手の片寄りをもっていただろうか。
夜分に紫煙がけぶるそんな界隈を徘徊すると、村八分の柴田和志・山口富士夫、羅生門のクニ河内、ザ・リードのアラン・メリル、たいてい六本木のキャンティ(1659夜)にいた加藤和彦・かまやつひろし、DJの大貫憲章、デザイナーの藤原ヒロシ、RCサクセションの忌野清志郎、ハルオフォンの近田春夫らがちらちら出入りしていた。みんなぼくより若かった。いまは遠い遠い日々となった4〜50年前の話だ。

そんなこんなで(何が「そんなこんな」かはまことに無責任で漠然としているが)、ぼくは若いころからシャーマン(shaman)やシャーマニズム(shamanism)にひとかどの関心をもってきた。
街のシャーマンを観察しようというのではない。むしろ原始古代のシャーマニズム、あるいは地域的なシャーマニズムを知りたくなった。たとえば沖縄のユタとノロ、盲目の瞽女(ごぜ)、ヤマトトモモソヒメ、各地のメディシンマンが気になった。
そこでミルチア・エリアーデ(1002夜)の大著『シャーマニズム』(冬樹社→ちくま学芸文庫)をはじめ、ウノ・ハルヴァの『シャマニズム』(三省堂)、ヨアン・ルイスの『エクスタシーの人類学』(法政大学出版局)、カーメン・ブラッカーの『あずさ弓』(岩波現代選書)などを読み、佐々木宏幹の『シャーマニズムの世界』(弘文堂→講談社学術文庫)で、シャーマンにも脱魂型、予言者型、霊媒型、精霊制御型、見者型などがあることを知った、
ただ、これらの多くはたいてい「憑依」(独Besessenheit 英possession)やエクスタシー(ecstasy 恍惚)やヒプノティズム(hypbotism 催眠現象)を前提にしているシャーマニズム論で、宇宙観や世界観、シンボリック・ストラクチャーとしての建物や造作物、選択した神々のレキジット・バラエティ(少数多様性)についてはあまり着目していない。
正直にいうと、知り合いは多いのにぼくはヒーラーになりたがる連中にはあまり惹かれない。それよりも、かつての歴史的シャーマン文化がどんなシンポリズムや儀式や創作行為や建造物に向かったのか、そちらのほうにずっと注目してきた。なぜ原始古代社会はシャーマンを必要としたかということだ。けれども、そういう視点の本があまりなかったのである。それが本書に出会って喉を潤した。
本書の著者はれっきとした天文学者で、長らくロサンンゼルスのグリフィス天文台台長だった研究者である。
当然、天体の本も書いている。ぼくは親戚の子にクラップ天文台長の『空のひしゃく北斗七星』(岩波書店)を贈ったことがある。この子はその後結婚してドイツに留学し、テューリンゲン大学で細胞生物学を学び、いまは東北大学でタンパク質研究室を仕切っている。
グリフィス天文台はわが中学時代からの憧れの巨大天文台で、誠文堂新光社の「天文ガイド」や地人書館の「天文と気象」アメリカの「スカテレ」(SKY & TELESCOPE)に載っている天文台の写真を見るたびにどぎまぎし、そのつど溜息をついていた。
そういう著者が天体つながりとはいえ、世界の天空信仰のアーキタイプに興味をもった。この天文学者がどんなきっかけでシャーマニズムに没頭したのかは知らないが、まるで全天を天体望遠鏡がくまなくサーベイしているかのように、原始・古代・未開の人間たちに汲み取られた地球各所の「天空と王とシャーマンの痕跡」を精査して、本書に仕上げた。
邦訳は2段組で500ページ近い。そのまるごとが古代における天空信仰とその造形感覚や、今日にのこる未開部族のシャーマニックなリーダーシップの話で埋まっている。いささか雑然とはしているが、まことに夥しい情報が網羅されていた。
が、ぼくはこの本のことをほったらかしにしていた。千夜千冊しようとも思わなかった。それが数年前に和泉佳奈子とともに六本木の国立新美術館で《イメージの力》展を見ているうちに、懐かしく蘇ったのである。《イメージの力》は大阪の民博(国立民族学博物館)のコレクションを再構成したもので、格別に新しいものが展示されたのではなかったのだが、あらためて組み合わせ展示の数々を見ていると、なんとも深い堪能がやってきて、ああ、これは『天と王とシャーマン』を書かなくちゃと思わせたのだ。それからまた数年がたった。千夜千冊はいつもいつも、こんなていたらく、なんとも不如意なことである。

以下、本書で気になったところ、ぜひとも知っておいてほしいところを少しだけ紹介することにするが、その前にいくつかの定説を示しておく。
シャーマンの語源はツングース系の「シャマン」(知る人)に由来する。呪術師・巫師をあらわした。サンスクリット語の「シャマン」は入信者という意味で「沙門」と訳されるが、こちらはシャーマンの語源ではない。
伝統的なシャーマンの多くに共通する特徴は、トランス(trance 恍惚・忘我)、エクスタシー(ecstacy 脱魂)、ポゼッション(possession 憑依・憑霊)、アルタード・ステート(altered state of consciousness:ASC 変性意識状態)を身近かにしていたということにある。日本では巫女(みこ)、巫覡(ふげき)、口寄せ、イタコなどと呼ばれる。男のばあいも女のばあいもある。ノロとユタは琉球王国時代からのシャーマン(神女)だ。
一部のシャーマンはナチュラル・ヒーラーで、巫医だった。つまりメディシンマン(呪医)だった。悪霊と闘い、異界を出入りし、疫病を退散させる。そんなふうに言うとそれって霊媒(medium,spirit medium)と同じだろうと思うかもしれないが、そうとはかぎらない。霊媒はシャーマンであろうが、シャーマンが霊媒であるとはかぎらない。
シャーマニズムはしばしばアニミズム(animism)とともに語られることがあるが、多くのアニミズムはシャーマンを介さないし、ほとんど組織もつくらない。しかしシャーマンはアニマ(霊魂)の実在を確信するアニミストでありながら、シャーマン組織(仲間)の一員(メンバーシップ)ともなった。
トーテミズム(totemism)もシャーマニズムとみなされることがあるけれど、トーテムは部族や血縁の集団の力に結び付けられた標章や象徴物のことである。トーテミズムはそのトーテムを物神(フェティッシュ)とみなし、しばしば共同体の各所にトーテムポールを立てた。南方熊楠(1624夜)はトーテムを「族霊」と訳した。
というわけで、シャーマニズムという言い方は、やはり特別なのである。民族学や宗教学ではシベリアと中央アジアの民間宗教現象をさす用語としてつかわれるようになった。「今夜、シャーマンしてみる?」というわけにはいかない。エリアーデは、自然民族(Naturvölker)や未開民族(primitives ou savages)がセアンス(巫儀)をもっているばあいをシャーマニズムとみなした。



本書は原題が“Skywatchers, Shamans & Kings”となっているように、原始・古代のスカイウォッチャー(天空を見る人・感じる者)の出現を世界各地の初源を、まるでドローンを飛ばすように追いかけた1冊である。
太古、世界は「天空・地上・地中・水中」の四象圏に分けられた。その世界に上と下、中心と周縁、「ここ」と」むこう」、此岸と彼岸、生と死などが定められた。そこから「方位」が生じ、リクツで推断できないめぼしい現象の多くが「吉凶」によって判定された。このような原始古代の世界観にとって、天空は最大のカプセルあるいはフレームないしはアクシスだった。
天空には「天を司る神」が想定され、絶対的で壮大なる力を発揮するとみなされた。これが天空神だ。天空神の想定は原始古代社会に、①世界の秩序とはどういうものか、②自然の力はどのように猛威をふるうのか、③時間はどんなふうに周期性や循環性をもたらすのか、を教えた。
各地の天空神はいろいろだが、似たような天空神も多い。古代インドの『ヴェーダ』に描かれたティアウス(デーヴァ)、古代ギリシア神話のゼウス、古代ローマのユピテル(ジュピター)はほぼ同じたぐいの最高神で、かつ「天空の王」に当たっていた。
やがて天空神にはさまざまな眷属や従者や敵対者があらわれた。ついで、いくつもの信じがたいようなエピソードが集められ、長い時間をかけて「物語としての神話」が辻褄をあわせるかのように複合的に編集され、しだいに神々のファミリーが形成されていった。
ふつう、神話論や古代信仰論はそういう神々の体系を追いかけるのだが、本書はそちらには目を移さず、天空神の力を受信してその力を借り受けるかのようなシャーマンの存在と、そのための装置や意匠や持ち物に熱心な関心を注いでいく。
その書きっぷりがいかにも巨大天文台で古代の天空に浸っているふうで、自在な連想力に富んでいるせいもあるが、とてもすらすら読める。諸君も、読んでいくと実にさまざなシャーマンのありかたがあったことに驚かされるにちがいない。
すでに述べたように、天空神を戴くシャーマンの基本型は古代アジア・中古シベリアの北方シャーマンにある。エリアーデもウノ・ハルヴァも北方シャーマンの研究を基礎においた。
たとえばシャーマンの語源をつくったツングース族では、最高の天空神はブガと呼ばれ、そのシンボルが北極星に同定された。シャーマンはそのブガと交信できた。ツングース系のシャーマニズムをさらに広く拡張させたアルタイ系のシャーマンは、やはり北極星と同定されたバイ・ウルガンという最高天空神と交信した。そのために、かれらは独特のユルト(テント)を構えて、バイ・ウルガンとの行き来を可能にさせる柱や梯子を用意した。
衣裳もとびきり凝っていた。ツングース族は鳥めいた羽根を付け、ヤクート族は太陽と月のコートを羽織り、ユカギル族はジャケットに鳥の肌をまねた細かい十字文様をほどこした。ゴリド族のシャーマンのコスチュームは熊の皮でできていて宇宙の光景が描かれた。ゴリド族はオロチ族とも言われ、サハリン、タタールから間宮海峡に及んだ。アイヌ族とも関係があるらしく、アイヌではオロチョンと呼ばれた。
かれらはしばしばギザギザの刻み目のついた長い梯子を昇降した。北方シャーマンは天空を行ったり来たりするとみなされたのである。このとき各部族ではそれぞれ独特の天空ドラムを激しく打った。
天空ドラムの皮にはたいてい天界の様子が描かれて、ドラミングのリズムがシャーマンを高揚させた。アルタイ系の天空ドラムには天空神ウルゲンの娘たちが、ショル族のドラムには太陽と月とともな金星が描かれ、テレウト族のドラムには天地を分かつ大地のストライプが描かれた。
これらの天空神、星の力、テント、梯子、天空ドラム、動物トーテム、飾り立てた衣裳などの組み合わせは、やがて北方シャーマンだけではなく、さまざまな変容やヴァージョンはあるものの、どこのシャーマンにも共通した。
北米先住民シャイアン族は、それ以前のツィスツィスタ族のオオカミ信仰を継承し、天空神マヘオのための「青い空のテント小屋」を拠点にするようになった。これを拠点にマッサウムという祭礼を仕切るのである。森林に白いオオカミが出現したときは、これをシリウスに見立てた。こうして天空神、動物の王、星、シャーマンは渾然一体になっていった。


中央アメリカのシャーマニズムにとっては、金星は武力の象徴であった。メキシコのテオティワカンの伝承には、トラロクという稲妻を体現する天空神が金星の軍事力と結託して、たびたびの危難を超越したという物語が数多くのこっている。
その物語では、シャーマンは女神ククルカンとなって星の模様のスカートをはき(動物の皮、とくにジャガーの皮でできている)、羽毛のはえたヘビに乗って闘ったのである。考古学や人類学ではしばしば「トラロク金星戦争」とよばれる時期の衣裳だ。マヤ文明のシャーマンは金星をサソリの尾に見立て、自身の高揚に駆り立てた。
このように見てくると、シャーマンは「スター・チェンバー」(星の部屋)そのものに起居していたのだろうと思えてくる。なんらかの方法で「天空を纏(まと)うこと」がお役目だったのだ。ただし、漫然とはしていてはいけない。どの星に狙いを定めるか、どんな方位を重視するか、そのためどんなドラミングやコズミックダンスを踊るのか、シャーマンはそこを際立たせた。
1554夜の千夜千冊だが、マルセル・グリオールの『青い狐』と『水の神』(せりか書房)をとりあげ、アフリカ・マリ(スーダン)のドゴン族の驚くべき伝承の話を紹介しておいた。ニジェール川流域のとても村落がありそうもない絶壁にしがみついていたドゴン族は、シリウスをヴァーチャル・リアルな「ディジタリアの星」とみなし、独特の絵文字をつかって、一族すべてをシャーマン化していたようなのである。本書第8章にもドゴン族の異様な天文マニアぶりが報告されている。
しかしドゴン族だけが天文マニアであったわけではなく、どの部族のシャーマンも「スター・チェンバー」に仮住まいしていたのである。それゆえカラハリ砂漠のサン族(ブッシュマン)は「星たちは狩りがうまい」とのべつ噂していたし、カナダ西部のハイダ族は「ハマグリが天空の夢を見た」と信じきっていた。どんなシャーマンも、天空とマザーアースと村落を、文様衣裳や天の梯子や宇宙太鼓で結びつけたのである。



本書は世界各地のシャーマンの「天空足跡」を蘇らせるために書かれたもので、厳密な研究成果を積み上げるためのものではない。だからすらすら読める。好奇心に富む天文学者が光学望遠鏡に代えて歴史文化の望遠鏡に映った原初の天空記録を次々に観測してみせたのだ。
けれども、こうしたシャーマンの動向からいったい何を感じればいいのか、何を受け取ればいいのかというと、テレビ朝日の変態プロデューサー「ナスD」ならばともかくも、おそらく今日の読者には戸惑うことばかりだろう。
いまさらシャーマンではあるまい、動物の皮を着て星に向かうだなんてクレイジーだ、まるでゾンビのような気がする、呪術めいたことは怖すぎる。こんな感想も多いことだろう。
こういう本を読んでいると気分がだんだん澄んで、ふんわりした気持ちになってくるという、ぼくのような“変態読者”はべつとして(ぼくはこの手の本のほうが心が落ち着いてくるのだ)、本書はとうてい今日の読者の現在には引っ掛からないのかもしれない。
しかしそれならちょっと言っておきたいのだが、では諸君は何をもって「兆候」を感知し、その兆候とどのように向き合いたいのか。何をもって幻想と現実を区別しているのか。何をもってヴァーチャル・リアリティが感じられると思っているのか。
問いを変えてもいい。諸君はどうして『火の鳥』から『鬼滅の刃』に及ぶマンガやアニメに夢中になれるのか。ロックバンドはどうしてオオカミの被りものをするのか。レディ・ガガやきゃりーぱみゅぱみゅはどうしていつも衣裳を変えたくなるのか、いつまでもミュージカル『ライオン・キング』が当たったり、いつまでも『ワンピース』が続くのはどうしてか。皆既月食や獅子座流星群がやっぱり見たくなるのはどうしてか。
われわれはいつだってスカイウォッチャーとともにありたいはずなのだ。星占いや手相が気になるように、その解読のヒントに出会っていたいのだ。それがシャーマンであっても、哲学者であっても、ポップシンガーであってもだ。
クラップ天文台台長の興味津々の好奇心を案内するつもりが、《イメージの力》展がトリガーになったせいだろうが、ついつい脱線気味の話を駆け抜けることになった。書いてみてよくわかったが、ぼくはヒーラーや癒し系ではなく、別してパンクなシャーマニズムをこそ待望しているわけだった。

【おまけ・1】
アメリカの「今夜はシャーマン」ブームについて、ハーバード大学の文化人類学者でユング研究者のリチャード・ノルは、今日の都市型シャーマニズムが「メンタル・イメージのスキル開発の技法」として捉えられていると分析した。スタンフオード大学の宗教人類学者ターニャ・ラーマンはこれを承けて、いまどきのシャーマンは「神の声を聴く」のではなく「内的感覚の才能開発」に向かいたいのだとみなした。
【おまけ・2】
モンゴルのヒップホップについては、島本一平(滋賀県立大学→国立民族学博物館)の『ヒップホップ・モンゴリア』(青土社)がやたらに詳しい。ポスト社会主義に舵を切ったモンゴルで、世界最悪の大気汚染都市のウランバートルで、そのウランバートルの極貧地区のゲル地区で、なぜ急激にヒップホップが熱くなったのか、その一部始終をみごとに描き出している。とくにモンゴルの口承文芸、ホーミー(喉歌)、ユルールチ(祝詞詩人)とヒップホップとの関係、現代モンゴルにおける外来文化のモンゴル化(モンゴルチロホ)の輻湊的関係をうまく説明している。
モンゴル・ヒップホップの群像にも詳しい。MCアーヴがリーダーのダイン・バ・エンヘ、プロデューサー役を演じたMCITエンフタイワン、「今こそ訊こうじゃないか。シャーマンに精霊を呼んでもらって道を尋ねようじゃないか」のIce Top、一世風靡したLumino、初の女性ラッパーのジェニー、覆面フェミニストのMrs Mなどが次々に紹介されている。
ちなみに今日のモンゴル音楽にいちはやくのめりこんでいった日本の代表選手はジャズサックス奏者でミジンコ研究者の坂田明(124夜)だった。なんとも納得がいく話だ。またちなみに『ヒップホップ・モンゴリア』は、すでに松岡正剛事務所の上杉公志が読んで、寺平賢司がこれを借り見していた。

【おまけ・3】
近代以降のシャーマニズムの盛衰については、グローリア・フラハティが18世紀のエカチェリーナ女帝、ゲーテ、モーツァルトに照準を当てた『シャーマニズムの想像力』(工作舎)、ブラヴァツキーやクルックスの動向を追ったジャネット・オッペンハイムの『英国心霊主義の抬頭』(工作舎)、近代以降のシャーマニズム関係の図版を収録したミハイル・ホッパールの『シャーマニズムの世界』(青土社)が参考になる。

⊕『天と王とシャーマン――天に思いを馳せる支配者たち』⊕
∈ 著者:E・C・クラップ
∈ 訳者:田川憲二郎
∈ 編集:林美樹
∈ 発行者:三田順啓
∈ 発行所:三田出版会・出版文化社
∈ 発行:1998年
⊕ 目次情報 ⊕
∈∈ 謝辞
∈ 序章 権力を手に入れたければ、まず宇宙を学べ
∈ 第1章 世界の中心はここにある―各国の「世界の中心」
∈ 第2章 コズミック・パワー―力にはさまざまな顔がある
∈ 第3章 創造の場―すべてが始まる場所
∈ 第4章 母なる大地―マザー・アース
∈ 第5章 再生の担い手たち―甦る生命
∈ 第6章 シャーマン、族長、そして神となってしまった王
∈ 第7章 天空の帝国
∈ 第8章 目覚めた利己と密やかな動機
∈ 第9章 誇示することは良いことである―花開くコズミック・パワー
∈ 第10章 権威を求めてもっと高くもっと鋭く
∈∈ 参考文献
∈∈ 図版クレジット
∈∈ 索引
⊕ 著者略歴 ⊕
E・C・クラップ(E.C.Krupp)
天文学者で、グリフィス天文台長。"Echoes of the Ancient"や"Beyond the Blue Horizon"の著者で、雑誌"Sky & Telescope"にもコラムを掲載している。また、講演会やテレビ、ラジオの出演など多方面で活躍。子供向け大型絵本の邦訳『空のひしゃく北斗七星』(訳:藤田千絵、岩波書店)が1993年に刊行。ロサンゼルス在住。
⊕ 訳者略歴 ⊕
田川憲次郎(たがわ・けんじろう)
国際基督教大学教養学部卒業、同大学院終了。訳書に『"カイシャ"の中の外国人』(ジェトロブックス)、『ロシアは甦る 資本主義大国への道』(三田出版会)がある。