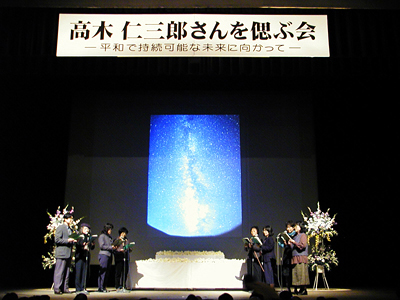原発事故はなぜくりかえすのか
岩波新書 2000
編集:岩波新書編集部
装幀:岩波書店
本格的な運動として立ち上げたのは、
市民科学者の高木仁三郎だった。
早くからプルトニウムの危険を訴え、
ついでは「原子力安全」と「原子力文化」が
決して成立しえないことを、
つねに根底から告発しつづけた。
頑固で、勇気があって、誠実な人だった。
しかし激痛と闘病のなかでJCOの臨界事故を知り、
本書を遺して、無念のまま他界した。
もしフクシマのことを知ったら、
どうなっていたことか。
2000年10月8日、築地の聖路加国際病院で高木仁三郎が亡くなった。最終病名は直腸ガン。62歳と2カ月余。その3年ほど前に会ったときは顔色はすぐれなかったが、大病を患っているとは思わなかった。しばらくして大腸ガンであることが判明したと人づてに聞いた。
高木さんには最後の最後に口述した『鳥たちの舞うとき』(工作舎)という唯一のフィクションがある。十川治江が編集した。その「あとがき」を書いた久仁子さんによると、1998年の7月に大腸ガンだとわかって切除手術をしたときにはすでに肝臓や胆嚢に転移していたようで、本人も1年くらいの余命だと覚悟していたらしい。それでもなんとか退院をして、新たに計画していた高木学校の連続講座で第1回の「プルトニウムと市民」を講演した。
1999年は闘病しつつも6回分の高木学校を了えたのだが、腫瘍マーカーの値がどんどん上がり、たちまち抗ガン剤を打ちながらの日々に変じた。そんなときの9月30日にJCOの臨界事故がおこった。何度も何度も、いや数百回にわたって高木さんが警告していた原発事故だった。本書はその記述から始まっている。
しかし容体はますます悪化するばかりで、2000年には東京女子医大病院の人となり、9月18日に聖路加に移っていた。もう、時間はない。すべてを察知して最後の仕事に向かおうとしていた高木さんは、自身で酸素チューブをはずし、本書のゲラと『鳥たちの舞うとき』のゲラを遺して死んでいった。今日はその高木さんの祥月命日なのである。追悼したい。
本書には、原発事故はなくならないということが「原子力文化というものなんてありえない」という視点から、繰り返し説かれている。「原子力は文明であるかもしれないが、とうてい文化にはなりえない」というのが高木仁三郎の確信なのである。
たしかに原子力技術にもとづいた原子力文明はありうるだろう。また、原子力発電がすでにそうなっているのだけれど、利潤を追求する原子力産業もありうるし、医療や宇宙開発に応用することも可能であろう。けれども生活の安心や安全を満喫する原子力文化がどこかにあるとは思えない。このことを高木さんは原子力技術の研究開発にかかわった現場で実感した。
高木仁三郎が日本原子力事業という会社に入ったのは、東大理学部化学科卒業直後の1961年である。1955年に原子力基本法ができて、その翌年から日本の原子力研究が少しずつ本格化すると、三井(東芝)・三菱・日立・富士・住友などによる原子力産業グループが形成されるのだが、高木が入ったのはその三井系の会社だった。
そこは東芝や石川島播磨や三井東圧から派遣された人材によって構成されていたらしく、高木は核化学研究室に配属になった。核化学はもともと高木の専門で、ウェット・ケミストリーとして放射性物質を水溶液状態で扱う研究開発に携わった。むろん心高鳴る職場であったはずなのだが(当時は原子力産業は学生に非常に人気が高く、工学部のエリートのほとんどが憧れていた)、しかし実情は、原子力委員会が組み上げた「日本の国産炉」をどうするかという計画の前で、①まず研究所をつくる、②そこに実験原子炉をつくる、③それに関連した仕事をみんなでやるというようなことしか、決まっていなかった。
はっきりいって「無思想」だったのである。空想的には放射性物質をクラスレートに閉じ込めてアイソトープ商品をつくるなどといったたぐいのことも、あれこれ企画に上がったそうだが、とうてい原子力商品をもって新たな産業文化に寄与するというようなものは一つとしてなかったらしい。本格的な議論もなかった。つまり「無思想」なのである。
それで何をしたかというと、アメリカの例に倣おうということで、ひとつは原子力潜水艦のような方向を、もうひとつは原子力発電のほうへ向かおうということになった。
ぼくもよく憶えている。10歳の頃だったが、学校のクラスの男の子たちは原子力潜水艦ノーチラス号の話題でもちきりだったのだ。1954年、アメリカのジェネラル・ダイナミックス社が華々しく進水させたノーチラス号の姿は、当時の子供にとってはジュール・ヴェルヌの『海底二万哩』の世界そのものだったのだ。それはまた『鉄腕アトム』に始まった夢多い原子力ロボットにわくわくしていた時期でもあった。
これらはまことに他愛のない子供ドリームにすぎなかったけれど、高木によると、日本原子力事業という“本気の原子力屋”の議論も実はそんな程度だったというのだ。
こうして日本はアメリカを追随しての原子力発電にとりくんでいくことになる。これは高木から見ると、「放射能を知らない原子力屋」(本書第3章のタイトルにもなっている)による目標のない大プロジェクトだったと見えた。しかしその集団こそが“原子力村”をつくり、日本の原子力発電の産業化にとりくんだわけだった。
1999年9月30日の東海村JCOでおきた臨界事故は、病身の高木仁三郎を激怒させ、悲しみの深淵に突き落とした。核燃料加工のプロセスで本来の手順を逸脱してウラン235の高濃度溶液が一つの容器に集中し、そのため核分裂反応が持続したまま中性子がこの世に放出された事故だった。
80日後、現場作業員の大内久氏が放射線急性障害で死亡し、ついで二人目の篠原理人氏が大量被爆で死亡した。日本の原子力開発がもたらした初めての死亡事故である。これで日本人は三たび、青い光の告発を受けることになってしまった。
青い光というのは、原子炉で核分裂反応の高いエネルギーをもった粒子が水の中を通過するときに発する特殊な光のことである。核爆発や核分裂の現象に特有の光で、科学用語では「チェレンコフの光」という。日本人はこの青い光を、第1には1945年8月6日に広島で、第2には8月9日の長崎で、そしてそれから54年たった東海村で見ることになった。そのほか1954年3月1日に、ビキニ環礁で被爆して死亡した第五福竜丸の久保山愛吉氏も、チェレンコフの光から派生した光を見たかもしれない。
JCO臨界事故は、濃縮ウラン溶液を手作業でバケツ7杯も運んだせいだと言われているが、そのようなことをさせた原子力関係者の意識が大問題になった。本来なら原発での仕事には、すべての関係者が放射能事故について過敏でなければならないのだが、ところが日本の原子力関係者は、その理論を組み立てる者も設計に携わる者も、現場のメンテナンスに従事する者も、その意識がきわめて薄いのだ。とくに事故に対する意識が薄い。
日本だけではない。アメリカでもけっこう希薄だった。原発の安全性については1975年に発表されたラスムッセン報告というものがあって、原発事故を確率論的に評価して、「メルトダウンといった大事故がおきる可能性は10のマイナス5乗から6乗だ」と発表し、「ヤンキースタジアムに隕石が落ちるようなもの」と付け加えたのである。ところがこの報告のあとスリーマイル島の原発事故がおこった。
何かの底がすっかり抜けている。その底こそは、ほんとうは文明が文化を生み出すための根底にあるべきものだったのに、そうではなかったのだ。
1989年の『巨大事故の時代』(弘文堂)という本がある。そこで高木さんは事故の原因を「重畳型、共倒れ型、将棋倒し型」の3つに分けた。
重畳型は、単独ではそれほど深刻ではないはずの故障やミスが、“偶然”に重なりあって大事故になるというケースで、ニューデリーの南200キロのボパールでおきた農薬工場の例をあげている。
その工場ではコークスと塩素を反応させてホスゲンを発生させ、そこからMIC(イソシアン酸メチル)を生成していたのだが、貯蔵タンクと反応槽をつなぐパイプを清掃中に遮断シートを使うのを忘れたため、水分とホスゲンあるいはMICが反応して大量のガスとなり、それでタンクの内圧が上昇して爆発した。洗浄のミス、メーターの無視、生ガス焼却装置の欠陥、タンク操作ミスが重なったのである。その重なりは確率でいえば10万回に1回くらいのことであるのに、それがおこったのだ。
共倒れ型は、1975年にアメリカのブラウンズフェリー1号炉の事故に見てとれる。原子炉建屋の中の空気の流れを調べようとして調査作業員がローソクを灯したのだが、それが火災につながり、ケーブルが燃え、制御装置と安全装置を使用不能状態にした。多重に防衛されていたはずの装置が、たった一本のローソクで共倒れになってしまったのだ。
将棋倒し型は、1986年のチェルノブイリの大事故に顕著だった。すでに詳しい解説書がいくつも公開されているので、いまさら説明するまでもないだろうが、高木さんの闘いはここから始まっているので、以下、概略だけを書いておく。
詳しいことは高木仁三郎講義録『反原発出前します』(七つ森書館 1993)などを読んでいただきたい。この講義録は1987年1月から始まった出前講義の集大成で、出前そのものは3年間で300回をこえた。科学論としても技術論としても、めっぽう詳しい。
チェルノブイリ原発の4号炉は、現在でこそ建設当時からいろいろの設計ミスや不手際があった欠陥原発だったということになっているが、そのころは世界的にも有能な原子炉だと思われていた。ソ連もとても自慢していた。
1986年4月25日、ディーゼル発電機が立ち上がるまでにタービンの慣性回転を利用して緊急炉心冷却系に電力を供給するテストをしようということになり、この日の夜の11時から出力降下作業が着手されることになった。
このテストは実は2度目のトライで、最初はその半日前におこなわれ、出力を低下させ始めた運転員は、そのとき緊急炉心冷却装置(ECCS)の信号を切っていた。炉心の水位が下がったときはECCSが作動して注水が勝手におこなわれてしまうから、信号のスウィッチを切ったことは妥当だった。
ところが、出力をさらに下げようとしたとき、キエフから指示があって、電力需要の必要で50パーセントの出力で運転をしろと言ってきた。その段階でテストは半日延期されたのである。こうしてその後に交代した作業員がテストを再開させた。直後に出力が3万キロワットに落ちた。
慌てた作業員は出力を回復させようとして、なんとか20万キロワットまで戻したのだが、これで原子炉の内部がきわめて不安定な状態になった。すぐに制御棒を引き抜いたところ、これは引き抜きすぎていた。加えて作業員はタービン停止にともなって原子炉を緊急停止させる信号も切ってしまった。これはルール違反だが、最初のテストがうまくいかなかったときに再度トライするためだったらしい。
午前1時23分、緊急閉鎖弁が閉じられ、タービンは慣性で回転を続けるのだが、むろんその回転数は落ちはじめ、タービン発電機につながる循環ポンプの能力も落ちてきた。これで炉心を流れる冷却水の量が減り、温度が上がって出力暴走が始まった。その直後のたった1秒のあいだに、出力が3億2000万キロワットに上昇すると、燃料ウランが内部から粉々に砕け、高熱になった酸化ウランが冷却水と接触して、かの蒸気爆発をおこしたのである。
原子炉建屋の上部は吹き飛ばされ、原子炉は破壊されて内部にたまっていた放射性物質を大気中に放出していった。
これが将棋倒し型である。高木さんはこう説明した。「これは、一つ一つの信じられないような規則違反が重なって信じられないことがおこったのではなく、一つ一つではおこりにくい出来事や規則違反が連なって、かえって最も信じられないことがおこりやすくなったのである」というふうに。
原発事故については、高木さんは基本的には二つに大別できると言っていた。Aは暴走事故型で、核分裂反応の制御に失敗する事故である。Bは冷却に失敗して炉心が溶けるという事故、すなわちメルトダウンにいたる事故である。しかし当時から、これらの複合型の事故もおこりうる、その危険性のほうがかえって高いとも警告し、その複合性を技術はカバーしきれないのではないかと見ていた。
たとえば暴走には、エネルギー出力の反応度の事故と原子炉の事故があり、後者の場合は燃料棒が壊れるだけでなく、それによって熱くなった燃料と蒸気が接触すると蒸気爆発になることも、その途中で水が分解して水素になり、それが水素爆発になることもあり、一方、冷却材が破損あるいは喪失した場合は、メルトダウンがおこって炉心が溶けるだけでなく、そのまま原子炉の底を貫通して放射能が外部に漏れたり、それが他のエネルギーに転換して蒸気爆発や水素爆発を併発させることがありうるとも予告していたのである。
いまさらその先見性を高く評価したってなんだかむなしいが、高木さんは原発事故のほとんどすべてを予見していたわけだ。しかしそのことを警告するのが高木さんの仕事を占めていたわけではなかったとも言っておかなければならまい。そもそも高木さんは「プルトニウム社会」というものを問題にしてきたのだった。『プルトニウムの恐怖』『プルトニウムの未来』(いずれも岩波新書)を読まれるといい。
念のために書いておく。
一言でいえば、プルトニウムは原爆開発のために人工的につくられた元素である。核分裂性と毒性がやたらに高い物質で、核兵器の大半に使われる。たった1グラムでも人の命を脅かす。そのプルトニウムは、なぜ原発と関係があるのか。
もともと原子炉による原子力発電にはウラン235とウラン238が使われてきた。この数字は原子核をつくる粒子、すなわち陽子+中性子の数をいう。ウラン235に中性子が衝突すると原子核が分裂して熱を出す。ウラン238に中性子が衝突しても核分裂はあまりおこらず、そのかわりに中性子を吸収してごく短時間でプルトニウム239に変化することが多い。そのプルトニウムに中性子が衝突すると原子核が分裂して熱を出す。これらの熱を利用して蒸気をつくり、タービンを回すのが原子力発電の基本原理になっている。
この原理で発電するとき、地中から採掘される天然ウランには「核分裂するウラン235」がわずか0・7パーセントしか含有していない。たいへんな希少価値になる。一方、「核分裂しないウラン238」を使えばプルトニウムに変えられるから、かなりの有効活用ができる。
これらのことから、原子力発電をするとプルトニウムが抽出できて、それを再処理できるということになってきた。100万キロワット級の軽水炉を1年間フルに動かせば、約250キログラムのプルトニウムが生成できる。ただしこれは、日本の全人口を何度かにわたってガンで致死できる量である。プルトニウムが7~8キロほどあれば一個の原爆が作れるし、日本中の43基の原発が稼働すれば、毎日原爆2~3個が作れるという計算になる。
アメリカは原発王国ではあるが、核兵器用のプルトニウムをしこたま保有しているものの、民間原発からはプルトニウムを取り出していない。ドイツと日本がプルトニウム再処理をして核燃料サイクルを確立しようとしてきた。いまやドイツはこれをやめようとしているが、日本はまだそこまで踏み切っていない。なぜなら核燃料サイクルがあれば、燃料の有効利用ができて、ウランに依存するよりずっと効率的になるからである。
こうして日本はプルトニウムをふやすしくみに開発費をかけることにした。それが高速増殖炉の開発で、「もんじゅ」に結実した。
もう少し説明しておくと、高速増殖炉は中心部にプルトニウムを20パーセント前後に濃縮したMOX燃料(ウラン・プルトラウム混合酸化物燃料)を入れておいて、その周囲にウラン238を配置して、高温度の金属ナトリウムをどろとろの液体にして使う。
中心部のプルトニウムが核分裂しながら、その熱をナトリウムに伝えて発電エネルギーとしていくと、核から飛び出した高速の中性子がナトリウムの中を走るので、これを首尾よくウラン238に捕獲させようというしくみなのである。これでウランがプルトニウム239に変化していく。
その結果、消費されたプルトニウムより、新しく生まれたプルトニウムの量が多ければ、資源が増していくということになる。発電ができて資源も増加するから、一石二鳥なのである。
しかし、1995年に「もんじゅ」はナトリウム火災をおこして、停止した。核燃料再処理サイクルは止まったままなのだ。
まあ、このくらいでいいだろう。それで高木さんは、このようなプルトニウムを活用しようとする社会そのものが病んでいるのではないかと告発しつづけたのだった。これらの技術を活用する社会はアクティブすぎると言ったのだ。「原発はアクティヴィズムの極致の技術である」とも書いている。そういうアクティヴィズムよりも、むしろパッシブな社会に転換したほうがいい。私はパッシヴィズムに向かいたい。そう、断言したのである。
これはぼくの見方でいえば、もっと社会をフラジャイルでヴァルネラブルなものだ見たほうがいいということになる。そこを高木さんは日本を「イントリンシックな社会」に戻したほうがいいとも言っている。イントリンシックとは「本来の社会」ということである。ぼくもずっとそう思ってきた。日本の本来と将来をつなげることが、日本という方法の課題なのであると。

岩波新書(新赤版)703
『原発事故はなぜくりかえすのか』
著者:高木仁三郎
2000年12月20日 第1刷発行
発行者:山口昭男
発行所:株式会社 岩波書店
【目次情報】
はじめに
臨界事故/青い閃光/八月六日/峠三吉の詩/饒舌な報告書
1 議論なし、批判なし、思想なし
安全神話の崩壊/安全文化/原子力文化/安全第一/自己点検のなさ/
原子力産業の状況/さまざまな用途の研究/相互批判なし/議論なし、思想なし/
原子力の導入の歴史/原子力村の形成/奇妙なブーム/ある経験
2 押しつけられた運命共同体
国家まかせ/大事故の評価/トップダウン型の開発/サッカーにたとえると/
「三ない主義」/「我が国」という発想/マイ・カントリー
3 放射能を知らない原子力屋さん
バケツにウランの衝撃/物理屋さんと科学屋さん/放射化学屋の感覚/
物理屋さんの感覚/自分の手で扱う/放射能は計算したより漏れ易い/
事故調査委員会も化学抜き
4 個人の中に見る「公」のなさ
パブリックな「私」/普遍性と没主体性/公益性と普遍性/仏師の公共性/
技術の基本/原子力は特殊?/科学技術庁のいう公益性
5 自己検証のなさ
自己検証のない原子力産業/自己に対する甘さ/自己検証型と防衛型/
委員会への誘われ方/結論を内包した委員会/アカウンタビリティー/
寄せ集め技術の危険性
6 隠蔽から改ざんへ
隠蔽の時代/質的転換/技術にあってはならない改ざん/技術者なし
7 技術者像の変貌
物の確かな感触/ヴァーチャルな世界/倫理的バリアの欠如/
新しい時代の技術者倫理綱領
8 技術の向かうべきところ
トーンを変えた政府/JCOの事故の意味/技術の極致/現代技術の非武装化
あとがきにかえて
友へ 高木仁三郎からの最後のメッセージ/高木さんを送る
高木仁三郎・年譜
【著者情報】
高木仁三郎[たかぎ じんざぶろう]
1938年生まれ。群馬県前橋市出身。1961年東京大学理学部卒業。日本原子力事業、東京大学原子核研究所、東京都立大学などを経て、1975年に原子力資料情報室の設立に参加し、87年から98年まで代表を務める。1997年ライト・ライブリフッド賞受賞。