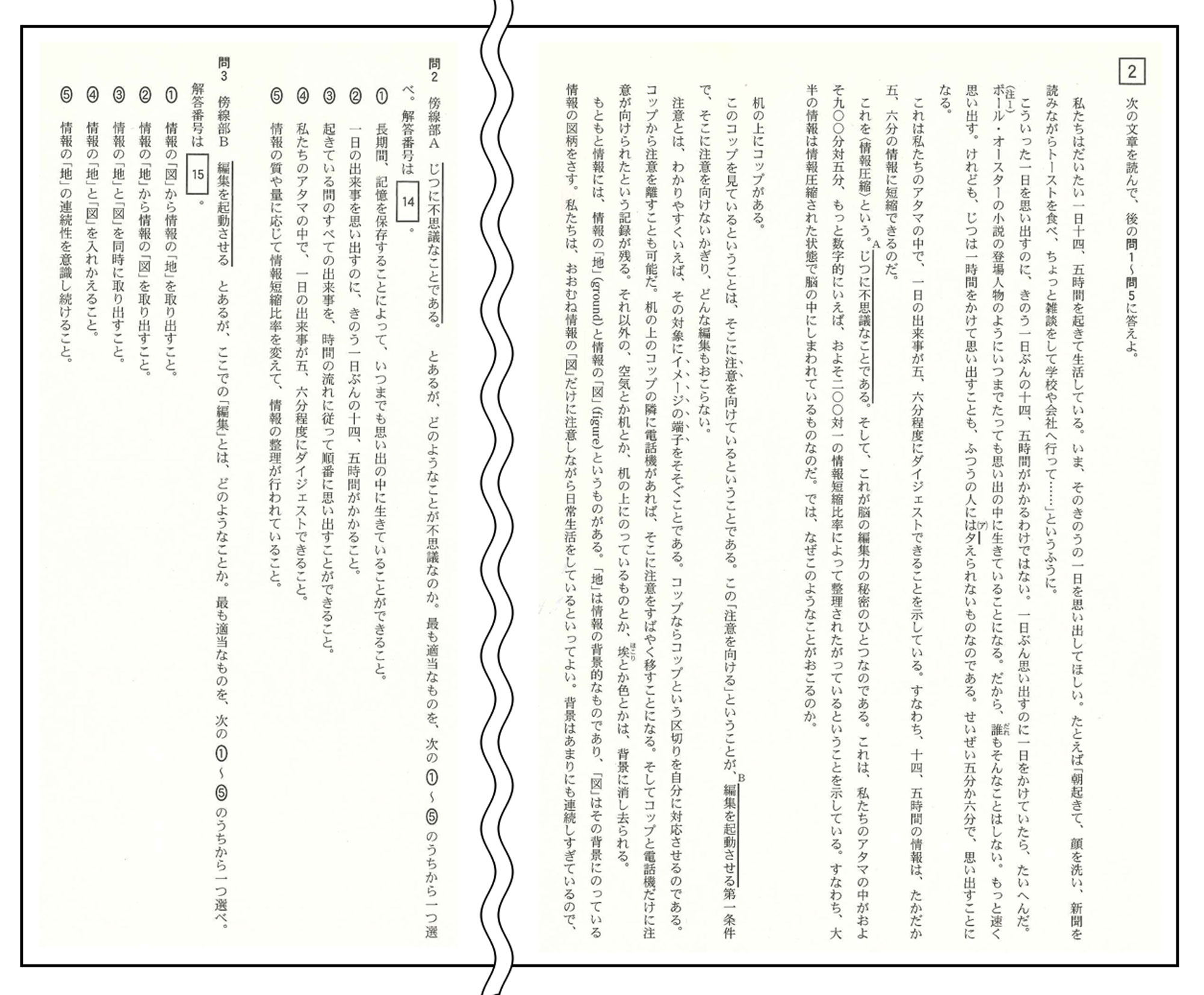この短篇を読んだときは、不意打ちを食らった。巧妙に高校の国語問題や大学入試の国語問題の胡乱な特徴を言い当てている。皮肉な手法がちらつくパロディ作品としても感心した。主人公の浅香一郎君が月坂先生という国語教師から入試問題必勝法を教わるという小説仕立ての設定になっているのだが...
この短篇を読んだときは、不意打ちを食らった。陽光の中の眩しい不意打ちだ。巧妙に高校や大学入試の国語問題の胡乱な特徴を言い当てている。皮肉な手法がちらつくパロディ作品としても感心した。
主人公の浅香一郎君が月坂先生という国語教師から入試問題必勝法を教わるという設定の小説仕立てになっているのだが、これがなんともおかしい。どんなふうなのか少し紹介しておく。浅香君が国語問題を読むところから始まる。
次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。
‥‥積極的な停滞というものがあるなら、消極的な破壊というものもあるだろうと人は言うかもしれない。なるほどそれはアイロニーである。濃密な気配にかかわる信念の自浄というものが、時として透明な悪意を持つことがあるということは万人の知るところであろう。
ここまで読んで浅香君は頭がくらっとした。何が書いてあるのか皆目わからない。ひとつひとつの言葉はだいたい知っている。「積極的」もわかるし「停滞」もわかる。けれども「積極的な停滞」はお手上げだ。イメージが浮かばない。続いて、設問部分の問題文を読む。
‥‥エヒエルト・シャフナーは①その窮極のテーゼに等身大の思考を持ち込んで②センメイな構図を示した。人間は道具の製作及び使用によって自己を自然と結びつけ、それによって人は敗北主義から独断家になるわけである。③粗密は気質の差によるものである。すなわちその経験に関して④****を蓄積することができないのは、いうまでもない。比喩的表現は直観的で、飛躍的、超論理的、⑤****であるように見ることも可能である。神は集団の象徴であり、宗教とは集団の自己⑥スウハイにほかならない。
こりゃダメだ。浅香君は絶望的な気分になった。問1「傍線のカタカナを漢字に改めよ」は、まあなんとかなる。問2の「傍線①の「その」の内容にふさわしいものを次の中からひとつだけ選べ」は、もういけない。
(1)文化が時には自然と対決するという
(2)古人の経験と自己の相異から生まれる
(3)いろいろのことがあるその全体の
(4)夏目漱石の文学における
問3の「傍線③の文章の内容と最も近いものを次の中からひとつだけ選べ」は、もっと脱力させられる。何を問われているのかもわからない。
(1)粗と密は気質というものの差による。
(2)粗は粗であり、密は密であり、それははっきり別のも
のであって、そんなこともわからないのは馬鹿だ。
(3)人間の多様性。
(4)あたかもトマトとレモンは別のものであるように。
国語の試験にさっぱり答えられない浅香君は、やむなく月坂先生の特訓を受けることになった。先生が最初に言うには、大切なのは設問に正しく答えるということであって、原文の文章を理解するということではないということらしい。
浅香君はびっくりした。なぜ文章を理解できなくてもいいのだろうか。先生は「国語の入試問題は原文とは無縁の点取りゲームになっているからだ」と言う。設問文がそのためにある。だから設問ゲームのルールをマスターすれば、だいたい答えられるらしい。それには設問の選択肢がどのように用意されているかを知ればいいらしい。
先生は選択肢か4つある場合は「大」「小」「展」「外」になっていることがほとんどなんだという。選択肢が5つの場合はこれに「誤」が加わる。そういうふうになっていると思うべきなのだそうだ。「大」「小」「展」「外」「誤」とは何だ?
設問文が「大」であるとは、原文に書かれていることよりも話の内容を大きくしてあるということらしい。たいていは一般論に拡大しているという。だから一般論としては正しいという設問文になっている。「小」は原文の中の一部分だけを取り出したもので、たしかに原文の文章の中にはそういうことは書いてあるが、書いてあることはそれだけじゃない。それなのに初心者はそこにひっかかる。
「展」は原文の論旨をもう一歩展開させていて、原文に書いてあることではなく、原文から予想される結論や想像される作者の主張が問題文になっている。しかしそれをうっかり選ぶと「文章の内容と最も近いものを次の中からひとつだけ選べ」という設問の指示からはずれることになる。これもかなりひっかかりやすい。「外」はちょっとピントが外れているものをいう。「誤」はでたらめに近い。
これらからひとつだけ選択肢を決めるのだが、月坂先生はそれには「正論除外の法則」を使うのがいいと断言する。浅香君がキョトンとしていると、「いかにも立派な正論めいたことを書いてあるほうを捨てよ」という法則なんだと説明があった。わかったかな、それじゃこれを解いてみなさいと、月坂先生はこんな問題を提示した。
問 次の****に入れる最も適当な語句をabcdeの中か
ら選べ。
「百羽ばかりの雁が一列になって飛んでいく」「暖かい静かな夕方の空を」おもうと、私どももどこか分からない遠い空への****にさそわれる。
a幻想 b虚無 c郷愁 d悲哀 e想像
かんたんのようで、そうでもない。どうも迷う。浅香君がまごまごしていると、先生がこう言った。「いいか、オカルトはひっかけ、人情ものが案外いけるんだよ」。
先生がさらに言うには、世の中の文章にはもちろん神秘的な言葉や考え方を好むものは少なくないが、そういうものはかなり個人的な趣向による。でも、それには高度な判断がいる。教育機関はそんなオカルト問題を受験生には出さないし、それに神秘をどう解釈するか、出題者たちもわかっちゃいない。出題者たちにわかるのは人情やふつうの気分のことが多いんだ。浅香君はなるほどと思った。やっぱりこの先生は天才だ。
で、とりくんだ。オカルトというのはこの問題なら「a幻想」だろう。「b虚無」も神秘っぽいし、哲学すぎる。そう見ていくと「d悲哀」も感情が行きすぎだし、「e想像」では無定形になりすぎる。そうか、こうやって消していけばいいのか。だったら「c郷愁」かなと思ってそう答えると、月坂先生が「そう、正解だ」「つまり人情が答えになるんだよ」。
清水の短篇はこのあと、もう少し「国語問題」の妙についての先生の独自の「読み」が紹介され、感動きわまった浅香君が先生の家に遊びに行きたくなって、次のようなメモを渡すというところでおわる。
問 ぼくはよい生徒でしたか。次の中から最も近いものをひ
とつ選べ。
①大変よい生徒だった
②覚えの悪い生徒だった
③性格に問題のある生徒だった
④どうでもよい生徒だった
⑤幻妙で客体化された生徒だった

【松岡正剛試験問題1】『フラジャイル』
(試験問題より抜粋)
清水にはいろいろパロディックな傑作がある。初期に話題になった『永遠のジャック&ベティ』(講談社文庫)も虚を突いて、笑わせた。ジャック君とベティ嬢のあやしい恋の物語なのだが、会話がぼくも中学で使った懐かしの英語教科書『ジャック&ベティ』を準えている。
二人が出会うと「あなたはベティですか」「はい、私はベティです」と始まる。「あなたはベティ・スミスですか」「はい、私はベティ・スミスです」「あなたは一人ですか」「はい、私は一人です」。ジャックはベティをなんとかしたいので「一杯のコーヒーか、または一杯のお茶を飲みましょう」と言う。これでなんとかコーヒーショップに連れこんだが、会話は「これはテーブルですか」「はい、これはテーブルです」「これはソファですか」「いいえ、これはソファではありません。これは椅子です」「どうぞ、座ってください」「はい、ありがとう」というふうにしか続かない。
この場面から30年がたって、話はジャックがベティと再会するチャンスにめぐりあえることになる。ジャックはどきどきしているのだが、そこでも「あなたは結婚していますか」「私はかつて結婚してました」「一人で暮らしているのですか」「はい、一人で生活しています」というふうなのだ。ジャックは色気むんむんのベティとねんごろになりたいのに、会話はなかなかそこまで辿りつかない。そのもどかしさが捩れて「このあと二人でやりませんか」とも問えず、ラストでも笑わせる。そういう話だ。
こうした清水のような作品はパロディ文学やユーモア文学に属するが、「パスティーシュ」(pastiche)といったほうがぴったりする。中世フランスのコントから派生したもので、先行する作家の主題や文体を模倣したり、引用を組み合わせてモザイクにしたりしながら、いつのまにか新しい文脈をつくりあげてしまう手法のことをいう。編集工学屋からするとエディティング・スキルの極みと深みを走っているというお手本だ。
パロディやパスティーシュはめずらしいものではない。どんな作家や著述家も身におぼえのある手法だし、厚顔無恥な勇気があって編集技法を駆使したいと思える気質さえあれば、腕試しをしたくなるというていのものだ。だから多くの書き手が歴史や文学の本質を抉るようなパロディや、上品きわまりないお洒落なパスティーシュに挑戦したいと思っている。
実際にも、オスカー・ワイルド(40夜)はそう思って『サロメ』を書いたのだし、漱石(583夜)は『吾輩は猫である』にロレンス・スターンの『トリストラム・シャムディ』やアマデウス・ホフマンの『牡猫ムルの人生観』をちゃっかり借用した。
ジェラール・ド・ネルヴァル(1222夜)に『アンジェリック』がある。そのおしまいのところに、次のような会話が出てくる。「君はほかならぬディドロ(180夜)の模倣をした」「とんでもない、ディドロがスターンの模倣をしたのだ」「いや、スターンはスウィフト(324夜)を真似て、スウィフトはフランソワ・ラブレー(1533夜)を借りた」「ラブレーはメルリヌス・コッカイウスを下敷きにしただろう」「コッカイウスはペトロニウスの模倣だよ」「そのペトロニウスはルキアノスをまるまる借りたね」。
そんなふうに会話が進んで、次のようにおわる、「まあ、いいじゃないか、とどのつまりは、あの『オデュッセイア』(999夜)の作者が最初の最初のお手本だということになったって」。
ことほどさように、世界文学はほぼすべからくパロディの歴史なのである。西洋でいうなら古代ギリシアのアリストファネスの戯曲からずっとそうだった。ダンテ(913夜)の『神曲』は夥しい下敷きと引用とミメーシスに満ちているし、ボッカチオの『デカメロン』(1189夜)やシェイクスピア(600夜)の戯曲は何十回何百回もパロディの対象になってきた。模倣は文学の隠れた王道で、パスティーシュはその極上のカットアップやアペリティフなのである。

【松岡正剛試験問題2】『日本流』
(試験問題より抜粋)
清水義範がパスティーシュを書き始めたのは35歳前後のことだったらしい。「小説現代」から依頼があったので、大いに気合を入れて書いてみたらボツだった。それで3カ月かけて新しいものを仕上げてみたら、またボツになった。
打ちひしがれていたとき、ふいに司馬遼太郎(914夜)の書きっぷりに関心が出てきて、あの司馬調を下敷きのフォーマットにして猿蟹合戦を書いてみようと思い立ち、『猿蟹の賦』を書き上げてみたところ、これが採用された。「小説現代」のタイトル・ページには嬉しくも「パスティーシュ小説の異色作」と謳ってあった。
若い頃からパロディやミミクリーは得意だったようだ。教育系の大学だったので小学生にやらせる「道徳性テスト」を履修させられるのだが、そこに「Nくんは掃除当番なのに掃除をしない。そのときどうするか選びなさい」という小学生向けのお題があって、選択肢に「①先生に言いつける、②Nくんに掃除をするように言う、③Nくんのことはあきらめる」とあれば、清水はさっそく、「①Nくんに無言電話をかける、②Nくんを人間として認めない、③全員で掃除をボイコットする、④せせら笑う」というふうにパロった。
根っからの名古屋人が東京人のフリをして名古屋の悪口を書いた『蕎麦ときしめん』(講談社文庫)では、全体を日本人論のパロディにするとともに、「でたらめ名古屋人論」のパスティーシュになるようにした。言うまでもないだろうが、『国語入試問題必勝法』も入試問題からしてでたらめで、むろん月坂先生の必勝法もでたらめなのである。
清水のパスティーシュは「毒がない」と言われることもある。しかし、清水は笑いのめして何かを否定したいとか、毒舌で文句をつけたいとは思っていない。
そうではなくむしろまったく逆に、好きなお手本を下敷きにパロディアとミメーシスとアナロギアによって、「現象や対象の本質に奇妙に接近する」ということを狙う。そういうパロディ小説、パスティーシュ小説なのである。ビートたけしやお笑い芸人のような偽悪はない。
だから「本歌どり」や「江戸の戯作」に近いといったほうがいいだろう。烏丸光広作といわれる『仁勢物語』(伊勢物語のパロディ)や柳亭種彦の『偐紫(にせむらさき)田舎源氏』(源氏物語のパロディ)ふうなのだ。ただし地口に落ちたり、諧謔のかぎりを尽くしたり、批判をあからさまにするといったことはしない。香ばしいヒューモアを文体に漂わせるほうだ。まあ、ずばりいえば「もどき」の芸なのだ。
ちくま文庫に「清水義範パスティーシュ100」というシリーズが組まれているのだが、その『翼よ、あれは何の灯だ』や『インパクトの瞬間』などで、その存分の味が愉しめる。
ちなみに「インパクトの瞬間」というのは長島茂雄の例の言いまわしを駆使したものの総称と思ってもらえばよく、アナウンサーが「長島さん、原の不振の原因は何なんでしょうか」と聞くと、長島が「それはその、いわゆるひとつのインパクトの瞬間というか、なかなか明快にならない、ディフィカルトな、原君自身も自分でどーにもならないジレンマといいますか、いわゆるナイーブなインパクトの瞬間がですねえ、ええ、ええ、ええ、まあ、そこが欠けてるんですよ」というふうになる。
清水は「これでいこう」という模倣模作の「技」が決まったら、その「技」を丹念に解凍しながら、これを寿司屋にも大工仕事にも、外交問題にも女子校生モンダイにもあてはめていく。この「あてがい」も絶妙でなければならない。だから話の展開もそれらしくなければならない。
パロディとパスティーシュの王道は「らしさ」の徹底なのである。騙すのではない、偽るのでもない。「もどき」に徹するのだ。この「もどき」の漲りがファンにはたまらない。
ところで、私事ながら大事なことを付け加えておきたい。わが国語試験能力にかかわることだ。
実はぼくの文章はこれまで大学入試から中学の国語問題まで、何度も使われてきた。数えてはいないが、50回は越えていると思う。たとえば『日本という方法』が広島大学・佛教大学・岐阜大学、日比谷高校などに、『知の編集工学』が神戸芸工大・愛知淑徳大学・久留米大・三重大学などに、『日本数寄』が京都精華大・千葉商科大・広島国際大などに、千夜千冊あれこれが立命館大・関西学院大・桃山学院大などに使われた。
意外だったのは『フラジャイル』を防衛大学校が問題文にしたことだ。『試験によく出る松岡正剛』という本になるねえと、スタッフたちに冗談を言ったほどだ。
試験問題だから使用前には知らされない。使用後に事務的なペーパーが郵送されてきて、「貴殿の『花鳥風月の科学』の✕✕✕✕の個所を****の試験問題に使用しました」と連絡がくる。なかには問題文とともに送られるので、試しに解いてみるのだが、これがなんとほとんどハズれてしまうのだ。とくに「傍線の箇所と同じ意味をあらわしているのは、イロハニホのどれか」という問題が、からっきしできない。みんな当たっているように思うのだ。
おそらくその文脈でその文章を書いた本人は、さまざまな含意をもってその個所を書いているので、イロハニホのいずれもカバーしてしまうからなのだろう。そうだとすると月坂先生が正しいのかもしれない。まっこと、国語入試問題とは奇っ怪なものである。
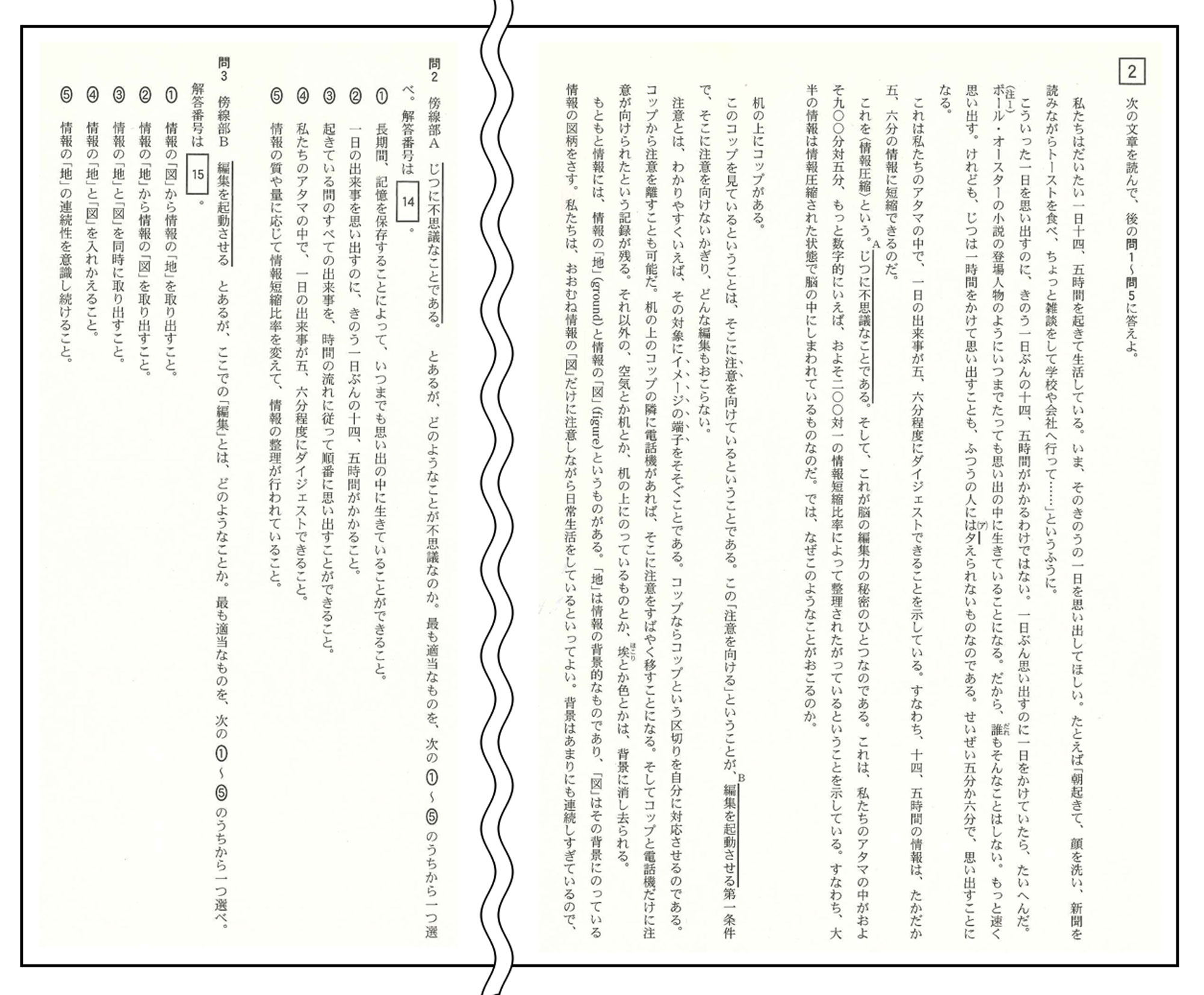
【松岡正剛試験問題3】『知の編集工学』
(試験問題より抜粋)

⊕ 国語入試問題必勝法 ⊕
∈ 著者:清水義範
∈ 発行者:鈴木哲
∈ 発行所:株式会社講談社
∈ 組版:豊国印刷株式会社
∈ 印刷:豊国印刷株式会社
∈ 製本:株式会社若林製本工場
∈∈ 発行:1990年10月15日
⊕ 目次情報 ⊕
∈ 猿蟹合戦とは何か
∈ 国語入試問題必勝法
∈ 時代食堂の特別料理
∈ 靄の中の終章
∈ ブガロンチョのルノワール風マルケロ酒煮
∈ いわゆるひとつのトータル的な長嶋節
∈ 人間の風景
∈∈ あとがき
∈∈ 解説
⊕ 著者略歴 ⊕
清水義範
1947年、愛知県名古屋市生まれ。愛知教育大学国語科卒業。’81年『昭和御前試合』で文壇デビュー後、’86年『蕎麦ときしめん』でパスティーシュ文学を確立し、’88年『国語入試問題必勝法』で第9回吉川英治文学新人賞を受賞。著書に『雑学のすすめ』(絵・西原理恵子)『いい奴じゃん』『考えすぎた人』『学校では教えてくれない日本文学史』『ifの幕末』『ドン・キ・ホーテの末裔』など多数。