父の先見


徳間書店 1964・1996
[訳]和田武司
墨守という。絶対に守り抜くという意味だ。
歴史的には、墨子の死後も師の教えを守りつづけた墨家の言動と態度のことが墨守なのである。墨家はそれほどに師の墨子を大切にした。しかし、墨守にはもうひとつの意味があった。それは専守防衛という意味だった。
墨家はたんなる思想集団ではない。戦国期の思想集団としても、同時期の儒家とは比較にならないほどに体系化された思想と論理をもっていたのだが、そのうえ実は、強力に組織された軍事集団でもあった。初期こそ怠惰な者も役得目当ての者も多かったのだが、やがてはどんな集団にもありがちの、堕落する者や脱落する者がほとんどいなくなっていた。墨家は戦国期最大の思想的軍事集団あるいは軍事的思想集団の総称なのである。
ところが、この墨家集団が始皇帝による秦の建国事業のなかで、忽然とその姿を消してしまう。それだけではない。その後の中国2000年の歴史において墨家はまったく忘れられ、絶学の道を辿ったのである。なぜなのか。その理由がいまもってわからない。まるで時限装置を隠しもっていたかのように、墨家は消えた。
こんな思想集団は稀有である。いや、おそらくは空前絶後であろう。こんな事例はほとんど歴史に登場していない。
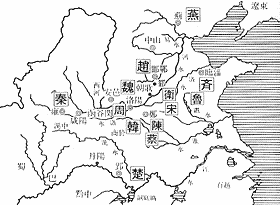
墨子は、本名を墨擢(ぼくてき=テヘンはない)という。生涯には不明なところが多く、生没年さえわからない。
孔子と同世代とも、孔子没(前479年)後の出身不明の人とも言われるが、その言行録の『墨子』には「耕柱」「貴義」「公孟」「魯問」があって、これらが墨家誕生のころの経緯を知らせてくれる。
それらによると、墨子が創成した学団の本拠は魯の国にあった。孔子の学団と同じ国である。けれども『論語』はただの一度も墨子にふれることがない。墨家はかなり多くの門弟を集めたネットワークをもっていたから、その名が孔子に届かないはずがない。それがふれられていないというのは、墨子や墨家集団が孔子よりも後の時代の活動だったということになる。一方、孟子は墨子のことを強い口調で非難し、墨家思想の流行を憂いていた。ということは墨子の活動は孟子より少し前の活動期だったということになる。
いずれにしても諸子百家の時代の半ば、紀元前5世紀くらいに墨子は活動していたにちがいない。「儒家・道家・陰陽家・法家・名家・墨家・従横家・雑家・農家・小説家」の九流十家に加えて、兵術・方術・医術を専門とする諸子が、ある意味ではクリエイティブに、ある意味ではデスペレートに争っていた時期である。
そうした諸子百家のなかで、意外におもわれるかもしれないが、墨家が最も勢力をもっていた。韓非子も「世の顕学は儒墨なり」と書いている。
ところが孟子の批判だけでなく、諸子百家のいずれの派からも墨家はことごとく無視された。それだけならまだしも、その後の歴史家たちもまったくといってよいほどに墨家の思想と活動を扱おうとはしなかった。あれほど古今の史料にあたった司馬遷ですら、墨子については伝を採らず、たった24字の注記にする程度なのである。そこまでしているのを見ていると、これはひょっとして、あえて墨家を歴史から抹殺する意図があったとしか思えない。
そのように墨家が扱われたのには、理由がないわけではない。あまりに墨家の思想と行動は独創的であり、あまりに奇怪であって、また、あまりに頑固きわまりないものをもっていた。
まずもって、墨家はことごとく儒家に逆らった。孔子の『論語』が鬼神を相手にしなかったのに対し、墨子は鬼神をこそ確信すべきだと説いて(天志・明鬼)、儒家がそもそも祭礼を重んじているのに鬼神だけを排斥するのは自家撞着だと非難した。また、儒家がその礼と楽とを並べて尊重したのに対しても、墨子は歌舞音曲などはいたずらに妄想や幻想をもたらすだけだと言って、これを公然と軽視した(非楽)。もっと実用に徹するべきだと考えたのだ。したがって、葬礼なども簡便にすますべきだと説いた(節葬)。
このように儒家イデオロギーに真っ向から対立する墨家は、天志と明鬼の関与を信じるがゆえに、人は天の志に従うべきだという哲学をもっていて、そういう天の下にいる人はすべからく兼ね合って博愛に徹するべきだと説いた。
これが有名な「兼愛」である。
この兼愛主義も儒学的立場からすると甚だもって煙たいもので、儒家の愛は一家の愛を中心に国家愛にまで高めようとしているのだが、墨家はこれを「別愛」(差別愛)だと批判した。
墨家の別愛批判はとことん貫かれたようだ。世界史上最初の普遍的博愛主義ともいうべきほどである。しかし「兼愛」は君子と臣下のあいだに上意下達の制度と哲学をおこうとする者にとっては、邪魔なものである。国をつくるにも障害になる。墨家はこのような事情からも、各派に嫌われ、排斥されることになる。
これだけでも墨家の異例の特質が際立つが、さらに墨家の異様な相貌を代表する思想と行動が「非攻」であった。
一般に、人を殺すことは、どんな時代の、どんな政治家も思想家も容認していない。村や町で一人の人間を殺すことは、ただちに犯罪とみなされる。それなのに戦争となると、多数の殺害が平気で容認される。一人の殺害を国法や社会の法で裁いている一方で、他方では多数の殺害を正当化する何かが動いている。いったい戦争とは何なのか。いっさいの哲学と制度と愛を踏みにじるためにあるものなのか。
戦争を仕掛ける行為をこそ問うべきである。相手に攻撃をかけたい社会意識と国家主義こそ打倒すべきである。
墨子と墨家はこのことに敢然と主張した。一個の黒や少数の黒を見ているときは、それは黒だと言いながら、多数の黒を見るときはそれを白だと言うのはおかしいのではないかと、その詭弁の真っ只中に向かって、反旗を翻した。
これを墨家の「非攻」論という。
攻撃による戦争をすべて否定しようとしたものだ。
しかしながら、これはふつうなら単なる理想主義あるいは反戦主義というもので、ジョージ・ブッシュの戦争が始まってしまえば、それですべては押し潰される。それがふつうである。いくら反戦を唱えても、そんなものはほとんど無力になりかねない。
ところが墨家はここからが異常だったのである。「非攻」ではあっても「墨守」なのである。戦いは決して仕掛けないが、その戦いに屈することも肯んじえない。墨家はここで立ち上がって、守り抜くための戦争を断固として挑む。
実際に、墨家がどこでどのように守備戦闘にかかわっていたかという記録は少ない。しかし、さまざまな史料や見解を総合すると、墨家は頼まれれば、どんな都邑の城郭の防御のためにも傭兵的集団として出向いていた。そのリーダーを巨子(鉅子)といった。
巨子が組み立てる戦術は微に入り細に及んでいて、敵の攻撃を数十のパターンに分け、そのひとつひとつに用意周到な反撃をもたらす計画を積み上げた。また、それらの多様な作戦に対応できるだけの軍事訓練と軍事機器の開発を怠らなかった。
たとえば、敵が城の外に土塁などを積み上げてそこから矢を射たりする攻撃の「臨」に対しては、場内に土塁をさらに高く積み上げて矢を同時に何本も連射する「連弩」(れんど)を発明して対抗する。梯子を使って城壁を越えようとる敵には、今日でいうハシゴ車にあたる折り畳み式の「雲梯」を開発して、一気に火を落とす。敵が水を使ってくるなら、あらかじめ城内に水位の高低の地形を作っておいて、その水路におびき寄せ、船を加速して逆襲する。敵が穴をあけてくる「突」を用いてくるなら、墨家は逆トンネルを掘って迷路で迎え撃つ。
ざっとこうした作戦が兵器の開発とともに、ふんだんに用意されるのである。けれども、そのいっさいは守り抜くための戦闘だったのである。
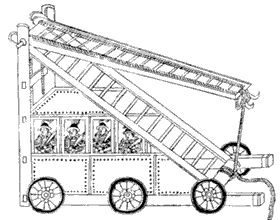
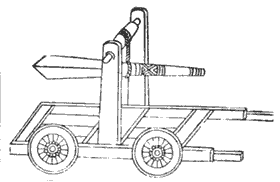
墨家軍団がそうとうに強力であったらしいことは、魯や秦の君主たちがしばしば墨家に援軍を求めて危機を潜り抜けている記述からも、うかがえる。
墨家はこれを応じて、まず作戦を練り、軍団を配備して、よく敵と闘った。このような墨家軍団において最も奇妙なことは、墨家の集団自体は城塞を築くわけでもなく、また攻撃されるわけでもないのに、つねに攻撃する者にのみ自ら進んで姿をあらわして対抗し、自らの主戦場を次々に移していっていることである。
わかりやすくいうなら助っ人だが、ただひたすら助っ人をするために哲学と兵器を磨くというのは、やはり異様である。ひとまずそれを軍事的傭兵組織だとみなしても、それなら「兼愛」の思想も「非攻」の思想も必要はない。相手に勝つための傭兵組織なら、先制攻撃もありうるからである。敵が攻めてくるまで待つだけの傭兵など、ありえない。
また、わかりやすくいうなら、これはさしずめNPO型の支援組織ということにもなるけれど、戦闘に対してはつねに過激であろうとしているところが、やはり変である。軍事的NPOとみなしたとしても、やはり守備だけの“受けの戦闘”に徹するところが理解しにくいものになっている。
しかも、ふだんの墨家集団はかなりおとなしい。目立たない。諸国を遊行する布広班、学団の典籍や教本を編集する講書班、食料調達から守城兵器の開発まで担当する工作班などに分かれ、非常のための日常の充填にのみ徹してばかりいた。
墨家が集団をつねに別動組織のように分派していたことも、当時の諸子百家の集団のなかでは格別に風変わりだった。
荘子は、墨子亡きあとの墨家が三派に分かれたと書いていて、墨家に内部分裂がおこったように読めるのであるが、どうもそうではなくて、あえていくつもの分派を作り出していたとも想定できる。戦国時代、儒家が八派に分かれたように、墨家はやむなく三派に分かれたのではなかったのである。
このような墨家集団が、秦の始皇帝の建国を前にして跡かたもなく姿を消してしまうのだ。
いったい何がおこったか、その経緯をたどるのは容易ではないが、ひとつには集団自殺をしたとも考えられる。すでに巨子孟勝の時代、采邑没収に侵攻してきた楚王の直轄軍と戦って、城が守りきれなくなったことがあるのだが、このとき孟勝は集団自決をしようとして、弟子の徐弱に「そんなことをしては墨家の系統が絶える」と諌められている。しかし孟勝はおめおめ生きていてもいったん失敗したわれわれの汚辱は晴れるわけではない。きっと宋の田襄子がわれわれの気概を知って墨家の意思を伝えるだろうと言うと、徐弱も納得して、師とともに自決してしまったというのだ。こういうことが何度かおこったのだろう。
しかしもうひとつには、戦国時代が終焉を迎えつつあって、秦の始皇帝による一大事業に墨家が役割を果たせなかったか、役割を果たしたにもかかわらず評価されなかったという事情も関与していただろうと思われる。
秦の国家システムの基本は、封建制を廃して郡県制に移行するところにあった。墨家の理想は封建制にある。とくに郡県制の主唱者である丞相李斯が、封建制にまつわる民間人の蔵書と読書に問題があるとみて「挟書の律」の制定を求めたときに、始皇帝がこれを裁可して「焚書」を断行するにおよんで、墨家はもはやこれまでと息絶えることを選んだようにも思われる。古代戦国時代の“薔薇の名前”の遂行だった。
けれども、いっさいはいまのところは謎なのである。何も詳しいことはわかっていない。ただ、戦国時代を駆け抜けた最も強力な軍事集団が「兼愛」と「非攻」を説いて、数々の“敵”を沈黙させていったことだけが、残るばかりなのである。
墨家の「墨」とは入れ墨のことではなかったかという説がある。本当かどうかはもとより知るべくもないのだが、本当のような気もするのは、もし墨家の組織が入れ墨まで彫りこんでの紐帯によって結ばれていなかったのなら、これほど容易に一網打尽を甘んじることもなかったろうと思われるからである。
かえってその強靭な集団維持力と組織紐帯力が災いして、まるでヤクザか暴力団か任侠の徒のごとく、国家の犠牲になっていったとも想像されるのだ。
そういえば、秦墨とよばれた一団がいた。そのようによばれるからには、秦が傭った一団である。秦の爆発的な進行にはおそらくこの秦墨の活動があずかっていたのではあるまいか。しかし、かれらは“官軍”ではなかったのだ。相楽総三ではないが、一国の確立が成就したあとは、どこかで粛正されてしまったのであろう。
墨家は「任」の一字をしばしば標榜した。この「任」は墨家こそ潰えたものの、姿を変えて太平道や五斗米道に、また『水滸伝』のなかに蘇っている。
ひるがえって、墨子その人が賤民の出身だったという説がある。きっと工人の技術をもっていた。あるいは数学の技法に長けていたかもしれない。墨子はやっと清の時代になって評価されることになるのだが、そのとき清は西洋列強の餌食になろうとしていた矢先であった。慌てた中国の知識人たちは、ついに墨子を探しあてたのである。そして、「西欧の学は古来、わが墨子に備われり」と気がついた。けれども、時すでに遅かった。あの中国にして、墨子を思い出すのが遅すぎた。
ここにおいてぼくがふと思うのは、はたして“日本の墨子”をわれわれは知っているのかということである。いつの日かそんな話をちゃんとしてみたい。