父の先見


文芸春秋 2006
Adam Fawer
Improbable 2005
[訳]矢口誠
アルバート・アインシュタイン(570夜)が「量子力学はとても注目すべきものだと思います。けれども私の内なる声は、これは本物ではないと告げています。神はサイコロ遊びをしないんです」と言った。スティーブン・ホーキング(192夜)はもっと乾いていた。「神はサイコロを振るだけじゃない。目隠しして走る」。
ピエール=シモン・ラプラス(1009夜)は「未来を予知するにはすべてを知っている魔物が必要だ」と言った。ウェルナー・ハイゼンベルク(220夜)は「現実にはどんなものにも真の位置も運動もないんだから、すべてを知ることが不可能だ」と言った。
こういう問答がノンストップ・サスペンスの途中に出入りする超絶ミステリーをアダム・ファウアーが書いた。原題は“Improbable”、矢口誠が『数学的にありえない』というふうにうまく訳した。陰の主人公はなんと「ラプラスの魔」あるいは「集合的無意識」なのだ。
筋書きを言うのは野暮だろう。表の主人公はデイヴィッド・ケインという天才的な数学者だ。それも統計学を専門とする。このケインがときおり奇妙な神経状態になる。ところが、これを「能力」だとみなしたドクター・トヴァスキーという研究者がいた。いまだ正体がつきとめられていない「謎の能力」だ。
これだけで早くも物語がラプラスめくのだが、そこに双子の兄のジャスパー・ケインが絡む。のみならず、この事情を察知したアメリカ国家安全保障局の秘密機関とCIAとFBIが動き出した。ケインをひっぱるのは、これはよくあるキャスティングだが、ナヴァ・ヴァナーという小股の切れ上がった女だ。この、O型Rhマイナスの血液をもったCIAの女はアルカイダやハマスの連中を自由に殺せるライセンスをもっている。そのほか、北朝鮮の工作員やらトヴァスキーの変な患者やら、地下カジノの親父やHIV陽性の持ち主やプロの追跡屋やハッカーらがいろいろ出てきて、ときどきミック・ジャガーとザ・フーとジム・モリソンの音楽が流れる。ジム・モリソンは「ピープル・アー・ストレンジ」だ。そういうサスペンス・ミステリーなのである。
これでは筋書きはさっぱりわからないだろうが(ふっふっふ)、そのほうがいいだろう。文体もいいし、「巻き戻し」と称する意識のフィードバックがときおり文中にあらわれるのも、ITフラッシュのようでおもしろい。それは、ほかならないぼくが保証する。
ケインの口調の語尾がときどき狂って地口合わせのようになっていくのも(「お帰り‐お参り‐お回り‐お触り」というように)、巧みな手法だった。だいたい物語の仕立てはすぐにでもハリウッド映画になりそうなサスペンス・アクションなのだ。そういうことを愉しむためにも、筋書きは知らないほうがいいだろう。
しかしそれでいて、裏の主人公は「ラプラスの魔」と「ユングの集合的無意識」なのである。そこにトマス・ピンチョン(456夜)ふうのエントロピーと量子条件がからむのだ。これはまことに意外な、とんでもない陰の主人公である。そんなことアリなのかという設定だ。掟破りだ。こんなことを発想した奴の気が知れない。
作品には、しばしば確率論の講義や相対性理論の講義が巧妙に挟まっている。読者へのサービスだろう。ハイゼンベルクの不確定性理論についても、ケイン自身が説明してみせる。とくにラプラスの『確率の哲学的試論』についての芸達者な説明は、「千夜千冊」をちょっとばかり上回る。そんななか、超高速の駆け引きが波打っていく。殺し合いもしょっちゅうだ。そんなサスペンス・アクションなのである。
いや、もうひとつ裏の裏の主人公がいた。脳の側頭葉だ。非局所場におこっている刺激を感知してしまう脳である。物語はそもそもケインの側頭葉が見る未来にかかわっていた。
この世の宇宙というものは、ない。宇宙はビッグバン以来、ともかくも隙間とダークマターをあれこれふやしながらここまで進んできたけれど、そのどこからが「この世」であるかはわからない。そもそも10億光年のかなたの星が、いま実在しているかどうかもわからない。「この世」とは、われわれの投影現実なのだ。
現在は、つねに相対的なものなのだ。空間も時間も、物質も運動も相対的でしかありえない。ニュートンはすべてのものは時空に特定のアドレスをもっていると考えたけれど、いまはこれではマクロの宇宙には通用しない。同時にミクロコスモスにもまったく通用しない。相対性理論と量子力学によって「世界は見方によって分かれている」ということがわかるようになってからは、どんな状態にいる観測者が、どの座標の出来事を見ているかという関係だけが、世界で唯一の確認できることになったのだ。
そのうえ、世界はアップ・クォークとダウン・クォークとレプトンたちのほかは、出現したとたんに消えてしまうか、変容してしまっているといっていい。ということは、われわれはこのいくつかのクォークとレプトンをもって生命体を組織にしていられるわけで(それが構成元素やアミノ酸やタンパク質になるわけで)、その生命体の一部のそのまた一部の脳の片隅で、自分たちをつくりあげたこのような宇宙や世界の過去の出来事を組み立てたからといって、いったいそれがどの時空の出来事だったかを決定することは不可能なのだ。
というようなことを、この作者アダム・ファウアーは大前提にして、この作品を書いたようだ。1970年生まれで、幼いころに病気で視力を失い、それを治癒するために何度も病院生活をして手術をしてきたらしい。さいわい視力は回復し、そのあとはペンシルヴァニア大学で統計学を学び、さらにスタンフォード大学でMBAを取得した。
MBAをとったからにはというので企業に入り、マーケティングを担当するのだが、これはすぐにばかばかしくなって、(他の理由もあって悲しくもなったらしいが)宇宙と人間の関係の謎に挑戦するエンタテイメントにとりくんだ。その第一作が、この『数学的にありえない』なのである。たちまち16カ国以上で翻訳された。
悪臭がする。それがデイヴィッド・ケインが自分の異常に気がついた最初だった。TLE(側頭葉系癲癇)らしい。
主治医のドクター・クマールは、ケインの左頸部迷走神経の下に電極を差しこみ、ヴェガス・ナーヴ・スティミュレーションなる治療を施した。こんなものが効くはずがない。
抗癲癇薬も投じたが、ドーパミンを増大させる副作用がおこるだけだった。ケインは呟く。「俺は狂犬病になるかもしれないんだぞ‐さぞ‐マゾ‐謎」。
その後、ケインには名状しがたい既視感が頻繁に襲ってくる‐くるくる‐狂う。こうしてアダム・ファウアーは、表の主人公ケインの身におこっていることを、物語のサンスペンスのなかで自在に、意地悪に、ゆさぶっていく。いったい何がおこっているのか。その謎を、国家安全保障局のジェイムズ・フォーサイスにはハイゼンベルクの不確定性原理との関連で推理させ、謎好きの科学者のドクター・トヴァスキーには、ハイゼンベルクを否定した決定論的な推理をさせていく。心にくい配当だ。
フォーサイスにとっては、電子の速度や方向が確率的であることが宇宙の支えになっているとしか思えない。トヴァスキーには熱力学第二法則が確率的な真理でしかないことが、がまんがならない。二人はまったく対立する見方で対峙する。しかし作者はついにトヴァスキーに、こう言い放たせる。「電子の動きを何が決定しているかなんて、どうでもいいことだ。そこを操っているのはクォークよりも小さな有機的分子かもしれないし、非局所的な現実から流れてくるエネルギーかもしれないじゃないか」。
ケインのほうはケインのほうで、自分が狂犬病じゃなければ、「シュレディンガーの猫」になったような気がしてくる。23パーセント生きていて、かつ34パーセントほど死んでいるという猫だ。
こういった仕込みをさんざんしておいて、作者アダム・ファウアーはしだいにケインが「確率そのものであるような存在」になっているということをだんだん仄めかし、そのうえでナヴァ・ヴァナーに「あなたはラプラスの魔そのものなのよ」と言わせていく。ケインはそんな馬鹿なことはありえないと思う。
ところが、双子の兄のジャスパー・ケインが思いがけないことを言うのだ。「ラプラスの魔っていうものは、実は人間にもおこっていることなんだ。それは集合的無意識なんだ」。
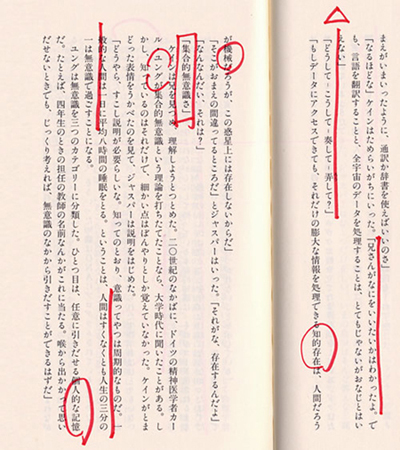
こうしてデイヴィッドとジャスパーの問答は、物語がいよいよサスペンスの核心に近づきつつあることを暗示する。こんな調子だ。
J 「俺たちが生きているのはクォークとレプトンのおかげだが、重要なことはこれらは物質ではないということなんだ」。
D 「なら、何なんだい?」。
J 「エネルギーさ。アインシュタインの方程式どおりさ。もともと物質はエネルギーの見かけなんだよ。それは俺たちにもおこっていることなんだ」。
D 「俺にもおこっているということか‐ことから‐ことだま‐か。そんなものがあるはずがない」。
J 「あるさ。それが思考というもんだ‐門だ‐問題だ」。
ジャスパー・ケインが言いたいのは、ぶっちゃけていえば、意識も無意識も、どんな思考のプロセスもニューロンの発火による電気的なシグナルでおこっている以上、すべての思考はそもそもエネルギーであるはずだということである。
ここから話は、量子的なレベルの意識と東洋のタオイズムやブッディズムが想定した意識の仮説との関係に片寄っていき、そんなきわどい話を持ち出してどうするのかとぼくをハラハラさせたうえで、ひょっとするとケインの脳の側頭葉だけにはこのことがあてはまるのかもしれないという気にさせていく。しかも、こうした不気味な会話をしているジャスパーとデイヴィッドが一卵性双生児であることが、どうにも気掛かりでしょうがなくなっていく。
まあ、このあたりからはぼくもこの物語の仕掛けの大半が読めたのだが、その謎はここでは明かさないことにしておこう(ふっふっふ)。
そのかわり、ラストに近くになってナヴァとデイヴィッドがこんな話を交わしているところを紹介しておこう。ちょっとした「見方のサイエンス」に強い諸君なら、まあ、以下の会話でもおよその見当がつくにちがいない。
N 「わかった?」。
D 「未来は観察されるまでかたちがないってわけだ」。
N 「そうなのよ」。
D 「もしコインを投げれば、おこりうる未来は二つあるということになる。ひとつはコインの表が出る未来、もうひとつはコインの裏が出る未来。けれども観察されるまではどちらの未来もないわけだ」。
N 「そうよ。素粒子が同時にいろんな場所にありうるのもそのせいよ」。
D 「それはでも、ラプラスの魔の理論には合わないね。未来が多数あるってことになる」。
N 「ラプラスが不完全だということね。あなたはそのラプラスの魔になってしまったのよ」。
D 「それにしても、よりによって、なぜぼくがそうなったんだろう?」。
N 「誰だってそうなる可能性をもっているけれど、きっとみんなはそれを閉じこめているんでしょうね」。
D 「閉じこめないときもある?」。
N 「閉じこめられない人もいるってことね」。
D 「どんな連中?」
N 「ソクラテスとかゴッホとか。ジャンヌ・ダルクとかアルフレッド・ノーベルとか‥」。
ぼく 「ドストエフスキーとかニーチェとか」。
N 「そう、そうね」。
ぼく 「エジソンとかフロイトとか、ユングとかヴィトゲンシュタインとか‥」。
よろしかったでしょうか‐消化‐昇華‐仕様かね。