父の先見


文藝春秋 2013
Alics Roberts
The Incredible Human Journey 2009
[訳]野中香代子
編集:下山進・高橋夏樹
装幀:野中深雪
ほとんど言及されてことなかったことだが、文学にはめっぽう苦手な分野がある。文学というもの、どんな歴史的人物の細部や1億年先の未来SFに強くても、太古の物語が書けないのだ。作家たちも、からっきしである。いまだクロマニヨン人の恋やネアンデルタール人の家族の葛藤についての話など、お目にかかったことがない。
だからたとえば、エリザベス・トーマス(174夜)の『トナカイ月』(草思社)はめずらしかった。後期旧石器時代を舞台にして、太古の北方母系社会を描いた。ヘミングウェイ賞をとったが、作家ではなかった。文化人類学者だった。
千夜千冊では『ウッツ男爵』を採り上げたブルース・チャトウィン(1467夜)こそは、オーリニャック文化やギョグリ・テペの物語が書けそうな比類ない才能の持ち主だったけれど、残念ながら夭折した。いまとなっては、その才能を「過去に戻る紀行文学」ともいうべき『ソングライン』(英治出版)や『パタゴニア』(河出文庫)や『どうしてぼくはこんなところに』(角川文庫)で偲ぶしかない。
チャトウィンの代表作『ソングライン』はアボリジニの想像力に迫るもので、そのくせノマディックな私小説のようにも読めた。ソングラインとはオーストラリアの大地を目に見えぬ歌の記憶でつなげている網の目のことだ。かつて人類は今日のわれわれからは思いもよらないソングラインを各地にもっていたはずなのである。
文学が先史や上古を相手にできない欠陥をもっていることとは逆に、図鑑や写真集、あるいは映像作品やテレビのドキュメンタリーでは、みごとに時間をまたいで大過去の只中に歴史的現在を感じさせてくれる場合がけっこう多い。ぼくは幾多の記録写真集や、ナショジオやBBCやNHKの番組で、ずいぶん愉快で刺戟に富んだ大過去旅行をさせてもらってきた。映像は「時の旅」にはもってこいなのだ。
BBCのマイケル・モーズリーら3人のプロデューサーから「太古の人類の足跡をたずねる旅に行きませんか」と声をかけられ、アリス・ロバーツの26週間におよぶ Incredible Journey が敢行された。2008年のことだ。日本のテレビ番組は案内人を選ぶのがへたくそで、女優かジャニーズのタレントが5日くらいの海外ロケをして、3分程度のシーンを9回ほど収めるところだろう。あれは、つまらない。
アリス・ロバーツはブリストル大学の解剖学者で、いまはバーミンガム大学でも教えている。考古学や人類学の研究者でもあって、BBCの科学番組のコメンテーターなどもしていた。しかしこの番組でアリスは物見遊山のための旅行者になったわけではない。本書を読むとかなりハードな探索の旅をした。行く先々でのアリスの視点やツッコミはかなり鋭く、冒険的集中力にかなり満ちていたことがわかる。
のちにまとめた文章もよかった(日本語訳もうまい)。序文も堂々としていた。アリスは実はチャトウィンの愛読者でもあった。本書にも『ソングライン』の話が出てくる。
ちなみにこの番組はNHKでも3回に分けてETV「地球ドラマチック」で放映したのだが(本書の1、3、5章だけ)、なんとアリスの出番はすべてカットされ、渡辺謙のナレーションで流れが進むように構成されていた。これにはがっかりした。この「NHKふう」はそろそろやめてもらいたい。
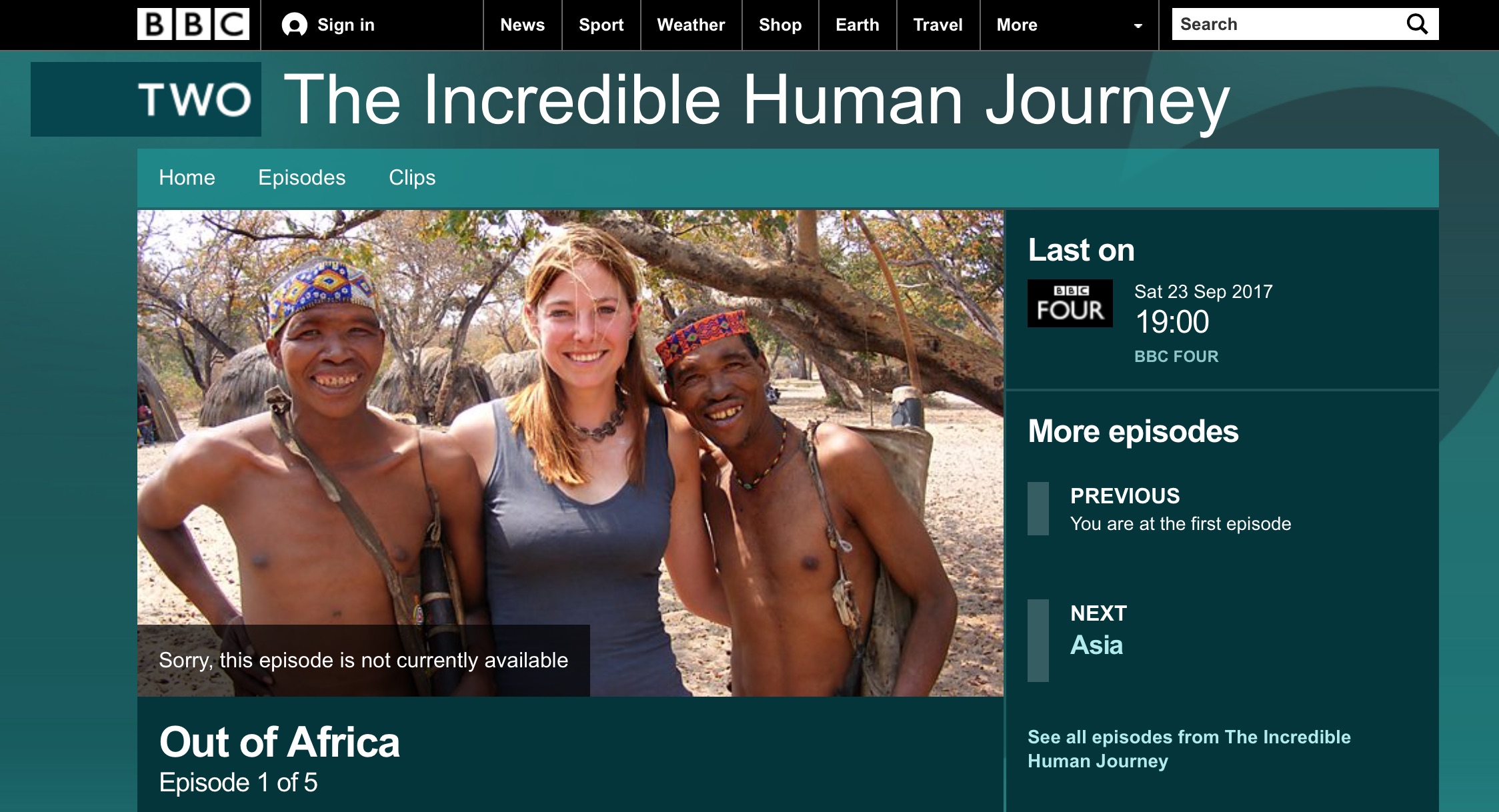
アリスの旅はアフリカ・ナミビアの最深部、カラハリ砂漠の真ん中でテントに寝起きしながらブッシュマンの日々に入りこみ、吸着音型の現地語を学習するところから始まる。
ついで南アフリカの中期旧石器(MSA)遺跡群から現生人類最初の化石が出たエチオピアのオモ川沿いの集落を見たのち、きっと何かの目印に用いただろう赤色オーカーの破片のある南アフリカのピナクルポイントをへて、さまざまなチームや現地の研究者と合流しながら「出アフリカ」をした祖先の跡をたどるというルートにもとづいて、中東からアジアへと進む。
イスラエルのスフールやオマーンのカラ山地では、シュメール風の刺青をしている考古学者ジェフ・ローズと会った。中東やペルシャ湾の領域は不安定な政治事情がずうっと続いているため、発掘研究が遅れているのである。
74000年前、いまのスマトラ島のトバで巨大な火山が爆発した。インドのジュワラブラム遺跡ではそのときの「灰」と考古学とが結びつく。カルナタ大学のラヴィ・コリセッターがその専門家だった。
火山岩と石器の関係からも人類の足跡がたどれることも知った。ケンブリッジ大学のマイク・ペトラリアが教えてくれた。アリスはそれらの遺物や研究者との会話から20万年前の出来事をあれこれ想像する。
しかし遺物だけでは、太古の担い手がホモ・エレクトゥスだったのかネアンデルタール人だったのか、それともハイデルベルク人がその地を通過していたのかは、わからない。骨とともに遺伝子を調べる必要がある。オックスフォード大学のスティーヴン・オッペンハイマーがその統括力の持ち主だ。ぼくも主著『人類の足跡 10万年全史』(草思社)で大いに触発された。
アリスはそのオッペンハイマーとクアラルンプールのホテルで初めて会って、この憧れの人類学者(遺伝系統地理学)と東南アジア熱帯雨林の狩猟採集民の奥にひそむ人類史をたずねる。
いったいジャワ原人とは誰だったのか。
かれらはあの「ミトコンドリア・イヴ」や「ルーシー」とは関係がないのか。アリスはマレー半島で唯一農耕をしないラノー族のあいだに入って、ジャワ原人を生んだ「人類という遺伝子」について考えこんでいく。そしてオッペンハイマーと話していくうちに、人類の「アフリカ単一起源説」に傾いていった。
出アフリカ後の現生人類がいつ、どのようにアジアに渡っていったかは、まだ正確なことはわかっていない。アジア大陸は人類学や考古学にとっては18世紀までのアフリカ以上の"暗黒大陸"なのである。
アリスはボルネオのニア洞窟で、サラワク博物館のトム・ハリソンに「ディープ・スカル」(深い頭骨)を見せられて唸り、インドネシアのフローレス島で「エブ・ゴゴ」が12000年前まで生存していたことに驚愕する。「エブ・ゴゴ」は脳も体も小さいホビット(小人)だ。その頭骨は学術上はLB1(リアンブア1号)と名付けられ、人類学的には「ホモ・フロレシエンシス」の一種と認定されたのだが、アリスにはなぜアジアにホビットがいるのか、釈然としない。
とはいえ、ボルネオやジャワやニューギニアは、かつてはスンダ大陸やサフル大陸を形成していたところだ。そのころに何があってもおかしくはなかった。それなら、アジアのホモ・エレクトゥスやホモ・フロレシエンシスはそこから舟でポリネシアにも行ったのだろうか。アリスたちの旅は南太平洋を越えてオーストラリアに向かう。
オーストラリアは進化生物学的には他の大陸とは隔絶した進化を遂げた特別な地域である。肉食の大トカゲやカンガルー・コアラなどの有袋類がいて、ガラパゴスのような異質な生態系が維持されてきた。
そんな場所へ現生人類の末裔はどのように棲みつき、先史のアボリジニのような一群をきずいたのか。
アリスは高鳴る興奮を抑えてオーストラリアに入るのだが、そこに待っていたのは先住民アボリジニたちが確信している先祖たちの頭骨や足跡だった。それらはマンゴマンとかマンゴレディとか巨人ウィランドラの頭骨や足跡だ。まとめてWLH(ウィランドラ湖畔の人類)と呼ばれる。
本書はWLHについての仮説をいろいろ紹介し、ジム・ボウラーとアラン・ソーンが発見したWLH50の年代測定についてのさまざまな見方を比較しているが、統一見解がどのようなものになりうるかは、示していない。
それにしても、世界各地に巨人伝説や小人伝説がたいてい残っている理由が、アリスにはわからない。東南アジアの現生人類がオーストラリアに渡ってからホモ・エレクトゥスに南方進化したという流れが浮上するばかりなのである。はたして「ビッグマン」や「小さ子」は考古学や形質人類学が対象にしていい相手なのだろうか。
ミトコンドリアDNAとY染色体の調査分析では、北アジア人はすべて南アジアのハプログループMとNにさかのぼることが知られている。そうだとすると、ロシア人や中国人のルーツはどのように形成されたのか。南アジアから流入してきたのか。アリスたちはサントペテルベルクから北アジアと東アジアに降りていくことにした。
まずは氷河期のシベリア人の足跡を追い、マンモス・ステップやLGM(最終氷期極相期)で何がおこったかを考えてみた。次にトナカイ遊牧民に焦点をあてて小さなプロペラ機で北のオレニョクに向かい、エヴェンキ族やエヴェン族から時計をさかのぼってみた。けれども核心点がつかめない。近くのヤクート族がチュルク語を話すのに対して、エヴェンキやエヴェンはトゥングース語なのだが、そのことが遺跡や頭骨や遺伝子では説明ができないのだ。
遺伝学者のダグラス・ウォレスは「熱帯地方のミトコンドリアは効率がいいが、極寒地域のミトコンドリアは遺伝子の変異によって効率が落ちて熱を発生させる」という仮説をたてていたものの、さて、それでどこまで説明がつくのか。
いくつもの「?」をかかえたまま、一行は中国に入っていく。北京原人(シナントロプス・ペキネンシス)とは何だったのかを知るためだ。指南役は古人類学の大立者ウー・シンジー(呉新智)だった。
以前からアリスは周口店に行ってみたかった。けれども、北京原人の完璧な複製と当時の破片を手にして嬉しくはなったものの、この骨から北京原人がホモ・エレクトゥスの直系であるとする中国考古人類学の見方には合点がいかない。香港科技大学のバリー・ソートマンが批判したように、中国政府は北京原人をもって中国人が人類の直系であることを強調しすぎているのである。しかし、ここがもっとあきらかになってこないと、北アジアや東アジアの人類史はダイナミックな歴史を描けない。モンゴリアンがどのようにツングース人、満州人、朝鮮人、日本人となったかは説明がつかない。
アリスはジョー・カミンガとともに北中国遼寧省の祝家屯に行って、新たな視点がありうることを知った。中国では旧石器時代に「竹」が注目されていたということ、そのことが中国における石器をアフリカやヨーロッパの特徴と分けているということだ。
復旦大学の遺伝学研究所で、東アジア人の起源に関する仮説を検証する大規模なプロジェクトが進んでいると聞いて、BBCチームはそのプロジェクト・リーダーのジン・リー(金力)にコンタクトをとった。
研究所が利用しているマーカーはM168というY染色体上の突然変異(シトシンがチミンに置き換わったもの)で、これはすべての非アフリカ系の男性がもっているマーカーだった。ジン・リーはM168のサンプルを東南アジア、オセアニア、東アジア、シベリア、中央アジアの12000人から採取し、アフリカ以外に起源をもつY染色体を見つけようとした。
ところが結果は、予想に反して約8万年前にアフリカでおきた変異と同じものしか検出できなかったのだ。今日の中国やアジアの男性の起源はすべてアフリカ起源だったのである。
ということは、それ以前に東アジアにいたかもしれない旧人類は、その後すべてアフリカ起源の現生人類にとって代わったということになる。アリスは聞いた。「この結果をどう見ているんですか」。ジン・リーは「もちろん中国人としては、われわれのルーツが太古の中国にあるという証拠がほしかったのですが、またそういうふうに教育もされているのですが、残念ながらそうではないということです。いまはアジア人のアフリカ単一起源説を受け入れています」と答えた。
ついでながら、オッペンハイマーはY染色体のM130というマーカーを調査研究した結果、東南アジア沿岸にいた一群がやがて北上して日本に移住してきたことを証拠だてた。朝鮮半島と日本列島にに4万年前から37000年前あたりに、この移住の波があったとも推察された。
ぼくが見るところ、アリス・ロバーツのアジア探索はたいして深まらなかったように見えるが、次のイスタンブールを船で渡って入ったヨーロッパ探索はすでに勝手知ったるホームグラウンドであって、今度は細部に分け入りすぎたようだ。
コースは玄人好みだ。まずブルガリアのバチョ・キロでオーリニャック文化前期の石器を感じ、黒海沿岸を北上した移住者同様にルーマニア東端に広がるトナウ川を後期旧石器遺跡をたどりながら、4万年前を想像しながらヨーロッパを東から西へ横切っていく。現生人類がヨーロッパに入ったのはおよそ45000年前から35000年前のことだったからだ。
次に、いったんルーマニアのシルヴィウ・コンスタンティンの遺跡(「骨の洞窟」や「先祖の坂」がある)で、ヨーロッパ最古の現生人類の化石を見ると、ネアンデルタール人の頭骨と遺伝子の関係を知るためにライプツィッヒの進化人類学研究所に寄った。チオクロヴィナ洞窟でリン酸塩に埋もれた頭骨を分析したばかりのカテリナ・ハバティの話を聞くためだ。カテリナはネアンデルタール人が「混血」だったという仮説をもっていた。寒さにも適応していたという。
どんな混血だったのか。アリスはもう少しその事情を知りたがった。それというのも、すでにネアンデルタール人については新たな定説が確立されつつあったからだ。
有名なニュースだが、1997年、スバンテ・ペーポのチームが歴史上初めて、ネアンデル谷で発見された化石からミトコンドリアDNAを抽出した。
ただちにノンコーディング領域(遺伝子をコードしていない部分)の分析が始まり、精密なデータが得られた。現生人類のミトコンドリア(16569個の塩基対)の配列は400個の塩基対に対して平均8個のちがいが出てくるのだが、現生人類とネアンデルタール人はそうではなかった。400個中、平均26個のちがいが見られたのである。
このデータの差は、ネアンデルタール人と現生人類のミトコンドリアDNAがおよそ60万年にわたって別々の進化の道筋をとってきたことを物語る。このことは、現生人類がアフリカに誕生したのち世界各地に拡散し、ヨーロッパの旧人類とほぼ完全に入れ替わったことを示していた。
分岐は51万年前くらいだと想定される。ただし、この分岐推定についてはカリフォルニア大学のエドワード・ルービンのチームは70万年前だというふうに、別のチームは37万年前だという年代を示していた。アリスはルービンの推定は早すぎる気がしたが、これらの推定のちがいはネアンデルタール人がどこまで動いたかということにかかっていたようにも思われた。
ウズベキスタンのテシク・タシュから出土した子供の骨格は最も東で発見されたネアンデルタール人だが、そのDNAはきっと別の値を示すかもしれないような気もした。
番組はこのあと、ヨーロッパのネアンデルタール追跡のほうに片寄っていく。
赤毛のネアンデルタールがいたことを示すmclr遺伝子の話、ワシントン大学のエリック・トリンカウスがFOXP2遺伝子を調べて、かれらが社会的言語をもつていたのではないかという話(80万年前に旧言語があったというのだ!)、その他のネアンデルタール・ゲノムプロジェクトのあれこれの話‥‥。
いささか探検っぽくない話がふえていったあと、チームは今度は後期旧石器時代の繁栄の謎に向かっていく。一言でいえばオーリニャック文化の謎だ。かつてバール・ヨセフが「技術の急速な変化、自意識の誕生、集団としてのアイデンティテイの萌芽、社会の多様化、遠方集団との交流、情報を記号で記録する能力のめざめ」を特徴とした、あのオーリニャック文化を含む後期旧石器時代のほうへ。
アリス自身はオーリニャック文化(3万年前)やグラヴェット文化(2・5万年前)やマドレーヌ文化(2万年前)が、バール・ヨセフが言うような現代社会にも匹敵するような特徴をもっていたことを訝っていたのだが、ヨーロッパの旅の最後にラスコーとクーニャクを訪れてその造形感覚のすばらしさを目の当たりにし、トルコに戻ってギョベクリ・テペ遺跡ストーンサークルを目の当たりにしたときは、ヨーロッパの祖先たちの表現意識の高さに驚いてしまっていた。
人類20万年の移動の跡をたずねる旅の最後は南北アメリカである。アリスたちは、かつてマンモスやモンゴロイドが渡ったであろうベーリング陸橋を進んで先住民の足跡を見聞する。
遺伝学のトレーシー・ピエールとはカルガリーのパウワウを訪れた。パウワウは先住民の踊り祭のことで、かつて本木昭子が青山スパイラルホールで金子郁容(1125夜)をナビゲーターにしてトークイベント・シリーズをつくっていたのだが、そのタイトルがPOWWOWだった。ネイティブ・アメリカンの暮らしが大好きなコピーライター藤原ようこの命名だった。
ピエールは「アメリカ先住民の祖先であるパレオ・インディアンのDNAはシベリアでした」と言った。トランプのWASPのルーツは、プーチンのロシアだったのである。ほんとうに、そうなのだろうか。
アメリカ先住民を言語学的に見ると、アメリンド語族、ナ・ディネ語族、エスキモー・アレウト語族の3つに分かれる。Y染色体のハプロタイプはQ系統(76%)とC系統(6%)に大別される。そうしたことをあれこれ勘案しみると、ベーリング陸橋(ベーリンジア)は「陸橋」というより、アジアのさまざまな地域の群血を受け入れた「中継帯」で、そこでかれらの系統はいったん混ぜ合わされ(1000年くらいのあいだに)、その遺伝子を継承した子孫たちがアメリカ大陸に移住したのであろうということになる。
その後、この子孫たちが18000年前あたりから南北アメリカ大陸全体に拡散していったにちがいない。だとすると、遺伝的多様性から推して「最初のアメリカ人」は5000人程度だったろう。
バンクーバーではサイモン・フレーザー大学のロルフ・マシューズに会った。古生態学と法医学の専門家だマシューズは氷河期にアメリカ大陸が退避地だった可能性を調べていた。植物化石や花粉の過去状況を放射性炭素年代法で測定しているのだ。
とくにクィーン・シャーロット諸島のスゲの花粉が決め手になるらしい。花粉測定によって、知られているかぎり最も早期に退氷が進んでいたことがわかったのである。北極圏のイヌイット(エスキモー)たちは氷床が退散した頃合いに移住をしたという算段になる。
最後の旅はおまけだろう。太平洋に浮かぶサンタ・ローザ島の更新世のコビトマンモスの骨に出会うこと、南米ラゴア・サンタのスミドウロ洞窟の人骨「ルシア」に挨拶をすること、そして南チリ大学の地質学者マリオ・ピーノとともにアメリカ大陸最古のモンテ・ヴェルデの遺跡を覗くことだ。
こうして26週間の幕が降りた。あとは本を書くだけだ。長い旅の終わりをふりかえったアリス・ロバーツは、スティーヴン・ジェイ・グールド(209夜)の次の意味深長な言葉で本書を結んでいる。「生命とは、おびただしく枝分かれした樹木で、種の絶滅という死神にわって絶え間なく剪定されてきたものなのである」。
ごくかんたんに言うと、人類の進化は猿人(アウストラロピテクス)から原人(ホモ・エレクトゥス)へ、そこから旧人(ホモ・ネアンデルタレンシス)をへて新人(ホモ・サピエンス)に向かっていった。草原で立ち上がって二足歩行をしたのは180万年前のホモ・エレクトゥスである。その最初の女性が「ルーシー」と名付けられている。
その原人がやがて出アフリカを遂げる。いつごろアフリカから拡散していったかということに関しては、なかなか定説が仕上がらなかった。長らく二つの説が対立していた。
ひとつは、原人が180万年前からユーラシア各地に拡散して、それぞれの新人(ジャワ原人や北京原人)になったという説だ。かれらはジャワや北京に100万年前に到達していたことになる。この説では現生人類はそれぞれの地域で多様に進化していったことになる。「多地域進化説」と呼ばれている。
もうひとつは、今日につながる現生人類はアフリカの草原で約20万年前に「旧人から進化した新人」として、ユーラシアにグレート・ジャーニーを始めたという説だ。今日では、ミトコンドリアDNAによる測定によってこの後者の説が認められている。「単一起源説」という。本書も、こちらの年代記にしたがって敢行された。
ということは、われわれのコモン・アンセスター(共通祖先)がいつしかヒト族(現生人類=ホミニン)となって、火や道具を使い、埋葬をして死後を想い、言葉を喋って文字を扱うようになったのは、アフリカのどこかにまだネアンデルタール人と併存する地域が少しあっただろう僅か3万年ほど前のことだったということになる。
人類の出アフリカ記は、まだまだ空白の多い物語にしかならない。足跡が埋まらないだけでなく、われわれは人類がどういう生物で、どういう生態的動物なのかを、決めていないのだ。
はたしてヒト族が「種」(species)であったかどうかということさえ、いまなお議論が分かれる。古人類学のクリス・ストリンガーは真正ホミニンは、ホモ・エレクトゥス、ホモ・ハイデルベルゲンシス、ホモ・サピエンス、ホモ・ネアンデルタレンシスの4種であったと主張し、自然人類学のクラーク・ハウエルはそれらは種というよりも「古代個体群」(palaeodemes)というべきだと、妙な名を提唱した。どちらにしても地上に生きて残ったのはホモ・サピエンスだけだったのである。
いつたい人類(human)とはどこから始まったものなのか。コモン・アンセスターは「人類譜」に入ってはいけないのか。ホモ・ハビリス、ホモ・エレクトゥス、ネアンデルタール人、ホモ・サピエンスはそれぞれが別種の「断絶人類史」の登場者だったとみなすべきなのか。これらはいまなお悩ましい連続と非連続の問題なのである。
もっと厄介な問題もある。それは、人類の「心」がいつごろ発生していたのかという問題だ。これについては、スティーヴン・オッペンハイマーもアリス・ロバーツもお手上げだ。ぼくはスティーブン・ミズンやコリン・レンフルーの見解を借りることになる。また、「心の発生」が言語や農業とどう切り結んでいるかということを、ピーター・ベルウッドやロビン・ダンバーの見解を参考にすることになる。

⊕ 人類20万年 遙かなる旅路 ⊕
∈ 著者:アリス・ロバーツ
∈ 訳者:野中香方子
∈ 発行者:飯窪成幸
∈ 発行所:株式会社 文藝春秋
∈ 印刷:大日本印刷
∈ 製本所:加藤製本
∈∈ 発行:2013年5月15日
⊕ 目次情報 ⊕
∈∈ 序文
∈ 第1章 すべての始まり アフリカ
∈ 第2章 祖先の足跡 インドからオーストラリアへ
∈ 第3章 遊牧から稲作へ 北アジア・東アジア
∈ 第4章 未開の地での革命 ヨーロッパ
∈ 第5章 そして新世界へ アメリカ
∈∈ 旅の終わりに
∈∈ 謝辞
∈∈ 訳者あとがき
⊕ 著者略歴 ⊕
アリス・ロバーツ
1973年、英国生まれ。医師。1999年からブリストル大学で解剖学の講師を務める。2012年よりバーミンガム大学教授。
古生物病理学(古代の骨にみられる病気の痕跡の研究)での博士号を持つ。
解剖学から見た進化を研究対象とし、人類の体がどうやって今のようになったかの研究を行っている。たとえば、人類はなぜ他の霊長類に比べて、肩の関節炎にかかりやすいのだろうか。これはいまだに謎だが、彼女はおそらく、人類が木にぶらさがることをやめたのと関係があるのではないかと考えている。
大学外での一般に向けた科学啓蒙にも深く関わり、講演や科学フェスティバルへの協力を数多く行ってきた。テレビの科学番組にも多く出演し、英国チャンネル4の「Time Team」に骨の専門家として登場したほか、BBC2の人気シリーズ「Coast」にも出演。また、自ら出演した解剖学と健康に関する番組の本「Don’t Die Young」(未邦訳)も執筆している。編著に『人類の進化大図鑑』(河内書房新社)。